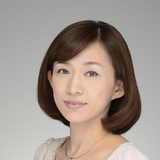| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 生産地 | アルコール度数 | 内容量 | 日本酒度 | 酸度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大関『極上の甘口』 |

|
※各社通販サイトの 2025年03月31日時点 での税込価格 |
上品な甘みと濃厚な味わいが魅力的なお酒 | - | 10度 | 720ml | -50 | 2.3 |
| 一ノ蔵『すず音Wabi』 |

|
※各社通販サイトの 2025年03月31日時点 での税込価格 |
マスカットのようなフルーティーな香り | 宮城県 | 5度 | 375ml | - | - |
| 菊正宗酒造『嘉宝蔵 雅』 |

|
※各社通販サイトの 2025年03月31日時点 での税込価格 |
古来伝承の生酛造りが織り成す至高の原酒 | - | 17.5% | 1800ml | +6 | - |
| 山本本家『上撰 純米大吟醸 松の翠』 |

|
※各社通販サイトの 2025年03月31日時点 での税込価格 |
高い香りとしっかりとした味わいが絶妙 | - | 15.8度 | 720ml | +5 | 1.3 |
| 青木酒造『鶴齢 雪男 純米酒』 |

|
※各社通販サイトの 2025年03月31日時点 での税込価格 |
米の旨味とキリッと締まる後味の良さ | 新潟県 | 15度以上16度未満 | 720ml | +12 | 1.2 |
| 旭酒造『獺祭(だっさい) おためしセット』 |

|
※各社通販サイトの 2025年03月31日時点 での税込価格 |
獺祭の「磨き」を3種類試せる贅沢なセット | 山口県 | 16度 | 180ml×3本(各1種ずつ) | - | - |
| 方舟『純米大吟醸 飲み比べセット』 |

|
※各社通販サイトの 2025年03月31日時点 での税込価格 |
人気銘柄からここでしか味わえない銘柄まで | 上善如水:新潟県、幻の瀧:富山県、加賀ノ月:石川県 | 上善如水:15度以上16度未満、幻の瀧:15度、加賀ノ月:15.5度 | 300ml×3本(各1種ずつ) | 上善如水:+2、幻の瀧:+4、加賀ノ月:+3.5 | 上善如水:1.5、幻の瀧:1.5、加賀ノ月:1.6 |
日本酒の基礎知識 まずは知っておこう!
まずは、日本酒の種類や味わいの違いなど、日本酒の基礎知識を知っておきましょう。おいしい日本酒、自分の好みに合う日本酒を探しやすくなりますよ。
日本酒の種類は? 本醸造酒、特別純米酒、純米大吟醸酒など
まずは日本酒の種類について知っておきましょう。日本酒は、米、米麹、醸造アルコールを原料として製造されており、精米歩合(原料である米を精米して残った割合のこと。精米歩合40%は、米の外側60%を削って、残ったのが40%という意味)と醸造アルコールの添加割合の組み合わせで、表のとおりに分けられます。

Photo by マイナビおすすめナビ

Photo by マイナビおすすめナビ
醸造アルコールを添加しない純米酒は、米の旨みやコクが味わえ、醸造アルコールを添加する醸造酒は、すっきりした口あたりが楽しめます。そして、精米歩合が高い日本酒ほど、香りが引き立ちフルーティーで口あたりがよいとされ、飲みやすく感じることでしょう。
また、一般的に大吟醸酒や吟醸酒は、燗酒よりも冷や(常温)や冷酒での飲み方に、純米酒や本醸造酒は、冷や(常温)から燗酒に向いているといわれます。あくまでも一般的な傾向なので、銘柄ごとに確かめてみてください。
「甘口」「辛口」って? 味わいも異なる

Photo by マイナビおすすめナビ

Photo by マイナビおすすめナビ
日本酒は、大きく甘口と辛口に分けられますが、日本酒度と酸度のバランスによって、さらに濃醇(のうじゅん=深い味わいやたしかなコクがあること)と淡麗(たんれい=癖が少なく、すっきり・さっぱりしていること)に分けられます。
初心者にとって、甘口か辛口かは、日本酒を選ぶ大事なポイントになると思いますので、表をよく覚えておいてください。
日本酒度は、甘口や辛口の目安になる数値。日本酒度がマイナス=糖分が多く甘口に、プラス=糖分が少なく辛口になります。
酸度は、日本酒に含まれるクエン酸やリンゴ酸などの酸がどのぐらい含まれるかを相対的に表す数値で、日本酒の酸味や旨味を表すものです。酸度が高いほど濃厚で辛い味わい、酸度が低いほど淡麗で甘い味わいになります。
初心者向け日本酒の選び方 飲みやすいものを選ぼう
和酒コーディネーター・あおい有紀さんへの取材をもとに、初心者向けの日本酒を選ぶときのポイントをご紹介します。ポイントは下記。
【1】ラベルをチェックしよう
【2】見た目の好みで選んでもOK!
【3】詳しい人に教えてもらうのもあり!
上記のポイントを押さえることで、より欲しい商品をみつけることができます。一つひとつ解説していきます。
【1】ラベルをチェックしよう 精米歩合、日本酒度、酸度
日本酒のラベルには、味わいが連想できるさまざまな情報が記載されています。ここからは、初心者がチェックすべきラベルのポイントをご紹介します。
精米歩合
ラベルに記載されている「精米歩合」とは、精米して残った米の割合を表したものです。精米歩合と醸造アルコールの添加割合の組み合わせで、日本酒の種類が変わるのは前述のとおり。
精米歩合の%が低いほど米の外側(糠の部分)を多く削っています。そのため、精米歩合の%が低いほど雑味が少なくクリアですっきりとした味わい、精米歩合の%が高いほど複雑味がありしっかりしたボディとなる傾向にあります。
また、日本酒度、酸度が表示されている場合は、その数値を見て、甘い、甘酸っぱい、キレがよいなど、ある程度味のタイプをイメージすることができます。
【2】見た目の好みで選んでもOK!
ラベルを見てジャケ買いする、というのもひとつの方法。最近はかわいいイラストや、ワインのようにオシャレなラベルも増えています。
蔵元としても、日本酒の前にある壁を取り払い、新たな層の人達にもっと飲んでもらいたい、という想いがあるためです。かわいいイラストや、おしゃれなラベルのお酒は、初心者にも入りやすい味わいが多い傾向にあるので、チャレンジしてみてはいかがでしょう。
【3】詳しい人に教えてもらうのもあり!
初心者にとって、はじめから自力で好みの味わいのお酒を探すのはなかなか難しいもの。まずは日本酒に力を入れている居酒屋、もしくは酒店で、店主やスタッフに好みの味わいをお伝えし、おすすめの銘柄を飲んでみるといいかもしれません。
その体験を繰り返す中で、気に入った味わいのお酒ラベルをスマホで撮影するなどして記憶していくと、少しずつレパートリーが増えていきます。
初心者向け日本酒のおすすめ|ユーザーイチオシ
ここでは、日本酒はほぼ初心者という人がおすすめする「買ってよかった商品」だけを厳選。商品の口コミはもちろん、コスパや味・おいしさ、香り・風味といった評価ポイントも聞いてみたので、各項目にも注目して商品選びの参考にしてください!
その他にもおすすめしたい商品があるよという方は、ぜひ記事の下部にある投稿フォームからご紹介をお願いします。

愛用者
飲みやすくフルーティーな日本酒
私が初めて飲んだ日本酒です。飲み口が柔らかく、風味がフルーティーなのでどちらかと言えばカクテルのような感覚で飲むことができます。最初にこれから入ると、日本酒という飲み物を勘違いさせてしまうため、プレゼントした方は本格的な日本酒も飲ませてあげてください!(N.R.さん/男性/35歳/会社員)
※各社通販サイトの 2025年03月31日時点 での税込価格
| コスパ | ★★★★★ |
|---|---|
| 味・おいしさ | ★★★★☆ |
| 香り・風味 | ★★★★★ |
| 総合評価 | 4.7点 |
| コスパ | ★★★★★ |
|---|---|
| 味・おいしさ | ★★★★☆ |
| 香り・風味 | ★★★★★ |
| 総合評価 | 4.7点 |

愛用者
少量から楽しめる日本酒
おしゃれなパッケージに惹かれて購入したのがきっかけでしたが、日本酒とは思えない甘さを味わえる日本酒です。日本酒になじみがない人でも気軽に飲めるサイズなので、最初に試すにはちょうどいいと思います。日本酒が好きな人でも満足できる味ではないでしょうか。(M.M.さん/男性/31歳/会社員)
※各社通販サイトの 2025年03月31日時点 での税込価格
| コスパ | ★★★★☆ |
|---|---|
| 味・おいしさ | ★★★★★ |
| 香り・風味 | ★★★★★ |
| 総合評価 | 4.7点 |
| コスパ | ★★★★☆ |
|---|---|
| 味・おいしさ | ★★★★★ |
| 香り・風味 | ★★★★★ |
| 総合評価 | 4.7点 |

愛用者
軽い飲み口でフルーティー
軽い飲み口でフルーティーですが、洋酒のような酸味があるわけではなく日本酒独特の甘味が強いといった印象です。パッケージもおしゃれで飲みやすいのですが、実はアルコール度数が高いので飲みすぎに注意のお酒です。(Y.K.さん/男性/24歳/会社員)
※各社通販サイトの 2025年03月31日時点 での税込価格
| コスパ | ★★★☆☆ |
|---|---|
| 味・おいしさ | ★★★★☆ |
| 香り・風味 | ★★★★★ |
| 総合評価 | 4.0点 |
| コスパ | ★★★☆☆ |
|---|---|
| 味・おいしさ | ★★★★☆ |
| 香り・風味 | ★★★★★ |
| 総合評価 | 4.0点 |

愛用者
フルーティーで飲みやすい日本酒
親戚からプレゼントしてもらいました。甘くフルーティーな香りが漂い、飲みやすいので、正月以外は日本酒をほとんど飲まなかった私でも毎週のように楽しむようになりました。友人にもすすめたところ「飲みやすくておいしい」と好評でした。どんな料理とも合うので、晩酌の時間が一段と楽しみになりました。(F.R.さん/男性/27歳/会社員)
※各社通販サイトの 2025年03月31日時点 での税込価格
| コスパ | ★★★★☆ |
|---|---|
| 味・おいしさ | ★★★★☆ |
| 香り・風味 | ★★★★★ |
| 総合評価 | 4.3点 |
| コスパ | ★★★★☆ |
|---|---|
| 味・おいしさ | ★★★★☆ |
| 香り・風味 | ★★★★★ |
| 総合評価 | 4.3点 |
初心者向け日本酒のおすすめ|甘口 初心者でも飲みやすい!
甘口、辛口別に、日本酒初心者向けのおすすめ商品を紹介していきます。まずは、甘口からチェックしていきましょう。
上品な甘みと濃厚な味わいが魅力的なお酒
「極上の甘口」はアジア国際美酒コンテストにて、最高点を獲得した商品に与えられるゴールデンドラゴン賞を受賞したお酒。原料米を通常よりも1.4倍使用して製造しているので、よりお米の甘みを感じられる芯のある味わいに仕上がっています。
その味わいは飲んだあとの爽やかな後味を引き連れて来てくれるので、味の変化としても面白い一本です。海外での高い評価を得た味わいを、是非ご自宅でお楽しみ下さい。
※Amazonは1本、楽天市場・Yahoo!ショッピングは6本の価格です。
※各社通販サイトの 2025年03月31日時点 での税込価格
| 生産地 | - |
|---|---|
| アルコール度数 | 10度 |
| 内容量 | 720ml |
| 日本酒度 | -50 |
| 酸度 | 2.3 |
| 生産地 | - |
|---|---|
| アルコール度数 | 10度 |
| 内容量 | 720ml |
| 日本酒度 | -50 |
| 酸度 | 2.3 |

マスカットのようなフルーティーな香り
アルコール度数が5%と低いので、アルコールがあまり飲めない方にもおすすめ。マスカットのようなフルーティーな香り、甘味もありながらシュワッと立ち上る泡がすっきりとした後口に導いてくれます。
従来の『すず音』は薄にごりですが、『すず音Wabi』は透明なタイプ。2015年、2018年と2度にわたり、IWC(インターナショナルワインチャレンジ)スパークリング清酒部門にて、最高賞のトロフィーを受賞しています。
※各社通販サイトの 2025年03月31日時点 での税込価格
| 生産地 | 宮城県 |
|---|---|
| アルコール度数 | 5度 |
| 内容量 | 375ml |
| 日本酒度 | - |
| 酸度 | - |
| 生産地 | 宮城県 |
|---|---|
| アルコール度数 | 5度 |
| 内容量 | 375ml |
| 日本酒度 | - |
| 酸度 | - |
初心者向け日本酒のおすすめ|辛口 慣れてきたら挑戦!
ここからは、初心者におすすめの辛口の日本酒をご紹介します。
古来伝承の生酛造りが織り成す至高の原酒
伝統の技術を現在に至るまで受け継いできた菊正宗嘉宝蔵。「嘉宝蔵 雅 特別純米酒」製造の際には丹波杜氏である「小島喜代輝」の指導を受け、古来より伝承の技である「生酛造り」によって特別純米酒の原酒を提供できるに至りました。
酒米には好適米の最高峰である「山田錦」を100%使用しているほかに、仕込みの水には灘の名水である「宮水」を使用しています。菊正宗が自信を持って送り出した日本酒です。
※各社通販サイトの 2025年03月31日時点 での税込価格
| 生産地 | - |
|---|---|
| アルコール度数 | 17.5% |
| 内容量 | 1800ml |
| 日本酒度 | +6 |
| 酸度 | - |
| 生産地 | - |
|---|---|
| アルコール度数 | 17.5% |
| 内容量 | 1800ml |
| 日本酒度 | +6 |
| 酸度 | - |
高い香りとしっかりとした味わいが絶妙
すっきりとした後味が特徴的な辛口の純米大吟醸です。主張し過ぎない香りが飲む際に邪魔にならず、それでいてまったく雑味を感じさせない飲み口。さわやかな後味は、合わせたお料理をさらに引き立ててくれます。
すっきりとした飲み口とほかを邪魔しない後味のため、茶事の席でもふるまわれるほどです。適度に冷やした状態で楽しみつつ、ぬる燗でもおいしくいただけるでしょう。
※各社通販サイトの 2025年03月31日時点 での税込価格
| 生産地 | - |
|---|---|
| アルコール度数 | 15.8度 |
| 内容量 | 720ml |
| 日本酒度 | +5 |
| 酸度 | 1.3 |
| 生産地 | - |
|---|---|
| アルコール度数 | 15.8度 |
| 内容量 | 720ml |
| 日本酒度 | +5 |
| 酸度 | 1.3 |
米の旨味とキリッと締まる後味の良さ
純米酒の持ち味である、お米の味わいを最大限に活かした辛口の日本酒『鶴齢 雪男 純米酒』。青木酒造はコシヒカリや豪雪地帯でも有名な、新潟県は魚沼地方に位置する酒蔵です。その歴史は古く創業は1717年、300年という長きに渡って酒造りを営んでいます。
雪国でしか得られない大自然の恵みと、越後杜氏の伝統的な技が合わさることで、素晴らしい味わいのお酒が誕生しました。酒米の持つ本来の旨味をしっかりと出した「淡麗辛口」を是非ご堪能ください。
※各社通販サイトの 2025年03月31日時点 での税込価格
| 生産地 | 新潟県 |
|---|---|
| アルコール度数 | 15度以上16度未満 |
| 内容量 | 720ml |
| 日本酒度 | +12 |
| 酸度 | 1.2 |
| 生産地 | 新潟県 |
|---|---|
| アルコール度数 | 15度以上16度未満 |
| 内容量 | 720ml |
| 日本酒度 | +12 |
| 酸度 | 1.2 |
初心者向け日本酒のおすすめ|飲み比べセット プレゼント用にも!
自分用でもプレゼント用でも楽しめる! おすすめの日本酒飲み比べセットをご紹介します。
獺祭の「磨き」を3種類試せる贅沢なセット
言わずと知れた人気商品の獺祭、その「磨き」シリーズの23%、39%、45%(精米配合)の3品を飲み比べられるお試しセットです。この数字は精米したときにお米が残っている割合(精米歩合)をあらわしており、数字が小さいほどお米のごく一部のみ使用している贅沢な品といえます。
ただし、数字が大きいからおいしくないということはなく、数字が大きければお米の味や香りを楽しむことができ、数字が小さいほど香りが華やかでフルーティに変化していきます。その変化を段階ごとに味わえる贅沢なセットといえるでしょう。
※各社通販サイトの 2025年03月31日時点 での税込価格
| 生産地 | 山口県 |
|---|---|
| アルコール度数 | 16度 |
| 内容量 | 180ml×3本(各1種ずつ) |
| 日本酒度 | - |
| 酸度 | - |
| 生産地 | 山口県 |
|---|---|
| アルコール度数 | 16度 |
| 内容量 | 180ml×3本(各1種ずつ) |
| 日本酒度 | - |
| 酸度 | - |
人気銘柄からここでしか味わえない銘柄まで
新潟県、富山県、石川県の純米大吟醸3種を飲み比べできるセットです。日本酒初心者から、日本酒好きの方まで幅広く楽しめる商品。人気の『上善如水』、ここでしか味わえない『幻の瀧』、隠れた逸品『加賀ノ月』という3種類が入っています。
すべて300mlなので、ちょうどよい容量で飲み切りやすいですよ。
※各社通販サイトの 2025年03月31日時点 での税込価格
| 生産地 | 上善如水:新潟県、幻の瀧:富山県、加賀ノ月:石川県 |
|---|---|
| アルコール度数 | 上善如水:15度以上16度未満、幻の瀧:15度、加賀ノ月:15.5度 |
| 内容量 | 300ml×3本(各1種ずつ) |
| 日本酒度 | 上善如水:+2、幻の瀧:+4、加賀ノ月:+3.5 |
| 酸度 | 上善如水:1.5、幻の瀧:1.5、加賀ノ月:1.6 |
| 生産地 | 上善如水:新潟県、幻の瀧:富山県、加賀ノ月:石川県 |
|---|---|
| アルコール度数 | 上善如水:15度以上16度未満、幻の瀧:15度、加賀ノ月:15.5度 |
| 内容量 | 300ml×3本(各1種ずつ) |
| 日本酒度 | 上善如水:+2、幻の瀧:+4、加賀ノ月:+3.5 |
| 酸度 | 上善如水:1.5、幻の瀧:1.5、加賀ノ月:1.6 |
「初心者向けの日本酒」のおすすめ商品の比較一覧表
| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 生産地 | アルコール度数 | 内容量 | 日本酒度 | 酸度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大関『極上の甘口』 |

|
※各社通販サイトの 2025年03月31日時点 での税込価格 |
上品な甘みと濃厚な味わいが魅力的なお酒 | - | 10度 | 720ml | -50 | 2.3 |
| 一ノ蔵『すず音Wabi』 |

|
※各社通販サイトの 2025年03月31日時点 での税込価格 |
マスカットのようなフルーティーな香り | 宮城県 | 5度 | 375ml | - | - |
| 菊正宗酒造『嘉宝蔵 雅』 |

|
※各社通販サイトの 2025年03月31日時点 での税込価格 |
古来伝承の生酛造りが織り成す至高の原酒 | - | 17.5% | 1800ml | +6 | - |
| 山本本家『上撰 純米大吟醸 松の翠』 |

|
※各社通販サイトの 2025年03月31日時点 での税込価格 |
高い香りとしっかりとした味わいが絶妙 | - | 15.8度 | 720ml | +5 | 1.3 |
| 青木酒造『鶴齢 雪男 純米酒』 |

|
※各社通販サイトの 2025年03月31日時点 での税込価格 |
米の旨味とキリッと締まる後味の良さ | 新潟県 | 15度以上16度未満 | 720ml | +12 | 1.2 |
| 旭酒造『獺祭(だっさい) おためしセット』 |

|
※各社通販サイトの 2025年03月31日時点 での税込価格 |
獺祭の「磨き」を3種類試せる贅沢なセット | 山口県 | 16度 | 180ml×3本(各1種ずつ) | - | - |
| 方舟『純米大吟醸 飲み比べセット』 |

|
※各社通販サイトの 2025年03月31日時点 での税込価格 |
人気銘柄からここでしか味わえない銘柄まで | 上善如水:新潟県、幻の瀧:富山県、加賀ノ月:石川県 | 上善如水:15度以上16度未満、幻の瀧:15度、加賀ノ月:15.5度 | 300ml×3本(各1種ずつ) | 上善如水:+2、幻の瀧:+4、加賀ノ月:+3.5 | 上善如水:1.5、幻の瀧:1.5、加賀ノ月:1.6 |
通販サイトの最新人気ランキングを参考にする 初心者向けの日本酒の売れ筋をチェック
Amazon、楽天市場での初心者向けの日本酒の売れ筋ランキングも参考にしてみてください。
※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。
日本全国・都道府県別 日本酒のおすすめ特集!
各地方ごとに特色ある地酒が紹介されていますので、ぜひ参考にしてみてください。各都道府県をクリックするとおすすめの日本酒記事に飛べます。
北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島
茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川
富山 石川 福井 山梨 長野 新潟
岐阜 静岡 愛知 三重
滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山
鳥取 島根 岡山 広島 山口
徳島 香川 愛媛 高知
福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島
沖縄
日本酒の飲み方・割り方
日本酒の楽しみ方として、「熱燗」や「冷酒」、なにかと割って飲むなどがあります。初心者さんにおすすめの飲み方をご紹介します。
甘みが広がる「熱燗(あつかん)」
温めたお酒のことを「熱燗」という、と思っている方も多いかもしれませんが、実は温度によってきちんと呼び分けされています。代表的なもので、「熱燗」は50度程度、45度が「上燗(じょうかん)」、40度が「ぬる燗」です。
日本酒は、温度によって香りや飲み口が変わってきます。温めることで香りが広がり、飲み口はまろやか、甘みが広がり飲みやすいですよ。
キリっとした飲み口の「冷酒(れいしゅ)」
冷たく冷やした日本酒を、「冷酒(れいしゅ)」といいます。温めたお酒同様に温度によって呼び分けされていて、15度が「涼冷え(すずびえ)」、10度が「花冷え(はなびえ)」、5度が「雪冷え(ゆきびえ)」です。ちなみに、「冷や(ひや)」は冷たくしたお酒ではなく、常温のお酒を指すので要注意。
冷やすほどに香りがおさえられ、キリっとシャープな飲み心地になります。すっきりした味わいを楽しみたい方には、冷酒がおすすめです。
日本酒を楽しむ割り方
「日本酒を割るの?」と思う方もいるかもしれませんが、日本酒独特の香りや高いアルコールが苦手な方にはとくに飲みやすくておすすめです。代表的なのは、「水割り」や「お湯割り」。いずれも酒8に対して2くらいの割合で割ってみてください。
ほかにも、お茶で割ったり、ビールで割ったり、最近ではいろいろな飲み方も浸透しています。好みの割り方を見つけてみてくださいね。
日本酒をもっと深く知りたい方へ
日本酒を学べる書籍があるのでご紹介します。
東京書籍『日本酒手帳』
出張や旅先で地酒を楽しみたい時の強い味方!
日本酒ファンであれば、仕事や旅行などで地酒を味わいたいところでしょう。「日本酒手帳」なら自分の好みに合った銘柄を見つけたいときに、日本酒の基本的な情報を知ることができます。各都道府県の有名な銘柄の特長などを把握したり、そのほかのラインナップもおさえることも。
さらには香味がわかる4タイプの分類をはじめ、各情報が満載です。初心者からベテランまで幅広い層の方達が便利に使える一冊となっています。
正規販売店で購入するのが安心 和酒コーディネーターからのアドバイス
日本酒は、その希少性などから、定価に金額を上乗せして転売するサイトなどを見かけることがあります。その場合は正規販売店ではない可能性が高く、価格だけでなく品質の維持管理上でも安心とは言い切れません。
正規ルートで販売している優良店で購入し、確かな品質の日本酒の、真のおいしさを楽しんでいただくことをおすすめします。
そのほかの日本酒もチェック 【関連商品】
ポイントを押さえればぴったりの日本酒を選べる
初心者におすすめの日本酒の選び方とおすすめ商品をご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?
日本酒に不慣れな方でも、ラベルや見た目の好みにこだわったり、詳しい人にアドバイスをもらったりすれば、自分にぴったりのものを選ぶことができます。この記事を参考にして、お気に入りの1本を見つけてくださいね!
おすすめ商品・口コミの投稿はこちら
※メーカーや販売店の方は、ページ下部の「お問い合わせはこちら」から商品情報をお送りください。
ユーザーのおすすめ商品や口コミ情報は、マイナビおすすめナビを閲覧したユーザー、マイナビニュース会員、外部パートナー企業と契約する一般ユーザーからの投稿をもとにしています。
◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。