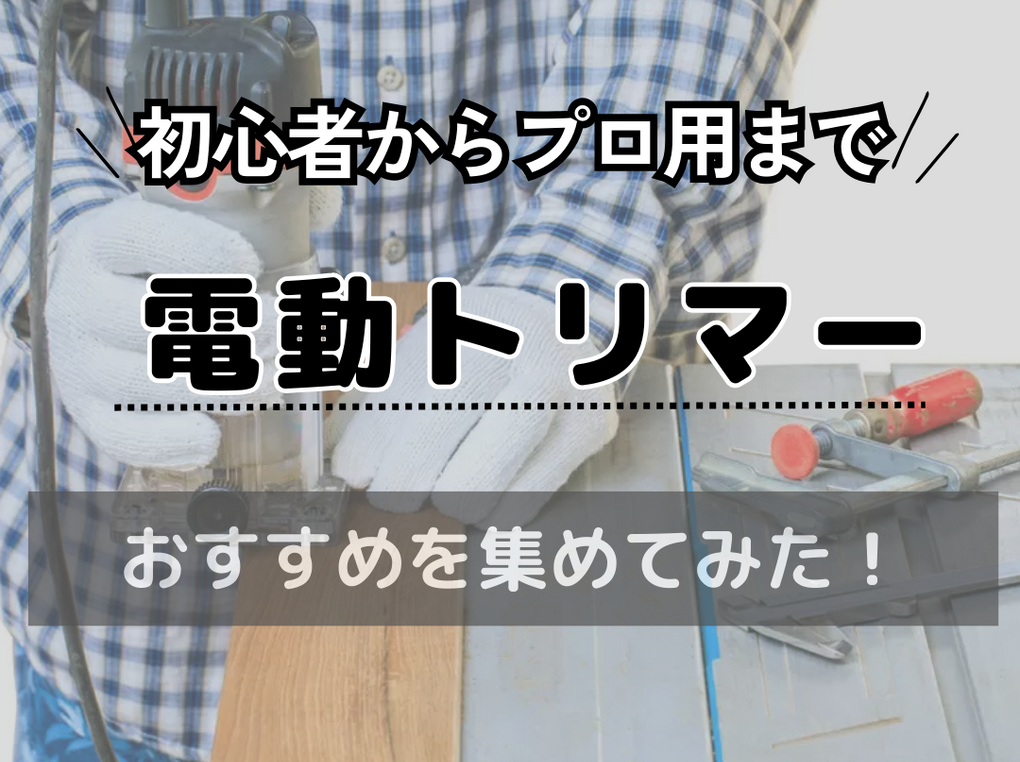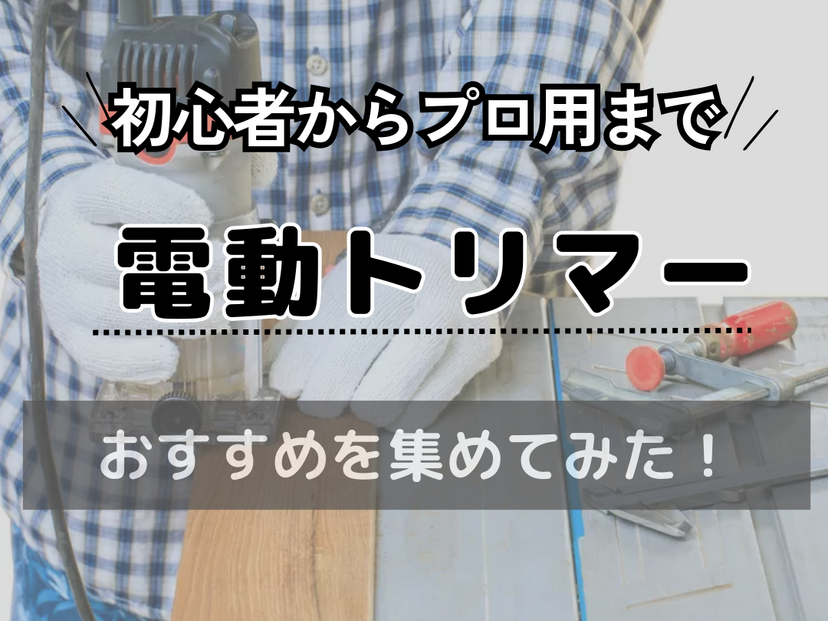| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 重さ | 回転数 | ビット軸径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RYOBI(リョービ)『MTR-42』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格 |
初心者にも使いやすいエントリーモデル | 1.1kg | 32,000min-1(回転/分) | 6mm |
| マキタ(Makita) 『充電式トリマ(RT40DRG)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格 |
機能充実の充電式電動トリマー | 1.7kg | 10,000~28,000min-1(回転/分) | 6mm、8mm |
| BOSCH(ボッシュ)『PMR 500』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格 |
ハイパワーで精度も高いボッシュの電動トリマー | 1.5kg | 30,000min-1(回転/分) | 6mm |
| 高儀『EARTH MAN 電動トリマ TR-400A』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格 |
圧倒的な安さで人気の高儀のトリマー | 1.4kg | 約32,000min-1(回転/分) | 6mm |
| 京セラ『電子トリマ ATRE-60V』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格 |
プロも満足! 電子制御の高性能トリマー | 1.2kg | 16,000~30,000min-1(回転/分) | 6mm |
| HiKOKI(ハイコーキ)『トリマ M6SB』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格 |
角度調整ができる便利な電動トリマー | 1.4kg | 30,000min-1(回転/分) | 6mm |
| makita(マキタ)『充電式トリマ RT50DZ』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格 |
取り回し抜群のバッテリータイプの電動トリマー | 1.9kg | 10,000~30,000min-1(回転/分) | 6mm、8mm |
| Black+Decker(ブラック・アンド・デッカー)『ERH183』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格 |
小作業に役立つ低価格トリマー | 約0.4kg | 9000 | 6mm |
| イチネン『RELIEF(リリーフ) トリマー TRS-340』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格 |
値段は安く、シンプルな作り!初心者向け。 | 約1.5kg | 30000 | 6mm |
| BOSCH(ボッシュ)『GKF10.8V-8H』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格 |
コードレスで使える、高級感のある電動トリマー | 約1.3kg | 13000 | 6mm |
| Kyocera(キョウセラ)『ATRE40』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格 |
「ソフトスタート機能」が最大の特徴のトリマー | 1.3kg | 30000min-1 | 6mm |
| makita(マキタ)『M373』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格 |
オーソドックスで安定の電動トリマー | 1.4kg | 35000 | 6mm |
電動トリマーとは
電動トリマーとは、木材の面取りなどのトリミングや溝切りを行なうための電動工具です。トリマービットをつけかえることで、さまざまなかたちの加工ができます。
電動トリマーを使うと、DIY作品の仕上がりに違いが生まれます。使いこなすには少し慣れが必要ですが、DIYの仕上がりを美しくするために使ってみましょう。
電動トリマーの選び方
それでは、電動トリマーの基本的な選び方を見ていきましょう。
【1】取り付け径
【2】回転数が変更可能か
【3】ベースプレート・加工精度
【4】電源をチェック
【5】便利な機能
上記のポイントをおさえることで、より具体的にほしい機能を知ることができます。一つひとつ解説していきます。
【1】取り付け径をチェック
市販のトリマー刃は基本的に6mm軸の商品が多いため、電動トリマーを購入される際は取り付け径が6mmの機種を選ぶようにしましょう。トリマー刃はいろいろなメーカーが販売を行なっており、刃物形状もひじょうにさまざまな種類があります。
そのためトリマーを最大限活用するなら、いろいろな刃物を取り付けることができる6mm軸がおすすめです。海外ブランドや安価なトリマーの場合、軸径が特殊な場合もあります。念のため確認するように注意しましょう。
【2】回転数が変更可能かチェック
電動トリマーは刃物を回転させながら削り取る工具です。木材に対しての使用が主ですが、一括りに木材と言っても硬い木や柔らかい木があり、硬度により適切な回転数は変わります。
回転数を変更できるタイプのトリマーは、材料の硬さに合わせ、効率よい加工が可能。材料の焦げを予防したり、綺麗な加工面に仕上げることができます。少し価格は上がってしまいますが、回転数の変更ができるトリマーをおすすめします。
【3】ベースプレート・加工精度をチェック
電動トリマーは。加工材にベースプレートを押し当てながら削る電動工具なので、接地するプレートの作りが直接、加工精度に影響します。また、トリマー刃の出し具合の微調整もベースプレートの上下で行ないます。
つまみを回してギアにより上下させるタイプだと、刃の出し具合の微調整を行ないやすいです。本体とプレートの固定が甘いと、加工中にプレートがズレて刃が設定した出し幅よりも出てしまいます。プレートの固定がしっかりできる機種を選ぶ方がいいでしょう。
【4】電源をチェック
電動トリマーの電源タイプには「コード式」と「充電式」があります。それぞれ特徴が異なるので、使いやすいものを選びましょう。
コード式:長時間の作業が必要な方に
コード式のメリットは、バッテリー残量を気にしなくてよいので、長時間でも作業できる点です。コードが届く範囲でしか作業できないという制約はありますが、バッテリー切れや充電などを気にしなくて済みます。
価格も充電式のものより安い傾向にあり、長時間じっくり作業したい人やコストを掛けずに電動トリマーを購入したい人にぴったりです。
充電式:取り回しに便利
充電式のメリットは、持ち運びがしやすく、電源を気にしなくてよい点です。充電さえしておけば、どこでも作業できます。コードがないため、移動範囲の制限もありません。
ただし、長時間作業するときは、バッテリー切れを起こしてしまうおそれがあります。価格もコード式より高価なものが多いです。
取り回しやすさや持ち運びやすさを重視する人に適しています。
【5】便利な機能をチェック
電動トリマーを選ぶときは、便利な機能にも注目してみましょう。
(a)電子制御機能:DIY初心者におすすめ
DIY初心者の人は、電子制御機能つきの電動トリマーを選ぶとよいでしょう。電子制御機能は、自動で刃の回転数を調節してくれる機能です。
ブレることなく安定して使えるので、初心者でもらくに木材の断面を加工できます。
回転数が一定になることで、力のコントロールもしやすくなるので、電動トリマーの扱いに慣れていない人はぜひ電子制御機能つきのものを選んでください。
(b)吸塵機能:削りかすを取り除いて作業がラク
木材を削ると、どうしても削りかすが手元に溜まります。溜まった削りかすをそのままにしておくと作業ミスにつながってしまうこともあるので、注意が必要です。
削りかすをこまめに取り除くのが面倒な人は、吸塵機能つきの電動トリマーを選ぶとよいでしょう。削りかすを吸い込んでくれるので、手元に削りかすが溜まらず、見やすいです。
使い終わったあとの掃除もかんたんにできます。
(c)静音機能:作業時の音対策に便利
電動トリマーの音が気になる人は、静音機能がついたものを選びましょう。
電動トリマーは、刃を高速で回転させて木材を削る道具なので、どうしても作業音は発生してしまいます。人によってはうるさいと感じることもあるでしょう。
しかし、静音機能がついた電動トリマーであれば、ある程度音を抑えて作業ができます。騒音が気になる人はぜひチェックしてみてください。
エキスパートのアドバイス
電動トリマーで、ワンランク上のDIYにチャレンジ
電動トリマーは、持っているとDIYのクオリティーや作業効率がぐっと上がる工具。意外と知られていませんが、他の工具ではできない加工がこなせます。
使い慣れるまでには少し練習が必要ですが、紹介したようないい電動トリマーは上達するのも早く、精度も出しやすいため、おすすめです。お気に入りのトリマーを見つけて、楽しくワンランク上のDIYにチャレンジしてみましょう。
ユーザーが選んだイチオシ5選
ここからは、電動トリマーを愛用しているユーザーがイチオシする商品を紹介。5点満点で「コスパ」「機能性」「使いやすさ」を評価してもらいました。イチオシのポイント、おすすめする理由や口コミもぜひ参考にしてください!
その他にもおすすめしたい商品があるよという方は、ぜひ記事の下部にある投稿フォームからご紹介をお願いします。

愛用者
コスパ良しの電動トリマー
電動トリマーは2台目の購入です。回転が安定していて問題なく使うことができます。さらにアタッチメントもいろいろとついていて、これだけのセットにしてはかなり良心的な価格設定だと思います。コスパ良いと思います。(R.F.さん/男性/39歳/会社員)
【デメリットや気になった点】
使用していると前に使っていた製品よりも熱を帯びるのが早い気がします。発熱が気になって長時間使用ができません。(R.F.さん/男性/39歳/会社員)
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格
| コスパ | ★★★★☆ |
|---|---|
| 機能性 | ★★★★☆ |
| 使いやすさ | ★★★★☆ |
| 総合評価 | 4.0点 |
| コスパ | ★★★★☆ |
|---|---|
| 機能性 | ★★★★☆ |
| 使いやすさ | ★★★★☆ |
| 総合評価 | 4.0点 |

愛用者
日曜大工には十分です
日曜大工で気が向いた時にいろいろと作っています。今回はBBQ用のテーブルを作ろうと思い、トリマーを初めて導入しました。使い方は簡単だったのですぐに使うことができ、出来上がりもきれいで、バリは残っていませんでした。(M.F.さん/女性/45歳/主婦)
【デメリットや気になった点】
結構大きな音がします。集合住宅のベランダで作業したり、一軒家でも夜間に使用したりするのは避けるべきだと思います。(M.F.さん/女性/45歳/主婦)
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格
| コスパ | ★★★★☆ |
|---|---|
| 機能性 | ★★★★☆ |
| 使いやすさ | ★★★★☆ |
| 総合評価 | 4.0点 |
| コスパ | ★★★★☆ |
|---|---|
| 機能性 | ★★★★☆ |
| 使いやすさ | ★★★★☆ |
| 総合評価 | 4.0点 |

愛用者
安定動作で満足しています
聞いたことがあるメーカーだったのでこの製品にしました。あまり詳しくなく、初心者の日曜大工レベルなので詳しくはわかりませんが、合板のトリミングが上手にできました。パワーも問題なさそうで取り扱いも簡単でした。(A.F.さん/女性/38歳/自営業)
【デメリットや気になった点】
ちょっと細かいですが、高さ調整のためのネジがまわしにくく調整するのに手間がかかるなと思います。それほど多用するわけではないので我慢できるレベルではあります。(A.F.さん/女性/38歳/自営業)
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格
| コスパ | ★★★☆☆ |
|---|---|
| 機能性 | ★★★★☆ |
| 使いやすさ | ★★★★☆ |
| 総合評価 | 3.7点 |
| コスパ | ★★★☆☆ |
|---|---|
| 機能性 | ★★★★☆ |
| 使いやすさ | ★★★★☆ |
| 総合評価 | 3.7点 |

愛用者
安い割にそこそこ活躍します
日曜大工で角をけずって丸くしたかったので電動トリマーを購入しました。この製品は電動トリマーの中では安い方だったので、選んだのですが、ガイドもあって簡単にきれいな丸みをつけることができ、満足しています。(K.F.さん/男性/45歳/会社員)
【デメリットや気になった点】
電動工具は仕方のないことかもしれませんが、音が結構大きいです。閑静な住宅街では使用をはばかられるくらいの音がします。(K.F.さん/男性/45歳/会社員)
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格
| コスパ | ★★★★☆ |
|---|---|
| 機能性 | ★★★☆☆ |
| 使いやすさ | ★★★★☆ |
| 総合評価 | 3.7点 |
| コスパ | ★★★★☆ |
|---|---|
| 機能性 | ★★★☆☆ |
| 使いやすさ | ★★★★☆ |
| 総合評価 | 3.7点 |

愛用者
良い買い物でした
電動トリマーがずっと欲しくて、とうとう購入してしまいました。いろいろと製品候補はあったのですが、こちらの製品はトリマービットもきちんと付属しており、しかもケースに収納可能ということで選択しました。使い方も簡単でとくに困惑することなく使用できました。(M.F.さん/男性/40歳/会社員)
【デメリットや気になった点】
ダストフードを使わなければかなり飛び散ります。必ずダストフードで木屑をとりながらしたほうが良いと思います。(M.F.さん/男性/40歳/会社員)
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格
| コスパ | ★★★★☆ |
|---|---|
| 機能性 | ★★★☆☆ |
| 使いやすさ | ★★★☆☆ |
| 総合評価 | 3.3点 |
| コスパ | ★★★★☆ |
|---|---|
| 機能性 | ★★★☆☆ |
| 使いやすさ | ★★★☆☆ |
| 総合評価 | 3.3点 |
電動トリマーのおすすめ12選
続いては、編集部が選んだおすすめ商品を紹介していきます。ぜひ参考にしてくださいね。
初心者にも使いやすいエントリーモデル
固定がかんたんなワンタッチクランプ式のベースを採用した電動トリマーです。ストレートガイド(案内定規)がついているので、長い直線の面取りや溝掘りの直線加工、円切り加工がらくにできます。
スピンドルロックつきで刃ものの交換がかんたんにできるのもポイント。DIY初心者にも使いやすいエントリーモデルです。
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格
| 重さ | 1.1kg |
|---|---|
| 回転数 | 32,000min-1(回転/分) |
| ビット軸径 | 6mm |
| 重さ | 1.1kg |
|---|---|
| 回転数 | 32,000min-1(回転/分) |
| ビット軸径 | 6mm |
機能充実の充電式電動トリマー
すばやく作業ができる充電式の電動トリマーです。14.4Vリチウムイオンバッテリが使い回せます。シャフトロックつきで、スパナが1本あればかんたんにビット交換ができるのもポイントです。
作業に合わせて回転数を無段階に変えられる「速度調整ダイヤル」や、不意の起動を防ぐ「待機スイッチ」など機能も充実。ダストノズルが付属しているので、集塵機にも接続できます。
機能が充実した電動トリマーを探している人は、ぜひチェックしてみてください。
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格
| 重さ | 1.7kg |
|---|---|
| 回転数 | 10,000~28,000min-1(回転/分) |
| ビット軸径 | 6mm、8mm |
| 重さ | 1.7kg |
|---|---|
| 回転数 | 10,000~28,000min-1(回転/分) |
| ビット軸径 | 6mm、8mm |
ハイパワーで精度も高いボッシュの電動トリマー
ボッシュの『PMR 500』は、DIY用としては500Wモーター搭載とパワーが強く、いろいろな木材への加工がスムーズです。電動トリマーには珍しく、ベースプレートはアルミ製のため、強度と精度が高く、長く愛用できます。
切削の深さの調整は専用ダイヤルを回して微調整でき、精度の高い加工が行ないやすいです。本体持ち手部分とベースプレートは、ラバーグリップやくぼみで、持ちやすいように設計されているため、安全に使用することができます。初心者からプロにまでおすすめのトリマーです。
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格
| 重さ | 1.5kg |
|---|---|
| 回転数 | 30,000min-1(回転/分) |
| ビット軸径 | 6mm |
| 重さ | 1.5kg |
|---|---|
| 回転数 | 30,000min-1(回転/分) |
| ビット軸径 | 6mm |
圧倒的な安さで人気の高儀のトリマー
新潟のメーカー・高儀から発売されているこちらの電動トリマーは、圧倒的なコストパフォーマンスで人気の機種。安価ではありますがパワーもあり、必要なガイド類は揃っているので、DIY使用としては問題ありません。
ソフトスタート機能が付いており、始動の際に反動が少ないため初心者の方でも安心して使いやすくなっています。低価格で購入しやすく、収納用のバッグまで付いているので「ちょっと電動トリマーを使ってみたい」というライトユーザーの方におすすめの一台です。
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格
| 重さ | 1.4kg |
|---|---|
| 回転数 | 約32,000min-1(回転/分) |
| ビット軸径 | 6mm |
| 重さ | 1.4kg |
|---|---|
| 回転数 | 約32,000min-1(回転/分) |
| ビット軸径 | 6mm |
プロも満足! 電子制御の高性能トリマー
京セラブランドのこちらの電子トリマーは、非常に高性能で人気です。刃物の回転速度調整や切削の深さの微調整ができ、本体とベースの取り付け部分はアルミダイカスト製で強度と精度も高いです。
一番の特徴は電子制御により、刃物に負荷がかかっても刃の回転速度が落ちず快適で綺麗な加工が可能なところ。プロの現場でも満足できる高性能トリマーで使い心地がよく、安全性や精度も高いためどんな方にもおすすめの一台です。
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格
| 重さ | 1.2kg |
|---|---|
| 回転数 | 16,000~30,000min-1(回転/分) |
| ビット軸径 | 6mm |
| 重さ | 1.2kg |
|---|---|
| 回転数 | 16,000~30,000min-1(回転/分) |
| ビット軸径 | 6mm |
角度調整ができる便利な電動トリマー
こちらの電動トリマーは購入した際に、本体の角度を調整することができるベースプレートが装備されます。この角度を変えることで、ストレート刃を使用して角度のついた溝切りや面取りができ、通常の加工ではできないような幅広い加工が可能です。
刃の出し具合もダイヤル式のため微調整が可能。本体は小型で軽く、DIY用としても、非常に使いやすい機種となっています。
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格
| 重さ | 1.4kg |
|---|---|
| 回転数 | 30,000min-1(回転/分) |
| ビット軸径 | 6mm |
| 重さ | 1.4kg |
|---|---|
| 回転数 | 30,000min-1(回転/分) |
| ビット軸径 | 6mm |
取り回し抜群のバッテリータイプの電動トリマー
電動トリマーはパワーが必要な工具のため、一般的にはコード式が多く発売されていますが、マキタから発売されているこちらのトリマーは珍しい18Vのバッテリータイプとなっています。大物の加工などで、移動距離が大きい際にもこのバッテリートリマーは圧倒的な作業性を発揮してくれます。バッテリー式ですがパワーはコード式に劣らず非常に強く、効率的に作業を行なうことができます。
速度調整機能付きで、刃の出し具合も微調整を行ないやすく、本体性能もハイクオリティーの一台です。マキタのバッテリートリマーは、コンセントのない場所や、大物の加工などさまざまなシーンで活躍してくれるおすすめです。
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格
| 重さ | 1.9kg |
|---|---|
| 回転数 | 10,000~30,000min-1(回転/分) |
| ビット軸径 | 6mm、8mm |
| 重さ | 1.9kg |
|---|---|
| 回転数 | 10,000~30,000min-1(回転/分) |
| ビット軸径 | 6mm、8mm |
小作業に役立つ低価格トリマー
こちらのトリマーは、小作業専用につくられた製品。そのため、価格帯がほかの製品より低めで比較的手に入れやすいのがポイント。回転数などを鑑みると少々物足りないかもしれませんが、「ちょっとした箇所だけ整えたい」「細かい作業をしたい」という方にはぴったりの電動トリマーです。手にもなじみやすく、コスパの面では◎な商品です。
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格
| 重さ | 約0.4kg |
|---|---|
| 回転数 | 9000 |
| ビット軸径 | 6mm |
| 重さ | 約0.4kg |
|---|---|
| 回転数 | 9000 |
| ビット軸径 | 6mm |
値段は安く、シンプルな作り!初心者向け。
トリマーのなかでも比較的シンプルなつくりとなっているのがこちらの商品です。刃先には透明なベースが付いており、初心者でも安心して使うことができます。加えてソフトスタート機能がついており、従来のトリマーと比べるとコスパがいいのが特徴的。はじめての電動トリマーを探している方や、まずはお試しで使ってみたい方におすすめ。
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格
| 重さ | 約1.5kg |
|---|---|
| 回転数 | 30000 |
| ビット軸径 | 6mm |
| 重さ | 約1.5kg |
|---|---|
| 回転数 | 30000 |
| ビット軸径 | 6mm |
コードレスで使える、高級感のある電動トリマー
こちらの電動トリマーは、小型でコードレスという非常に便利な商品です。コードが邪魔をせず可動域が広がるほか、女性の方でも比較的使いやすい仕様となっています。さらに、「ドロップシャットダウン機能」という、誤って落としてしまった際に停止してくれる優れた機能がついています。少々値は張りますが、快適な使い心地を求める方にはおすすめ。
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格
| 重さ | 約1.3kg |
|---|---|
| 回転数 | 13000 |
| ビット軸径 | 6mm |
| 重さ | 約1.3kg |
|---|---|
| 回転数 | 13000 |
| ビット軸径 | 6mm |
「ソフトスタート機能」が最大の特徴のトリマー
電動トリマーを使用するうえで悩みの種となりがちなのが、「縦横にぶれやすい」ことです。こちらの電動トリマーには「ソフトスタート機能」がついており、ブレづらく緩やかに刃を進めることが可能。持ち手がソフトグリップとなっており、持ちやすいのも特徴的です。ある程度電動トリマーを使用しており、アップデートを考えている方などにおすすめ。
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格
| 重さ | 1.3kg |
|---|---|
| 回転数 | 30000min-1 |
| ビット軸径 | 6mm |
| 重さ | 1.3kg |
|---|---|
| 回転数 | 30000min-1 |
| ビット軸径 | 6mm |
オーソドックスで安定の電動トリマー
掃除機なども有名なMakitaから、比較的リーズナブルな電動トリマーが販売されています。回転数が多くDIYに適しているうえに、ソフトグリップや透明ベースなど装備も充分です。オーソドックスな電動トリマーともいえるため、初めての購入を考えている方などにもおすすめ。緑のカラーもおしゃれで、デザイン性も◎です。
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格
| 重さ | 1.4kg |
|---|---|
| 回転数 | 35000 |
| ビット軸径 | 6mm |
| 重さ | 1.4kg |
|---|---|
| 回転数 | 35000 |
| ビット軸径 | 6mm |
「電動トリマー」のおすすめ商品の比較一覧表
| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 重さ | 回転数 | ビット軸径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RYOBI(リョービ)『MTR-42』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格 |
初心者にも使いやすいエントリーモデル | 1.1kg | 32,000min-1(回転/分) | 6mm |
| マキタ(Makita) 『充電式トリマ(RT40DRG)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格 |
機能充実の充電式電動トリマー | 1.7kg | 10,000~28,000min-1(回転/分) | 6mm、8mm |
| BOSCH(ボッシュ)『PMR 500』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格 |
ハイパワーで精度も高いボッシュの電動トリマー | 1.5kg | 30,000min-1(回転/分) | 6mm |
| 高儀『EARTH MAN 電動トリマ TR-400A』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格 |
圧倒的な安さで人気の高儀のトリマー | 1.4kg | 約32,000min-1(回転/分) | 6mm |
| 京セラ『電子トリマ ATRE-60V』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格 |
プロも満足! 電子制御の高性能トリマー | 1.2kg | 16,000~30,000min-1(回転/分) | 6mm |
| HiKOKI(ハイコーキ)『トリマ M6SB』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格 |
角度調整ができる便利な電動トリマー | 1.4kg | 30,000min-1(回転/分) | 6mm |
| makita(マキタ)『充電式トリマ RT50DZ』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格 |
取り回し抜群のバッテリータイプの電動トリマー | 1.9kg | 10,000~30,000min-1(回転/分) | 6mm、8mm |
| Black+Decker(ブラック・アンド・デッカー)『ERH183』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格 |
小作業に役立つ低価格トリマー | 約0.4kg | 9000 | 6mm |
| イチネン『RELIEF(リリーフ) トリマー TRS-340』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格 |
値段は安く、シンプルな作り!初心者向け。 | 約1.5kg | 30000 | 6mm |
| BOSCH(ボッシュ)『GKF10.8V-8H』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格 |
コードレスで使える、高級感のある電動トリマー | 約1.3kg | 13000 | 6mm |
| Kyocera(キョウセラ)『ATRE40』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格 |
「ソフトスタート機能」が最大の特徴のトリマー | 1.3kg | 30000min-1 | 6mm |
| makita(マキタ)『M373』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格 |
オーソドックスで安定の電動トリマー | 1.4kg | 35000 | 6mm |
各通販サイトのランキングを見る 電動トリマーの売れ筋をチェック
Amazon、楽天市場での電動トリマーの売れ筋ランキングも参考にしてみてください。
※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。
電動トリマーの使い方
電動トリマーの使い方をかんたんに説明します。購入する前に使い方のポイントを押さえておきましょう。
削りたい形状に合うビットに交換して使おう
電動トリマーを使うときは、溝彫りや溝切り、溝加工など、行ないたい作業に合わせてトリマービットを交換しましょう。トリマービットとひと口に言っても、面取り用に角度がついたビットもあれば、まっすぐに削っていくのに適したストレートビットもあります。
作業に適したビットに交換したら、少しずつ木材を削っていくのもポイントです。木材を削るときはビットを通じて負荷がかかり、負荷が重くなりすぎるとキックバックなど事故が起こりやすくなります。
高さや位置調節
電動トリマーで木材を削るときは、トリマーについている目盛りを目安に高さや位置を調節しましょう。ストレートビットで溝を掘るときは、目盛りを見ながら少しずつ削っていくことが美しく仕上げるポイントです。
面取りをするときは、基準となる木材の表面に位置を合わせます。位置合わせに失敗すると、表面に段差ができてしまうので注意してください。
キックバック対策
電動トリマーを使うときは、キックバック対策も忘れずに行ないましょう。キックバックとは、切断するものとトリマーの刃がぶつかってしまうことをいいます。大きなケガや事故につながることもあるので、電動トリマーを使うときは取扱説明書をよく読んで、キックバック対策を行なってください。
キックバックを防ぐには、ビットをプレート面から出し過ぎないことと、ジグを使って跳ね返りを防ぐことが重要です。
【関連記事】そのほかの関連アイテムもチェック
まとめ|自分にピッタリの商品を選ぼう
この記事では、電動トリマーの選び方とおすすめの商品を紹介しました。刀の長さや回転数、便利な機能など選ぶ際のポイントはたくさんありますマキタやリョービ、ボッシュなど人気メーカーからさまざまなタイプの電動トリマーが販売されているので、自分にとって使いやすいものを探してくださいね。
また、電動トリマーを上手に使ってDIY初心者の方でも作るものの仕上がりにこだわりましょう!
おすすめ商品・口コミの投稿はこちら
※メーカーや販売店の方は、ページ下部の「お問い合わせはこちら」から商品情報をお送りください。
ユーザーのおすすめ商品や口コミ情報は、マイナビおすすめナビを閲覧したユーザー、マイナビニュース会員、外部パートナー企業と契約する一般ユーザーからの投稿をもとにしています。
◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。