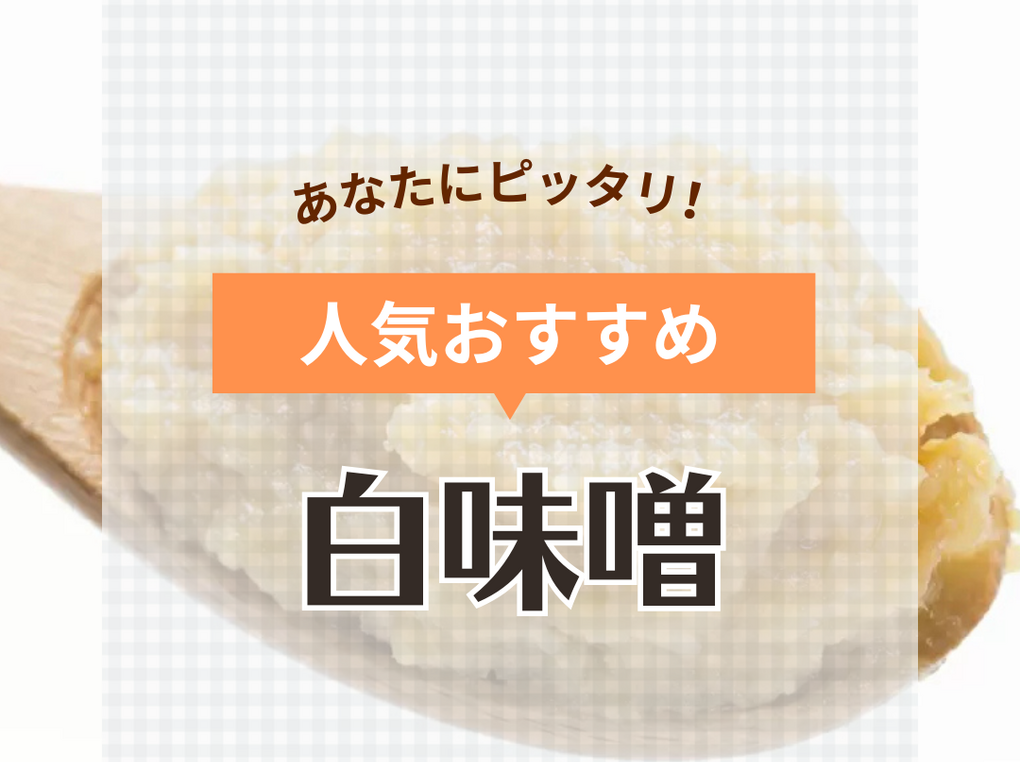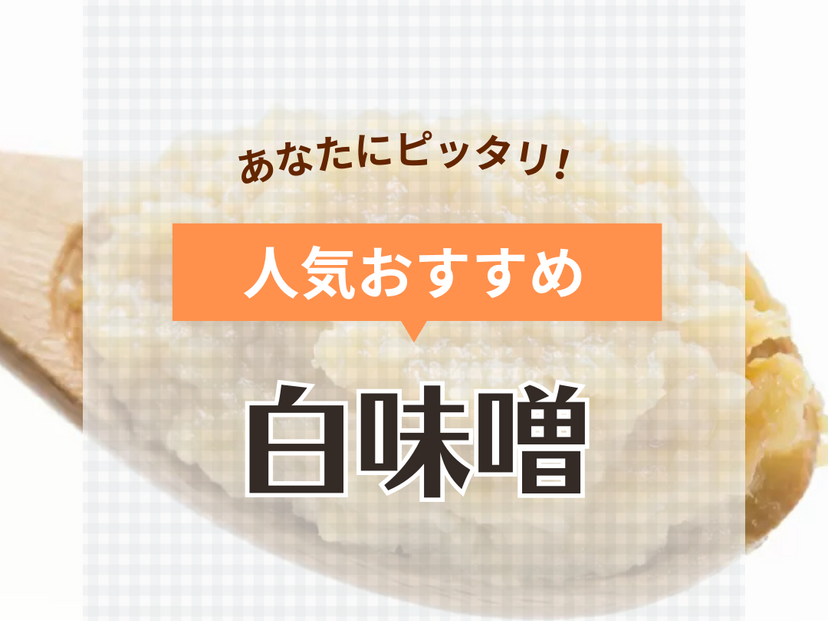| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 生産地 | 原材料 | 内容量 | 麹歩合 | 塩分量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸新本家『白みそ』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格 |
白味噌初心者におすすめな長期熟成の一品 | 和歌山県 | 北海道産丸大豆、国産米、長崎の塩、酒精 | 400g/950g | - | 10% |
| しま村『しま村の白粒味噌』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格 |
西京漬けに使いたい、京都の粒味噌 | 京都 | 米、大豆、食塩、水飴、酒精 | 1kg | - | - |
| 石野味噌『石野白味噌』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格 |
長い歴史をもつ白味噌本場の味! | 京都 | 米、大豆、食塩、酒精、ビタミンB2 | 500g | - | 4.83g(100gあたり) |
| マルカワみそ『自然栽培 白味噌』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格 |
こだわった材料で作った甘みが強い白味噌 | 日本 | 大豆、米、食塩 | 400g | 20歩 | 4.6g(100gあたり) |
| 山万加島屋信州みそ『信州白みそ 十二割糀木桶仕込み』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格 |
100年以上続く伝統の味 | 日本 | 大豆、米、食塩 | 750g | - | 11.6% |
| マルクラ食品『マルクラの白味噌』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格 |
甘酒屋の白味噌! | 日本 | 米、大豆、塩 | 250g×4個 | - | 6% |
| 西京『白みそ 京の彩』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格 |
上質で旨味や甘みを感じられる味噌 | 日本 | 米、大豆、食塩、水飴、酒精 | 300g×8個 | - | 4.9g(100gあたり) |
| 石野味噌『上撰白味噌 白粒味噌』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格 |
滑らかで優しい甘み | 京都府 | 米、大豆、食塩、酒精、ビタミンB2 | 2kg | - | - |
| 石野味噌『懐石白味噌』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格 |
特別な日にもぴったりな贅沢な白味噌 | 京都府 | - | 500g | - | - |
| 八木澤商店『蔵出し気仙みそ』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格 |
漂白していない優しい味噌 | - | 大豆、米、食塩 | 1kg | - | - |
| 石野味噌『名匠味噌蔵』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格 |
伝統の技で仕上げられた白味噌 | 京都府 | 米、大豆、食塩、酒精、ビタミンB2 | 300g | - | - |
| ヤマニ醸造『純正みそ』 |

|
※各社通販サイトの 2024年12月9日時点 での税込価格 |
厳選された原料で丁寧に手作り | 三重県 | 大豆、米、食塩 | 900g | - | - |
| フンドーキン『無添加あわせみそ』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格 |
九州の伝統的な味噌の味わいを楽しめる | 大分県 | 米、大豆、食塩、大麦 | 850g | - | - |
| marukome(マルコメ)『液みそ 料亭の味 白みそ だし入り』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格 |
片手で中身を出せる手軽さが魅力 | - | 米みそ、還元水飴、食塩、かつおエキス、かつお節粉末(かつお節、宗田かつお節)、昆布エキス、たん白加水分解物/酒精、調味料など | 430g | 食塩相当量0.7g | |
| 信州青木『善光寺生白』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格 |
まろやかな味わいを楽しめる | 長野県 | - | 1kg | - | - |
| 中屋味噌『特選 讃岐白みそ』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格 |
通常商品の1.2倍の麹を配合 | 香川県 | 米(米国産)、大豆、食塩、水あめ、甘味料(天草)、調味料(アミノ酸等)、漂白剤(次亜硫酸Na)、ビタミンB2 | 500g | - | 5% |
| マルマン『酵母菌が生きている! 無添加生みそ』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格 |
3か月以上熟成した樽からそのままパック | 長野県 | 大豆(カナダ・アメリカ産)、米(国産)、天日塩(オーストラリア産) | 750g | 8歩 | 11.7% |
| トモエ『田舎みそ白こし』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格 |
万人受けするあっさりとした白みそ | 北海道 | 大豆(カナダ又はアメリカ又は国産)、米、食塩/酒精 | 750g | - | - |
| marukome(マルコメ)『プロ用 白味噌 1kg』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格 |
家庭でもふんだんに使える1kg入り | 長野県 | 大豆(アメリカ又はカナダ又はその他)、米、食塩/酒精 | 1kg | - | - |
白味噌の選び方 米麹の割合(麹歩合)などもチェック!
料理研究家の松本葉子さんへの取材をもとに、白味噌を選ぶときのポイントをご紹介します。
白味噌の種類から選ぶ
白味噌と呼ばれる白色の味噌には、米味噌、麦味噌などの種類があります。料理に合わせて使い分けるのが一番ですが、それぞれの特徴を知っておくとより選びやすくなるでしょう。
米味噌は甘みの強さが特徴
大豆、塩そして米麹で作られる味噌が「米味噌」です。米味噌は日本では一般的によく使われる味噌です。3つの材料のバランスや仕込みの方法などで、さらに甘口・辛口の味に分かれます。
なお、米味噌は米麹の量が多くなればなるほど甘みが強くなります。逆に、米麹の割合が低いと、大豆のうまみと塩味をしっかり感じられるようになります。
さっぱりとした味の麦味噌
大豆と塩、そして麦麹で作られた味噌を「麦味噌」と言います。麦味噌は甘みの強さが特徴ですが、味わいはさっぱりしています。
その起源は平安時代まで遡ると言われており、現在では九州・四国でよく作られています。代表的な麦味噌としては「瀬戸内麦味噌」や「薩摩麦味噌」などがあり、日本各地で個性豊かな麦味噌が見られます。
原材料の成分をチェックしてから選ぶ
白味噌の甘みは本来、麹由来のもので、仕込むときの大豆に対する米麹の割合(麹歩合)によって変わります。麹歩合が上がるほど甘口の味噌になりますが、塩分量との兼ね合いや保存性、価格なども考慮して、最近では水飴や砂糖などで甘みを加えた白味噌も多くなっています。
原材料に甘み成分が用いられているかどうかも、白味噌を選ぶときのチェックポイントになります。
ダシが入っているか、入っていないかで選ぶ
米、大豆、塩などの基本的な原材料のほかに、ダシ入りの商品もあります。時短でお味噌汁を作る場合などに便利です。ダシが必要のないレシピを作る場合は、ダシなしの商品がおすすめ。西京漬け、味噌漬け、白和えなどのレシピにはダシなしで作るのがおすすめです。
こだわり派は添加物の有無の確認
味噌は発酵商品なので、風味や色が変わるのを防ぐために「酒精」というアルコールが使われている商品があります。酒精を用いることで賞味期限を長くし、容器の膨張を防ぐこともできます。
しかし、酒精が入っていないものは、白味噌本来の香りや味の変化を楽しめます。原材料にこだわって選びたい方は添加物の有無もチェックして選ぶといいでしょう。ただし、無添加の白味噌はその分賞味期限が短くなります。長い期間使う場合は、開封後冷凍保存するのも手です。
賞味期限内に使い切れる量を選ぶ
家族が多く、頻繁に白味噌を使う家庭は、容量が多いものの方がコスパも高いです。しかし、たまにしか使わない場合には賞味期限内に使い切れる小さめの量を選びましょう。
商品によって異なりますが、白味噌の賞味期限は、開封後冷蔵庫で1カ月といわれています。たまに全体をかき混ぜてあげましょう。
また、冷凍保存も可能です。使う期間が長くなりそうだなと思ったら、早い段階で冷凍しましょう。
【ユーザーが選んだ】イチオシ5選 みんなに人気の白味噌はこれ
ここからは、白味噌を買ったユーザーがイチオシの商品を紹介。5点満点で「コスパ」「味・おいしさ」を評価してもらいました。イチオシのポイント、おすすめする理由や口コミもぜひ参考にしてください!
その他にもおすすめしたい商品があるよという方は、ぜひ記事後半にある投稿フォームからご紹介をお願いします。

愛用者
ちょっといいお味噌
高いけれど、美味しいです。いつも適当に作っているお味噌汁の味が、一気に本格的になって感動しました。味噌一つでこんなに変わるのかと驚いています。とても上品で旅館のような味を楽しめるので、ぜひ試してみて下さい。(Y.T.さん/女性/37歳/フリーランス)
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格
| コスパ | ★★★☆☆ |
|---|---|
| 味・おいしさ | ★★★★★ |
| 総合評価 | 4.0点 |
| コスパ | ★★★☆☆ |
|---|---|
| 味・おいしさ | ★★★★★ |
| 総合評価 | 4.0点 |

愛用者
1人分のお味噌汁が簡単に作れる
お湯に注ぐだけで簡単にお味噌汁ができます。一人分から作れるのでかなり便利です。好みの濃さも調整できるのもありがたい。だしの風味も感じられて、おいしかったです。(R.F.さん/男性/39歳/会社員)
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格
| コスパ | ★★★★☆ |
|---|---|
| 味・おいしさ | ★★★★★ |
| 総合評価 | 4.5点 |
| コスパ | ★★★★☆ |
|---|---|
| 味・おいしさ | ★★★★★ |
| 総合評価 | 4.5点 |

愛用者
まろみのあるやわらかい味わい
愛媛の味噌といえば麦味噌。甘みはあるものの、甘すぎずさっぱりとしているので飽きません。我が家では、気分やお味噌汁に入れる具材に合わせて、合わせみそと麦味噌を使い分けています。この味噌でお味噌汁を作るときは、玉ねぎやさつまいもを入れてみてください。相性が良いのできっとおいしく仕上がりますよ。(Y.Y.さん/女性/31歳/会社員)
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格
| コスパ | ★★★★★ |
|---|---|
| 味・おいしさ | ★★★★★ |
| 総合評価 | 5.0点 |
| コスパ | ★★★★★ |
|---|---|
| 味・おいしさ | ★★★★★ |
| 総合評価 | 5.0点 |

愛用者
隠し味として活躍中
コクを出すためにコーンスープの隠し味に入れています。かなりまろやかな味に仕上がりますよ。また、無添加でよく入っている水飴のようなものも入っていませんので、安心して口に入れることができます。合わせ味噌用としても使えると思います。(N.M.さん/女性/37歳/主婦)
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格
| コスパ | ★★★★★ |
|---|---|
| 味・おいしさ | ★★★★☆ |
| 総合評価 | 4.5点 |
| コスパ | ★★★★★ |
|---|---|
| 味・おいしさ | ★★★★☆ |
| 総合評価 | 4.5点 |

愛用者
お雑煮などにぴったり
白味噌を使ったお雑煮を食べたいときに購入しています。とても甘く上品な味わいのお味噌です。値段も高くなく、スーパーなどでお手軽に購入できる点もおすすめのポイントです。一度白味噌でつくったお雑煮を食べたいと思った方は、ぜひ試してみてください。(M.N.さん/女性/44歳/事務職)
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格
| コスパ | ★★★★★ |
|---|---|
| 味・おいしさ | ★★★★★ |
| 総合評価 | 5.0点 |
| コスパ | ★★★★★ |
|---|---|
| 味・おいしさ | ★★★★★ |
| 総合評価 | 5.0点 |
白味噌のおすすめ19選 味噌レシピにぴったりの商品を厳選
うえでご紹介した白味噌の選び方のポイントをふまえて、料理研究家の松本葉子さんと編集部でおすすめする白味噌をご紹介します。

白味噌初心者におすすめな長期熟成の一品
白味噌は使ってみたいけれど、なんだかとても甘そうで……という方におすすめなのが、和歌山有数の金山寺味噌メーカーがつくっているこの白味噌。大豆、米、塩、すべて国産原料を用いており、白味噌としては珍しく、3~6カ月間自然熟成させて仕上げています。
塩分は10%なので、中辛味噌より少し甘い程度。普段白味噌を使い慣れていない方にも抵抗がないでしょう。また、甘い白味噌と混ぜて使うのもおすすめです。白い色味は残したままで、塩分とコクを深めることができますよ。
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格
| 生産地 | 和歌山県 |
|---|---|
| 原材料 | 北海道産丸大豆、国産米、長崎の塩、酒精 |
| 内容量 | 400g/950g |
| 麹歩合 | - |
| 塩分量 | 10% |
| 生産地 | 和歌山県 |
|---|---|
| 原材料 | 北海道産丸大豆、国産米、長崎の塩、酒精 |
| 内容量 | 400g/950g |
| 麹歩合 | - |
| 塩分量 | 10% |

西京漬けに使いたい、京都の粒味噌
老舗が多い京都ではまだ新しい昭和の創業ながら、料理人をはじめとする多くのファンをもつお店の白味噌です。普通の白味噌も取り扱っていますが、おすすめするのは西京漬け用の粒味噌。わが家では、定番のサワラなどの魚はもちろん、牛、鶏、豚など、いろいろなお肉を味噌漬けにしています。
甘さ控えめなので、適度なかたさになるよう、みりんを加えて練って使うといいでしょう。また、粒状味噌は少々漬けすぎても塩辛くなりにくいのがポイント。西京漬けに挑戦してみたい! という方におすすめしたい一品です。
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格
| 生産地 | 京都 |
|---|---|
| 原材料 | 米、大豆、食塩、水飴、酒精 |
| 内容量 | 1kg |
| 麹歩合 | - |
| 塩分量 | - |
| 生産地 | 京都 |
|---|---|
| 原材料 | 米、大豆、食塩、水飴、酒精 |
| 内容量 | 1kg |
| 麹歩合 | - |
| 塩分量 | - |

マイナビおすすめナビ編集部
大豆と米を原料に木桶で長期間じっくりと発酵熟成させた白味噌。上品な香りとまろやかな旨味を存分に味わえますよ。お吸い物や和え物、焼き魚のつけだれなど、さまざまな料理に使えば風味もアップ!
長い歴史をもつ白味噌本場の味!
京都は白味噌の発祥地。石野味噌は1782年に創業し、230年以上続く老舗です。現在に至るまで9代にわたって伝承されてきた味噌ですが、リーズナブルな価格で購入できるのが魅力的です。
石野味噌の白味噌は、米、大豆、食塩、酒精、ビタミンB2を原材料とし、米糀に蒸煮大豆と塩を加えて配合し、1週間ほどねかせて作っています。塩分量は100gあたり4.83gで、濃い目の味噌汁や正月に作るお雑煮などに適した味です。
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格
| 生産地 | 京都 |
|---|---|
| 原材料 | 米、大豆、食塩、酒精、ビタミンB2 |
| 内容量 | 500g |
| 麹歩合 | - |
| 塩分量 | 4.83g(100gあたり) |
| 生産地 | 京都 |
|---|---|
| 原材料 | 米、大豆、食塩、酒精、ビタミンB2 |
| 内容量 | 500g |
| 麹歩合 | - |
| 塩分量 | 4.83g(100gあたり) |

マイナビおすすめナビ編集部
化学調味料は一切使っておらず、昔ながらの木桶仕込みで丁寧に発酵熟成させています。淡白でまろやかな味わいながら、大豆本来の風味とコクがしっかりと感じられますよ。お吸い物やお料理の隠し味としても!
こだわった材料で作った甘みが強い白味噌
原料は100%無肥料無農薬の材料で作っている味噌です。北海道の大豆、新潟県や福井県、宮城県の米、蔵つき麹菌と伊豆大島の海水100%の日本伝統の塩「海の精」も使用しています。
麹の独特な香りや甘みが口の中に広がります。甘みが強いので、シチューなどの料理の隠し味としても使用するのもよいでしょう。白味噌は他の味噌と比較して約半分程度と塩分濃度が低いので、味噌汁や雑煮に入れて作るときには多めに入れるのがおすすめです。
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格
| 生産地 | 日本 |
|---|---|
| 原材料 | 大豆、米、食塩 |
| 内容量 | 400g |
| 麹歩合 | 20歩 |
| 塩分量 | 4.6g(100gあたり) |
| 生産地 | 日本 |
|---|---|
| 原材料 | 大豆、米、食塩 |
| 内容量 | 400g |
| 麹歩合 | 20歩 |
| 塩分量 | 4.6g(100gあたり) |

マイナビおすすめナビ編集部
伝統製法で作られた味噌は食べたことありますか? こちらは、大豆と米を12割の糀で発酵させて木桶で長期熟成した長野の伝統的な製法によるもの。化学調味料は一切使っていないので、素材本来の旨味が凝縮されています!
100年以上続く伝統の味
山万加島屋信州みそは小さな味噌屋ですが、代々伝わる製法で味噌を丁寧に作っています。手間を惜しまないこと、こだわりの製法で作っていることなどが人気の理由です。
実際に見て選び抜いた材料を使用。信州産の大豆と米糀を12割使用しています。杉木桶は100年にわたって伝統的に使用されてきたもので、この桶の中でじっくりと熟成しています。
塩分濃度が高く旨味もあるので、出汁を使わずに味噌を溶いた汁を飲んでも美味しいです。
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格
| 生産地 | 日本 |
|---|---|
| 原材料 | 大豆、米、食塩 |
| 内容量 | 750g |
| 麹歩合 | - |
| 塩分量 | 11.6% |
| 生産地 | 日本 |
|---|---|
| 原材料 | 大豆、米、食塩 |
| 内容量 | 750g |
| 麹歩合 | - |
| 塩分量 | 11.6% |
甘酒屋の白味噌!
マルクラ食品は主に甘酒、他には玄米や白米の麹、白味噌などを作っています。カリフォルニア産オーガニック米やオーガニック大豆、沖縄の塩を原材料とし、食品添加物は一切使用していません。
甘酒屋ならではの知識や経験をもとに作られているので、甘さがあり汁物や雑煮などに合う美味しい味噌です。海外ではサラダのドレッシングや和え物としても人気があります。出汁が入っていないシンプルな味付けで、手頃な価格なのも魅力的です。
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格
| 生産地 | 日本 |
|---|---|
| 原材料 | 米、大豆、塩 |
| 内容量 | 250g×4個 |
| 麹歩合 | - |
| 塩分量 | 6% |
| 生産地 | 日本 |
|---|---|
| 原材料 | 米、大豆、塩 |
| 内容量 | 250g×4個 |
| 麹歩合 | - |
| 塩分量 | 6% |
上質で旨味や甘みを感じられる味噌
西京味噌は、京都を中心に主に関西圏で作られている白味噌です。米や大豆などの原材料を厳選し、それぞれの素材を活かす味噌作りが行われています。
大豆は艶のある白目大豆を使用しています。コンピュータでデータ化した情報と、職人が実際に見て触った感覚を大切にしながら、時代のニーズに合わせて進化し続ける味噌。京料理に欠かせない調味料で、米麹がふんだんに使用されているので、上品な味わいと柔らかな甘みを楽しめます。
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格
| 生産地 | 日本 |
|---|---|
| 原材料 | 米、大豆、食塩、水飴、酒精 |
| 内容量 | 300g×8個 |
| 麹歩合 | - |
| 塩分量 | 4.9g(100gあたり) |
| 生産地 | 日本 |
|---|---|
| 原材料 | 米、大豆、食塩、水飴、酒精 |
| 内容量 | 300g×8個 |
| 麹歩合 | - |
| 塩分量 | 4.9g(100gあたり) |
滑らかで優しい甘み
上質な西京味噌ですが、甘さはそれほど強くはなく、優しい味わいを楽しむことができます。お味噌汁はもちろんのこと、魚などを漬け込んで西京焼きを楽しみたいという方にもおすすめです。伝統的な製法で丁寧に作られている味噌なので、さまざまな料理の味をしっかりと引き立ててくれます。甘すぎる西京味噌は苦手という方にもおすすめ。
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格
| 生産地 | 京都府 |
|---|---|
| 原材料 | 米、大豆、食塩、酒精、ビタミンB2 |
| 内容量 | 2kg |
| 麹歩合 | - |
| 塩分量 | - |
| 生産地 | 京都府 |
|---|---|
| 原材料 | 米、大豆、食塩、酒精、ビタミンB2 |
| 内容量 | 2kg |
| 麹歩合 | - |
| 塩分量 | - |
特別な日にもぴったりな贅沢な白味噌
関西では新年を迎える際のお雑煮にも使われる特別な白味噌です。長い伝統を誇る石野味噌の中でも特に麹歩合が高く仕上げられていますので、上質な本来の味噌の味わいを楽しむことができます。関西風のお雑煮や味噌汁はもちろんのこと、さまざまな料理を引き立ててくれるので、ちょっと上質な味噌を探しているという方におすすめです。
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格
| 生産地 | 京都府 |
|---|---|
| 原材料 | - |
| 内容量 | 500g |
| 麹歩合 | - |
| 塩分量 | - |
| 生産地 | 京都府 |
|---|---|
| 原材料 | - |
| 内容量 | 500g |
| 麹歩合 | - |
| 塩分量 | - |
漂白していない優しい味噌
漂白剤を使用していないので、若干黄色がかった見た目が特徴の白味噌です。自然な味噌の風味を味わうことができる逸品です。そのままさまざまな料理に使用することができるのみでなく、赤味噌とあわせるといったアレンジをしてもしっかりとその味を活かせます。さまざまな用途で使えるオーソドックスな白味噌を求める方におすすめです。
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格
| 生産地 | - |
|---|---|
| 原材料 | 大豆、米、食塩 |
| 内容量 | 1kg |
| 麹歩合 | - |
| 塩分量 | - |
| 生産地 | - |
|---|---|
| 原材料 | 大豆、米、食塩 |
| 内容量 | 1kg |
| 麹歩合 | - |
| 塩分量 | - |
伝統の技で仕上げられた白味噌
京都の地で天明元年の創業以来守られ続けている伝統の技を守りながら丁寧に仕上げられた白味噌です。しっかりとした味噌の風味を楽しめますが、味わいはとても上品なのでお味噌汁をはじめとしたさまざまな料理で使える万能タイプとなっています。日々の食事にはもちろんのこと、特別な日のための味噌を探している方にもおすすめです。
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格
| 生産地 | 京都府 |
|---|---|
| 原材料 | 米、大豆、食塩、酒精、ビタミンB2 |
| 内容量 | 300g |
| 麹歩合 | - |
| 塩分量 | - |
| 生産地 | 京都府 |
|---|---|
| 原材料 | 米、大豆、食塩、酒精、ビタミンB2 |
| 内容量 | 300g |
| 麹歩合 | - |
| 塩分量 | - |
厳選された原料で丁寧に手作り
国内産の大豆や米、自然塩など原材料にこだわって伝統的な手作りで丁寧に仕上げられた白味噌です。天然醸造で熟成されていますのでとても優しい味わいを楽しめます。生きたままの生味噌なので、味噌の秘めたパワーをしっかりと感じることができるでしょう。毎日の食卓にぴったりの昔ながらのおいしい定番味噌となっています。
※各社通販サイトの 2024年12月9日時点 での税込価格
| 生産地 | 三重県 |
|---|---|
| 原材料 | 大豆、米、食塩 |
| 内容量 | 900g |
| 麹歩合 | - |
| 塩分量 | - |
| 生産地 | 三重県 |
|---|---|
| 原材料 | 大豆、米、食塩 |
| 内容量 | 900g |
| 麹歩合 | - |
| 塩分量 | - |
九州の伝統的な味噌の味わいを楽しめる
九州は大分県で創業150年以上の歴史を持つフンドーキンの白味噌です。無添加なので優しい味噌本来の味わいをしっかりと楽しむことができます。価格もリーズナブルなので、毎日の食卓で使える味噌を探しているという方にもおすすめです。お味噌汁はもちろんのこと、あらゆる食材の味わいを活かしてくれますのでいろんな料理に使えます。
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格
| 生産地 | 大分県 |
|---|---|
| 原材料 | 米、大豆、食塩、大麦 |
| 内容量 | 850g |
| 麹歩合 | - |
| 塩分量 | - |
| 生産地 | 大分県 |
|---|---|
| 原材料 | 米、大豆、食塩、大麦 |
| 内容量 | 850g |
| 麹歩合 | - |
| 塩分量 | - |
片手で中身を出せる手軽さが魅力
しょうゆなどのように、パックから片手で中身を出すことができる液タイプの白味噌です。出汁も入っているので、お湯を入れれば簡単にみそ汁ができあがります。もちろん、野菜炒めなどに入れてもOK。
味わいといえば、米麹を多く含んでいるので、甘みとクリーミーな舌触りが特徴です。和食だけでなく、洋食にも使えますよ。
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格
| 生産地 | - |
|---|---|
| 原材料 | 米みそ、還元水飴、食塩、かつおエキス、かつお節粉末(かつお節、宗田かつお節)、昆布エキス、たん白加水分解物/酒精、調味料など |
| 内容量 | 430g |
| 麹歩合 | |
| 塩分量 | 食塩相当量0.7g |
| 生産地 | - |
|---|---|
| 原材料 | 米みそ、還元水飴、食塩、かつおエキス、かつお節粉末(かつお節、宗田かつお節)、昆布エキス、たん白加水分解物/酒精、調味料など |
| 内容量 | 430g |
| 麹歩合 | |
| 塩分量 | 食塩相当量0.7g |
まろやかな味わいを楽しめる
原材料にはもちろんのこと、伝統的な製法にこだわって作ることによってとてもまろやかで優しい味わいに仕上げられた白味噌です。毎日の食卓のお味噌汁にはもちろんのこと、さまざまな料理にマッチしてくれるマルチタイプです。天然の素材のみで作られていますので、どんな方でも安心して口にすることができるという点も嬉しいポイント。
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格
| 生産地 | 長野県 |
|---|---|
| 原材料 | - |
| 内容量 | 1kg |
| 麹歩合 | - |
| 塩分量 | - |
| 生産地 | 長野県 |
|---|---|
| 原材料 | - |
| 内容量 | 1kg |
| 麹歩合 | - |
| 塩分量 | - |
通常商品の1.2倍の麹を配合
もともとの米麹の割合が多い白みそに、さらに2割増しで米麹を使用した甘みたっぷりの白味噌です。香川県の名物料理である白みそを使用したお雑煮にもぴったりで、豊かで優しい甘みが口の中に広がります。
米麹が多いということで、腸活にもピッタリのため、美容や健康を意識している方におすすめのお味噌です。
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格
| 生産地 | 香川県 |
|---|---|
| 原材料 | 米(米国産)、大豆、食塩、水あめ、甘味料(天草)、調味料(アミノ酸等)、漂白剤(次亜硫酸Na)、ビタミンB2 |
| 内容量 | 500g |
| 麹歩合 | - |
| 塩分量 | 5% |
| 生産地 | 香川県 |
|---|---|
| 原材料 | 米(米国産)、大豆、食塩、水あめ、甘味料(天草)、調味料(アミノ酸等)、漂白剤(次亜硫酸Na)、ビタミンB2 |
| 内容量 | 500g |
| 麹歩合 | - |
| 塩分量 | 5% |
3か月以上熟成した樽からそのままパック
添加物や保存料などを一切使用せず丁寧に醸造し、3か月以上も熟成させた素材の味が活きている味噌です。樽からそのまま容器に移しているので、酵母菌も生きたまま、自宅で少量ずつ使用している間も発酵が進みます。
全体的にバランスが良い味噌のため、具材は豆腐やわかめなどだけでなく、お肉や魚、野菜など何にでも合わせられるのが魅力です。
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格
| 生産地 | 長野県 |
|---|---|
| 原材料 | 大豆(カナダ・アメリカ産)、米(国産)、天日塩(オーストラリア産) |
| 内容量 | 750g |
| 麹歩合 | 8歩 |
| 塩分量 | 11.7% |
| 生産地 | 長野県 |
|---|---|
| 原材料 | 大豆(カナダ・アメリカ産)、米(国産)、天日塩(オーストラリア産) |
| 内容量 | 750g |
| 麹歩合 | 8歩 |
| 塩分量 | 11.7% |
万人受けするあっさりとした白みそ
すっきりした甘みとまろやかな味わいがどの食材にも合わせやすい白みそです。すでに漉しているため、パックからそのままお鍋の中にいれて味噌汁を仕立てることができて便利です。
製造している醸造所のなかでもロングセラーで安定した味わいが好評を得ている逸品となっています。大豆の豊かな味わいと麹の優しい甘みを堪能できます。
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格
| 生産地 | 北海道 |
|---|---|
| 原材料 | 大豆(カナダ又はアメリカ又は国産)、米、食塩/酒精 |
| 内容量 | 750g |
| 麹歩合 | - |
| 塩分量 | - |
| 生産地 | 北海道 |
|---|---|
| 原材料 | 大豆(カナダ又はアメリカ又は国産)、米、食塩/酒精 |
| 内容量 | 750g |
| 麹歩合 | - |
| 塩分量 | - |
家庭でもふんだんに使える1kg入り
白みそは、その淡くて優しい味わいや見た目から味噌汁以外にもいろんな料理で活躍します。味噌焼きおにぎりや味噌漬けなど家庭でも活躍場面はあり、白みそを頻繁に使う人にもおすすめの1Kg入りの白みそです。カレーやシチューの隠し味にも使えて重宝します。
長期保存も可能で、その間にも発酵が進むため、色が赤みを帯びてきますが味わいに深みが増します。
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格
| 生産地 | 長野県 |
|---|---|
| 原材料 | 大豆(アメリカ又はカナダ又はその他)、米、食塩/酒精 |
| 内容量 | 1kg |
| 麹歩合 | - |
| 塩分量 | - |
| 生産地 | 長野県 |
|---|---|
| 原材料 | 大豆(アメリカ又はカナダ又はその他)、米、食塩/酒精 |
| 内容量 | 1kg |
| 麹歩合 | - |
| 塩分量 | - |
「白味噌」のおすすめ商品の比較一覧表
| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 生産地 | 原材料 | 内容量 | 麹歩合 | 塩分量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸新本家『白みそ』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格 |
白味噌初心者におすすめな長期熟成の一品 | 和歌山県 | 北海道産丸大豆、国産米、長崎の塩、酒精 | 400g/950g | - | 10% |
| しま村『しま村の白粒味噌』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格 |
西京漬けに使いたい、京都の粒味噌 | 京都 | 米、大豆、食塩、水飴、酒精 | 1kg | - | - |
| 石野味噌『石野白味噌』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格 |
長い歴史をもつ白味噌本場の味! | 京都 | 米、大豆、食塩、酒精、ビタミンB2 | 500g | - | 4.83g(100gあたり) |
| マルカワみそ『自然栽培 白味噌』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格 |
こだわった材料で作った甘みが強い白味噌 | 日本 | 大豆、米、食塩 | 400g | 20歩 | 4.6g(100gあたり) |
| 山万加島屋信州みそ『信州白みそ 十二割糀木桶仕込み』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格 |
100年以上続く伝統の味 | 日本 | 大豆、米、食塩 | 750g | - | 11.6% |
| マルクラ食品『マルクラの白味噌』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格 |
甘酒屋の白味噌! | 日本 | 米、大豆、塩 | 250g×4個 | - | 6% |
| 西京『白みそ 京の彩』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格 |
上質で旨味や甘みを感じられる味噌 | 日本 | 米、大豆、食塩、水飴、酒精 | 300g×8個 | - | 4.9g(100gあたり) |
| 石野味噌『上撰白味噌 白粒味噌』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格 |
滑らかで優しい甘み | 京都府 | 米、大豆、食塩、酒精、ビタミンB2 | 2kg | - | - |
| 石野味噌『懐石白味噌』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格 |
特別な日にもぴったりな贅沢な白味噌 | 京都府 | - | 500g | - | - |
| 八木澤商店『蔵出し気仙みそ』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格 |
漂白していない優しい味噌 | - | 大豆、米、食塩 | 1kg | - | - |
| 石野味噌『名匠味噌蔵』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格 |
伝統の技で仕上げられた白味噌 | 京都府 | 米、大豆、食塩、酒精、ビタミンB2 | 300g | - | - |
| ヤマニ醸造『純正みそ』 |

|
※各社通販サイトの 2024年12月9日時点 での税込価格 |
厳選された原料で丁寧に手作り | 三重県 | 大豆、米、食塩 | 900g | - | - |
| フンドーキン『無添加あわせみそ』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格 |
九州の伝統的な味噌の味わいを楽しめる | 大分県 | 米、大豆、食塩、大麦 | 850g | - | - |
| marukome(マルコメ)『液みそ 料亭の味 白みそ だし入り』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格 |
片手で中身を出せる手軽さが魅力 | - | 米みそ、還元水飴、食塩、かつおエキス、かつお節粉末(かつお節、宗田かつお節)、昆布エキス、たん白加水分解物/酒精、調味料など | 430g | 食塩相当量0.7g | |
| 信州青木『善光寺生白』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格 |
まろやかな味わいを楽しめる | 長野県 | - | 1kg | - | - |
| 中屋味噌『特選 讃岐白みそ』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格 |
通常商品の1.2倍の麹を配合 | 香川県 | 米(米国産)、大豆、食塩、水あめ、甘味料(天草)、調味料(アミノ酸等)、漂白剤(次亜硫酸Na)、ビタミンB2 | 500g | - | 5% |
| マルマン『酵母菌が生きている! 無添加生みそ』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格 |
3か月以上熟成した樽からそのままパック | 長野県 | 大豆(カナダ・アメリカ産)、米(国産)、天日塩(オーストラリア産) | 750g | 8歩 | 11.7% |
| トモエ『田舎みそ白こし』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格 |
万人受けするあっさりとした白みそ | 北海道 | 大豆(カナダ又はアメリカ又は国産)、米、食塩/酒精 | 750g | - | - |
| marukome(マルコメ)『プロ用 白味噌 1kg』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月25日時点 での税込価格 |
家庭でもふんだんに使える1kg入り | 長野県 | 大豆(アメリカ又はカナダ又はその他)、米、食塩/酒精 | 1kg | - | - |
通販サイトの最新人気ランキングを参考にする 白味噌の売れ筋をチェック
Amazon、楽天市場での白味噌の売れ筋ランキングも参考にしてみてください。
※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。
白味噌はレシピに幅広く使える調味料
白味噌は赤味噌と違って色が薄いことから、様々な料理に応用できます。また塩分も赤味噌より強くないため、甘みが引き立つ料理と相性抜群です。
●魚や鶏肉に漬け込む
●味噌汁
●雑煮
●グラタン
●スイーツ
これら以外の料理レシピも豊富にあるので、気になる人はレシピサイトをみて参考にしてみてくださいね。
白味噌の保存方法 料理研究家からアドバイス
味噌は常温保存も可能な食品ですが、白味噌は塩分濃度が低いのでカビがでやすく、また変色やにおい移りもしやすいため、一般の味噌よりも保存に注意が必要です。
空気に触れないよう密封して冷蔵庫で保存し、なるべく早く使い切るのが基本ですが、おすすめは冷凍保存。冷凍してもカチカチにはならないので、必要な分だけ切り取って使うことができますよ。
白味噌に関するよくある質問


色の違いは、熟成するさいに、メイラード反応と呼ばれる、大豆に含まれるアミノ酸と糖が化学反応を起こして褐色に変化することで違いが生まれます。白味噌は熟成期間が短いため、メイラード反応が抑えられて、白っぽい色に仕上がります。反対に、赤味噌は熟成期間が長く、赤味噌特有の茶色っぽい色に仕上がります。また、赤味噌のほうが塩分濃度が高めになります。


できません。白味噌と赤味噌では原材料が同じでも、熟成期間の差から塩分濃度の違いがあります。白味噌を使う料理に赤味噌を使うと色も変わりますし、味付けも塩分が高めになります。
美味しい白味噌をみつけてくださいね
白味噌のおすすめ記事はいかがでしたか? 白味噌といっても種類があり、料理によって使い分けるといいことがわかりました。この記事を参考に美味しい白味噌を見つけてくださいね。
おすすめ商品・口コミの投稿はこちら
※メーカーや販売店の方は、ページ下部の「お問い合わせはこちら」から商品情報をお送りください。
ユーザーのおすすめ商品や口コミ情報は、マイナビおすすめナビを閲覧したユーザー、マイナビニュース会員、外部パートナー企業と契約する一般ユーザーからの投稿をもとにしています。
◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。