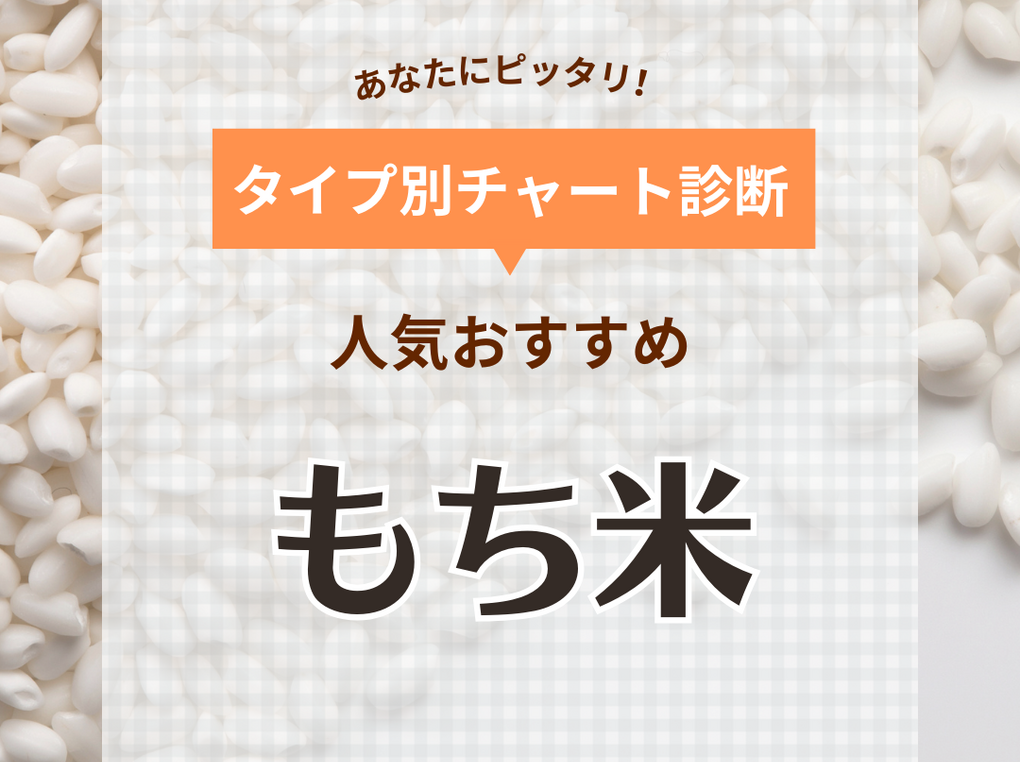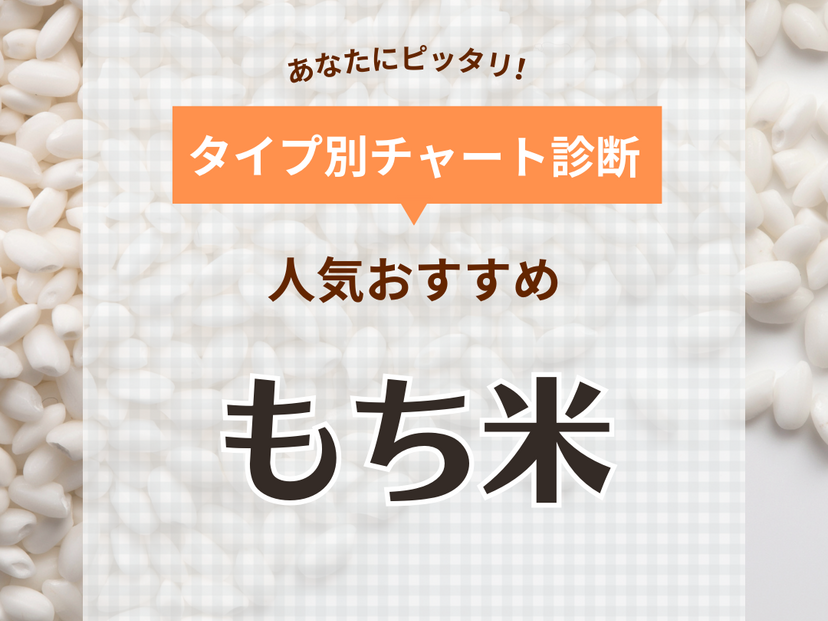| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 生産地 | 品種 | 内容量 | 農薬情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡萬『晴れの国岡山で穫れたヒメノモチ』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月4日時点 での税込価格 |
ももたろう印の上品な味わい | 岡山県 | ヒメノモチ | 5kg | なし |
| 水菜土農園『秋田県産 きぬのはだ』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月4日時点 での税込価格 |
滑らかで絹のような食感 | 秋田県 | きぬのはだ | 5kg | - |
| 今議商店『新潟県産 こがねもち米』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月4日時点 での税込価格 |
ワンランク上の味わいを楽しめる | 新潟県 | こがねもち | 10kg(5kg×2袋) | - |
| ほくべい『きたゆきもち 』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月4日時点 での税込価格 |
使いやすい1kgパック | 北海道 | きたゆきもち | 1kg | なし |
| グラントマト『キラッと玄米』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月4日時点 での税込価格 |
玄米食を気軽に楽しめる! | 複数原料米 国内産 | こがねもち、ヒメノモチ | 10kg | - |
| ホクレン『北海道産 きたゆきもち米 1kg』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月4日時点 での税込価格 |
和菓子づくりにおすすめ! 保存に便利な少量パック | 北海道 | きたゆきもち | 1kg | - |
| 田中米穀『新潟県産 もち米 わたぼうし』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月4日時点 での税込価格 |
甘味と強い粘りで、白くふっくら搗きあがり | 新潟県 | わたぼうし | 2kg | - |
もち米の魅力とは? さまざまな種類を楽しもう!
日常的に食べる「うるち米」に対して、おもちや赤飯、おこわなどに使われる「もち米」。お正月やお祝い事など、行事食に欠かせない食材として古くから親しまれてきました。
その名のとおり、もちもちとした粘り気と食感が特徴で、冷めてもおいしいのが魅力です。このもち米は、収穫年や産地のほかさまざまな品種があり、それぞれ異なる特徴があるので、用途や好みに応じて選びましょう。
もち米のカロリーや栄養効果について 腹持ちが良く栄養たっぷり!
もち米はカロリーが高く腹もちがいいだけでなく、健康的な食材です。ふだん食べているうるち米は100gあたり168kcalなのに対し、もち米は234kcalです。
また、うるち米にはたんぱく質のアミロースとアミロペクチンが約2:8の割合で含まれていますが、もち米はすべてがアミロペクチンでできています。アミロペクチンはねばりの元であるとともに、消化酵素が働きやすく、でんぷんの分解が早まります。
もち米にはフェルラ酸、GABA、食物繊維、イノシトールなどの成分が含まれ、健康維持が期待できる食材でもあります。
もち米の代表的な品種
もち米には「ヒメノモチ」「こがねもち」などさまざまな品種があります。また、有色もち米として黒米の「朝紫」、赤米の「つくし赤もち」などももち米の品種です。
もち米は、栽培する地域の気候風土に合った品種が数種類あり、奨励品種として選定されます。ここでは代表的な品種についてみていきましょう。
こがねもち|コシが強く煮物やお雑煮にぴったり
「こがねもち」はもち米の栽培が盛んな新潟県をはじめ、宮城県、福島県、岩手県、山梨県で作付されています。宮城県で作られているこがねもちは「みやこがねもち」と呼ばれ、その品質が高く評価されています。
昭和33年に奨励品種に採用されたもち米界のロングセラー品種。もち米らしいねばりやコシ、舌ざわり、歯ごたえのもっちり感などにすぐれたもち米の王様です。
ヒメノモチ|おこわや赤飯にぴったりなあっさり感
ヒメノモチは岩手県を中心に、山形県、千葉県、鳥取県、岡山県、広島県で作付が多い品種。「大系227」と「こがねもち」の交配品種で昭和47年に奨励品種に指定されました。高級もち米と称され、人気があります。
米粒が白く、もちに加工すると滑らかなコシが楽しめます。もち米のなかでは味わいがあっさりめなところも特徴。赤飯やおこわなどに向いています。
ヒヨクモチ|硬くなりにくくずっと美味しい
「ヒヨクモチ」は福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、静岡県、山口県、宮崎県など九州地方を中心に栽培されています。昭和46年に奨励品種に採用され、とくに福岡県では作付けされるもち米のうちすべてがこの「ヒヨクモチ」です。
炊いたあとでかたくなりにくく、もっちりとした食感が特徴的な品種。ふ先の色は褐色です。
はくちょうもち|炊飯器で炊けて和菓子にもぴったり
「はくちょうもち」は「たんねもち」と「おんねもち」の交配でできた品種。平成元年に推奨品種に指定され、以後北海道のもち米ブランドとして広く知られてきました。
炊飯器でも炊けるもち米として使い勝手がよく、一般家庭でもよく使われます。炊いたあとはやわらかさが持続し、ねばりも強いため、赤飯やおこわのほか、大福などの和菓子にも便利です。
風の子もち|コシとキメを楽しめる
「風の子もち」は収量性がよく、安定供給につながりやすいということから、もち米の生産が多い北海道でもっとも多く作付けされている品種です。「はくちょうもち」と「上系85201」から交配されました。
白度が高く、粒張りもよいうえに冷めてもやわらかく、ねばりが長持ちするのが特徴。もちにするとねばりやコシ、きめのこまかさが楽しめます。
わたぼうし|つやつやでしっかりとした粘り気
「わたぼうし」は新潟県で生産され「こがねもち」と人気を二分しています。
冷めたあとでもやわらかく、赤飯やおこわはもちろん、もちにする場合の加工性にもすぐれています。おもちにしたときの仕上がりが綿花の綿帽子のようだということから命名されました。
米粒がやや大粒で、炊きあがったあとの光沢や粒張り、ねばりにすぐれていて味、質ともに好評を得ている品種です。
もち米の選び方 おこわやおはぎに合う!
フードアナリスト・市岡充重さんに取材をして、もち米の選び方のポイントを4つ教えていただきました。
【1】収穫年度
【2】生産地
【3】サイズや値段
【4】有機JAS認証されているか
一つひとつ解説しているので、ぜひ、もち米選びの参考にしてみてください。
【1】もち米の収穫年度で選ぶ
もち米は8月下旬から10月上旬に収穫されるのが一般的で、収穫した年の12月31日までに精米・袋詰めされたもち米を「新米」と言います。また、新しく新米が出ると1年前のもち米は「古米」、2年前のもち米は「古古米」と呼ばれます。
新米の魅力はみずみずしさ。脱穀されたばかりの米はツヤがあり水分含有量も豊富です。もち米らしい光沢や香り、風味が味わえるのは新米の魅力です。
しかし、古米は水分が少ないため、水っぽくなりがちな新米よりもしっかり炊きあがる魅力があります。おこわのようにご飯の粒感を大切にしたい料理の場合は、古米が合っている場合もあります。
【2】もち米の生産地で選ぶ
もちとして販売されている商品は使用しているもち米の種類がわからないことも多いです。しかし、もち米はうるち米と同様に、土壌や水、気候などさまざまな要因により味とねばりが変わります。
また、もち米はタイやアメリカなどから輸入されているものも多いです。
こだわりの料理を作るためには、ぜひひとつひとつのもち米の味わいにもこだわって選びましょう。
【3】サイズや値段で選ぶ
もち米は重さをもとに量り売りされるため、一度に使い切れる量を買ったり保存用に多めに買ったりすることができます。同じもち米でも量に比例して値段が変わるので、予算が決まっている場合には目安にしやすいでしょう。
もち米の相場は1kgが500~1,000円程度、5kgは2,000~3,000円です。ただし、銘柄によって相場に差があります。
【4】「有機JAS認証」をうけているか確認しよう
もち米には、病害虫や雑草をのぞいたり、作物の生理機能を抑える目的などで農薬を使うのが一般的です。しかし法律の範囲で適切に使用されていても、商品には多少農薬が残ってしまうことが考えられます。生産者独自の努力でできるだけ農薬を使わない「有機栽培」や「減農薬栽培」などがおこなわれることもあります。
農薬の使用に対して国で明確な基準を設けているのが「有機JAS認証」。もち米や野菜のように1年生の作物は、種まきや植え付けの前、2年のあいだ化学合成農薬・化学肥料を使っていないことを条件に認定されます。これは毎年監査されているため、農薬が気になる場合にはJAS認証を目安に選ぶことができます。
もち米のおすすめ7選 おいしいお米を見つけよう!
ここまでの選び方をふまえて、フードアナリストの市岡充重さんと編集部が選んだ、もち米のおすすめ商品を紹介します。

ももたろう印の上品な味わい
岡山県で生産されるもち米の約半数がヒメノモチ。米肌の白さとあっさりした上品な味わいが魅力です。ねばり、ツヤ、香りが際立つ品種で、もちのほか赤飯、おこわに使いやすい品種です。
古米などぱさつくうるち米と一緒に混ぜて炊くとふっくらもちもちの白米が味わえます。保管期間内に使い切れる量ごとで購入するとカビや害虫の心配なく食べられるでしょう。
※各社通販サイトの 2025年3月4日時点 での税込価格
| 生産地 | 岡山県 |
|---|---|
| 品種 | ヒメノモチ |
| 内容量 | 5kg |
| 農薬情報 | なし |
| 生産地 | 岡山県 |
|---|---|
| 品種 | ヒメノモチ |
| 内容量 | 5kg |
| 農薬情報 | なし |
滑らかで絹のような食感
米の名産地、秋田県の水菜土農園が作る「きぬのはだ」は、絹のようなきめ細かさと滑らかな食感が特徴です。コシやねばりもあり、お餅やおこわにして美味しく食べられます。
可能な限り有機肥料で育てた特別栽培の高品質なもち米なので、家族みんなで安心して楽しめるでしょう。
※楽天市場は2袋セットでの販売となります。
※各社通販サイトの 2025年3月4日時点 での税込価格
| 生産地 | 秋田県 |
|---|---|
| 品種 | きぬのはだ |
| 内容量 | 5kg |
| 農薬情報 | - |
| 生産地 | 秋田県 |
|---|---|
| 品種 | きぬのはだ |
| 内容量 | 5kg |
| 農薬情報 | - |
ワンランク上の味わいを楽しめる
こがねもちの生産が盛んな新潟県産のもち米。味とコシの強さは一級品であり、餅つきやお赤飯、おはぎなど幅広く使えます。舌触りもよく、噛めば噛むほど味の魅力を感じられるお米となってます。
※各社通販サイトの 2025年3月4日時点 での税込価格
| 生産地 | 新潟県 |
|---|---|
| 品種 | こがねもち |
| 内容量 | 10kg(5kg×2袋) |
| 農薬情報 | - |
| 生産地 | 新潟県 |
|---|---|
| 品種 | こがねもち |
| 内容量 | 10kg(5kg×2袋) |
| 農薬情報 | - |
使いやすい1kgパック
「きたゆきもち」は、北海道の低温気候にも適した品種で実入りがよく、おいしさと強さを兼ね備えた品種です。
「はくちょうもち」のようなやわらかさとねばりが長持ちするのが特徴で、炊飯器で炊いてもおいしく食べられる点が魅力。おこわや大福、おはぎなどに使いやすく、白さとツヤ、食味のよさが評価されています。
※各社通販サイトの 2025年3月4日時点 での税込価格
| 生産地 | 北海道 |
|---|---|
| 品種 | きたゆきもち |
| 内容量 | 1kg |
| 農薬情報 | なし |
| 生産地 | 北海道 |
|---|---|
| 品種 | きたゆきもち |
| 内容量 | 1kg |
| 農薬情報 | なし |
玄米食を気軽に楽しめる!
粘りやコシ、風味の質が高く、最高級と称される「こがねもち」と、美しい白さと滑らかな食感が特徴の「ヒメノモチ」をブレンドした商品です。玄米なので、健康面を意識している方にぴったり。
小石や小さな草の実などを取り除いた調整済み玄米なので、石抜きの必要なくそのまま家庭用精米機にかけることができます。
もち米のモチモチ感と玄米のプチプチ感を一緒に楽しめるのも、もち米玄米ならではの魅力です。
※各社通販サイトの 2025年3月4日時点 での税込価格
| 生産地 | 複数原料米 国内産 |
|---|---|
| 品種 | こがねもち、ヒメノモチ |
| 内容量 | 10kg |
| 農薬情報 | - |
| 生産地 | 複数原料米 国内産 |
|---|---|
| 品種 | こがねもち、ヒメノモチ |
| 内容量 | 10kg |
| 農薬情報 | - |
和菓子づくりにおすすめ! 保存に便利な少量パック
ツヤのある見た目とコシのある食感が特徴のきたゆきもち。白さが強いのも特徴で、赤飯やおはぎづくりに向いています。
さらにこちらの商品は
1kgの少量タイプなので、和菓子作りや正月のお雑煮など、たまにしかもち米を使わない方におすすめです。チャック付きのパッケージに入っているので、しっかり口を閉じて保存できます。
※Amazonは1袋、楽天市場、Yahoo!ショッピングは2袋セットです。
※各社通販サイトの 2025年3月4日時点 での税込価格
| 生産地 | 北海道 |
|---|---|
| 品種 | きたゆきもち |
| 内容量 | 1kg |
| 農薬情報 | - |
| 生産地 | 北海道 |
|---|---|
| 品種 | きたゆきもち |
| 内容量 | 1kg |
| 農薬情報 | - |
甘味と強い粘りで、白くふっくら搗きあがり
白くふっくらと搗きあがることから、その名がついた「わたぼうし」。その特徴は何といっても甘味とコシの強さ。噛むたびにもち米そのものの甘味を楽しめます。煮崩れしない強い粘りは、おはぎや大福といった和菓子はもちろん、赤飯やおこわ、イカメシなどのお料理にもぴったり。きめ細やかな「わたぼうし」は、家庭用炊飯器で簡単においしくいただけます。歯切れの良い食感ともち米本来の甘味をお楽しみください。
※各社通販サイトの 2025年3月4日時点 での税込価格
| 生産地 | 新潟県 |
|---|---|
| 品種 | わたぼうし |
| 内容量 | 2kg |
| 農薬情報 | - |
| 生産地 | 新潟県 |
|---|---|
| 品種 | わたぼうし |
| 内容量 | 2kg |
| 農薬情報 | - |
おすすめ商品の比較一覧表
| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 生産地 | 品種 | 内容量 | 農薬情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡萬『晴れの国岡山で穫れたヒメノモチ』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月4日時点 での税込価格 |
ももたろう印の上品な味わい | 岡山県 | ヒメノモチ | 5kg | なし |
| 水菜土農園『秋田県産 きぬのはだ』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月4日時点 での税込価格 |
滑らかで絹のような食感 | 秋田県 | きぬのはだ | 5kg | - |
| 今議商店『新潟県産 こがねもち米』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月4日時点 での税込価格 |
ワンランク上の味わいを楽しめる | 新潟県 | こがねもち | 10kg(5kg×2袋) | - |
| ほくべい『きたゆきもち 』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月4日時点 での税込価格 |
使いやすい1kgパック | 北海道 | きたゆきもち | 1kg | なし |
| グラントマト『キラッと玄米』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月4日時点 での税込価格 |
玄米食を気軽に楽しめる! | 複数原料米 国内産 | こがねもち、ヒメノモチ | 10kg | - |
| ホクレン『北海道産 きたゆきもち米 1kg』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月4日時点 での税込価格 |
和菓子づくりにおすすめ! 保存に便利な少量パック | 北海道 | きたゆきもち | 1kg | - |
| 田中米穀『新潟県産 もち米 わたぼうし』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月4日時点 での税込価格 |
甘味と強い粘りで、白くふっくら搗きあがり | 新潟県 | わたぼうし | 2kg | - |
各通販サイトの最新人気ランキングを見る もち米の売れ筋をチェック
Amazon、楽天市場でのもち米の売れ筋ランキングも参考にしてみてください。
※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。
炊飯器を使ったもち米の炊き方 浸水時間や水加減は?
ご家庭の炊飯器でもち米を炊くときの方法をご紹介します!
1.もち米をすすぐ
炊飯器にもち米を入れて、手早くすすぎ洗いをして水を捨てます。手早くすることで、研ぎ汁を吸ってヌカ臭くなるのを防ぎます。力を入れすぎないように研ぎましょう。
2.水を入れる
水をきって、もち米1カップに対して水を180cc入れます。もち米は吸収率が高いため、白米より多めに水を入れましょう。
3.もち米をほぐす
もち米が炊けたら素早くしゃもじを一周させます。余分な水分をとばすことで透明感のあるご飯になります。
普通の精米は芯が残ってしまうため30分以上浸水させてから炊きます。一方でもち米は、浸水時間が長いと水を吸い込んでしまい炊くための水が無くなってしまいます。そのため、すぐに炊いて問題ありません。
もち米に関するQ&A よくある質問に答えます!
ここでは、もち米を購入しようと考えている方が抱きがちな疑問にお答えします!


もち米の名産地の中でも、「北海道」「佐賀県」「新潟県」の3つは「日本三大もち米処」として知られています。北海道は「はくちょうもち」、佐賀県なら「ヒヨクモチ」、新潟県では「こがねもち」などが有名な品種として挙げられます。


もち米は、スーパーのお米売り場などで販売されていますが、時期や店舗によってはもち米を置いていないこともあるようです。通販サイトなら、さまざまな品種のもち米を取り寄せることができるだけでなく、重くて運ぶのが大変なもち米も、自宅まで届けてもらえます。本記事でもおすすめのもち米を紹介しているので、ぜひ、こちらからチェックしてみてください!
出来たてのお餅を食べよう!おすすめ餅つき機をご紹介 家族で楽しめる!
家庭で臼や杵を準備して餅つきするのは、かなりの手間がかかりますよね。自動餅つき機なら、力いらずで出来立ての美味しいお餅を楽しめます。
場所を取らないコンパクトタイプ、パンも焼けるホームベーカリー兼用タイプなども便利ですよ。詳しくは下記の記事でご紹介しています。
もち米に合う食品の記事はこちら 【関連記事】
こだわりをもってもち米を選ぼう!
もち米には精米年度や産地のほか、品種や農薬についても記載されています。自分でもちや料理をつくるならもち米の味にもこだわりたいところ。
代表的な「こがねもち」や「ヒメノモチ」のほかにも魅力的なもち米は複数あります。
また、生鮮食品のもち米はできるだけ冷暗所に保管して早めに使うのがポイント。使いやすい量にこだわって選ぶとおいしく食べられるでしょう。
◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。