| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 解像度 | 輝度 | コントラスト比 | ゲームモード | 投射可能距離 | 最小騒音レベル | HDMI端子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiraArc(ミラアーク)『CINEMAGE Pro(シネマージュプロ)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月2日時点 での税込価格 |
どこでも高解像度・大画面のスクリーンを楽しめる! | FULL HD1080P(1920×1080) | 200ANSIルーメン | - | - | 1.2:1(38インチ/1メートル) | - | 1系統 |
| Anker(アンカー)『Nebula (ネビュラ) Capsule 3 Laser』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月2日時点 での税込価格 |
フルHDの解像度と大画面でゲームが楽しめる | フルHD (1920 × 1080 画素) | 300lm | - | - | - | 28dB | 1系統 |
| Anker(アンカー)『Nebula Nova(D2160521)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月2日時点 での税込価格 |
世界初Android TV搭載家庭プロジェクター | フルHD (1920 × 1080 画素) | 800lm | - | - | 0.9m(40インチ) | 50dB | 1系統 |
| BenQ(ベンキュー)『DLP 4Kホームプロジェクター(TK700)』 |
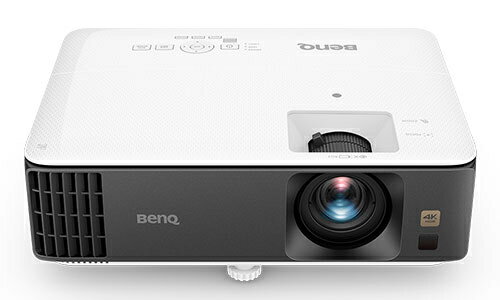
|
※各社通販サイトの 2025年3月2日時点 での税込価格 |
スポーツ鑑賞にもゲームプレイにもおすすめ! | 4K(3840 x 2160) | 3,200lm | 10000:1 | 〇 | - | 34dB | 2系統 |
| BenQ(ベンキュー)『GV30 HD モバイルLEDプロジェクター』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月2日時点 での税込価格 |
自宅のあらゆる場所がミニシアターに | HD(1280×720) | 300lm | 100,000:1 | - | - | 27dB | 2系統 |
| XGIMI『XGIMI Halo+』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月2日時点 での税込価格 |
自宅はもちろん、キャンプ、寝室でも | フルHD(1920x1080) | 900lm | - | - | - | 30dB | - |
| EPSON(エプソン)『ドリーミオ ホームプロジェクター(EH-TW750)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月2日時点 での税込価格 |
場所を選ばずに設置できる「ピタッと補正機能」搭載 | フルHD(1920×1080) | 3400lm | 16000:1 | あり | 1.3m | 28dB | 2系統 |
| EPSON(エプソン)『ドリーミオ ホームプロジェクター(EH-LS800B)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月2日時点 での税込価格 |
4K相当の高画質で最大150インチの大画面 | 4K | 4000lm | 2,500,000:1 | - | - | 19dB | 2系統 |
| BenQ(ベンキュー)『Home Entertainment(TH671ST)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月2日時点 での税込価格 |
ゲーム用に作られたプロジェクター | フルHD(1920×1080) | 3000lm | 10000:1 | あり | 2.5m(100インチ) | - | 2系統 |
ゲームプロジェクターの魅力
部屋に白い壁があればスクリーンを用意しなくても大画面でゲームを楽しめるのが、ゲームプロジェクターの魅力。大きな画面でプレイすると、よりゲームの世界に入り込めます。ひとりで楽しむときはもちろん、友だちや家族とプレイするとき大画面ならいっそう盛り上がるでしょう。
本体サイズがコンパクトな機種も多く、なかには携帯できるサイズのプロジェクターも販売されています。どこでも美しい大画面でゲームを楽しめますよ。
ゲームプロジェクターの選び方
それでは、ゲームプロジェクターの基本的な選び方を見ていきましょう。ポイントは下記の5つ。
【1】解像度
【2】明るさ
【3】コントラスト比
【4】HDMI入力対応か
【5】搭載機能
上記の5つのポイントをおさえることで、より具体的に欲しい機能を知ることができます。一つひとつ解説していきます。
【1】解像度をチェック
解像度はフルハイビジョン以上であれば快適にプレイできます。ゲームだけではなく、映画鑑賞やスポーツ観戦にも使えるほど画面が美しいですよ。
ゲームのなかには、グラフィックの美しさが魅力の作品もあります。その映像美に浸りたい方は、4K対応プロジェクターという選択肢も。PS5などの4K対応ゲーム機なら、4K対応プロジェクターで投影すると映像の美しさを味わえるでしょう。
ただし4K対応プロジェクターはかなり高価なうえ、ゲーム自体が4K出力に対応していないと、まったく意味がありません。また解像度を上げることによってフレームレート(動きの滑らかさ)が下がってしまうゲームもあります。4K対応の恩恵をきちんと受けられるゲームなのか、事前に確認しておく必要があります。
【2】明るさをチェック
「昼間でもゲームをしたい」「視力低下が気になるから部屋を明るくしてゲームをしたい」といった方も多いでしょう。その場合は輝値に注意してください。プロジェクターの輝度はルーメン(lm)という単位であらわされ、数字が大きいほど映像が明るくなります。
昼間もしくは明るい部屋で使用する場合、輝度は3000ルーメン以上が目安。これ以下だとなにが映っているかわかりづらい場合があるので、忘れずにチェックしてくださいね。ただし輝度と解像度がともに高い製品はかなり高価になります。その点は注意しましょう。
【3】コントラスト比をチェック
ホラーゲームやダンジョン探索型ゲームなど、暗い画面でプレイするゲームが好きなら、コントラスト比も重要です。
画面の暗いところと明るいところの差をあらわすコントラスト比は、10000:1以上あると明暗がはっきりします。数値が低いと明暗のメリハリがないぼんやりとした映像になることもあるので、ぜひチェックしておきたいポイントです。
【4】HDMI入力対応かチェック
ゲームをするためには、プロジェクターがHDMI対応かどうか要チェック。PS5、PS4、Nintendo Switch、Xboxなどをプロジェクターで楽しむには、ゲーム機とプロジェクターをHDMIケーブルでつなぐ必要があります。
多くのプロジェクターがHDMIに対応していますが、まれに対応していないものもあるので注意してください。万が一対応していない場合は、画質があまりよくありませんが、VGA→HDMIコンバーターなどを使用するという方法もあります。
【5】搭載機能をチェック
ゲームプロジェクターは商品によって機能が異なります。そのため、必要な搭載機能を確認してから選ぶようにしましょう。
ゲーム用のプロジェクターを選ぶときに見ておきたいポイントは、遅延対策・投射可能距離・動作音の3点です。この3点をおさえておくと、より快適にゲームが楽しめますよ。
遅延の少ないゲームモード搭載モデルならノンストレス
プロジェクターの内部ではさまざまな情報処理が行なわれており、入力した情報を投射するのが遅れる遅延現象が起きることがあります。ゲームの操作と映像に反映されるまでの時間にラグがあると、動きが一瞬止まってしまってイライラしてしまうかもしれません。
「ゲームモード」搭載のプロジェクターなら遅延を減らすことができるので、ラグによるストレスから解放されるでしょう。FPSや格闘ゲームなど、スピード感が命のゲームも快適にプレイできますよ。
ただし、ゲームモードと謳っていても実際はあまりラグの軽減になっていない製品も中にはあります。口コミや実際に試せる家電量販店やオーディオショップなどで試遊するのが確実です。
投射可能距離は? 短焦点タイプなら至近距離でもOK
大画面でゲームを楽しもうとするときに気になるのが投射可能距離です。大きいサイズで投影しようとすると、プロジェクターと壁の距離を長く取らざるをえないことも多いでしょう。
しかし「短焦点」タイプなら、短い距離でも大画面で投影できます。小さめの部屋でも大画面で映すことが可能なので、ゲームの世界に思いきり入り込めますね。ただし、画面に歪みが生じやすいため、台形補正機能がついているものが望ましいです。
動作音も確認! 集中できる静音モード搭載機種も
プロジェクターは作動時の放熱をやわらげるため、冷却ファンが作動します。この冷却ファンの音が大きいと、気になってゲームに集中できないかもしれません。ゲームでは効果音やBGMも重要なので、雑音に邪魔されたくないですよね。
「静音モード」搭載のプロジェクターなら、動作音に気を取られることなくゲームに集中できます。ささやき声レベルの30dB前後を目安に選んでみましょう。
ゲームプロジェクターおすすめ9選
それでは、ゲームプロジェクターのおすすめ商品をご紹介します。高解像度で美しい映像が魅力のものや、超コンパクトで持ち運びができるものなど、幅広くピックアップしました。
あなたのゲームライフをもっと快適にするゲームプロジェクターが見つかるはずですよ。
どこでも高解像度・大画面のスクリーンを楽しめる!
どこでも設置ができるモバイルタイプのプロジェクター。すでにYouTubeやAmazonPrime、Netflixなどのアプリがインストールされているので、電源をいれるだけで動画コンテンツを見ることができます。
また、フルHDの解像度ながら最大300インチの大画面を楽しめるのも魅力的です。スピーカー機能も充実しているので、これ1台でゲームをとことん楽しむことができるでしょう。
※各社通販サイトの 2025年3月2日時点 での税込価格
| 解像度 | FULL HD1080P(1920×1080) |
|---|---|
| 輝度 | 200ANSIルーメン |
| コントラスト比 | - |
| ゲームモード | - |
| 投射可能距離 | 1.2:1(38インチ/1メートル) |
| 最小騒音レベル | - |
| HDMI端子 | 1系統 |
| 解像度 | FULL HD1080P(1920×1080) |
|---|---|
| 輝度 | 200ANSIルーメン |
| コントラスト比 | - |
| ゲームモード | - |
| 投射可能距離 | 1.2:1(38インチ/1メートル) |
| 最小騒音レベル | - |
| HDMI端子 | 1系統 |
フルHDの解像度と大画面でゲームが楽しめる
フルHD (1920 × 1080 画素)の高解像度できれいな映像が楽しめるプロジェクター。ゲーム画面の細部まで映し出し、こだわり抜かれた美しさや技術の高さを実感できます。
コンパクトな本体なのに、100インチの大画面投影が可能です。壁や天井など好きな場所に映して大画面でゲームをプレイしましょう。ゲームの世界にどっぷり浸れますよ。
※各社通販サイトの 2025年3月2日時点 での税込価格
| 解像度 | フルHD (1920 × 1080 画素) |
|---|---|
| 輝度 | 300lm |
| コントラスト比 | - |
| ゲームモード | - |
| 投射可能距離 | - |
| 最小騒音レベル | 28dB |
| HDMI端子 | 1系統 |
| 解像度 | フルHD (1920 × 1080 画素) |
|---|---|
| 輝度 | 300lm |
| コントラスト比 | - |
| ゲームモード | - |
| 投射可能距離 | - |
| 最小騒音レベル | 28dB |
| HDMI端子 | 1系統 |
世界初Android TV搭載家庭プロジェクター
Android TV 9.0を搭載しており、YoutubeやNetflix、Disney+を含む3,600以上のアプリからお気に入りのコンテンツを探すことができます。天井から降り注ぐ新感覚の音響体験はまるで映画館のような臨場感あるサウンド。
800ANSIルーメンの高精細映像は昼間でも鮮明に投影が可能です。電源を入れると、自動でピントを合わせてくれるので細かな設定は不要。耐震性にも優れており、安全対策もバッチリです!
※各社通販サイトの 2025年3月2日時点 での税込価格
| 解像度 | フルHD (1920 × 1080 画素) |
|---|---|
| 輝度 | 800lm |
| コントラスト比 | - |
| ゲームモード | - |
| 投射可能距離 | 0.9m(40インチ) |
| 最小騒音レベル | 50dB |
| HDMI端子 | 1系統 |
| 解像度 | フルHD (1920 × 1080 画素) |
|---|---|
| 輝度 | 800lm |
| コントラスト比 | - |
| ゲームモード | - |
| 投射可能距離 | 0.9m(40インチ) |
| 最小騒音レベル | 50dB |
| HDMI端子 | 1系統 |
スポーツ鑑賞にもゲームプレイにもおすすめ!
4K UHD(3840x2160)の解像度と830万ピクセルを実現したハイスペックタイプのプロジェクター。高速16.7msの低入力遅延により、リアルタイムでスムーズな再生が求められるスポーツ観戦におすすめ。
また、ゲームモードが搭載されており、インターフェイスも豊富でPS5・PS4、Nintendo Switchなどとの互換性も抜群。深みのある低音が特徴のtreVoloステレオスピーカーが装備されている点も魅力です。
※各社通販サイトの 2025年3月2日時点 での税込価格
| 解像度 | 4K(3840 x 2160) |
|---|---|
| 輝度 | 3,200lm |
| コントラスト比 | 10000:1 |
| ゲームモード | 〇 |
| 投射可能距離 | - |
| 最小騒音レベル | 34dB |
| HDMI端子 | 2系統 |
| 解像度 | 4K(3840 x 2160) |
|---|---|
| 輝度 | 3,200lm |
| コントラスト比 | 10000:1 |
| ゲームモード | 〇 |
| 投射可能距離 | - |
| 最小騒音レベル | 34dB |
| HDMI端子 | 2系統 |
自宅のあらゆる場所がミニシアターに
オートフォーカス・自動垂直台形補正機能と角度調整機能が搭載されており、自宅のあらゆる場所に投影が可能。その空間に最適な角度とサイズで鮮明な映像を映し出します。
縦横20cmのコンパクトサイズと本革のハンドル付きで持ち運びもラクラク。最大2.5時間のバッテリーが内蔵されているので、お庭やベランダでも映画1本分なら気軽に視聴できます。
※各社通販サイトの 2025年3月2日時点 での税込価格
| 解像度 | HD(1280×720) |
|---|---|
| 輝度 | 300lm |
| コントラスト比 | 100,000:1 |
| ゲームモード | - |
| 投射可能距離 | - |
| 最小騒音レベル | 27dB |
| HDMI端子 | 2系統 |
| 解像度 | HD(1280×720) |
|---|---|
| 輝度 | 300lm |
| コントラスト比 | 100,000:1 |
| ゲームモード | - |
| 投射可能距離 | - |
| 最小騒音レベル | 27dB |
| HDMI端子 | 2系統 |
自宅はもちろん、キャンプ、寝室でも
ポータブルタイプのプロジェクターの中でもトップクラスに明るい900ANSI ルーメンのフルHDプロジェクター。Android TV 10.0搭載により、Google Playから5000を超えるアプリのダウンロードが可能です。
HDR10技術により、高いコントラスト比で細かな色深度の映像を再現。本体底部には、折りたたみ式のスタンドを備え、最大30度までお好みの角度調節ができます。
※各社通販サイトの 2025年3月2日時点 での税込価格
| 解像度 | フルHD(1920x1080) |
|---|---|
| 輝度 | 900lm |
| コントラスト比 | - |
| ゲームモード | - |
| 投射可能距離 | - |
| 最小騒音レベル | 30dB |
| HDMI端子 | - |
| 解像度 | フルHD(1920x1080) |
|---|---|
| 輝度 | 900lm |
| コントラスト比 | - |
| ゲームモード | - |
| 投射可能距離 | - |
| 最小騒音レベル | 30dB |
| HDMI端子 | - |
場所を選ばずに設置できる「ピタッと補正機能」搭載
ピタッと補正機能搭載で、置くだけで縦横ゆがみのないきれいな長方形画面を投影できる機種です。プロジェクターを設置するとき、画面が台形にならないよう気をつけて置いていた方も多いのではないでしょうか。こちらのモデルなら置く場所を選ばずに使用できて便利です。
コントラスト比16000:1なので、映像の暗いゲームもお任せ。奥行き感のあるリッチな映像が楽しめます。ゲームの奥深い世界に没頭できますね。
※各社通販サイトの 2025年3月2日時点 での税込価格
| 解像度 | フルHD(1920×1080) |
|---|---|
| 輝度 | 3400lm |
| コントラスト比 | 16000:1 |
| ゲームモード | あり |
| 投射可能距離 | 1.3m |
| 最小騒音レベル | 28dB |
| HDMI端子 | 2系統 |
| 解像度 | フルHD(1920×1080) |
|---|---|
| 輝度 | 3400lm |
| コントラスト比 | 16000:1 |
| ゲームモード | あり |
| 投射可能距離 | 1.3m |
| 最小騒音レベル | 28dB |
| HDMI端子 | 2系統 |
4K相当の高画質で最大150インチの大画面
最大150インチの大画面で4K相当の高画質な映像を投影可能なプロジェクターです。超短焦点レンズ採用により、壁やスクリーンから約2.5cm離れたところに設置して、80インチの大画面を実現。
本体にはヤマハ製2.1ch(ステレオスピーカー+ウーファー)の高音質スピーカーを搭載しており、パワフルで立体感のあるサウンドを体験できます。入力遅延20ms以下のHDMIに接続することでよりゲームを快適に楽しめます。
※各社通販サイトの 2025年3月2日時点 での税込価格
| 解像度 | 4K |
|---|---|
| 輝度 | 4000lm |
| コントラスト比 | 2,500,000:1 |
| ゲームモード | - |
| 投射可能距離 | - |
| 最小騒音レベル | 19dB |
| HDMI端子 | 2系統 |
| 解像度 | 4K |
|---|---|
| 輝度 | 4000lm |
| コントラスト比 | 2,500,000:1 |
| ゲームモード | - |
| 投射可能距離 | - |
| 最小騒音レベル | 19dB |
| HDMI端子 | 2系統 |
ゲーム用に作られたプロジェクター
16.67msの応答速度で遅延が少なく、動きのブレやタイミングのズレに悩まされません。ストレスなくゲームに没頭できるでしょう。バトルゲームやスポーツゲームなどが、思いどおりの滑らかでスピーディーなモーションで楽しめます。
ゲームモードを搭載したスピーカーで、迫力のある低音やシャープな高音を響かせるのが魅力。臨場感のあるサウンドでゲームができ、手に汗を握るリアリティーを楽しめます。
※各社通販サイトの 2025年3月2日時点 での税込価格
| 解像度 | フルHD(1920×1080) |
|---|---|
| 輝度 | 3000lm |
| コントラスト比 | 10000:1 |
| ゲームモード | あり |
| 投射可能距離 | 2.5m(100インチ) |
| 最小騒音レベル | - |
| HDMI端子 | 2系統 |
| 解像度 | フルHD(1920×1080) |
|---|---|
| 輝度 | 3000lm |
| コントラスト比 | 10000:1 |
| ゲームモード | あり |
| 投射可能距離 | 2.5m(100インチ) |
| 最小騒音レベル | - |
| HDMI端子 | 2系統 |
「ゲームプロジェクター」のおすすめ商品の比較一覧表
| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 解像度 | 輝度 | コントラスト比 | ゲームモード | 投射可能距離 | 最小騒音レベル | HDMI端子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiraArc(ミラアーク)『CINEMAGE Pro(シネマージュプロ)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月2日時点 での税込価格 |
どこでも高解像度・大画面のスクリーンを楽しめる! | FULL HD1080P(1920×1080) | 200ANSIルーメン | - | - | 1.2:1(38インチ/1メートル) | - | 1系統 |
| Anker(アンカー)『Nebula (ネビュラ) Capsule 3 Laser』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月2日時点 での税込価格 |
フルHDの解像度と大画面でゲームが楽しめる | フルHD (1920 × 1080 画素) | 300lm | - | - | - | 28dB | 1系統 |
| Anker(アンカー)『Nebula Nova(D2160521)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月2日時点 での税込価格 |
世界初Android TV搭載家庭プロジェクター | フルHD (1920 × 1080 画素) | 800lm | - | - | 0.9m(40インチ) | 50dB | 1系統 |
| BenQ(ベンキュー)『DLP 4Kホームプロジェクター(TK700)』 |
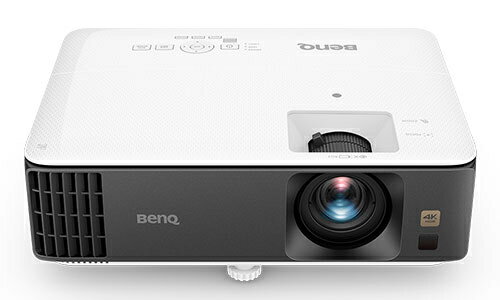
|
※各社通販サイトの 2025年3月2日時点 での税込価格 |
スポーツ鑑賞にもゲームプレイにもおすすめ! | 4K(3840 x 2160) | 3,200lm | 10000:1 | 〇 | - | 34dB | 2系統 |
| BenQ(ベンキュー)『GV30 HD モバイルLEDプロジェクター』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月2日時点 での税込価格 |
自宅のあらゆる場所がミニシアターに | HD(1280×720) | 300lm | 100,000:1 | - | - | 27dB | 2系統 |
| XGIMI『XGIMI Halo+』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月2日時点 での税込価格 |
自宅はもちろん、キャンプ、寝室でも | フルHD(1920x1080) | 900lm | - | - | - | 30dB | - |
| EPSON(エプソン)『ドリーミオ ホームプロジェクター(EH-TW750)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月2日時点 での税込価格 |
場所を選ばずに設置できる「ピタッと補正機能」搭載 | フルHD(1920×1080) | 3400lm | 16000:1 | あり | 1.3m | 28dB | 2系統 |
| EPSON(エプソン)『ドリーミオ ホームプロジェクター(EH-LS800B)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月2日時点 での税込価格 |
4K相当の高画質で最大150インチの大画面 | 4K | 4000lm | 2,500,000:1 | - | - | 19dB | 2系統 |
| BenQ(ベンキュー)『Home Entertainment(TH671ST)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月2日時点 での税込価格 |
ゲーム用に作られたプロジェクター | フルHD(1920×1080) | 3000lm | 10000:1 | あり | 2.5m(100インチ) | - | 2系統 |
通販サイトの最新人気ランキングを参考にする ゲームプロジェクターの売れ筋をチェック
Amazon、楽天市場でのゲームプロジェクターの売れ筋ランキングも参考にしてみてください。
※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。
ゲームプロジェクターに関するQ&A よくある質問


プロジェクターの耐用年数は、プロジェクタの光源にあたるランプの性能の影響が大きく、ここ数年で技術的に耐用年数が伸びています。
古い機種や現行の一部機種ではランプの耐用時間2,000時間程度、最新の機種では4,000時間~、LEDタイプでは数万時間まであります。
薄型テレビはバックライトがLEDになり耐用年数が6万時間程度と一般家庭では10年以上。プロジェクターはテレビと比べるとやや耐用年数が短いとも言えます。
プロジェクターではバックライトの寿命がスペック上に記載されている製品が多いので、毎日一日中映像を流し続けるような場合は、耐用時間を確認しておきましょう。(ランプの寿命が過ぎたプロジェクターはランプ交換のできる機種もあります。)
処分する際、プロジェクターは家電リサイクルの対象品ではないので、個人で利用している方は自治体の定める一般的な家電ゴミとして処分ができます。
リサイクルショップ等に持ち込んで買い取ってもらうこともおすすめです。


NHK受信料の支払い義務は生じません。まず前提として、プロジェクターはテレビのアンテナが不要です。テレビ番組を観られる環境、またアンテナがあってテレビとの接続が可能な状況にのみ受信料の契約義務が生じます。普段、テレビ番組を観ない、YouTubeやゲーム、動画配信サービス、仕事などで使う人にはプロジェクターがおすすめです。
ゲームプロジェクターに関するそのほかのおすすめ記事 【関連記事】
「ゲームモード」搭載かにも注目! 家電・ITライターからのアドバイス
みんなでワイワイとパーティゲームをするなら、FHD対応のコスパ重視のもの。FPSや格闘ゲームなどをストイックにやり込みたいなら、ゲームモードを搭載したゲーム用のプロジェクターがいいですね。プロジェクターを使用するときは「ある程度暗くできる」「無地の白い壁がある」ことが必要になります。それ以外の環境で投影しようとすると、細部が見づらかったりするなどの弊害があることもおさえておきましょう。
解像度や輝度、コントラスト比など高スペックのものがベター
ゲームプロジェクターのおすすめ商品をご紹介しました。ゲームプロジェクターを選ぶときは、解像度や輝度、コントラスト比など映像の見やすさ、遅延の少なさや投射可能距離、冷却ファンの作動音などの搭載機能をチェックしましょう。
この記事を商品選びの参考にして、あなたにぴったりのゲームプロジェクターを見つけてくださいね。
◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。



























































