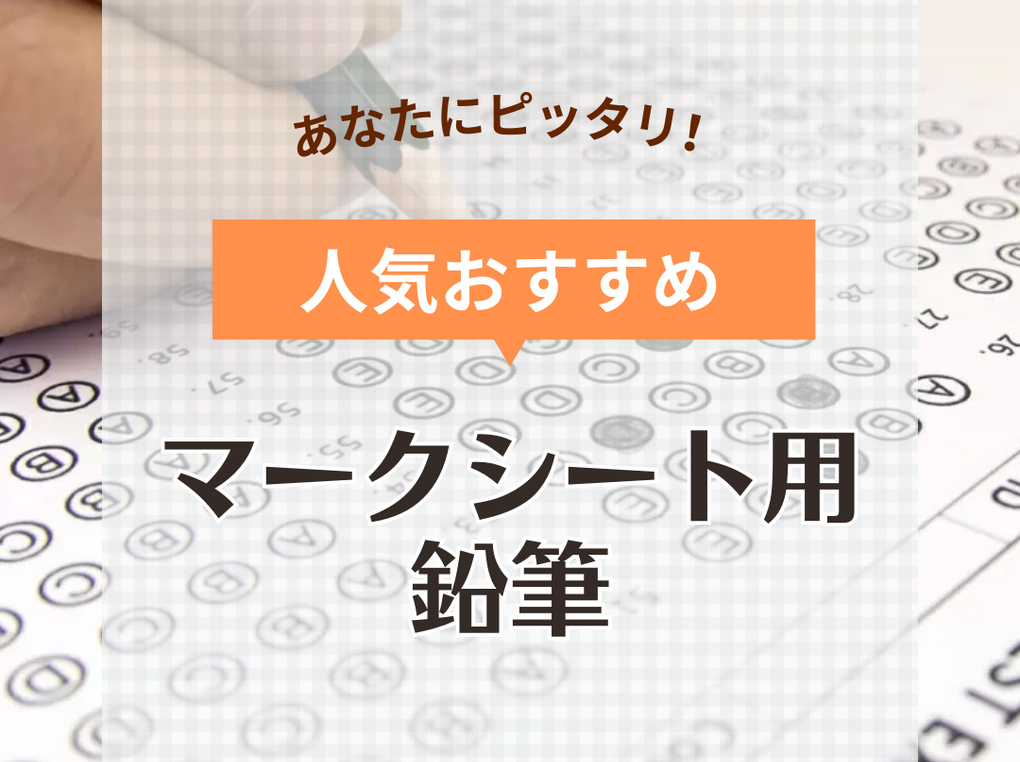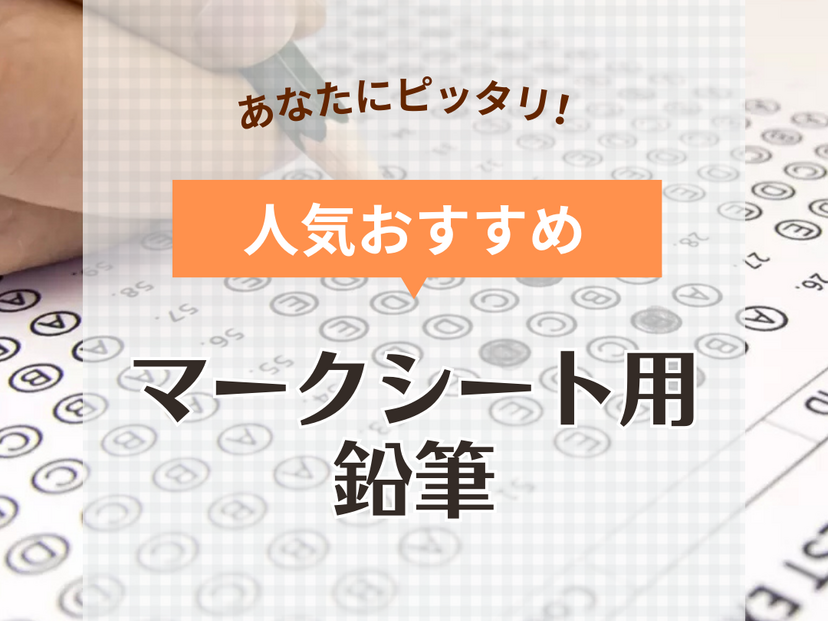| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 濃さ | 先削り | 内容量 | 付属品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱鉛筆『uni マークシート用鉛筆』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月1日時点 での税込価格 |
滑らかで折れにくく消しやすい | HB | × | 12本 | - |
| トンボ鉛筆『MONO マークシート用鉛筆 無地』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月1日時点 での税込価格 |
MONO鉛筆、無地仕様でどんな試験にも | HB | ○ | 3本 | キャップ |
| ステッドラー『ホワイト試験用鉛筆』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月1日時点 での税込価格 |
高級製図用鉛筆と同じ書き味で試験を | HB | × | 3本 | キャップ |
| クツワ『HiLiNe オレンピツ 試験用3本セット』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月1日時点 での税込価格 |
芯強度2倍! 折れるのが不安な方に | HB | ○ | 3本 | キャップ |
| 三菱鉛筆『uni マークシート用鉛筆 受験・テスト用 無地柄鉛筆』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月1日時点 での税込価格 |
マークシート用鉛筆の定番「uni」の無地タイプも | HB | ○ | 3本 | キャップ |
| 南三陸復興ダコの会『オクトパス君 合格えんぴつ』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月1日時点 での税込価格 |
縁起がよく、転がりにくい五角形鉛筆 | HB | × | 3本 | - |
| 大和だるまじ『必勝! だるま 合格 (五角) 鉛筆』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月1日時点 での税込価格 |
奈良達磨寺にて合格祈願済みの鉛筆 | HB | × | 10本 | のし袋 |
| アイボール鉛筆『OLEN MARK SHEET(マークシート鉛筆)』 |
|
※各社通販サイトの 2025年3月1日時点 での税込価格 |
老舗鉛筆メーカーのマークシート専用鉛筆 | HB | × | 1本 | - |
| Stabilo(スタビロ)『イグザムグレード鉛筆』 |
|
※各社通販サイトの 2025年3月1日時点 での税込価格 |
学生向けに調整された試験のための鉛筆 | 2B | × | 12本 | - |
| ソニック『キュポット えんぴつキャップ』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月1日時点 での税込価格 |
抜け落ちにくく割れにくい鉛筆キャップ | ‐ | ‐ | 6個入 | - |
| クツワ『HiLiNe 補助軸(ツイン)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月1日時点 での税込価格 |
両頭使いの補助軸は長いままの鉛筆も差せる | ‐ | ‐ | 1本 | - |
| クツワ『STAD プニュグリップ』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月1日時点 での税込価格 |
鉛筆にもやわらかグリップをどうぞ | ‐ | ‐ | 4個 | - |
普通の鉛筆とマークシート用鉛筆の違いは? 使い分ける必要はある?
マークシート用鉛筆は普通の鉛筆と違い、マークシートの読み取りに最適な硬度や塗りつぶしやすさに長けています。
マークシート用鉛筆と一口にいってもその種類やこだわりは様々。メーカーや商品によって軽い力で濃く書けるように芯の材料にこだわっていたり、消しゴムで簡単に消せるようになっている商品が販売されています。
中には合格祈願済みのえんぴつもあるので、入試や受験を控えている方はぜひチェックしてみてください。
マークシート用鉛筆の選び方 受験や資格試験に必須のアイテム!
文房具ユーザーの他故壁氏さんのアドバイスをもとに、マークシート用鉛筆の選び方を紹介します。ポイントは下記のとおり。
【1】品質・折れにくさ・商品&メーカー名の有無
【2】消えやすさ
【3】キャップ付きか
【4】補助軸やグリップの装着も検討
上記のポイントをおさえることで、より具体的に自分に合うマークシート用鉛筆を選ぶことができます。一つひとつ解説していきます。
【1】着目すべきは「品質」「文字の有無」「折れにくさ」
マークシート用をうたう製品の多くは、HBでありながら濃く、なめらかで、折れにくく、芯が減りにくい高級鉛筆です。迷ったら「マークシート用」と書かれた製品をまず探してみてください。
「ふだん鉛筆を使わないので選び方がわからない」という方は、日本製の製品を選びましょう。JISによって品質が保証されています。
「筆圧が強く、鉛筆の芯が折れやすい」と不安を感じている方は、同じHBでもより折れにくい特徴をもった製品を。持ち込みできる鉛筆が無地に指定されている試験を受ける際には、メーカー名や商品名などが印刷されていない鉛筆を選ぶことも必要となってきます。
【2】消えやすさも重要なポイント
鉛筆は、硬度が高い(H以上)と黒鉛より粘土の量が多く硬くなり、逆に硬度が低い(B以上)になると黒鉛の量が粘土より多くなり柔らかくなります。マークシート読み取り機は鉛筆の黒鉛 = 炭素に反応しますから、硬度が高いものは反応が鈍くなります。
とはいえ、ただ濃ければいいというわけでもなく、間違いを消しゴムで消した場合、紙の上に炭素が残ってしまうようでは誤認の原因となってしまいます。
マークシート専用鉛筆は同硬度の市販の鉛筆より綺麗に消せるよう調整がされていますが、原則HB程度の濃さのものを選ぶようにしましょう。
【3】鉛筆キャップ付きのものだと安心
マークシート用鉛筆を持ち込むにあたり、鉛筆キャップをつけておくことをおすすめします。仮にペンケースごと机上から床に落下させてしまい、先端が折れて書きにくくなってしまった鉛筆が多数発生したら目も当てられません。
幸いなことに、鉛筆キャップを持ち込んではいけない試験はさほどないようですので、鉛筆にはぜひキャップをつけてください。最初からキャップがついている製品を選ぶと安心です。また、学童用に実用的な鉛筆キャップがありますので、それを使うのもいいでしょう。
【4】握りにくいときは、補助軸やグリップを活用して
普段はシャープペンシルやボールペンを使っているのに、いざ試験となるとマークシートのため鉛筆を握らざるをえない、という方も多いでしょう。そういう方の不満のひとつに、「鉛筆がふだん使っている筆記具より細くて握りづらい」という点があげられます。
これを回避する方法として、マークシート用鉛筆をある程度太さをもった鉛筆補助軸に入れる方法や、持ち手に当たる部分にラバー製のカバーを装着して太さを出す、といった策を採ることも必要かもしれません。
エキスパートからのアドバイス
迷ったら「専用」のものを!
マークシート鉛筆と一般的な鉛筆の差は、興味のない方からすれば微々たるものかもしれません。
しかしながら、マークシートの読み取りに最適な硬度で、塗りつぶしたときに引っかかりがなく、消しゴムで消したときに炭素残りがないなど、たくさんの長所がある専用鉛筆を選んだことによる精神的な余裕は、必ず試験にプラスに働くと思います。
専用には専用の意味があります。極端に高いわけでもありませんから、マークシート試験を受ける方にはマークシート専用の鉛筆をおすすめいたします。
マークシート用鉛筆おすすめ9選 文房具ユーザーと編集部が厳選!
うえで紹介したマークシート用鉛筆の選び方のポイントをふまえて、文房具ユーザーの他故壁氏さんに選んでもらったおすすめ商品を紹介します。

滑らかで折れにくく消しやすい
マークシート用紙にマークするために調整された専用鉛筆で、HBでありながら濃くて折れにくく、消しゴムでよく消えます。市販の鉛筆に比べてなめらかで、試験中のストレスを最大限に押さえ込むことができます。
パックで販売されているものは先端がすでに削られており、鉛筆キャップが装着されています。試験本番に向けて、鉛筆を大量に準備したい方のために、ダース箱が準備されているのも心強いです。
※各社通販サイトの 2025年3月1日時点 での税込価格
| 濃さ | HB |
|---|---|
| 先削り | × |
| 内容量 | 12本 |
| 付属品 | - |
| 濃さ | HB |
|---|---|
| 先削り | × |
| 内容量 | 12本 |
| 付属品 | - |

MONO鉛筆、無地仕様でどんな試験にも
最近増えてきた、文字が書いてある鉛筆や消しゴムなどの持ち込みを禁止する試験に対応したマークシート鉛筆です。ボディにトンボマークのみ入った無地仕様になっています。
濃くマークでき、こすれにも強いマークシート専用鉛筆で、先端がすでに削られており、鉛筆キャップが付属しています。
日本でもっとも使われている『MONO消しゴム』との相性が抜群で、消し損ねによるマークシート読み取り機の誤判断を防いでくれます。
※各社通販サイトの 2025年3月1日時点 での税込価格
| 濃さ | HB |
|---|---|
| 先削り | ○ |
| 内容量 | 3本 |
| 付属品 | キャップ |
| 濃さ | HB |
|---|---|
| 先削り | ○ |
| 内容量 | 3本 |
| 付属品 | キャップ |

高級製図用鉛筆と同じ書き味で試験を
製図用鉛筆で著名なドイツの「ステッドラー」のマークシート用鉛筆。こちらもキャップつきで白無地(ステッドラーロゴとマークは入っています)と、最近のさまざまな試験に対応しています。
高級製図用鉛筆『マルスルモグラフ』と同じ芯を使用しており、日本製のものと比べやや硬めで芯の減りが少ない製品です。硬いタッチがお好みの方、減りの少ない鉛筆を欲している方におすすめします。
この鉛筆は販売時に削られていませんので、自宅で削ってからご使用ください。
※各社通販サイトの 2025年3月1日時点 での税込価格
| 濃さ | HB |
|---|---|
| 先削り | × |
| 内容量 | 3本 |
| 付属品 | キャップ |
| 濃さ | HB |
|---|---|
| 先削り | × |
| 内容量 | 3本 |
| 付属品 | キャップ |

芯強度2倍! 折れるのが不安な方に
他社製品との違いは、芯の強度。「芯の強度2倍以上」をうたい文句にした、落下してもペンケースで揺さぶられても折れない鉛筆です。折れにくくても書き味はなめらかで、試験に支障が出ることはありません。筆圧が高く、折れるのを心配している方は一度お試しください。
他社にない特徴として、本製品は尾部に消しゴムを装着しています。試験中に消しゴムを落としてしまっても、予備がある安心感は大きいでしょう。
ただし、本製品は「マークシート用」の表記がありません。専用鉛筆ではないことをご承知おきください。
※各社通販サイトの 2025年3月1日時点 での税込価格
| 濃さ | HB |
|---|---|
| 先削り | ○ |
| 内容量 | 3本 |
| 付属品 | キャップ |
| 濃さ | HB |
|---|---|
| 先削り | ○ |
| 内容量 | 3本 |
| 付属品 | キャップ |
マークシート用鉛筆の定番「uni」の無地タイプも
「uni」の無地タイプのマークシート用鉛筆。濃くきれいにマークすることができ、芯の硬度が均一なので細かいマーク箇所にも最適です。
3本入りのパックで販売されており、削り済み。それぞれに鉛筆キャップがついているのもうれしいポイントです。
※各社通販サイトの 2025年3月1日時点 での税込価格
| 濃さ | HB |
|---|---|
| 先削り | ○ |
| 内容量 | 3本 |
| 付属品 | キャップ |
| 濃さ | HB |
|---|---|
| 先削り | ○ |
| 内容量 | 3本 |
| 付属品 | キャップ |
縁起がよく、転がりにくい五角形鉛筆
タコの名産地である南三陸のゆるキャラ、オクトパスくんにちなんだ鉛筆です。オクトパスくんは、「置くとパス」するというシャレから縁起をかつがれ、試験にいどむ多くの方が買い求めているそうです。
HBの3本入りで、合格と五角をひっかけた五角形の鉛筆という点もポイントです。鉛筆の形は円に近いほど転がりやすく、五角形の鉛筆は六角形の鉛筆よりも、転がりにくいという特徴を持っています。
試験場の机は、やや前方に傾斜しているところもあります。この五角形の鉛筆なら、そんな環境でも安心して試験にいどめるかもしれません。
※各社通販サイトの 2025年3月1日時点 での税込価格
| 濃さ | HB |
|---|---|
| 先削り | × |
| 内容量 | 3本 |
| 付属品 | - |
| 濃さ | HB |
|---|---|
| 先削り | × |
| 内容量 | 3本 |
| 付属品 | - |
奈良達磨寺にて合格祈願済みの鉛筆
奈良のお寺の合格祈願鉛筆です。これも鉛筆としては標準的なHB。本製品も軸が五角形です。試験中につい鉛筆を落としてしまうという方は、縁起かつぎを抜きにして、使用を検討してもいいでしょう。
ただ、形が特殊なため使っていて指が痛くなる可能性もあります。あらかじめよく慣れておくか、ペン軸のような補助具の併用も検討しておきましょう。
※各社通販サイトの 2025年3月1日時点 での税込価格
| 濃さ | HB |
|---|---|
| 先削り | × |
| 内容量 | 10本 |
| 付属品 | のし袋 |
| 濃さ | HB |
|---|---|
| 先削り | × |
| 内容量 | 10本 |
| 付属品 | のし袋 |

老舗鉛筆メーカーのマークシート専用鉛筆
東京都葛飾区にある鉛筆メーカー「アイボール鉛筆」のマークシート用鉛筆です。
日本鉛筆工業協同組合に加盟しているメーカーはJIS(日本工業規格)の規定に沿って作られており、現在では技術的に成熟した産業であるためJISマークを入れずとも品質に問題はない製品となっています。アイボール鉛筆も組合加盟企業で、品質は保証されています。
マークシート専用鉛筆の滑らかさ、濃さ、折れにくさと消去性能のよさをぜひご堪能ください。なお、本製品は削られておらず、鉛筆キャップも付属しません。
※各社通販サイトの 2025年3月1日時点 での税込価格
| 濃さ | HB |
|---|---|
| 先削り | × |
| 内容量 | 1本 |
| 付属品 | - |
| 濃さ | HB |
|---|---|
| 先削り | × |
| 内容量 | 1本 |
| 付属品 | - |

学生向けに調整された試験のための鉛筆
「スタビロ」はドイツの老舗筆記具メーカー。HBだけでなく、他社にない2Bをラインナップしているのがイグザムグレードシリーズの特徴です。
芯径がHBよりも太くなる分、塗りやすくマークシートに適しています。マークシート専用をうたっているわけではありませんが、安価な価格も魅力的です。
コストパフォーマンスを重視される方は参考にしてみてください。
※各社通販サイトの 2025年3月1日時点 での税込価格
| 濃さ | 2B |
|---|---|
| 先削り | × |
| 内容量 | 12本 |
| 付属品 | - |
| 濃さ | 2B |
|---|---|
| 先削り | × |
| 内容量 | 12本 |
| 付属品 | - |
マークシート用鉛筆の便利な補助具はこちら
マークシート用鉛筆とあわせて用意しておきたい、鉛筆用の補助具を「番外編」として紹介します。安心して試験にいどむために、こちらもチェックしてみてください。

抜け落ちにくく割れにくい鉛筆キャップ
学童用ですが、実用的な鉛筆キャップです。差し込み口がゴムになっており、差し込むときはソフトに、そして不意にはずれてしまわないよう工夫が成されています。
鉛筆キャップは強く差し込むと割れやすいものですが、キュポットは力を分散し、大人の力で強く差し込んでも破断が起きません。
鉛筆をダースで購入したり、キャップが附属されていない鉛筆を購入した際には、こうした高性能な鉛筆キャップを別に用意しておくと安心です。
※各社通販サイトの 2025年3月1日時点 での税込価格
| 濃さ | ‐ |
|---|---|
| 先削り | ‐ |
| 内容量 | 6個入 |
| 付属品 | - |
| 濃さ | ‐ |
|---|---|
| 先削り | ‐ |
| 内容量 | 6個入 |
| 付属品 | - |

両頭使いの補助軸は長いままの鉛筆も差せる
短くなった鉛筆を差して使う補助軸ですが、本製品は前後にチャックパーツがついており、2本の鉛筆を差して使うことができます。
「クツワ」の補助軸はグリップ部分がローレット加工されたアルミで、ほどよい太さとすべり止めも効いています。また『補助軸ツイン』は、長いままの鉛筆をセットすることも可能です。
お好みのマークシート鉛筆をセットし、試験にいどんでください。
※各社通販サイトの 2025年3月1日時点 での税込価格
| 濃さ | ‐ |
|---|---|
| 先削り | ‐ |
| 内容量 | 1本 |
| 付属品 | - |
| 濃さ | ‐ |
|---|---|
| 先削り | ‐ |
| 内容量 | 1本 |
| 付属品 | - |

鉛筆にもやわらかグリップをどうぞ
鉛筆に装着するラバーグリップ。鉛筆は細くて持ちにくいとお考えの方に最適です。学童用のラインナップですが、カラーのバリエーションも多く、また色、長さ、右利き用、左利き用と選択肢も豊富です。
グリップから色に合わせた香りがするのも特徴です。お気に入りのマークシート鉛筆に装着して、試験にいどんでみてください。
※各社通販サイトの 2025年3月1日時点 での税込価格
| 濃さ | ‐ |
|---|---|
| 先削り | ‐ |
| 内容量 | 4個 |
| 付属品 | - |
| 濃さ | ‐ |
|---|---|
| 先削り | ‐ |
| 内容量 | 4個 |
| 付属品 | - |
「マークシート用鉛筆」のおすすめ商品の比較一覧表
| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 濃さ | 先削り | 内容量 | 付属品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱鉛筆『uni マークシート用鉛筆』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月1日時点 での税込価格 |
滑らかで折れにくく消しやすい | HB | × | 12本 | - |
| トンボ鉛筆『MONO マークシート用鉛筆 無地』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月1日時点 での税込価格 |
MONO鉛筆、無地仕様でどんな試験にも | HB | ○ | 3本 | キャップ |
| ステッドラー『ホワイト試験用鉛筆』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月1日時点 での税込価格 |
高級製図用鉛筆と同じ書き味で試験を | HB | × | 3本 | キャップ |
| クツワ『HiLiNe オレンピツ 試験用3本セット』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月1日時点 での税込価格 |
芯強度2倍! 折れるのが不安な方に | HB | ○ | 3本 | キャップ |
| 三菱鉛筆『uni マークシート用鉛筆 受験・テスト用 無地柄鉛筆』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月1日時点 での税込価格 |
マークシート用鉛筆の定番「uni」の無地タイプも | HB | ○ | 3本 | キャップ |
| 南三陸復興ダコの会『オクトパス君 合格えんぴつ』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月1日時点 での税込価格 |
縁起がよく、転がりにくい五角形鉛筆 | HB | × | 3本 | - |
| 大和だるまじ『必勝! だるま 合格 (五角) 鉛筆』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月1日時点 での税込価格 |
奈良達磨寺にて合格祈願済みの鉛筆 | HB | × | 10本 | のし袋 |
| アイボール鉛筆『OLEN MARK SHEET(マークシート鉛筆)』 |
|
※各社通販サイトの 2025年3月1日時点 での税込価格 |
老舗鉛筆メーカーのマークシート専用鉛筆 | HB | × | 1本 | - |
| Stabilo(スタビロ)『イグザムグレード鉛筆』 |
|
※各社通販サイトの 2025年3月1日時点 での税込価格 |
学生向けに調整された試験のための鉛筆 | 2B | × | 12本 | - |
| ソニック『キュポット えんぴつキャップ』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月1日時点 での税込価格 |
抜け落ちにくく割れにくい鉛筆キャップ | ‐ | ‐ | 6個入 | - |
| クツワ『HiLiNe 補助軸(ツイン)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月1日時点 での税込価格 |
両頭使いの補助軸は長いままの鉛筆も差せる | ‐ | ‐ | 1本 | - |
| クツワ『STAD プニュグリップ』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月1日時点 での税込価格 |
鉛筆にもやわらかグリップをどうぞ | ‐ | ‐ | 4個 | - |
各通販サイトの最新人気ランキング 鉛筆の売れ筋をチェック
Amazon、楽天市場での鉛筆の売れ筋ランキングも参考にしてみてください。
※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。
この記事をご覧の方におすすめ! 【関連記事】
試験のルールに注意して、折れにくく書きやすいものを
マークシート用鉛筆の選び方とおすすめ商品、さらにはにぎりやすく快適に使用するための補助アイテムを紹介しました。
他故壁氏さんのアドバイスのように、マークシート方式の試験での誤答を減らすには専用の鉛筆が有効です。それぞれの特徴から、自分に合った鉛筆と、必要に応じて補助アイテムの使用も検討してみてください。
◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。