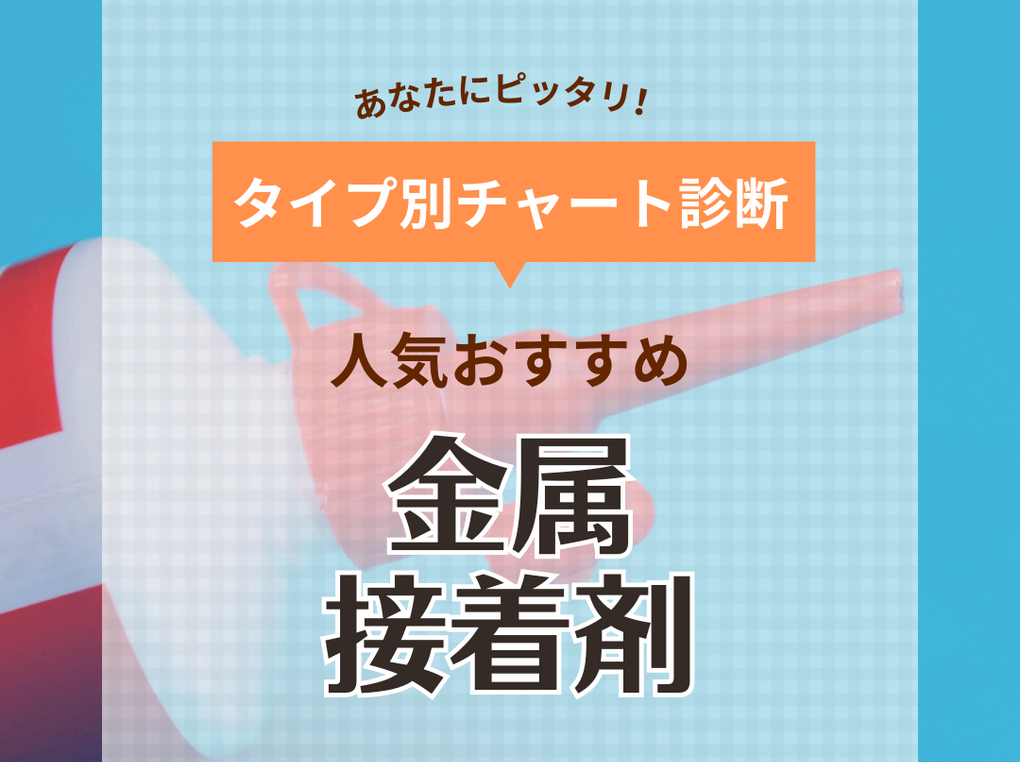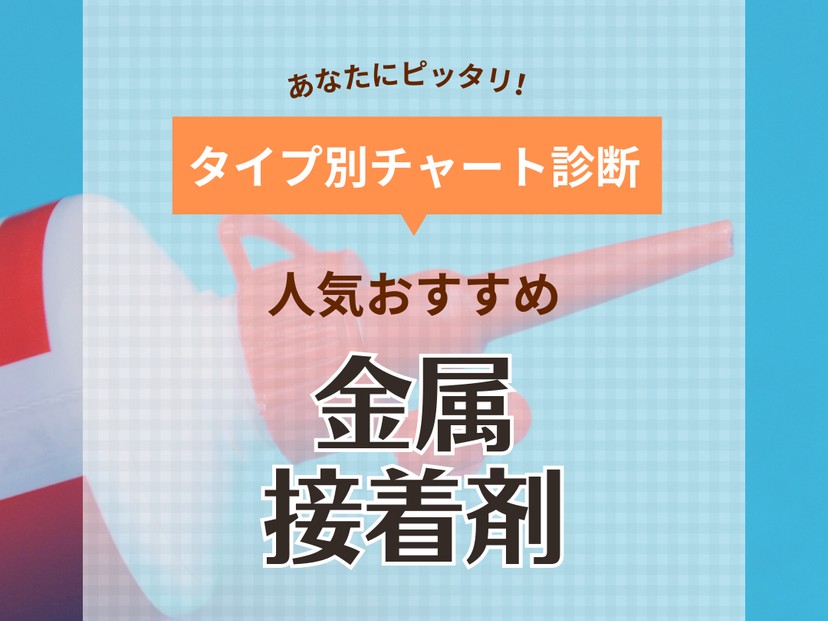| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 接着できない素材 | 耐熱温度 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コニシ『ボンド アロンアルフア プロ用耐衝撃(#31701)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月27日時点 での税込価格 |
衝撃や振動に強くて耐震性が高い | ポリエチレン系樹脂、ポリプロピレン系樹脂、シリコン樹脂、フッ素系樹脂、PET系樹脂、発砲スチロール | - | チューブ |
| セメダイン『メタルロック(AY-123)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月27日時点 での税込価格 |
金属同士もしっかり接着できる | ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、塩化ビニル など | - | チューブ |
| 隆成コミュニティ『J-B オートウエルド(AW-20Z)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月27日時点 での税込価格 |
幅広い素材に使用できる | - | 300℃ | チューブ |
| スピリットオブワンダー『BONDIC スターターキット コンプリート(BD-SKCJ)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月27日時点 での税込価格 |
さまざまな家庭用品に対応 | ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、 シリコーンゴム(パッキン等) ほか など | - | チューブ |
| スピリットオブワンダー『BONDIC EVO スターターキット コンプリート(BD-SKEJ)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月27日時点 での税込価格 |
ピストル型で使いやすい | ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、 シリコーンゴム(パッキン等) ほか など | - | ピストル型 |
| ヘンケル『LOCTITE 強力瞬間接着剤 高強度金属用(LKK-020)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月27日時点 での税込価格 |
ハイスピードで乾く瞬間接着剤 | おもちゃ、プラモデル、金属模型、アクセサリーや小物、陶磁器の置物、電気製品の樹脂/金属、PE、PP、シリコーン樹脂 ほか など | - | チューブ |
| コニシ『ボンド ウルトラ多用途SU(#04593)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月27日時点 での税込価格 |
クリア素材でさまざまな用途に使用できる | ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、フッ素樹脂、貴金属、高価格品 など | -30~80℃ | チューブ |
| ロックタイト『強力瞬間接着剤 ピンポインターゼリー状(LPJ-005)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月27日時点 での税込価格 |
耐水性・耐熱性にすぐれたアイテム | ガラス、PP、ナイロン、シリコンなど | 120℃ | チューブ |
| 呉工業『KURE ゴリラグルー クリア(1770)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月27日時点 での税込価格 |
凸凹部分もなんのその | PP、樹脂、貴金属など | 82℃ | チューブタイプ |
金属用接着剤はどのようなもの?
金属接着剤は、金属同士や金属とほかの素材を接着できるもの。普通の接着剤では紙やプラスチック、布の接着を目的としているものが多いですが、金属接着剤は、普通の接着剤では難しい金属を接着させられるのが特徴です。家庭内から屋外まで幅広く使用できます。また、耐久性や耐熱性、耐衝撃性、耐水性がある商品が多いです。
金属用接着剤の選び方 耐久性・耐熱性・耐水性が高いのはどれ?
金属接着剤の選び方にはいくつかのポイントがあります。ポイントは以下のとおりです。
【1】金属とどんな素材を接着させるか
【2】弾性
【3】耐久性や耐熱性
【4】衝撃への耐性
【5】作業のしやすさ
上記のポイントを押さえることで、あなたに合った商品を見つけることができます。ぜひ参考にしてみてください。
【1】金属とどんな素材を接着させるのか
金属とどの素材を接着させるかによっても、接着剤の種類が違ってきます。たとえば、金属同士の場合は金属用の接着剤、金属と紙やほかの素材を接着させる場合は多目的用の接着剤を購入しましょう。
使う用途によって選ぶことで、しっかりとした効果が得られます。一方、素材によっては、接着が難しい場合もあるので注意が必要です。
【2】異なる素材には弾性がある接着剤を使用する
異なる素材を接着させると、熱膨張係数の違いによって剥がれたり、ひび割れが起きる可能性があります。そのため、異なる素材同士の接着には、弾性接着剤を使用するのがよいでしょう。弾性接着剤は乾燥したあとにかたくならず、弾性をたもったままにしてくれます。
安定した追従性と接着性能を発揮してくれるので、ムーブメントを受けやすいコンクリートなど厳しい施工環境で使われていることが多いです。
【3】耐久性や耐熱性はあるか
金属は力がかかったり、熱くなるなどの特徴があります。そのため、金属接着剤は耐久性や耐熱性の高さが重要で、少しでも熱くなると溶けてしまうような接着剤ではきちんと接着できません。
一般には70〜80℃に対応できる接着剤がよいとされており、高い耐熱性の商品では100℃まで対応できるものもあります。
【4】衝撃には強いのか
衝撃に強い接着剤は、かたい素材などもかんたんに接着できるので便利です。
衝撃に強いのは基本的に弾性の接着剤ですが、耐衝撃性が高い瞬間接着剤というのもあります。瞬間接着剤で衝撃に強いものを選びたい場合は、「耐衝撃」の記載がある商品を選ぶようにしましょう。
【5】作業のしやすさなら、ピストル型の接着剤
ピストル型の接着剤は、チューブ型やヘラで塗る接着剤と比べて、作業しやすいのが便利なポイント。引き金を引いて使用できる接着剤で、接着させたい箇所にピンポイントに付着できるので、仕上がりがきれいになります。
また、ピストル型の接着剤は手が汚れにくく、作業がしやすいのもメリットのひとつでしょう。
ユーザーが選んだイチオシ5選 口コミで人気の金属用接着剤はコレ!
ここからは、金属接着剤を使用しているユーザーがイチオシの商品を紹介。5点満点で「コスパ」「使いやすさ」「粘着力」を評価してもらいました。イチオシのポイント、おすすめする理由や口コミもぜひ参考にしてください!
その他にもおすすめしたい商品があるよという方は、ぜひ記事の下部にある投稿フォームからご紹介をお願いします。

愛用者
すぐに接着したいときの味方
5分ほどで効果がはじまり、仮押さえできるのでラクです。多少気候の変化で硬化時間が変わる気がするので手際よく接着できるように準備しておいたほうがよかったです。液を混ぜ合わられているかわかるように、青色からクリアに変わるので、塗りはじめるタイミングもわかりやすいでした。(M.S.さん/男性/53歳/会社員)
【デメリットや気になった点】
少し匂いがキツいので、密室では使えないです。(M.S.さん/男性/53歳/会社員)
※各社通販サイトの 2025年3月27日時点 での税込価格
| コスパ | ★★★★☆ |
|---|---|
| 使いやすさ | ★★★☆☆ |
| 粘着力 | ★★★★★ |
| 総合評価 | 4.0点 |
| コスパ | ★★★★☆ |
|---|---|
| 使いやすさ | ★★★☆☆ |
| 粘着力 | ★★★★★ |
| 総合評価 | 4.0点 |

愛用者
コスパがよく接着力もGOOD!
金属やプラスチックなどの素材に、問題なくしっかりと接着することができました。イヤなニオイがしないのも気に入っています。耐久性もあり、シリコンゴムのくっつきにくい素材にも対応しているのもうれしいポイントです。(S.O.さん/女性/34歳/主婦)
【デメリットや気になった点】
接着時間が短くなればうれしいです。(S.O.さん/女性/34歳/主婦)
※各社通販サイトの 2025年3月27日時点 での税込価格
| コスパ | ★★★★☆ |
|---|---|
| 使いやすさ | ★★★★☆ |
| 粘着力 | ★★★★★ |
| 総合評価 | 4.3点 |
| コスパ | ★★★★☆ |
|---|---|
| 使いやすさ | ★★★★☆ |
| 粘着力 | ★★★★★ |
| 総合評価 | 4.3点 |

愛用者
さまざまなシーンで使える家庭に1本ほしいアイテム
使いつづけていると徐々にふたがかたまって開かなくなるのは瞬間接着剤のあるあるだと思いますが、この商品は長期間使用しなくても、ふたがくっついていませんでした。大容量ですが、最後まできちんと使いきれました。高齢の初心者でも使いやすかったです。(T.M.さん/女性/78歳/主婦)
【デメリットや気になった点】
粘度があるので、流し込んで使いたいときに、少々不便に感じました。(T.M.さん/女性/78歳/主婦)
※各社通販サイトの 2025年3月27日時点 での税込価格
| コスパ | ★★★★☆ |
|---|---|
| 使いやすさ | ★★★★☆ |
| 粘着力 | ★★★★☆ |
| 総合評価 | 4.0点 |
| コスパ | ★★★★☆ |
|---|---|
| 使いやすさ | ★★★★☆ |
| 粘着力 | ★★★★☆ |
| 総合評価 | 4.0点 |

愛用者
コスパがよく耐熱性もある金属用接着剤
こちらは1,000円以下とコスパがよく、耐熱性があるところが気に入っています。また私が以前使用していた製品と比べると、比較的硬化するまでの時間が短いです。汎用性が高く、あらゆる金属に使えます。2液タイプなので、はじめは使い勝手に戸惑うかもしれませんが、慣れてくれば使いやすい接着剤です。(J.S.さん/男性/37歳/会社員)
【デメリットや気になった点】
2液タイプなので使用に手間がかかります。(J.S.さん/男性/37歳/会社員)
※各社通販サイトの 2025年3月27日時点 での税込価格
| コスパ | ★★★★★ |
|---|---|
| 使いやすさ | ★★★☆☆ |
| 粘着力 | ★★★★★ |
| 総合評価 | 4.3点 |
| コスパ | ★★★★★ |
|---|---|
| 使いやすさ | ★★★☆☆ |
| 粘着力 | ★★★★★ |
| 総合評価 | 4.3点 |

愛用者
衝撃に強いのは本当でした!
強力な接着剤を探していたところ、金属に対応し衝撃に強いとのことでこちらを購入してみました。普通のアロンアルファに比べると粘度が高い感じがします。折れた傘に使ってみましたが、しっかりとくっつき壊れていません。(M.S.さん/女性/36歳/会社員)
【デメリットや気になった点】
ものによってはくっつかない場合もあります。(M.S.さん/女性/36歳/会社員)
※各社通販サイトの 2025年3月27日時点 での税込価格
| コスパ | ★★★★★ |
|---|---|
| 使いやすさ | ★★★★☆ |
| 粘着力 | ★★★★☆ |
| 総合評価 | 4.3点 |
| コスパ | ★★★★★ |
|---|---|
| 使いやすさ | ★★★★☆ |
| 粘着力 | ★★★★☆ |
| 総合評価 | 4.3点 |
金属用接着剤おすすめ9選 速乾性が高い!衝撃や振動に強い!幅広い素材使える!
続いては、金属接着剤のおすすめ商品を紹介します。どれも使い勝手がよく、さまざまな場所で使用できるので便利です。これから購入を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
アロンアルファはとても種類が多いです。なかでもこの『アロンアルフア プロ用耐衝撃(#31701)』は金属のような衝撃が、直接伝わるような素材にも対応できるよう、耐衝撃性を高めた瞬間接着剤。
また、接着剤は中粘度でツルツルの金属のうえでも垂れにくいため、失敗しにくく使い勝手がいいです。

衝撃や振動に強くて耐震性が高い
衝撃や振動に強い、耐震性にすぐれた金属接着剤。衝撃を受けやすい部分に使用できるので、接着後もすぐれた耐久性を保持してくれます。
金属だけでなく、陶磁器・硬質プラスチック・合成ゴムの接着など、幅広い素材に使用可能。逆に、シリコン樹脂・フッ素系樹脂・発泡スチロールなどには使えないので、注意が必要です。
※各社通販サイトの 2025年3月27日時点 での税込価格
| 接着できない素材 | ポリエチレン系樹脂、ポリプロピレン系樹脂、シリコン樹脂、フッ素系樹脂、PET系樹脂、発砲スチロール |
|---|---|
| 耐熱温度 | - |
| タイプ | チューブ |
| 接着できない素材 | ポリエチレン系樹脂、ポリプロピレン系樹脂、シリコン樹脂、フッ素系樹脂、PET系樹脂、発砲スチロール |
|---|---|
| 耐熱温度 | - |
| タイプ | チューブ |
金属同士もしっかり接着できる
高強度で衝撃に非常に強く、硬度の高い素材に使用できる金属接着剤。チタン・ステンレス・鉄・銅・亜鉛メッキ銅などの金属や、炭素繊維にも使用できるので便利です。
幅広い金属素材に対応できるため、ふだん使っている金属アクセサリーや家庭内にある金属製品に活用できるのがポイント。
※各社通販サイトの 2025年3月27日時点 での税込価格
| 接着できない素材 | ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、塩化ビニル など |
|---|---|
| 耐熱温度 | - |
| タイプ | チューブ |
| 接着できない素材 | ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、塩化ビニル など |
|---|---|
| 耐熱温度 | - |
| タイプ | チューブ |
『オートウェルド(AW-20Z)』は主成分のほかに、こまかな鉄粉が含まれているのが特徴で、硬化後も削ったりねじ切りなどが可能というすぐれもの。
硬化後は、ガソリンなどの溶剤に対する耐性も高く、300℃の高温まで耐えられるため、車パーツの補修にも使用することができます。

幅広い素材に使用できる
鉄・アルミ・金属など、幅広い素材に使用できる接着剤。2液混合タイプで、主剤と硬化剤を混ぜて使用します。
かたいものが接着できることで、家庭内のものの修理が自分でできるようになるので、活用しやすいでしょう。硬化するまで6時間と時間は必要ですが、硬化したあとはしっかりと接着されているので安心できます。
※各社通販サイトの 2025年3月27日時点 での税込価格
| 接着できない素材 | - |
|---|---|
| 耐熱温度 | 300℃ |
| タイプ | チューブ |
| 接着できない素材 | - |
|---|---|
| 耐熱温度 | 300℃ |
| タイプ | チューブ |
さまざまな家庭用品に対応
金属・プラスチック・木材・石・レンガ・セラミックなど、幅広い素材に対応していて、家庭内での使用にも便利な接着剤。ふだん身につけるアクセサリーの修理や、DIYなどでも使用できるのでとても便利です。
コンパクトな形で、持ち運びや保管が便利な商品。耐熱性は低いですが、温度が関係ない場所では使用しやすいので、室内でも屋外でも使用できるでしょう。
※各社通販サイトの 2025年3月27日時点 での税込価格
| 接着できない素材 | ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、 シリコーンゴム(パッキン等) ほか など |
|---|---|
| 耐熱温度 | - |
| タイプ | チューブ |
| 接着できない素材 | ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、 シリコーンゴム(パッキン等) ほか など |
|---|---|
| 耐熱温度 | - |
| タイプ | チューブ |
ピストル型で使いやすい
人間工学にもとづいたピストル型で握りやすいグリップは、持ちやすさと手の疲れにくさを追求し設計されています。
接着剤が出てくる部分の上には硬化用UVのLEDライトがついており、こまかい作業もラクラクとおこなえるので便利です。
※各社通販サイトの 2025年3月27日時点 での税込価格
| 接着できない素材 | ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、 シリコーンゴム(パッキン等) ほか など |
|---|---|
| 耐熱温度 | - |
| タイプ | ピストル型 |
| 接着できない素材 | ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、 シリコーンゴム(パッキン等) ほか など |
|---|---|
| 耐熱温度 | - |
| タイプ | ピストル型 |
ハイスピードで乾く瞬間接着剤
速乾性にすぐれている接着剤で、一度接着するとずれることがなく、ハイスピードで接着することが可能。衝撃に非常に強く、接着した部分がしっかりと硬化します。
内容量は20gと多めに入っており、硬質プラスチック・合成ゴム・金属などの接着が行えます。幅広い素材に使用できるので、家庭内でも活用しやすいでしょう。
※各社通販サイトの 2025年3月27日時点 での税込価格
| 接着できない素材 | おもちゃ、プラモデル、金属模型、アクセサリーや小物、陶磁器の置物、電気製品の樹脂/金属、PE、PP、シリコーン樹脂 ほか など |
|---|---|
| 耐熱温度 | - |
| タイプ | チューブ |
| 接着できない素材 | おもちゃ、プラモデル、金属模型、アクセサリーや小物、陶磁器の置物、電気製品の樹脂/金属、PE、PP、シリコーン樹脂 ほか など |
|---|---|
| 耐熱温度 | - |
| タイプ | チューブ |
クリア素材でさまざまな用途に使用できる
クリア素材で、接着部分が目立たずに使用できる接着剤。色のあるものや透明なものまで幅広く使えるので、これひとつあればどんなものにも使用できます。
耐水性があり、水がかかりやすい場所でも問題なく使える商品です。水の使用が欠かせない観葉植物や、屋外のガーデニングアイテムの補修にも適しています。
※各社通販サイトの 2025年3月27日時点 での税込価格
| 接着できない素材 | ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、フッ素樹脂、貴金属、高価格品 など |
|---|---|
| 耐熱温度 | -30~80℃ |
| タイプ | チューブ |
| 接着できない素材 | ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、フッ素樹脂、貴金属、高価格品 など |
|---|---|
| 耐熱温度 | -30~80℃ |
| タイプ | チューブ |
耐水性・耐熱性にすぐれたアイテム
硬質プラスチック、合成ゴム、金属、陶磁器に加え、木材、厚紙などの浸透性の素材にも適しています。また、垂直面でもたれずに使用できるため、DIYプロジェクトや木製家具の緊急補修、リメイク作業にピッタリ。サイドボタンと極細ノズルを備えており、液量もコントロールできます。
多くの材料に対応する万能タイプで、おもちゃの修理やデコレーションなど精密な作業に適しています。
※各社通販サイトの 2025年3月27日時点 での税込価格
| 接着できない素材 | ガラス、PP、ナイロン、シリコンなど |
|---|---|
| 耐熱温度 | 120℃ |
| タイプ | チューブ |
| 接着できない素材 | ガラス、PP、ナイロン、シリコンなど |
|---|---|
| 耐熱温度 | 120℃ |
| タイプ | チューブ |
凸凹部分もなんのその
凹凸面や平滑面、広い面、狭い面など、あらゆる箇所での接着や補修に最適な接着剤です。この接着剤は耐寒・耐熱性があり、温度範囲(-29〜82℃)で使用でき、肉やせが発生せず、凹凸面でもしっかりと接着します。
湿気と反応して強力に接着しますが、塗布後は5分間調整が可能です。耐水性にも優れており、屋内と屋外の両方で使用できます。
※各社通販サイトの 2025年3月27日時点 での税込価格
| 接着できない素材 | PP、樹脂、貴金属など |
|---|---|
| 耐熱温度 | 82℃ |
| タイプ | チューブタイプ |
| 接着できない素材 | PP、樹脂、貴金属など |
|---|---|
| 耐熱温度 | 82℃ |
| タイプ | チューブタイプ |
「金属用接着剤」のおすすめ商品の比較一覧表
| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 接着できない素材 | 耐熱温度 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コニシ『ボンド アロンアルフア プロ用耐衝撃(#31701)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月27日時点 での税込価格 |
衝撃や振動に強くて耐震性が高い | ポリエチレン系樹脂、ポリプロピレン系樹脂、シリコン樹脂、フッ素系樹脂、PET系樹脂、発砲スチロール | - | チューブ |
| セメダイン『メタルロック(AY-123)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月27日時点 での税込価格 |
金属同士もしっかり接着できる | ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、塩化ビニル など | - | チューブ |
| 隆成コミュニティ『J-B オートウエルド(AW-20Z)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月27日時点 での税込価格 |
幅広い素材に使用できる | - | 300℃ | チューブ |
| スピリットオブワンダー『BONDIC スターターキット コンプリート(BD-SKCJ)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月27日時点 での税込価格 |
さまざまな家庭用品に対応 | ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、 シリコーンゴム(パッキン等) ほか など | - | チューブ |
| スピリットオブワンダー『BONDIC EVO スターターキット コンプリート(BD-SKEJ)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月27日時点 での税込価格 |
ピストル型で使いやすい | ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、 シリコーンゴム(パッキン等) ほか など | - | ピストル型 |
| ヘンケル『LOCTITE 強力瞬間接着剤 高強度金属用(LKK-020)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月27日時点 での税込価格 |
ハイスピードで乾く瞬間接着剤 | おもちゃ、プラモデル、金属模型、アクセサリーや小物、陶磁器の置物、電気製品の樹脂/金属、PE、PP、シリコーン樹脂 ほか など | - | チューブ |
| コニシ『ボンド ウルトラ多用途SU(#04593)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月27日時点 での税込価格 |
クリア素材でさまざまな用途に使用できる | ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、フッ素樹脂、貴金属、高価格品 など | -30~80℃ | チューブ |
| ロックタイト『強力瞬間接着剤 ピンポインターゼリー状(LPJ-005)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月27日時点 での税込価格 |
耐水性・耐熱性にすぐれたアイテム | ガラス、PP、ナイロン、シリコンなど | 120℃ | チューブ |
| 呉工業『KURE ゴリラグルー クリア(1770)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月27日時点 での税込価格 |
凸凹部分もなんのその | PP、樹脂、貴金属など | 82℃ | チューブタイプ |
通販サイトの最新人気ランキングを参考にする 接着剤の売れ筋をチェック
Amazon、楽天市場での接着剤の売れ筋ランキングも参考にしてみてください。
※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。
金属用接着剤を使う時には表面の処理もお忘れなく! 使う前のひと手間!
金属接着剤を使う時には、くっつける金属に適した接着剤を選ぶことも必要ですが、それと同じほど、使用する金属の表面を金属ごとに適した処理をすることも重要です。ここではその方法をご紹介します。
表面処理のポイント
金属接着剤の性能を十分に発揮するためには、表面の「不要なもの」を取り除く必要があります。不要なものは例えば「ゴミ」や「ホコリ」、「水分」、そして「サビ」など目に見えるものから、表面に塗布されている「酸化被膜」や「油」があります。
ゴミやホコリ、水分などは拭き取ればOKですし、サビであればヤスリ(200〜80番台)で削り落としましょう。塗装が表面全体に施してある場合は、ヤスリでは大変なので、サンドブラストなどで剥がしておきましょう。
一方、目には見えないような酸化皮膜や油分はシンナーやアルカリ性の洗浄剤を使うと落とすことができます。
金属ごとの注意点
上記の表面処理方法を代表的な金属ごとに当てはめてみると、汚れ落としはどの金属でも共通で行いますが、「鉄」や「アルミニウム」、「銅」などの場合はサビを落として、表面の酸化皮膜や油分を落とすだけで大丈夫です。
ただし、錫や亜鉛、ブリキなど表面がメッキ加工されているものはサンドブラストやヤスリで表面の塗装や被膜を剥いでおきましょう。
接着後の環境も考慮して選ぶのがポイント DIYアドバイザーがアドバイス
金属同士の接着をする際は、硬化後に硬くなる接着剤、金属と別の素材を接着する際は、硬化後に弾性が残る接着剤を選びましょう。
また、接着後にどのような環境で使われるかもしっかりと確認し、商品の「耐性」を環境に合わせることで、接着後も長く安全に使うことができます。一概に金属がつくという点だけではなく、接着後の環境も視野に入れることが、金属用接着剤を選ぶうえで大切なポイントです。
金属用接着剤でDIYを楽に
金属接着剤の選び方やおすすめ商品を紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?
自分が何をDIYしたいかに合わせて選ぶと、作業がぐっと楽になります。この記事で紹介したポイントを参考に、自分に合ったものを選ぶようにしてくださいね。
おすすめ商品・口コミの投稿はこちら
※メーカーや販売店の方は、ページ下部の「お問い合わせはこちら」から商品情報をお送りください。
ユーザーのおすすめ商品や口コミ情報は、マイナビおすすめナビを閲覧したユーザー、マイナビニュース会員、外部パートナー企業と契約する一般ユーザーからの投稿をもとにしています。
◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。