| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 内容量 | ブドウ品種 | 種別 | 生産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドメーヌ・グロ・フレール・エ・スール『ヴォーヌ・ロマネ』 |
|
※各社通販サイトの 2024年12月4日時点 での税込価格 |
グラン・クリュの片鱗が味わえるヴォーヌ・ロマネ | 750ml | ピノ・ノワール | フルボディ | コート・ド・ニュイ |
| ポール・ボーデ『サン・タムール』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月27日時点 での税込価格 |
「聖なる愛」の名をもつクリュ・ボージョレの1本 | 750ml | ガメイ | ミディアムボディ | ボジョレー・サン タムール |
| ルイ・ジャド『ボージョレ・ヴィラージュ コンボー・ジャック 2017』 |
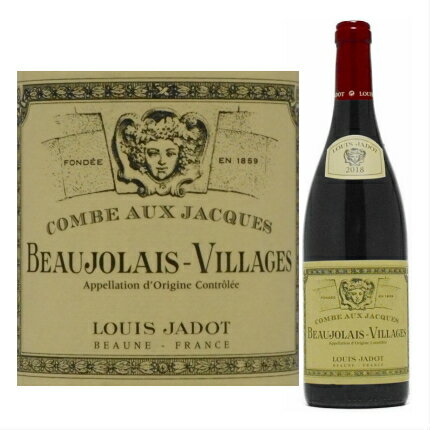
|
※各社通販サイトの 2024年11月26日時点 での税込価格 |
ブルゴーニュ最大級の生産者のボージョレワイン | 375ml/750ml | ガメイ | ミディアムボディ | ボージョレ |
| エルヴェ・ケルラン『ブルゴーニュ ピノ・ノワール』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月27日時点 での税込価格 |
手ごろな価格で本格的な味わいが楽しめる1本 | 750ml | ピノ・ノワール | ミディアムボディ | I.G.P.サント・マリー・ラ・ブランシュ |
| ルイ・ラトゥール『キュヴェ・ラトゥール・ルージュ 2017』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月27日時点 での税込価格 |
200年以上の伝統を持つワイナリーが品種を厳選 | 375ml、750ml | ピノ・ノワール | ミディアムボディ | コート・ド・ボーヌ |
| メゾン・ジョゼフ・ドルーアン『ボジョレ・ヴィラージュ 2016』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月27日時点 での税込価格 |
産地の土壌を活かした花のようなワイン | 750ml | ガメイ | ライトボディ | ボージョレ |
| ラブレ・ロワ『ムーラン・ア・ヴァン』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月27日時点 での税込価格 |
多くの航空会社に採用されたワイナリーの一本 | 750ml | ガメイ | ライトボディ | ムーラン・ア・ヴァン |
| クロ・ド・タール『クロ・ド・タール グラン・クリュ』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月27日時点 での税込価格 |
所有者交代で新スタートを切った伝統ワイン | 750ml | ピノ・ノワール | フルボディ | コート・ド・ニュイ |
ブルゴーニュ赤ワインの特徴
ブルゴーニュワインは、フランス東部のブルゴーニュ地方で造られるワインです。ブルゴーニュ地方は、ボルドーワインで有名なボルドー地方と並ぶ世界的な銘醸地で、赤ワインでは高級ワインとして有名な『ロマネ・コンティ』や秋の風物詩としてもおなじみの『ボージョレ・ヌーヴォー』など、すぐれたワインを多く生産しています。
赤ワインも白ワインも傑作揃いで「ワインの王」とも呼ばれるブルゴーニュワインの特徴は、単一品種でつくられていること。赤ワインはおもに「ピノ・ノワール」か「ガメイ」が使われます。
地区によって特徴が異なり、それぞれの土地で個性の異なる味わいのワインが生まれます。そのため、畑ことに格付けされているのもブルゴーニュワインの特徴です。
ブルゴーニュ赤ワインの選び方 品種や生産地区など
日本ソムリエ協会認定ワインエキスパートの石関華子さんに、ブルゴーニュ赤ワインを選ぶときのポイントを教えてもらいました。
ワインの個性を育む生産地区で選ぶ
ブルゴーニュ地方の赤ワインが生産されている地区ごとにワインの個性も異なるので、好みや気分に合わせて生産地区から選ぶのがおすすめです。
「コート・ド・ニュイ地区」は『ロマネ・コンティ』をはじめとした豊かな芳香をもつ長期熟成向きのワイン、「コート・ド・ボーヌ地区」はしなやかで軽めな良質なワインを多く生産しています。「コート・シャロネーズ地区」は口当たりのよいカジュアルなワイン、「ボージョレ地区」はボージョレ・ヌーヴォーでおなじみのガメイという品種からフルーティーなワインを生み出している地域です。
※ブルゴーニュ地方の赤ワインが生産されている地区には、「コート・ド・ニュイ地区」「コート・ド・ボーヌ地区」「コート・ド・ボーヌ地区」「コート・シャロネーズ地区」「ボージョレ地区」があります。
ワインの味わいに影響するブドウ品種で選ぶ
ブドウ品種はワインの味に大きく影響するので、好みに合わせてブドウ品種から選ぶというのもおすすめ。ブルゴーニュ地方の赤ワインは、「ピノ・ノワール」もしくは「ガメイ」というブドウ品種からつくられます。
ピノ・ノワールは高級赤ワインの原料ともなる品種で、熟したベリー系の果実の香りやスミレ、バラのような魅惑的な香り、熟成が進むと紅茶やトリュフのような香りがあらわれます。渋みは控えめでエレガントなワインになるのも特徴です。
ガメイはボージョレ地区のワインに用いられる品種で、チェリーやラズベリーのような香りと、軽さとさわやかさをもちあわせるチャーミングなワインを生み出します。
「ドメーヌ」か「ネゴシアン」か、生産者から選ぶ
ブルゴーニュ地方のワインの生産者は、ブドウ栽培からワインづくりを一貫して行う「ドメーヌ」と、農家から買い取ったブドウでワインづくりを行う「ネゴシアン」の2つに大きく分けられます。
一般的にドメーヌのワインは個性的で希少性が高く、ネゴシアンのワインは安定的でより万人受けのする味わいです。ブルゴーニュワイン初心者の方は、まずはネゴシアンのワインから試すのがおすすめ。
また、ブルゴーニュではひとつの畑を複数の生産者が所有しているケースが多く、たとえ同じ畑のワインでも、生産者が違えばワインの味わいはまったく別のものになります。そのため、ワインの生産者にも目を向けながら選ぶのが重要です。
ブドウ畑の格づけから選ぶ
ブルゴーニュ地方のワインの特徴のひとつに、ブドウ畑の区画ごとに格づけがされているということが挙げられます。格づけも、ワイン選びのひとつの目安にすることができるでしょう。
格づけは上から順に、特級と規定された畑のブドウでつくられる「特級畑名ワイン(グラン・クリュ)」、1級と規定された畑の「1級畑名ワイン(プルミエ・クリュ)」、ある村の畑のブドウでつくられる「村名ワイン」、ある地区の畑のブドウからつくられる「地区名ワイン」、ブルゴーニュ地方全域のブドウからつくられる「一般広域名ワイン」です。
ブドウの生産区画がより限定的になるほど、格づけは上位になります。
ワイン専門家からのアドバイス
ブルゴーニュ地方の赤ワインには、『ロマネ・コンティ』などのような何十万円もするような高級ワインから1,000円程度で買えるものまで、幅広い価格帯のものが存在します。
デイリーワインとして自宅で楽しむのであれば、2,000円以内の「一般広域名ワイン」でもじゅうぶん楽しめますが、もし贈答品にするのなら3,000円以上の「村名ワイン」以上の格づけのものがおすすめです。
ただし、価格とおいしさは必ずしも比例するわけではありませんので、価格はあくまでひとつの目安と考えるようにしましょう。
ブルゴーニュ赤ワインおすすめ|プロ厳選
ここからはブルゴーニュ赤ワインのおすすめ商品をご紹介します。日本ソムリエ協会認定ワインエキスパートの石関 華子がおすすめする商品も掲載しているのでぜひチェックしてみてください。

グラン・クリュの片鱗が味わえるヴォーヌ・ロマネ
贈りものにもおすすめな、特級畑(グラン・クリュ)の片鱗(へんりん)が味わえるワインがこちら。産地はコート・ド・ニュイ地区のなかでも『ロマネ・コンティ』の畑をはじめ、秀逸な特級畑をいくつも有するヴォーヌ・ロマネ村。「村名ワイン」に格づけされますが、原料の一部には特級畑のひとつであるエシェゾーで収穫されたブドウが含まれています。
生産者は、ブドウ栽培からワインづくりまで一貫して行うドメーヌのなかでも、最新の醸造技術の導入に積極的なドメーヌ・グロ・フレール・エ・スール。
ブドウ品種はピノ・ノワールで、プラムやヴァニラのような甘い香りに、ふくよかな果実味とほどよい酸が見事に調和した1本です。
※各社通販サイトの 2024年12月4日時点 での税込価格
| 内容量 | 750ml |
|---|---|
| ブドウ品種 | ピノ・ノワール |
| 種別 | フルボディ |
| 生産地 | コート・ド・ニュイ |
| 内容量 | 750ml |
|---|---|
| ブドウ品種 | ピノ・ノワール |
| 種別 | フルボディ |
| 生産地 | コート・ド・ニュイ |

「聖なる愛」の名をもつクリュ・ボージョレの1本
ロマンチックに恋人同士やご夫婦で飲むのにおすすめの1本がこちら。ボージョレ地区のなかでも、すぐれたワインを生産している10の地区「クリュ・ボージョレ」のひとつで、フランス語で「聖なる愛」という意味をもつ「サン・タムール」という地区のワインです。
生産者は1869年創業以来、並々ならぬ情熱をもってワインづくりに取り組み、地道な努力を重ねてきたポール・ボーデ。
ブドウ品種はガメイで、チェリーやラズベリーを思わせる香りに、果実味に富んだ、やさしく繊細な味わいが特徴のワインです。
※各社通販サイトの 2024年11月27日時点 での税込価格
| 内容量 | 750ml |
|---|---|
| ブドウ品種 | ガメイ |
| 種別 | ミディアムボディ |
| 生産地 | ボジョレー・サン タムール |
| 内容量 | 750ml |
|---|---|
| ブドウ品種 | ガメイ |
| 種別 | ミディアムボディ |
| 生産地 | ボジョレー・サン タムール |

ブルゴーニュ最大級の生産者のボージョレワイン
比較的飲みやすい味わいで、赤ワイン初心者の方におすすめワインがこちら。ボージョレ地区のなかでも、良質なワインを生み出すとして「ボージョレ・ヴィラージュ」に格づけされている地区のワインです。
生産者は、ブルゴーニュ最大級のネゴシアンのひとつであるルイ・ジャドで、ブドウ品種はガメイ。新鮮な果実や花の香りと、フルーティーでやわらかみのある味わいが特徴です。その飲み口のよさから、夏の暑い時期に飲む赤ワインとしてもおすすめです。
※各社通販サイトの 2024年11月26日時点 での税込価格
| 内容量 | 375ml/750ml |
|---|---|
| ブドウ品種 | ガメイ |
| 種別 | ミディアムボディ |
| 生産地 | ボージョレ |
| 内容量 | 375ml/750ml |
|---|---|
| ブドウ品種 | ガメイ |
| 種別 | ミディアムボディ |
| 生産地 | ボージョレ |

手ごろな価格で本格的な味わいが楽しめる1本
気軽に楽しめるブルゴーニュの赤ワインをお探しの方におすすめのワインがこちら。「手頃な高級品」をつくることをコンセプトにしているエルヴェ・ケルランが手掛ける『ブルゴーニュ ピノ・ノワール』です。
ブドウはブルゴーニュ地方全域で栽培されたピノ・ノワールが使用されており、格づけは「一般広域名ワイン」にあたります。色調は鮮やかなルビーレッド。
チェリーやイチゴジャム、バラなどの香りなかに、ほのかに野性的な香りも加わり、複雑な香りを醸し出しています。フレッシュでみずみずしい果実味のなかにも、ほどよく酸とタンニン(渋み)が感じられ、手ごろな価格ながら本格的な味わいが楽しめる1本です。
※各社通販サイトの 2024年11月27日時点 での税込価格
| 内容量 | 750ml |
|---|---|
| ブドウ品種 | ピノ・ノワール |
| 種別 | ミディアムボディ |
| 生産地 | I.G.P.サント・マリー・ラ・ブランシュ |
| 内容量 | 750ml |
|---|---|
| ブドウ品種 | ピノ・ノワール |
| 種別 | ミディアムボディ |
| 生産地 | I.G.P.サント・マリー・ラ・ブランシュ |
ブルゴーニュ赤ワインおすすめ|5000円以下
普段の食卓で気軽にブルゴーニュ赤ワインを楽しみたいときや、初めてブルゴーニュ赤ワインを試したいときにもぴったりの、5,000円以下で購入できるブルゴーニュ赤ワインを紹介します。
200年以上の伝統を持つワイナリーが品種を厳選
200年以上も続く家族経営の、ブルゴーニュを代表するワイナリー「ルイ・ラトゥール」のブルゴーニュ赤ワインのひとつ。使用するぶどうの品種はサントネやオークセイ・デュレスなどのコート・ドール南部産のピノ・ノワール種を厳選しています。
伝統の製法と革新を繰り返しながら、コート・ド・ボーヌのファインワインの特徴を見事に表した商品です。
※各社通販サイトの 2024年11月27日時点 での税込価格
| 内容量 | 375ml、750ml |
|---|---|
| ブドウ品種 | ピノ・ノワール |
| 種別 | ミディアムボディ |
| 生産地 | コート・ド・ボーヌ |
| 内容量 | 375ml、750ml |
|---|---|
| ブドウ品種 | ピノ・ノワール |
| 種別 | ミディアムボディ |
| 生産地 | コート・ド・ボーヌ |
産地の土壌を活かした花のようなワイン
ボージョレ地区でワイン産業に古くから関わる、ボジョレワインのパイオニア的存在「メゾン・ジョゼフ・ドルーアン」によるライトボディの赤ワインです。
ピンク色の花崗岩で育ったテロワールやミクロクリマの魅力をうまく引きだしたワインで、滑らかな舌触り、スミレやラズベリーのような香りと明るい紫色が特徴的なワインです。
※各社通販サイトの 2024年11月27日時点 での税込価格
| 内容量 | 750ml |
|---|---|
| ブドウ品種 | ガメイ |
| 種別 | ライトボディ |
| 生産地 | ボージョレ |
| 内容量 | 750ml |
|---|---|
| ブドウ品種 | ガメイ |
| 種別 | ライトボディ |
| 生産地 | ボージョレ |
多くの航空会社に採用されたワイナリーの一本
1832年に創立され、ブルゴーニュでもその規模の大きさ、品質の高さで注目されているワイナリー「ラブレ・ロワ」の手がけた赤ワインです。高品質なワインを安定的に供給できる独自の体制を整えることで、世界30社以上の航空会社の機内ワインとして採用された実績を持ちます。
深みのある味わいと、ベリー系の香り、美しいルビー色が楽しめる1本です。
※各社通販サイトの 2024年11月27日時点 での税込価格
| 内容量 | 750ml |
|---|---|
| ブドウ品種 | ガメイ |
| 種別 | ライトボディ |
| 生産地 | ムーラン・ア・ヴァン |
| 内容量 | 750ml |
|---|---|
| ブドウ品種 | ガメイ |
| 種別 | ライトボディ |
| 生産地 | ムーラン・ア・ヴァン |
ブルゴーニュ赤ワインおすすめ|1万円以上
記念日やお祝いなどの特別なシーンでは高級なワインを楽しみたい方も多いですよね。思い出に残るすてきな時間に華を添える、1万円以上のブルゴーニュ赤ワインを紹介します。
所有者交代で新スタートを切った伝統ワイン
ブルゴーニュ地方モレ・サン・ドニの著名なワイナリー「クロ・ド・タール」の赤ワインです。900年近く一切の分割や譲渡を行わず、所有者となったのはたった3人。ボジョレーのトップ生産者であるモメサン家が85年近く単独所有していましたが、2017年よりシャトー・ラトゥールのオーナー、フランソワ・ピノー氏一族が所有者となりました。
絶好の立地条件と優れた土壌が育んだワインで、濃厚な果実味、繊細なタンニンが特徴。伝統と新しい試みが融合されたワインです。
※各社通販サイトの 2024年11月27日時点 での税込価格
| 内容量 | 750ml |
|---|---|
| ブドウ品種 | ピノ・ノワール |
| 種別 | フルボディ |
| 生産地 | コート・ド・ニュイ |
| 内容量 | 750ml |
|---|---|
| ブドウ品種 | ピノ・ノワール |
| 種別 | フルボディ |
| 生産地 | コート・ド・ニュイ |
「ブルゴーニュ赤ワイン」のおすすめ商品の比較一覧表
| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 内容量 | ブドウ品種 | 種別 | 生産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドメーヌ・グロ・フレール・エ・スール『ヴォーヌ・ロマネ』 |
|
※各社通販サイトの 2024年12月4日時点 での税込価格 |
グラン・クリュの片鱗が味わえるヴォーヌ・ロマネ | 750ml | ピノ・ノワール | フルボディ | コート・ド・ニュイ |
| ポール・ボーデ『サン・タムール』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月27日時点 での税込価格 |
「聖なる愛」の名をもつクリュ・ボージョレの1本 | 750ml | ガメイ | ミディアムボディ | ボジョレー・サン タムール |
| ルイ・ジャド『ボージョレ・ヴィラージュ コンボー・ジャック 2017』 |
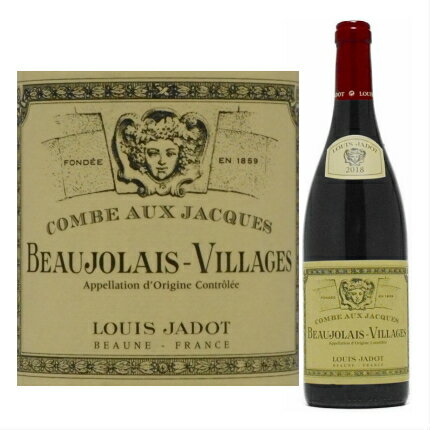
|
※各社通販サイトの 2024年11月26日時点 での税込価格 |
ブルゴーニュ最大級の生産者のボージョレワイン | 375ml/750ml | ガメイ | ミディアムボディ | ボージョレ |
| エルヴェ・ケルラン『ブルゴーニュ ピノ・ノワール』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月27日時点 での税込価格 |
手ごろな価格で本格的な味わいが楽しめる1本 | 750ml | ピノ・ノワール | ミディアムボディ | I.G.P.サント・マリー・ラ・ブランシュ |
| ルイ・ラトゥール『キュヴェ・ラトゥール・ルージュ 2017』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月27日時点 での税込価格 |
200年以上の伝統を持つワイナリーが品種を厳選 | 375ml、750ml | ピノ・ノワール | ミディアムボディ | コート・ド・ボーヌ |
| メゾン・ジョゼフ・ドルーアン『ボジョレ・ヴィラージュ 2016』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月27日時点 での税込価格 |
産地の土壌を活かした花のようなワイン | 750ml | ガメイ | ライトボディ | ボージョレ |
| ラブレ・ロワ『ムーラン・ア・ヴァン』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月27日時点 での税込価格 |
多くの航空会社に採用されたワイナリーの一本 | 750ml | ガメイ | ライトボディ | ムーラン・ア・ヴァン |
| クロ・ド・タール『クロ・ド・タール グラン・クリュ』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月27日時点 での税込価格 |
所有者交代で新スタートを切った伝統ワイン | 750ml | ピノ・ノワール | フルボディ | コート・ド・ニュイ |
通販サイトの最新人気ランキングを参考にする ブルゴーニュ赤ワインの売れ筋をチェック
楽天市場でのブルゴーニュ赤ワインの売れ筋ランキングも参考にしてみてください。
※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。
ワインの「保管場所」「温度」もチェック! ワインをおいしく飲むために
ワインの種類によって飲むのに適した時期や保管方法もさまざま。できるだけおいしくいただけるよう、飲みごろや温度はチェックしておきたいポイントです。また購入後すぐに飲まないという場合は保管場所にも気を配りましょう。
飲みごろや保管場所にも気をつけよう
ブルゴーニュの赤ワインには、コート・ド・ニュイ地区のもののように長期熟成しておいしく飲めるタイプのものと、ボージョレ地区のもののように早めに飲んでしまったほうがいいものがあります。
いずれにしても、1万円以下のブルゴーニュの赤ワインで市場に出回っているものの多くは、すでに飲みごろを迎えていると考えられるため、購入後はなるべく早めに召し上がったほうがいいでしょう。
また、保管するのであればセラーが最適ですが、自宅にセラーがない場合は床下や納戸(なんど)など、温度変化が少なく涼しい場所で保管するのがおすすめです。
赤ワインの飲みごろの温度は?
赤ワインにはライトボディ、ミディアムボディ、フルボディがあり、それぞれ最もおいしく飲める温度が異なります。用意したワインをおいしく飲めるために、ワインの種類別に飲みごろの温度を紹介します。
フルボディの場合|16~20度と少し温かめ
ワイン本来の味や香り、色、さらに渋みも濃厚なフルボディの赤ワインは、高めの温度で飲むのに適しています。ワインの温度を上げることで酸味が緩和され、全体的にふくよかな味わいになります。
フルボディの温度を上げることで酸味が和らぐ代わりに、甘みを感じやすくなります。そのため、フルボディの渋みを感じにくく、本来の複雑な味や香りを存分に堪能できる16~20度がおいしい飲みごろとなります。
ミディアムボディの場合|13~16度が目安
フルボディとライトボディの中間にあたる、渋み、味の濃厚さ、香りのバランスが取れている種別がミディアムボディです。
ミディアムボディがおいしく飲める温度は、13~16度とされています。中間層にあたるミディアムボディは、冷やしすぎると渋みが強くなり、温めすぎるとキレがなくなってしまいます。フルボディよりも少し冷やすことで、バランスのよい渋みと果実感を味わえます。
ライトボディの場合|10~12度に軽く冷やして
軽くさらっとしたワインであるライトボディは、軽く冷やすとキレのある、引き締まった飲み口が楽しめます。
ワインを冷やす際には、氷水を入れたワインクーラーや冷蔵庫を使用します。ワインクーラーで冷やす場合は5分、家庭用冷蔵庫なら30分~1時間が適切です。冷やしすぎてしまうと、常温から適切な温度に上げるのに時間がかかってしまうので、気をつけましょう。
ブルゴーニュ赤ワインに合う料理は?
お酒と相性のよい料理の組み合わせを、結婚にちなみ「マリアージュ」と呼びます。ブルゴーニュ赤ワインとのマリアージュが楽しめる食材や料理を知っておくと、もっとワインのシーンを楽しめるようになるでしょう。参考までに、ここではいくつかの食材、料理を紹介します。
ブルゴーニュの食事と合わせる
ワインは、産地の風土に適したものがつくられています。そのため、産地の食材や料理と相性がよいので、ブルゴーニュ地方の食材や料理と合わせるのもよいでしょう。
代表的なのが、ブルゴーニュのエポワス村で生まれたウォッシュチーズ「エポワス」とのマリアージュです。チーズの王様とも呼ばれるエポワスは濃厚な味わいが特徴。ワインのなかでもブルゴーニュ産赤ワインとぜひ合わせてみてください。
ピノ・ノワールには甘酸っぱいものや軽めのものを
ブルゴーニュ地方の代表的なブドウの品種「ピノ・ノワール」でつくられた赤ワインは、渋みが弱くほどよい酸味が楽しめるのが特徴。ラズベリーなどの赤い果実系の香りも楽しめます。
ピノ・ノワールと同じ酸味のある料理や、軽めの料理との相性が抜群。ベリー系ソースでつくった料理や、スイーツ系など軽めの食事やおつまみとよく合います。
ワインの色と重さと料理を合わせる
ワインの軽さ・重さや色を、食材や料理と合わせることも、相性のよい組み合わせのひとつ。たとえば、フルボディの赤ワインなら渋みが強く濃厚で重い味と色が特徴のため、牛の赤身肉やビーフシチューなど、こってりとした重めの料理がよく合います。
一方、キリっとした酸味と軽めの口当たりのライトボディなら、生ハムなど軽めの肉料理、中トロなど脂身の強い魚料理などが合います。
ブルゴーニュワイン白ワインのおすすめを紹介 【関連記事】
好みやシーンに合わせてブルゴーニュ赤ワインを楽しんで
日本ソムリエ協会認定ワインエキスパートの石関華子さんにおうかがいしたブルゴーニュ赤ワインの選び方やおすすめの商品に加えて、価格別で購入できるブルゴーニュ赤ワインを紹介しました。
ブドウの品種や生産地区、生産者がそれぞれで異なるブルゴーニュ赤ワインは、個性的なものも豊富にあります。食事やシーンにぴったりのものを選んで、もっとブルゴーニュ赤ワインを楽しんでくださいね。
◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。

















