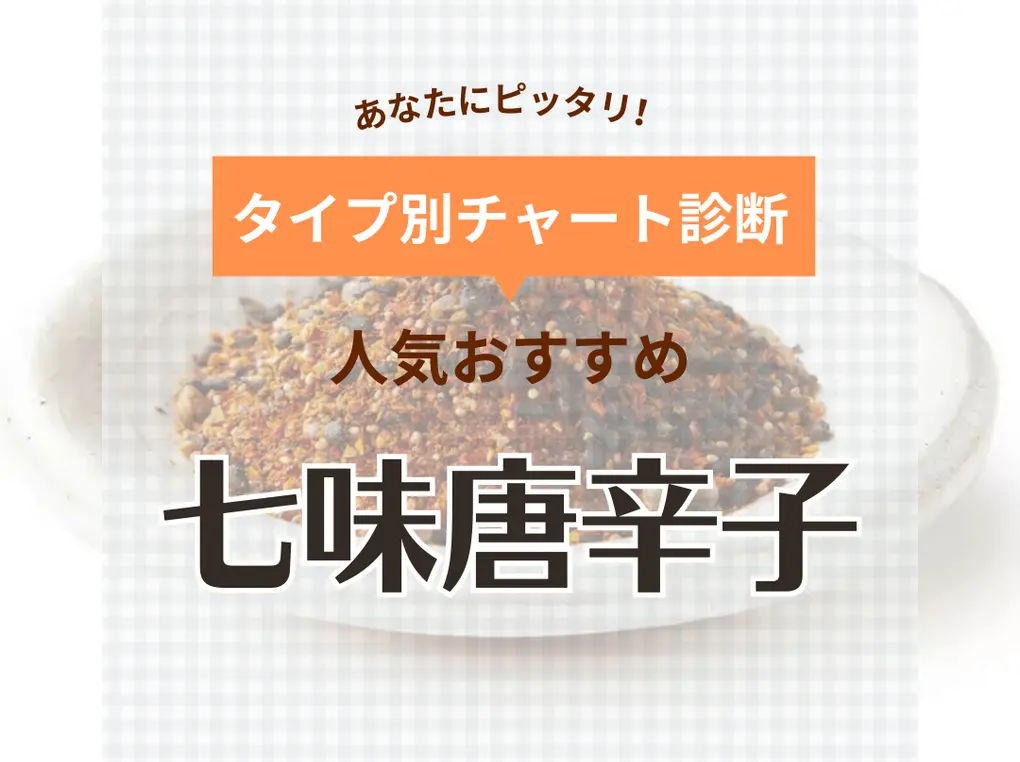| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 内容量 | 原材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 原了郭『黒七味 袋(大)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月3日時点 での税込価格 |
風味豊かな黒七味の袋詰めタイプ | 8g | ‐ |
| 一休堂『京七味』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月3日時点 での税込価格 |
原材料、製法にもこだわった逸品 | 20g | ‐ |
| 根元 八幡屋礒五郎『七味◎缶』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月3日時点 での税込価格 |
秘伝の調合で辛さが際立つ七味唐辛子 | 14g | 唐辛子、陳皮、胡麻、麻種、紫蘇、山椒、生姜(一部にごまを含む) |
| 原了郭『黒七味 四角』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月3日時点 での税込価格 |
木筒がポイント! 山椒の刺激を感じられる七味 | 6g | 白ごま、唐辛子、山椒、青のり、けしの実、黒ごま、おの実 |
| 根元 八幡屋礒五郎『ゆず七味 缶』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月3日時点 での税込価格 |
秘伝の調合と柚子の風味のコラボレーション | 12g | 唐辛子、柚子、陳皮、胡麻、麻種、紫蘇、山椒、生姜 |
| オーガニックファームHARA『キャロライナリーパー超激辛七味唐辛子』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月3日時点 での税込価格 |
激辛好きの方におすすめ! | 12g | 唐辛子、赤山椒、黒胡麻、青のり、陳皮、紫蘇、生姜 |
| おちゃのこさいさい『京の柚子七味 缶』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月3日時点 での税込価格 |
あっさりとした和食にマッチ | 10g | 柚子、本鷹唐辛子、胡麻、青のり、山椒、芥子の実、紫蘇、麻の実 |
| エヴァウェイ『和の七彩』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月3日時点 での税込価格 |
国産原料にこだわった香り豊かな逸品 | 12g | 青唐辛子(九州産)、赤唐辛子(九州産)、ごま(金・黒)、あおさ、きくらげ粉末、柚子、山椒 |
| ユウキ『MC 京風七味』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月3日時点 での税込価格 |
山椒の効いた京風七味 | 250g | ちんぴ、唐辛子、山椒、ごま、けしの実、麻の実、あおさ |
| うれし野ラボ『新感覚調味料 とける唐辛子』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月3日時点 での税込価格 |
パウダータイプの七味。持ち運びにも便利! | 8g | 粉飴(国内製造)、麦芽糖、唐辛子エキス/レシチン(大豆由来)、パプリカ色素、酸化防止剤 |
| やげん堀『七味唐辛子 中辛』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月3日時点 での税込価格 |
まろやかな辛みと香ばしい香りが特長 | 24g | 唐辛子(中国、日本)(焼粉・赤粉)、黒ごま、陳皮(みかんの皮)、山椒、けしの実、麻の実 |
| やまつ辻田『極上七味 西高野街道から』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月3日時点 での税込価格 |
辛さと風味が見事に調和! | 15g | 唐辛子、金ごま、黒ごま、山椒、柚子、青のり、けしの実、しそ |
| S&B『袋入り七味唐からし』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月3日時点 での税込価格 |
七味唐辛子の定番! 毎日の料理に手軽に使える | 14g | 赤唐辛子、黒ごま、ちんぴ、山椒、麻の実、けしの実、青のり |
| 久原本家『茅乃舎 生七味』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月3日時点 での税込価格 |
料理を引き立てる風味豊かな生タイプの七味 | 60g | 赤唐辛子、黄ゆず皮、海塩、山椒、黒ごま、生姜、青海苔 |
| 味の海翁堂『長者様の七味にんにく』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月3日時点 での税込価格 |
食欲をそそる! 多彩な料理に使える七味にんにく | 90g | - |
風味豊かなスパイス「七味唐辛子」とは?
七味唐辛子は、江戸時代に日本橋薬研堀町で生まれた日本古来のブレンドスパイスです。からしや徳右衛門が、漢方薬をベースに生薬としても使われていた素材を組み合わせてつくりあげました。当時は、スパイスというよりも一種の薬のような感覚で使われており、寺社仏閣の門前で売られることが多かったようです。
七味といってもブレンドするスパイスの種類や数に決まりはないため、メーカーごとに原料と調合の割合が異なります。唐辛子の辛さだけでなく、ゴマや紫蘇、陳皮、山椒などの豊かな香りも楽しめるのが七味唐辛子の魅力です。最近では東京や京都をはじめとして各地に七味唐辛子の専門店も増えています。
黒七味などの従来のイメージを覆すものや、やげん堀など素材やブレンドにとことんこだわった有名メーカーもあり、選択肢は無数にあります。身近なところで言えば全国に店舗を展開しているカルディなどにもさまざまなものが揃っています。
七味唐辛子の選び方
ここからは七味唐辛子の選び方を詳しく解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
タイプで選ぶ
七味唐辛子を選ぶときは、まず七味唐辛子のタイプを決めましょう。粉末タイプと生タイプがあるので、それぞれの特徴を紹介します。
粉末タイプ
丼に振りかけたり、汁物に加えたりしたいなら、粉末タイプの七味唐辛子がよいでしょう。食べながら味を変えたいときでも、あとから好きなだけ振りかけられます。完成した料理にアクセントを加えたいときや、素材にまんべんなく味をつけたいときにもぴったりです。
粉末タイプの七味唐辛子を選ぶときは、振りかけるまえに容器を数回振りましょう。なかで七味が混ざり合い、バランスよく出てきます。
生タイプ
食べるラー油のような感覚で、ごはんに乗せたり、冷ややっこに乗せたりして味わえるのが生タイプの魅力です。生の原材料を使用しているため、香りや辛さが強く感じられます。
液体にも溶けやすいので、鍋の味つけやドレッシングなどにも使いやすいのがポイント。粉末の七味では刺激が物足りないと感じる人は、ぜひ一度味わってみてください。
原材料で選ぶ

出典:マイナビおすすめナビ

出典:マイナビおすすめナビ
七味唐辛子を選ぶときは、どんなスパイスがブレンドされているのかをチェックしましょう。
「辛味重視」なら唐辛子にこだわったものを
辛いものが好きな人は、唐辛子が多く配合されているものや、唐辛子の種類にこだわったものを選ぶとよいでしょう。メーカーによっては辛さを強めた「大辛」のものや、アフリカ原産の辛みの強い唐辛子を使ったものもあるので、チェックしてみてください。
辛味の質にもこだわりたい人は、原材料にも注目しましょう。複数の唐辛子をブレンドして、深みのある辛さに仕上げているものもあります。
「香り重視」なら柑橘類が多く入ったものを
七味唐辛子に辛さだけでなくさわやかな香りも求めているのであれば、かんきつ類が多く入ったものを選ぶとよいでしょう。陳皮や柚子が多く入った「ゆず七味」などは口に入れるとふんわりと和かんきつの香りが広がります。素材の味を生かした湯豆腐や鍋料理のアクセントにぴったりです。
さっぱりとした風味なので、ドレッシングに入れるのもよいでしょう。
「しびれる辛さ」には山椒や生姜入りをチェック
山椒や生姜が多く入った七味唐辛子は、ピリッとした唐辛子の辛味としびれるような山椒や生姜の辛味が楽しめます。
とくに山椒が多く入った「山椒七味」は、さわやかな山椒の香りも楽しめるのが魅力です。麻婆豆腐に入れたり、鶏の唐揚げやてんぷらに掛けたりするとよいでしょう。オーソドックスな唐辛子の辛さに飽きてしまった人にも試してもらいたい七味唐辛子です。
パッケージで選ぶ
七味唐辛子は、香りと辛さが命です。七味唐辛子を選ぶときは、辛さと香りが飛ばないうちに使いきれる容量・パッケージに入ったものを選びましょう。
瓶詰め・木箱
瓶詰めや木箱タイプのものは、そのまま料理にかけることができるので使い勝手がいいのが魅力です。量の調整がしやすいという点もポイント。ただし、穴の小さなタイプは詰まりやすいので注意が必要です。
袋詰め
袋詰めは瓶詰めのようにそのままでは使いにくいため、便などに詰め替える必要があります。その一方でコストパフォーマンスが高いものも多いので、大量に七味唐辛子が必要な場合にもおすすめです。
有名メーカーで選ぶ
七味唐辛子を選ぶときは、メーカーにも注目してみましょう。よく知られた七味唐辛子メーカーには、次の3つがあります。
京都・清水の「七味家本舗」
京都にある清水寺の参道に店を構える「七味家本舗」は、明暦年間に創業したお店です。
七味唐辛子に入っているのは、青のり・山椒・黒ゴマ・白ゴマ・唐辛子・青紫蘇・麻の実の7つです。香り豊かな素材を組み合わせた七味は、辛さよりも香りのよさが引き立ちます。
京料理の繊細な味わいを壊さない上品な風味が特徴です。
長野・善光寺の「八幡屋磯五郎」
長野にある善光寺の参道で元文元年に創業した「八幡屋磯五郎」の七味唐辛子は、バランスのよい味わいが特徴です。唐辛子・山椒・生姜・麻種・ゴマ・陳皮・紫蘇の7つをブレンドしています。近年は長野県産の原料を多く使って作られているのもポイントです。
「ガラムマサラ七味」や「バードアイ」といった変わり種の七味も販売しています。
ご当地色豊かなものを選ぶ
お土産やギフトとして七味唐辛子を選ぶときは、ご当地色豊かなものを選ぶのもよいでしょう。全国には、その土地の特産品などを使ったご当地七味がたくさんあります。遠くまで足を延ばしたときは、その土地でしか手に入らない七味を探してスーパーマーケットなどに立ち寄ってみてください。
七味唐辛子の味わいは、東と西で異なるのもポイント。東の七味は辛さに重点を置いてブレンドされており、西の七味は香りに重点を置いてブレンドされています。全国各地のご当地七味のなかから自分のお気に入りを探してみましょう。
ユーザーが選んだイチオシ5選
ここでは、みんながおすすめする「七味唐辛子」だけを紹介します。商品の口コミはもちろん、コスパや味・おいしさ、香り・風味といった評価ポイントも聞いてみたので、各項目にも注目して商品選びの参考にしてください!
その他にもおすすめしたい商品があるよという方は、ぜひ記事後半にある投稿フォームからご紹介をお願いします。

愛用者
ほどよいバランスの辛さと香りで使いやすい
辛さも香りも絶妙な塩梅なのが気に入って、繰り返し購入しています。それでいて、うどんなどに入れるとしっかり味のアクセントになってくれるので使いやすいです。瓶タイプもありますが、ゴミの少ない袋タイプを選んでいます。袋の切り口が細くなっていて、ほかの容器に移し替えやすいのもグッド!(K.N.さん/男性/49歳/自営業)
※各社通販サイトの 2025年3月3日時点 での税込価格
| コスパ | ★★★★★ |
|---|---|
| 味・おいしさ | ★★★★☆ |
| 香り・風味 | ★★★★☆ |
| 総合評価 | 4.3点 |
| コスパ | ★★★★★ |
|---|---|
| 味・おいしさ | ★★★★☆ |
| 香り・風味 | ★★★★☆ |
| 総合評価 | 4.3点 |

愛用者
長野県の名産品! おいしい七味です
以前お土産でもらって、とてもおいしかったのでリピートしています。こちらの七味を使ったら他の七味は使えないくらい気に入っていますね。香ばしさが料理をおいしく引き立ててくれます。特に、うどんやそばとの相性は抜群。小粋なデザインなので、ちょっとしたプレゼントにもいいですよ。(E.S.さん/女性/50代/パート主婦)
※各社通販サイトの 2025年3月3日時点 での税込価格
| コスパ | ★★★★☆ |
|---|---|
| 味・おいしさ | ★★★★☆ |
| 香り・風味 | ★★★★★ |
| 総合評価 | 4.3点 |
| コスパ | ★★★★☆ |
|---|---|
| 味・おいしさ | ★★★★☆ |
| 香り・風味 | ★★★★★ |
| 総合評価 | 4.3点 |

愛用者
上品でしっとりとした黒七味
京都・祇園に本店を構える老舗が生み出すこだわりの黒七味です。素材を煎っているので、色は真っ黒ですが、いろんな風味がします。ほかの七味よりも辛味はツンと来なくてまろやか。複雑味と上品な香りが特徴的だと思います。個人的には、チーズとの相性もいいと思います。牛内臓のトリッパのトマト煮込みに、軽くチーズを乗せて、仕上げにこの黒七味を振りかけたところ、ベストマッチでした。(M.S.さん/男性/49歳/会社員)
※各社通販サイトの 2025年3月3日時点 での税込価格
| コスパ | ★★★★☆ |
|---|---|
| 味・おいしさ | ★★★★☆ |
| 香り・風味 | ★★★★☆ |
| 総合評価 | 4.0点 |
| コスパ | ★★★★☆ |
|---|---|
| 味・おいしさ | ★★★★☆ |
| 香り・風味 | ★★★★☆ |
| 総合評価 | 4.0点 |

愛用者
ゆずの香りが楽しめる!
柚子コショウのネーミングに惹かれて購入しました。柚子の香りはしっかりしていて、料理にニュアンスを加えてくれます。素そばに振りかけるだけでも、贅沢な香りと味わいが楽しめると思います。(Y.I.さん/女性/50歳/自営業)
※各社通販サイトの 2025年3月3日時点 での税込価格
| コスパ | ★★★★☆ |
|---|---|
| 味・おいしさ | ★★★★☆ |
| 香り・風味 | ★★★★☆ |
| 総合評価 | 4.0点 |
| コスパ | ★★★★☆ |
|---|---|
| 味・おいしさ | ★★★★☆ |
| 香り・風味 | ★★★★☆ |
| 総合評価 | 4.0点 |

愛用者
辛みと風味のバランスが魅力
風味豊かな七味唐辛子です。単なる辛さだけでなく深い味わいがあるように思いました。ラーメンやうどん、スープなどに振りかけると味が引き締まっておいしさがアップします。容器も使いやすく、いつでも手軽に使えるので便利です。(H.Y.さん/男性/40歳/自営業)
※各社通販サイトの 2025年3月3日時点 での税込価格
| コスパ | ★★★☆☆ |
|---|---|
| 味・おいしさ | ★★★★☆ |
| 香り・風味 | ★★★★☆ |
| 総合評価 | 3.7点 |
| コスパ | ★★★☆☆ |
|---|---|
| 味・おいしさ | ★★★★☆ |
| 香り・風味 | ★★★★☆ |
| 総合評価 | 3.7点 |
七味唐辛子おすすめ15選 京都や長野の人気商品も!
上で紹介した七味唐辛子の選び方のポイントをふまえて、ここからは厳選したおすすめ商品をご紹介します。

マイナビおすすめナビ編集部
丁寧に材料を煎り、唐辛子や山椒の風味が調和した深い茶色が特徴の黒七味。風合いはしっとりとしており、和食にぴったり。特に山椒がぴりりと効き、ミートソースとも意外なほど相性ぴったりです。
風味豊かな黒七味の袋詰めタイプ
唐辛子をはじめとして白ごまや山椒、青のり、けしの実、黒ごまなど厳選された材料を独自にブレンドし、丁寧にから煎り、揉み込みを行うことによって独特の黒っぽい色に仕上げられています。風味がしっかりとしており、すべての素材が豊かに香る逸品となりました。高級七味唐辛子ですが、袋詰めタイプなのでリーズナブルなのも嬉しいポイントです。
※各社通販サイトの 2025年3月3日時点 での税込価格
| 内容量 | 8g |
|---|---|
| 原材料 | ‐ |
| 内容量 | 8g |
|---|---|
| 原材料 | ‐ |

マイナビおすすめナビ編集部
粒子を細かくするほど辛味が増す独特の一味はクセになります。日本料理はもちろん、イタリア料理にもぴったり。うどんやそば、麻婆豆腐、ラーメンなどいろんな料理に合わせたいですね。
原材料、製法にもこだわった逸品
赤唐辛子をベースとしたオーソドックスな七味唐辛子ですが、素材や製法にとことんこだわることによって辛さのみでなく風味豊かな味わいを楽しめる逸品です。一般的な七味唐辛子よりも粒子が細かく仕上げられていますので、辛味もしっかりとしておりどんな食材と組み合わせても存在感があり、同時に食材の味を引き立ててくれます。
※各社通販サイトの 2025年3月3日時点 での税込価格
| 内容量 | 20g |
|---|---|
| 原材料 | ‐ |
| 内容量 | 20g |
|---|---|
| 原材料 | ‐ |

秘伝の調合で辛さが際立つ七味唐辛子
風味の豊かさが特徴の七味唐辛子で、辛すぎないので小さなお子さまや辛いものがあまり得意でない方にもおすすめです。素材そのものの味を引き立てるようなバランスのいい味わいで、どんなお料理にもマッチします。
缶タイプですが中身は2袋に小分けされているため、使用頻度が少ない方でも香りが飛ぶのをあまり気にせず使えるのがうれしいポイントです。
※各社通販サイトの 2025年3月3日時点 での税込価格
| 内容量 | 14g |
|---|---|
| 原材料 | 唐辛子、陳皮、胡麻、麻種、紫蘇、山椒、生姜(一部にごまを含む) |
| 内容量 | 14g |
|---|---|
| 原材料 | 唐辛子、陳皮、胡麻、麻種、紫蘇、山椒、生姜(一部にごまを含む) |

木筒がポイント! 山椒の刺激を感じられる七味
濃い茶色が特徴的な七味唐辛子。製造過程でそれぞれの素材を煎ってもみ込んでいるので香りがよく、唐辛子の辛味よりも山椒のピリッとした刺激が舌に残ります。
辛味だけでなくコクも感じられるので、丼ものや麺類との相性はもちろん、豆腐や魚など比較的あっさりとした食材との相性も抜群です。高級感のある木筒でちょっとした贈り物にもおすすめです。
※各社通販サイトの 2025年3月3日時点 での税込価格
| 内容量 | 6g |
|---|---|
| 原材料 | 白ごま、唐辛子、山椒、青のり、けしの実、黒ごま、おの実 |
| 内容量 | 6g |
|---|---|
| 原材料 | 白ごま、唐辛子、山椒、青のり、けしの実、黒ごま、おの実 |

マイナビおすすめナビ編集部
唐辛子の辛さとゆずの爽やかな香りが絶妙に調和し、料理に奥深い味わいをプラスしてくれます。辛さは控えめで、ゆずの香りが漂い、うどんやそばなどにもピッタリです。
秘伝の調合と柚子の風味のコラボレーション
こだわりの原材料を独自に調合することによって、絶妙な風味や味わいを楽しむことができる定番七味唐辛子に柚子をプラスしたものとなっています。ベースとなっているのは中辛で、控えめの辛みと柚子の爽やかな香りが見事にマッチしています。鍋物やお味噌汁などに一振りするだけでワンランク上の味わいを楽しむことができます。
※各社通販サイトの 2025年3月3日時点 での税込価格
| 内容量 | 12g |
|---|---|
| 原材料 | 唐辛子、柚子、陳皮、胡麻、麻種、紫蘇、山椒、生姜 |
| 内容量 | 12g |
|---|---|
| 原材料 | 唐辛子、柚子、陳皮、胡麻、麻種、紫蘇、山椒、生姜 |
激辛好きの方におすすめ!
七味唐辛子にはやっぱり辛さを求めている…そんな方にぴったりなのが、激辛唐辛子であるキャロライナリーパーを使ったこちらの七味唐辛子です。2013年にはギネス世界記録にも認定された世界一辛い唐辛子であるキャロライナリーパーを使用しているだけあって、まさに激辛。辛いもの好きな方にぴったりな七味唐辛子となっています。
※各社通販サイトの 2025年3月3日時点 での税込価格
| 内容量 | 12g |
|---|---|
| 原材料 | 唐辛子、赤山椒、黒胡麻、青のり、陳皮、紫蘇、生姜 |
| 内容量 | 12g |
|---|---|
| 原材料 | 唐辛子、赤山椒、黒胡麻、青のり、陳皮、紫蘇、生姜 |
あっさりとした和食にマッチ
唐辛子にプラスして実生柚子を贅沢に使用することによって、爽やかな風味を楽しめる七味唐辛子です。辛さは控えめに仕上げられていますので、あっさりとしたお吸い物や湯豆腐、寄せ鍋といったあっさりとした和食の味わいをさらに引き立たせてくれます。しっかりと内部を密閉することで長く風味を保ってくれる缶タイプです。
※各社通販サイトの 2025年3月3日時点 での税込価格
| 内容量 | 10g |
|---|---|
| 原材料 | 柚子、本鷹唐辛子、胡麻、青のり、山椒、芥子の実、紫蘇、麻の実 |
| 内容量 | 10g |
|---|---|
| 原材料 | 柚子、本鷹唐辛子、胡麻、青のり、山椒、芥子の実、紫蘇、麻の実 |
国産原料にこだわった香り豊かな逸品
唐辛子による辛さのみでなく、国産の山椒や柚子などを使用することによって豊かな香りにこだわった七味唐辛子となっています。すべての原料を国産にこだわることによって、より豊かな風味と奥深い味わいを実現しています。汁物の風味付けはもちろんのこと、さまざまな食材や料理とあわせて楽しむことのできる七味唐辛子に仕上がっています。
※各社通販サイトの 2025年3月3日時点 での税込価格
| 内容量 | 12g |
|---|---|
| 原材料 | 青唐辛子(九州産)、赤唐辛子(九州産)、ごま(金・黒)、あおさ、きくらげ粉末、柚子、山椒 |
| 内容量 | 12g |
|---|---|
| 原材料 | 青唐辛子(九州産)、赤唐辛子(九州産)、ごま(金・黒)、あおさ、きくらげ粉末、柚子、山椒 |
山椒の効いた京風七味
山椒を効かせた京風の七味唐辛子です。刺激のみでなく柑橘の香りも効いていますのでさまざまな料理や食材にあわせて楽しむことができます。香りは豊かですがすべての原材料がしっかりと調和していますので、癖もありません。七味唐辛子独特の風味があまり好きではないという方にもおすすめすることができます。250gと大容量なので七味好きには堪らない商品です。
※各社通販サイトの 2025年3月3日時点 での税込価格
| 内容量 | 250g |
|---|---|
| 原材料 | ちんぴ、唐辛子、山椒、ごま、けしの実、麻の実、あおさ |
| 内容量 | 250g |
|---|---|
| 原材料 | ちんぴ、唐辛子、山椒、ごま、けしの実、麻の実、あおさ |
パウダータイプの七味。持ち運びにも便利!
水にほとんど溶けない唐辛子の辛味成分『カプサイシン』と唐辛子の豊かな風味をナノテクノロジーを利用し、水に溶けるように改良した顆粒タイプの唐辛子調味料です。
辛味がダイレクトに舌へ伝わり、辛さを強く感じるでしょう。酸味や塩味など余計な味を加えていないので、どんな料理でも味を損なうことなく、仕上げにふりかけるだけでお好みの辛さにチェンジ!
持ち運び、携帯に便利な小瓶入りで、マイ唐辛子として、外出先でも手軽に使いやすいですよ。
※各社通販サイトの 2025年3月3日時点 での税込価格
| 内容量 | 8g |
|---|---|
| 原材料 | 粉飴(国内製造)、麦芽糖、唐辛子エキス/レシチン(大豆由来)、パプリカ色素、酸化防止剤 |
| 内容量 | 8g |
|---|---|
| 原材料 | 粉飴(国内製造)、麦芽糖、唐辛子エキス/レシチン(大豆由来)、パプリカ色素、酸化防止剤 |
まろやかな辛みと香ばしい香りが特長
純粋な辛味を楽しめる「生の唐辛子」と、唐辛子を焙煎した「焼き唐辛子」の2種類をブレンド。さらに香り高い山椒や黒ごま、陳皮、麻の実、けしの実などを配合しています。
まろやかな辛みと、唐辛子と香辛料が合わさった味の深みをしっかりと感じることができますよ。
※各社通販サイトの 2025年3月3日時点 での税込価格
| 内容量 | 24g |
|---|---|
| 原材料 | 唐辛子(中国、日本)(焼粉・赤粉)、黒ごま、陳皮(みかんの皮)、山椒、けしの実、麻の実 |
| 内容量 | 24g |
|---|---|
| 原材料 | 唐辛子(中国、日本)(焼粉・赤粉)、黒ごま、陳皮(みかんの皮)、山椒、けしの実、麻の実 |
辛さと風味が見事に調和!
国内産唐辛子を使用し、そこに朝倉粉山椒、有機黒ごま、柚子、高知糸すじ青のり、有機金ごまなど7つの原料を創業100年の秘伝でブレンド。奥深い味わいを演出しています。
明治35年以来の石臼製法で生産された七味唐辛子で、長く愛され続けています。
※各社通販サイトの 2025年3月3日時点 での税込価格
| 内容量 | 15g |
|---|---|
| 原材料 | 唐辛子、金ごま、黒ごま、山椒、柚子、青のり、けしの実、しそ |
| 内容量 | 15g |
|---|---|
| 原材料 | 唐辛子、金ごま、黒ごま、山椒、柚子、青のり、けしの実、しそ |
七味唐辛子の定番! 毎日の料理に手軽に使える
スーパーでもよく見かける、有名なS&Bブランドの七味唐辛子。唐辛子に香り豊かな山椒、黒ごま、ちんぴ、麻の実、けしの実、青のりが配合されています。
スーパーでも買いやすく、値段もお手頃なのがうれしいポイント。ビンでも販売されていますが、こちらは袋入りのタイプです。
※各社通販サイトの 2025年3月3日時点 での税込価格
| 内容量 | 14g |
|---|---|
| 原材料 | 赤唐辛子、黒ごま、ちんぴ、山椒、麻の実、けしの実、青のり |
| 内容量 | 14g |
|---|---|
| 原材料 | 赤唐辛子、黒ごま、ちんぴ、山椒、麻の実、けしの実、青のり |

料理を引き立てる風味豊かな生タイプの七味
乾燥も加熱もせずに作られた、生タイプの七味唐辛子です。ねっとりとした食感と、あとからジワジワ追いかけてくる辛味がクセになります。
鍋料理の薬味にはもちろん、グリルチキンやポークソテーなどの肉料理や焼き魚など、さまざまな料理にベストマッチ。素材の臭みを消しながらうまみを引き出してくれるので、少量でもグッと味わいがランクアップします。しっとりしたタイプなのでお刺身の薬味としてもおいしくいただけます。
※各社通販サイトの 2025年3月3日時点 での税込価格
| 内容量 | 60g |
|---|---|
| 原材料 | 赤唐辛子、黄ゆず皮、海塩、山椒、黒ごま、生姜、青海苔 |
| 内容量 | 60g |
|---|---|
| 原材料 | 赤唐辛子、黄ゆず皮、海塩、山椒、黒ごま、生姜、青海苔 |
食欲をそそる! 多彩な料理に使える七味にんにく
七味唐辛子ににんにくがブレンドされた『七味にんにく』。にんにくの風味が加わることで、料理の風味を一層引き立てます。
にんにくは、香り豊かな青森県産にんにくを100%使用しているのがポイント。うどんやそば、焼き鳥などさまざまな料理と相性がよく、食欲をそそります。
※各社通販サイトの 2025年3月3日時点 での税込価格
| 内容量 | 90g |
|---|---|
| 原材料 | - |
| 内容量 | 90g |
|---|---|
| 原材料 | - |
「七味唐辛子」のおすすめ商品の比較一覧表
| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 内容量 | 原材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 原了郭『黒七味 袋(大)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月3日時点 での税込価格 |
風味豊かな黒七味の袋詰めタイプ | 8g | ‐ |
| 一休堂『京七味』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月3日時点 での税込価格 |
原材料、製法にもこだわった逸品 | 20g | ‐ |
| 根元 八幡屋礒五郎『七味◎缶』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月3日時点 での税込価格 |
秘伝の調合で辛さが際立つ七味唐辛子 | 14g | 唐辛子、陳皮、胡麻、麻種、紫蘇、山椒、生姜(一部にごまを含む) |
| 原了郭『黒七味 四角』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月3日時点 での税込価格 |
木筒がポイント! 山椒の刺激を感じられる七味 | 6g | 白ごま、唐辛子、山椒、青のり、けしの実、黒ごま、おの実 |
| 根元 八幡屋礒五郎『ゆず七味 缶』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月3日時点 での税込価格 |
秘伝の調合と柚子の風味のコラボレーション | 12g | 唐辛子、柚子、陳皮、胡麻、麻種、紫蘇、山椒、生姜 |
| オーガニックファームHARA『キャロライナリーパー超激辛七味唐辛子』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月3日時点 での税込価格 |
激辛好きの方におすすめ! | 12g | 唐辛子、赤山椒、黒胡麻、青のり、陳皮、紫蘇、生姜 |
| おちゃのこさいさい『京の柚子七味 缶』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月3日時点 での税込価格 |
あっさりとした和食にマッチ | 10g | 柚子、本鷹唐辛子、胡麻、青のり、山椒、芥子の実、紫蘇、麻の実 |
| エヴァウェイ『和の七彩』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月3日時点 での税込価格 |
国産原料にこだわった香り豊かな逸品 | 12g | 青唐辛子(九州産)、赤唐辛子(九州産)、ごま(金・黒)、あおさ、きくらげ粉末、柚子、山椒 |
| ユウキ『MC 京風七味』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月3日時点 での税込価格 |
山椒の効いた京風七味 | 250g | ちんぴ、唐辛子、山椒、ごま、けしの実、麻の実、あおさ |
| うれし野ラボ『新感覚調味料 とける唐辛子』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月3日時点 での税込価格 |
パウダータイプの七味。持ち運びにも便利! | 8g | 粉飴(国内製造)、麦芽糖、唐辛子エキス/レシチン(大豆由来)、パプリカ色素、酸化防止剤 |
| やげん堀『七味唐辛子 中辛』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月3日時点 での税込価格 |
まろやかな辛みと香ばしい香りが特長 | 24g | 唐辛子(中国、日本)(焼粉・赤粉)、黒ごま、陳皮(みかんの皮)、山椒、けしの実、麻の実 |
| やまつ辻田『極上七味 西高野街道から』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月3日時点 での税込価格 |
辛さと風味が見事に調和! | 15g | 唐辛子、金ごま、黒ごま、山椒、柚子、青のり、けしの実、しそ |
| S&B『袋入り七味唐からし』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月3日時点 での税込価格 |
七味唐辛子の定番! 毎日の料理に手軽に使える | 14g | 赤唐辛子、黒ごま、ちんぴ、山椒、麻の実、けしの実、青のり |
| 久原本家『茅乃舎 生七味』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月3日時点 での税込価格 |
料理を引き立てる風味豊かな生タイプの七味 | 60g | 赤唐辛子、黄ゆず皮、海塩、山椒、黒ごま、生姜、青海苔 |
| 味の海翁堂『長者様の七味にんにく』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月3日時点 での税込価格 |
食欲をそそる! 多彩な料理に使える七味にんにく | 90g | - |
通販サイトの最新人気ランキングを参考にする 七味唐辛子の売れ筋をチェック
Amazon、楽天市場での七味唐辛子の売れ筋ランキングも参考にしてみてください。
※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。
おすすめレシピを紹介 七味唐辛子を使いこなそう!
七味唐辛子は日本を代表するスパイスです。よく利用されてる七味の中身/原料としては、唐辛子、山椒、ちんぴ、青のり、ごま、麻の実、けしの実などがあげられます。香りと辛味のバランスを重視して配合されているので和食のアクセントとして使うのがおすすめ!
ここではそんな和食と相性のいい七味唐辛子を使ったレシピを少し紹介したいと思います。
お手軽きんぴらごぼう
【材料】
ごぼう 1本
にんじん 1/3本
ごま油 小さじ2
酒40cc
★砂糖大さじ1.5
★しょう油大さじ1.5
★みりん大さじ2
いりごま 適量
七味唐辛子 適量
【作り方】
まずは、ゴボウを洗って泥を落とします。ゴボウはささがきにして千切りにしたら水にさらし、にんじんも同じくらいに千切りにします。フライパンを火にかけ、ごま油をひいたら、ゴボウとにんじんを炒めます。しんなりとしてきたら酒を入れ、★の調味料を加えます。最後に、七味唐辛子とごまをふって完成です。
豚の七味唐辛子焼き
【材料】
しょうが焼き用の豚ロース 4枚
★味噌 大さじ1
★酒 小さじ2
★砂糖 小さじ1
★みりん 大さじ1
★七味唐辛子 適量
【作り方】
★の調味料を容器に入れて混ぜ合わせ、豚ロースに揉み込むようにからめます。フライパンを熱し、中火でゆっくりと火が通るまで焼きましょう。最後に残った調味液をかけて、お好みで七味唐辛子をふったら完成です。
自分好みの七味唐辛子を見つけよう
七味唐辛子は食卓の主役というわけではありませんが、食材やお料理を引き立ててくれる名脇役です。メインの唐辛子とさまざまな素材を組み合わせることによってさまざまな味わいのものがあり、選択肢は無数にあります。
毎日の食卓にちょっと特別な唐辛子をプラスすることによって、食事の時間がもっと豊かになることでしょう。好みの七味唐辛子を揃えて、料理に合わせて使い分けるのもおすすめです。今回は、七味唐辛子の選び方や、特におすすめのアイテムをピックアップしてみました。好みや用途に合わせて選んでみてください。
おすすめ商品・口コミの投稿はこちら
※メーカーや販売店の方は、ページ下部の「お問い合わせはこちら」から商品情報をお送りください。
ユーザーのおすすめ商品や口コミ情報は、マイナビおすすめナビを閲覧したユーザー、マイナビニュース会員、外部パートナー企業と契約する一般ユーザーからの投稿をもとにしています。
◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。