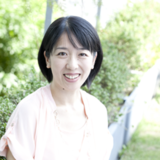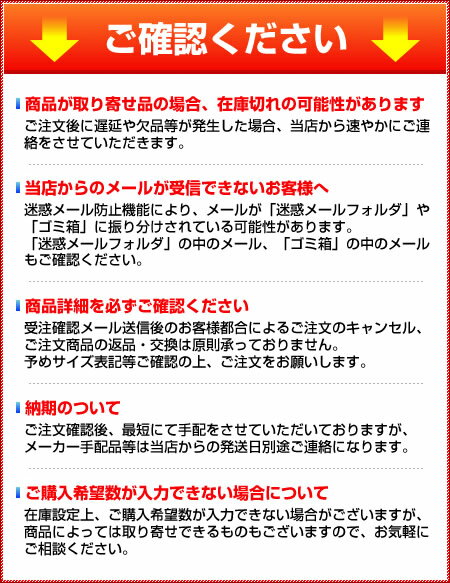| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 材質 | サイズ | 重量/容量 | 板厚 | IH対応 | 目盛り | コーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中尾アルミ製作所『N-40 打出ヤットコ鍋 18cm』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月05日時点 での税込価格 |
サイズ展開が豊富! 槌目が美しい鍋 | アルミ | 内径:18cm、深さ:7.5cm | 0.4kg/1.8L | 3.0mm | - | 〇 | - |
| アカオアルミ『ヤットコ鍋(AYT02015)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月05日時点 での税込価格 |
使いやすくて丈夫なアルミ製 | 硬質アルミ | 内径:15cm、深さ:6.5cm | 0.34kg/1.0L | 2.9mm | × | - | - |
| 中尾アルミ製作所『N-40 打出ヤットコ鍋 21cm』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月05日時点 での税込価格 |
アルミ製なら中尾アルミ! サイズ違いでそろえたい | アルミ | 内寸:21cm、深さ:8.7cm | 0.6kg/2.7L | 3.0mm | - | 〇 | - |
| 中尾アルミ製作所『キングデンジヤットコ鍋(psczlm-4)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月05日時点 での税込価格 |
耐久性が高い業務用! 使い勝手のよいIH対応鍋 | SUS445M2(モリブデン鋼2%含有) | 内径:18cm、深さ:7.5cm | 0.8kg/1.8L | 2.0mm | 〇 | 〇 | - |
| 玉虎堂製作所『矢床鍋(ヤットコ鍋)(044529) 22cm』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月05日時点 での税込価格 |
目盛りつきのボウルとして活用できる | 有磁性特殊ステンレス鋼 | 直径:22cm、高さ:8cm | 0.699kg/2.8L | 1.2mm | 〇 | 〇 | - |
| フジノス『20-0 ロイヤルヤットコ鍋(XZD-160) 16cm』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月05日時点 での税込価格 |
ガスでの使用も可! 家電メーカー推奨鍋 | 20-0ステンレス | 内寸:15.5cm、深さ:6.5cm、底径:11cm | 0.3kg/1.0L | 底板厚:1.5mm | 〇 | - | コーティング |
| 丸新銅器『銅ヤットコ鍋 15cm』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月05日時点 での税込価格 |
少量の水で下ごしらえできる | 銅 | 内寸:15cm、深さ:6.8cm | 0.375kg/1.0L | - | × | × | - |
| 木屋『やっとこ鍋 五寸(0506002001) 15cm』 |
|
※各社通販サイトの 2024年11月6日時点 での税込価格 |
育てがいのある銅製は経年変化を楽しめる | 鍋:銅(内面:錫めっき)、やっとこ:鉄、クロームメッキ | 直径:15cm(五寸) | 約0.546kg/1.2L | 底厚:1.5mm | × | - | - |
| 江部松商事 EBM『モリブデンジII ヤットコ鍋 18cm』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月05日時点 での税込価格 |
ステンレス製+厚底のガス&IH対応モデル | SUS316(18%クローム、14%ニッケル、3%モリブデン) | 外径:18cm、高さ:7cm、底径:13.5cm | 0.6kg/1.3L | 底板厚:3mm | 〇 | - | - |
| 本間製作所『3層鋼クラッドヤットコ鍋(1047) 15cm』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月05日時点 での税込価格 |
3層鋼クラッド材使用! 扱いやすいIH対応鍋 | 3層鋼:18-8ステンレス(クロム18%、ニッケル8%)、アルミニウム、ステンレス(クロム18%) | 15cm | -/0.9L | 2.3mm | 〇 | × | - |
やっとこ鍋とは? どんな風に使うの? キャンプ飯にも人気!
やっとこ鍋は、柄がついていない雪平鍋のような形状が特徴のお鍋。漢字では矢床鍋と書きます。
移動させるときは、ペンチのような形状の「やっとこ」で鍋のフチをはさんで使います。柄がついておらず、コロンとした丸い形のため火が均等に入るのも特徴。煮ものなども煮汁が染みておいしく仕上がります。
また、作った料理を鍋のまま出せるので、自宅だけでなくアウトドアで使う人も増えてきました。ふだん使いからレジャーまで活用できる便利な鍋になります。
やっとこ鍋の選び方 管理栄養士が監修!
管理栄養士の山田由紀子さん監修のもと、やっとこ鍋の選び方を紹介します。購入に際しては、材質や板厚、サイズなどをよくチェックすることが大切です。
ポイントは下記の通り。
【1】材質
【2】板厚
【3】サイズ
【4】機能
上記のポイントをおさえることで、より欲しい商品をみつけることができます。一つひとつ解説していきます。
【1】やっとこ鍋の材質の特徴から選ぼう
やっとこ鍋はアルミ製・ステンレス製・銅製・モリブデン製など、商品によって材質はさまざまです。それぞれの材質の特徴をご説明します。
アルミ製|料理人も愛用する使いやすさが魅力
アルミ製は軽くて熱伝導率が高いため、スムーズに調理ができます。そのため、料理人の愛用者も多い材質です。しかし、アルミ製の鍋は酸性の食材の調理に向いていません。トマトや酢などを使用した料理を調理すると、酸の影響で鍋が変色してしまうので注意してください。
お求めやすい価格帯なので、やっとこ鍋はどんな鍋なのか、試してみたい方も購入しやすいでしょう。
ステンレス製|お手入れしやすくて長く愛用できる
ステンレス製はサビにくく、耐久性にすぐれているのが特徴。食洗機対応などお手入れのしやすさもポイントです。熱伝導率はあまりよくありませんが、保温性があるので冷めにくいのがメリット。みそ汁など調理後に保温しておきたい料理に向いています。
重量があるため、料理を入れたまま持ちあげるのはサイズによって難しいかもしれません。見た目はステンレスボウルのようなので、小さいサイズのやっとこ鍋なら食卓にそのまま出してもいいでしょう。
銅製|見た目の美しさと熱伝導率にすぐれる
銅製はほかの金属よりも熱伝導率が高く、熱を均一に伝えることができる特性があります。耐久性にもすぐれており、見た目にも美しいので調理器具にこだわりをもっている方にぴったり。
ただし、酸や塩素に弱いので料理を入れっぱなしにしていると、サビの一種「緑青(ろくしょう)」がでてしまいます。人体に影響はないといわれていますが、気になるなら使用後はしっかり洗って乾かして、湿気の少ない場所で保管するなど、お手入れを怠らないようにしましょう。
モリブデン製|酸に強くて頑丈
モリブデン製はステンレスにモリブデンが含まれているため酸や塩分に強く、サビにくいのが特徴です。ガス、IH兼用なのも便利です。
また、加熱による変形や変色も少ないなどメリットが多いため、価格相場はやや高め。そのぶん、長く愛用できるので買い替えずに使い続けたい方にぴったりです。
【2】板厚は作りたい料理に合わせて選ぶ
やっとこ鍋を選ぶときにチェックしてほしいのが板厚です。板の厚さによって向いている料理などが変わってきます。板厚による違いをご説明します。
板が厚いものほど温度ムラが出にくい
板が厚いお鍋を加熱しても、内面まで熱が届きにくく、横に広がっていきます。底面全体が温まってから食材に火をとおすので、鍋のなかで温度ムラが出にくいのが特徴です。異なる食材でも同じように火がとおり、少ない火力でじっくりと調理できるため、煮崩れもしにくくなります。
また、板が厚いことで蓄熱性も高くなり、火からおろしても冷めにくいのが特徴です。調理後もできるだけ温かさをたもっておきたいみそ汁などに向いているでしょう。
板が薄い鍋は下ごしらえ用として重宝する
板が薄いと熱が直接伝わるので、お湯が沸騰するまでの時間が短くて済みます。そのため、出汁づくりやゆで卵、野菜の下ゆでなど、調理の下ごしらえに便利です。また、レトルトパウチを温めるときやインスタントラーメンの調理にも、お湯が沸くのが早いので重宝するでしょう。
スープなどの調理も可能ですが、具材が多いと焦げついてしまうこともあるので注意してください。
【3】作りたい料理と食べる量に合わせてサイズを選ぶ
やっとこ鍋にはさまざまなサイズがあります。調理する食材の大きさや1回で作る分量など、作りたい量に合ったサイズを選びましょう。小さいものだと15cm程度で、ゆで卵やソースづくりなど少量の調理や下ごしらえに向いています。25cm以上になると魚をまるごと入れた煮つけなども作れるでしょう。
持っておくと便利なサイズは18cmと20cmです。4人家族のみそ汁やご飯もこのサイズを選べばじゅうぶんに活用できます。もしみそ汁用として雪平鍋をお持ちなら、雪平鍋よりも小さいサイズを持っておくと活用しやすいです。
【4】独自の機能にも注目!
やっとこ鍋を選ぶときは、便利な機能もチェックしてみましょう。鍋肌に目盛りがついていると、計量しながら食材を入れられるので時短調理にもなります。
また、フッ素加工などコーティングが施されたやっとこ鍋は焦げつきにくいため、煮物だけではなく、炒めものもできます。大きいサイズのやっとこ鍋なら、カレーもやっとこ鍋ひとつで調理できるので便利です。
>> 管理栄養士のワンポイントアドバイス
使い慣れるとメリットいっぱい!
やっとこ鍋の利点は、鍋に柄がついていないので重ねて収納しやすく、作った料理をそのまま冷蔵庫で保存したり調理用ボウルとして使ったりと、幅広い用途に使えるところです。
選ぶ際は、台所の熱源に合わせてIH用かガス用かをチェックしてください。長く使うならオール熱源対応を選ぶのがおすすめです。
毎日使うなら重さも重要。ステンレス製は重めなので小さいサイズを選ぶといいでしょう。
やっとこ鍋のおすすめ4選|アルミ製 料理人も愛用する使いやすさ
うえでご紹介したやっとこ鍋を選ぶポイントをふまえて、管理栄養士の山田由紀子さんと編集部で選んだおすすめのやっとこ鍋をご紹介します。昔ながらの槌目模様やIH対応、ステンレス製や銅製など、ご自身にとって使いやすいやっとこ鍋を探してみてください。
まずは、軽くて扱いやすいアルミ製のやっとこ鍋からおすすめ商品をご紹介します。
サイズ展開が豊富! 槌目が美しい鍋
1958年創業の中尾アルミのやっとこ鍋です。アルミ製は熱伝導率が高く、火加減によっては焦げやすいというデメリットがあります。そこで、こちらは板厚を3mmと厚くすることでじっくりと熱が入ります。
サイズは18cmで使いやすい大きさ。また、こちらの商品は昔ながらの打出製法でつくられているので、耐久性にもすぐれています。
※各社通販サイトの 2024年11月05日時点 での税込価格
| 材質 | アルミ |
|---|---|
| サイズ | 内径:18cm、深さ:7.5cm |
| 重量/容量 | 0.4kg/1.8L |
| 板厚 | 3.0mm |
| IH対応 | - |
| 目盛り | 〇 |
| コーティング | - |
| 材質 | アルミ |
|---|---|
| サイズ | 内径:18cm、深さ:7.5cm |
| 重量/容量 | 0.4kg/1.8L |
| 板厚 | 3.0mm |
| IH対応 | - |
| 目盛り | 〇 |
| コーティング | - |
使いやすくて丈夫なアルミ製
アルミニウム総合メーカーのアカオアルミのやっとこ鍋です。槌目が美しい昔ながらの形状が特徴。アルミ合金を使用しているため、軽くて耐久性にもすぐれています。丈夫ながら、求めやすい価格帯が魅力。料理人をはじめ、飲食業界のプロも愛用しています。
はじめてやっとこ鍋の購入を検討されている方にぴったりです。
※各社通販サイトの 2024年11月05日時点 での税込価格
| 材質 | 硬質アルミ |
|---|---|
| サイズ | 内径:15cm、深さ:6.5cm |
| 重量/容量 | 0.34kg/1.0L |
| 板厚 | 2.9mm |
| IH対応 | × |
| 目盛り | - |
| コーティング | - |
| 材質 | 硬質アルミ |
|---|---|
| サイズ | 内径:15cm、深さ:6.5cm |
| 重量/容量 | 0.34kg/1.0L |
| 板厚 | 2.9mm |
| IH対応 | × |
| 目盛り | - |
| コーティング | - |
アルミ製なら中尾アルミ! サイズ違いでそろえたい
昔ながらの打出製法でつくられたアルミ製のやっとこ鍋。みそ汁やスープ用としてはやや大きめですが、カレーなどの煮込み料理がつくりやすいサイズです。中尾アルミ製作所は業務用鍋を中心に展開しているため、ひとつの商品でサイズ展開が豊富なのも特徴。15cmをはじめ、30cmまでぜんぶで11サイズから選べます。
軽量なのでアウトドアシーンにもぴったり! ボウルとしても使い勝手のよいサイズなので、いくつかそろえておくと便利です。
※各社通販サイトの 2024年11月05日時点 での税込価格
| 材質 | アルミ |
|---|---|
| サイズ | 内寸:21cm、深さ:8.7cm |
| 重量/容量 | 0.6kg/2.7L |
| 板厚 | 3.0mm |
| IH対応 | - |
| 目盛り | 〇 |
| コーティング | - |
| 材質 | アルミ |
|---|---|
| サイズ | 内寸:21cm、深さ:8.7cm |
| 重量/容量 | 0.6kg/2.7L |
| 板厚 | 3.0mm |
| IH対応 | - |
| 目盛り | 〇 |
| コーティング | - |
耐久性が高い業務用! 使い勝手のよいIH対応鍋
中尾アルミ製作所の鍋でもIH調理機対応の「キングデンジシリーズ」のやっとこ鍋です。家庭にIH調理器が普及する20年前に誕生しました。モリブデン鋼を含むステンレスを使用しており、耐久性にもすぐれています。板厚は2.5mmで保温性もあるので便利です。
IHは200Vに対応していますが、材質の特性から変形のリスクもあるため、中以下でご使用ください。
※各社通販サイトの 2024年11月05日時点 での税込価格
| 材質 | SUS445M2(モリブデン鋼2%含有) |
|---|---|
| サイズ | 内径:18cm、深さ:7.5cm |
| 重量/容量 | 0.8kg/1.8L |
| 板厚 | 2.0mm |
| IH対応 | 〇 |
| 目盛り | 〇 |
| コーティング | - |
| 材質 | SUS445M2(モリブデン鋼2%含有) |
|---|---|
| サイズ | 内径:18cm、深さ:7.5cm |
| 重量/容量 | 0.8kg/1.8L |
| 板厚 | 2.0mm |
| IH対応 | 〇 |
| 目盛り | 〇 |
| コーティング | - |
やっとこ鍋のおすすめ2選|ステンレス製 耐久性抜群!
続いては、耐久性に優れ見た目も美しいステンレス製のおすすめやっとこ鍋をご紹介します。

玉虎堂製作所『矢床鍋(ヤットコ鍋)(044529)』は、容量目盛付きで、スープやだしなどの量が計りやすく調理に便利。ステンレス製で、煮込み料理に向いています。
目盛りつきのボウルとして活用できる
サビに強いステンレス鋼のやっとこ鍋は、ツヤのある美しい見た目が特徴。板厚は1.2mmと薄く、ボウルとしても活用しやすい形状です。熱源はガスやIHに対応。目盛りつきで食材の計量にも使え、アウトドアシーンでも役立つことでしょう。
サイズは22cmと大きめなので、カレーなどたっぷり作っておきたい煮込み調理にぴったりです。
※各社通販サイトの 2024年11月05日時点 での税込価格
| 材質 | 有磁性特殊ステンレス鋼 |
|---|---|
| サイズ | 直径:22cm、高さ:8cm |
| 重量/容量 | 0.699kg/2.8L |
| 板厚 | 1.2mm |
| IH対応 | 〇 |
| 目盛り | 〇 |
| コーティング | - |
| 材質 | 有磁性特殊ステンレス鋼 |
|---|---|
| サイズ | 直径:22cm、高さ:8cm |
| 重量/容量 | 0.699kg/2.8L |
| 板厚 | 1.2mm |
| IH対応 | 〇 |
| 目盛り | 〇 |
| コーティング | - |
ガスでの使用も可! 家電メーカー推奨鍋
はじめてのIH調理器対応鍋を開発したフジノスのやっとこ鍋。板厚1.5mmと薄いですが、ボウルのように使えるスタイリッシュな形状が特徴です。こちらのサイズは、みそ汁や煮物の調理におすすめ。耐衝撃性にもすぐれているため、長く愛用できるでしょう。
使用後は、サビないように中性洗剤で洗って、水気をある程度ふき取ってから乾燥させてください。
※各社通販サイトの 2024年11月05日時点 での税込価格
| 材質 | 20-0ステンレス |
|---|---|
| サイズ | 内寸:15.5cm、深さ:6.5cm、底径:11cm |
| 重量/容量 | 0.3kg/1.0L |
| 板厚 | 底板厚:1.5mm |
| IH対応 | 〇 |
| 目盛り | - |
| コーティング | コーティング |
| 材質 | 20-0ステンレス |
|---|---|
| サイズ | 内寸:15.5cm、深さ:6.5cm、底径:11cm |
| 重量/容量 | 0.3kg/1.0L |
| 板厚 | 底板厚:1.5mm |
| IH対応 | 〇 |
| 目盛り | - |
| コーティング | コーティング |
やっとこ鍋のおすすめ2選|銅製 熱伝導率が高く、均一に火が入る
ここからは、銅製のおすすめやっとこ鍋をご紹介します。
少量の水で下ごしらえできる
金属加工業が盛んな新潟県燕市にある丸新銅器のやっとこ鍋。15cmと小さいサイズなので、野菜の下ゆでやゆで卵などたくさんのお湯が必要でない調理に向いています。単身者ならひとりぶんの料理を作るのに適しているサイズです。
銅製の鍋は熱伝導率が高く、火加減が調整しやすいので料理人でも愛用者が多いのが特徴。お手入れを楽しみたい方にぴったりです。
※各社通販サイトの 2024年11月05日時点 での税込価格
| 材質 | 銅 |
|---|---|
| サイズ | 内寸:15cm、深さ:6.8cm |
| 重量/容量 | 0.375kg/1.0L |
| 板厚 | - |
| IH対応 | × |
| 目盛り | × |
| コーティング | - |
| 材質 | 銅 |
|---|---|
| サイズ | 内寸:15cm、深さ:6.8cm |
| 重量/容量 | 0.375kg/1.0L |
| 板厚 | - |
| IH対応 | × |
| 目盛り | × |
| コーティング | - |

木屋『やっとこ鍋』は、熱伝導のいい銅製で、湯を沸かしたり、煮物を炊いたりする時間が短縮できます。軽いので女性でも扱いやすいです。
育てがいのある銅製は経年変化を楽しめる
1792年創業の日本橋木屋のやっとこ鍋は、職人の手でひとつひとつていねいにつくられています。下ごしらえには15cm、みそ汁には18cm、豚汁なら21cmと作りたい料理に合わせてそろえてみてもいいでしょう。
銅は経年で風合いが変化します。お手入れがたいへんそうだと心配される方もいますが、使用後は洗ってしっかりと乾燥させれば長く使い続けることができます。
※各社通販サイトの 2024年11月6日時点 での税込価格
| 材質 | 鍋:銅(内面:錫めっき)、やっとこ:鉄、クロームメッキ |
|---|---|
| サイズ | 直径:15cm(五寸) |
| 重量/容量 | 約0.546kg/1.2L |
| 板厚 | 底厚:1.5mm |
| IH対応 | × |
| 目盛り | - |
| コーティング | - |
| 材質 | 鍋:銅(内面:錫めっき)、やっとこ:鉄、クロームメッキ |
|---|---|
| サイズ | 直径:15cm(五寸) |
| 重量/容量 | 約0.546kg/1.2L |
| 板厚 | 底厚:1.5mm |
| IH対応 | × |
| 目盛り | - |
| コーティング | - |
やっとこ鍋のおすすめ2選|モリブデン製など サビに強い!
最後は、モリブデン製や複数の素材を組み合わせた材質のおすすめやっとこ鍋をご紹介します。
ステンレス製+厚底のガス&IH対応モデル
ミラー加工が施されているやっとこ鍋は、通常のステンレスよりもサビにくいのが特徴。ステンレスにモリブデンジをくわえて、耐久性を高めているため、ソースやたれなど酸性の食材の調理に向いています。
熱源はガスとIH調理器具に対応しており、3mmと底面が厚いのでIHの高出力でも変形を防いでくれます。食材に熱が均等に入るのでおいしく仕上がるでしょう。
※各社通販サイトの 2024年11月05日時点 での税込価格
| 材質 | SUS316(18%クローム、14%ニッケル、3%モリブデン) |
|---|---|
| サイズ | 外径:18cm、高さ:7cm、底径:13.5cm |
| 重量/容量 | 0.6kg/1.3L |
| 板厚 | 底板厚:3mm |
| IH対応 | 〇 |
| 目盛り | - |
| コーティング | - |
| 材質 | SUS316(18%クローム、14%ニッケル、3%モリブデン) |
|---|---|
| サイズ | 外径:18cm、高さ:7cm、底径:13.5cm |
| 重量/容量 | 0.6kg/1.3L |
| 板厚 | 底板厚:3mm |
| IH対応 | 〇 |
| 目盛り | - |
| コーティング | - |
3層鋼クラッド材使用! 扱いやすいIH対応鍋
本間製作所のやっとこ鍋は、調理時のボウルとしても活用できます。扱いやすいように、軽量なアルミニウムをステンレスで挟んだ3層鋼クラッド材を使用。コーティングは施されていませんが、内面は鏡面仕上げで料理がこびりつきにくく、水アカも残りにくいのが特徴です。
外面はツヤ消し加工が施されているので、キズがついても目立ちにくい仕様。別売りでつまみの形状が異なる蓋も購入可能です。おそろいで使ってみてもいいでしょう。
※各社通販サイトの 2024年11月05日時点 での税込価格
| 材質 | 3層鋼:18-8ステンレス(クロム18%、ニッケル8%)、アルミニウム、ステンレス(クロム18%) |
|---|---|
| サイズ | 15cm |
| 重量/容量 | -/0.9L |
| 板厚 | 2.3mm |
| IH対応 | 〇 |
| 目盛り | × |
| コーティング | - |
| 材質 | 3層鋼:18-8ステンレス(クロム18%、ニッケル8%)、アルミニウム、ステンレス(クロム18%) |
|---|---|
| サイズ | 15cm |
| 重量/容量 | -/0.9L |
| 板厚 | 2.3mm |
| IH対応 | 〇 |
| 目盛り | × |
| コーティング | - |
「やっとこ鍋」のおすすめ商品の比較一覧表
| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 材質 | サイズ | 重量/容量 | 板厚 | IH対応 | 目盛り | コーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中尾アルミ製作所『N-40 打出ヤットコ鍋 18cm』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月05日時点 での税込価格 |
サイズ展開が豊富! 槌目が美しい鍋 | アルミ | 内径:18cm、深さ:7.5cm | 0.4kg/1.8L | 3.0mm | - | 〇 | - |
| アカオアルミ『ヤットコ鍋(AYT02015)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月05日時点 での税込価格 |
使いやすくて丈夫なアルミ製 | 硬質アルミ | 内径:15cm、深さ:6.5cm | 0.34kg/1.0L | 2.9mm | × | - | - |
| 中尾アルミ製作所『N-40 打出ヤットコ鍋 21cm』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月05日時点 での税込価格 |
アルミ製なら中尾アルミ! サイズ違いでそろえたい | アルミ | 内寸:21cm、深さ:8.7cm | 0.6kg/2.7L | 3.0mm | - | 〇 | - |
| 中尾アルミ製作所『キングデンジヤットコ鍋(psczlm-4)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月05日時点 での税込価格 |
耐久性が高い業務用! 使い勝手のよいIH対応鍋 | SUS445M2(モリブデン鋼2%含有) | 内径:18cm、深さ:7.5cm | 0.8kg/1.8L | 2.0mm | 〇 | 〇 | - |
| 玉虎堂製作所『矢床鍋(ヤットコ鍋)(044529) 22cm』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月05日時点 での税込価格 |
目盛りつきのボウルとして活用できる | 有磁性特殊ステンレス鋼 | 直径:22cm、高さ:8cm | 0.699kg/2.8L | 1.2mm | 〇 | 〇 | - |
| フジノス『20-0 ロイヤルヤットコ鍋(XZD-160) 16cm』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月05日時点 での税込価格 |
ガスでの使用も可! 家電メーカー推奨鍋 | 20-0ステンレス | 内寸:15.5cm、深さ:6.5cm、底径:11cm | 0.3kg/1.0L | 底板厚:1.5mm | 〇 | - | コーティング |
| 丸新銅器『銅ヤットコ鍋 15cm』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月05日時点 での税込価格 |
少量の水で下ごしらえできる | 銅 | 内寸:15cm、深さ:6.8cm | 0.375kg/1.0L | - | × | × | - |
| 木屋『やっとこ鍋 五寸(0506002001) 15cm』 |
|
※各社通販サイトの 2024年11月6日時点 での税込価格 |
育てがいのある銅製は経年変化を楽しめる | 鍋:銅(内面:錫めっき)、やっとこ:鉄、クロームメッキ | 直径:15cm(五寸) | 約0.546kg/1.2L | 底厚:1.5mm | × | - | - |
| 江部松商事 EBM『モリブデンジII ヤットコ鍋 18cm』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月05日時点 での税込価格 |
ステンレス製+厚底のガス&IH対応モデル | SUS316(18%クローム、14%ニッケル、3%モリブデン) | 外径:18cm、高さ:7cm、底径:13.5cm | 0.6kg/1.3L | 底板厚:3mm | 〇 | - | - |
| 本間製作所『3層鋼クラッドヤットコ鍋(1047) 15cm』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月05日時点 での税込価格 |
3層鋼クラッド材使用! 扱いやすいIH対応鍋 | 3層鋼:18-8ステンレス(クロム18%、ニッケル8%)、アルミニウム、ステンレス(クロム18%) | 15cm | -/0.9L | 2.3mm | 〇 | × | - |
通販サイトの人気ランキングを見る 鍋の売れ筋をチェック
Amazon、楽天市場での鍋の売れ筋ランキングも参考にしてみてください。
※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。
あわせて揃えたいアイテムをご紹介! おすすめ商品をたっぷり厳選!
やっとこ鍋で料理のレパートリー広げよう 使い方いろいろ! 料理がもっと楽しくなる!
管理栄養士の山田由紀子さんと編集部で選んだやっとこ鍋をご紹介しました。アルミ製やステンレス製、銅製、モリブデン製などさまざまな材質が使われているやっとこ鍋。板の厚みで保温性や熱伝導率も変わってきます。各材質の特徴をふまえて、やっとこ鍋でつくれる料理のレパートリーを広げてみてもいいですね。
軽くて持ち運びもしやすいため、キャンプやバーベキューでも活躍します。ぜひ本記事を参考にして、お気に入りのやっとこ鍋を探してみてください。
◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。