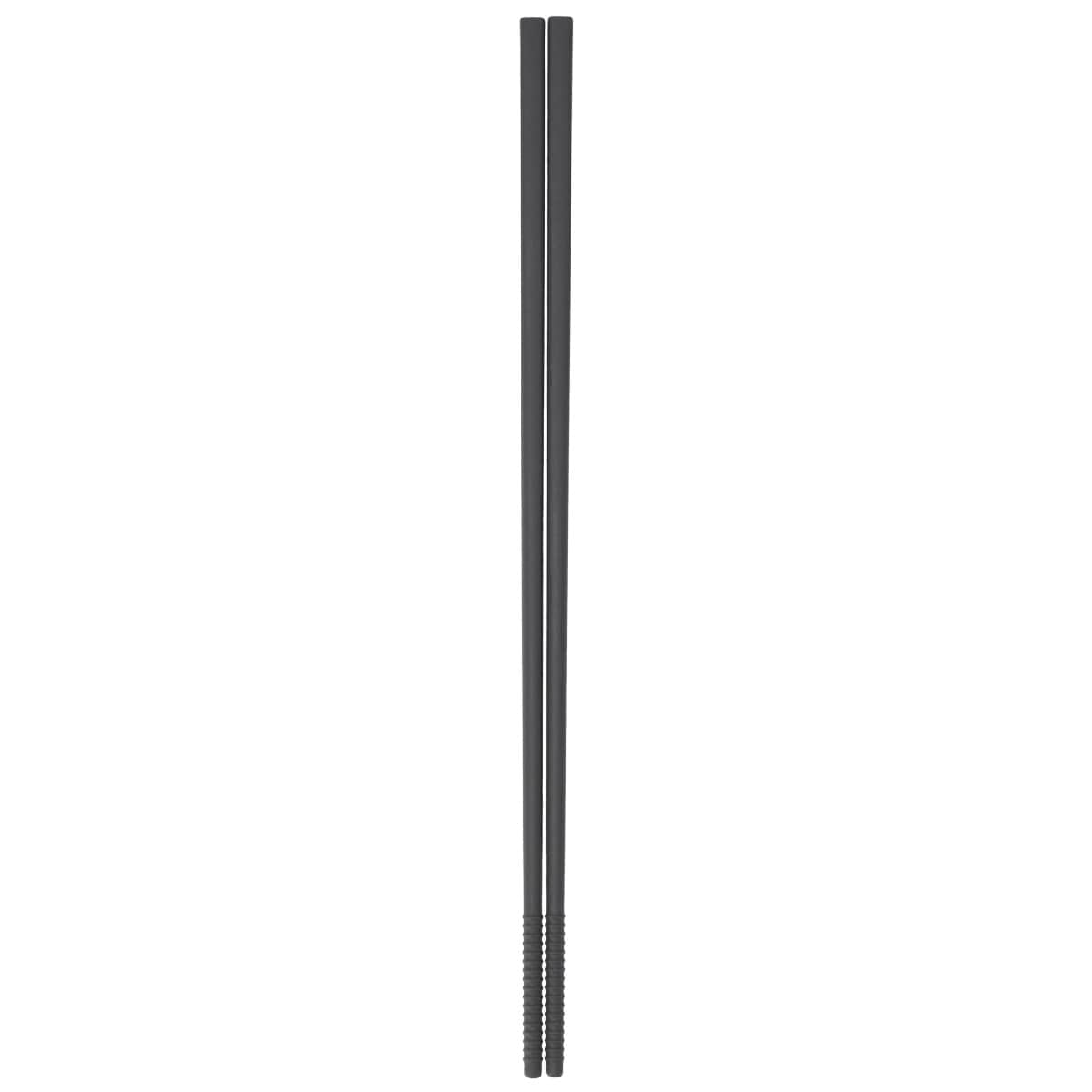| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | サイズ | 素材 | 食洗機対応 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜みらい『ののじ 驚異の耐熱220℃ 朝の菜箸24』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月20日時点 での税込価格 |
高温調理にも対応した耐久性のある菜箸 | 24cm | SPS樹脂 | ‐ |
| 山崎実業『tower(タワー) シリコーン菜箸』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格 |
調理中の置き場に便利な菜箸キーパーつき | 長さ300mm | シリコン、ナイロン | - |
| マーナ『シリコーン菜ばし ミニ chocotto(チョコット)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格 |
こまかい作業に便利な短めのシリコン製菜箸 | 幅6×高さ6×長さ250mm | ナイロン、シリコンゴム、ステンレス | 可 |
| NITORI(ニトリ)『シリコーン菜箸』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格 |
耐熱温度220度。デイリーで活躍する菜箸 | 幅0.7×奥行0.7×高さ30cm | シリコーン | 可 |
| パール金属『味見チョップスティック』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格 |
味見ができるナイロン製菜箸 | 35 x 4.9 x 2 cm | ナイロン(グラスファイバー含有)(先端表面シリコーンゴム) | 可 |
| OXO(オクソー)『シリコン 菜箸 ブラック』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格 |
先端がシリコンで出来た菜箸 | 幅20×高さ10×長さ290mm | ナイロン、シリコン、ステンレス鋼 | 可 |
| THERMOS(サーモス)『シリコーン菜箸』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格 |
食洗器OK!耐熱性にすぐれたシリコーン菜箸 | 0.7×0.7×30cm | シリコーン | 〇 |
| 貝印『セレクト100 ステンレス菜箸 33cm』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格 |
揚げもの用におすすめ! 長めの菜箸 | 幅18×高さ9×長さ330mm | 18-8ステンレススチール、ポリアセタール樹脂 | - |
| 杉安製作所『ステンレス 菜箸』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格 |
ステンレス製でとても軽い菜箸 | 長さ300mm | 18-8ステンレス | - |
| BESTOYARD『菜箸 料理用』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格 |
ステンレス製で溝が付いた長い菜箸 | 長さ360mm | ステンレス | - |
| 金口製作所『本焼ステンレス黒檀柄盛箸』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格 |
ステンレスの先端に最高級の黒檀を使用した菜箸 | 長さ305mm | 黒檀、ステンレス | ‐ |
| 福井クラフト『クッキングスティックス』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格 |
調理が楽しくなるカラフルな菜箸 | 長さ300mm | 飽和ポリエステル樹脂 | 可 |
| サンクラフト『ナイロン菜ばしトング L』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月20日時点 での税込価格 |
トングと一体化した耐熱性の菜箸 | 幅69×高さ90×長さ280mm | ナイロン(グラスファイバー含む) | 〇 |
| 貝印『ねこの菜箸 Nyammy(ニャミー)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格 |
料理が楽しくなる!かわいいデザイン | 長さ270mm | ポリスチレン | 可 |
| 貝印『プラスチックハンドル菜箸』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格 |
2種類の素材を使い軽量性と実用性がアップ | 幅10×高さ10×長さ300mm | ステンレススチール、ポリプロピレン | - |
| オークス『ワンクリック菜箸』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格 |
28 x 1.9 x 2.3 cm | ステンレス | 〇 | |
| パール金属『Easy Cooking 竹製料理用箸セット』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格 |
用途によって使い分けられる3本セット | 大330、中300、小270mm | 竹 | 不可 |
| 小関工芸『すべらない竹のお箸』 |
|
※各社通販サイトの 2024年11月20日時点 での税込価格 |
料亭などでも使われる「取り分け箸」 | 長さ320mm | 竹 | 可 |
| 山下工芸『菜箸三膳セット』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格 |
天然素材で作られた菜箸三点セット | 大330、中300、小270mm | 竹 | - |
| 日々道具『菜ばしそろえ 無垢 2膳組』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格 |
竹製無塗装の菜箸 | 大330、小300mm | 国産天然竹 | - |
| ゆとりの空間『栗原はるみ 用途別菜箸3組セット』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格 |
炒め、煮物、盛り付けに便利な用途別菜箸セット | ネイビー・ブラウン/30.5cm 、 グリーン/23.5cm | 竹 | 不可 |
菜箸の選び方 料理や盛り付けに欠かせない
生活コラムニスト・ももせ いづみさんからのアドバイスをもとに、菜箸を選ぶときのポイントをご紹介します。
【1】長さをチェック!
【2】用途に合わせて素材を選ぶ
【3】いくつか用意しておくと便利
【4】豊富な機能に注目
上記のポイントをおさえることで、より具体的に自分に合う菜箸を選ぶことができます。
【1】長さをチェック!
一般的な菜箸の長さは30cmです。長めの菜箸には、32cmや38cmほどの長さのものが売られていますが、揚げものや炒めものには、長めの菜箸のほうが手が熱くならないのでおすすめです。
しかし、盛りつけには長すぎる菜箸は扱いにくくなりますので、少し短めのものが使いやすくなります。
竹製の菜箸には、長さが違うものがセットで売られているものもあり、調理により使い分けられるので便利です。
盛り付けなどの細かい作業は短いものがしやすい
短めサイズの菜箸は、盛り付けやお弁当におかずを詰めるのにぴったりです。
長さにして24~2cm程度が使いやすいでしょう。長い菜箸に比べ、短い菜箸はあまり売られていないので、長さの違う菜箸がセットになってる場合があるので、チェックしてみてください。
【2】用途に合わせて素材を選ぶ
菜箸には、主に「シリコン製」「ステンレス製」「竹製」「プラスチック製」があります。
それぞれの特徴をみていきましょう。
シリコン製|フライパンや鍋を傷つけにくい
シリコン製の菜箸は、フライパンや鍋を傷つけにくいことと、熱が伝わりにくいため、焦げつきにくいのが特徴です。
商品によっては、揚げ物に使えない場合や、火をつけた鍋やフライパンに入れたまま放置すると、溶けてしまうものもあります。購入する際に、耐熱温度を確認しましょう。
ステンレス製|焦げたり調味料の色移りの心配不要
ステンレス製の菜箸は、焦げたり調味料などの色移りの心配がありません。カビが生えないので、衛生的に使用でき、丈夫で長持ちするというメリットもあります。
ただし、重くて持ちにくくすべりやすいのがデメリット。
竹製|軽くて熱に強い定番の素材
竹製は、昔から定番でよく使われている菜箸です。軽くて熱に強いのが特徴。ただし、お手入れ次第ではカビが発生する可能性もあります。
また、焦げて折れやすくなってしまうというデメリットも。何本か用意しておくのがおすすめです。
プラスチック製|比較的安価で購入できる
ナイロンなどのプラスチック製の菜箸は、シリコンと同様にフライパンや鍋を傷つけにくいのがポイント。
プラスチックは熱に弱いイメージがありますが、ナイロン素材は耐熱性が高いので安心です。それでも耐熱性が気になる方には、菜箸の先端にシリコンがコーティングしてあるタイプがおすすめ。
また、比較的価格が安い商品が多いので、コストパフォーマンスに優れています。
【3】用途ごとにいくつか用意しておくと便利
ひとつの菜箸を多用途に使いまわすより、揚げもの用、調理用、盛りつけ用といくつかの菜箸を用意しておくと、格段に使い勝手がよくなります。
また調理中にはいくつかの作業を、平行しておこなうことが多いので、そのたびに菜箸を洗うよりも、複数の菜箸を使い分けるほうが手間がかかりません。
すぐ手に取れる場所に、使いやすく収納して使うようにしましょう。
【4】豊富な機能に注目
菜箸を使いながら、塩や砂糖などの調味料を足したり、味見をしたりと、調理中にはさまざまな作業があります。
菜箸の先端に小さなスプーンやフォークがついたものは、調理の流れを止めずにこうした作業ができるので便利です。
もし、菜箸の取り扱いがうまくできないという方には、トング型の菜箸もあります。
調理に使うトングよりも細めに作られているので、盛りつけに使うこともできて便利です。
>> 生活コラムニストからのワンポイントアドバイス
菜箸の選び方ひとつで調理がグッとらくに
ひとつの菜箸を調理から盛りつけまで、万能に使っているという方もいると思いますが、用途別に使い分けるほうが調理が格段にらくになります。
調理には熱に強く、衛生的に使えるものを。盛りつけには、こまかいものまできちんとつまめる、先端の細いものをぜひそろえて使い分けてみてください。
調理での普段使いには定期的に買い替えが利く手頃なものを使い、盛りつけ用に少しいいものをそろえておくという使い方もおすすめです。
菜箸おすすめ5選|ユーザーのイチオシ
ここでは、普段、菜箸を使っている人がおすすめする「買ってよかった商品」だけをご紹介します。商品の口コミはもちろん、コスパや使いやすさ、お手入れなど満足度の評価ポイントも聞いてみたので、各項目にも注目して商品選びの参考にしてください!
その他にもおすすめしたい商品があるよという方は、ぜひ記事の下部にある投稿フォームからご紹介をお願いします。

愛用者
菜箸の概念を変えてくれた
菜箸といえば竹! という先入観をもっていましたが、母にすすめられてこちらを購入。すると、シリコンならではの使用感に虜になりました。とにかく、とてもはさみやすいです! 手に感覚が伝わってくる感じで、どんなものでも軽くはさめます。(T.K.さん/女性/34歳/主婦)
※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格
| コスパ | ★★★☆☆ |
|---|---|
| 使いやすさ | ★★★★★ |
| お手入れ | ★★★★★ |
| 総合評価 | 4.3点 |
| コスパ | ★★★☆☆ |
|---|---|
| 使いやすさ | ★★★★★ |
| お手入れ | ★★★★★ |
| 総合評価 | 4.3点 |

愛用者
木製の菜箸とおさらば
いつも木製の菜箸を使ったりシリコンのものを使ったりしていましたが、まず木製のものはすべて捨ててしまいました。かなり使いやすいし、衛生的な感じがしています。焦げ付かないため、調理中に鍋の中に箸を放置しても問題ありませんでした。あと、中が空洞になっているためか、かなり軽いです。(N.M.さん/女性/37歳/主婦)
※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格
| コスパ | ★★★★★ |
|---|---|
| 使いやすさ | ★★★★★ |
| お手入れ | ★★★★★ |
| 総合評価 | 5.0点 |
| コスパ | ★★★★★ |
|---|---|
| 使いやすさ | ★★★★★ |
| お手入れ | ★★★★★ |
| 総合評価 | 5.0点 |

愛用者
3種セットで使い分けに便利
竹製の菜箸は、清潔感があって使いやすく大好きです。このタイプは長さが違うものが3つ入っていて、ひもも付いているので、行方不明になりにくく便利に使えます。また、軽いのでお料理をしていても手が疲れません。食洗機に入れていますが、曲がることもなくとても扱いやすいです。(S.Y.さん/女性/53歳/主婦)
※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格
| コスパ | ★★★★★ |
|---|---|
| 使いやすさ | ★★★★★ |
| お手入れ | ★★★★★ |
| 総合評価 | 5.0点 |
| コスパ | ★★★★★ |
|---|---|
| 使いやすさ | ★★★★★ |
| お手入れ | ★★★★★ |
| 総合評価 | 5.0点 |

愛用者
安くてシンプル
安かったので購入しましたが、シンプルで使いやすいので重宝しています。いろいろ工夫されている菜箸もよいですが、結局このオーソドックスなタイプが一番好きだなと最近気付きました。おそらくリピートすると思います。(Y.T.さん/女性/37歳/フリーランス)
※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格
| コスパ | ★★★★★ |
|---|---|
| 使いやすさ | ★★★★★ |
| お手入れ | ★★★★☆ |
| 総合評価 | 4.7点 |
| コスパ | ★★★★★ |
|---|---|
| 使いやすさ | ★★★★★ |
| お手入れ | ★★★★☆ |
| 総合評価 | 4.7点 |

愛用者
猫好きにはたまらない
持ち手部分にある猫の肉球柄がとっても可愛いです。一般的な菜箸よりは短めで、普通のお箸よりは長めです。先はエンボス加工で滑りにくく扱いやすいので、盛り付けや食卓で使う取り分け用などによく使っています。(Y.T.さん/女性/43歳/主婦)
※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格
| コスパ | ★★★☆☆ |
|---|---|
| 使いやすさ | ★★★★☆ |
| お手入れ | ★★★★☆ |
| 総合評価 | 3.7点 |
| コスパ | ★★★☆☆ |
|---|---|
| 使いやすさ | ★★★★☆ |
| お手入れ | ★★★★☆ |
| 総合評価 | 3.7点 |
菜箸おすすめ7選|シリコン製
シリコン製の菜箸を紹介します。鍋やフライパンを傷つけにくいのが魅力。なかには、お鍋に入れっぱなしにしていると溶けてしまうものもあるので、耐熱温度はよく確認しましょう。
高温調理にも対応した耐久性のある菜箸
揚げ物や炒め物をした際に菜箸の先端が焦げついてしまった…という経験をしている方は多いはず。調理時のフライパンの温度は200℃超えてしまいますが、この菜箸は耐熱温度が220℃なので、焦げつきにくく長く愛用できるのが特徴。
とりわけや盛り付けがしやすい24cmの長さがある菜箸なので、揚げ物や炒め物調理をした後に盛り付けもそのままらくらく!
忙しい朝や時間のない夕飯作りに大活躍すること間違いなしです。
※各社通販サイトの 2024年11月20日時点 での税込価格
| サイズ | 24cm |
|---|---|
| 素材 | SPS樹脂 |
| 食洗機対応 | ‐ |
| サイズ | 24cm |
|---|---|
| 素材 | SPS樹脂 |
| 食洗機対応 | ‐ |

調理中の置き場に便利な菜箸キーパーつき
滑りにくく、調理器具もキズつけにくいシリコン製の菜箸です。こちらの菜箸の一番の特徴は、菜箸の先を浮かせて置くことができる菜箸キーパーがついていること。調理中の菜箸を直接カウンターの上に置いても、先端が浮くので汚れることなく使うことができます。
この菜箸キーパーは位置を変えることができるので、お鍋の縁に立てかけておくのにも便利です。キーパーを取り外した状態でも、太めの角型なので転がる心配もなく、耐熱温度も220度まで対応と使い勝手のよい菜箸です。
※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格
| サイズ | 長さ300mm |
|---|---|
| 素材 | シリコン、ナイロン |
| 食洗機対応 | - |
| サイズ | 長さ300mm |
|---|---|
| 素材 | シリコン、ナイロン |
| 食洗機対応 | - |

こまかい作業に便利な短めのシリコン製菜箸
お弁当の盛りつけなど、こまかい作業に長すぎる菜箸は使いにくいものです。
こちらは25cmと、やや短めの菜箸になります。ハンドル部分は樹脂製で、先端がシリコン製なので小さな食材も滑らずつかむことができます。先端にシリコンが配されている菜箸は、ステンレスのボウルでの和えものの際に、カチャカチャと音を立てないのも特徴です。
卵焼きを作ったり、食材を和える作業も多いお弁当作りにぴったりです。
※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格
| サイズ | 幅6×高さ6×長さ250mm |
|---|---|
| 素材 | ナイロン、シリコンゴム、ステンレス |
| 食洗機対応 | 可 |
| サイズ | 幅6×高さ6×長さ250mm |
|---|---|
| 素材 | ナイロン、シリコンゴム、ステンレス |
| 食洗機対応 | 可 |
耐熱温度220度。デイリーで活躍する菜箸
耐久性が高く、コスパが良好なことで定評のあるニトリのシリコーン菜箸。溝が付いているから、食材をつかみやすく、箸先が丸いから、鍋・フライパンの表面を傷付けにくいのが特徴です。なめらかに仕上げた四角形状だから、持ちやすくて転がりにくいですよ。
使った後は食洗器で洗えるので、お手入れもラクラク。シンプルなデザインでどんなキッチンにも似合いそうですね。
※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格
| サイズ | 幅0.7×奥行0.7×高さ30cm |
|---|---|
| 素材 | シリコーン |
| 食洗機対応 | 可 |
| サイズ | 幅0.7×奥行0.7×高さ30cm |
|---|---|
| 素材 | シリコーン |
| 食洗機対応 | 可 |
味見ができるナイロン製菜箸
すくって味見、刺して味見ができちゃうモノトーン柄のオシャレな菜箸。ナイロンとシリコンゴムでできているので、軽量で先端がシリコーン製だからつかみやすいのが特徴。
さらに、スプーンには2.5ml(cc)、5ml(cc)の目盛り付き。これ一つで、料理、味付け、混ぜるなど色々できてとっても便利です。
一見ちょっと変わった菜箸ながら、さすがの機能性。これは試す価値がありそうですね。
※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格
| サイズ | 35 x 4.9 x 2 cm |
|---|---|
| 素材 | ナイロン(グラスファイバー含有)(先端表面シリコーンゴム) |
| 食洗機対応 | 可 |
| サイズ | 35 x 4.9 x 2 cm |
|---|---|
| 素材 | ナイロン(グラスファイバー含有)(先端表面シリコーンゴム) |
| 食洗機対応 | 可 |
先端がシリコンで出来た菜箸
先端がシリコンで出来た菜箸で、料理の盛り付け、とりわけ等に用いるのに最適な箸です。高耐熱シリコンですので、揚げ物などの調理中に使用しても問題ありません。
またとても便利なのが、ホルダーがついている点。箸を束ねて保管でき、使用中は箸置きにもなるのでとても使い勝手がいいです。箸の形は円形でなく四角形を採用しているので、平台においても転がりにくくて安心です。
※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格
| サイズ | 幅20×高さ10×長さ290mm |
|---|---|
| 素材 | ナイロン、シリコン、ステンレス鋼 |
| 食洗機対応 | 可 |
| サイズ | 幅20×高さ10×長さ290mm |
|---|---|
| 素材 | ナイロン、シリコン、ステンレス鋼 |
| 食洗機対応 | 可 |
食洗器OK!耐熱性にすぐれたシリコーン菜箸
◆フライパンなどのふっ素コーティングにやさしいシリコーン製
◆食洗器で洗えて、毎日使えるアイテム
◆高い耐熱性だから、デイリー料理の強い味方
◆先端がシリコーンですべりにくくつかみやすい
※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格
| サイズ | 0.7×0.7×30cm |
|---|---|
| 素材 | シリコーン |
| 食洗機対応 | 〇 |
| サイズ | 0.7×0.7×30cm |
|---|---|
| 素材 | シリコーン |
| 食洗機対応 | 〇 |
菜箸おすすめ4選|ステンレス製
つづいて、ステンレス製の菜箸です。ステンレス製は、耐久性に優れていて長く愛用できるのが特徴。他の材質に比べると、重い商品が多いので持ちやすいものを選びましょう。

揚げもの用におすすめ! 長めの菜箸
先端に滑り止めのついた、ステンレス製の菜箸です。
持ち手部分は六角の樹脂製でつかみやすく、長さが33cmと長めなので、揚げものにぴったり。高温での使用を続けても劣化が少ないので、揚げもの用としてひとつ持っておくととても便利です。デザインもとてもスタイリッシュなので、菜箸にもこだわりたいという方にもおすすめ。
テフロン加工のフライパンは、ステンレス製の先端でキズをつけてしまうこともありますので、調理により使い分けるようにしましょう。
※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格
| サイズ | 幅18×高さ9×長さ330mm |
|---|---|
| 素材 | 18-8ステンレススチール、ポリアセタール樹脂 |
| 食洗機対応 | - |
| サイズ | 幅18×高さ9×長さ330mm |
|---|---|
| 素材 | 18-8ステンレススチール、ポリアセタール樹脂 |
| 食洗機対応 | - |
ステンレス製でとても軽い菜箸
ステンレス製のとても軽い菜箸です。ステンレス製のため、食べ物がついたりしても汚れが浸透することや、変色する心配もなく、水洗いで簡単に洗えるので使い勝手も抜群。
箸の先端に滑り止め加工が施されているため、食材などが滑ることなく取り分けるのがラクです。カビたりすることもないので、長い期間愛用することができます。
※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格
| サイズ | 長さ300mm |
|---|---|
| 素材 | 18-8ステンレス |
| 食洗機対応 | - |
| サイズ | 長さ300mm |
|---|---|
| 素材 | 18-8ステンレス |
| 食洗機対応 | - |
ステンレス製で溝が付いた長い菜箸
ステンレスのシルバーの色味がスタイリッシュさを醸し出す菜箸。ステンレスは錆びにくく、長く愛用できます。もちろん、色移りによる変色や、ニオイの吸収もありません。
箸先に付いた溝が滑り止めとなっているため、食材を持ち上げやすい仕組みになっています。36センチの長い柄によって、熱いものを挟んだときも、食べ物と手の距離がじゅうぶんにあるので、揚げ物をする際の油の飛び跳ねなどを気にせずに利用できます。
※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格
| サイズ | 長さ360mm |
|---|---|
| 素材 | ステンレス |
| 食洗機対応 | - |
| サイズ | 長さ360mm |
|---|---|
| 素材 | ステンレス |
| 食洗機対応 | - |
ステンレスの先端に最高級の黒檀を使用した菜箸
箸の素材としては最高級素材の黒檀(コクタン)を使用した菜箸です。黒檀は材質が非常に硬い上、見た目は美しい光沢があり、スタイリッシュな雰囲気のある高級菜箸に仕上がります。
大事なお客様がお見えになった際の、おもてなしの機会などに映える菜箸と言えます。本焼ステンレスにより先まで非常に丈夫なつくりになっており、汚れも取れやすく、錆にくく耐久性に優れています。
※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格
| サイズ | 長さ305mm |
|---|---|
| 素材 | 黒檀、ステンレス |
| 食洗機対応 | ‐ |
| サイズ | 長さ305mm |
|---|---|
| 素材 | 黒檀、ステンレス |
| 食洗機対応 | ‐ |
菜箸おすすめ5選|プラスチック製
つづいて、プラスチック製の菜箸です。軽くて扱いやすいものが多く、盛り付けに適しています。

調理が楽しくなるカラフルな菜箸
歯ブラシの柄に使われている、樹脂を使用したカラフルな菜箸です。
角型で転がりにくく、先端に滑り止めもついています。軽くて使いまわしがよいので、日常使いにぴったりです。食洗機で洗えますが、耐熱温度は160度と低めなので揚げものなどには向いていません。
7色そろっているので、用途に合わせて色をわけて使ってみるのもいいでしょう。
※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格
| サイズ | 長さ300mm |
|---|---|
| 素材 | 飽和ポリエステル樹脂 |
| 食洗機対応 | 可 |
| サイズ | 長さ300mm |
|---|---|
| 素材 | 飽和ポリエステル樹脂 |
| 食洗機対応 | 可 |
トングと一体化した耐熱性の菜箸
菜箸のように使えるナイロン製のトングです。調理用のトングに比べ、細身でこまかいものまでつまめるのが特徴。大きなものをつまんだときに、先端部分がねじれてしまうのを防ぐために、ストッパーがついています。
フライパンから炒めものをお皿に移すときや、お鍋から煮ものを盛りつけるときなど、お箸よりもかんたんに使えるので便利です。
ひとつあると調理だけでなく、食卓でサラダなどの取り分けにも使えて重宝します。
※各社通販サイトの 2024年11月20日時点 での税込価格
| サイズ | 幅69×高さ90×長さ280mm |
|---|---|
| 素材 | ナイロン(グラスファイバー含む) |
| 食洗機対応 | 〇 |
| サイズ | 幅69×高さ90×長さ280mm |
|---|---|
| 素材 | ナイロン(グラスファイバー含む) |
| 食洗機対応 | 〇 |
料理が楽しくなる!かわいいデザイン
持ち手にさりげなくネコの足跡のイラストが描かれていてキュートな菜箸。箸先はエンボス加工がほどこされているので、すべりにくく、食材をしっかりと掴むことができます。
その他にもNyammyシリーズから、包丁やピーラー、計量カップなども展開されているので、たくさん揃えたくなりますね。
※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格
| サイズ | 長さ270mm |
|---|---|
| 素材 | ポリスチレン |
| 食洗機対応 | 可 |
| サイズ | 長さ270mm |
|---|---|
| 素材 | ポリスチレン |
| 食洗機対応 | 可 |
2種類の素材を使い軽量性と実用性がアップ
持ち手部分がプラスチック、箸の先端部はステンレスでできた菜箸。長さは30センチで、調理した食材や盛り付け用の菜箸としてぴったりです。
先端はステンレスで加工されているので、熱い食品を挟んでも焦げたりせず、かつ錆びたり折れたりすることもないので、とても耐久性に優れた菜箸です。
柄の部分は角型のプラスチック素材で持ちやすく、扱いやすくなってます。スタイリッシュな見た目ながらも利用できる幅が多いので、毎日の料理に重宝します。
※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格
| サイズ | 幅10×高さ10×長さ300mm |
|---|---|
| 素材 | ステンレススチール、ポリプロピレン |
| 食洗機対応 | - |
| サイズ | 幅10×高さ10×長さ300mm |
|---|---|
| 素材 | ステンレススチール、ポリプロピレン |
| 食洗機対応 | - |
◆片手でロック&解除でき、狭いスペースにも置ける
◆つかむ、ほぐす、盛り付けるなど繊細な作業に便利
◆先端が浮くので汚さずに置ける
◆ギザギザの先端でしっかりつかめて女性やお年寄りにも使いやすい
※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格
| サイズ | 28 x 1.9 x 2.3 cm |
|---|---|
| 素材 | ステンレス |
| 食洗機対応 | 〇 |
| サイズ | 28 x 1.9 x 2.3 cm |
|---|---|
| 素材 | ステンレス |
| 食洗機対応 | 〇 |
菜箸おすすめ5選|竹製
つづいて、定番で扱いやすく手軽な竹製の菜箸です。

用途によって使い分けられる3本セット
ベーシックな竹製の菜箸が、33cm、30cm、27cmと3本セットになっています。33cmは揚げものや炒めものに、30cmは煮ものや和えものなどの調理に、一番短い27cmは盛りつけにちょうど使いやすい長さです。
こうしたベーシックな竹製の菜箸のなかには、2本が紐でつながっているタイプもありますが、紐はないほうが使いやすいので、こちらのタイプのようにシンプルな構造がおすすめ。
竹製の菜箸は焦げや汚れで寿命はあまり長くないので、一定期間で交換して清潔に使い続けることが大切です。
※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格
| サイズ | 大330、中300、小270mm |
|---|---|
| 素材 | 竹 |
| 食洗機対応 | 不可 |
| サイズ | 大330、中300、小270mm |
|---|---|
| 素材 | 竹 |
| 食洗機対応 | 不可 |

料亭などでも使われる「取り分け箸」
こちらの菜箸は、先端まで長さがそろうのが特徴です。一般的な菜箸は先端が丸まっていて、こまかい素材はつかみにくいものが多いのですが、こちらは米粒ひとつまでつまむことができます。
こまかい盛りつけの作業にぴったりで、料亭などでもこうした細い先端の竹製の菜箸がよく使われているようです。四角い形状なのでお皿の上に乗せても転がりにくく、調理だけでなく食卓での取り分け用の箸として使ってもおしゃれでしょう。
ただし繊細な作りなので、揚げものや炒めものなどに多用するのには不向きです。
※各社通販サイトの 2024年11月20日時点 での税込価格
| サイズ | 長さ320mm |
|---|---|
| 素材 | 竹 |
| 食洗機対応 | 可 |
| サイズ | 長さ320mm |
|---|---|
| 素材 | 竹 |
| 食洗機対応 | 可 |
天然素材で作られた菜箸三点セット
中国産の天然の竹で作られた菜箸です。大中小それぞれの3点セット。2本が常にペアになるよう持ち手側の先端にはひもが付いており、片方の箸を探し回る手間が減ります。加えて、カンタンに台所の壁の取っ手などにぶら下げて保管することも出来ます。
軽くて丈夫、かつ値段もお手頃。昔ながらのデザインで使う人を選ばない商品です。
※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格
| サイズ | 大330、中300、小270mm |
|---|---|
| 素材 | 竹 |
| 食洗機対応 | - |
| サイズ | 大330、中300、小270mm |
|---|---|
| 素材 | 竹 |
| 食洗機対応 | - |
竹製無塗装の菜箸
秋から冬の間だけに伐採した硬く締まった竹を用いて作られた菜箸。無塗装のため、竹そのものの質感が残っており、竹本来の味わいをじっくり楽しめます。
軽くて持ちやすく、さらには先端が適度に尖っていて、小さな食品なども挟みやすくデザインされています。また持ち柄側の先端部が少し削られたデザインになっているのがアクセントで、他の箸と混ざった場合も見つけやすいという特徴もあります。
※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格
| サイズ | 大330、小300mm |
|---|---|
| 素材 | 国産天然竹 |
| 食洗機対応 | - |
| サイズ | 大330、小300mm |
|---|---|
| 素材 | 国産天然竹 |
| 食洗機対応 | - |
炒め、煮物、盛り付けに便利な用途別菜箸セット
◆炒めものに使いやすいブラウンは先を四角く
◆煮ものに使いやすいネイビーには滑り止め付き
◆グリーンは先を細くし、扱いやすいよう長さは少し短め
◆抗菌にすぐれた竹製で持ちやすい
※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格
| サイズ | ネイビー・ブラウン/30.5cm 、 グリーン/23.5cm |
|---|---|
| 素材 | 竹 |
| 食洗機対応 | 不可 |
| サイズ | ネイビー・ブラウン/30.5cm 、 グリーン/23.5cm |
|---|---|
| 素材 | 竹 |
| 食洗機対応 | 不可 |
おすすめ商品の比較一覧表
| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | サイズ | 素材 | 食洗機対応 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜みらい『ののじ 驚異の耐熱220℃ 朝の菜箸24』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月20日時点 での税込価格 |
高温調理にも対応した耐久性のある菜箸 | 24cm | SPS樹脂 | ‐ |
| 山崎実業『tower(タワー) シリコーン菜箸』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格 |
調理中の置き場に便利な菜箸キーパーつき | 長さ300mm | シリコン、ナイロン | - |
| マーナ『シリコーン菜ばし ミニ chocotto(チョコット)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格 |
こまかい作業に便利な短めのシリコン製菜箸 | 幅6×高さ6×長さ250mm | ナイロン、シリコンゴム、ステンレス | 可 |
| NITORI(ニトリ)『シリコーン菜箸』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格 |
耐熱温度220度。デイリーで活躍する菜箸 | 幅0.7×奥行0.7×高さ30cm | シリコーン | 可 |
| パール金属『味見チョップスティック』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格 |
味見ができるナイロン製菜箸 | 35 x 4.9 x 2 cm | ナイロン(グラスファイバー含有)(先端表面シリコーンゴム) | 可 |
| OXO(オクソー)『シリコン 菜箸 ブラック』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格 |
先端がシリコンで出来た菜箸 | 幅20×高さ10×長さ290mm | ナイロン、シリコン、ステンレス鋼 | 可 |
| THERMOS(サーモス)『シリコーン菜箸』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格 |
食洗器OK!耐熱性にすぐれたシリコーン菜箸 | 0.7×0.7×30cm | シリコーン | 〇 |
| 貝印『セレクト100 ステンレス菜箸 33cm』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格 |
揚げもの用におすすめ! 長めの菜箸 | 幅18×高さ9×長さ330mm | 18-8ステンレススチール、ポリアセタール樹脂 | - |
| 杉安製作所『ステンレス 菜箸』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格 |
ステンレス製でとても軽い菜箸 | 長さ300mm | 18-8ステンレス | - |
| BESTOYARD『菜箸 料理用』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格 |
ステンレス製で溝が付いた長い菜箸 | 長さ360mm | ステンレス | - |
| 金口製作所『本焼ステンレス黒檀柄盛箸』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格 |
ステンレスの先端に最高級の黒檀を使用した菜箸 | 長さ305mm | 黒檀、ステンレス | ‐ |
| 福井クラフト『クッキングスティックス』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格 |
調理が楽しくなるカラフルな菜箸 | 長さ300mm | 飽和ポリエステル樹脂 | 可 |
| サンクラフト『ナイロン菜ばしトング L』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月20日時点 での税込価格 |
トングと一体化した耐熱性の菜箸 | 幅69×高さ90×長さ280mm | ナイロン(グラスファイバー含む) | 〇 |
| 貝印『ねこの菜箸 Nyammy(ニャミー)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格 |
料理が楽しくなる!かわいいデザイン | 長さ270mm | ポリスチレン | 可 |
| 貝印『プラスチックハンドル菜箸』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格 |
2種類の素材を使い軽量性と実用性がアップ | 幅10×高さ10×長さ300mm | ステンレススチール、ポリプロピレン | - |
| オークス『ワンクリック菜箸』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格 |
28 x 1.9 x 2.3 cm | ステンレス | 〇 | |
| パール金属『Easy Cooking 竹製料理用箸セット』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格 |
用途によって使い分けられる3本セット | 大330、中300、小270mm | 竹 | 不可 |
| 小関工芸『すべらない竹のお箸』 |
|
※各社通販サイトの 2024年11月20日時点 での税込価格 |
料亭などでも使われる「取り分け箸」 | 長さ320mm | 竹 | 可 |
| 山下工芸『菜箸三膳セット』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格 |
天然素材で作られた菜箸三点セット | 大330、中300、小270mm | 竹 | - |
| 日々道具『菜ばしそろえ 無垢 2膳組』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格 |
竹製無塗装の菜箸 | 大330、小300mm | 国産天然竹 | - |
| ゆとりの空間『栗原はるみ 用途別菜箸3組セット』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格 |
炒め、煮物、盛り付けに便利な用途別菜箸セット | ネイビー・ブラウン/30.5cm 、 グリーン/23.5cm | 竹 | 不可 |
通販サイトの人気ランキング 菜箸の売れ筋をチェック
Amazon、楽天市場での菜箸の売れ筋ランキングも参考にしてみてください。
※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。
菜箸の収納アイデアを紹介! キッチンの整理整頓に!
菜箸はほかのキッチンツールと一緒にしまうとごちゃごちゃして取りづらいうえ、食事用の箸と比べると長くて意外と収納に困りがち。菜箸を頻繁に使う人は、菜箸立てに立てて収納すると使うときも片付けるときも便利です。
引き出しに収納するときは、100円ショップや無印良品などの整理ボックスを複数活用してみるときれいに整理整頓できます。菜箸用、おたま・フライ返し用というようにケースを分ければすぐに取り出せますよ。
あると便利な「菜箸置き」もチェック あわせて使いたい!
調理中、菜箸の置き場所に困りますよね。あとで使うからまだシンクには置きたくない、調理台に箸先をつけたくない……そんなときに便利なのが「菜箸置き」です。調理中の菜箸の定位置が決まることで、効率よく調理できますよ。
菜箸置きとしておすすめの商品をご紹介します!
便利な調理グッズで料理を楽しく! 【関連記事】
使い勝手の良い菜箸を選ぼう いかがでしたか?
菜箸の選び方とおすすめの商品を紹介しました。
最近では、セリアやダイソーなどの100均や3coins(スリーコインズ)でも手軽に購入できるアイテムとなりましたが、普段使いするものはある程度コストパフォーマンスの良いもので、物持ちのよいものを選ぶと良いでしょう。
また実際に使ってみると、例えば人によってはステンレス製は少し重いなどと使い勝手の良い点、悪い点を感じるかもしれません。ぜひ使ってみて、自分に合うものを選びましょう。
おすすめ商品・口コミの投稿はこちら
※メーカーや販売店の方は、ページ下部の「お問い合わせはこちら」から商品情報をお送りください。
ユーザーのおすすめ商品や口コミ情報は、マイナビおすすめナビを閲覧したユーザー、マイナビニュース会員、外部パートナー企業と契約する一般ユーザーからの投稿をもとにしています。
◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。