| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | サイズ | 材質 | 重量 | 容量 | 形状 | 機能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THERMOS(サーモス)『シリコーンクッキングスプーン』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
マルチに使える黒のスプーン型 | 幅7.5×奥行27×高さ3.5cm | シリコーン | 100g | - | スプーン型 | フック穴 |
| 無印良品 『シリコーン調理スプーン 長さ約26cm』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
適度にしなりながらも強度を持ったおたま | 約26cm | シリコーンゴム、ステンレス鋼、ナイロン | 約110g | - | スプーン型 | フック穴 |
| マーナ『トライアングリップ シリコーンお玉』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
持つことを重視した三角構造と熱に強いシリコーン製 | 約幅8.7×奥行27.4×高さ7cm | ナイロン・シリコーンゴム | 76g | - | お椀型 | フック穴 |
| ティファール『インジニオ プロフレックス レードル』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月19日時点 での税込価格 |
においや色移りが心配ないシリコーンおたま | 幅7×奥行10×高さ33cm | シリコーンゴム、ナイロン(芯) | - | - | お椀型 | フック穴 |
| ストウブ『シリコン スープレードル』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
キッチンをよりおしゃれな空間にするおたま | 幅9.8×奥行31cm | 本体:シリコン、ナイロン ハンドル:アカシア | - | - | お椀型 | フック穴 |
| 山崎実業『シリコーンお玉 タワー』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
鍋肌にフィット! 平らな形状できれいにすくえる | (約)幅80×奥行60×高さ255mm | シリコン | 60g | 15cc、30cc | 計量機能付きおたま | フック穴、計量機能付き、先端が浮く加工 |
| KEYUCA(ケユカ)『バタリニー ナイロンレードルII』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
つなぎ目のない衛生的なおたま | 幅9.5×奥行28.7×高さ8cm | ナイロン、グラスファイバー | - | - | お椀型 | フック穴 |
| サンクラフト『ナイロンミニお玉』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
フライパンを傷つける心配のないナイロン製おたま | 約 幅6.5×奥行23×高さ5cm | グラスファイバー強化ナイロン | 約32g | 約30cc(5cc/15cc) | - | フック穴・計量機能付き |
| マーナ『きれいにすくえる計量お玉』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
計量できる機能性のあるおたま | 約 幅8.4×奥行28×高さ8cm | ナイロン | - | 小さじ:5ml、大さじ:15ml、1/4カップ:50ml | 計量機能付きおたま | フック穴・計量機能付き |
| OXO(オクソー)『ナイロン目盛り付きレードル』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
使い勝手のよさが人気の秘訣! | 約 幅9×奥行31×高さ9cm | ヘッド:ナイロン、グリップ:サントプレーン、ポリプロピレン | 約73g | - | 計量機能付きおたま | フック穴・計量機能付き |
| 貝印『汁も切れるスプーン』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月19日時点 での税込価格 |
すくいやすさと汁切り機能が便利なおたま | 幅8.5×奥行25×高さ6.5cm | ナイロン | 57g | - | - | フック穴・穴杓子(一部) |
| パール金属『Action Tool 自立お玉(目盛り付き)(ブラック)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
自立するおたま! 料理の邪魔になりにくい | 幅90×奥行80×高さ275mm | ナイロン | 約50g | 20ml、40ml、60ml | 計量機能付きおたま | フック穴、計量機能付き |
| 柳宗理『レードルM』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
シャープなフォルムがモダンな印象を与える | 幅8.6×奥行29.8cm | 18-8ステンレス | 130g | - | 楕円状 | フック穴 |
| パール金属『ニュートレンド お玉(大)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
シンプルだからこそ長く使える | 幅8.1×奥行28×高さ7.5cm | ステンレス鋼、ポリプロピレン | 95g | - | お椀型 | フック穴 |
| ヨシカワ『生活のかたち 目盛り付き 横口おたま』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
軽量+横口で料理がかんたん&スムーズ | 幅10.5×奥行25cm | 18-8ステンレス | 95g | 5cc、15cc、30cc | 横口おたま | フック穴・横口・計量機能付き |
| 霜鳥製作所『パッカーウッド 穴明お玉』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
木製の持ち手がオシャレな穴あきおたま | 幅8.4×奥行29cm | ハンドル部:強化木、金属部:ステンレススチール、樹脂部:66ナイロン樹脂 | 59g | - | 穴杓子おたま | - |
| 下村企販『ママクック ステンレスお玉 3点セット』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月19日時点 での税込価格 |
お得な大中小のおたま3点セット | プチ:約 7.1×6×21.8cm、中:約 8.2×6.7×25.6cm、大:約 9.2×7.9×30cm | 18-8ステンレス | プチ:約60g、中:約80g、大:約100g | プチ:約30ml、中:約50ml、大:約75ml | 楕円状 | フック穴 |
| ZWILLING(ツヴィリング)『ツインキュイジーヌ 横口レードル(39754-000)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
美しいデザインと機能性の高さがひかる | 奥行26cm | ハンドル:ABS樹脂、ステンレス 金属:ステンレス | - | 約100g | - | フック穴・横口 |
| ナガオ『燕三条 プロフェッショナル おたま』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月19日時点 での税込価格 |
プロ仕様で本格的!燕三条で作られた日本製 | 幅8×奥行29.5cm | 18-8ステンレス | 120g | - | - | フックタイプ |
| ル・クルーゼ『メープル・ウッド・スプーン(L)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
木のぬくもりを感じる木製おたま | 幅8×奥行28.5×高さ3cm | 天然木 | 90g | 80ml | - | フック穴 |
| みよし漆器本舗『天然木製 欅の木 お玉 大』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
天然木のぬくもりと漆塗りのツヤが美しい逸品 | 長さ約28cm 直径約9cm | 天然木製(欅の木) | - | 約80cc | お椀型 | 食品衛生法規格基準適合品 |
| 高桑金属『日々道具 ホーロー 穴あきレードル』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
おしゃれな見た目で使い勝手もよい | 幅80×奥行85×H高さ260mm | 本体:ステンレス(ホーロー仕上げ) | 91g | - | お椀型 | フック穴・穴杓子 |
| 若林工業『中華お玉』 |
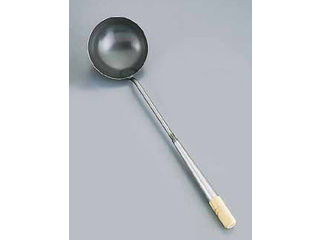
|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
気分は達人! プロ仕様の中華おたま | 幅11.4×奥行43.5×高さ7.6cm | 鉄(クリア塗装)、天然木 | 約270g | - | 中華おたま | - |
| 和平フレイズ『中華お玉(小)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
チャーハンづくりはおまかせ! 本格的な中華おたま | 幅105×奥行86×高さ441mm | 本体:鉄 木部分:自然木 | 約240g | - | 中華おたま | - |
おたまは料理に欠かせないキッチンツール! 一人暮らしにも!
カレーやスープ、味噌汁などの汁ものを混ぜたり、よそう際に欠かせない「おたま」。おしゃれなダイニングやカフェで見かける「レードル」との違いはどこでしょうか? 実は、おたまもレードルも同じもの。どちらも便利なキッチンアイテムです。
おたまの正式名称は「お玉杓子(おたまじゃくし)」。滋賀の多賀神社の縁起物「お多賀杓子」が由来ともいわれています。調理の際ひとつあると便利なおたまについて詳しくみていきましょう。
おたまの選び方 材質や形状、お手入れのしやすさや機能に注目!
ここからは、おたまの選び方を詳しく解説していきます!ポイントは下記のとおり。
【1】材質
【2】形状
【3】洗いやすい一体型
【4】便利な機能
上記のポイントをおさえることで、より欲しい商品をみつけることができます。ぜひ最後までチェックしてみてくださいね。
【1】おたまの材質を確認する
おたまの材質はシリコン、ナイロン、ステンレス、木製、ホーローなどさまざまなものがあり、それぞれ材質によって特徴があります。
「シリコン製」は柔らかくて使いやすい
柔らかくて軽く、あつかいやすいのがシリコン素材おたまの特徴です。熱に強いイメージのあるシリコン素材ですが、商品によっては耐熱温度がそれほどではないものもあります。購入する前に耐熱温度を確認しておきましょう。
おたま自体が変形しやすいので、鍋の底にのこった食材やスープもすくい取りやすいメリットもあります。
「ナイロン製」は鍋を傷つけにくい
適度なかたさがあるナイロン製のおたまは、軽くて丈夫なのが特徴です。柔らかくフライパンや鍋にあたっても傷がつきにくいので、フッ素コーティングしているお鍋やフライパンに使うのにぴったり。食洗機で洗える商品もあるので、お手入れもかんたんです。
ほかの素材より熱に弱いので、耐熱温度は購入前にチェックしておくようにしましょう。
「ステンレス製」は耐久性があり熱にも強い
ステンレス製おたまは、熱に強く丈夫なのが特徴です。シンプルなつくりのものが多く、見た目がおしゃれなのでキッチンの見える場所にかけておきたくなるような商品も。熱を気にせず思い切り使えるのですが、素材のかたさから当たると鍋やフライパンを傷つけてしまう場合もあります。
また、熱が伝わりやすいので持ち手が熱くて持てない場合も。気になる人は、持ち手に違う素材が使われているステンレスおたまを選ぶようにしましょう。
「木製」はあたたかみがありおしゃれ
自然素材である木製のおたま。おしゃれで飾っておきたくなるような見た目なので、ホームパーティなどでも積極的に使いたくなるキッチンツールです。ただし、お鍋などに入れたまま火にかけてしまうと焦げてしまうことも。
また、しっかり乾かさないとカビが生えるなど、お手入れに少し手間がかかるデメリットがあります。
「ホーロー製」は見た目も機能性も抜群!
ホーロー製のおたまは、ニオイ移りなどが気になる料理を盛り付けるのに便利です。見た目もかわいく、使い勝手もよいのが魅力。ホーロー鍋を使っている方は、おたまのデザインもあわせるのもおしゃれでおすすめです。
【2】おたまの形状で選ぶ
おたまの形状にもさまざまなものがあり、計量付きなど便利な機能がついたものまであります。ここでは、おたまの形状や機能について紹介します。
「お椀型」は初心者でも使いやすい
一般的なおたまの形状です。深さがあるものが多く、大きな具材の料理やスープなどをしっかりすくってくれます。料理初心者の方でも使いやすく、一本持っておくと便利です。
「楕円型」は具材や汁をすくいやすい
お椀型のおたまより横に広がり、鍋につく面積が広いタイプ。具材や汁をすくいやすいので、スープやカレー、味噌汁などの料理に使うと便利です。
「横口おたま」はゆで野菜や肉じゃがに便利
おたまの横がすぼまっていて、煮汁を細い口の容器に移したり、煮汁を残して具材だけをすくったりすることができます。肉じゃがやゆで野菜のときにあると便利な一本です。
ほかにも、お出汁を取るときにも重宝します。ちょっと味見をして味がうすいときには、横口おたまの口から少しずつ微調整しながら調味料を追加できるので便利です。ただし、横口おたまは利き手があるので、左利きの人は左利き用の横口おたまを買うように注意してください。
「中華おたま」は炒飯などの中華料理を作るときに
スープや具材をすくうのはもちろん、中華鍋などで食材を炒めるときにも使えるおたま。本格的な中華料理を作りたいときに便利です。鉄製のものが多く販売されていますが、ステンレス製のものもあります。
「穴杓子おたま」は具材だけを取り出しやすい
よりかんたんに具材だけを取り出したい場合は、穴杓子おたまが便利です。おたまに穴が開いているので、煮汁を残して確実に具材だけを取り出せます。煮物や揚げ物などで一本あると便利なおたまです。
そのほか、泡立て器やマッシャーの代用品として利用することも可能。ただし、鉄製やステンレスでしっかりとした強度がないと、すぐに曲がってしまうので注意が必要です。
【3】洗いやすさ重視なら継ぎ目のない「一体型」がおすすめ
おたまには、持ち手と頭の部分が異なる素材などでつくられた継ぎ目があるタイプと一体型になったタイプがあります。継ぎ目部分はどうしても洗いにくく、汚れがたまってしまうことがあります。衛生面を気にするのであれば、継ぎ目のないおたまを選ぶとよいでしょう。
継ぎ目部分がはずれてしまうこともないので、長く使い続けることができます。
【4】便利な機能があるかもチェック!
おたまは、シンプルにみえていろんな便利機能が備わっています。ここでは、いくつかの便利機能を紹介します。
「目盛りつき」の計量おたまは手早く調理できる
完成したカレーやシチューなどを盛り付けるためにおたまを使う場合もあれば、煮込み料理などで調理中におたまを使うこともあります。調理中におたまを使う方の場合、計量機能の付いたおたまが便利です。
たとえば、醤油や清酒などを加える際、おたまで計量ができれば、わざわざ計量スプーンや計量カップなどを用意する必要がありません。計量スプーンや計量カップなどを使わずに済むので、洗い物も減らすことができます。
食卓でも活躍する「自立するおたま」は調理にも
鍋をみんなで囲むとき、おたまをどこに置くかで悩むことがあるかもしれません。自立してくれるタイプのおたまなら、おたまを置く小皿などを用意する必要がありません。おたま自体を支える必要がないので、調理中にちょっとおたまを置いておくのにも便利です。
「フック穴」や「スタンド」があると収納に便利
おたまをフックにかけて収納している人や、スタンドに立てて収納している人は多いかもしれません。商品によってはフックにかけられる穴がないタイプもあります。おたまを購入するときには、自分がどのように収納するのか、フックに収納するのであれば穴はあいているのかもチェックしておきましょう。
おたまの収納に便利なキッチンツールスタンドをご紹介します。こちらもチェックしてみてください。
おたまと一緒に使う調理器具との相性を考えて選ぼう >>>料理研究家からのワンポイントアドバイス
ご自身が使用している鍋やフライパンのサイズ、材質などに合わせておたまを選ぶようにしてください。
たとえば、ステンレスのおたまの場合、フッ素加工の鍋などに使用すると、傷が付いてしまう可能性があります。ご家庭にある鍋が小さい場合、あまりにも大きすぎるおたまだと使い勝手がよくありません。反対に大きな鍋の場合、おたまが小さすぎると何度もすくわないといけなくなってしまいます。
いろいろなおたまを比較し、お気に入りのおたまを見つけてみてくださいね。
おたまの人気ブランド・メーカー おたま選びで迷っている方は参考にしてみよう!
おたま選びに悩んだら、人気のブランドやメーカーで選ぶのもひとつの方法です。ここからは、おたまを販売する人気ブランド・メーカーをいくつか紹介していきます!
無印良品|シンプルだから使いやすい
日用品からインテリア、食品まで幅広いアイテムをそろえる無印良品。おたまだけでも、ステンレス製、木製、シリコン製などさまざまな材質で展開しています。なかでもシリコン製は、軽くて丈夫、衛生的に使えることからも幅広い客層に支持されているアイテムです。
シンプルな見た目ですが、炒める・混ぜる・すくう・よそうとさまざまな場面で活躍してくれます。
マーナ(MARNA) |使いやすい機能が充実
マーナは、創業140年を超える家庭用品のメーカーです。200度までの温度に耐えるナイロン製のおたまは、フッ素樹脂加工のフライパンなどをキズつけることもなく、つなぎ目もないことから衛生的に使えるのが特徴です。
シリコン製のおたまもあり、柔軟なシリコン素材が鍋のそこや側面をスクレーパーのようにフィットして、無駄なく食品をすくい取ることができるのがポイントです。用途に合わせたおたまが選べます。
柳宗理|洗練されたデザインと心地良い使用感
柳宗理は、日本のインダストリアルデザイナーとして幅広いデザインを手がけた人物です。柳宗理のおたまは、機能美とシンプルさを追求したステンレス製。腐食に強く、耐久性もあるので、長く使えることを考えるとコスパも高い製品といえます。
つなぎ目がなく、シンプルなフォルムのため、洗いやすく衛生的に使えます。食洗機の使用も可能です。和食の調理・盛り付けに適した形をしています。
【ユーザーが選んだ】イチオシ5選 みんなに人気のおたまはこれ
ここからは、おたまを愛用しているユーザーがイチオシの商品を紹介。5点満点で「コスパ」「使いやすさ」「お手入れ」を評価してもらいました。イチオシのポイント、おすすめする理由や口コミもぜひ参考にしてください!
その他にもおすすめしたい商品があるよという方は、ぜひ記事の下部にある投稿フォームからご紹介をお願いします。

愛用者
使い勝手よし!
炒め物をする時やポテトサラダなど、食材を混ぜる時に活用しています。フライパンからお皿に取り分ける時もそのまま使えるし、先が平たくなっていて、フライパンや鍋にくっつきやすい物でも簡単にすくえるすぐれもの!
ただ一つ難点をいうと、持ち手のところに金属部分があり、フライパンに乗せたままにしておくと熱くなってしまいます。(N.O.さん/女性/42歳/主婦)
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| コスパ | ★★★★☆ |
|---|---|
| 使いやすさ | ★★★★☆ |
| お手入れ | ★★★★☆ |
| 総合評価 | 4.0点 |
| コスパ | ★★★★☆ |
|---|---|
| 使いやすさ | ★★★★☆ |
| お手入れ | ★★★★☆ |
| 総合評価 | 4.0点 |

愛用者
食洗機に入れられてお手入れかんたん
シリコン製などいろいろ使ってきましたが、私の場合は結局これに戻ってきました。持ち手が熱くならず安心して持っていられますし、ステンレスのお玉部分もすくいやすく作られていて、ストレスを感じません。
食洗機にぽんっと入れて洗えるのもポイントが高いですね。日本製がこの値段で手に入るのもうれしいです。(S.Y.さん/女性/53歳/主婦)
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| コスパ | ★★★★★ |
|---|---|
| 使いやすさ | ★★★★★ |
| お手入れ | ★★★★★ |
| 総合評価 | 5.0点 |
| コスパ | ★★★★★ |
|---|---|
| 使いやすさ | ★★★★★ |
| お手入れ | ★★★★★ |
| 総合評価 | 5.0点 |

愛用者
どんな料理にも使いやすい
色んな料理に使えて重宝しています。和食、洋食、中華どの料理にも適応し、料理の幅が広がるのもうれしい点です。また、シリコンで持ちやすいため小さい子供と一緒に料理を楽しめます。
コスパ最強なため、複数持っていてもお財布にやさしい商品です。(Y.N.さん/女性/43歳/事務職)
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| コスパ | ★★★★★ |
|---|---|
| 使いやすさ | ★★★★★ |
| お手入れ | ★★★★☆ |
| 総合評価 | 4.7点 |
| コスパ | ★★★★★ |
|---|---|
| 使いやすさ | ★★★★★ |
| お手入れ | ★★★★☆ |
| 総合評価 | 4.7点 |

愛用者
これ発明した人すごい
この商品の凄い点が、プラスチックとシリコンのハイブリット型ということ。先端だけがシリコンになっていて、最後にカレーをこそいで取る時には残すことなくすくってくれます。
また、小さいSサイズの割にしっかりと深さがあり、食洗器で洗えるのもおすすめです。 (N.M.さん/女性/37歳/主婦)
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| コスパ | ★★★★★ |
|---|---|
| 使いやすさ | ★★★★★ |
| お手入れ | ★★★★☆ |
| 総合評価 | 4.7点 |
| コスパ | ★★★★★ |
|---|---|
| 使いやすさ | ★★★★★ |
| お手入れ | ★★★★☆ |
| 総合評価 | 4.7点 |

愛用者
汁も切れるのが意外に便利
おたまはたくさんあると思いますし、拘りがある人も多くないかもしれませんが、ぜひこのおたまを一度使ってみてほしいです!
私も汁をきるタイミングはあるのだろうかと思って使い始めましたが、意外と機会がありとても便利です。こういうちょっとした工夫が好きな人はぜひ使ってみてください。(F.T.さん/男性/36歳/会社員)
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| コスパ | ★★★★☆ |
|---|---|
| 使いやすさ | ★★★★★ |
| お手入れ | ★★★★★ |
| 総合評価 | 4.7点 |
| コスパ | ★★★★☆ |
|---|---|
| 使いやすさ | ★★★★★ |
| お手入れ | ★★★★★ |
| 総合評価 | 4.7点 |
おたまのおすすめ6選|シリコン製
ポタージュや煮込み料理など、鍋底に残った食材もかき集めてキレイにすくい取れるシリコン製のおたまをご紹介します。
マルチに使える黒のスプーン型
シリコーン製の大きなスプーン型おたまです。フッ素コーティングされた鍋やフライパンをキズつけずに使えます。先端は平らになっているので、鍋底にフィット。カレーなど鍋に残りがちな食品もきれいに取れます。
また、炒めものをする際やおかずの取り分けにも活躍します。食洗器で使えるのも忙しい人にはうれしいポイントですね。
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| サイズ | 幅7.5×奥行27×高さ3.5cm |
|---|---|
| 材質 | シリコーン |
| 重量 | 100g |
| 容量 | - |
| 形状 | スプーン型 |
| 機能 | フック穴 |
| サイズ | 幅7.5×奥行27×高さ3.5cm |
|---|---|
| 材質 | シリコーン |
| 重量 | 100g |
| 容量 | - |
| 形状 | スプーン型 |
| 機能 | フック穴 |
適度にしなりながらも強度を持ったおたま
多くのアイテムを取り扱う無印良品の「シリコーン調理スプーン」は、大きなカレースプーンのようなおたまです。材料の混ぜ合わせから炒める・焼くといった加熱調理、取りわけまで幅広く使えます。
スプーンの内部にはステンレス鋼の芯材が入っていますが、へりの部分にはステンレスが入っていないので適度なしなり具合で、鍋に残ったものをしっかりと掻きだすこともできます。
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| サイズ | 約26cm |
|---|---|
| 材質 | シリコーンゴム、ステンレス鋼、ナイロン |
| 重量 | 約110g |
| 容量 | - |
| 形状 | スプーン型 |
| 機能 | フック穴 |
| サイズ | 約26cm |
|---|---|
| 材質 | シリコーンゴム、ステンレス鋼、ナイロン |
| 重量 | 約110g |
| 容量 | - |
| 形状 | スプーン型 |
| 機能 | フック穴 |
持つことを重視した三角構造と熱に強いシリコーン製
具だくさんのスープをかき混ぜる際など、おたまをしっかりと握るシーンは意外と多いもの。そんなときでも、握りやすいように柄の部分が「三角構造」になったおたまです。
おたまの形状はお椀型の変形バージョンで、少し角度がついているので、汁ものなどを注ぎやすいつくりになっています。シリコーン製などで鍋底や鍋肌をキズつけにくいのも特徴です。
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| サイズ | 約幅8.7×奥行27.4×高さ7cm |
|---|---|
| 材質 | ナイロン・シリコーンゴム |
| 重量 | 76g |
| 容量 | - |
| 形状 | お椀型 |
| 機能 | フック穴 |
| サイズ | 約幅8.7×奥行27.4×高さ7cm |
|---|---|
| 材質 | ナイロン・シリコーンゴム |
| 重量 | 76g |
| 容量 | - |
| 形状 | お椀型 |
| 機能 | フック穴 |

においや色移りが心配ないシリコーンおたま
鍋やフライパンを傷付けにくく、初心者の方でも扱いやすいおたま。フッ素加工の鍋やフライパンといっしょに使用できるおたまを探している方におすすめです。
シリコーンタイプと言えば、色移りが気になるところ。こちらはプラチナシリコーン製なので、においも付きにくいタイプです。
カレーなど香辛料を使用する料理に使っても、においや色移りが気になりにくいです。見た目も鮮やかな赤色なので、キッチンを華やかに演出してくれます。
※各社通販サイトの 2024年11月19日時点 での税込価格
| サイズ | 幅7×奥行10×高さ33cm |
|---|---|
| 材質 | シリコーンゴム、ナイロン(芯) |
| 重量 | - |
| 容量 | - |
| 形状 | お椀型 |
| 機能 | フック穴 |
| サイズ | 幅7×奥行10×高さ33cm |
|---|---|
| 材質 | シリコーンゴム、ナイロン(芯) |
| 重量 | - |
| 容量 | - |
| 形状 | お椀型 |
| 機能 | フック穴 |
キッチンをよりおしゃれな空間にするおたま
ストウブのおしゃれなおたま。ハンドル部分はアカシアの天然木を使用していて、手に馴染みやすくなっています。本体はシリコン素材で、鍋やフライパンを傷つける心配がありません。
ワンポイントのロゴもおしゃれ。同シリーズの鍋と使うとより料理が楽しくなりますよ。家ではもちろんキャンプやバーベキューにも活躍するアイテム。プレゼントにもおすすめです。
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| サイズ | 幅9.8×奥行31cm |
|---|---|
| 材質 | 本体:シリコン、ナイロン ハンドル:アカシア |
| 重量 | - |
| 容量 | - |
| 形状 | お椀型 |
| 機能 | フック穴 |
| サイズ | 幅9.8×奥行31cm |
|---|---|
| 材質 | 本体:シリコン、ナイロン ハンドル:アカシア |
| 重量 | - |
| 容量 | - |
| 形状 | お椀型 |
| 機能 | フック穴 |
鍋肌にフィット! 平らな形状できれいにすくえる
先端が平らな形状なので、カレーのルーなども残らない鍋肌に沿わせてすくえます。
シリコン製ならではの滑りにくく弾力性があるおたまで、鍋をキズつけません。調理台においても先端が浮く設定になっているから衛生的です。15ccと30ccが量れる目盛り付きで、洗い物を減らせます。
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| サイズ | (約)幅80×奥行60×高さ255mm |
|---|---|
| 材質 | シリコン |
| 重量 | 60g |
| 容量 | 15cc、30cc |
| 形状 | 計量機能付きおたま |
| 機能 | フック穴、計量機能付き、先端が浮く加工 |
| サイズ | (約)幅80×奥行60×高さ255mm |
|---|---|
| 材質 | シリコン |
| 重量 | 60g |
| 容量 | 15cc、30cc |
| 形状 | 計量機能付きおたま |
| 機能 | フック穴、計量機能付き、先端が浮く加工 |
おたまのおすすめ6選|ナイロン製
フッ素コーティングの鍋やフライパンでも使える、ナイロン製のおたまをご紹介します!
つなぎ目のない衛生的なおたま
「バタリニー ナイロンレードルII」は、オールナイロンのおたま。つなぎ目がなく、食品のカスなどが残ることもなく、衛生的に使えます。
ナイロン製で、フッ素加工や、金属の鍋のまわりや底をキズつけることがないのもうれしいポイントです。グラスファイバーも20%配合されており、炒めものや煮込み料理などの加熱調理にも活躍します。
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| サイズ | 幅9.5×奥行28.7×高さ8cm |
|---|---|
| 材質 | ナイロン、グラスファイバー |
| 重量 | - |
| 容量 | - |
| 形状 | お椀型 |
| 機能 | フック穴 |
| サイズ | 幅9.5×奥行28.7×高さ8cm |
|---|---|
| 材質 | ナイロン、グラスファイバー |
| 重量 | - |
| 容量 | - |
| 形状 | お椀型 |
| 機能 | フック穴 |

フライパンを傷つける心配のないナイロン製おたま
材質は強化ナイロンで、約32gと驚くほど軽量。ナイロン素材は鍋やフライパンを傷つける心配もありません。価格もリーズナブルなので、ひとり暮らしの方やカップルの方におすすめです。
継ぎ目のないオシャレなデザインで、汚れが落ちやすいのもポイント。これなら家事の負担も軽減できるはず。使いやすいミニサイズなので、収納にも便利です。
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| サイズ | 約 幅6.5×奥行23×高さ5cm |
|---|---|
| 材質 | グラスファイバー強化ナイロン |
| 重量 | 約32g |
| 容量 | 約30cc(5cc/15cc) |
| 形状 | - |
| 機能 | フック穴・計量機能付き |
| サイズ | 約 幅6.5×奥行23×高さ5cm |
|---|---|
| 材質 | グラスファイバー強化ナイロン |
| 重量 | 約32g |
| 容量 | 約30cc(5cc/15cc) |
| 形状 | - |
| 機能 | フック穴・計量機能付き |

計量できる機能性のあるおたま
こちらは小さじ1、大さじ1、1/4カップと計量できるおたま。
計量カップや計量スプーンの代わりに使えるおたまを探している方におすすめです。縁掛けの段差があり、お鍋などにおたまを入れて落ちてしまう心配もなく、調理をする方にとって使いやすいデザインになっています。
材質はナイロンで、食器洗い乾燥機も使用可能。カレーなどにより変色することもあるため、あまり入れっぱなしにしないほうが無難です。
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| サイズ | 約 幅8.4×奥行28×高さ8cm |
|---|---|
| 材質 | ナイロン |
| 重量 | - |
| 容量 | 小さじ:5ml、大さじ:15ml、1/4カップ:50ml |
| 形状 | 計量機能付きおたま |
| 機能 | フック穴・計量機能付き |
| サイズ | 約 幅8.4×奥行28×高さ8cm |
|---|---|
| 材質 | ナイロン |
| 重量 | - |
| 容量 | 小さじ:5ml、大さじ:15ml、1/4カップ:50ml |
| 形状 | 計量機能付きおたま |
| 機能 | フック穴・計量機能付き |

使い勝手のよさが人気の秘訣!
元々アメリカで発売されているモデルですが、日本向けに改良された商品。使い勝手のいいおたまを探している方におすすめです。
鉛筆のように持っても疲れにくく、やわらかい持ち心地。持ち手も握りやすく、滑りにくい設計になっています。目盛り付きなので計量カップや計量スプーンもいらず、一本は持っておくと便利です。出汁を作ったり、煮物などの料理を作ったりするのにも向いています。
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| サイズ | 約 幅9×奥行31×高さ9cm |
|---|---|
| 材質 | ヘッド:ナイロン、グリップ:サントプレーン、ポリプロピレン |
| 重量 | 約73g |
| 容量 | - |
| 形状 | 計量機能付きおたま |
| 機能 | フック穴・計量機能付き |
| サイズ | 約 幅9×奥行31×高さ9cm |
|---|---|
| 材質 | ヘッド:ナイロン、グリップ:サントプレーン、ポリプロピレン |
| 重量 | 約73g |
| 容量 | - |
| 形状 | 計量機能付きおたま |
| 機能 | フック穴・計量機能付き |
すくいやすさと汁切り機能が便利なおたま
持ちやすいハンドルと汁が切れる穴が便利なおたまです。食材を崩さずにすくいあげ、他の食材と分けられます。
底の部分は二重コーティングされているので鍋底に当たっても破損しにくく、柔らかい素材をつぶすことも可能です。アク取りにも使用できます。
※各社通販サイトの 2024年11月19日時点 での税込価格
| サイズ | 幅8.5×奥行25×高さ6.5cm |
|---|---|
| 材質 | ナイロン |
| 重量 | 57g |
| 容量 | - |
| 形状 | - |
| 機能 | フック穴・穴杓子(一部) |
| サイズ | 幅8.5×奥行25×高さ6.5cm |
|---|---|
| 材質 | ナイロン |
| 重量 | 57g |
| 容量 | - |
| 形状 | - |
| 機能 | フック穴・穴杓子(一部) |
自立するおたま! 料理の邪魔になりにくい
おたまが自立するので省スペースで使えます! 小皿に立たせておけばサッと手に取れますよ。
ナイロン製なので鍋やフライパンのコーティングをキズつけにくいのもポイント。20・40・60mlが計量できる目盛りつきです。食洗機で洗えてお手入れもラクラク!
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| サイズ | 幅90×奥行80×高さ275mm |
|---|---|
| 材質 | ナイロン |
| 重量 | 約50g |
| 容量 | 20ml、40ml、60ml |
| 形状 | 計量機能付きおたま |
| 機能 | フック穴、計量機能付き |
| サイズ | 幅90×奥行80×高さ275mm |
|---|---|
| 材質 | ナイロン |
| 重量 | 約50g |
| 容量 | 20ml、40ml、60ml |
| 形状 | 計量機能付きおたま |
| 機能 | フック穴、計量機能付き |
おたまのおすすめ7選|ステンレス製
熱に強く耐久性が高いので、長く使えるのが魅力のステンレス製おたまをご紹介します!

シャープなフォルムがモダンな印象を与える
世界的に有名な工業デザイナーである柳宗理氏のシリーズ。ステンレス素材のおたまで、水に強くてさびにくく、お手入れもかんたん。とても頑丈なので、長く愛用できるはず。
サイズはSとMがあり、1~2人用ならSサイズ、3~4人用ならMサイズが最適。普遍的なデザインなので、新生活のギフトなどにプレゼントしても喜ばれるでしょう。デザイン性の高いおたまを探している方におすすめです。
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| サイズ | 幅8.6×奥行29.8cm |
|---|---|
| 材質 | 18-8ステンレス |
| 重量 | 130g |
| 容量 | - |
| 形状 | 楕円状 |
| 機能 | フック穴 |
| サイズ | 幅8.6×奥行29.8cm |
|---|---|
| 材質 | 18-8ステンレス |
| 重量 | 130g |
| 容量 | - |
| 形状 | 楕円状 |
| 機能 | フック穴 |
シンプルだからこそ長く使える
ニュートレンドと言いながらも、どこか懐かしさも感じるフォルムのおたまです。金属部分は腐食に強く、耐熱性のあるステンレス。強度もあるので長く使い続けることができます。丸洗いでき、食洗機の使用も可能です。
柄の部分はポリプロピレン製で100℃の耐熱性を持つ素材だから、うっかり柄の部分を鍋に当ててしまっても、燃えたり溶けたりする心配はありません。
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| サイズ | 幅8.1×奥行28×高さ7.5cm |
|---|---|
| 材質 | ステンレス鋼、ポリプロピレン |
| 重量 | 95g |
| 容量 | - |
| 形状 | お椀型 |
| 機能 | フック穴 |
| サイズ | 幅8.1×奥行28×高さ7.5cm |
|---|---|
| 材質 | ステンレス鋼、ポリプロピレン |
| 重量 | 95g |
| 容量 | - |
| 形状 | お椀型 |
| 機能 | フック穴 |
軽量+横口で料理がかんたん&スムーズ
軽量目盛りと横口が一体になっているおたまです。料理中、少し味付けが足りないというときに、毎回計量スプーンを持ってきてはかるのも面倒に感じるもの。この商品であれば、調味料をはかりながら味を足せて便利です。
また、横口おたまなので、スープなどの汁物を口の小さい容器に注ぐのもこれ一本でかんたんにできます。
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| サイズ | 幅10.5×奥行25cm |
|---|---|
| 材質 | 18-8ステンレス |
| 重量 | 95g |
| 容量 | 5cc、15cc、30cc |
| 形状 | 横口おたま |
| 機能 | フック穴・横口・計量機能付き |
| サイズ | 幅10.5×奥行25cm |
|---|---|
| 材質 | 18-8ステンレス |
| 重量 | 95g |
| 容量 | 5cc、15cc、30cc |
| 形状 | 横口おたま |
| 機能 | フック穴・横口・計量機能付き |
木製の持ち手がオシャレな穴あきおたま
木製の持ち手が手にしっかりなじみ、使いやすい穴あきおたまです。作りがしっかりしているので、泡立て用としても安心して利用できます。
そのほか、マッシャー代わりに利用している方もいるようです。作りが弱いとすぐに変形してしまいますが、しっかりした作りのおたまだからできる使い方ですね。
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| サイズ | 幅8.4×奥行29cm |
|---|---|
| 材質 | ハンドル部:強化木、金属部:ステンレススチール、樹脂部:66ナイロン樹脂 |
| 重量 | 59g |
| 容量 | - |
| 形状 | 穴杓子おたま |
| 機能 | - |
| サイズ | 幅8.4×奥行29cm |
|---|---|
| 材質 | ハンドル部:強化木、金属部:ステンレススチール、樹脂部:66ナイロン樹脂 |
| 重量 | 59g |
| 容量 | - |
| 形状 | 穴杓子おたま |
| 機能 | - |
お得な大中小のおたま3点セット
お鍋の大きさに合わせておたまを使い分けたい方にピッタリのおたま3点セットです。ステンレス製でつなぎ目のない作りなので、カスが溜まらず衛生的に使えるのが特徴。絶妙なカーブになっている皿部は鍋底から側面にフィットして、最後まできれいにすくい取ることができます。
鍛冶の町として知られる新潟県燕三条地域で作られた商品で、その強度、品質は確かなものです。
※各社通販サイトの 2024年11月19日時点 での税込価格
| サイズ | プチ:約 7.1×6×21.8cm、中:約 8.2×6.7×25.6cm、大:約 9.2×7.9×30cm |
|---|---|
| 材質 | 18-8ステンレス |
| 重量 | プチ:約60g、中:約80g、大:約100g |
| 容量 | プチ:約30ml、中:約50ml、大:約75ml |
| 形状 | 楕円状 |
| 機能 | フック穴 |
| サイズ | プチ:約 7.1×6×21.8cm、中:約 8.2×6.7×25.6cm、大:約 9.2×7.9×30cm |
|---|---|
| 材質 | 18-8ステンレス |
| 重量 | プチ:約60g、中:約80g、大:約100g |
| 容量 | プチ:約30ml、中:約50ml、大:約75ml |
| 形状 | 楕円状 |
| 機能 | フック穴 |
美しいデザインと機能性の高さがひかる
機能性の高さと美しいデザインで、キッチンを楽しくしてくれるツヴィリングのおたまです。ステンレスの輝きが、キッチンを高級感あふれる空間にしてくれます。
横に注ぎやすくなっていて、スープやソースを皿にこぼしにくい設計です。耐久性、耐熱性に優れているので長く使うことができます。
レードルシリーズはほかにも穴あきタイプや計量機能が付いたタイプなど、豊富にあるので目的別に買い揃えてみてはいかがでしょうか。
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| サイズ | 奥行26cm |
|---|---|
| 材質 | ハンドル:ABS樹脂、ステンレス 金属:ステンレス |
| 重量 | - |
| 容量 | 約100g |
| 形状 | - |
| 機能 | フック穴・横口 |
| サイズ | 奥行26cm |
|---|---|
| 材質 | ハンドル:ABS樹脂、ステンレス 金属:ステンレス |
| 重量 | - |
| 容量 | 約100g |
| 形状 | - |
| 機能 | フック穴・横口 |
プロ仕様で本格的!燕三条で作られた日本製
高品質なステンレスでつくられたおたまです。つなぎ目がなく、菌の繁殖を抑えて衛生的。持ち手部分の幅が太く、手にフィットするので、長時間使用しても疲れにくい構造です。
新潟県の燕三条で作られている日本製で、プロの現場でも使われています。丁寧に磨かれたステンレスは美しい輝きを放ち、キッチンをより特別な空間にしてくれます。使いやすさと扱いやすさを考えて作られたおたまです。食器洗浄機にも対応しているので手入れも楽でおすすめ。プレゼントとしても喜ばれるアイテムです。
※各社通販サイトの 2024年11月19日時点 での税込価格
| サイズ | 幅8×奥行29.5cm |
|---|---|
| 材質 | 18-8ステンレス |
| 重量 | 120g |
| 容量 | - |
| 形状 | - |
| 機能 | フックタイプ |
| サイズ | 幅8×奥行29.5cm |
|---|---|
| 材質 | 18-8ステンレス |
| 重量 | 120g |
| 容量 | - |
| 形状 | - |
| 機能 | フックタイプ |
おたまのおすすめ2選|木製
木ならではの温かみのあるデザインが魅力的な木製おたまのおすすめ商品をご紹介します。

木のぬくもりを感じる木製おたま
木製のおたまを探している方におすすめ。フッ素加工された鍋に使っても傷が付きにくく、木べらのように使えるすぐれものです。丸みのあるフォルムで、鍋の底に合わせたように作られています。スープやシチュー、煮物やピラフなどにも使いやすいです。
ル・クルーゼの鍋を愛用している方なら、キッチンアイテムもル・クルーゼに合わせてみてはいかがでしょうか。見た目もオシャレなので、キッチンにレイアウトするのにも向いています。
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| サイズ | 幅8×奥行28.5×高さ3cm |
|---|---|
| 材質 | 天然木 |
| 重量 | 90g |
| 容量 | 80ml |
| 形状 | - |
| 機能 | フック穴 |
| サイズ | 幅8×奥行28.5×高さ3cm |
|---|---|
| 材質 | 天然木 |
| 重量 | 90g |
| 容量 | 80ml |
| 形状 | - |
| 機能 | フック穴 |
天然木のぬくもりと漆塗りのツヤが美しい逸品
天然の欅の木を使用♪ 使いこむほどに手になじむ+風合いがプラスされています。
木製だから鍋やフライパンをキズつけずに使用できますね。金属が擦れる音が苦手な人にもぴったりです。食品衛生法&食品添加物などの規格に適合している製品だから安心して使えます。
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| サイズ | 長さ約28cm 直径約9cm |
|---|---|
| 材質 | 天然木製(欅の木) |
| 重量 | - |
| 容量 | 約80cc |
| 形状 | お椀型 |
| 機能 | 食品衛生法規格基準適合品 |
| サイズ | 長さ約28cm 直径約9cm |
|---|---|
| 材質 | 天然木製(欅の木) |
| 重量 | - |
| 容量 | 約80cc |
| 形状 | お椀型 |
| 機能 | 食品衛生法規格基準適合品 |
おたまのおすすめ3選|ホーロー製・鉄製
酸に強くニオイ移りしにくいホーロー製のおたま、本格的な炒飯作りに活躍する鉄製の中華おたまをご紹介します。
おしゃれな見た目で使い勝手もよい
新潟県燕市にあるメーカーから発売されているホーロー製のおたま。ホーロー製の鍋との相性がよく、鍋と一緒に使うのに向いています。
ホワイトのあたたかい色合いがかわいく、キッチンにレイアウトするだけでも料理が楽しくなるはず。お椀型なのでカレーやシチューなどを盛り付けるのにぴったりです。
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| サイズ | 幅80×奥行85×H高さ260mm |
|---|---|
| 材質 | 本体:ステンレス(ホーロー仕上げ) |
| 重量 | 91g |
| 容量 | - |
| 形状 | お椀型 |
| 機能 | フック穴・穴杓子 |
| サイズ | 幅80×奥行85×H高さ260mm |
|---|---|
| 材質 | 本体:ステンレス(ホーロー仕上げ) |
| 重量 | 91g |
| 容量 | - |
| 形状 | お椀型 |
| 機能 | フック穴・穴杓子 |
気分は達人! プロ仕様の中華おたま
新潟県燕市で製造されている日本製おたまです。木製の持ち手がしっかりと手になじみ、料理をするのが苦になりません。
鉄製のおたまなのでテフロン(フッ素)加工のフライパンには傷がつきやすく注意が必要ですが、中華鍋であれば思う存分、その品質を感じることができるでしょう。思わず豪快にチャーハンを作りたくなる、そんなおたまです。
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| サイズ | 幅11.4×奥行43.5×高さ7.6cm |
|---|---|
| 材質 | 鉄(クリア塗装)、天然木 |
| 重量 | 約270g |
| 容量 | - |
| 形状 | 中華おたま |
| 機能 | - |
| サイズ | 幅11.4×奥行43.5×高さ7.6cm |
|---|---|
| 材質 | 鉄(クリア塗装)、天然木 |
| 重量 | 約270g |
| 容量 | - |
| 形状 | 中華おたま |
| 機能 | - |
チャーハンづくりはおまかせ! 本格的な中華おたま
本格的な中華料理をつくるのにぴったりな鉄製の中華おたま。おたまの鉄部分にはサビにくい黒皮銅板を使用しています。
柄が長くて火元から距離があるので、調理中に熱さを感じにくく安心です。「適度に重さがあって使いやすい!」と高評価の口コミが多数あがっています。
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| サイズ | 幅105×奥行86×高さ441mm |
|---|---|
| 材質 | 本体:鉄 木部分:自然木 |
| 重量 | 約240g |
| 容量 | - |
| 形状 | 中華おたま |
| 機能 | - |
| サイズ | 幅105×奥行86×高さ441mm |
|---|---|
| 材質 | 本体:鉄 木部分:自然木 |
| 重量 | 約240g |
| 容量 | - |
| 形状 | 中華おたま |
| 機能 | - |
「おたま」のおすすめ商品の比較一覧表
| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | サイズ | 材質 | 重量 | 容量 | 形状 | 機能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THERMOS(サーモス)『シリコーンクッキングスプーン』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
マルチに使える黒のスプーン型 | 幅7.5×奥行27×高さ3.5cm | シリコーン | 100g | - | スプーン型 | フック穴 |
| 無印良品 『シリコーン調理スプーン 長さ約26cm』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
適度にしなりながらも強度を持ったおたま | 約26cm | シリコーンゴム、ステンレス鋼、ナイロン | 約110g | - | スプーン型 | フック穴 |
| マーナ『トライアングリップ シリコーンお玉』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
持つことを重視した三角構造と熱に強いシリコーン製 | 約幅8.7×奥行27.4×高さ7cm | ナイロン・シリコーンゴム | 76g | - | お椀型 | フック穴 |
| ティファール『インジニオ プロフレックス レードル』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月19日時点 での税込価格 |
においや色移りが心配ないシリコーンおたま | 幅7×奥行10×高さ33cm | シリコーンゴム、ナイロン(芯) | - | - | お椀型 | フック穴 |
| ストウブ『シリコン スープレードル』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
キッチンをよりおしゃれな空間にするおたま | 幅9.8×奥行31cm | 本体:シリコン、ナイロン ハンドル:アカシア | - | - | お椀型 | フック穴 |
| 山崎実業『シリコーンお玉 タワー』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
鍋肌にフィット! 平らな形状できれいにすくえる | (約)幅80×奥行60×高さ255mm | シリコン | 60g | 15cc、30cc | 計量機能付きおたま | フック穴、計量機能付き、先端が浮く加工 |
| KEYUCA(ケユカ)『バタリニー ナイロンレードルII』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
つなぎ目のない衛生的なおたま | 幅9.5×奥行28.7×高さ8cm | ナイロン、グラスファイバー | - | - | お椀型 | フック穴 |
| サンクラフト『ナイロンミニお玉』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
フライパンを傷つける心配のないナイロン製おたま | 約 幅6.5×奥行23×高さ5cm | グラスファイバー強化ナイロン | 約32g | 約30cc(5cc/15cc) | - | フック穴・計量機能付き |
| マーナ『きれいにすくえる計量お玉』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
計量できる機能性のあるおたま | 約 幅8.4×奥行28×高さ8cm | ナイロン | - | 小さじ:5ml、大さじ:15ml、1/4カップ:50ml | 計量機能付きおたま | フック穴・計量機能付き |
| OXO(オクソー)『ナイロン目盛り付きレードル』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
使い勝手のよさが人気の秘訣! | 約 幅9×奥行31×高さ9cm | ヘッド:ナイロン、グリップ:サントプレーン、ポリプロピレン | 約73g | - | 計量機能付きおたま | フック穴・計量機能付き |
| 貝印『汁も切れるスプーン』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月19日時点 での税込価格 |
すくいやすさと汁切り機能が便利なおたま | 幅8.5×奥行25×高さ6.5cm | ナイロン | 57g | - | - | フック穴・穴杓子(一部) |
| パール金属『Action Tool 自立お玉(目盛り付き)(ブラック)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
自立するおたま! 料理の邪魔になりにくい | 幅90×奥行80×高さ275mm | ナイロン | 約50g | 20ml、40ml、60ml | 計量機能付きおたま | フック穴、計量機能付き |
| 柳宗理『レードルM』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
シャープなフォルムがモダンな印象を与える | 幅8.6×奥行29.8cm | 18-8ステンレス | 130g | - | 楕円状 | フック穴 |
| パール金属『ニュートレンド お玉(大)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
シンプルだからこそ長く使える | 幅8.1×奥行28×高さ7.5cm | ステンレス鋼、ポリプロピレン | 95g | - | お椀型 | フック穴 |
| ヨシカワ『生活のかたち 目盛り付き 横口おたま』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
軽量+横口で料理がかんたん&スムーズ | 幅10.5×奥行25cm | 18-8ステンレス | 95g | 5cc、15cc、30cc | 横口おたま | フック穴・横口・計量機能付き |
| 霜鳥製作所『パッカーウッド 穴明お玉』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
木製の持ち手がオシャレな穴あきおたま | 幅8.4×奥行29cm | ハンドル部:強化木、金属部:ステンレススチール、樹脂部:66ナイロン樹脂 | 59g | - | 穴杓子おたま | - |
| 下村企販『ママクック ステンレスお玉 3点セット』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月19日時点 での税込価格 |
お得な大中小のおたま3点セット | プチ:約 7.1×6×21.8cm、中:約 8.2×6.7×25.6cm、大:約 9.2×7.9×30cm | 18-8ステンレス | プチ:約60g、中:約80g、大:約100g | プチ:約30ml、中:約50ml、大:約75ml | 楕円状 | フック穴 |
| ZWILLING(ツヴィリング)『ツインキュイジーヌ 横口レードル(39754-000)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
美しいデザインと機能性の高さがひかる | 奥行26cm | ハンドル:ABS樹脂、ステンレス 金属:ステンレス | - | 約100g | - | フック穴・横口 |
| ナガオ『燕三条 プロフェッショナル おたま』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月19日時点 での税込価格 |
プロ仕様で本格的!燕三条で作られた日本製 | 幅8×奥行29.5cm | 18-8ステンレス | 120g | - | - | フックタイプ |
| ル・クルーゼ『メープル・ウッド・スプーン(L)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
木のぬくもりを感じる木製おたま | 幅8×奥行28.5×高さ3cm | 天然木 | 90g | 80ml | - | フック穴 |
| みよし漆器本舗『天然木製 欅の木 お玉 大』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
天然木のぬくもりと漆塗りのツヤが美しい逸品 | 長さ約28cm 直径約9cm | 天然木製(欅の木) | - | 約80cc | お椀型 | 食品衛生法規格基準適合品 |
| 高桑金属『日々道具 ホーロー 穴あきレードル』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
おしゃれな見た目で使い勝手もよい | 幅80×奥行85×H高さ260mm | 本体:ステンレス(ホーロー仕上げ) | 91g | - | お椀型 | フック穴・穴杓子 |
| 若林工業『中華お玉』 |
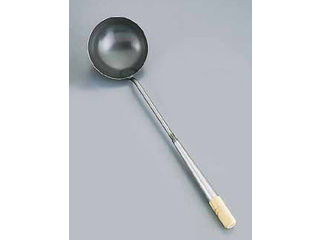
|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
気分は達人! プロ仕様の中華おたま | 幅11.4×奥行43.5×高さ7.6cm | 鉄(クリア塗装)、天然木 | 約270g | - | 中華おたま | - |
| 和平フレイズ『中華お玉(小)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
チャーハンづくりはおまかせ! 本格的な中華おたま | 幅105×奥行86×高さ441mm | 本体:鉄 木部分:自然木 | 約240g | - | 中華おたま | - |
通販サイトの最新人気ランキングを参考にする おたまの売れ筋をチェック
Amazon、楽天市場でのおたまの売れ筋ランキングも参考にしてみてください。
※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。
使い勝手の良いおたまをどんどん使おう! いかがでしたか?
ここまで、調理の際には欠かせないおたまの選び方と厳選した商品をご紹介してきました。
おたまには「おたまといえば……」というスタンダードなタイプから、軽量ができたり、汁切りができたりと、さまざまな機能を持ったものがあります。またすくう、混ぜるといった作業だけではなく、取りわけたり、炒めたりできるおたまもありました。
この記事を参考にして自分の調理スタイルにあったものを長く使って、食生活をもっと豊かにしてください。
おすすめ商品・口コミの投稿はこちら
※メーカーや販売店の方は、ページ下部の「お問い合わせはこちら」から商品情報をお送りください。
ユーザーのおすすめ商品や口コミ情報は、マイナビおすすめナビを閲覧したユーザー、マイナビニュース会員、外部パートナー企業と契約する一般ユーザーからの投稿をもとにしています。
◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。














































































































