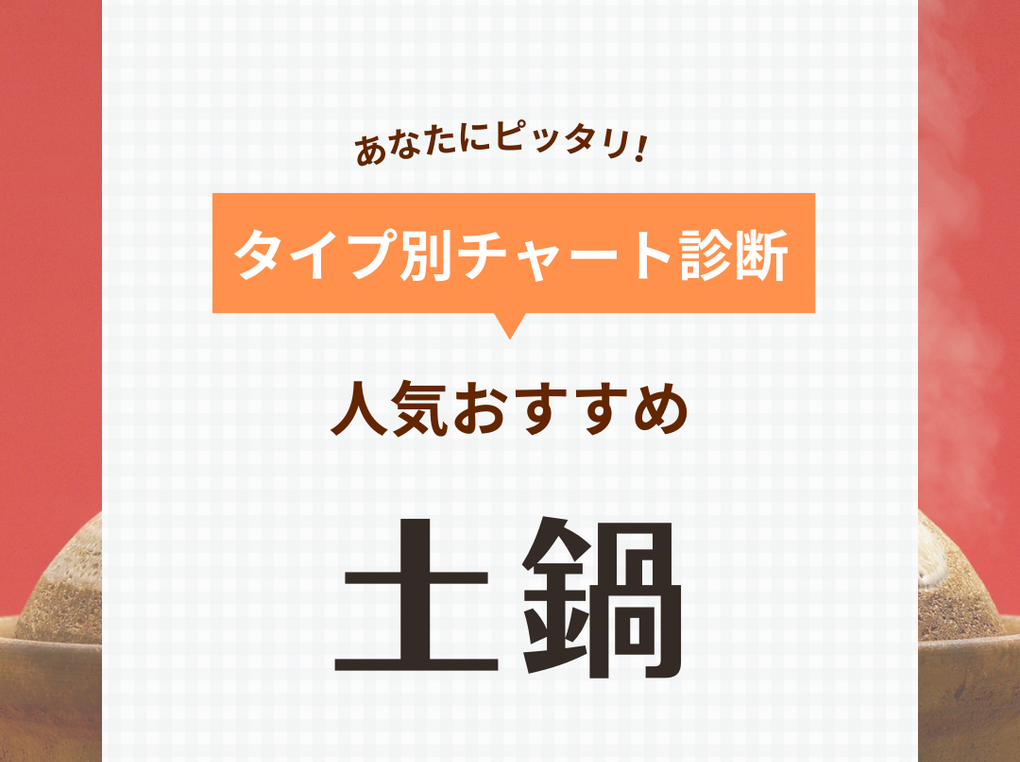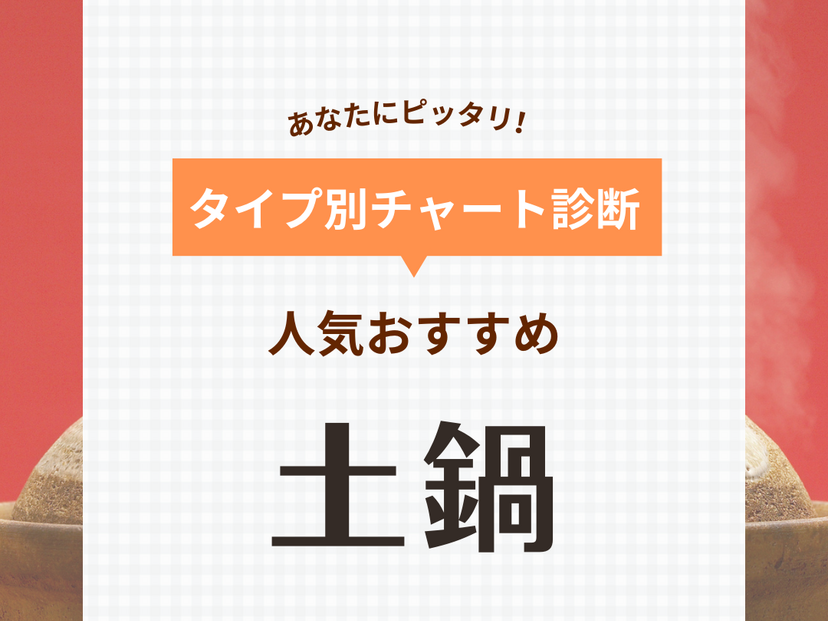| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 対応人数 | 材質 | カラー | IH対応 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ishigaki(イシガキ)『収納性がいい土鍋 5号』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
鍋キューブ1つにぴったりサイズ | 1人 | 本体:耐熱陶器 蓋:陶器 | ホワイト | × |
| Kakusee(カクセー)『土鍋 5号』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
土鍋のイメージを覆す軽さが扱いやすい | 1人 | 本体:耐熱陶器、蓋:陶器 | 黒・紺 | × |
| 青雲商店『韓国土鍋 トッペギ 4号』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月19日時点 での税込価格 |
韓国料理を見た目でも楽しみたい人に | 1~2人 | 陶器 | ブルー | - |
| 三鈴陶器『萬古焼 ごはん鍋』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
一人暮らしにも最適! 萬古焼で炊き上げる極上ご飯 | 2~3人 | 耐熱陶器 | こげ茶 | × |
| 三鈴陶器『トクサ 絵付け土鍋』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
ファミリー向けの大型土鍋 | 2〜3人 | 耐熱陶器 | トクサ柄 | × |
| 陶器のふる里『10種のフタから選べる土鍋』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
フタの組み合わせ自由!好みの土鍋がきっと見つかる | 2人 | 蓋:磁器、本体:超耐熱陶器 | 10種 | - |
| 長谷園『伊賀土鍋 利休十草』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
確かな品質の日本製土鍋 | 3~5人 | 陶器 | 利休十草 | × |
| M.STYLE(エムスタイル)『Karl(カール)土鍋 9号』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
一般的な土鍋の約1/2の驚きの軽さ | 4~5人 | 高耐熱陶器 | ベージュ・グレー | ◯(オールメタル加熱方式IHは非対応) |
| TOJIKI TONYA(トウジキトンヤ)『伊賀土鍋 8号』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
「育てる土鍋」であなただけのごちそうを | 3~4人 | 耐熱陶器 | ブラック・ホワイト | × |
| MIYAWO(ミヤオ)『土鍋 サークル / グラデーション』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
においが残りにくいからどんな料理にも毎日使える | 3~4人 | 本体:高耐熱セラミック、蓋:硬質陶器 | サークル・グラデーション | ◯ |
| HARIO(ハリオ)『フタがガラスの土鍋9号』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
中身が見えるガラスのフタが使いやすい | 3~4人 | 鍋:耐熱陶器・フタ:耐熱ガラス | ブラック・ホワイト | × |
| 長谷園『ふっくらさん 黒らく』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
蓋を裏返すと器に、老舗メーカーがつくる万能土鍋 | 2~3人 | 陶器 | 黒らく | × |
| GIMPO(銀峯陶器)『菊花 土鍋 萬古焼 9号』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
煮込み料理ならこの土鍋! | 3〜4人 | 陶器 | ブルー・ブラウン・ホワイト・マゼンタ | × |
| Living(リビング)『New宴 土鍋 8号』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
吹きこぼれにくく、香ばしいご飯も炊ける | 3~4人 | 陶磁器 | ブラック/ホワイト | × |
| 長谷園『みそ汁鍋 大』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
火を止めた後の余熱でお料理をおいしく | 3~4人 | 陶磁器 | イエロー | × |
| 長谷園『かまどさん ご飯 鍋 二合炊き(ACT-03)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
火加減要らずでおいしいご飯が炊ける、伊賀焼土鍋 | 2~3人 | 粗土 | -- | × |
| HARIO(ハリオ)『フタがガラスのご飯釜』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
なかを確認しながら炊き上げられる | 2~3人 | フタ:耐熱ガラス、鍋身:耐熱陶器、ツマミ:ポリプロピレン・シリコーンゴム | ブラック | ×(IH対応モデルもあり) |
| Tsukamoto(つかもと)『かまっこ 一合炊き』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
手軽に簡単に土鍋ご飯を楽しめる | - | 陶器 | ブラウン・ブラック・ホワイト | × |
| TAMAKI『土鍋 2合用』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
白米から炊き込みご飯まで土鍋ごはんが楽しめる | - | 本体:高耐熱セラミック・蓋:硬質陶器 | ブラック | × |
| たいせい窯『ご飯鍋 5合炊き』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
二重蓋構造でふっくらおいしいご飯が炊ける | - | 耐熱陶器 | ホワイト・ブラック | × |
| プライムダイレクト『伊賀ノ匠』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
レンジで10分、手軽なお一人様サイズ | - | 陶器 | ブラック | × |
| Ishigaki(イシガキ)『デリッシュライフ 炊飯土鍋』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
二重ぶた構造でもっちりつやつやご飯 | - | 本体:耐熱陶器、蓋:陶器 | ブラック | × |
| TAMAKI『土鍋 TOTE T-928486』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
和洋何でもお料理が映える | 4~5人 | 蓋:硬質陶器、本体:高耐熱セラミック | ホワイト | × |
| KINTO(キントー)『KAKOMI IH土鍋(25191)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
シンプルなデザインで蒸し料理にも最適 | 1~2人(1.2L) | 胴部:高耐熱陶器、蓋・すのこ:陶器 | ホワイト、ブラック | 〇 |
| 銀峯陶器『萬古焼 花三島 IH対応』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
レンジやオーブンでも使えるオールラウンダー | 2~3人 | 胴部:耐熱陶器、蓋:陶器 | - | 〇 |
| Molatura(モラトゥーラ)『ベストポット』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
他にはないミニマルなデザイン性がツボ! | 2~4人 | ステンレス、カーボン、セラミック、鋳鉄、ホーロー | ホワイト・グリーン・イエロー・ピンク・ブラック・オーシャンブルー・インディゴブルー | 〇 |
| 武田コーポレーション(Takeda corporation)『一人用土鍋17cm』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
1人用にぴったり、気軽に楽しんでみたい人に | 1人 | 陶器 | ブラック | × |
| Living(リビング)『刷毛目柄 土鍋 4号』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
一人で手軽に食べたいときにちょうどいいサイズ | 1人 | 刷毛目柄 土鍋 4号 | - | × |
| Living(リビング)『蓋がお茶碗にもなる土鍋 17cm』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
フタが茶碗になり便利な一人用鍋 | 1人 | 陶磁器 | ホワイト | × |
| 銀峯陶器『菊花 7号』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
1~2人用鍋におすすめのミニ土鍋 | 1~2人 | 胴部:耐熱陶器、蓋:陶器 | 瑠璃色 | × |
| パール金属『土鍋 さくら』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
安くてコスパ抜群のおしゃれ土鍋 | 3~4人 | 陶器 | さくら | × |
| セラミックジャパン『do-nabe IH(DN-240IH-WH)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
シンプルで近代的なデザインが特徴 | L:2~3人(S:1~2人) | 本体:耐熱陶器、金属プレート:ステンレス、焦げ付き防止プレート:耐熱陶器 | ホワイト、ブラック | ○ |
| 手作り工房 夕立窯『立体アルファベット土鍋』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
ギフトにぴったり! 名前が入れられる | 4~5人 | 陶器 | ブルー、オレンジ、ピンク、ホワイト、ブラウン、グリーン、グレー、ブラック、イエロー、トルコブルー | ○ |
| 長谷園『かまどさんプレミアム 三合炊き』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
火加減いらずで吹きこぼれなしの簡単調理 | - | 陶磁器 | ブラック | × |
| KYOTOH(京陶窯業)『DONABE 205』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
1つで6役の万能土鍋 | 2~4人 | 陶磁器 | ホワイト・ブラック | × |
土鍋の魅力
土鍋の魅力は何といっても保温性の高さ。土を原料とする陶器でできているため、アルミやステンレスといった金属製の鍋よりも熱伝導率が低いです。そのため、ゆっくりと温まり一度温まると冷めにくいという特徴があります。
また、土鍋でじっくりと火を通した食材は煮崩れしにくく、やわらかく仕上がります。鍋料理や蒸し物、煮物やスイーツなど幅広い料理に使える多用途性の高さも魅力です。
さらに、陶器ならではの自然な風合い、温かみのあるデザインも楽しむことができます。割れない限りずっと使える一生ものなので、用途や好みに合ったお気に入りの土鍋を探してみてください。
あなたにぴったりの土鍋は? タイプ別診断で発見!

出典:マイナビおすすめナビ

出典:マイナビおすすめナビ
土鍋は、商品によってサイズや形状がさまざまです。まずは、どんな土鍋がぴったり合うのかチャートでチェックしてみましょう!
診断チャートで簡単チェック!

出典:マイナビおすすめナビ

出典:マイナビおすすめナビ
求めている土鍋が見つかりましたか?タイプ別にそれぞれの特徴を説明していくので、気になるタイプがあったらぜひチェックしてみてくださいね。
A:1人用なら直径15~20cmの「3~5号サイズ」
小さめの3号~5号の土鍋は、子ども用や少食の1人用にちょうどいいサイズ。ちょっとした雑炊や湯豆腐などを盛るのにぴったりです。ただ、商品によっては1人用の冷凍うどんが入らないことも。使いやすいサイズかどうかは、購入前に商品ホームページなどでしっかりとサイズを確認しましょう。
B:2~3人用なら直径22~25cmの「6~7号サイズ」
2~3人用なら6号~7号サイズがおすすめ。1人でしっかりと食べたいときにもちょうどいい大きさです。大きめの具材のおでんやポトフなども作りやすいですよ。1合~2合のお米を炊くことができるので、少人数でのキャンプ飯を作るときなどに重宝するでしょう。
C:4~5人用なら直径28~31cm「8~9号サイズ」
4~5人なら、8号・9号がおすすめです。食べ盛りの子どもがいる家庭はワンサイズ上を選んでもよいでしょう。8号・9号は鍋自体のサイズも大きくなってくるので、収納できるかどうかにも注意して選んでみてください。
同じ号数でも商品によって大きさが異なる!
土鍋の場合、いろいろなサイズがあるため、使いやすいサイズを選ぶとよいでしょう。同じ商品であっても、さまざまな大きさを展開しているものが多いため、メーカーの販売しているサイトをチェックしてみてください。
一人暮らしの方やカップルの方であれば、小さめのサイズで十分ですし、ご家族で囲むのであれば、大きめの土鍋を試してみてはいかがでしょうか。下記人数とサイズの目安も参考にしてください。
3号~5号(15cm~20cm):1人用
6号(22cm):1~2人用
7号(25cm):2~3人用
8号(28cm):3~4人用
9号(31cm):4~5人用
10号(35cm):5~6人用
D:鍋やすき焼きをテーブルで囲みやすい「浅型土鍋」
大人数で鍋を囲むときには、浅型の土鍋がおすすめ。口径が大きくて深すぎないので、テーブルの中央に置いても各自が具材を取り出しやすいのが特徴です。
ただし、吹きこぼれやすいので汁気の多い料理を作るときには注意しましょう。ほかにも、煮込みハンバーグや蒸し料理などでも活躍します。
E:汁気が多い料理でもこぼれにくい「深型土鍋」
おでんや煮込み料理など、汁気の多い料理を作るのであれば深型が使いやすいでしょう。深型の土鍋は吹きこぼれにくくなっているので、長時間火にかけていても大丈夫です。じっくりと煮込んでいくことで、味がしっかりと染み込みます。煮込みうどんやスープパスタ、土鍋プリンなど幅広い調理に使えます。
F:美味しい土鍋ご飯を炊きたいなら「炊飯専用土鍋」
底が丸くて深いのが特徴の炊飯専用鍋は、吹きこぼれにくくて空間に余裕があるためお米に均一に火が通りやすいのが特徴です。ゆっくりと火が回ることでお米本来の甘みを引き出してくれます。炊飯器のものとはまた違った味わいで、おいしいご飯が炊けますよ。炊きあがったらそのまま食卓に出して使うこともできます。
G:調理の幅が広がる!温め直しもしやすい「オーブン・電子レンジ対応」
土鍋は1000℃以上の高温で焼き上げて作るため、熱に強いという特徴があります。土鍋とオーブンを使えばメニューの幅も広がりますよ。ケーキやパエリア、グラタンなどのオーブン料理を楽しめます。
また、電子レンジ対応の土鍋なら料理の温め直しに便利。もちろん調理にも使えるので、焦げるのが心配、火の調節が難しいという初心者でも簡単に使うことができます。食材を均一に加熱するため、ムラなくおいしく仕上げることができます。
H:IH調理なら必須の「IH対応土鍋」
普通の土鍋だと電気を通さないため、IHコンロでは使うことができません。IHコンロで使える土鍋は、鍋底に金属のプレートを敷くタイプや、コイルやその他素材が鍋底に使われているタイプなどがあります。外箱や鍋底に「IH対応」や「IH」「CH‐IH」と明記されていれば、大体がIHコンロで使用可能です。
なお、一般財団法人製品安全協会の安全基準を満たしている「SG」マークが付いていれば、より安全に使うことができます。ただ、これらのマークが付いていても土鍋の使用を推奨していないIHコンロもあるので、自宅のIHコンロを確認してから購入するようにしましょう。
ご家庭にIHしかないからといって、土鍋の購入をあきらめなくても大丈夫。土鍋の多くはガス火を前提としていますが、なかにはIHに対応したモデルも発売されています。IHに対応したモデルにすれば、IH機器を購入し、土鍋をサブの調理器具としても使用できます。
今まで炊飯器で炊いていたご飯を土鍋で炊けば、ご家族や友人にも喜ばれるでしょう。
I:迷ったら口コミを参考に!「ユーザーのイチオシ土鍋」
どれにしようか迷っている人は、ぜひ実際に土鍋を購入したユーザーの口コミを参考にするのが一番です。使ってみないとわからないサイズ感や使用感などのリアルな口コミを紹介しています。
土鍋の素材の違いにも着目

出典:マイナビおすすめナビ

出典:マイナビおすすめナビ
土鍋にはさまざまな素材があり、それぞれに特徴があります。ここでは、よく使われている4つの素材について紹介します。
◆萬古焼(ばんこやき)
三重県四日市市でつくられる萬古焼は、日本国内のシェア80~90%近くを占めています。大きな特徴は、耐熱性にすぐれていること。ガスレンジや炭火での空焚きや直火にも耐えられる、抜群の耐久性が魅力です。
◆ 伊賀焼(いがやき)
三重県伊賀市でつくられる伊賀焼は、厚みがあって蓄熱性が高いのが特徴です。じっくりと食材に火を通すので煮込み料理に適しています。目が粗いため匂い移りや色移りがしやすくて、定期的な目止めが必要な場合があります。
◆信楽焼(しがらきやき)
滋賀県信楽町で作られる信楽焼は、独特の風合いと色合いが特徴的です。木節や実土などの複数の粘土を混ぜ合わせてつくられているためコシのある肉厚なつくりになっています。空気をたっぷり含んだ土でつくられているため蓄熱性が非常に高いです。
◆セラミック
セラミックは、土鍋っぽさを感じさせない現代的なデザインの商品が多いです。IH対応の土鍋もあります。ニオイ移りがしにくく、お手入れがしやすいのが特徴です。萬古焼などの伝統的な焼き物にセラミック加工を施して、IHに対応させている商品もあります。
土鍋といってもいろいろな種類があり、伝統的な粗土(あらつち)を使ったものもあれば、セラミック製の土鍋もあります。
土鍋の魅力は、なんといっても遠赤外線効果による仕上がり。材質によって料理の仕上がりも異なるので、どのような素材を使っているか確認してみてください。
とくに玄米ご飯や炊き込みご飯を炊く場合、どのような土鍋で炊くかによって、完成度が左右されます。
【目的別】おすすめの土鍋
ここからは、おすすめの土鍋を紹介していきます。気になる商品はぜひチェックしてくださいね!
1人用にぴったりな【3~5号サイズ】
1人鍋用やちょっとした料理のお椀代わりにもなる3~5号サイズの土鍋を紹介していきます。
鍋キューブ1つにぴったりサイズ
白い色がどんな料理もおいしく引き立ててくれる、1人ようにぴったりの土鍋です。鍋キューブ1個を入れて調理するのにちょうどいいサイズ。土鍋ならではの遠赤外線効果で食材が本来持つうまみをしっかり引き出します。保温性が高いので冷めにくく、いつまでも温かいまま料理を楽しめるのも、寒い季節には特にうれしいですね。
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| 対応人数 | 1人 |
|---|---|
| 材質 | 本体:耐熱陶器 蓋:陶器 |
| カラー | ホワイト |
| IH対応 | × |
| 対応人数 | 1人 |
|---|---|
| 材質 | 本体:耐熱陶器 蓋:陶器 |
| カラー | ホワイト |
| IH対応 | × |
土鍋のイメージを覆す軽さが扱いやすい
従来の土鍋の、重くて扱いにくいというイメージを覆す、軽くて扱いやすく、お手入れも簡単な土鍋です。モダンなデザインが和にも洋にも合い、これ1つでいろいろな料理に使えます。フタがお茶碗になるので、洗い物が少なくてすむのもうれしいポイント。保温性が高く温かさは持続しますが、冷めたら電子レンジで温めなおしも可能です。
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| 対応人数 | 1人 |
|---|---|
| 材質 | 本体:耐熱陶器、蓋:陶器 |
| カラー | 黒・紺 |
| IH対応 | × |
| 対応人数 | 1人 |
|---|---|
| 材質 | 本体:耐熱陶器、蓋:陶器 |
| カラー | 黒・紺 |
| IH対応 | × |
韓国料理を見た目でも楽しみたい人に
韓国の土鍋、トッペギと下敷きのセットです。ラーメン1個が入ります。他にも、キムチチゲ、デンジャンチゲ、純豆腐チゲなど、1~2人前にちょうどいいサイズ。韓国料理がお好きな方、韓国式の土鍋を使って、見た目も本格的に韓国風に楽しみませんか。土鍋なので冷めにくく、熱々のまま料理を楽しめます。
※各社通販サイトの 2024年11月19日時点 での税込価格
| 対応人数 | 1~2人 |
|---|---|
| 材質 | 陶器 |
| カラー | ブルー |
| IH対応 | - |
| 対応人数 | 1~2人 |
|---|---|
| 材質 | 陶器 |
| カラー | ブルー |
| IH対応 | - |
2~3人用なら【6~7号サイズ】
2~3人用の土鍋を紹介していきます。夫婦やカップル、3人家族ならこのサイズがぴったりです。また、一人暮らしでも煮込み料理や鍋料理をたくさん作っておきたい人におすすめです。
一人暮らしにも最適! 萬古焼で炊き上げる極上ご飯
ご飯をふっくらおいしく炊き上げるご飯土鍋。萬古焼でできており、丸い独特のフォルムがダルマのようでかわいらしいですね。
紹介しているのは3合炊きですが、1合から7合炊きにまで幅広いラインナップがあるので、家族構成に合わせて選ぶことができます。水加減は目盛りを見ながら調整できるので、初心者でも安心して炊くことができますよ。白米のほかに、玄米、赤飯、おかゆも。炊飯器では味わえない、土鍋ならではのご飯を体験できますので、ぜひ試してみてください。
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| 対応人数 | 2~3人 |
|---|---|
| 材質 | 耐熱陶器 |
| カラー | こげ茶 |
| IH対応 | × |
| 対応人数 | 2~3人 |
|---|---|
| 材質 | 耐熱陶器 |
| カラー | こげ茶 |
| IH対応 | × |

ファミリー向けの大型土鍋
三重県四日市市にある、萬古焼の窯元である三鈴陶器製の土鍋。8号サイズは2~3人、9号サイズは4~5人向けの大きさ。ご家族であたたかい土鍋を囲んだ食事を楽しみたいという方におすすめです。
とくに白ご飯や玄米ご飯が好きなご家庭であれば、土鍋ならではの炊き上がりに満足いただけるはず。手描きの絵付けもかわいいので、食卓に並べるだけで、普段の食事もすてきに演出できますよ。蓋の高さもあるので、カサのある野菜なども上手に調理できます。
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| 対応人数 | 2〜3人 |
|---|---|
| 材質 | 耐熱陶器 |
| カラー | トクサ柄 |
| IH対応 | × |
| 対応人数 | 2〜3人 |
|---|---|
| 材質 | 耐熱陶器 |
| カラー | トクサ柄 |
| IH対応 | × |
フタの組み合わせ自由!好みの土鍋がきっと見つかる
色やデザイン、質感が異なる10種類のフタからお好きなデザインを選べる土鍋です。どれも素敵で、迷ってしまうかもしれません。重ねて収納が可能なので、複数そろえるのもいいですね。一般の土鍋と比べて、熱衝撃・物理衝撃の両面で耐久性にすぐれているのが特長です。温度差500度にも耐えらえるほどの高耐久性。熱々のお料理を存分に味わってください。
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| 対応人数 | 2人 |
|---|---|
| 材質 | 蓋:磁器、本体:超耐熱陶器 |
| カラー | 10種 |
| IH対応 | - |
| 対応人数 | 2人 |
|---|---|
| 材質 | 蓋:磁器、本体:超耐熱陶器 |
| カラー | 10種 |
| IH対応 | - |
4~5人用なら【8~9号サイズ】
4~5人で鍋を囲むときにもぴったりなファミリーサイズです。翌日分の作り置きをしたい場合にもおすすめです。

確かな品質の日本製土鍋
蓄熱性と保温性が高いといわれている、伊賀の粗土を使った土鍋。生産地や素材にこだわった日本製の土鍋を探している方におすすめです。じっくりと食材に火を通すことができ、遠赤外線効果もあり、素材本来の旨味をしっかりと引き出すことができます。
水炊きやうどんすきなどの料理はもちろん、洋風にもマッチするため、トマト鍋やエスニック料理にチャレンジしてみてもよいでしょう。
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| 対応人数 | 3~5人 |
|---|---|
| 材質 | 陶器 |
| カラー | 利休十草 |
| IH対応 | × |
| 対応人数 | 3~5人 |
|---|---|
| 材質 | 陶器 |
| カラー | 利休十草 |
| IH対応 | × |
一般的な土鍋の約1/2の驚きの軽さ
土鍋というと、重くて扱いにくいので洗ったり出し入れが面倒という方もいるのでは。この土鍋は、一般的な土鍋の約1/2という驚きの軽さを実現。しかも丈夫でおしゃれ。吸水率も0.5%以下なので、スープが染みこみにくく、におい移りがしにくいです。例えば、カレーの翌日に水炊きでも大丈夫。使い勝手がいいので、毎日の食卓に登場させられます。
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| 対応人数 | 4~5人 |
|---|---|
| 材質 | 高耐熱陶器 |
| カラー | ベージュ・グレー |
| IH対応 | ◯(オールメタル加熱方式IHは非対応) |
| 対応人数 | 4~5人 |
|---|---|
| 材質 | 高耐熱陶器 |
| カラー | ベージュ・グレー |
| IH対応 | ◯(オールメタル加熱方式IHは非対応) |
「育てる土鍋」であなただけのごちそうを
細かな穴が無数にあり、「呼吸する土」と呼ばれる伊賀の粗土を使用した、伊賀焼の土鍋です。遠赤外線効果が高く、うまみをギュッと閉じ込めます。また、蓄熱性、耐熱性も高く、長時間の煮込み料理にもぴったり。火からおろしたあともトロ火で煮込むのと同じ温度帯を保つことで、食材にじっくり味をしみこませます。伊賀鍋は、「育てる鍋」と言われ、使えば使うほど、丈夫でおいしく煮える良い鍋になっていきます。長く使って、自分だけの愛着のある鍋に育ててください。
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| 対応人数 | 3~4人 |
|---|---|
| 材質 | 耐熱陶器 |
| カラー | ブラック・ホワイト |
| IH対応 | × |
| 対応人数 | 3~4人 |
|---|---|
| 材質 | 耐熱陶器 |
| カラー | ブラック・ホワイト |
| IH対応 | × |
においが残りにくいからどんな料理にも毎日使える
直火とIH、そして電子レンジにも対応していて使い勝手の良い土鍋です。シックなデザインで、和洋どんな料理にも合わせやすく、食卓にそのまま出しても雰囲気をおしゃれに彩ってくれます。
土鍋なのに、吸水率が0.5%以下と染みこみにくく、カレーやチゲなど、においの強い料理に使っても大丈夫。毎日土鍋料理でも使えるくらい、使いまわしがききます。
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| 対応人数 | 3~4人 |
|---|---|
| 材質 | 本体:高耐熱セラミック、蓋:硬質陶器 |
| カラー | サークル・グラデーション |
| IH対応 | ◯ |
| 対応人数 | 3~4人 |
|---|---|
| 材質 | 本体:高耐熱セラミック、蓋:硬質陶器 |
| カラー | サークル・グラデーション |
| IH対応 | ◯ |
中身が見えるガラスのフタが使いやすい
フタがガラスなので、中身が見やすく、普段使いしやすい土鍋です。シンプルな形状で、和食にも洋食にも、どんなシーンにも合わせやすいデザインなので、幅広くいろいろな料理に使えます。フタの中央に蒸気の出る穴があるので、吹きこぼれがないのもうれしい。容量が大きめなので、家族の食卓にぴったり。だんらんの時間をぜひこの土鍋で温かく過ごしてください。
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| 対応人数 | 3~4人 |
|---|---|
| 材質 | 鍋:耐熱陶器・フタ:耐熱ガラス |
| カラー | ブラック・ホワイト |
| IH対応 | × |
| 対応人数 | 3~4人 |
|---|---|
| 材質 | 鍋:耐熱陶器・フタ:耐熱ガラス |
| カラー | ブラック・ホワイト |
| IH対応 | × |
鍋やすき焼きをするときには【浅型土鍋】
テーブルで鍋やすき焼きを楽しむなら、具材を取り出しやすい形状の浅型土鍋がおすすめです。
蓋を裏返すと器に、老舗メーカーがつくる万能土鍋
1832年から続く老舗、伊賀焼の「長谷園」が販売している万能調理土鍋です。煮る、焼く、蒸す、燻(いぶ)すといったすべての用途に使えます。
モロッコのタジン鍋を思わせるフォルムは、溜まった水蒸気を循環させるのに最適で、IHにも対応しています。蓋を返せば、器としても使用可能です。
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| 対応人数 | 2~3人 |
|---|---|
| 材質 | 陶器 |
| カラー | 黒らく |
| IH対応 | × |
| 対応人数 | 2~3人 |
|---|---|
| 材質 | 陶器 |
| カラー | 黒らく |
| IH対応 | × |
煮込み料理ならこの土鍋!
菊花は蓄熱性が高いため、煮込み料理に最適です。柔らかく味のしみた煮込み料理が作れます。また、土鍋の遠赤外線効果で、食材のうまみをしっかり引き出してくれますよ。煮込み料理だけでなく、お鍋はもちろん、ご飯を炊いたり、蒸し料理もできます。オーブン・電子レンジにも対応しているので、さらに料理の幅は広がり、さまざまな料理に大活躍します。
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| 対応人数 | 3〜4人 |
|---|---|
| 材質 | 陶器 |
| カラー | ブルー・ブラウン・ホワイト・マゼンタ |
| IH対応 | × |
| 対応人数 | 3〜4人 |
|---|---|
| 材質 | 陶器 |
| カラー | ブルー・ブラウン・ホワイト・マゼンタ |
| IH対応 | × |
汁気が多くてもこぼれにくい【深型土鍋】
おでんや煮込み料理など長時間火にかけて作る汁気の多い料理なら深型土鍋がおすすめです。
吹きこぼれにくく、香ばしいご飯も炊ける
深型で高いフチが特長の土鍋。深型なうえフチが高いため吹きこぼれにくく、丸みを帯びた形が対流も起こしやすいです。そのため、鍋料理はもちろんのこと、香ばしいご飯もふっくら炊ける、炊飯にもぴったりの土鍋です。深型なので、食材はたっぷり入り、家族の食卓にちょうどよい量。遠赤外線効果で食材のうまみをしっかり引き出し、保温力にも優れているので、食材に味がしっかりしみ込みます。
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| 対応人数 | 3~4人 |
|---|---|
| 材質 | 陶磁器 |
| カラー | ブラック/ホワイト |
| IH対応 | × |
| 対応人数 | 3~4人 |
|---|---|
| 材質 | 陶磁器 |
| カラー | ブラック/ホワイト |
| IH対応 | × |
火を止めた後の余熱でお料理をおいしく
丸い形状と肉厚な土鍋で、火を止めた後の余熱でじっくり食材に味がしみこみ、お料理を優しくおいしく仕上げてくれる「みそ汁鍋」。でも、みそ汁だけではありません。煮込み料理もおいしくホクホクにしてくれます。空焚きもできるので、焼いたり炒めたりと幅広い使い方ができます。土鍋の内側にマイナスイオンが発生し続けるラジウム系鉱石を使用しいるため、食材の芯までしっかり味をしみこませ、塩分をまろやかにしてくれるので、より一層おいしく仕上がります。
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| 対応人数 | 3~4人 |
|---|---|
| 材質 | 陶磁器 |
| カラー | イエロー |
| IH対応 | × |
| 対応人数 | 3~4人 |
|---|---|
| 材質 | 陶磁器 |
| カラー | イエロー |
| IH対応 | × |
おいしいご飯を炊くなら【炊飯専用土鍋】
おいしいご飯を炊きたいなら、専用の炊飯土鍋もあります。炊飯器で炊いたご飯とはまた違った味わいに仕上がります。
火加減要らずでおいしいご飯が炊ける、伊賀焼土鍋
火加減要らずでおいしいご飯が炊けると評判の炊飯土鍋です。熟練の技術を持った職人が作る伊賀焼のアイテム。遠赤外線効果でお米の芯まで熱が通り、ふっくらとしたご飯に仕上がります。土鍋が木のおひつと同じように呼吸し、ご飯がべとつくこともないです。
圧力釜のような機能を果たす二重蓋仕様で、吹きこぼれにくいのもポイント。炊き上げ時間を1分前後延ばすと香ばしいおこげができます。
サイズ展開も豊富なので、家族の人数に合わせて選ぶことができますよ。炊飯だけでなく鍋料理にも使えるので、1つ持っていると重宝します。
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| 対応人数 | 2~3人 |
|---|---|
| 材質 | 粗土 |
| カラー | -- |
| IH対応 | × |
| 対応人数 | 2~3人 |
|---|---|
| 材質 | 粗土 |
| カラー | -- |
| IH対応 | × |
なかを確認しながら炊き上げられる
こちらは名前のとおり、蓋がガラスで本体は萬古焼のご飯鍋です。分厚い釜で、直火でもご飯を焦がさずにふっくらと炊き上げます。
ガラスからご飯がどのように炊けていくのかを見ることができ、初心者でも安心して調理できますよ。ツマミにはホイッスルがついているので、炊けたら音で教えてくれて便利です。
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| 対応人数 | 2~3人 |
|---|---|
| 材質 | フタ:耐熱ガラス、鍋身:耐熱陶器、ツマミ:ポリプロピレン・シリコーンゴム |
| カラー | ブラック |
| IH対応 | ×(IH対応モデルもあり) |
| 対応人数 | 2~3人 |
|---|---|
| 材質 | フタ:耐熱ガラス、鍋身:耐熱陶器、ツマミ:ポリプロピレン・シリコーンゴム |
| カラー | ブラック |
| IH対応 | ×(IH対応モデルもあり) |
手軽に簡単に土鍋ご飯を楽しめる
1合炊きで一人分のご飯にちょうどよい量。少量でも、ご飯がおいしく炊ける土鍋です。内蓋は計量カップになり、外蓋は茶碗になるという無駄なく使える機能を兼ね備えているのがうれしいです。遠赤外線効果でじっくり中まで温まり、おいしいご飯が手軽に炊けます。
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| 対応人数 | - |
|---|---|
| 材質 | 陶器 |
| カラー | ブラウン・ブラック・ホワイト |
| IH対応 | × |
| 対応人数 | - |
|---|---|
| 材質 | 陶器 |
| カラー | ブラウン・ブラック・ホワイト |
| IH対応 | × |
白米から炊き込みご飯まで土鍋ごはんが楽しめる
直火専用のモダンなご飯鍋。重めのフタでしっかり圧力をかけたら、厚みの蓄熱効果、対流しやすい形状で、お米のおいしさをしっかり引き出しておいしいご飯が炊きあがります。専用レシピがついており、白米だけでなく、いろいろな炊き込みご飯も楽しめるので、毎日の食事をおいしく彩ってくれます。
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| 対応人数 | - |
|---|---|
| 材質 | 本体:高耐熱セラミック・蓋:硬質陶器 |
| カラー | ブラック |
| IH対応 | × |
| 対応人数 | - |
|---|---|
| 材質 | 本体:高耐熱セラミック・蓋:硬質陶器 |
| カラー | ブラック |
| IH対応 | × |
二重蓋構造でふっくらおいしいご飯が炊ける
一つ一つ職人の手で作られたごはん鍋です。圧力鍋の機能を果たす二重蓋構造。上蓋の穴から炊飯時の蒸気を逃がし、吹きこぼれを防いでくれます。炊き上がった後は穴のない中蓋でしっかり蒸気を閉じ込めて蒸らすことで、ふっくらおいしいごはんが炊き上がります。コロンと丸みを帯びたかわいい見た目や軽さは、毎日の使いやすさにもしっかり配慮されています。
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| 対応人数 | - |
|---|---|
| 材質 | 耐熱陶器 |
| カラー | ホワイト・ブラック |
| IH対応 | × |
| 対応人数 | - |
|---|---|
| 材質 | 耐熱陶器 |
| カラー | ホワイト・ブラック |
| IH対応 | × |
料理のレパートリーが増える【オーブン・電子レンジ対応】
再加熱や時短料理に使いやすいオーブン・電子レンジ対応土鍋。ぜひ活用して料理のレパートリーを増やしましょう。
レンジで10分、手軽なお一人様サイズ
0.5~1合の手軽なお一人様サイズの伊賀焼のご飯炊き用の土鍋です。レンジで10分で炊けるので、手間なく手軽に本格的な土鍋ご飯を楽しめます。炊飯時に発生する水分が土鍋に吸収されて徐々に放出されるので、水分量を上手に調節。蓄熱性にもすぐれているので、レンジ後の蒸らしの段階でも、じっくりとご飯のうまみを引き出してくれます。
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| 対応人数 | - |
|---|---|
| 材質 | 陶器 |
| カラー | ブラック |
| IH対応 | × |
| 対応人数 | - |
|---|---|
| 材質 | 陶器 |
| カラー | ブラック |
| IH対応 | × |
二重ぶた構造でもっちりつやつやご飯
電子レンジとガスコンロの両方に対応している炊飯用の土鍋です。鍋の内側には電子レンジ用の発熱材を使用しており、高温加熱でしっかりご飯が炊けます。フタが二重になっており、お米にしっかり圧力がかかるので、もっちりつやつやしたご飯が炊きあがります。炊き込みご飯やおかゆも作れますし、ガスコンロでおこげを楽しむのもいいですね。
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| 対応人数 | - |
|---|---|
| 材質 | 本体:耐熱陶器、蓋:陶器 |
| カラー | ブラック |
| IH対応 | × |
| 対応人数 | - |
|---|---|
| 材質 | 本体:耐熱陶器、蓋:陶器 |
| カラー | ブラック |
| IH対応 | × |
和洋何でもお料理が映える
モダンテイストの土鍋で、スクエアの持ち手も持ちやすいだけでなく見た目にもおしゃれ。土鍋の概念を覆し、アクアパッツァでもキムチ鍋でも、何にでも合わせやすく、食卓を豊かに彩ってくれます。独自開発のサーマクラフト加工によって、色素沈着や臭い移りも軽減してくれるので、いろいろなお料理に使えます。
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| 対応人数 | 4~5人 |
|---|---|
| 材質 | 蓋:硬質陶器、本体:高耐熱セラミック |
| カラー | ホワイト |
| IH対応 | × |
| 対応人数 | 4~5人 |
|---|---|
| 材質 | 蓋:硬質陶器、本体:高耐熱セラミック |
| カラー | ホワイト |
| IH対応 | × |
IHコンロでも使える【IH対応土鍋】
IHだからといって土鍋を使うのをあきらめないで。IHコンロでも使える土鍋はたくさんありますよ。ぜひチェックしてくださいね。

シンプルなデザインで蒸し料理にも最適
生産国はマレーシア。シンプルで飽きのこないデザインなので、長く愛用できるはず。IHにも対応しているため、新生活や結婚祝いなどのギフトにも喜ばれるでしょう。
オーブンやレンジでも使用できるため、煮物をレンジで作ったり、鶏の丸焼きなどを作るのにも向いています。付属しているすのこをセットすれば、旬の野菜やお肉をのせ、ヘルシーな蒸し料理も楽しめますよ。
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| 対応人数 | 1~2人(1.2L) |
|---|---|
| 材質 | 胴部:高耐熱陶器、蓋・すのこ:陶器 |
| カラー | ホワイト、ブラック |
| IH対応 | 〇 |
| 対応人数 | 1~2人(1.2L) |
|---|---|
| 材質 | 胴部:高耐熱陶器、蓋・すのこ:陶器 |
| カラー | ホワイト、ブラック |
| IH対応 | 〇 |
レンジやオーブンでも使えるオールラウンダー
土鍋といえば、この『花三島』を思い浮かべる人もいるのでは。表面に菊の花があしらわれていて、優雅な印象を与えます。こちらはIH対応タイプです。
家庭用だけでなく、業務用としても古くから愛されている商品で、素材の旨味を閉じ込めながら火を通してくれますよ。電子レンジやオーブンにも対応しているので、調理のレパートリーが増えるでしょう。
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| 対応人数 | 2~3人 |
|---|---|
| 材質 | 胴部:耐熱陶器、蓋:陶器 |
| カラー | - |
| IH対応 | 〇 |
| 対応人数 | 2~3人 |
|---|---|
| 材質 | 胴部:耐熱陶器、蓋:陶器 |
| カラー | - |
| IH対応 | 〇 |
他にはないミニマルなデザイン性がツボ!
ミニマルでモダンなデザインと、蓄熱機能が魅力のIHにも対応した土鍋です。「羽釜形状」を採用することで、熱を保持しやすい蓄熱調理に適した作りになっています。また、気密性が高く、食材から蒸発した水分を逃さないため、無水調理にももってこいです。
鍋の容量は2Lで、2~4人分のカレーを作るのにぴったりなサイズ。カラーバリエーションも豊富で、ホワイトのほかに、グリーン・ピンク・ブラック・オーシャンブルー・インディゴブルーなど7種類から選べます。他にはないデザインの土鍋に仕上がっていますよ。
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| 対応人数 | 2~4人 |
|---|---|
| 材質 | ステンレス、カーボン、セラミック、鋳鉄、ホーロー |
| カラー | ホワイト・グリーン・イエロー・ピンク・ブラック・オーシャンブルー・インディゴブルー |
| IH対応 | 〇 |
| 対応人数 | 2~4人 |
|---|---|
| 材質 | ステンレス、カーボン、セラミック、鋳鉄、ホーロー |
| カラー | ホワイト・グリーン・イエロー・ピンク・ブラック・オーシャンブルー・インディゴブルー |
| IH対応 | 〇 |
迷ったらこれ【ユーザーのイチオシ土鍋】
ここからは、土鍋を愛用しているユーザーがイチオシの商品を紹介。5点満点で「コスパ」「お手入れ」「耐久性」を評価してもらいました。イチオシのポイント、おすすめする理由や口コミもぜひ参考にしてください!
その他にもおすすめしたい商品があるよという方は、ぜひ記事の下部にある投稿フォームからご紹介をお願いします。

愛用者
やはり土鍋は保温性が違う
鍋料理に使える調理器具はいくつか持っていますが、やはり土鍋にしかない良さがあると思いました。4人家族で使うには小さいサイズなので、大人用と子ども用で味を分けたいときに使っています。保温性も高く、おいしい鍋ができます。(T.K.さん/女性/34歳/主婦)
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| コスパ | ★★★★☆ |
|---|---|
| お手入れ | ★★★★☆ |
| 耐久性 | ★★★★☆ |
| 総合評価 | 4.0点 |
| コスパ | ★★★★☆ |
|---|---|
| お手入れ | ★★★★☆ |
| 耐久性 | ★★★★☆ |
| 総合評価 | 4.0点 |

愛用者
いろいろな料理に使ってみたい
鍋物やおでんに大活躍しています。大きさや深さが気に入っています。取っ手も大きいので運びやすいです。あと保温性が高くて寒い冬にもおすすめです。IHやレンジにも対応しているので、いろいろな料理が作れるのかなと思います。(A.F.さん/女性/38歳/自営業)
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| コスパ | ★★★★★ |
|---|---|
| お手入れ | ★★★★★ |
| 耐久性 | ★★★★★ |
| 総合評価 | 5.0点 |
| コスパ | ★★★★★ |
|---|---|
| お手入れ | ★★★★★ |
| 耐久性 | ★★★★★ |
| 総合評価 | 5.0点 |

愛用者
やはり土鍋はいい
一人暮らしのときに、一人用のすき焼きや鍋を作るのに使用していました。洗うときに落としたりぶつけたりしたら割れるのではないかと慎重になっていましたが、案外頑丈でぶつけても割れませんでした。ご飯を炊いてもいいおこげができておいしいです。(N.M.さん/女性/37歳/主婦)
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| コスパ | ★★★★★ |
|---|---|
| お手入れ | ★★★★☆ |
| 耐久性 | ★★★★★ |
| 総合評価 | 4.7点 |
| コスパ | ★★★★★ |
|---|---|
| お手入れ | ★★★★☆ |
| 耐久性 | ★★★★★ |
| 総合評価 | 4.7点 |

愛用者
ちょっとしたお料理に便利
初めて土鍋でご飯を炊きましたが、ふっくらと炊き上がりとてもおいしくなりました。これは病みつきになりそうですね。そのほかにも、ちょっと一人分のお料理を作るときなどにも使っていて、ちょうどいいサイズで便利です。(K.K.さん/女性/60歳/主婦)
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| コスパ | ★★★★☆ |
|---|---|
| お手入れ | ★★★★☆ |
| 耐久性 | ★★★★★ |
| 総合評価 | 4.3点 |
| コスパ | ★★★★☆ |
|---|---|
| お手入れ | ★★★★☆ |
| 耐久性 | ★★★★★ |
| 総合評価 | 4.3点 |

愛用者
焦げ付きにくく洗いやすい
セラミックコーティングなので、料理が焦げ付かず洗いやすいのが特徴です。また、清潔さもキープできます。料理が冷めにくく、温かい料理を長時間楽しめるのも魅力です。見た目も美しく、伝統的なデザインがキッチンを彩ります。高品質ながらも手頃な値段に満足しています。(T.K.さん/男性/55歳/自営業)
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| コスパ | ★★★★☆ |
|---|---|
| お手入れ | ★★★★★ |
| 耐久性 | ★★★★☆ |
| 総合評価 | 4.3点 |
| コスパ | ★★★★☆ |
|---|---|
| お手入れ | ★★★★★ |
| 耐久性 | ★★★★☆ |
| 総合評価 | 4.3点 |
【価格別】おすすめの土鍋
ここからは、おすすめの土鍋を価格別で紹介していきます。
【1,000円以下】一人用に向くミニサイズ
1,000円以下で購入できる土鍋は、一人用のミニサイズがメイン。一人鍋やちょっとした料理の盛り付けなどにも使えますよ。
1人用にぴったり、気軽に楽しんでみたい人に
1人用にぴったりサイズ、直火専用の土鍋です。鍋焼きうどんや雑炊など、一人の昼食や小腹が空いたときの夜食など、手軽にパパっと作りたいときに便利。お値段も手ごろなので、初めて土鍋を使ってみようかな?と考えている人も手に取りやすいですね。
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| 対応人数 | 1人 |
|---|---|
| 材質 | 陶器 |
| カラー | ブラック |
| IH対応 | × |
| 対応人数 | 1人 |
|---|---|
| 材質 | 陶器 |
| カラー | ブラック |
| IH対応 | × |
一人で手軽に食べたいときにちょうどいいサイズ
span class="text_mark text_strong">一人分だけ作りたいとき、簡単にお鍋一つで済ませたいときにちょうどいいサイズの一人用の土鍋です。ベージュの明るい色味に刷毛目がおしゃれ。雑炊やうどんなども、この土鍋なら料亭のような気分が味わえそうですね。
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| 対応人数 | 1人 |
|---|---|
| 材質 | 刷毛目柄 土鍋 4号 |
| カラー | - |
| IH対応 | × |
| 対応人数 | 1人 |
|---|---|
| 材質 | 刷毛目柄 土鍋 4号 |
| カラー | - |
| IH対応 | × |
フタが茶碗になり便利な一人用鍋
フタが茶碗になるので、洗い物も少なくて済み、便利な一人用サイズの土鍋です。深型でふちが高いので吹きこぼれにくく、一人分の鍋料理も安心して調理できます。具材もたくさん入れられるので、これ1つで手軽に満足な具だくさんの鍋や煮込み料理などを楽しめます。
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| 対応人数 | 1人 |
|---|---|
| 材質 | 陶磁器 |
| カラー | ホワイト |
| IH対応 | × |
| 対応人数 | 1人 |
|---|---|
| 材質 | 陶磁器 |
| カラー | ホワイト |
| IH対応 | × |
【3,000円前後】高コスパのスタンダード土鍋
価格と機能がちょうどいいバランスのスタンダードモデル。大切に使えば長持ちさせることも可能です。一番コスパがいい価格帯かもしれません。

1~2人用鍋におすすめのミニ土鍋
使い勝手のいい7号サイズは、1人暮らしやカップルの方などにおすすめ。土鍋の内側に水位の目盛が付いているので、おいしい土鍋ご飯を炊いてもよいでしょう。オシャレな形状なので、土鍋を囲んだ食卓を演出するのにも向いています。
和食だけではなく、チキンクリームシチューやミネストローネなどの料理にも最適。価格もお手ごろなので、初めて土鍋を購入するという方にもピッタリです。
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| 対応人数 | 1~2人 |
|---|---|
| 材質 | 胴部:耐熱陶器、蓋:陶器 |
| カラー | 瑠璃色 |
| IH対応 | × |
| 対応人数 | 1~2人 |
|---|---|
| 材質 | 胴部:耐熱陶器、蓋:陶器 |
| カラー | 瑠璃色 |
| IH対応 | × |
安くてコスパ抜群のおしゃれ土鍋
新潟県三条市にあるキッチン用品メーカー、パール金属の土鍋です。やわらかいタッチで描かれたさくらの柄がかわいらしいですね。
サイズは6号から10号まで幅広く展開していて、ご家族の人数や使用シーンに合わせて好きなサイズを選ぶことができます。安価なので、気軽に購入できるのもポイントです。
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| 対応人数 | 3~4人 |
|---|---|
| 材質 | 陶器 |
| カラー | さくら |
| IH対応 | × |
| 対応人数 | 3~4人 |
|---|---|
| 材質 | 陶器 |
| カラー | さくら |
| IH対応 | × |
【10,000円以上】高品質な土鍋が手に入る
品質にこだわってつくられた土鍋が揃っているので、こんな土鍋がほしい! と明確に決まっている人にぴったりです。
シンプルで近代的なデザインが特徴
スタイリッシュなデザインのこちらは、プロダクトデザイナーの秋田道夫さんがデザインしたもの。鍋底をフラットにし、持ち手を外側ではなく内側にくぼませてつくることで、収納しやすいよう工夫されています。
モノトーンのシンプルなデザインは、インテリアにもなじみそうですね。IH対応、オーブンや電子レンジにも対応していて、機能性もじゅうぶんです。
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| 対応人数 | L:2~3人(S:1~2人) |
|---|---|
| 材質 | 本体:耐熱陶器、金属プレート:ステンレス、焦げ付き防止プレート:耐熱陶器 |
| カラー | ホワイト、ブラック |
| IH対応 | ○ |
| 対応人数 | L:2~3人(S:1~2人) |
|---|---|
| 材質 | 本体:耐熱陶器、金属プレート:ステンレス、焦げ付き防止プレート:耐熱陶器 |
| カラー | ホワイト、ブラック |
| IH対応 | ○ |
ギフトにぴったり! 名前が入れられる
岐阜県瑞浪市でひとつひとつ丁寧に作られている土鍋です。鍋のフタに立体でアルファベットの名前を入れることができるので、結婚祝いなどのギフトにも喜ばれそうです。
また、カラーバリエーションも豊富でポップな色合いからシックな色合いまで幅広く選べます。北欧風のおしゃれなデザインで、ついつい使いたくなってしまうでしょう。
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| 対応人数 | 4~5人 |
|---|---|
| 材質 | 陶器 |
| カラー | ブルー、オレンジ、ピンク、ホワイト、ブラウン、グリーン、グレー、ブラック、イエロー、トルコブルー |
| IH対応 | ○ |
| 対応人数 | 4~5人 |
|---|---|
| 材質 | 陶器 |
| カラー | ブルー、オレンジ、ピンク、ホワイト、ブラウン、グリーン、グレー、ブラック、イエロー、トルコブルー |
| IH対応 | ○ |
火加減いらずで吹きこぼれなしの簡単調理
ガスの直火専用の土鍋です。炊飯時には、途中で火加減を調整する必要がなく、中強火だけ。フタから蒸気が出たら火を止めて蒸らしたら完成です。空焚きもできるので、ローストチキンのようなメニューも可能です。もちろん、炊き込みご飯や煮込み料理にも。「陶製すのこ」を使えば蒸し料理もできます。熱々をそのまま食卓に出してもスタイリッシュな見た目で、どんなメニューも見た目でワンランクアップさせてくれます。
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| 対応人数 | - |
|---|---|
| 材質 | 陶磁器 |
| カラー | ブラック |
| IH対応 | × |
| 対応人数 | - |
|---|---|
| 材質 | 陶磁器 |
| カラー | ブラック |
| IH対応 | × |
1つで6役の万能土鍋
炊飯、煮る、炒める、蒸す、無水調理、オーブン料理と、これ1つで6種類の調理が可能な万能な土鍋です。土鍋の遠赤外線効果と、高い密閉性により、食材のうまみをしっかりじっくり引き出し、よりおいしく仕上げてくれます。食卓にそのまま出してもおしゃれなデザインなので、普段使いはもちろん、パーティーシーンでも食卓を華やかに彩ってくれます。
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| 対応人数 | 2~4人 |
|---|---|
| 材質 | 陶磁器 |
| カラー | ホワイト・ブラック |
| IH対応 | × |
| 対応人数 | 2~4人 |
|---|---|
| 材質 | 陶磁器 |
| カラー | ホワイト・ブラック |
| IH対応 | × |
「土鍋」のおすすめ商品の比較一覧表
| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 対応人数 | 材質 | カラー | IH対応 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ishigaki(イシガキ)『収納性がいい土鍋 5号』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
鍋キューブ1つにぴったりサイズ | 1人 | 本体:耐熱陶器 蓋:陶器 | ホワイト | × |
| Kakusee(カクセー)『土鍋 5号』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
土鍋のイメージを覆す軽さが扱いやすい | 1人 | 本体:耐熱陶器、蓋:陶器 | 黒・紺 | × |
| 青雲商店『韓国土鍋 トッペギ 4号』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月19日時点 での税込価格 |
韓国料理を見た目でも楽しみたい人に | 1~2人 | 陶器 | ブルー | - |
| 三鈴陶器『萬古焼 ごはん鍋』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
一人暮らしにも最適! 萬古焼で炊き上げる極上ご飯 | 2~3人 | 耐熱陶器 | こげ茶 | × |
| 三鈴陶器『トクサ 絵付け土鍋』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
ファミリー向けの大型土鍋 | 2〜3人 | 耐熱陶器 | トクサ柄 | × |
| 陶器のふる里『10種のフタから選べる土鍋』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
フタの組み合わせ自由!好みの土鍋がきっと見つかる | 2人 | 蓋:磁器、本体:超耐熱陶器 | 10種 | - |
| 長谷園『伊賀土鍋 利休十草』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
確かな品質の日本製土鍋 | 3~5人 | 陶器 | 利休十草 | × |
| M.STYLE(エムスタイル)『Karl(カール)土鍋 9号』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
一般的な土鍋の約1/2の驚きの軽さ | 4~5人 | 高耐熱陶器 | ベージュ・グレー | ◯(オールメタル加熱方式IHは非対応) |
| TOJIKI TONYA(トウジキトンヤ)『伊賀土鍋 8号』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
「育てる土鍋」であなただけのごちそうを | 3~4人 | 耐熱陶器 | ブラック・ホワイト | × |
| MIYAWO(ミヤオ)『土鍋 サークル / グラデーション』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
においが残りにくいからどんな料理にも毎日使える | 3~4人 | 本体:高耐熱セラミック、蓋:硬質陶器 | サークル・グラデーション | ◯ |
| HARIO(ハリオ)『フタがガラスの土鍋9号』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
中身が見えるガラスのフタが使いやすい | 3~4人 | 鍋:耐熱陶器・フタ:耐熱ガラス | ブラック・ホワイト | × |
| 長谷園『ふっくらさん 黒らく』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
蓋を裏返すと器に、老舗メーカーがつくる万能土鍋 | 2~3人 | 陶器 | 黒らく | × |
| GIMPO(銀峯陶器)『菊花 土鍋 萬古焼 9号』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
煮込み料理ならこの土鍋! | 3〜4人 | 陶器 | ブルー・ブラウン・ホワイト・マゼンタ | × |
| Living(リビング)『New宴 土鍋 8号』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
吹きこぼれにくく、香ばしいご飯も炊ける | 3~4人 | 陶磁器 | ブラック/ホワイト | × |
| 長谷園『みそ汁鍋 大』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
火を止めた後の余熱でお料理をおいしく | 3~4人 | 陶磁器 | イエロー | × |
| 長谷園『かまどさん ご飯 鍋 二合炊き(ACT-03)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
火加減要らずでおいしいご飯が炊ける、伊賀焼土鍋 | 2~3人 | 粗土 | -- | × |
| HARIO(ハリオ)『フタがガラスのご飯釜』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
なかを確認しながら炊き上げられる | 2~3人 | フタ:耐熱ガラス、鍋身:耐熱陶器、ツマミ:ポリプロピレン・シリコーンゴム | ブラック | ×(IH対応モデルもあり) |
| Tsukamoto(つかもと)『かまっこ 一合炊き』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
手軽に簡単に土鍋ご飯を楽しめる | - | 陶器 | ブラウン・ブラック・ホワイト | × |
| TAMAKI『土鍋 2合用』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
白米から炊き込みご飯まで土鍋ごはんが楽しめる | - | 本体:高耐熱セラミック・蓋:硬質陶器 | ブラック | × |
| たいせい窯『ご飯鍋 5合炊き』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
二重蓋構造でふっくらおいしいご飯が炊ける | - | 耐熱陶器 | ホワイト・ブラック | × |
| プライムダイレクト『伊賀ノ匠』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
レンジで10分、手軽なお一人様サイズ | - | 陶器 | ブラック | × |
| Ishigaki(イシガキ)『デリッシュライフ 炊飯土鍋』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
二重ぶた構造でもっちりつやつやご飯 | - | 本体:耐熱陶器、蓋:陶器 | ブラック | × |
| TAMAKI『土鍋 TOTE T-928486』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
和洋何でもお料理が映える | 4~5人 | 蓋:硬質陶器、本体:高耐熱セラミック | ホワイト | × |
| KINTO(キントー)『KAKOMI IH土鍋(25191)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
シンプルなデザインで蒸し料理にも最適 | 1~2人(1.2L) | 胴部:高耐熱陶器、蓋・すのこ:陶器 | ホワイト、ブラック | 〇 |
| 銀峯陶器『萬古焼 花三島 IH対応』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
レンジやオーブンでも使えるオールラウンダー | 2~3人 | 胴部:耐熱陶器、蓋:陶器 | - | 〇 |
| Molatura(モラトゥーラ)『ベストポット』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
他にはないミニマルなデザイン性がツボ! | 2~4人 | ステンレス、カーボン、セラミック、鋳鉄、ホーロー | ホワイト・グリーン・イエロー・ピンク・ブラック・オーシャンブルー・インディゴブルー | 〇 |
| 武田コーポレーション(Takeda corporation)『一人用土鍋17cm』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
1人用にぴったり、気軽に楽しんでみたい人に | 1人 | 陶器 | ブラック | × |
| Living(リビング)『刷毛目柄 土鍋 4号』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
一人で手軽に食べたいときにちょうどいいサイズ | 1人 | 刷毛目柄 土鍋 4号 | - | × |
| Living(リビング)『蓋がお茶碗にもなる土鍋 17cm』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
フタが茶碗になり便利な一人用鍋 | 1人 | 陶磁器 | ホワイト | × |
| 銀峯陶器『菊花 7号』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
1~2人用鍋におすすめのミニ土鍋 | 1~2人 | 胴部:耐熱陶器、蓋:陶器 | 瑠璃色 | × |
| パール金属『土鍋 さくら』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
安くてコスパ抜群のおしゃれ土鍋 | 3~4人 | 陶器 | さくら | × |
| セラミックジャパン『do-nabe IH(DN-240IH-WH)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
シンプルで近代的なデザインが特徴 | L:2~3人(S:1~2人) | 本体:耐熱陶器、金属プレート:ステンレス、焦げ付き防止プレート:耐熱陶器 | ホワイト、ブラック | ○ |
| 手作り工房 夕立窯『立体アルファベット土鍋』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
ギフトにぴったり! 名前が入れられる | 4~5人 | 陶器 | ブルー、オレンジ、ピンク、ホワイト、ブラウン、グリーン、グレー、ブラック、イエロー、トルコブルー | ○ |
| 長谷園『かまどさんプレミアム 三合炊き』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
火加減いらずで吹きこぼれなしの簡単調理 | - | 陶磁器 | ブラック | × |
| KYOTOH(京陶窯業)『DONABE 205』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
1つで6役の万能土鍋 | 2~4人 | 陶磁器 | ホワイト・ブラック | × |
通販サイトの最新人気ランキングを参考にする 土鍋の売れ筋をチェック
Amazon、楽天市場での土鍋の売れ筋ランキングも参考にしてみてください。
※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。
人気メーカーの特徴と比較
サイズや用途は決まっているけど、どこのメーカーやブランドがいいのか迷ってしまう……、という方は、メーカーやブランドで決めるというのもひとつの手です。
多くの利用者から評価されているので、安心して使うことができますよ。
長谷園
1832年より続く伝統と技術を継承する、伊賀焼の郷「長谷園」。「登り窯」や「大正館」などが国の登録有形文化財になっています。長谷園が目指しているのは、土鍋製品を通して、おいしいものを楽しく食べたい、という人びとの想いに応えること。
土鍋の技術を応用した炊飯専用の土鍋「かまどさん」が人気。ほかにも、「みそしる鍋」「ヘルシー蒸し鍋」燻製が作れる「いぶしぎん」、洋風のオーブン料理も作れる「ビストロ鍋」など多種多様な土鍋を開発しているブランドです。
三鈴陶器
萬古焼の著名なブランドであるのが「三鈴陶器」。昭和40年の創業以来、ご飯鍋・蒸し鍋・燻製鍋・パエリア鍋など、幅広い料理に使えるオリジナル製品を多数作り続けています。
三鈴陶器の耐熱陶器に対するこだわりは高く、厳選した6種類の耐熱陶土、20種類以上の釉薬を組み合わせることにより、焼き物ならではのきれいな質感を表現しています。土の管理から焼き上げ過程に至るまで、熟練した職人の技術によって高品質な土鍋が作られていますよ。
HARIO(ハリオ)
「ハリオ」は1921年に創業した耐熱ガラスメーカー。ハリオのコーヒードリッパーやサーバーを持っている人も多いでしょう。最近は、耐熱ガラスを制作してきたメーカー独自の技術を活かした「ガラスフタのある土鍋」が注目を集めています。
なかでもおすすめなのが、炊飯用。ガラス製なのでご飯の炊き具合が見えたり、炊飯が終わるとホイッスルが鳴ったりするので、初めて土鍋でご飯を炊く初心者にも使いやすいです。土鍋本体は萬古焼のものを採用しているので品質に関しても安心できますよ。
ニトリ
ニトリでは、ガス火・オーブン・電子レンジで使える土鍋が販売されています。シンプルで温かみのあるデザインで和洋どちらの料理にも合います。
持ち手がシリコン製になっているので持ち運びもらくらく。IH対応の商品は、「土鍋風」なので確認してから購入しましょう。
無印良品
どんな食卓にも合うカラーと形状の無印良品の土鍋。デザインは柄がなくてシンプル、洗練されたルックスが人気です。
IH対応や一人鍋が楽しめるこなべ、ごはんが炊ける土釜などラインナップも充実。家族の人数に合わせてサイズも選べます。
使用前に行う「目止め」の方法は?
土を焼いて作る土鍋などの陶器には、無数の穴が開いています。何もせずに鍋を使うと水が鍋に染み込んで、鍋の水漏れやひび割れ、におい移りの原因となることも。
そのため、土鍋は、使用する前に「目止め」という作業を行う必要があります。具体的な目止め方法は下記のとおりです。
▼目止め処理の方法
ステップ1:土鍋を水でよく洗ってしっかりと乾燥させる
ステップ2:土鍋の8分目まで、お米のとぎ汁を入れる
とぎ汁がない場合は、水に片栗粉や小麦粉を水の量の1/5程度を入れて混ぜる
ステップ3:弱火で1時間程度じっくりと煮込む
お米を入れた場合は、そのままおかゆにすることも可能
この「目止め」を行うだけで土鍋の寿命がグッと延びるので、購入後、使用前には忘れずに行いましょう。
土鍋の正しいお手入れ方法
大切な土鍋を長く使うために、こちらの3つのポイントを覚えておきましょう。
・冷めてから洗う
土鍋は温度変化に弱いです。熱いうちに洗うとひび割れの原因となるので、十分に冷めてから流水で洗浄しましょう。
・使い終わったらしっかりと乾かす
土鍋は吸水性がとても高いので、水分が残っているとカビが発生する可能性があります。収納棚などに入れる前に風通しのいい場所などでしっかりと乾かすことが大切です。
・おこげなどが落ちない場合は、お湯を沸かす
土鍋にこびりついたおこげなどを取ろうとしてスポンジなどで強く擦るとキズがつき、そこから劣化するおそれも。土鍋でお湯を沸かして汚れを浮かせることで、簡単に汚れが取れるようになります。
土鍋でおいしいご飯を炊く方法
土鍋でご飯を炊いたことはありますか? お米ひと粒ずつが、ふっくらと香り良く炊き上がり、とてもおいしく仕上がりますよ。
飯盒気にある火力調整や、タイマー機能がないので、うまく炊けるか心配になってしまうかもしれないですが、一度炊いてみると意外に簡単なんです。こちらを参考にぜひ挑戦してみてください。
ステップ1:お米を洗って水に浸ける
水の量はお米の1.1倍。夏なら1時間、冬なら2時間程度。冷蔵庫に入れてしっかり吸水させると、よりおいしくなる。固めに仕上げるなら水分を若干少なめに。
ステップ2:約8分ほど火にかけて沸騰させる火加減は中火と強火の間くらい。
ステップ3:火を小さくして12~15分ほど炊く
沸騰させたままで大丈夫。おこげを作るなら、最後に20~30秒程度、火を強める。
ステップ4:火を止めて15分ほど蒸らす
このとき、鍋の中の様子を見ようと開けないこと。
ステップ5:しゃもじで混ぜて蒸気を逃がす
鍋底からしっかり混ぜるのが大切。
ステップ6:おひつや皿に移せば完成
料理研究家からのアドバイス
土鍋で炊いたご飯を食べてもらいたい!
土鍋と聞くと、どうしても手間がかかりそうで、ご自身には難しい調理道具だと思っている方も多いかもしれません。
そんな方は、ぜひ土鍋で炊いたご飯を味わってみてください。炊飯器とはまるで違ったご飯を食べれば、きっと土鍋の魅力に気がつくはず。
使いはじめのとき、米のとぎ汁やおかゆを炊き、目止め(※)をしてください。土鍋に少々ヒビが入った場合も同様で、長持ちしますし、愛着も生まれます。
お気に入りのいい土鍋を見つければ、きっと毎日の食事が楽しくなることでしょう。
※新しい土鍋で米や小麦粉を入れた汁を煮て、表面の細かい穴をふさぐこと。煮汁や臭いがしみ込むのを防ぎます。
【関連記事】そのほかの鍋をチェック!
用途や形状、デザインなど自分に合った土鍋を選ぼう!
この記事では、土鍋の選び方やおすすめ商品、おいしいご飯の炊き方などを紹介しました。
土鍋にもさまざまな形状や材質があります。何人で食べるかだけでなく、用途に合った最適な土鍋を選ぶようにしましょう。
おすすめ商品・口コミの投稿はこちら
※メーカーや販売店の方は、ページ下部の「お問い合わせはこちら」から商品情報をお送りください。
ユーザーのおすすめ商品や口コミ情報は、マイナビおすすめナビを閲覧したユーザー、マイナビニュース会員、外部パートナー企業と契約する一般ユーザーからの投稿をもとにしています。
◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。