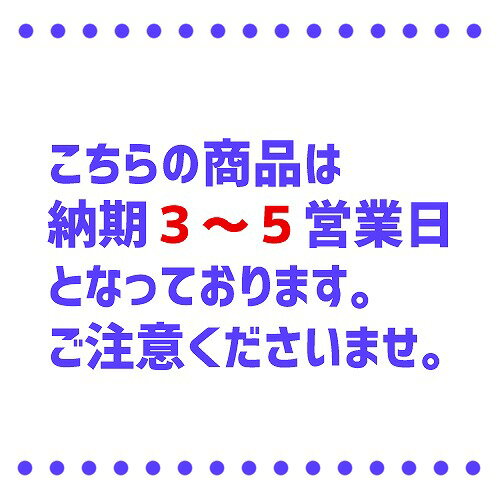| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 軸径 | 長さ | 軸素材 | 毛素材 | 毛質 | 穂の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志昌堂 国産熊野筆『太筆 4号白峰 白毛(FF-0130)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月24日時点 での税込価格 |
確かな弾力で初心者や子ども用にぴったりの書道筆 | - | - | - | 山羊・馬 | ややかたい | - |
| あかしや『桂林 [けいりん] (AL-150)』 |
![あかしや『桂林 [けいりん] (AL-150)』](https://m.media-amazon.com/images/I/31IO6MmNmyL._SL500_.jpg)
|
※各社通販サイトの 2025年2月24日時点 での税込価格 |
力強い表現が可能に! 脱初心者用の書道筆 | 13mm | 268mm | - | 馬尾脇毛・羊毛・狸毛 | やや硬め | 中鋒 |
| あかしや『書道筆 太筆 千字文 3号(PL-104)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月24日時点 での税込価格 |
柔らかく墨含みがよいのが特徴 | 約10mm | 約230mm | 竹 | 馬尾脇毛、羊毛、狸毛 | 柔らかく、墨含みが良い | 中鋒 |
| あかしや『3号 一條秋水 [いちじょうしゅうすい](PL-201)』 |
』](https://m.media-amazon.com/images/I/31KherLj-ZL._SL500_.jpg)
|
※各社通販サイトの 2025年2月24日時点 での税込価格 |
大胆に筆を動かせて漢字を美しく表現できる書道筆 | 12.5mm | 256mm | - | 馬尾脇毛・羊毛・狸毛・鹿毛 | 柔 | 中鋒 |
| あかしや『書写楽 [しょしゃらく] (ASP-51)』 |
![あかしや『書写楽 [しょしゃらく] (ASP-51)』](https://m.media-amazon.com/images/I/31OCy9LCyfL._SL500_.jpg)
|
※各社通販サイトの 2025年2月24日時点 での税込価格 |
弾力のある人造毛製の細筆で基本を学べる | 7.8mm | 204mm | - | 特殊ポリエステル毛 | ほどよい硬さ | 中鋒 |
| 呉竹『太筆 清晞 [せいき] 3号茶毛(JC336-3)』 |
![呉竹『太筆 清晞 [せいき] 3号茶毛(JC336-3)』](https://m.media-amazon.com/images/I/41rVIsQuVAL._SL500_.jpg)
|
※各社通販サイトの 2025年2月24日時点 での税込価格 |
力強い線でややかためタイプの3号茶毛の書道筆 | 13.5mm | 245mm | 天然竹軸 | 羊毛・馬毛 | やや硬め | 中鋒 |
| 呉竹 くれ竹優筆『のどか 7号茶毛パック(JE51-7S)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月24日時点 での税込価格 |
人造の毛でお手入れがかんたんな細筆 | 7.6mm | 203mm | ABS | PEs | - | - |
| 呉竹『太筆 光春 3号白毛パック(JC317-3S)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月24日時点 での税込価格 |
弾力性が強く力強いラインが書けるだるま筆 | 12.3mm | 255mm | 天然竹軸 | 羊毛・白天尾 | 硬め | 中鋒 |
| 広島筆産業『地 兼毫墨禅(F-29)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月24日時点 での税込価格 |
やわらかめで上級者向けの3号竹軸筆 | 12mm | 260mm | 竹軸 | 尾脇毛・羊毛・馬毛 | やわらかめ | - |
| 広島筆産業『剛毫三号 書懐(F-53)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月24日時点 での税込価格 |
楷書用としてつくられた剛毫の広島筆 | 11mm | 270mm | 竹軸 | 馬尾脇毛・羊毛・天尾・狸 | - | - |
| 一休園『兼毫半紙用 短鋒(127340)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月24日時点 での税込価格 |
書きやすさを求めた伝統工芸品の短鋒筆 | 13mm | - | - | 馬毛・狸毛 | - | 短鋒 |
| 一休園『古今』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月24日時点 での税込価格 |
イタチの毛を使った広島熊野産の細筆 | 6mm | - | - | イタチ | - | - |
| 墨運堂『写経筆白軸(23117)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月24日時点 での税込価格 |
イタチ毛で写経に向いている白軸筆 | 7.5mm | 184mm | - | イタチ毛 | - | - |
| 志昌堂 書初筆 6号 白毛 B-51 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月24日時点 での税込価格 |
書き初め用にぴったりの6号太筆 | - | - | - | 馬毛 | ほどよい硬さ | - |
| 文宏堂『細光峰毫 白鳳 六号』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月24日時点 での税込価格 |
高級な首周りの毛を使用した幻の筆 | 10mm | - | - | 羊毛 | やわらかめ | - |
目的に合う筆をチェック!

出典:マイナビおすすめナビ

出典:マイナビおすすめナビ
書道筆は毛の種類やサイズなどがさまざま。どんな文字を書きたいか、どんな用紙に書きたいかによって、選ぶべき製品が変わってくるので上の図を参考にしてみてくださいね。
書道筆の選び方 初心者の方は必見!
それでは、書道筆の基本的な選び方を見ていきましょう。
【1】よい書道筆の条件「四徳(しとく)」で選ぶ
【2】書きたい文字に合わせて毛の種類を選ぶ
【3】軸の形で選ぶ
【4】穂先の長さもチェック
【5】筆の太さと号数をチェック
上記のポイントをおさえることで、より具体的に欲しい機能を知ることができます。一つひとつ解説していきます。
【1】よい書道筆の条件「四徳(尖・斉・円・健)」で選ぶ
よい書道筆の条件としてあげられるのが、「四徳(しとく)」。四徳には「尖(せん)」「斉(さい)」「円(えん)」「健(けん)」の4つの項目があり、これらがそろっているものを選ぶといいといわれています。
各項目について、詳しく紹介していきましょう。
尖(せん)|穂先が尖っていること
四徳の一つ目の条件は、「尖(せん)」です。これは字のとおり、書道筆の穂先が尖っているかどうかというチェックポイントのこと。
筆の毛の先がしっかりと尖って形づくられているなら、まとまりがよく、思ったように筆で穂先の動きをコントロールすることが可能になります。尖っていなければ、きちんと筆を動かしたつもりでも、まとまりのない字になってしまいます。
斉(さい)|穂全体のまとまりがいいこと
四徳の二つ目は、「斉(さい)」です。これは、書道筆の穂先がきめこまかく整っていて、まとまりがあるかどうかをチェックすることを示しています。
たくさんの毛の集まりである筆は、毛がよくまとまっていることによって、よく墨を含ませることができます。また、まとまりから外れた小さな毛が、書面を汚してしまうことも防げます。
円(えん)|穂の形が円錐形になっていること
四徳の三つ目は、「円(えん)」です。これは、書道筆の穂がきれいな円錐形になっているかどうかをチェックするということを促してくれます。
筆の穂が円錐形になっているなら、まんべんなく墨を穂に含ませることができるようになり、なめらかな線を書けますし、ボリュームのある力強い字を書くこともできるようになります。
健(けん)|毛にコシと弾力性があること
四徳の四つ目は、「健(けん)」です。これは、書道筆の穂先にコシがあり、ほどよい弾力をもっているかどうかをチェックするというポイントです。
コシと弾力があるなら、しなやかでスムーズな動きができるので、書道のみどころである、「とめ」・「はね」・「はらい」などの表現を自在に操れるようになり、より書くことを楽しめます。
【2】書きたい文字に合わせて毛の種類を選ぶ
筆にはいろいろなタイプがあるので、どんな文字を表現したいかによって、選ぶ筆の種類も異なります。
「楷書」には弾力性の高い剛毛、「行書・草書」にはやわらかい柔毛を
楷書で大きめの文字を書きたいなら、ひと文字ひと文字をじっくり書けるように、コシがあって弾力性が高く、筆のレスポンスが高い剛毛筆(ごうもうひつ)を選びましょう。
一方、行書や草書で書きたいというケースには、筆の穂にたくさんの墨を含んで一気に書きあげることができるように、穂先のコシがやわらかい柔毛筆(じゅうもうひつ)を選びましょう。
初心者には毛のかたさのバランスの取れた兼豪筆がおすすめ
あまり書道の経験がないなら、扱いやすいタイプの筆を選ぶようにしましょう。バランスが取れていて扱いやすいのは、弾力性のある剛毛とやわらかい柔毛がちょうどよく組み合わされた兼豪(けんごう)筆です。
筆が墨を含む量や、コシの強さの加減もバランスがよく、くせがないので、初心者の方がこれから書道を楽しむというケースにぴったりです。
【3】軸の形で選ぶ
軸のタイプは大きく分けて、「だるま軸タイプ」と「ストレート軸タイプ」があります。
子供でも扱いやすいだるま軸タイプ
だるま軸タイプは、持ち手の部分は細く、穂の根本に向かって太くなっているタイプの筆です。そのため、手が小さくて太い軸ではうまくにぎれないという方でも、穂の大きな筆を持てるようになります。
子どもでも扱いやすいタイプなので、学童用としても多く用いられています。
指先で太さが感じられるストレート軸タイプ
穂の根本と軸がほぼ同じくらいの太さに作られている筆がストレート軸タイプです。
だるま軸タイプよりも軽く、持ち手が太くなるため、書きにくいと感じる方もいるかもしれません。軸の太さは好みも関係するので、いろいろ使ってみるのもよいでしょう。
【4】穂先の長さもチェック
初心者なら、持っている位置から穂先をコントロールしやすいので、筆の穂の長さは長くないほうがよいとされています。
経験を積んで、腕全体で文字を書くという感覚を持っている方なら、長い穂を持っていてより表現力を発揮できるタイプの筆に挑戦することができるでしょう。穂が長ければ、線の強弱などのディテールをよりこまかく表現できます。
【5】筆の太さと号数をチェック
筆のサイズは、穂の太さによって1~10号に分類されます。号数が大きくなるにつれて、筆の太さは細くなります。
書き初めなどの大きな字を書くときにぴったりなのは1~4号(太筆)、半紙や色紙には5~7号(中筆)、手紙や写経などの小さい字を書くなら8~10号(細筆)がおすすめです。
書道師範・筆耕士からのアドバイス
まず筆でなにを書きたいのか決めましょう
手紙や金封袋など実用的な文字を書く場合と半紙に漢字を書く場合、かな文字と漢字を書く場合で筆の太さや種類が違います。
初心者が練習するだけだから安価な筆でいいと思われがちですが、技術が上達してこそ筆を扱えるのであって、初心者はうまく扱えません。初心者用の筆はかたい毛とやわらかい毛が混ざった兼豪筆で扱いやすいです。筆が扱えるようになってはじめて文字が上達するので、いい筆を用意しましょう。
書道筆のおすすめ15選 有名ブランド厳選! 趣味の書道や子どもの習字に!
書道師範・筆耕士のぺんらいとさんと編集部で、おすすめの書道用筆を厳選! 初心者向けのほか、上級者向けも紹介するので、ぜひ最後までチェックしてみてくださいね。

太筆で半紙に漢字を書くならば、志昌堂『太筆白毛4号白峰』がおすすめ。穂の長さが少し短めなので、初心者でも扱いやすいです。
確かな弾力で初心者や子ども用にぴったりの書道筆
やや短穂型タイプの白毛の書道筆です。広島県熊野で生産された高品質な筆で、書き味に確かな弾力があり、初心者でも扱いやすく使いこなすことができるでしょう。
筆の軸が細く、穂先の部分との接続がだるま型になっているので、手が小さい方や子どもでも扱いやすいのが特徴です。
※各社通販サイトの 2025年2月24日時点 での税込価格
| 軸径 | - |
|---|---|
| 長さ | - |
| 軸素材 | - |
| 毛素材 | 山羊・馬 |
| 毛質 | ややかたい |
| 穂の長さ | - |
| 軸径 | - |
|---|---|
| 長さ | - |
| 軸素材 | - |
| 毛素材 | 山羊・馬 |
| 毛質 | ややかたい |
| 穂の長さ | - |

慣れてきていろいろな書体に挑戦するなら、あかしや『桂林』を選ぶといいでしょう。3号で少し太さがあります。
力強い表現が可能に! 脱初心者用の書道筆
書道教室や趣味としての書道で、中級者向けとして開発されている書道筆です。鋭く力強い表現ができるので、書道の楽しさをより体感できるようになります。
馬尾脇毛や羊毛や狸毛など、いろいろな獣毛を毛の部位からセレクトして組み合わせた書き味のよい穂が特徴。
12.5mmの筆径と268mmの長さと18gの重量というバランスで、とても持ちやすく、あかしやの筆匠たちの高い技術を感じられます。
※各社通販サイトの 2025年2月24日時点 での税込価格
| 軸径 | 13mm |
|---|---|
| 長さ | 268mm |
| 軸素材 | - |
| 毛素材 | 馬尾脇毛・羊毛・狸毛 |
| 毛質 | やや硬め |
| 穂の長さ | 中鋒 |
| 軸径 | 13mm |
|---|---|
| 長さ | 268mm |
| 軸素材 | - |
| 毛素材 | 馬尾脇毛・羊毛・狸毛 |
| 毛質 | やや硬め |
| 穂の長さ | 中鋒 |
柔らかく墨含みがよいのが特徴
あかしやの『書道筆 太筆 半紙漢字用 PL104』は、初心者から上級者まで幅広く使用できる高品質な書道筆です。軸は竹製で、長さは約230mm、軸径は約10mmです。毛素材には馬尾脇毛、羊毛、狸毛が使用されており、柔らかく墨含みがよいのが特徴です。穂の長さは約50mmで、中鋒のためトメ・ハネ・ハライが美しく書けます。
この筆は、半紙に漢字を書くのに最適で、書道の基本を学ぶのに適しています。耐久性も高く、長く使用できるため、書道を始める方や上達を目指す方におすすめです。
※各社通販サイトの 2025年2月24日時点 での税込価格
| 軸径 | 約10mm |
|---|---|
| 長さ | 約230mm |
| 軸素材 | 竹 |
| 毛素材 | 馬尾脇毛、羊毛、狸毛 |
| 毛質 | 柔らかく、墨含みが良い |
| 穂の長さ | 中鋒 |
| 軸径 | 約10mm |
|---|---|
| 長さ | 約230mm |
| 軸素材 | 竹 |
| 毛素材 | 馬尾脇毛、羊毛、狸毛 |
| 毛質 | 柔らかく、墨含みが良い |
| 穂の長さ | 中鋒 |
大胆に筆を動かせて漢字を美しく表現できる書道筆
中級者や上級者向けの3号書道筆です。漢字を書くために起筆から収筆までを大胆に筆を動かすことが可能なので、とめ・はね・はらいなどの表現をとても美しくあらわせ、書道の趣味をじゅうぶんに楽しめるでしょう。
筆のかたさがちょうどよくなるように、さまざまな獣毛の組み合わせを、毛の部位までこだわってブレンドしてあり、筆職人のこだわりを感じられます。
※各社通販サイトの 2025年2月24日時点 での税込価格
| 軸径 | 12.5mm |
|---|---|
| 長さ | 256mm |
| 軸素材 | - |
| 毛素材 | 馬尾脇毛・羊毛・狸毛・鹿毛 |
| 毛質 | 柔 |
| 穂の長さ | 中鋒 |
| 軸径 | 12.5mm |
|---|---|
| 長さ | 256mm |
| 軸素材 | - |
| 毛素材 | 馬尾脇毛・羊毛・狸毛・鹿毛 |
| 毛質 | 柔 |
| 穂の長さ | 中鋒 |
弾力のある人造毛製の細筆で基本を学べる
あかしやの白毛の細筆です。書写や名前書きの用途に適した筆の細さになっています。特殊な人造毛でつくられていて、自然の獣毛より耐久性が格段にあがっており毛抜けや毛切れの心配がありません。
先端が鋭くなっていて、強い弾力を感じられるので、書道・習字をはじめたばかりの初心者が、漢字のハネやハライなどの基本を学ぶのに適しています。
※各社通販サイトの 2025年2月24日時点 での税込価格
| 軸径 | 7.8mm |
|---|---|
| 長さ | 204mm |
| 軸素材 | - |
| 毛素材 | 特殊ポリエステル毛 |
| 毛質 | ほどよい硬さ |
| 穂の長さ | 中鋒 |
| 軸径 | 7.8mm |
|---|---|
| 長さ | 204mm |
| 軸素材 | - |
| 毛素材 | 特殊ポリエステル毛 |
| 毛質 | ほどよい硬さ |
| 穂の長さ | 中鋒 |
力強い線でややかためタイプの3号茶毛の書道筆
清晞(せいき)は、天然の竹を軸に使用した、持ちやすさを考慮された茶毛タイプの書道筆です。羊毛と馬毛を使って、ややかためのしっかりと力強いラインが書ける筆質が特徴。毛質はねばりがあって墨含みがほどよく、耐久性があります。
穂の長さもバランス重視タイプの中鋒で、おもに楷書や行書に向いている筆です。
※各社通販サイトの 2025年2月24日時点 での税込価格
| 軸径 | 13.5mm |
|---|---|
| 長さ | 245mm |
| 軸素材 | 天然竹軸 |
| 毛素材 | 羊毛・馬毛 |
| 毛質 | やや硬め |
| 穂の長さ | 中鋒 |
| 軸径 | 13.5mm |
|---|---|
| 長さ | 245mm |
| 軸素材 | 天然竹軸 |
| 毛素材 | 羊毛・馬毛 |
| 毛質 | やや硬め |
| 穂の長さ | 中鋒 |
人造の毛でお手入れがかんたんな細筆
ABS樹脂製の軸に、人造の材質の毛を合わせた7号の茶毛タイプの書道筆です。人工的に製造された毛は、耐久性にとてもすぐれていて、腐ったり、カビになったりする心配が少なく、お手入れがかんたん。
筆質は、細筆ながら毛がやわらかいのでよくしなり、しっかりとしたラインが書けるのが特徴です。
※各社通販サイトの 2025年2月24日時点 での税込価格
| 軸径 | 7.6mm |
|---|---|
| 長さ | 203mm |
| 軸素材 | ABS |
| 毛素材 | PEs |
| 毛質 | - |
| 穂の長さ | - |
| 軸径 | 7.6mm |
|---|---|
| 長さ | 203mm |
| 軸素材 | ABS |
| 毛素材 | PEs |
| 毛質 | - |
| 穂の長さ | - |
弾力性が強く力強いラインが書けるだるま筆
3号白毛タイプの書道筆です。毛の素材には、羊毛と白天尾を使用していて穂先に弾力があり、力強い線が書けます。穂の長さは中鋒の44ミリで、しっかりと墨を穂のなかに含めてじっくりと文字をしたためることが可能です。
だるま筆なのでグリップしやすく、初心者でも上級者でもしっかりとした書き味を楽しめるでしょう。
※各社通販サイトの 2025年2月24日時点 での税込価格
| 軸径 | 12.3mm |
|---|---|
| 長さ | 255mm |
| 軸素材 | 天然竹軸 |
| 毛素材 | 羊毛・白天尾 |
| 毛質 | 硬め |
| 穂の長さ | 中鋒 |
| 軸径 | 12.3mm |
|---|---|
| 長さ | 255mm |
| 軸素材 | 天然竹軸 |
| 毛素材 | 羊毛・白天尾 |
| 毛質 | 硬め |
| 穂の長さ | 中鋒 |
やわらかめで上級者向けの3号竹軸筆
12mmの竹製ストレート軸で、やわらかめの穂先を持つ3号太筆の書道筆です。毛の素材には、尾脇毛と羊毛と馬毛を使用して、弾力がほどよくあり、中級者や上級者向けの仕様になっています。
広島筆で墨の含みがとてもよく、太い字が書けます。半紙に漢字2文字から4文字程度を快適に書くことが可能で、楷書や行書にぴったりの筆です。
※各社通販サイトの 2025年2月24日時点 での税込価格
| 軸径 | 12mm |
|---|---|
| 長さ | 260mm |
| 軸素材 | 竹軸 |
| 毛素材 | 尾脇毛・羊毛・馬毛 |
| 毛質 | やわらかめ |
| 穂の長さ | - |
| 軸径 | 12mm |
|---|---|
| 長さ | 260mm |
| 軸素材 | 竹軸 |
| 毛素材 | 尾脇毛・羊毛・馬毛 |
| 毛質 | やわらかめ |
| 穂の長さ | - |
楷書用としてつくられた剛毫の広島筆
広島県でつくられている国産の太筆です。穂の直径は11mmあり、穂先がほどよくまとまっており書きやすい書き味です。穂の長さは54mmで、墨の含みもほどよく使いやすくなっています。
毛の素材には、馬尾脇毛や羊毛や狸の毛などがブレンドして組み合わされており、ほどよい弾力で書くことができます。
竹軸のデザインも、書道をたしなむのによい雰囲気を醸し出してくれます。
※各社通販サイトの 2025年2月24日時点 での税込価格
| 軸径 | 11mm |
|---|---|
| 長さ | 270mm |
| 軸素材 | 竹軸 |
| 毛素材 | 馬尾脇毛・羊毛・天尾・狸 |
| 毛質 | - |
| 穂の長さ | - |
| 軸径 | 11mm |
|---|---|
| 長さ | 270mm |
| 軸素材 | 竹軸 |
| 毛素材 | 馬尾脇毛・羊毛・天尾・狸 |
| 毛質 | - |
| 穂の長さ | - |
書きやすさを求めた伝統工芸品の短鋒筆
馬毛と狸の毛を素材に組み合わせて使用している、日本製の半紙用の兼毫筆です。伝統工芸品として書きやすさを追求して開発された筆で、だるま軸タイプになっているのでグリップしやすくのびのびと書けます。
短鋒タイプの穂先ですから筆のコントロールがしやすく、思ったとおりの筆の運びができます。書道・習字が楽しく上達できる筆です。
※各社通販サイトの 2025年2月24日時点 での税込価格
| 軸径 | 13mm |
|---|---|
| 長さ | - |
| 軸素材 | - |
| 毛素材 | 馬毛・狸毛 |
| 毛質 | - |
| 穂の長さ | 短鋒 |
| 軸径 | 13mm |
|---|---|
| 長さ | - |
| 軸素材 | - |
| 毛素材 | 馬毛・狸毛 |
| 毛質 | - |
| 穂の長さ | 短鋒 |
イタチの毛を使った広島熊野産の細筆
熊野筆のメーカーである「一休園」がつくっている、イタチの毛がきれいに円錐型にまとまっている細筆です。直径は6mmでとても細く、こまかくかなを書き記すのに向いています。
穂の長さは28mmで筆先をコントロールしやすく、ほどよく弾力性を持っておりとても書きやすいです。筆の長さも全体の重さとのバランスが取れていて、楽しく書きすすめることが可能です。
※各社通販サイトの 2025年2月24日時点 での税込価格
| 軸径 | 6mm |
|---|---|
| 長さ | - |
| 軸素材 | - |
| 毛素材 | イタチ |
| 毛質 | - |
| 穂の長さ | - |
| 軸径 | 6mm |
|---|---|
| 長さ | - |
| 軸素材 | - |
| 毛素材 | イタチ |
| 毛質 | - |
| 穂の長さ | - |

名前を書くのに小筆を使うなら、墨運堂『写経筆白軸』がおすすめ。写経用なので細くしっかりと点画が書ける筆です。
イタチ毛で写経に向いている白軸筆
穂の軸径が3.5mmと細字で細かい文字を書くのに適している書道筆です。穂の長さは19mmとコンパクトになっており、穂先をコントロールしやすいです。イタチ毛でやわらかく、写経をするのに向いているタイプの細筆です。
軸径は細身で、筆の長さもわりと短めになっており、写経のときに出かける用に持っておくと、便利に使えるでしょう。
※各社通販サイトの 2025年2月24日時点 での税込価格
| 軸径 | 7.5mm |
|---|---|
| 長さ | 184mm |
| 軸素材 | - |
| 毛素材 | イタチ毛 |
| 毛質 | - |
| 穂の長さ | - |
| 軸径 | 7.5mm |
|---|---|
| 長さ | 184mm |
| 軸素材 | - |
| 毛素材 | イタチ毛 |
| 毛質 | - |
| 穂の長さ | - |
書き初め用にぴったりの6号太筆
書き初めや大きい紙に書くのに適しているタイプの白毛太筆です。馬毛を使用しており、ほどよいかたさの穂先の毛なので、書き味がよく使いやすいのが特徴。
毛の根本の部分は18mmととても太く、独特のだるま型の形状です。力強い太い字が書きやすい弾力があるので、子どもが学校などで書道・習字を楽しむのに向いているでしょう。
※各社通販サイトの 2025年2月24日時点 での税込価格
| 軸径 | - |
|---|---|
| 長さ | - |
| 軸素材 | - |
| 毛素材 | 馬毛 |
| 毛質 | ほどよい硬さ |
| 穂の長さ | - |
| 軸径 | - |
|---|---|
| 長さ | - |
| 軸素材 | - |
| 毛素材 | 馬毛 |
| 毛質 | ほどよい硬さ |
| 穂の長さ | - |
高級な首周りの毛を使用した幻の筆
羊毛のなかでも、首の下まわりのもっとも高級な毛を使用してつくられた、光沢のあるモデルの書道の筆です。昭和40年代の細光峰を使って作成されているとても貴重な商品。
値段は高いですが、毛の一筋一筋に力があり、毛先がきれいにまとまっており、羊毛の特徴であるやわらかさやねばりや腰の強さがあります。だるま軸でにぎりやすいのもポイント。
※各社通販サイトの 2025年2月24日時点 での税込価格
| 軸径 | 10mm |
|---|---|
| 長さ | - |
| 軸素材 | - |
| 毛素材 | 羊毛 |
| 毛質 | やわらかめ |
| 穂の長さ | - |
| 軸径 | 10mm |
|---|---|
| 長さ | - |
| 軸素材 | - |
| 毛素材 | 羊毛 |
| 毛質 | やわらかめ |
| 穂の長さ | - |
おすすめ商品の比較一覧表
| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 軸径 | 長さ | 軸素材 | 毛素材 | 毛質 | 穂の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志昌堂 国産熊野筆『太筆 4号白峰 白毛(FF-0130)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月24日時点 での税込価格 |
確かな弾力で初心者や子ども用にぴったりの書道筆 | - | - | - | 山羊・馬 | ややかたい | - |
| あかしや『桂林 [けいりん] (AL-150)』 |
![あかしや『桂林 [けいりん] (AL-150)』](https://m.media-amazon.com/images/I/31IO6MmNmyL._SL500_.jpg)
|
※各社通販サイトの 2025年2月24日時点 での税込価格 |
力強い表現が可能に! 脱初心者用の書道筆 | 13mm | 268mm | - | 馬尾脇毛・羊毛・狸毛 | やや硬め | 中鋒 |
| あかしや『書道筆 太筆 千字文 3号(PL-104)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月24日時点 での税込価格 |
柔らかく墨含みがよいのが特徴 | 約10mm | 約230mm | 竹 | 馬尾脇毛、羊毛、狸毛 | 柔らかく、墨含みが良い | 中鋒 |
| あかしや『3号 一條秋水 [いちじょうしゅうすい](PL-201)』 |
』](https://m.media-amazon.com/images/I/31KherLj-ZL._SL500_.jpg)
|
※各社通販サイトの 2025年2月24日時点 での税込価格 |
大胆に筆を動かせて漢字を美しく表現できる書道筆 | 12.5mm | 256mm | - | 馬尾脇毛・羊毛・狸毛・鹿毛 | 柔 | 中鋒 |
| あかしや『書写楽 [しょしゃらく] (ASP-51)』 |
![あかしや『書写楽 [しょしゃらく] (ASP-51)』](https://m.media-amazon.com/images/I/31OCy9LCyfL._SL500_.jpg)
|
※各社通販サイトの 2025年2月24日時点 での税込価格 |
弾力のある人造毛製の細筆で基本を学べる | 7.8mm | 204mm | - | 特殊ポリエステル毛 | ほどよい硬さ | 中鋒 |
| 呉竹『太筆 清晞 [せいき] 3号茶毛(JC336-3)』 |
![呉竹『太筆 清晞 [せいき] 3号茶毛(JC336-3)』](https://m.media-amazon.com/images/I/41rVIsQuVAL._SL500_.jpg)
|
※各社通販サイトの 2025年2月24日時点 での税込価格 |
力強い線でややかためタイプの3号茶毛の書道筆 | 13.5mm | 245mm | 天然竹軸 | 羊毛・馬毛 | やや硬め | 中鋒 |
| 呉竹 くれ竹優筆『のどか 7号茶毛パック(JE51-7S)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月24日時点 での税込価格 |
人造の毛でお手入れがかんたんな細筆 | 7.6mm | 203mm | ABS | PEs | - | - |
| 呉竹『太筆 光春 3号白毛パック(JC317-3S)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月24日時点 での税込価格 |
弾力性が強く力強いラインが書けるだるま筆 | 12.3mm | 255mm | 天然竹軸 | 羊毛・白天尾 | 硬め | 中鋒 |
| 広島筆産業『地 兼毫墨禅(F-29)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月24日時点 での税込価格 |
やわらかめで上級者向けの3号竹軸筆 | 12mm | 260mm | 竹軸 | 尾脇毛・羊毛・馬毛 | やわらかめ | - |
| 広島筆産業『剛毫三号 書懐(F-53)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月24日時点 での税込価格 |
楷書用としてつくられた剛毫の広島筆 | 11mm | 270mm | 竹軸 | 馬尾脇毛・羊毛・天尾・狸 | - | - |
| 一休園『兼毫半紙用 短鋒(127340)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月24日時点 での税込価格 |
書きやすさを求めた伝統工芸品の短鋒筆 | 13mm | - | - | 馬毛・狸毛 | - | 短鋒 |
| 一休園『古今』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月24日時点 での税込価格 |
イタチの毛を使った広島熊野産の細筆 | 6mm | - | - | イタチ | - | - |
| 墨運堂『写経筆白軸(23117)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月24日時点 での税込価格 |
イタチ毛で写経に向いている白軸筆 | 7.5mm | 184mm | - | イタチ毛 | - | - |
| 志昌堂 書初筆 6号 白毛 B-51 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月24日時点 での税込価格 |
書き初め用にぴったりの6号太筆 | - | - | - | 馬毛 | ほどよい硬さ | - |
| 文宏堂『細光峰毫 白鳳 六号』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月24日時点 での税込価格 |
高級な首周りの毛を使用した幻の筆 | 10mm | - | - | 羊毛 | やわらかめ | - |
通販サイトの最新人気ランキングを参考にする 書道筆の売れ筋をチェック
Amazon、楽天市場での書道筆の売れ筋ランキングも参考にしてみてください。
※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。
書道と習字の違いは? 定義を理解しよう
書道と習字、似ているようで実は言葉の定義に違いがあります。まず習字とは、文字通り「字を習う」という意味。小学生、中学生などの子供が授業の一環として、正しい文字の書き順や美しい字の書き方を習うためのものです。
一方、書道は芸術色が強く、書体もさまざま。型にはまらず自分の個性や芸術センスを活かして自由に表現できます。子供だけでなく大人の趣味としても人気です。
書道筆の洗い方 太さでお手入れ方法が異なる
書道筆は使ったら毎度お手入れが必要です。ここでは筆の洗い方についても紹介します。
太筆の洗い方
使用後の太筆は毛全体に墨がたっぷり含まれている状態なので、正しい方法で綺麗に洗い落としましょう。
手順1.使い終えた筆は30~40℃のぬるま湯に浸す
手順2.根元部分をもみほぐすようにして内部まで筆全体を洗う、これを墨がほとんど出なくなるまで続ける
手順3.洗った筆の穂先の形を指で綺麗に整え、形が変わらないよう吊るして自然乾燥させる
細筆の洗い方
細筆は糊で固まっており、また毛先3分の1程度しか使わないため、水やお湯で全体を洗う必要はありません。洗わない方法でお手入れするようにしましょう。
手順1.いらない半紙やティッシュペーパーに水を数滴垂らす
手順2.その上に墨の付いた穂先を置き、ゆっくり回転させるようにして墨を拭き取る、これを墨が薄くなるまで続ける
手順3.太筆と同じく、指で穂先の形を整え、形が変わらないよう吊るして自然乾燥させる
洗い残しは筆が割れてしまう原因に!
墨がきちんと落ちていない状態で乾いてしまうと、穂先が二つに割れることがあります。筆の奥まで墨を含んでいると落とすのも大変ですが、使用後は根本までしっかり落としてから乾かしましょう。
また、筆を購入した際についてくるキャップは、新しい筆を保護するための役割です。使用後の筆にキャップをすることは、カビの原因になる恐れがあります。
ちなみに、シャンプーや洗剤を使って筆を洗うと、筆に必要な油分まで落としてしまいます。筆自体のダメージや、墨の含みが悪くなる原因にもつながるので避けましょう。
書道筆・習字筆セットや筆ペンのおすすめはこちら 【関連記事】
大人用の書道セットや、子供の初めての習字におすすめの習字セットなど、書道・習字の関連記事はこちらで紹介しています。
よい書道筆を選んで書道を楽しもう
書道を楽しむには、よい書道筆との出合いが欠かせません。自分の書き味の特徴や書道の腕に合わせたバランスの取れた書道筆があれば、書道をより楽しめるでしょう。
この記事で紹介した書道筆の選び方やおすすめ商品を参考に、自分にぴったりのアイテムを探してみてくださいね。
◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。

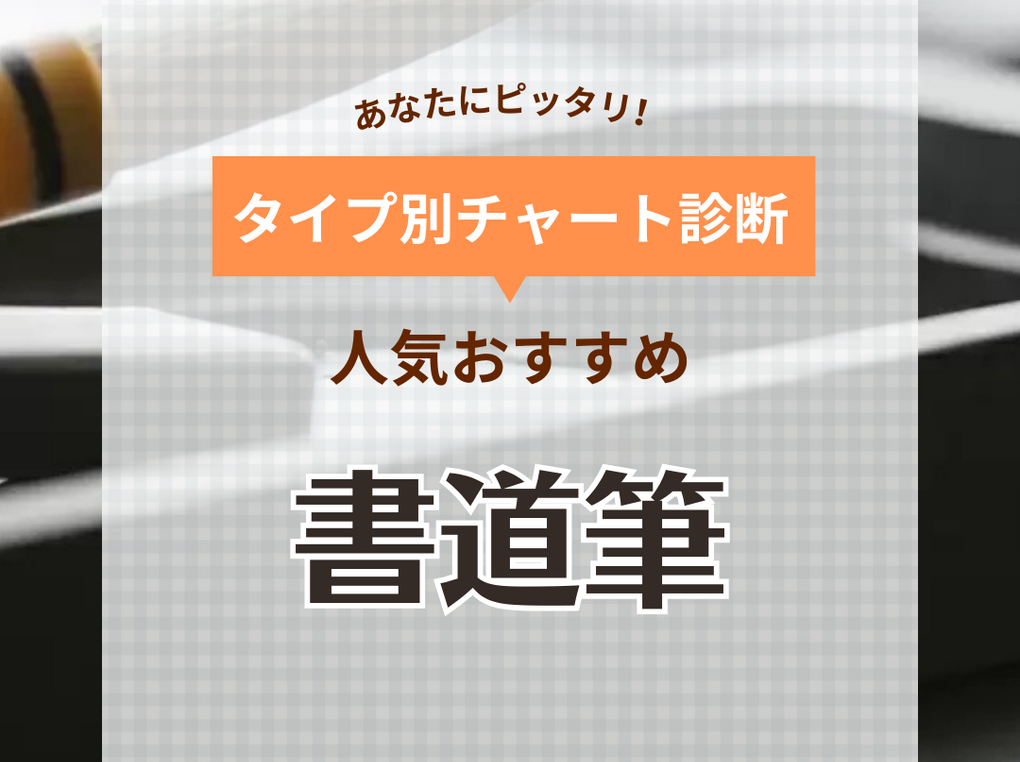
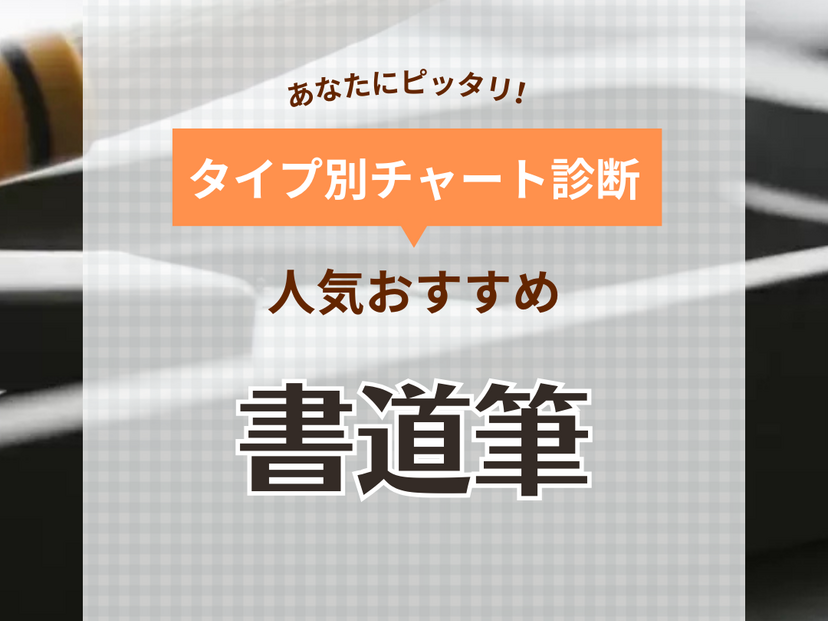




』](https://m.media-amazon.com/images/I/31Ff6OnCOpL._SL500_.jpg)
』](https://m.media-amazon.com/images/I/31ZrW3BX0FL._SL500_.jpg)
』](https://m.media-amazon.com/images/I/510fiY1bUXL._SL500_.jpg)
』](https://m.media-amazon.com/images/I/21myRpctSIS._SL500_.jpg)


』](https://m.media-amazon.com/images/I/310c41uQocL._SL500_.jpg)
』](https://m.media-amazon.com/images/I/31cq2zALN-L._SL500_.jpg)
』](https://m.media-amazon.com/images/I/31cC32wXUiL._SL500_.jpg)
![呉竹『太筆清晞[せいき]3号茶毛(JC336-3)』](https://m.media-amazon.com/images/I/31C2pOWrFyL._SL500_.jpg)
![呉竹『太筆清晞[せいき]3号茶毛(JC336-3)』](https://m.media-amazon.com/images/I/41IdbS93WVL._SL500_.jpg)
![呉竹『太筆清晞[せいき]3号茶毛(JC336-3)』](https://m.media-amazon.com/images/I/31HtLQIB7WL._SL500_.jpg)
![呉竹『太筆清晞[せいき]3号茶毛(JC336-3)』](https://m.media-amazon.com/images/I/51PK45GstOL._SL500_.jpg)
![呉竹『太筆清晞[せいき]3号茶毛(JC336-3)』](https://m.media-amazon.com/images/I/61sHbwItrqL._SL500_.jpg)