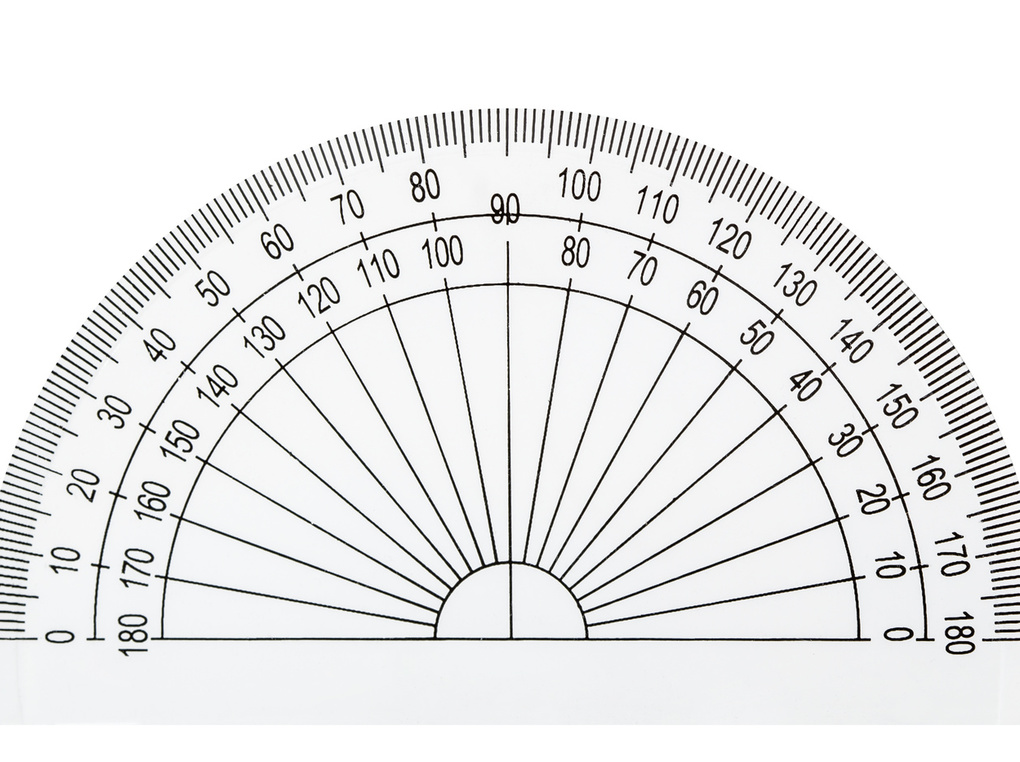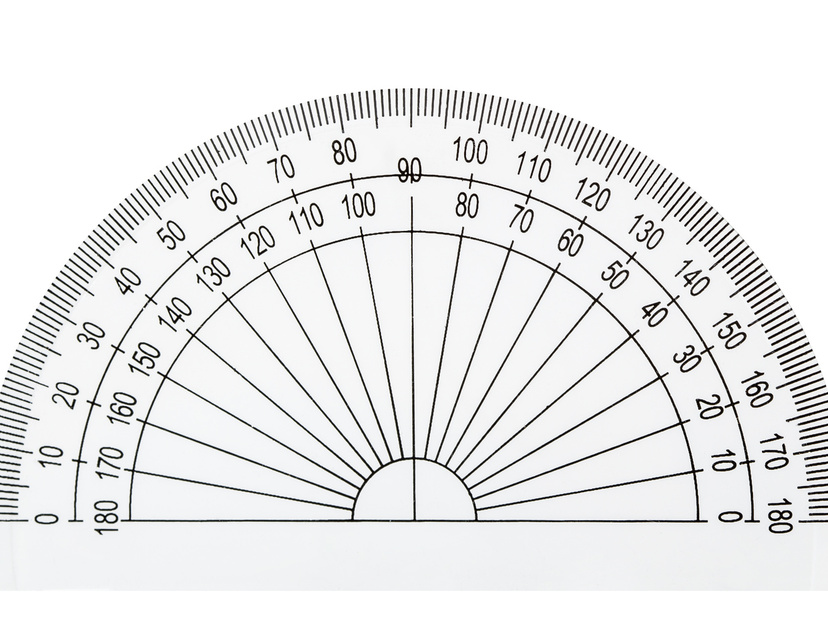| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | メーカー | 素材 | 直径 | 余白の有無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SONiC(ソニック)『ナノピタ 合格成就 分度器 リバーシブル(SK-3042)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月11日時点 での税込価格 |
分度器の表と裏ですべり止めオンとオフを使い分け | ソニック | PMMA | 9cm | あり |
| 共栄プラスチック『GAKUNOアクリル分度器(V-320)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月11日時点 での税込価格 |
丈夫で透明度が高く使いやすいアクリル製分度器 | 共栄プラスチック | アクリル樹脂 | 9cm | なし |
| クツワ『 STAD 算数分度器(HP09A)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月11日時点 での税込価格 |
小学校教科書に使用されるフォントを使い読みやすい | クツワ | メタクリル樹脂 | 9cm | なし |
| KOKUYO(コクヨ) まなびすと『分度器(GY-GBA310)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月11日時点 での税込価格 |
10度ごとに放射線状に色分けされ目盛が読みやすい | コクヨ | 再生PET樹脂 | 9cm | あり |
| アーテック『分度器 ゼロスタート(3327)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月11日時点 での税込価格 |
大きな矢印が左右両方から目盛を読むためにサポート | アーテック | PVC | 9cm | なし |
| SONiC(ソニック)『楽しく学習 分度器(SN-799)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月11日時点 での税込価格 |
色分けされているので読みやすくて使いやすい | ソニック | PMMA | 9cm | あり |
| 共栄プラスチック『カラー分度器ピンク(CPK-90-P)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月11日時点 での税込価格 |
左右どちらからも角度を測れるので左利きでも使える | 共栄プラスチック | アクリル樹脂 | 9cm | なし |
| クツワ『PUMA(プーマ)分度器(PM196)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月11日時点 での税込価格 |
スポーツブランドのプーマのブランド名が輝く分度器 | クツワ | メタクリル樹脂 | 9cm | なし |
| レイメイ藤井『はし0(ゼロ)メモリ分度器(APJ92)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月11日時点 での税込価格 |
リサイクル素材を使用し環境理解にも役立つ分度器 | レイメイ藤井 | 再生PET樹脂 | 9cm | なし |
分度器の選び方
まずは分度器の選び方をチェックしていきましょう。帝京平成大学 現代ライフ学部 児童学科 講師・鈴木邦明さんのアドバイスもご紹介しています。自分の使い方にぴったりの分度器を選ぶために参考にしてみてください。
目盛りの正確さが大事!信頼のメーカーから選ぶ
分度器は、小学生が学校で角度の学習をするときに利用する文房具のひとつです。デザインや製図などで使われる分度器は、小学生には理解が難しいもの。学童文具を製造するメーカーは、独自のノウハウで子どもが使いやすい分度器を製造しています。
はじめての分度器でつまずかないように、子どもの学習をサポートするノウハウを持った学童文具メーカーから選ぶとよいでしょう。
数字が大きく見やすいデザインを選ぶ
目盛の読みかたを練習する小学生にとって、文字の読みやすさも重要なポイントです。文字が大きく強調されている分度器を選ぶことが大切です。分度器を長く使っていると、数字が指の爪や鉛筆の先で削れてしまうことがあります。なるべく摩耗性の強いインクで書かれた分度器を選ぶとなおよいでしょう。
素材で選ぶ
ペットボトルにも使われている強度や透明度もじゅうぶんあるPET製や、すぐれた透明度と強度で知られるPMMA製の分度器を選びましょう。PMMAはメタクリル樹脂やアクリル樹脂とも呼ばれ、ノートやテスト用紙の文字や線を分度器ごしに読みとりやすく、落としても割れにくいのが特徴です。
サイズで選ぶ
小学生が使う分度器のサイズは9センチから12センチ程度がベストです。道具箱の中に入れていても邪魔になりませんし、ペンケースに入れて持ち運ぶにも丁度いいサイズでしょう。
余白の無い「目盛ゼロスタート」か確認する
分度器には直線部分に余白が設けられているものとないものがあります。余白がないタイプを目盛ゼロスタート分度器と呼び、分度器の底にあたる直線部分を測りたい対象物にピタリと重ねて角度をはかるタイプ。端メモリ、はしゼロメモリといった呼び方もあります。
そのため紙の上の図形だけでなく、立体物の角度も自在に計測可能。余白がないことで分度器の位置決めができるので、選ぶ目安にしてみてください。
帝京平成大学講師からのアドバイス
小学生向けの分度器選びでは「扱いやすいこと」「丈夫であること」がポイントです。きちんと自分の調べたい角度に合わせることができ、その角度を読み取ることがしやすいものが子どもにとって使いやすい分度器です。また、薄すぎて強度が弱いものなどは使用するなかで破損の可能性があります。丈夫な素材であることも重要です。
分度器のおすすめ9選
ここからは、学童文具メーカー製を中心に小学生が使いやすい分度器のおすすめを紹介します。エキスパートさんに聞いた選び方をベースに厳選したアイテムです。子どもにとって持つのが嬉しくなるようなデザインも選んでいるので、参考にしてみてください。
分度器の表と裏ですべり止めオンとオフを使い分け
学童用品や事務用品メーカーのソニック。ナノピタ独自のすべり止め加工にひっかけて、合格祈願のお守りデザインをパッケージに採用した分度器です。裏返しても数字が反転しないのでリバーシブルで使用可能。
角度の中心には赤い丸印がほどこされているので、子どもが角度を測るときに必要なポイントを迷わずにおさえることができます。
※各社通販サイトの 2025年3月11日時点 での税込価格
| メーカー | ソニック |
|---|---|
| 素材 | PMMA |
| 直径 | 9cm |
| 余白の有無 | あり |
| メーカー | ソニック |
|---|---|
| 素材 | PMMA |
| 直径 | 9cm |
| 余白の有無 | あり |

素材の透明度が高く、教科書やノートに書かれている線に合わせることがしやすくなっています。
丈夫で透明度が高く使いやすいアクリル製分度器
学童用品、オフィス用品や店舗用品まで扱う共栄プラスチックによる日本製の分度器。アクリル樹脂製なので透明度が高く、分度器ごしに文字や図形をはっきり読みとれます。丈夫な素材なので長く使えるのが特徴です。
目盛ゼロスタート分度器なので、立体物の角度も自在に計測可能。45度と135度の目盛があるので、小学生もかんたんに角度を把握できます。
※各社通販サイトの 2025年3月11日時点 での税込価格
| メーカー | 共栄プラスチック |
|---|---|
| 素材 | アクリル樹脂 |
| 直径 | 9cm |
| 余白の有無 | なし |
| メーカー | 共栄プラスチック |
|---|---|
| 素材 | アクリル樹脂 |
| 直径 | 9cm |
| 余白の有無 | なし |

STAD『算数分度器』は、教科書で使われている字体を使用しています。
小学校教科書に使用されるフォントを使い読みやすい
小学校の教科書で採用されている読みやすい数字を使うなど、小学生が学習につまずかないよう工夫された算数分度器。色分けされているので、右からでも左からでも角度を間違えないで読むことができます。
分度器の厚みは1.5ミリもあり、メタクリル樹脂なので丈夫で高級感もある分度器です。立体の角度もかんたんに測ることができるので、角度の学習がはかどります。
※各社通販サイトの 2025年3月11日時点 での税込価格
| メーカー | クツワ |
|---|---|
| 素材 | メタクリル樹脂 |
| 直径 | 9cm |
| 余白の有無 | なし |
| メーカー | クツワ |
|---|---|
| 素材 | メタクリル樹脂 |
| 直径 | 9cm |
| 余白の有無 | なし |

また、調べる頻度が高い角度(30度など)を見やすくしています。まなびすと『分度器』は、細かいメモリの長さを変えるなどの見やすい工夫がされています。
10度ごとに放射線状に色分けされ目盛が読みやすい
キャンパスノートでおなじみの文具メーカーのコクヨ。小学生用の分度器は30度ごとに数字を大きく表示し、目盛の長さを変えて山型に表示するなど読みやすい工夫がいっぱいです。
子どもの苦手意識をつくらないよう、放射線状に色分けして角度を把握しやすいようサポートしています。リサイクルされたPET樹脂製なので、割れにくく長く使える分度器です。
※各社通販サイトの 2025年3月11日時点 での税込価格
| メーカー | コクヨ |
|---|---|
| 素材 | 再生PET樹脂 |
| 直径 | 9cm |
| 余白の有無 | あり |
| メーカー | コクヨ |
|---|---|
| 素材 | 再生PET樹脂 |
| 直径 | 9cm |
| 余白の有無 | あり |
大きな矢印が左右両方から目盛を読むためにサポート
学校教材を手がけて60年になるアーテックがうんだ、使いやすいゼロスタート分度器。角度を誤まって計測する原因になりがちな底辺の余白をなくし、大きな矢印で子どもの目盛を追いかける作業をしっかりサポートしてくれます。
2色の色分けのおかげで読みやすいため角度を把握しやすく、子どもが混乱せずに角度を学習できるとても使い勝手のよい分度器です。
※各社通販サイトの 2025年3月11日時点 での税込価格
| メーカー | アーテック |
|---|---|
| 素材 | PVC |
| 直径 | 9cm |
| 余白の有無 | なし |
| メーカー | アーテック |
|---|---|
| 素材 | PVC |
| 直径 | 9cm |
| 余白の有無 | なし |
色分けされているので読みやすくて使いやすい
重要な角度をあらわす数字が大きく表示されているほか、左右で数字が色分けされているなど角度を測りやすい工夫がいっぱい。角度の中心を合わせやすいように、カラー基準線が入っていて子どもの学習をサポートしてくれます。
透明度や強度の高いPMMA製なので、うっかり落としても割れにくいので学習のパートナーにピッタリです。
※各社通販サイトの 2025年3月11日時点 での税込価格
| メーカー | ソニック |
|---|---|
| 素材 | PMMA |
| 直径 | 9cm |
| 余白の有無 | あり |
| メーカー | ソニック |
|---|---|
| 素材 | PMMA |
| 直径 | 9cm |
| 余白の有無 | あり |
左右どちらからも角度を測れるので左利きでも使える
余白がない目盛ゼロスタート分度器なので測りたい対象物に分度器を固定しやすく、より正確に角度を測れます。ピンクカラーでかわいく色分けされているので目盛りが読みやすく、文具はピンクでそろえたい小学生にピッタリ。
30度ごとに数字が大きいほか、45度と135度の目盛が強調されているので角度の把握もしやすい分度器です。
※各社通販サイトの 2025年3月11日時点 での税込価格
| メーカー | 共栄プラスチック |
|---|---|
| 素材 | アクリル樹脂 |
| 直径 | 9cm |
| 余白の有無 | なし |
| メーカー | 共栄プラスチック |
|---|---|
| 素材 | アクリル樹脂 |
| 直径 | 9cm |
| 余白の有無 | なし |
スポーツブランドのプーマのブランド名が輝く分度器
学童文具から大人向けまで扱うクツワ。透明な分度器とは一線を画すイエローとブラックのコントラストがカッコいい、プーマの分度器。スピード感を感じさせるデザインで、持っていると勉強するやる気がわいてきそうなアイテムです。
高級感のあるメタクリル樹脂製で、衝撃に強いので長く使えます。右からでも左からでも読める目盛つきなので右利きでも左利きでも使える仕様です。
※各社通販サイトの 2025年3月11日時点 での税込価格
| メーカー | クツワ |
|---|---|
| 素材 | メタクリル樹脂 |
| 直径 | 9cm |
| 余白の有無 | なし |
| メーカー | クツワ |
|---|---|
| 素材 | メタクリル樹脂 |
| 直径 | 9cm |
| 余白の有無 | なし |
リサイクル素材を使用し環境理解にも役立つ分度器
学童文具や大人向け文具、洋紙まで取り扱うレイメイ藤井。直感的に子どもが角度を測れるように、分度器の直線部分には余白を設けない「はし0(ゼロ)メモリ」を開発。2枚の分度器を上下に合わせれば、円の学習も可能です。
目盛には矢印もデザインされているので、子どもが目盛を確認する作業をしっかりサポート。より角度の理解をしやすい分度器を求めている人にピッタリです。
※各社通販サイトの 2025年3月11日時点 での税込価格
| メーカー | レイメイ藤井 |
|---|---|
| 素材 | 再生PET樹脂 |
| 直径 | 9cm |
| 余白の有無 | なし |
| メーカー | レイメイ藤井 |
|---|---|
| 素材 | 再生PET樹脂 |
| 直径 | 9cm |
| 余白の有無 | なし |
「分度器」のおすすめ商品の比較一覧表
| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | メーカー | 素材 | 直径 | 余白の有無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SONiC(ソニック)『ナノピタ 合格成就 分度器 リバーシブル(SK-3042)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月11日時点 での税込価格 |
分度器の表と裏ですべり止めオンとオフを使い分け | ソニック | PMMA | 9cm | あり |
| 共栄プラスチック『GAKUNOアクリル分度器(V-320)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月11日時点 での税込価格 |
丈夫で透明度が高く使いやすいアクリル製分度器 | 共栄プラスチック | アクリル樹脂 | 9cm | なし |
| クツワ『 STAD 算数分度器(HP09A)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月11日時点 での税込価格 |
小学校教科書に使用されるフォントを使い読みやすい | クツワ | メタクリル樹脂 | 9cm | なし |
| KOKUYO(コクヨ) まなびすと『分度器(GY-GBA310)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月11日時点 での税込価格 |
10度ごとに放射線状に色分けされ目盛が読みやすい | コクヨ | 再生PET樹脂 | 9cm | あり |
| アーテック『分度器 ゼロスタート(3327)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月11日時点 での税込価格 |
大きな矢印が左右両方から目盛を読むためにサポート | アーテック | PVC | 9cm | なし |
| SONiC(ソニック)『楽しく学習 分度器(SN-799)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月11日時点 での税込価格 |
色分けされているので読みやすくて使いやすい | ソニック | PMMA | 9cm | あり |
| 共栄プラスチック『カラー分度器ピンク(CPK-90-P)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月11日時点 での税込価格 |
左右どちらからも角度を測れるので左利きでも使える | 共栄プラスチック | アクリル樹脂 | 9cm | なし |
| クツワ『PUMA(プーマ)分度器(PM196)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月11日時点 での税込価格 |
スポーツブランドのプーマのブランド名が輝く分度器 | クツワ | メタクリル樹脂 | 9cm | なし |
| レイメイ藤井『はし0(ゼロ)メモリ分度器(APJ92)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月11日時点 での税込価格 |
リサイクル素材を使用し環境理解にも役立つ分度器 | レイメイ藤井 | 再生PET樹脂 | 9cm | なし |
通販サイトの最新人気ランキングを参考にする 分度器の売れ筋をチェック
Amazon、楽天市場での分度器の売れ筋ランキングも参考にしてみてください。
※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。
新学期準備に!小学生文房具特集! 人気メーカーもラインナップ
定規・ものさしについてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事もぜひチェックしてみてください。
子どものために使いやすい分度器を見つけてみてくださいね
小学3年生から小学校4年生になれば学習することになる分度器の使い方。角度の中心への分度器のあてかたや目盛の読みかたがうまくわからなくて困らないように、子どもの学習をサポートする工夫がほどこされた分度器が発売されています。
学童文具メーカーが知恵をしぼってうみだした分度器を紹介しましたので、子どもが直感的に使いやすいと感じる分度器を選ぶ参考にしてみてください。
◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。