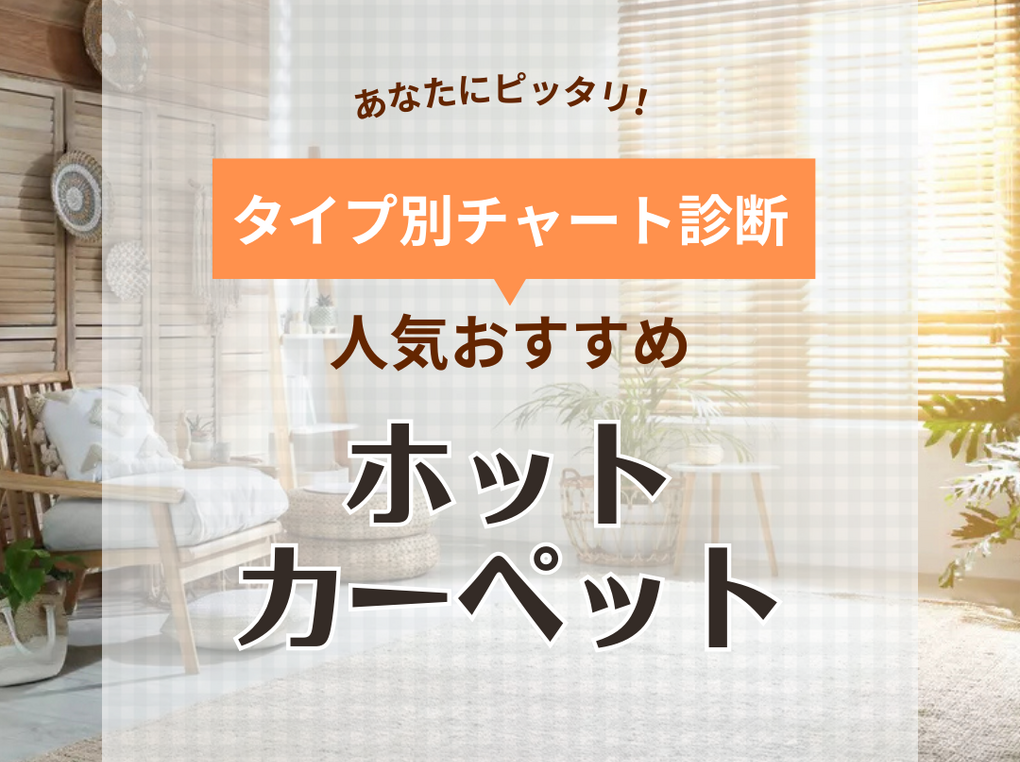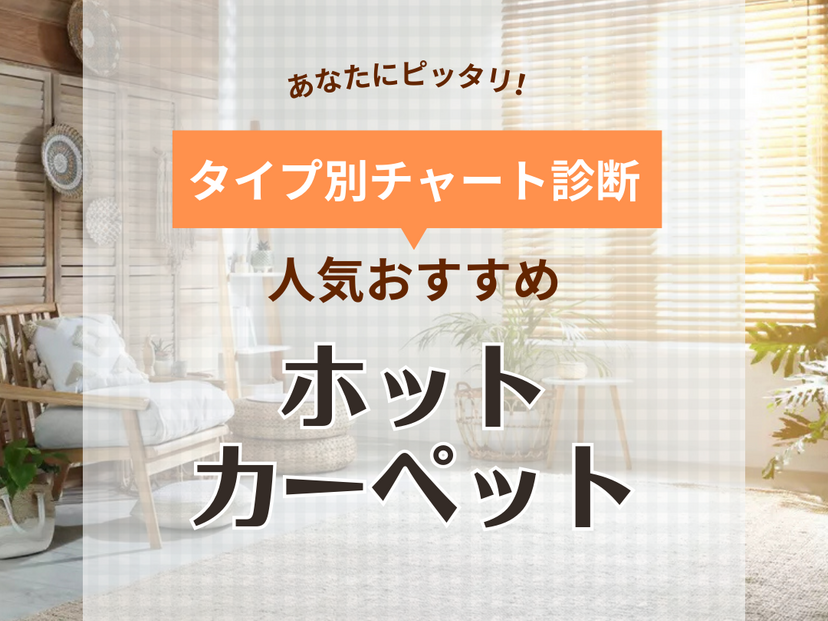| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | サイズ | 消費電力 | 機能 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)『ホットカーペット 木目調(HCM-1105FL-M)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |
水まわりに最適! お手入れ簡単で常に清潔 | 縦45×横110cm(0.3畳相当) | 64.5W | 温度調整2段階、撥水加工 | 表/ポリ塩化ビニル100%、裏/ポリエステル100% |
| TEKNOS(テクノス)『ミニマット(EC-K4001)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |
デスクワークのおともに最適! | 40×40cm | 26W | - | ポリエステル |
| IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)『ホットカーペット IHC-10-H』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |
1畳サイズの一人用ホットカーペット | 176×88cm | 200W | 5段階温度調節、ダニ退治機能 | ポリエステル100% |
| KODEN(広電)『電気カーペット(VWU1013)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |
コスパにこだわったおひとりさま用 | 約縦88×横176cm(1畳相当) | 200W | ダニクリーン、スライド調節 | ポリエステル100% |
| YAMAZEN(山善)『洗えるどこでもカーペット(YWC-182F)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |
やわらかいフランネルマットでくつろごう | 縦80×横180cm(1畳相当) | 70W | 丸洗い可能、フランネル仕上げ、室温センサー付き | ポリエステル100% |
| MORITA(モリタ)『電気カーペット(TMC-100)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |
温度幅の広い電気カーペット | 約176×88cm (1畳相当) | 100Ⅴ(50/60Hz)・200W | 8つ折り収納、ダニ対策機能 | ポリエステル100% |
| ライフジョイ『日本製 ホットカーペット 1畳 正方形 グレー』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |
ダニ退治できる正方形カーペット | 125cm×125cm | 中:約114W、強:約164W (50/60Hz) | ダニ退治機能 | ポリエステル100% |
| ユアサプライムス『ホットカーペット 1畳 YC-Y10Y』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月28日時点 での税込価格 |
基本的な機能をおさえたスタンダードなカーペット | 幅1760mm×奥行880mm | 中:約97W、強:約134.7W | ダニ退治機能 | ポリエステル100% |
| YAMAZEN(山善)『ホットカーペット カバーセット(YZF-132)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |
消臭機能付き! | 縦125×横125cm | 200W | ダニ退治機能 | ポリエステル100% |
| YAMAZEN(山善)『フローリング調 ホットカーペット 1畳(YZC-109FL)』 |
|
※各社通販サイトの 2024年10月28日時点 での税込価格 |
防水加工付きのフローリング調 | 126×180cm | 200W | ダニ退治機能、表面防水加工 | PVC |
| Panasonic(パナソニック)『ホットカーペット 着せかえカバー付きセット(DC-1NKB1-C)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |
トリプル断熱構造の便利機能付きカーペット | 約183cm×95cm | - | ダニ退治機能、2時間、4時間 切タイマー機能、8時間切り忘れ防止機能 | ポリエステル100% |
| Panasonic(パナソニック)『ホットカーペット ディズニーデザイン(DC-15NKCD2)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |
2面切り替えでエコに暖まる | ヒーター部:約176×126×0.6cm、カバー部:約183×133cm | - | ダニ対策機能、2・4時間 切タイマー機能、8時間切り忘れ防止機能 | ポリエステル |
| YAMAZEN(山善)『空気をきれいにする ホットカーペット 1畳(SUS-101)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月3日時点 での税込価格 |
トリプルフレッシュ採用のラグサイズカーペット | 85×170cm | 160W | ダニ退治機能、24時間サイクル消臭機能 | - |
| Keep warm『電気カーペット(HB82-080180)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |
フランネル素材のふわりとした肌触りが魅力 | 180×80cm | 80W | タイマー機能、6段階温度調整、消し忘れ防止機能、過熱保護機能、過圧保護機能、ダニ退治機能 | ポリエステル |
| Panasonic(パナソニック)『着せ替えカーペット セットタイプ(DC-2HAC3-C)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月18日時点 での税込価格 |
汚れたら丸洗い可能! | ヒーター部:約176×176×1cm、カバー部:約183×183cm | 480W | 省エネモード(室温センサー)、2時間、4時間、切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能など | ヒーター部:フェルト(ポリエステル)、カバー部:ポリエステル100% |
| YAMAZEN(山善)『ホットカーペット 2畳(AUB-200)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月28日時点 での税込価格 |
ベーシックな機能とデザインで人気! | 175cm×175cm(2畳) | 520W | ダニ退治機能、温度ヒューズ、オートオフタイマー、裏面滑り止め加工 | ポリエステル |
| Panasonic(パナソニック)『ホットカーペット(DC-2NK)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |
節電対策をしたい方におすすめ! | 176×176cm(2畳) | 490 W | 省エネモード、タイマー機能、8時間切り忘れ防止機能、ダニ対策機能 | フェルト、ポリエステル |
| TEKNOS(テクノス)『ホットカーペット 2畳用(TWA-2000B)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |
低価格ながら便利な機能を備える! | 2畳相当(176×176cm) | 500W | ポリエステル | ダニ防止機能、暖房面積切り替え、切り忘れ防止機能 |
| YAMAZEN(山善)『ホットカーペット フローリング調 2畳(YZC-207FL)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |
フローリング調なので部屋内どこでもなじむ | 2畳 | 520W | 滑り止め防止加工、ダニ防止機能、防水加工 | ポリエステル100%、平織木目調プリント、透明PPシート |
| MORITA(モリタ)『ホットカーペット 2畳用(TMC-200)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |
正方形の形が特徴的 | 2畳相当(176×176cm) | 500W | 6時間切り忘れタイマー、左右全面切り替え | ポリエステル |
| Panasonic(パナソニック)『ホットカーペット フローリング調(DC-2V4-MC)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |
エネルギー効率の良いホットカーペット | 2畳相当(約176×176cm) | - | 2面切り替え3通り暖房、8時間切り忘れタイマー | 塩化ビニール |
| IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)『電気ホットカーペット 単品(IHC-30-H)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |
基本性能を備えた3畳タイプ | 3畳 | 中/約90.0Wh 強/約134.7Wh | ダニ防止機能、自動切タイマー付き、連続通電防止機能付き | ポリエステル |
| ライフジョイ『ホットカーペット(JPU301H)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |
何年も利用したいならコレ! | 235cm×195cm(3畳) | 720 W | ダニ退治機能、8時間自動OFF機能、A面B面切替機能 | ポリエステル |
| タンスのゲン『ホットカーペット 約3畳』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |
3畳サイズでゆったりくつろげる | 195×235cm 約3畳 | 720W | 自動電源OFF機能、温度調節機能、ダニ退治機能 | ポリエステル100% |
| KOIZUMI(コイズミ)『電気カーペット カバー付きセット(KDC-30227)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月28日時点 での税込価格 |
フローリングタイプの決定版 | 235×195cm(3畳相当) | 740W | ダニ退治機能、2時間切タイマー、切り忘れ防止6時間自動オフ | ポリエステル100% |
ホットカーペットの選び方 サイズ、素材、省エネ、収納性、衛生面など
プロの家電販売員・たろっささんに、ホットカーペットを選ぶときのポイントを教えてもらいました。寒い時期には長く使用するものだからこそ、気をつけたい点ばかりです。
【1】敷く場所に合わせてサイズを選ぶ
【2】ホットカーペットの種類で選ぶ
【3】電気代を節約できる省エネ性をチェック
【4】コンパクトに収納できるか
【5】洗えるタイプか
購入前にしっかり確認して、ホットカーペットを選びましょう。
【1】敷く場所に合わせてサイズを選ぶ

出典:マイナビおすすめナビ

出典:マイナビおすすめナビ
1~3畳の大きさがあるので、自分の生活に合うサイズを選びましょう。
一人暮らしなら「1畳」で十分
一人暮らしなら、1畳で十分です。横になっても全身を温められます。人を招いた場合でも、テーブルの下に敷けば2人の足元を温められますよ。
1畳のホットカーペットは省スペースなのもメリット。コンパクトに折りたためると、場所をとらずに収納できます。
ただ、明らかに安い製品の場合、折りたたんだり重いものを乗せて使ったりすると破損につながることもあるので注意しましょう。
2~3人で使うなら「2畳」
2畳のホットカーペットは、2~3人の大人がリビングでくつろぐのにピッタリなサイズです。夫婦や、子どもがいる家庭で重宝しますよ。
なお、1人で使うこともあると思いますので、使う場所だけを温かくする「面切り替え機能」が搭載されているものを選ぶといいでしょう。
部屋が広い場合や家族が多いなら「3畳〜」
3畳以上のホットカーペットはリビングの大きさに合わせて選ぶのがおすすめです。テーブルの下に敷けば、大人数で食卓を囲むときにも重宝します。
ただ、サイズが大きなものほど広い収納スペースが必要になり、値段もかなり高くなるので注意しましょう。
【2】ホットカーペットの種類で選ぶ
ホットカーペットは大きく分けて、じゅうたんタイプとフローリングタイプの2つの種類があります。使う場所や目的によって選び方が異なってくるので、自分が使うシーンを想定してみましょう。
じゅうたんタイプ|そのままくつろげる
じゅうたんタイプはホットカーペットの主流のタイプで、カーペットやラグ状のカバーを上に乗せて使用します。横になってくつろぎたい人にぴったり。和室にも違和感なく溶け込むのはこちらのタイプです。
ただ、ダニなどが発生しやすいため、洗濯機でカバーを丸洗いできるタイプや、ダニを駆除できる機能が搭載されたアイテムを選びましょう。部屋の雰囲気に合わせて好みのカバーと組み合わせられるのもポイントです。
通常はカバーが付属していますが、別途で購入するケースもあるので注意しましょう。
フローリングタイプ|簡単にお手入れできる
木目調の見た目が特徴で、塩化ビニールなどの素材を使っているので簡単にお手入れできるのがメリットです。食べかすや飲み物をこぼしてしまっても、拭き取るだけできれいになるので、マットタイプと比べるとダニなどが発生する心配は少なくなります。
また、ペットの爪が引っ掛かる心配がないのと、ホコリが立ちにくいのも選ばれる理由です。水を使用するキッチンやダイニング用としてもおすすめです。
【3】電気代を節約できる省エネ性もチェック
ホットカーペットの電気代は、設定温度やメーカーによっても異なりますが、1時間あたり約6~9円になります。セラミックファンヒーターの場合、1時間あたり12~30円かかるので、半分くらいの料金で使うことができますよ。
基本的にどのホットカーペットを選んでも、そこまで電気代は変わらないので、本体に節電機能が搭載されているホットカーペットを選びましょう。
なお、ホットカーペットの下に断熱シートを敷くと、床に熱が逃げないので省エネ効果があります。
使う場所だけ温かくする「面切り替え機能」
2畳用や3畳用程度のホットカーペットの場合、滞在する場所だけ温めることができる切り替え機能を搭載したホットカーペットを選ぶと電気代の節約になります。
使う場所だけ温めることで、電気代を効率よく安くすることができます。
温めすぎを防ぐ「温度調節機能」
ホットカーペットの上に長時間座っていると暑くなってきます。そのとき温度調節で低い温度に設定することができれば、無駄な電気代を使わなくて済みます。
高い熱量を必要とするときは電気代もその分かかります。5段階調節できるタイプなど、段階的に下げていくことができる製品だと使いやすいでしょう。
つけっぱなしを防ぐ「切り忘れ防止機能」
エアコンや扇風機と違い、使っていても運転音がしないので「寝る前や外出時についつい消し忘れてそのまま……」なんてことも。そんなうっかりさんには、切り忘れ防止機能があると便利。
メーカーや機種によって異なりますが、設定した連続使用時間を超えると、自動的にスイッチが切れるので、無駄な電気代がかかる心配がありません。火災などの事故リスクを軽減することにも一役買います。
【4】コンパクトに収納できるかチェック
ホットカーペットが活躍するのは基本的に寒くなってきた秋~冬なので、それ以外の春~夏はクローゼットなどにしまっておく必要があります。
その際、意外とかさばり、見た目よりも重い場合があるので、コンパクトに折りたためるタイプや丸められるものがおすすめ。収納のしやすさは忘れがちですが、重要なポイントです。
【5】洗えるタイプか確認する
カバー付きのホットカーペットは、必ずカバーが丸洗いできるかどうかを確認しましょう。
毎日床に敷いて使用しているものは、自分たちが思っている以上に汚れています。丸洗いができない場合は、丸洗いできるものになるべく変更したほうがいいです。
洗わないでいるとダニの温床になりますし、何より臭いが気になってきます。抗菌や防ダニ機能など、カバーを清潔に保てる機能が備わっているかどうかもチェックしておきましょう。
ホットカーペットのおすすめメーカー パナソニック、山善、光電がおすすめ
ヤマダ電機などの家電量販店だけでなく、カインズなどのホームセンターでも多くのホットカーペットを扱っています。実際買うとなると、どの商品を選べばいいか難しい……という人は安心できるメーカーで選ぶのもアリです。人気のあるメーカーとその特徴を紹介しているので、アイテムを選ぶ際の参考にしてみてください。
Panasonic(パナソニック):高機能なアイテムを揃える
幅広い家電製品を手掛ける大手電機メーカー、パナソニック。ヒーター性能そのものが優れているだけではなく、省エネ機能や、ダニ対策などに対応したモデルを多く展開しており、高機能なホットカーペットを取り揃えています。
また、バリエーションが豊富なので、部屋に合わせてぴったりのサイズを見つけやすいのも魅力。あとは、部屋の雰囲気に合わせて柄を選ぶだけです。
YAMAZEN(山善):コスパに優れたアイテムが多い
山善は、ダニ対策や切り忘れ防止タイマー機能などを搭載しつつも、価格を抑えた商品をラインナップ。コスパに優れたホットカーペットということで人気を集めています。
ホットカーペット以外にも、さまざまな住宅設備機器を販売しているので、その品質は安心できますよ。価格と機能性のバランスがちょうどいい商品を欲しいあなたにおすすめです。
KODEN(広電):国内シェアトップの安心感!
1996年に創業し、ホットカーペットや電気毛布、電気マットなどの電気暖房器具を主に製造しているメーカー、広電。高品質で手ごろな価格のホットカーペットを多数ラインナップし、国内市場シェアトップを誇ります。
汗やペットのニオイを消臭する「デオテックス」機能や、オートオフになる「マイコン制御コントローラー」などを搭載していますよ。
ユーザーが選んだイチオシ5選
ここでは、みんながおすすめする「ホットカーペット」を紹介します。 商品の口コミはもちろん、コスパ、機能性、使いやすさといった評価ポイントも聞いてみたので、各項目にも注目して商品選びの参考にしてください!
その他にもおすすめしたい商品があるよという方は、ぜひ記事後半にある投稿フォームからご紹介をお願いします。

愛用者
安いのでずっとMORITAを使用
3畳用で、なかなかこの値段では売ってないのでありがたいです。電源入れてすぐ温まるし、一番低い「弱」でもちゃんと暖かい。冬にカーペットに寝転び、毛布をかけてぬくぬくお昼寝するのが最高です。消し忘れ防止のタイマーがついているので、安心して使用できます。(M.C.さん/女性/38歳/会社員)
【デメリットや気になった点】
端っこまで熱線がないので、端っこだと暖かくありません。(M.C.さん/女性/38歳/会社員)
※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格
| コスパ | ★★★★★ |
|---|---|
| 機能性 | ★★★★★ |
| 使いやすさ | ★★★★★ |
| 総合評価 | 5.0点 |
| コスパ | ★★★★★ |
|---|---|
| 機能性 | ★★★★★ |
| 使いやすさ | ★★★★★ |
| 総合評価 | 5.0点 |

愛用者
やわらかい&汚れにくいホットカーペット
想像していたよりクッション性があり、寝転んでも快適です。スイッチをオンにするとすぐに暖かくなり、ここちいい温度に保温してくれます。フローリング調で表面がつるっとしているので、汚れても拭くだけでOK! お手入れがラクちんなのも満足です。(M.N.さん/女性/32歳/主婦)
【デメリットや気になった点】
デザイン性や品質が高いぶん、それなりにコストがかかります。(M.N.さん/女性/32歳/主婦)
※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格
| コスパ | ★★★☆☆ |
|---|---|
| 機能性 | ★★★★☆ |
| 使いやすさ | ★★★★★ |
| 総合評価 | 4.0点 |
| コスパ | ★★★☆☆ |
|---|---|
| 機能性 | ★★★★☆ |
| 使いやすさ | ★★★★★ |
| 総合評価 | 4.0点 |

愛用者
すぐに暖まるので冬には欠かせません
電源を入れてから暖まるまでの時間がとても早く、寒さが苦手な私にはとても助かっています。温度設定もこまかくできるうえに6時間タイマーがあるので、それほど温度が必要ないときや切り忘れがあったときでも無駄に電気代がかからず安心です。(M.N.さん/女性/25歳/会社員)
【デメリットや気になった点】
部屋のコンセントの位置関係上、電源コードがもう少し長いと使いやすかったです。(M.N.さん/女性/25歳/会社員)
※各社通販サイトの 2025年2月3日時点 での税込価格
| コスパ | ★★★★★ |
|---|---|
| 機能性 | ★★★★★ |
| 使いやすさ | ★★★★★ |
| 総合評価 | 4.7点 |
| コスパ | ★★★★★ |
|---|---|
| 機能性 | ★★★★★ |
| 使いやすさ | ★★★★★ |
| 総合評価 | 4.7点 |

愛用者
ようやく見つけた丸いカーペット!
わが家の丸いラグにぴったりのサイズをようやく見つけました。小さい円形サイズはよくあるものの、大きなサイズはなかなか探しても見つからず。8時間の自動電源オフ機能も助かります。これで快適な冬を迎えられそうです。(K.T.さん/女性/42歳/主婦)
【デメリットや気になった点】
丸いので収納に少し困ります。(K.T.さん/女性/42歳/主婦)
※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格
| コスパ | ★★★★★ |
|---|---|
| 機能性 | ★★★★★ |
| 使いやすさ | ★★★★★ |
| 総合評価 | 5.0点 |
| コスパ | ★★★★★ |
|---|---|
| 機能性 | ★★★★★ |
| 使いやすさ | ★★★★★ |
| 総合評価 | 5.0点 |

愛用者
大人も子どももお気に入りのスペースに
水拭きできる仕様は、子どもがいる家庭にはとてもありがたい。リビングで飲食をするときは、このカーペットの上で! が我が家のルールになっています。リビングの隅っこのスペースが特別な場所になりました。ほどよく暖かく、衛生面でも安心しています。木目調柄もインテリアになじんで部屋の雰囲気を壊さないのもポイント高いです。(F.T.さん/女性/45歳/会社員)
【デメリットや気になった点】
もう少し暖かくなると、さらに快適です。(F.T.さん/女性/45歳/会社員)
※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格
| コスパ | ★★★☆☆ |
|---|---|
| 機能性 | ★★★★★ |
| 使いやすさ | ★★★★★ |
| 総合評価 | 4.3点 |
| コスパ | ★★★☆☆ |
|---|---|
| 機能性 | ★★★★★ |
| 使いやすさ | ★★★★★ |
| 総合評価 | 4.3点 |
ホットカーペットおすすめ2選|1畳未満
水まわりに最適! お手入れ簡単で常に清潔
明るい木目調のホットカーペットは、コンパクトで撥水加工が施されているため、水まわりの使用にもおすすめです。寒いキッチンでの長時間の作業でも、足元からポカポカと暖めてくれます。洗い物の水がはねても簡単に拭き取れるため、いつも清潔にきれいな状態で使用できます。
犬や猫などの毛が絡まることもなく、ペットを室内飼いしている場合でも安心です。温度の切り替えは48℃と40℃の強弱2段階。1時間あたりの電気代は、強モードで約1.7円というコスパのよさ。リビングや子ども部屋、一人暮らしにもおすすめです。
※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格
| サイズ | 縦45×横110cm(0.3畳相当) |
|---|---|
| 消費電力 | 64.5W |
| 機能 | 温度調整2段階、撥水加工 |
| 材質 | 表/ポリ塩化ビニル100%、裏/ポリエステル100% |
| サイズ | 縦45×横110cm(0.3畳相当) |
|---|---|
| 消費電力 | 64.5W |
| 機能 | 温度調整2段階、撥水加工 |
| 材質 | 表/ポリ塩化ビニル100%、裏/ポリエステル100% |
デスクワークのおともに最適!
40×40cmのコンパクトサイズのホットカーペットです。椅子の上に乗せたり、床に置いて足裏を温めたりして使うことができます。一人暮らしにはぴったりですし、コンパクトなので職場でも利用しやすいですね。
消費電力も26Wと少なく、電気代はおよそ毎時約0.3円と非常にリーズナブルなので、電気代を抑えたい人にも好都合。1つあればいろんなシーンで役立つはずですよ。
※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格
| サイズ | 40×40cm |
|---|---|
| 消費電力 | 26W |
| 機能 | - |
| 材質 | ポリエステル |
| サイズ | 40×40cm |
|---|---|
| 消費電力 | 26W |
| 機能 | - |
| 材質 | ポリエステル |
ホットカーペットおすすめ12選|1畳
1畳サイズの一人用ホットカーペット
一人暮らしにぴったりの1畳サイズ。横長なので、ソファやこたつの下にも敷けます。カーペットカバーは別途必要ですが、5段階温度調節機能で、状況によって使い分ければ電気代を節約することもできます。
※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格
| サイズ | 176×88cm |
|---|---|
| 消費電力 | 200W |
| 機能 | 5段階温度調節、ダニ退治機能 |
| 材質 | ポリエステル100% |
| サイズ | 176×88cm |
|---|---|
| 消費電力 | 200W |
| 機能 | 5段階温度調節、ダニ退治機能 |
| 材質 | ポリエステル100% |

リーズナブルな一人用ホットカーペット
1畳相当の電気カーペット本体です。こちらはなんといってもそのコストパフォーマンスの高さが魅力です。
比較的安価で買えて、1畳分をポカポカにしてくれる商品。自分好みのラグを探して、その下に敷けばOKです。
電気代の目安も、1時間あたりおよそ4.4円と比較的リーズナブル。一人暮らしの冬の強い味方になってくれます。
※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格
| サイズ | 約縦88×横176cm(1畳相当) |
|---|---|
| 消費電力 | 200W |
| 機能 | ダニクリーン、スライド調節 |
| 材質 | ポリエステル100% |
| サイズ | 約縦88×横176cm(1畳相当) |
|---|---|
| 消費電力 | 200W |
| 機能 | ダニクリーン、スライド調節 |
| 材質 | ポリエステル100% |
やわらかいフランネルマットでくつろごう
やわらかい肌触りのフランネルマットは厚みがあり、ふかふかなのでゴロ寝にもぴったり。平面だけでなくソファやイスの上に敷いて使うことも。
ダニ退治機能搭載のうえ、洗濯機で丸洗いできるため、いつも清潔に使えます。カラーは、ブラウン、ベージュ、レッド、グレーの4色展開です。
※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格
| サイズ | 縦80×横180cm(1畳相当) |
|---|---|
| 消費電力 | 70W |
| 機能 | 丸洗い可能、フランネル仕上げ、室温センサー付き |
| 材質 | ポリエステル100% |
| サイズ | 縦80×横180cm(1畳相当) |
|---|---|
| 消費電力 | 70W |
| 機能 | 丸洗い可能、フランネル仕上げ、室温センサー付き |
| 材質 | ポリエステル100% |
温度幅の広い電気カーペット
最大50℃まで調整可能なダニ対策機能付きのホットカーペットです。ツマミをスライドさせて簡単に温度調節ができる本製品は8つ折りが可能なのでコンパクトに収納が可能!
値段もお手頃で機能も十分かつ暖かさも問題ないので、コスパの良い商品だということができるでしょう。お好みのカバーと合わせて使ってみてください!
※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格
| サイズ | 約176×88cm (1畳相当) |
|---|---|
| 消費電力 | 100Ⅴ(50/60Hz)・200W |
| 機能 | 8つ折り収納、ダニ対策機能 |
| 材質 | ポリエステル100% |
| サイズ | 約176×88cm (1畳相当) |
|---|---|
| 消費電力 | 100Ⅴ(50/60Hz)・200W |
| 機能 | 8つ折り収納、ダニ対策機能 |
| 材質 | ポリエステル100% |
ダニ退治できる正方形カーペット
正方形1畳サイズのダニ退治機能付きホットカーペットです。部屋のちょっとしたスペースに敷いたり、正方形のテーブルやコタツの下に敷いたりなど、様々な使い方ができる本製品。
ホットカーペット本体の上にラグ、下に断熱シートを敷いてお使いいただくことで、さらに長持ちさせることも可能です。「長方形のカーペットは使いにくい…」と思っている方はお試しあれ。
※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格
| サイズ | 125cm×125cm |
|---|---|
| 消費電力 | 中:約114W、強:約164W (50/60Hz) |
| 機能 | ダニ退治機能 |
| 材質 | ポリエステル100% |
| サイズ | 125cm×125cm |
|---|---|
| 消費電力 | 中:約114W、強:約164W (50/60Hz) |
| 機能 | ダニ退治機能 |
| 材質 | ポリエステル100% |
基本的な機能をおさえたスタンダードなカーペット
88×176cmの1畳サイズホットカーペット。温度調節機能で好みのパワーに調節して利用でき、省エネにもなって電気代に優しい点が嬉しいポイントです。
ダニ退治機能などの基本的な機能もひと通りおさえた商品ですので、買い替えにもおすすめ!
※各社通販サイトの 2024年10月28日時点 での税込価格
| サイズ | 幅1760mm×奥行880mm |
|---|---|
| 消費電力 | 中:約97W、強:約134.7W |
| 機能 | ダニ退治機能 |
| 材質 | ポリエステル100% |
| サイズ | 幅1760mm×奥行880mm |
|---|---|
| 消費電力 | 中:約97W、強:約134.7W |
| 機能 | ダニ退治機能 |
| 材質 | ポリエステル100% |
消臭機能付き!
1畳スクエアタイプのボリュームラグ付きホットカーペット。トリプルフレッシュを採用した本製品は、部屋の気になる臭いを消臭できます。
ダニ退治機能や滑り止め加工など、あったら嬉しいおすすめ機能も備えています。
※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格
| サイズ | 縦125×横125cm |
|---|---|
| 消費電力 | 200W |
| 機能 | ダニ退治機能 |
| 材質 | ポリエステル100% |
| サイズ | 縦125×横125cm |
|---|---|
| 消費電力 | 200W |
| 機能 | ダニ退治機能 |
| 材質 | ポリエステル100% |
防水加工付きのフローリング調
1畳タイプのフローリングのようなホットカーペットです。防水加工付きの本製品は水などをこぼしてもサッと拭くだけなのでお手入れが簡単!
温度も5段階で調節できるので、その時の気温に合わせて設定可能です。裏面滑り止め加工やダニ退治機能も備わっています。
※各社通販サイトの 2024年10月28日時点 での税込価格
| サイズ | 126×180cm |
|---|---|
| 消費電力 | 200W |
| 機能 | ダニ退治機能、表面防水加工 |
| 材質 | PVC |
| サイズ | 126×180cm |
|---|---|
| 消費電力 | 200W |
| 機能 | ダニ退治機能、表面防水加工 |
| 材質 | PVC |
トリプル断熱構造の便利機能付きカーペット
高性能ヒーターと優しい肌触りと軽やかな色合いが特徴的なカーペットがセットになっています。「トリプル断熱構造」を採用した本製品の魅力は、熱が伝わりやすく逃げにくい点!
ダニ対策モードや2時間・4時間切タイマー機能、8時間切り忘れ防止機能などの便利機能も備えています。
※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格
| サイズ | 約183cm×95cm |
|---|---|
| 消費電力 | - |
| 機能 | ダニ退治機能、2時間、4時間 切タイマー機能、8時間切り忘れ防止機能 |
| 材質 | ポリエステル100% |
| サイズ | 約183cm×95cm |
|---|---|
| 消費電力 | - |
| 機能 | ダニ退治機能、2時間、4時間 切タイマー機能、8時間切り忘れ防止機能 |
| 材質 | ポリエステル100% |
2面切り替えでエコに暖まる
ディズニーデザインが特徴的な電気カーペットです。2面切り替えが可能で節電対策にもなります。
手洗い・クリーニングの他にも丸洗いが可能で、ダニ対策機能もついているので清潔感も申し分ない商品です。2・4時間切タイマー機能や8時間切り忘れ防止機能も。
※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格
| サイズ | ヒーター部:約176×126×0.6cm、カバー部:約183×133cm |
|---|---|
| 消費電力 | - |
| 機能 | ダニ対策機能、2・4時間 切タイマー機能、8時間切り忘れ防止機能 |
| 材質 | ポリエステル |
| サイズ | ヒーター部:約176×126×0.6cm、カバー部:約183×133cm |
|---|---|
| 消費電力 | - |
| 機能 | ダニ対策機能、2・4時間 切タイマー機能、8時間切り忘れ防止機能 |
| 材質 | ポリエステル |
トリプルフレッシュ採用のラグサイズカーペット
ラグサイズの1畳タイプのホットカーペットです。トリプルフレッシュを採用した本製品は、部屋のニオイを吸着・分解してくれる「空気をきれいにする」ホットカーペット!
暖房面を全面・左面・右面で切り替えができるので、暖めたい場所のみを温められて経済的です。ダニ退治機能も搭載。
※各社通販サイトの 2025年2月3日時点 での税込価格
| サイズ | 85×170cm |
|---|---|
| 消費電力 | 160W |
| 機能 | ダニ退治機能、24時間サイクル消臭機能 |
| 材質 | - |
| サイズ | 85×170cm |
|---|---|
| 消費電力 | 160W |
| 機能 | ダニ退治機能、24時間サイクル消臭機能 |
| 材質 | - |
フランネル素材のふわりとした肌触りが魅力
厚手でふわふわなフランネル仕上げの1人用ホットカーペットです。保温性が高く肌触りの良い生地は、ついついずっと上に寝転んでいたいと思ってしまうはず。
温度は6段階で調整可能なほか、タイマー機能もついており使い勝手も抜群。3時間での自動OFF機能も搭載されており、安全面にも配慮されています。コントローラーを外せば洗濯機で丸洗いできるのでお手入れも容易です。
※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格
| サイズ | 180×80cm |
|---|---|
| 消費電力 | 80W |
| 機能 | タイマー機能、6段階温度調整、消し忘れ防止機能、過熱保護機能、過圧保護機能、ダニ退治機能 |
| 材質 | ポリエステル |
| サイズ | 180×80cm |
|---|---|
| 消費電力 | 80W |
| 機能 | タイマー機能、6段階温度調整、消し忘れ防止機能、過熱保護機能、過圧保護機能、ダニ退治機能 |
| 材質 | ポリエステル |
ホットカーペットおすすめ7選|2畳 2~3人用におすすめ!
汚れたら丸洗い可能!
表面温度は45℃(高)と37℃(中)に設定でき、1時間あたりの電気料金はそれぞれ約9.9円、約7.1円で使うことが可能です。切り忘れ防止(8時間)、2・4時間切タイマー、室温センサーなども搭載しており、電源を切り忘れる心配がありません。
カバー部分はマイヤー網のポリエステル100%、シャンプークリーニングができ、洗濯機での丸洗いもできます。
※各社通販サイトの 2024年11月18日時点 での税込価格
| サイズ | ヒーター部:約176×176×1cm、カバー部:約183×183cm |
|---|---|
| 消費電力 | 480W |
| 機能 | 省エネモード(室温センサー)、2時間、4時間、切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能など |
| 材質 | ヒーター部:フェルト(ポリエステル)、カバー部:ポリエステル100% |
| サイズ | ヒーター部:約176×176×1cm、カバー部:約183×183cm |
|---|---|
| 消費電力 | 480W |
| 機能 | 省エネモード(室温センサー)、2時間、4時間、切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能など |
| 材質 | ヒーター部:フェルト(ポリエステル)、カバー部:ポリエステル100% |
ベーシックな機能とデザインで人気!
和室にも洋室にもなじみやすいオーソドックスなデザインのホットカーペットです。機能性もシンプルで、5段階の温度調整と、暖房面(前面・左・右)を切り替えるだけ。お子さんから高齢者まで利用しやすい仕様になっています。
また、電源を入れて6時間経過すると、電源が自動で切れるオートオフタイマー機能が備わっているので、万が一の切り忘れにも対応。冬が終わりクローゼットに収納するときにも16折というコンパクトなサイズにたためるので、省スペースですよ。
※各社通販サイトの 2024年10月28日時点 での税込価格
| サイズ | 175cm×175cm(2畳) |
|---|---|
| 消費電力 | 520W |
| 機能 | ダニ退治機能、温度ヒューズ、オートオフタイマー、裏面滑り止め加工 |
| 材質 | ポリエステル |
| サイズ | 175cm×175cm(2畳) |
|---|---|
| 消費電力 | 520W |
| 機能 | ダニ退治機能、温度ヒューズ、オートオフタイマー、裏面滑り止め加工 |
| 材質 | ポリエステル |
節電対策をしたい方におすすめ!
カーペット全体を即座に温めるアルミ均熱シート、熱が床に逃げるのを抑える断熱マット、滑りにくさを考慮したアクリルコーティングというトリプル断熱構造を採用し、省エネで快適に温めてくれます。
2・4時間で自動的に電源をオフにするタイマーや、電源を入れて8時間経つと自動的に切れる切り忘れ防止機能も備えています。前面、左面、右面で切り替えて使用することで節電にもつながるのでおすすめですよ。
※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格
| サイズ | 176×176cm(2畳) |
|---|---|
| 消費電力 | 490 W |
| 機能 | 省エネモード、タイマー機能、8時間切り忘れ防止機能、ダニ対策機能 |
| 材質 | フェルト、ポリエステル |
| サイズ | 176×176cm(2畳) |
|---|---|
| 消費電力 | 490 W |
| 機能 | 省エネモード、タイマー機能、8時間切り忘れ防止機能、ダニ対策機能 |
| 材質 | フェルト、ポリエステル |
低価格ながら便利な機能を備える!
温める面積を調整できる機能や、ダニ防止機能を備えながら低価格なのが魅力のホットカーペットです。
2畳相当の大きさで、子ども部屋にもぴったり。切り忘れタイマーも搭載されているので、切り忘れもなくなり安心です。折りたたんで収納しやすいのもグッド!
※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格
| サイズ | 2畳相当(176×176cm) |
|---|---|
| 消費電力 | 500W |
| 機能 | ポリエステル |
| 材質 | ダニ防止機能、暖房面積切り替え、切り忘れ防止機能 |
| サイズ | 2畳相当(176×176cm) |
|---|---|
| 消費電力 | 500W |
| 機能 | ポリエステル |
| 材質 | ダニ防止機能、暖房面積切り替え、切り忘れ防止機能 |
フローリング調なので部屋内どこでもなじむ
2畳サイズのフローリング調ホットカーペットです。食べ物などの汚れをサッとふき取ることができるので、ダイニングテーブルの下などに設置するのもおすすめ。
お手入れが簡単なので、家事に時間が取れない忙しい人でも使いやすいです。
※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格
| サイズ | 2畳 |
|---|---|
| 消費電力 | 520W |
| 機能 | 滑り止め防止加工、ダニ防止機能、防水加工 |
| 材質 | ポリエステル100%、平織木目調プリント、透明PPシート |
| サイズ | 2畳 |
|---|---|
| 消費電力 | 520W |
| 機能 | 滑り止め防止加工、ダニ防止機能、防水加工 |
| 材質 | ポリエステル100%、平織木目調プリント、透明PPシート |
正方形の形が特徴的
正方形の形をしている2畳ほどのホットカーペットです。長方形のホットカーペットが多いなか、正方形の形なので狭いスペースでも置きやすいでしょう。
また、切り忘れ防止モードや省エネモードを搭載し、電気代の節約にもつながります。折りたためるので、省スペースで収納することもOK!
※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格
| サイズ | 2畳相当(176×176cm) |
|---|---|
| 消費電力 | 500W |
| 機能 | 6時間切り忘れタイマー、左右全面切り替え |
| 材質 | ポリエステル |
| サイズ | 2畳相当(176×176cm) |
|---|---|
| 消費電力 | 500W |
| 機能 | 6時間切り忘れタイマー、左右全面切り替え |
| 材質 | ポリエステル |
エネルギー効率の良いホットカーペット
インテリアに馴染む木目調の2畳ホットカーペットです。ソフトな座り心地の本製品は、ダブル断熱構造を採用!熱が逃げにくくて暖かさが維持される点が嬉しいポイントです。
2面切り替えが可能で、省エネ性も高いです。
※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格
| サイズ | 2畳相当(約176×176cm) |
|---|---|
| 消費電力 | - |
| 機能 | 2面切り替え3通り暖房、8時間切り忘れタイマー |
| 材質 | 塩化ビニール |
| サイズ | 2畳相当(約176×176cm) |
|---|---|
| 消費電力 | - |
| 機能 | 2面切り替え3通り暖房、8時間切り忘れタイマー |
| 材質 | 塩化ビニール |
ホットカーペットおすすめ4選|3畳 ダイニングテーブルの下に敷いても!
基本性能を備えた3畳タイプ
3畳サイズのホットカーペットです。こたつのように使えば、全身がポッカポカになりますよ。
温度の5段階調整や、切り忘れ防止機能、ダニ防止機能、暖房切り替えスイッチなど、使いやすい基本的な機能を搭載しています。
※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格
| サイズ | 3畳 |
|---|---|
| 消費電力 | 中/約90.0Wh 強/約134.7Wh |
| 機能 | ダニ防止機能、自動切タイマー付き、連続通電防止機能付き |
| 材質 | ポリエステル |
| サイズ | 3畳 |
|---|---|
| 消費電力 | 中/約90.0Wh 強/約134.7Wh |
| 機能 | ダニ防止機能、自動切タイマー付き、連続通電防止機能付き |
| 材質 | ポリエステル |
何年も利用したいならコレ!
ホットカーペット以外にも、電気ヒザ掛けや、電気掛け敷き毛布など、いろんな暖房器具を展開するライフジョイ。こちらは、折りたたんで収納する際に電熱線が傷まないように、折りジワが付きにくいように工夫されているので、何年もきれいに使えます。
もちろん、二面切り替えや温度調整機能も搭載されており、ラクに経済的に使うことができます。電気安全環境研究所が認定するSマークを取得しているので、安心して利用できるのも魅力のひとつ!
※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格
| サイズ | 235cm×195cm(3畳) |
|---|---|
| 消費電力 | 720 W |
| 機能 | ダニ退治機能、8時間自動OFF機能、A面B面切替機能 |
| 材質 | ポリエステル |
| サイズ | 235cm×195cm(3畳) |
|---|---|
| 消費電力 | 720 W |
| 機能 | ダニ退治機能、8時間自動OFF機能、A面B面切替機能 |
| 材質 | ポリエステル |
3畳サイズでゆったりくつろげる
こたつとも併用できる3畳サイズのホットカーペット。使わないときはコンパクトに折りたためるので狭い空間でも使いやすいです。
8時間経つと自動で切れるタイマー機能や、ダニ防止機能、温度調節機能を備えています。
※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格
| サイズ | 195×235cm 約3畳 |
|---|---|
| 消費電力 | 720W |
| 機能 | 自動電源OFF機能、温度調節機能、ダニ退治機能 |
| 材質 | ポリエステル100% |
| サイズ | 195×235cm 約3畳 |
|---|---|
| 消費電力 | 720W |
| 機能 | 自動電源OFF機能、温度調節機能、ダニ退治機能 |
| 材質 | ポリエステル100% |
暖めたい部分だけを温められる3畳カーペット
暖房面を2面切り替えできる本製品は、暖めたい部分だけを効率よく暖めることができるので電気代の節約にもピッタリ!
ダニ退治機能を備えるほか、カバーを丸洗いすることもできます。
※各社通販サイトの 2024年10月28日時点 での税込価格
| サイズ | 235×195cm(3畳相当) |
|---|---|
| 消費電力 | 740W |
| 機能 | ダニ退治機能、2時間切タイマー、切り忘れ防止6時間自動オフ |
| 材質 | ポリエステル100% |
| サイズ | 235×195cm(3畳相当) |
|---|---|
| 消費電力 | 740W |
| 機能 | ダニ退治機能、2時間切タイマー、切り忘れ防止6時間自動オフ |
| 材質 | ポリエステル100% |
「ホットカーペット」のおすすめ商品の比較一覧表
| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | サイズ | 消費電力 | 機能 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)『ホットカーペット 木目調(HCM-1105FL-M)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |
水まわりに最適! お手入れ簡単で常に清潔 | 縦45×横110cm(0.3畳相当) | 64.5W | 温度調整2段階、撥水加工 | 表/ポリ塩化ビニル100%、裏/ポリエステル100% |
| TEKNOS(テクノス)『ミニマット(EC-K4001)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |
デスクワークのおともに最適! | 40×40cm | 26W | - | ポリエステル |
| IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)『ホットカーペット IHC-10-H』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |
1畳サイズの一人用ホットカーペット | 176×88cm | 200W | 5段階温度調節、ダニ退治機能 | ポリエステル100% |
| KODEN(広電)『電気カーペット(VWU1013)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |
コスパにこだわったおひとりさま用 | 約縦88×横176cm(1畳相当) | 200W | ダニクリーン、スライド調節 | ポリエステル100% |
| YAMAZEN(山善)『洗えるどこでもカーペット(YWC-182F)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |
やわらかいフランネルマットでくつろごう | 縦80×横180cm(1畳相当) | 70W | 丸洗い可能、フランネル仕上げ、室温センサー付き | ポリエステル100% |
| MORITA(モリタ)『電気カーペット(TMC-100)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |
温度幅の広い電気カーペット | 約176×88cm (1畳相当) | 100Ⅴ(50/60Hz)・200W | 8つ折り収納、ダニ対策機能 | ポリエステル100% |
| ライフジョイ『日本製 ホットカーペット 1畳 正方形 グレー』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |
ダニ退治できる正方形カーペット | 125cm×125cm | 中:約114W、強:約164W (50/60Hz) | ダニ退治機能 | ポリエステル100% |
| ユアサプライムス『ホットカーペット 1畳 YC-Y10Y』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月28日時点 での税込価格 |
基本的な機能をおさえたスタンダードなカーペット | 幅1760mm×奥行880mm | 中:約97W、強:約134.7W | ダニ退治機能 | ポリエステル100% |
| YAMAZEN(山善)『ホットカーペット カバーセット(YZF-132)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |
消臭機能付き! | 縦125×横125cm | 200W | ダニ退治機能 | ポリエステル100% |
| YAMAZEN(山善)『フローリング調 ホットカーペット 1畳(YZC-109FL)』 |
|
※各社通販サイトの 2024年10月28日時点 での税込価格 |
防水加工付きのフローリング調 | 126×180cm | 200W | ダニ退治機能、表面防水加工 | PVC |
| Panasonic(パナソニック)『ホットカーペット 着せかえカバー付きセット(DC-1NKB1-C)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |
トリプル断熱構造の便利機能付きカーペット | 約183cm×95cm | - | ダニ退治機能、2時間、4時間 切タイマー機能、8時間切り忘れ防止機能 | ポリエステル100% |
| Panasonic(パナソニック)『ホットカーペット ディズニーデザイン(DC-15NKCD2)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |
2面切り替えでエコに暖まる | ヒーター部:約176×126×0.6cm、カバー部:約183×133cm | - | ダニ対策機能、2・4時間 切タイマー機能、8時間切り忘れ防止機能 | ポリエステル |
| YAMAZEN(山善)『空気をきれいにする ホットカーペット 1畳(SUS-101)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月3日時点 での税込価格 |
トリプルフレッシュ採用のラグサイズカーペット | 85×170cm | 160W | ダニ退治機能、24時間サイクル消臭機能 | - |
| Keep warm『電気カーペット(HB82-080180)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |
フランネル素材のふわりとした肌触りが魅力 | 180×80cm | 80W | タイマー機能、6段階温度調整、消し忘れ防止機能、過熱保護機能、過圧保護機能、ダニ退治機能 | ポリエステル |
| Panasonic(パナソニック)『着せ替えカーペット セットタイプ(DC-2HAC3-C)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月18日時点 での税込価格 |
汚れたら丸洗い可能! | ヒーター部:約176×176×1cm、カバー部:約183×183cm | 480W | 省エネモード(室温センサー)、2時間、4時間、切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能など | ヒーター部:フェルト(ポリエステル)、カバー部:ポリエステル100% |
| YAMAZEN(山善)『ホットカーペット 2畳(AUB-200)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月28日時点 での税込価格 |
ベーシックな機能とデザインで人気! | 175cm×175cm(2畳) | 520W | ダニ退治機能、温度ヒューズ、オートオフタイマー、裏面滑り止め加工 | ポリエステル |
| Panasonic(パナソニック)『ホットカーペット(DC-2NK)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |
節電対策をしたい方におすすめ! | 176×176cm(2畳) | 490 W | 省エネモード、タイマー機能、8時間切り忘れ防止機能、ダニ対策機能 | フェルト、ポリエステル |
| TEKNOS(テクノス)『ホットカーペット 2畳用(TWA-2000B)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |
低価格ながら便利な機能を備える! | 2畳相当(176×176cm) | 500W | ポリエステル | ダニ防止機能、暖房面積切り替え、切り忘れ防止機能 |
| YAMAZEN(山善)『ホットカーペット フローリング調 2畳(YZC-207FL)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |
フローリング調なので部屋内どこでもなじむ | 2畳 | 520W | 滑り止め防止加工、ダニ防止機能、防水加工 | ポリエステル100%、平織木目調プリント、透明PPシート |
| MORITA(モリタ)『ホットカーペット 2畳用(TMC-200)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |
正方形の形が特徴的 | 2畳相当(176×176cm) | 500W | 6時間切り忘れタイマー、左右全面切り替え | ポリエステル |
| Panasonic(パナソニック)『ホットカーペット フローリング調(DC-2V4-MC)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |
エネルギー効率の良いホットカーペット | 2畳相当(約176×176cm) | - | 2面切り替え3通り暖房、8時間切り忘れタイマー | 塩化ビニール |
| IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)『電気ホットカーペット 単品(IHC-30-H)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |
基本性能を備えた3畳タイプ | 3畳 | 中/約90.0Wh 強/約134.7Wh | ダニ防止機能、自動切タイマー付き、連続通電防止機能付き | ポリエステル |
| ライフジョイ『ホットカーペット(JPU301H)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |
何年も利用したいならコレ! | 235cm×195cm(3畳) | 720 W | ダニ退治機能、8時間自動OFF機能、A面B面切替機能 | ポリエステル |
| タンスのゲン『ホットカーペット 約3畳』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |
3畳サイズでゆったりくつろげる | 195×235cm 約3畳 | 720W | 自動電源OFF機能、温度調節機能、ダニ退治機能 | ポリエステル100% |
| KOIZUMI(コイズミ)『電気カーペット カバー付きセット(KDC-30227)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月28日時点 での税込価格 |
フローリングタイプの決定版 | 235×195cm(3畳相当) | 740W | ダニ退治機能、2時間切タイマー、切り忘れ防止6時間自動オフ | ポリエステル100% |
【ランキング】通販サイトの最新人気! ホットカーペットの売れ筋をチェック
Amazon、楽天市場でのホットカーペットの売れ筋ランキングも参考にしてみてください。
※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。
【豆知識】ホットカーペットの電気代はいくら?
ホットカーペットの電気代は、サイズや使う電力量によって1カ月の電気代が異なります。おおよその目安は下記の計算式で求めることができます。
消費電力(W) ÷ 1,000 × 使用時間(h)×電気代単価(円/kWh)
例)消費電力200W、1日あたり8時間使用、電気代単価31円/kWhの場合
▼1日あたりの電気代
200(W) ÷1000×8(h)×31(円/kWh)=49.6(円)
▼1カ月あたりの電気代
49.6(円)×30(日)=1,488(円)
サイズが大きくなるほど使用電力が多くなり電気代もかかりますが、ファンヒーターや電気ヒーターなどに比べるとホットカーペットのほうが安く済みます。
【Q&A】悩みを解決!


消費電力200W、1日あたり8時間使用、電気代単価31円/kWhの場合の目安料金は下記のとおりです。
▼1日あたりの電気代
200(W) ÷1000×8(h)×27(円/kWh)=49.6(円)
▼1ヶ月あたりの電気代
49.6(円)×30(日)=1,488(円)
製品ごとに異なる消費電力と、電力会社ごとに異なる電気代の料金によって料金は変わってきます。電気代を求める計算式などはこちらに詳しく記してあります。
>>電気代の詳細をチェック


ホットカーペットの寿命は一般的に5年~6年といわれています。理由は、補修用性能部品の保有期間が製造打ち切り後、5年~6年となっている商品が多いことが理由です。
しかし、下記に当てはまる場合は買い替えを検討しましょう。
・電源がつかない
・温かくならない
・ボロボロ・破れている
・変な臭いがする
使用頻度が低い場合は、5~6年以上使える場合もありますが、故障する前に買い替えるようにしましょう。一つの目安として参考にしてみてください。


基本的には、住んでいる地域の自治体の決まりに合わせて捨てるようにしましょう。処分方法はまちまちですが、目安となる捨て方も一応ご紹介します。
ホットカーペットに付いているコード類を取り外します。コード類は金属ゴミとして、カーペットは燃えるゴミとして処分。カーペットはあまりにサイズが大きいと粗大ゴミ扱いになるので、切って小さくするか、折りたたむといいですよ。
【関連記事】犬用などのホットカーペットをチェック
最後に|エキスパートのアドバイス
ホットカーペット本体のみの場合、最大のメリットは価格の安さになります。
カバーつきのホットカーペットは2万~5万円程度のものが多いなか、本体のみであれば5,000円程度から買うことができ、ここに市販のラグを敷いてあげると、コスパとしては非常にいいです。
しかし、購入した市販のラグがあまりにも薄かったり厚かったりすると、ホットカーペットの温度が高くなりすぎたり、全く暖まらなかったりといった弊害が起こる場合も。予算的に余裕があるのであれば、カバーつきのほうが無難です。
おすすめ商品・口コミの投稿はこちら
※メーカーや販売店の方は、ページ下部の「お問い合わせはこちら」から商品情報をお送りください。
ユーザーが選んだイチオシ商品の口コミ情報は、マイナビおすすめナビを閲覧したユーザー、マイナビニュース会員、外部パートナー企業と契約する一般ユーザーからの投稿をもとにしています。
◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。