デスクヒーターの選び方
それでは、デスクヒーターの基本的な選び方を見ていきましょう。ポイントは下記。
【1】ヒーターのタイプ
【2】機能やデザイン
【3】安全性
【4】省エネ性能
【5】電源
上記のポイントを押さえることで、より具体的に欲しい製品を見つけることができます。一つひとつ解説していきます。
【1】デスクヒーターのタイプを選ぶ

出典:マイナビおすすめナビ

出典:マイナビおすすめナビ
デスクヒーターは大きく分けて「パネル」「マット」「スタンド」の3つのタイプがあります。それぞれに使いやすいポイントがあるのでシーンや、置く場所に応じて選んでみましょう。
パネル|デスク下に取りつける
「パネル型」は、デスクの引き出しの下や側面などに設置できるタイプです。熱を放つ面積が広いため、下半身を中心にポカポカと暖まります。ヒザ掛けと一緒に使えば、より暖かさを感じられるでしょう。
スチール製のデスクに取りつける場合は、マグネット式のパネル型ヒーターが便利です。床置きできるスタンドがセットになった商品も販売されています。
また多くのパネル式は、ホットマットのような使い方もできるので便利ですよ。
マグネット|金属部分に取りつける
デスクヒーターの「マグネット型」は、デスクの金属部分に簡単に取り付けられるパネルヒーターです。
主な特徴として、取り付けが簡単で、省エネ設計が施されており、電力消費を抑えつつ効果的に暖めます。また、自動オフタイマーや過熱防止機能が付いているため、安全に使用できます。薄型でコンパクトなデザインなので、デスク下に設置しても邪魔になりません。寒い季節に足元を暖めるのに最適なアイテムです。
スタンド|デスク下の脇に置く
デスク下の脇に置いて使用する「スタンド型」。温風を送り出して素早く暖める対流式と、穏やかな熱でじんわり暖める輻射式の2種類があります。デスクの側板を利用して、足元に暖かい空気を閉じ込めることができるのも、スタンド型のメリットです。
スタンド型は、席を立つ際にうっかり足をぶつけてしまう可能性があるので、安定感のある倒れにくい商品を選ぶといいでしょう。
マット|床置きで足裏から温まる
「マット型」は、マットのように床の上に置いて使用します。足を乗せると足裏から熱が伝わり、じんわりと温まるのが特徴です。床からの冷気を遮断してくれるので、椅子に座ったときに足元の冷えが気になるという人にぴったり!
サイズ展開が豊富でいろんな使い方ができるのが魅力。イスの上に敷いて下半身を温めたり、ヒザに乗せて腹部を温めたりできますよ。マットの中に足をすっぽり入れられる商品も販売されています。
【2】機能やデザインをチェック
デスクヒーターにはさまざまな種類があります。どこで使うかを考慮して機能やデザインを選びましょう。
オフィス用|コンパクトで静音性の高いものを
デスクヒーターを自宅以外の場所で使う場合は、周囲の迷惑にならないように配慮が必要です。もし、オフィスで使うなら、デスクの下に収まるコンパクトなものを選びましょう。デスクの脇や通路にヒーターを置くと、ほかの人が移動する際に邪魔になることがあります。
また、静かなオフィスなら、静音性の高さもチェックしておきたいポイントです。シンプルなデザインを選ぶのも重要ですね。
家庭用|収納しやすくて多機能なものを
デスクヒーターは寒い季節に活躍するアイテムです。それ以外の季節は押し入れなどにしまっておくことになるので、コンパクトに収納できるものが便利です。折りたためるものや軽いものや、取っ手がついたものなら、ラクに片づけられます。
もし、収納スペースに余裕がない場合は、サーキュレーター機能付きを選ぶのもひとつの手。オールシーズン使えるので、そのまま部屋に置いておくことができます。
【3】安全性もチェック
電気で発熱するデスクヒーターは、取扱説明書にしたがって適切に使う必要があります。これから紹介する機能にも注目してみてください。
自動電源オフ機能|切り忘れや、急な転倒でも安心
▼転倒時電源遮断機能
立てて使用するスタンド式ヒーターは安定性をチェック! 足元に置くため、うっかり足で蹴ったり引っかける可能性があります。転倒したとき、自動的に電源が切れるオフ機能があると安心です。
子どもやペットがいる家庭なら、いたずらして倒れても問題ないように、必ず転倒時電源遮断機能を搭載する商品を選ぶようにしましょう。
▼タイマー機能
一定時間が経つと自動的に電源が切れるタイマー機能があれば、うっかり電源を切り忘れても安心。余計な電気代もかけずに済みます。
人感センサー機能|人の動きを察知して稼働する
人感センサーとは、自動で人の動きを察知して、運転を開始・停止してくれる機能です。
ヒーターの前に人が来ると自動で運転を開始し、人がいなくなると自動で運転を停止します。運転停止後、そのまま一定時間経過すると自動で電源が切れる機能が付いた商品も販売されています。電気代を節約したい人に嬉しい機能です。
【4】省エネ性能をチェック
デスクヒーターは基本的に補助的な暖房なので、コンパクトで空気を汚さない電気式がおすすめです。さほど電力は消費しないものの、長時間連続して使用することが多いため、電気代は気になるところ。
なので、多少価格が高くても省エネタイプを選ぶといいでしょう。電気代か暖めるパワーか、どちらを優先させるかを決めてからアイテムを選択しましょう。
▼消費電力はなるべく抑えたい
熱源が小さいタイプ、マットヒーターやパネルヒーターがおすすめ
▼温かさが優先
遠赤外線ヒーターやファンヒーターがおすすめ。
なお、暖かさをとことん重視するなら、燃料代は別途かかるものの石油ストーブがピカイチ。
【5】電源をチェック
デスクヒーターはコンセントで給電するタイプが多いですが、なかにはUSBケーブルで給電できるものもあります。パソコンなどのUSBポートに接続して使えるため、近くにコンセントがない場合や、コンセントが足りない場合にも便利です。
USBタイプはコンパクトサイズで省電力なものが多いため、オフィスでの使用にも向いています。ただ出力が低いため、過度に期待するのは禁物。
ユーザーが選んだイチオシ4選
ここでは、みんながおすすめする「デスクヒーター」を紹介します。 商品の口コミはもちろん、コスパ、機能性、使いやすさといった評価ポイントも聞いてみたので、各項目にも注目して商品選びの参考にしてください!
その他にもおすすめしたい商品があるよという方は、ぜひ記事後半にある投稿フォームからご紹介をお願いします。
コンパクトなのにパワフル温風
手軽に使えるコンパクト設計のセラミックファンヒーターです。
生活防水対応で置き場所に困らず、机の下などに置いて快適に使えます。また、取っ手付きで持ち運びも楽で、コードも収納可能なスペース付き。
※各社通販サイトの 2025年1月9日時点 での税込価格
| サイズ | 幅28cm×高さ31.5cm×奥行き13.5cm |
|---|---|
| 重量 | 2.5kg |
| タイプ | スタンド式 |
| 消費電力 | 温風「強」:1170/1120W(50/60Hz温風「弱」:640/615W(50/60Hz) |
| 電源コード長さ | 1.8m |
| カラー | ホワイト |
| サイズ | 幅28cm×高さ31.5cm×奥行き13.5cm |
|---|---|
| 重量 | 2.5kg |
| タイプ | スタンド式 |
| 消費電力 | 温風「強」:1170/1120W(50/60Hz温風「弱」:640/615W(50/60Hz) |
| 電源コード長さ | 1.8m |
| カラー | ホワイト |

愛用者
人感センサーつきで便利
リモートワークが増えてきたので、こちらを購入しました。冬場足元が冷えると仕事に集中できなかったのですが、こちらを使用してから快適です。少し席を離れるときにも自動で運転を停止してくれるので重宝しています。(T.A.さん/女性/35歳/会社員)
【デメリットや気になった点】
しばらく動かないとセンサーで止まってしまうこともあります。(T.A.さん/女性/35歳/会社員)
※各社通販サイトの 2025年1月28日時点 での税込価格
| コスパ | ★★★★☆ |
|---|---|
| 機能性 | ★★★★★ |
| 使いやすさ | ★★★★★ |
| 総合評価 | 4.7点 |
| コスパ | ★★★★☆ |
|---|---|
| 機能性 | ★★★★★ |
| 使いやすさ | ★★★★★ |
| 総合評価 | 4.7点 |

愛用者
足でかんたんにスイッチオン!
足踏み式のコンパクトタイプだから、デスクワークにぴったりと思い購入しました。熱伝導率の高い遠赤外線のため、スイッチをオンしてから暖かさを感じるまでが早いのがうれしい。対応範囲も8畳までで、寝室や脱衣所などさまざまなシーンで活躍します。(A.I.さん/女性/38歳/パート)
【デメリットや気になった点】
店頭自動停止の機能はありますが、タイマー機能はないので、つけっぱなしには注意が必要。(A.I.さん/女性/38歳/パート)
※各社通販サイトの 2024年12月02日時点 での税込価格
| コスパ | ★★★☆☆ |
|---|---|
| 機能性 | ★★★☆☆ |
| 使いやすさ | ★★★★☆ |
| 総合評価 | 3.3点 |
| コスパ | ★★★☆☆ |
|---|---|
| 機能性 | ★★★☆☆ |
| 使いやすさ | ★★★★☆ |
| 総合評価 | 3.3点 |

愛用者
じんわりと足元を温めてくれる
マグネットに対応するデスクであれば、デスクにパネルをひっつけることができるので場所をとらず足元をあたためられます。さらに、とっても薄型でシンプルな作りをしているところも扱いやすくおすすめです。この機能性で1万円せずに購入できることにびっくりですよ。(T.S.さん/女性/25歳/会社員)
【デメリットや気になった点】
あたっているところからじんわり温まるので、足全体を温めたい方などには不向きかもしれません。(T.S.さん/女性/25歳/会社員)
※各社通販サイトの 2025年1月28日時点 での税込価格
| コスパ | ★★★★★ |
|---|---|
| 機能性 | ★★★★★ |
| 使いやすさ | ★★★★★ |
| 総合評価 | 5.0点 |
| コスパ | ★★★★★ |
|---|---|
| 機能性 | ★★★★★ |
| 使いやすさ | ★★★★★ |
| 総合評価 | 5.0点 |
デスクヒーターおすすめ6選|パネルタイプ
それでは、デスクヒーターのおすすめ商品をご紹介いたします。まずはパネルタイプの商品です。
デスクの下に立てるだけの薄型ヒーター
デスクの下で足元をじんわりと温めてくれるデスクヒーター。電気による輻射熱で温めるので、空気を汚さず、小さい子どもやペットがいる家でも安心です。
セッティングはコの字形に立てるだけ。ボディカラーはグレーでシンプルなデザインに仕上がっており、部屋に置いてもインテリアになじみやすいですよ。
3つ折りにしてコンパクトに収納することもできます。温度調節は強(標準表面温度55度)と弱(同37度)の2段階に切り替えが可能。
※各社通販サイトの 2024年12月02日時点 での税込価格
| サイズ | 48×45×30cm |
|---|---|
| 重量 | 2.2kg |
| タイプ | マット型 |
| 消費電力 | 165W |
| 電源コード長さ | 180cm |
| カラー | グレー |
| サイズ | 48×45×30cm |
|---|---|
| 重量 | 2.2kg |
| タイプ | マット型 |
| 消費電力 | 165W |
| 電源コード長さ | 180cm |
| カラー | グレー |
軽量コンパクトで設置しやすい
LaFuture『ロイヤルパネルヒーター』は、「速暖」「無補充」「クリーン」「無音無臭」と環境にやさしいスマートスタイル。遠赤外線のじんわりとした温かさ。高密度の定形炭素結晶が遠赤外線を放射伝達して体の芯から温めます。
5段階の温度調節が可能で、【強】55~60℃【中】45~50℃【弱】40℃。操作も簡単なのでお子さまからご年配の方まで操作できます。また、【温度の過上昇の防止】【本体が45°以上倒れると自動OFF】【9時間タイマー】といった3つの安全装置を装備しています。
※各社通販サイトの 2025年1月28日時点 での税込価格
| サイズ | 43×38×52cm |
|---|---|
| 重量 | 約1.3kg |
| タイプ | パネル型 |
| 消費電力 | 195W |
| 電源コード長さ | 245cm |
| カラー | ファブリックグレー、ファブリックベージュ、モロッカンロゼ |
| サイズ | 43×38×52cm |
|---|---|
| 重量 | 約1.3kg |
| タイプ | パネル型 |
| 消費電力 | 195W |
| 電源コード長さ | 245cm |
| カラー | ファブリックグレー、ファブリックベージュ、モロッカンロゼ |
軽量コンパクト・高い安全性
Orthland『デスクヒーター』は、足元を全方位から温める円柱型のパネルヒーターです。サイズは幅40cm×高さ50cm、重量は約1.08kgと軽量でコンパクト。消費電力は124Wで、電源コードの長さは約140cmです。シンプルなグレーカラーで、どんなインテリアにも馴染みます。
また、転倒時自動オフ機能や過熱防止装置を備えており、安全性も高いです。冷え性の方やデスクワーク中に足元の冷えを感じる方にとくにおすすめです。
※各社通販サイトの 2024年12月02日時点 での税込価格
| サイズ | 40×50cm |
|---|---|
| 重量 | 約1.08kg |
| タイプ | パネル型 |
| 消費電力 | 124W |
| 電源コード長さ | 約140cm |
| カラー | グレー |
| サイズ | 40×50cm |
|---|---|
| 重量 | 約1.08kg |
| タイプ | パネル型 |
| 消費電力 | 124W |
| 電源コード長さ | 約140cm |
| カラー | グレー |
四方から脚を温める!
脚を四方から温めてくれるデスクパネルヒーターです。ヒザ下全体を温めれば、パソコン作業も寒さを感じることなく行えるはずですよ。
温度調整は無段階で弱~強を選択できるので、寒さに応じて使い分けることも。折りたたむと厚さ数センチになるので、棚の隙間などに収納しやすいのもこちらの商品のいいところ。ヒザ掛けを合わせて使用すれば、よりあったかく感じるでしょう。
※各社通販サイトの 2024年12月02日時点 での税込価格
| サイズ | 幅50×奥行30×高さ50cm |
|---|---|
| 重量 | 1.6kg |
| タイプ | パネル式 |
| 消費電力 | 130W |
| 電源コード長さ | 2m |
| カラー | グレー |
| サイズ | 幅50×奥行30×高さ50cm |
|---|---|
| 重量 | 1.6kg |
| タイプ | パネル式 |
| 消費電力 | 130W |
| 電源コード長さ | 2m |
| カラー | グレー |
薄く軽い赤外線パネルで収納も楽チン!
人が近づくと自動で運転し、人がいなくなると停止する人感センサーを搭載したパネルヒーター。遠赤外線で脚を芯から温めてくれるタイプです。パワーがあるので、凍えるような寒い朝でもホッカホカにしてくるはずですよ。
また重さは約1.5kgと比較的軽量なので持ちやすく、スタンドは回転するので隙間に収納するのもラク。転倒オフスイッチや、温度ヒューズ、サーモスタットなど安全性もしっかり備えています。
※各社通販サイトの 2024年12月02日時点 での税込価格
| サイズ | W50×D23×H53.5cm |
|---|---|
| 重量 | 約1.5kg |
| タイプ | パネル式 |
| 消費電力 | 220W |
| 電源コード長さ | 2.0m |
| カラー | ブラウン |
| サイズ | W50×D23×H53.5cm |
|---|---|
| 重量 | 約1.5kg |
| タイプ | パネル式 |
| 消費電力 | 220W |
| 電源コード長さ | 2.0m |
| カラー | ブラウン |
コスパが良く、過熱防止機能付きで優れた製品
この製品は、急激に温める、というわけではなく、じんわりと足を温めてくれる製品です。パネル式でよくある悩みの一つである「パネルが転倒してしまう!」という悩みも、これが解決。地面にしっかり固定できるので、倒れる心配なく使えますよ。
サーモスタット機能と呼ばれる、過熱を防止してくれる優れた機能も搭載するのでおすすめです。
※各社通販サイトの 2025年1月28日時点 での税込価格
| サイズ | 幅40.5×奥行15×高さ32.5cm |
|---|---|
| 重量 | 1.7 kg |
| タイプ | パネル式 |
| 消費電力 | 160W |
| 電源コード長さ | 約1.9m |
| カラー | 1色 |
| サイズ | 幅40.5×奥行15×高さ32.5cm |
|---|---|
| 重量 | 1.7 kg |
| タイプ | パネル式 |
| 消費電力 | 160W |
| 電源コード長さ | 約1.9m |
| カラー | 1色 |
デスクヒーターおすすめ2選|マグネットタイプ
続いては、マグネット型のデスクヒーターです。こちらもぜひ参考にしてください。
デスクの下をコタツにする!? 小型ヒーター
机の下(引き出し下)に取りつけるタイプのデスクヒーター。机に座っていることが多いなら、このタイプがおすすめですよ。机と本体を付属の金具と両面テープ、マグネットでくっつける仕組みです。
ヒーターのまわりに専用フリースカバーをかぶせるため、暖かさを逃がさず、ヒザや太ももを優しく暖めてくれます。カバーはポリエステル100%で保温性が高く、洗濯機で洗えます。
温度の上がりすぎを防ぐ安全機能(抵抗付温度ヒューズ)のほか、3時間自動OFFタイマーも装備しています。
※各社通販サイトの 2024年12月02日時点 での税込価格
| サイズ | 幅46×奥行35×高さ3cm |
|---|---|
| 重量 | 約880g |
| タイプ | パネル型 |
| 消費電力 | 90W |
| 電源コード長さ | 約1.8m |
| カラー | ブラウン |
| サイズ | 幅46×奥行35×高さ3cm |
|---|---|
| 重量 | 約880g |
| タイプ | パネル型 |
| 消費電力 | 90W |
| 電源コード長さ | 約1.8m |
| カラー | ブラウン |
便利なマグネット式でオフィスで活躍
鉄製のデスクを使っている人におすすめのデスクヒーターです。裏にマグネットが付いており、机下にくっ付ければ脚を温められますよ。
これから寒くなる季節に、オフィスで活躍間違いなしです。手元のスイッチでオン・オフが調整でき、操作も簡単なのでオフィスの新戦力として期待できます。
※各社通販サイトの 2024年12月02日時点 での税込価格
| サイズ | 38×33×4cm |
|---|---|
| 重量 | 約1kg |
| タイプ | パネル式 |
| 消費電力 | 50W |
| 電源コード長さ | 約1.8m |
| カラー | 1色 |
| サイズ | 38×33×4cm |
|---|---|
| 重量 | 約1kg |
| タイプ | パネル式 |
| 消費電力 | 50W |
| 電源コード長さ | 約1.8m |
| カラー | 1色 |
デスクヒーターおすすめ6選|スタンドタイプ
続いては、スタンド型の赤外線ヒーター・ファンヒーターです。こちらもぜひ参考にしてください。
防滴仕様で水まわりでも安心
風向ルーバーや風量の2段階調節などの機能面も充実していますが、最大の特徴は、防滴仕様な点。トイレや脱衣所など、水しぶきがかかりそうな場所でも安心して設置できます。
幅21.8cm×奥行き12.5cm×高さ26.5cmというコンパクトサイズで、重量は2.0kgと軽量なので、いろんな場所に持ち運んで使えますよ。
※各社通販サイトの 2024年12月02日時点 での税込価格
| サイズ | W280×D135×H315㎜ |
|---|---|
| 重量 | 2.6kg |
| タイプ | スタンド式 |
| 消費電力 | 1170W/1120W(50/60Hz)、640/615W(50/60Hz) |
| 電源コード長さ | 180cm |
| カラー | ホワイト |
| サイズ | W280×D135×H315㎜ |
|---|---|
| 重量 | 2.6kg |
| タイプ | スタンド式 |
| 消費電力 | 1170W/1120W(50/60Hz)、640/615W(50/60Hz) |
| 電源コード長さ | 180cm |
| カラー | ホワイト |
大風量でコンパクト! すぐに温まる
重さ2.5kgとコンパクトなアイリスオーヤマのセラミックファンヒーター。大風量なので広い部屋でも活躍します。人感センサーが搭載されているので消し忘れの心配もなく、節電対策ができるのもグッド!
カラーバリエーションも豊富で、部屋のインテリアに合わせて購入できます。
※各社通販サイトの 2024年12月02日時点 での税込価格
| サイズ | 幅約26×奥行約13.5×高さ約37.9cm |
|---|---|
| 重量 | 2.5kg |
| タイプ | スタンダードタイプ |
| 消費電力 | 1200W |
| 電源コード長さ | - |
| カラー | ホワイト、ピンク、ブルーほか |
| サイズ | 幅約26×奥行約13.5×高さ約37.9cm |
|---|---|
| 重量 | 2.5kg |
| タイプ | スタンダードタイプ |
| 消費電力 | 1200W |
| 電源コード長さ | - |
| カラー | ホワイト、ピンク、ブルーほか |
グッドデザイン賞を受賞したパワフルマシン!
角を取り丸く仕上げたころんとした形状でセラミックヒーターらしくないデザイン性に富んだ1台。2022年にグッドデザイン賞を受賞しており、おしゃれな家にもぴったりハマるはずです。
ハンドル付きで、デスクヒーターとしてだけでなく、リビングや寝室、キッチンなどに気軽に持ち運んで利用できますよ。
快適な温度をキープしてくれる室温センサーや、人がいなくなると自動的に電源が切れる人感センサーなどを搭載し、使い勝手も良好。転倒や振動を検知する機能も付いており、子ども部屋にも利用しやすいですね。
※各社通販サイトの 2024年12月02日時点 での税込価格
| サイズ | W236×H203×D232 mm |
|---|---|
| 重量 | 2.5 kg |
| タイプ | スタンド式 |
| 消費電力 | 1200W |
| 電源コード長さ | 1.8m |
| カラー | ホワイト |
| サイズ | W236×H203×D232 mm |
|---|---|
| 重量 | 2.5 kg |
| タイプ | スタンド式 |
| 消費電力 | 1200W |
| 電源コード長さ | 1.8m |
| カラー | ホワイト |
コンパクトながら機能も優秀!
手のひらサイズかつ、重量が820gという設計で持ち運びやすいセラミックファンヒーターです。角度調整ができるため、いろんな足の部位をピンポイントで温めることができます。
転倒時には自動で電源がオフになるのも、デスク下で使うには嬉しいポイント。弱・中・強と3つから風量が選べたり、人感センサーを搭載していたりと、電気代を抑えながら使えるはずです!
※各社通販サイトの 2024年12月02日時点 での税込価格
| サイズ | W118×H157×D102 mm |
|---|---|
| 重量 | 0.82 kg |
| タイプ | スタンド式 |
| 消費電力 | 300W |
| 電源コード長さ | 約1.5m |
| カラー | ホワイト |
| サイズ | W118×H157×D102 mm |
|---|---|
| 重量 | 0.82 kg |
| タイプ | スタンド式 |
| 消費電力 | 300W |
| 電源コード長さ | 約1.5m |
| カラー | ホワイト |
レトロな雰囲気で使えるスタンダードタイプ
丸みを帯びたかわいらしいフォルムで、レトロな雰囲気の電気ストーブ。発熱体は石英管ヒーター1本なので、スポット的に利用しましょう。
コンパクトなのでデスク下はもちろん、風呂場の脱衣所やトイレの補助暖房としても活用できます。万が一倒しても自動的に電源が切れる転倒OFFスイッチも装備しています。
※各社通販サイトの 2024年12月02日時点 での税込価格
| サイズ | 幅33×奥行16.5×高さ19.5cm |
|---|---|
| 重量 | 1.1kg |
| タイプ | スタンダードタイプ |
| 消費電力 | 400W |
| 電源コード長さ | 約1.5m |
| カラー | ホワイト |
| サイズ | 幅33×奥行16.5×高さ19.5cm |
|---|---|
| 重量 | 1.1kg |
| タイプ | スタンダードタイプ |
| 消費電力 | 400W |
| 電源コード長さ | 約1.5m |
| カラー | ホワイト |
持ち運びラクラク!デスク以外でも広く利用可能
小型の縦型のセラミックファンヒーターは、ハンドル付きで片手で軽々運べるため、いろんな場所に持ち運んで使えるのが魅力。
リモコンが付属するので、デスク下に置いても温風の切り替えなどが手軽にできます。もちろん、本体のタッチパネルで操作することも!
速暖性に優れているため、電源を入れればわずか1秒で温めてくれます。首振り機能もあり、まんべんなく広範囲を温められるのも嬉しいですね。
※各社通販サイトの 2024年12月02日時点 での税込価格
| サイズ | 幅13×奥行13×高さ37cm |
|---|---|
| 重量 | 約1.9kg |
| タイプ | スタンダードタイプ |
| 消費電力 | 5~1200W |
| 電源コード長さ | 1.5m |
| カラー | - |
| サイズ | 幅13×奥行13×高さ37cm |
|---|---|
| 重量 | 約1.9kg |
| タイプ | スタンダードタイプ |
| 消費電力 | 5~1200W |
| 電源コード長さ | 1.5m |
| カラー | - |
デスクヒーターおすすめ5選|マットタイプ
最後は、マット型のデスクヒーターです。こちらもぜひ参考にしてください。
シンプルな仕様で使いやすい!
電源スイッチを兼ねた5段階の温度調整機能を操作するだけというシンプル設計なマットです。サイズは176×88cm(約1畳)なので、広々した机の下に置いて利用しやすいです。
デスク下だけでなく、こたつや布団と併用することもできるサイズ感なので、1つあるといろんな場面で役立つはずです。ダニ退治機能があるのも安心材料のひとつ!
※各社通販サイトの 2024年12月02日時点 での税込価格
| サイズ | 幅176×奥行88cm |
|---|---|
| 重量 | 1.5kg |
| タイプ | マット式 |
| 消費電力 | 200W |
| 電源コード長さ | 約1.5m |
| カラー | グレー |
| サイズ | 幅176×奥行88cm |
|---|---|
| 重量 | 1.5kg |
| タイプ | マット式 |
| 消費電力 | 200W |
| 電源コード長さ | 約1.5m |
| カラー | グレー |
撥水加工を施した水に強いマット!
表面に撥水加工が施されており、飲み物をこぼしてしまったとしてもすぐに拭き取れるタイプのホットカーペットです。デスク用としてだけではなく、キッチンでも使えますよ。
木目調のデザインで、フローリングにも相性がよくなじみやすいでしょう。操作は簡単で、切・弱・強の3段階で調整するだけ。老若男女が使いやすい仕様のホットカーペットに仕上がっています。
※各社通販サイトの 2024年12月02日時点 での税込価格
| サイズ | 幅45×奥行110cm |
|---|---|
| 重量 | 1.35kg |
| タイプ | マット式 |
| 消費電力 | 72W |
| 電源コード長さ | 約1.5m |
| カラー | 木目調ブラウン |
| サイズ | 幅45×奥行110cm |
|---|---|
| 重量 | 1.35kg |
| タイプ | マット式 |
| 消費電力 | 72W |
| 電源コード長さ | 約1.5m |
| カラー | 木目調ブラウン |
コンパクトに収納できる!
5段階で温度を調整できる、簡単操作のホットカーペットです。裏面には滑り止め加工が施されており、ズレてしまうこともありません。
折りたたみやすく、省スペースで収納することができます。もちろんダニ退治機能を搭載しているので、足裏を温めるだけでなく、お子さんが乗っても虫食いにあうこともないでしょう。
※各社通販サイトの 2024年12月02日時点 での税込価格
| サイズ | 幅88cm×長さ175cm |
|---|---|
| 重量 | 1.4kg |
| タイプ | マット式 |
| 消費電力 | 200W |
| 電源コード長さ | - |
| カラー | グレー |
| サイズ | 幅88cm×長さ175cm |
|---|---|
| 重量 | 1.4kg |
| タイプ | マット式 |
| 消費電力 | 200W |
| 電源コード長さ | - |
| カラー | グレー |
腰やお尻もピンポイントで温められる足温器
足先をすっぽり温めることができるフットウォーマー。ベッドに敷いてあんかとして使ったり、イスに置いて腰やお尻をピンポイントで温めたりと、マルチに使える足温器です。
カバーには肌触りのよいマイクロファイバーを使用。ヒーターユニットから外して、洗濯機で洗えるので衛生的に使えますね。
サーモスタットによって自動的に温度を制御。コントローラースイッチが付属しており、41度、39度、36度(標準表面温度)の3段階に温度調節できます。
※各社通販サイトの 2024年12月02日時点 での税込価格
| サイズ | 縦29×横39×厚さ5cm |
|---|---|
| 重量 | 0.6kg |
| タイプ | マット型 |
| 消費電力 | 30W |
| 電源コード長さ | 3m |
| カラー | ブラウン |
| サイズ | 縦29×横39×厚さ5cm |
|---|---|
| 重量 | 0.6kg |
| タイプ | マット型 |
| 消費電力 | 30W |
| 電源コード長さ | 3m |
| カラー | ブラウン |
足元にちょこっと敷ける省エネ電気マット
広電は1996年創業の暖房機器メーカー。電気毛布や電気あんかなどで有名です。そのなかでもこちらはサイズが縦40×横40cmと、足元に置いても邪魔にならないコンパクトな電気マット。椅子の上に置くこともできます。
カバーはポリエステル100%と比較的軽いので、洗濯機で丸洗いすることも!
※各社通販サイトの 2024年12月02日時点 での税込価格
| サイズ | 約40×40cm |
|---|---|
| 重量 | 0.42kg |
| タイプ | マット型 |
| 消費電力 | 27W |
| 電源コード長さ | - |
| カラー | ホワイト |
| サイズ | 約40×40cm |
|---|---|
| 重量 | 0.42kg |
| タイプ | マット型 |
| 消費電力 | 27W |
| 電源コード長さ | - |
| カラー | ホワイト |
おすすめ商品の比較一覧表
| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | サイズ | 重量 | タイプ | 消費電力 | 電源コード長さ | カラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panasonic(パナソニック)『セラミックファンヒーター(DS-FN1200-W)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年1月9日時点 での税込価格 |
コンパクトなのにパワフル温風 | 幅28cm×高さ31.5cm×奥行き13.5cm | 2.5kg | スタンド式 | 温風「強」:1170/1120W(50/60Hz温風「弱」:640/615W(50/60Hz) | 1.8m | ホワイト |
| Panasonic(パナソニック)『デスクヒーター(DC-PKD4)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年12月02日時点 での税込価格 |
デスクの下に立てるだけの薄型ヒーター | 48×45×30cm | 2.2kg | マット型 | 165W | 180cm | グレー |
| LaFuture 筒型パネルヒーター デスクヒーター 熱伝導ブランケット |

|
※各社通販サイトの 2025年1月28日時点 での税込価格 |
軽量コンパクトで設置しやすい | 43×38×52cm | 約1.3kg | パネル型 | 195W | 245cm | ファブリックグレー、ファブリックベージュ、モロッカンロゼ |
| Orthland『デスク用ヒーター』 |

|
※各社通販サイトの 2024年12月02日時点 での税込価格 |
軽量コンパクト・高い安全性 | 40×50cm | 約1.08kg | パネル型 | 124W | 約140cm | グレー |
| YAMAZEN(山善)『フリース付きパネルヒーター(YPP-181HK)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年12月02日時点 での税込価格 |
四方から脚を温める! | 幅50×奥行30×高さ50cm | 1.6kg | パネル式 | 130W | 2m | グレー |
| DOSHISHA(ドウシシャ)『パネルヒーター(PHX-021J)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年12月02日時点 での税込価格 |
薄く軽い赤外線パネルで収納も楽チン! | W50×D23×H53.5cm | 約1.5kg | パネル式 | 220W | 2.0m | ブラウン |
| YAMAZEN(山善)『ミニパネルヒーター(DP-SB1610(W))』 |

|
※各社通販サイトの 2025年1月28日時点 での税込価格 |
コスパが良く、過熱防止機能付きで優れた製品 | 幅40.5×奥行15×高さ32.5cm | 1.7 kg | パネル式 | 160W | 約1.9m | 1色 |
| IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)『デスクヒーター(DEH-45-T)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年12月02日時点 での税込価格 |
デスクの下をコタツにする!? 小型ヒーター | 幅46×奥行35×高さ3cm | 約880g | パネル型 | 90W | 約1.8m | ブラウン |
| SANWA SUPPLY(サンワサプライ)『デスクパネルヒーター(DPH-50)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年12月02日時点 での税込価格 |
便利なマグネット式でオフィスで活躍 | 38×33×4cm | 約1kg | パネル式 | 50W | 約1.8m | 1色 |
| Panasonic(パナソニック)『セラミックファンヒーター(DS-FS1200)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年12月02日時点 での税込価格 |
防滴仕様で水まわりでも安心 | W280×D135×H315㎜ | 2.6kg | スタンド式 | 1170W/1120W(50/60Hz)、640/615W(50/60Hz) | 180cm | ホワイト |
| IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)『セラミックファンヒーター(PCH-M12B)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年12月02日時点 での税込価格 |
大風量でコンパクト! すぐに温まる | 幅約26×奥行約13.5×高さ約37.9cm | 2.5kg | スタンダードタイプ | 1200W | - | ホワイト、ピンク、ブルーほか |
| siroca(シロカ)『ポカCUBE(SH-CF151)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年12月02日時点 での税込価格 |
グッドデザイン賞を受賞したパワフルマシン! | W236×H203×D232 mm | 2.5 kg | スタンド式 | 1200W | 1.8m | ホワイト |
| TOPLAND(トップランド)『コンパクトセラミックヒーター(SC-CH33WT)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年12月02日時点 での税込価格 |
コンパクトながら機能も優秀! | W118×H157×D102 mm | 0.82 kg | スタンド式 | 300W | 約1.5m | ホワイト |
| YAMAZEN(山善)『電気ストーブ(DS-F041)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年12月02日時点 での税込価格 |
レトロな雰囲気で使えるスタンダードタイプ | 幅33×奥行16.5×高さ19.5cm | 1.1kg | スタンダードタイプ | 400W | 約1.5m | ホワイト |
| AUZKIN『セラミックファンヒーター(DH-QN12-1)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年12月02日時点 での税込価格 |
持ち運びラクラク!デスク以外でも広く利用可能 | 幅13×奥行13×高さ37cm | 約1.9kg | スタンダードタイプ | 5~1200W | 1.5m | - |
| IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)『ホットカーペット(IHC-10-H)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年12月02日時点 での税込価格 |
シンプルな仕様で使いやすい! | 幅176×奥行88cm | 1.5kg | マット式 | 200W | 約1.5m | グレー |
| IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)『フローリング調ホットカーペット(HCM-1105FL)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年12月02日時点 での税込価格 |
撥水加工を施した水に強いマット! | 幅45×奥行110cm | 1.35kg | マット式 | 72W | 約1.5m | 木目調ブラウン |
| YAMAZEN(山善)『ホットカーペット(AUB-100)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年12月02日時点 での税込価格 |
コンパクトに収納できる! | 幅88cm×長さ175cm | 1.4kg | マット式 | 200W | - | グレー |
| Panasonic(パナソニック)『足温器(DF-SAC30)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年12月02日時点 での税込価格 |
腰やお尻もピンポイントで温められる足温器 | 縦29×横39×厚さ5cm | 0.6kg | マット型 | 30W | 3m | ブラウン |
| KODEN(広電)『VWM-401PC』 |

|
※各社通販サイトの 2024年12月02日時点 での税込価格 |
足元にちょこっと敷ける省エネ電気マット | 約40×40cm | 0.42kg | マット型 | 27W | - | ホワイト |
【ランキング】通販サイトの最新人気! デスクヒーターの売れ筋をチェック
Amazon、楽天市場でのデスクヒーターの売れ筋ランキングも参考にしてみてください。
※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。
【Q&A】疑問をここで解決!


デスクヒーターもタイプによって消費電力は異なります。安く済ませたいなら、マットヒーターやパネルヒーターがおすすめ。消費電力は100~200Wほどのアイテムがほとんどなので、1時間使用していても5.4円です。(※電気料金の目安とされている1kWh単価27円で計算)
1日8時間使用しても約43.2円なので、リーズナブルに利用できますよ。


本体を倒してしまったり、パンツに熱源が触れると引火するリスクがありますが、基本的にデスクヒーターは遠赤外線や温風でカラダを温める仕組みなので、火事になってしまう心配はほとんどないでしょう。
【まとめ】種類ごとの特徴を見極めて選ぼう
本記事では、デスクヒーターの種類ごとの特徴や選び方、おすすめ商品をご紹介しましたが、いかがでしたか。
寒い季節に自宅やオフィスでの作業や、家事・育児をしていると、足元から冷えてしまうことも。しっかりカラダを温めるためにも、用途に合わせてヒーターを選ぶことが大切です。ぜひ本記事を参考に、自分にぴったりの商品を見つけてくださいね。
おすすめ商品・口コミの投稿はこちら
※メーカーや販売店の方は、ページ下部の「お問い合わせはこちら」から商品情報をお送りください。
ユーザーが選んだイチオシ商品の口コミ情報は、マイナビおすすめナビを閲覧したユーザー、マイナビニュース会員、外部パートナー企業と契約する一般ユーザーからの投稿をもとにしています。
◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。

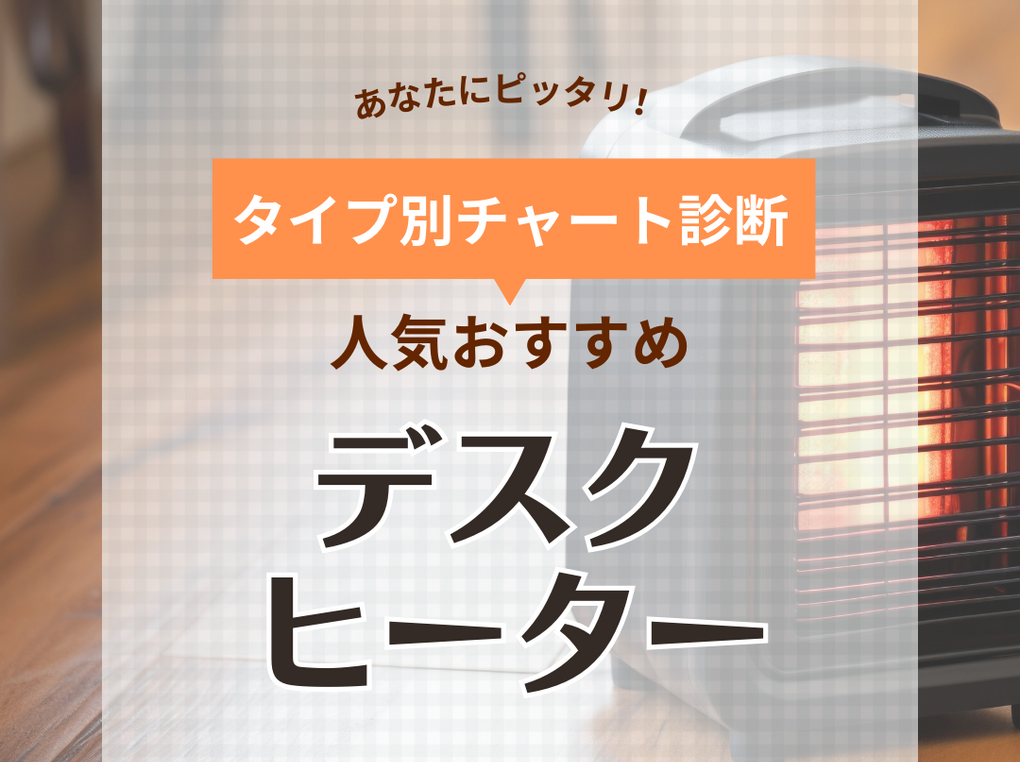
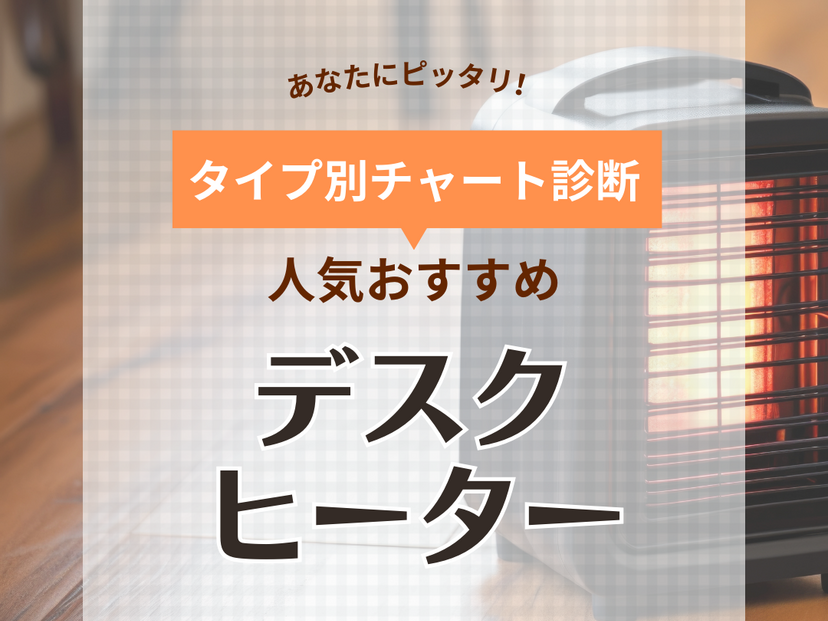



























































































































「家電・AV機器」「ゲーム・ホビー」「スポーツ・自転車」「PC・スマホ・カメラ」カテゴリー担当。休日はドライブ・写真・ペットといったアウトドアなものからゲーム・ホビーなどインドアなものまで多趣味。過去にゲームメディアのライターも経験し、現在はWEBメディアのディレクション業務やメディア制作に携わっている。