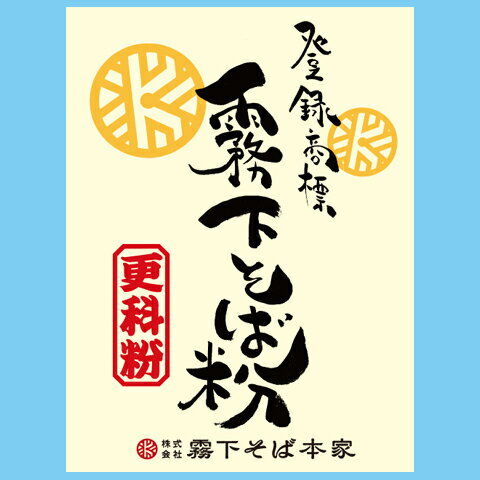| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 内容量 | 産地 | 製法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大西製粉『信州そば粉 金印』 |

|
※各社通販サイトの 2024年12月16日時点 での税込価格 |
初心者でも扱いやすいこまかく粒のそろったそば粉 | 1kg | 長野県 | ロール挽き |
| 霧下そば本家『霧下そば粉(更科粉)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年12月16日時点 での税込価格 |
真っ白でさらりとした上品な更科粉をお探しの方に | 1kg | 北海道、北米(2019年2月現在) | - |
| 吉粋『極上石臼一本挽きそば粉』 |

|
※各社通販サイトの 2024年12月16日時点 での税込価格 |
石臼でていねいに挽いた香り高いそば粉 | 1kg | 北海道 | 石臼挽き |
| 朝日製粉『そばクレープ(ガレット)用のそば粉』 |

|
※各社通販サイトの 2024年12月16日時点 での税込価格 |
ガレットなどさまざまなお菓子、料理に使えるそば粉 | 500g | 国産(時期により変動)、北米産のブレンド | - |
| 匠製粉 『そば粉 石臼挽き北海道産』 |

|
※各社通販サイトの 2024年12月16日時点 での税込価格 |
原料にこだわったそば粉 | 1.25kg | 北海道 | 石臼挽き |
| 松村製粉所『新そば そば打ちセット』 |

|
※各社通販サイトの 2024年12月16日時点 での税込価格 |
簡単にそばが作れるセット! | 1kg | 北海道 | - |
| 森のそば粉屋さん『高級挽きぐるみそば粉 山茶花(さざんか)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年12月16日時点 での税込価格 |
ルチンを多く含んだそば粉 | 1kg | 国産、北米産 | - |
| ダイコー製粉『上州秋そば花一文 石臼挽き』 |

|
※各社通販サイトの 2024年12月16日時点 での税込価格 |
メーカー自信作のそば粉 | 1kg | 群馬県 | 石臼挽き |
| 森のそば粉屋さん『そば粉 常磐』 |

|
※各社通販サイトの 2024年12月16日時点 での税込価格 |
のどごしと食感を楽しみたい方に! | 1kg | 国産、北米産 | - |
そば粉の選び方 そば打ち向きやガレットなどお菓子向きなども!
日本体質改善協会代表でフードアナリストの平林玲美さんに、そば粉を選ぶときのポイントを教えてもらいました。
挽き方で変わるそば粉の食感や味わいに注目! 一番粉、二番粉、三番粉の特徴も解説
そば粉は製法やふるい分けによって味わいや食感が異なるので、好みに合わせて選びましょう。代表的なものは一番粉(内層粉)、二番粉(中層粉)、三番粉(表層粉)の3種類です。
一番粉は、そばの実の中心部のみを挽いた粉のこと。色が白く、端切れや喉越しのよい仕上がりが特長です。
二番粉は、胚乳部(はいにゅうぶ)や胚芽部(はいがぶ)などの外皮まで挽いた粉のこと。そば特有の香りが強く、コシや風味のバランスがよいそばに仕上がります。
さらに色濃く、風味が強いのが三番粉です。外殻に近い部分まで挽くのでタンパク質が多く含まれるだけでなく、より深いそばの味わいが楽しめます。
そば粉の製法による味わいの違いを楽しもう 「石臼挽き」と「ロール挽き」があります
そば粉の製法はおもに「石臼挽き」と「ロール挽き」とに分けられます。
石臼挽きは、手作業や電動で長時間かけてゆっくりと製粉します。そば粉はとても熱に弱いため製粉時に熱が発生すると水分とともに風味が飛んでしまいますが、石臼挽きは熱が出にくく風味豊かなそばの強い香りを楽しめます。
ロール挽きは2つの重なったローラーを内側に引き込むように高速回転させ、ローラーに刻んだ溝でそばの実をつぶすように製粉していきます。メリットは、一番粉から五番粉までの階層による取り出しや、挽き分けができることです。
それぞれ異なるコシや弾力、のどごしを楽しめますので、購入の際には製法にも注目してみてください。
つくるメニューに合わせてそば粉を選ぼう ガレットやだんごにも!
そば粉は、手づくりのそばを楽しむほか、ガレット(クレープ)やそばだんごなどのお菓子や料理にも使用することができます。購入の際には、用途に合わせてそば粉を検討しましょう。
手づくりのそばを楽しみたいときには、優良な産地や製法に加えて新鮮であることも重要なポイントです。そばの香りは日ごとに飛んでしまいますので、新鮮なそば粉を使いきれる量だけ購入するようにしましょう。
また、お菓子や料理に使用する際には、甘皮(そばの実の殻の下の種皮)まで挽き混んだそば粉など加熱しても風味が損なわれにくいものを選ぶのがおすすめ。国産にこだわらず、北米産のそば粉がブレンドされたものを選ぶとコスパも良く気軽に使用できますよ。
そば粉のおすすめ9選 パンケーキやクレープなどのレシピにも大活躍!
うえで紹介したそば粉の選び方のポイントをふまえて、日本体質改善協会代表でフードアナリストの平林玲美さんと編集部で選んだおすすめ商品を厳選してご紹介します。

初心者でも扱いやすいこまかく粒のそろったそば粉
信州産のそば粉をお探しの方におすすめしたいのが、こちらのそば粉です。外皮を少しだけ挽きこんでいるので、香り、味わいともにバランスのよいそばに仕上がります。粒子がこまかく均一なため、そばを打ち慣れていない方でもまとまりやすいのが特徴。
二八そばや十割そばにしていただくのはもちろん、きめこまやかさを生かしてガレットに使用するのもおすすめです。
※各社通販サイトの 2024年12月16日時点 での税込価格
| 内容量 | 1kg |
|---|---|
| 産地 | 長野県 |
| 製法 | ロール挽き |
| 内容量 | 1kg |
|---|---|
| 産地 | 長野県 |
| 製法 | ロール挽き |

真っ白でさらりとした上品な更科粉をお探しの方に
更科そば粉をお探しの方におすすめのそば粉です。粘り気がなくサラッとした粉で、上品な更科の味わいを存分に楽しむことができます。繊細な風味であと味がさっぱりしているので、夏の暑い時期にもおいしくいただけるはず。
そば打ち上級者の方は、柚子(ゆず)や桜など季節に応じた変わりそばのベースとして使用するのもおすすめですよ。
※各社通販サイトの 2024年12月16日時点 での税込価格
| 内容量 | 1kg |
|---|---|
| 産地 | 北海道、北米(2019年2月現在) |
| 製法 | - |
| 内容量 | 1kg |
|---|---|
| 産地 | 北海道、北米(2019年2月現在) |
| 製法 | - |

石臼でていねいに挽いた香り高いそば粉
香り高いそば粉をお探しの方には、こちらがおすすめ。北海道産の玄そばを手作業でていねいにえりすぐり、甘皮まで挽き込んでいるので力強いそばの味わいを楽しむことができます。
極上の石臼一本挽きは粘着力があるので打ちやすく、ご家庭で茹でてもコシが残りやすいのが魅力。そばの香りもしっかりと感じられますので、そばを打ち慣れていない方はもちろん、そば好きの方にぜひ一度お試しいただきたいそば粉です。
※各社通販サイトの 2024年12月16日時点 での税込価格
| 内容量 | 1kg |
|---|---|
| 産地 | 北海道 |
| 製法 | 石臼挽き |
| 内容量 | 1kg |
|---|---|
| 産地 | 北海道 |
| 製法 | 石臼挽き |

ガレットなどさまざまなお菓子、料理に使えるそば粉
お菓子づくり用のそば粉をお探しの方におすすめなのが、こちらのそば粉。甘皮を挽きこんでいるため、加熱してもそばの香りをしっかりと楽しむことができます。お菓子づくり用にブレンドされているので、コスパがいいのも魅力のひとつ。
お好み焼きやおやき、ホットケーキなど、そば菓子以外のお菓子や料理に使用しても、ほんのり香ばしいそばの香りがプラスされてグッとおいしく仕上がりますよ。
※各社通販サイトの 2024年12月16日時点 での税込価格
| 内容量 | 500g |
|---|---|
| 産地 | 国産(時期により変動)、北米産のブレンド |
| 製法 | - |
| 内容量 | 500g |
|---|---|
| 産地 | 国産(時期により変動)、北米産のブレンド |
| 製法 | - |
原料にこだわったそば粉
北海道産の原料にこだわったそば粉です。北海道の玄そばは、冷涼な気候の中、昼夜の寒暖差が大きく、朝には霧が発生して日中の気温上昇も緩やかな気候となっているためおいしいそばができます。そんな原料にこだわったそばを、そばに適した冷蔵保存で保管、石臼でゆっくりと挽き、香りがとても強い美味しいそば粉になっています。
※各社通販サイトの 2024年12月16日時点 での税込価格
| 内容量 | 1.25kg |
|---|---|
| 産地 | 北海道 |
| 製法 | 石臼挽き |
| 内容量 | 1.25kg |
|---|---|
| 産地 | 北海道 |
| 製法 | 石臼挽き |
簡単にそばが作れるセット!
こちらも、北海道産のそばを使ったそば粉となっています。そば粉の他に、打ち粉やつなぎ用の小麦粉などがセットになっているので、この商品さえあれば誰でも簡単に本格的なそばを打つことができてしまいます。そば粉は1kgが2袋なので、少量ずつ使用することが可能です。北海道産の強いそばの香りと味を、ぜひ自分のご家庭で楽しんでみてください。
※各社通販サイトの 2024年12月16日時点 での税込価格
| 内容量 | 1kg |
|---|---|
| 産地 | 北海道 |
| 製法 | - |
| 内容量 | 1kg |
|---|---|
| 産地 | 北海道 |
| 製法 | - |
ルチンを多く含んだそば粉
高級な玄そばを甘皮部分まで引き込んでいるため、とても香りの強いそば粉です。甘皮にはルチンという栄養価が多く含まれているため、健康にも良いですし、そば切りにすると色が濃くなるのが特徴です。そばガレットなどのおかし作りにも使用でき、甘皮のおかげでしっとりとした出来上がりになります。十割そばとして使用するのもおすすめ。
※各社通販サイトの 2024年12月16日時点 での税込価格
| 内容量 | 1kg |
|---|---|
| 産地 | 国産、北米産 |
| 製法 | - |
| 内容量 | 1kg |
|---|---|
| 産地 | 国産、北米産 |
| 製法 | - |
メーカー自信作のそば粉
有名な上州産(群馬県)のそばを使用しているそば粉です。製法は石臼挽きとなっており、甘皮まで引き込んでいるので、とても香りが高くおいしいそば粉となっています。ネットで購入する場合、2回目からは価格も上がり送料もかかってしまうほどの自信作です。初回購入は安いので、まずは試しに購入してみるのもおすすめです。
※各社通販サイトの 2024年12月16日時点 での税込価格
| 内容量 | 1kg |
|---|---|
| 産地 | 群馬県 |
| 製法 | 石臼挽き |
| 内容量 | 1kg |
|---|---|
| 産地 | 群馬県 |
| 製法 | 石臼挽き |
のどごしと食感を楽しみたい方に!
森のそば粉屋さんから販売されている、選りすぐりの極上の玄そばを使用した2番粉(白めの上質な粉)です。そのため、プロのそば屋さんにも好評をもらうほど、色、風味、のどごし全てにおいて、評価が高い商品です。シャキッとした歯ごたえと、のどごしを楽しみたい方におすすめです。打つのが少し難しいので、何度かそば打ち経験がある方におすすめです。
※各社通販サイトの 2024年12月16日時点 での税込価格
| 内容量 | 1kg |
|---|---|
| 産地 | 国産、北米産 |
| 製法 | - |
| 内容量 | 1kg |
|---|---|
| 産地 | 国産、北米産 |
| 製法 | - |
「そば粉」のおすすめ商品の比較一覧表
| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 内容量 | 産地 | 製法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大西製粉『信州そば粉 金印』 |

|
※各社通販サイトの 2024年12月16日時点 での税込価格 |
初心者でも扱いやすいこまかく粒のそろったそば粉 | 1kg | 長野県 | ロール挽き |
| 霧下そば本家『霧下そば粉(更科粉)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年12月16日時点 での税込価格 |
真っ白でさらりとした上品な更科粉をお探しの方に | 1kg | 北海道、北米(2019年2月現在) | - |
| 吉粋『極上石臼一本挽きそば粉』 |

|
※各社通販サイトの 2024年12月16日時点 での税込価格 |
石臼でていねいに挽いた香り高いそば粉 | 1kg | 北海道 | 石臼挽き |
| 朝日製粉『そばクレープ(ガレット)用のそば粉』 |

|
※各社通販サイトの 2024年12月16日時点 での税込価格 |
ガレットなどさまざまなお菓子、料理に使えるそば粉 | 500g | 国産(時期により変動)、北米産のブレンド | - |
| 匠製粉 『そば粉 石臼挽き北海道産』 |

|
※各社通販サイトの 2024年12月16日時点 での税込価格 |
原料にこだわったそば粉 | 1.25kg | 北海道 | 石臼挽き |
| 松村製粉所『新そば そば打ちセット』 |

|
※各社通販サイトの 2024年12月16日時点 での税込価格 |
簡単にそばが作れるセット! | 1kg | 北海道 | - |
| 森のそば粉屋さん『高級挽きぐるみそば粉 山茶花(さざんか)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年12月16日時点 での税込価格 |
ルチンを多く含んだそば粉 | 1kg | 国産、北米産 | - |
| ダイコー製粉『上州秋そば花一文 石臼挽き』 |

|
※各社通販サイトの 2024年12月16日時点 での税込価格 |
メーカー自信作のそば粉 | 1kg | 群馬県 | 石臼挽き |
| 森のそば粉屋さん『そば粉 常磐』 |

|
※各社通販サイトの 2024年12月16日時点 での税込価格 |
のどごしと食感を楽しみたい方に! | 1kg | 国産、北米産 | - |
通販サイトの最新人気ランキングを参考にする そば粉の売れ筋をチェック
Amazon、楽天市場でのそば粉の売れ筋ランキングも参考にしてみてください。
※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。
そのほかのそばに関連する記事はこちら 【関連記事】
そば粉選びは使用目的と鮮度に気をつけて! フードアナリストからアドバイス
通販で買う際は鮮度に気をつけて!
優良なそば粉は、ほとんどが国内の寒冷地で生産されています。なかでも、北海道産や信州(長野県)産のそば粉は質が高くおすすめです。そば粉は産地だけではなく、種類や製法などによって風味や味わいはさまざま。購入の際は好みに合わせ、最適なそば粉を選ぶようにしましょう。
そばを打ち、手づくりのそばを楽しむ場合には、新鮮さも重要なポイントです。新しいものを選ぶことはもちろん、使用用途や頻度に合わせて使いきれる量を購入することも忘れないでくださいね。
◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。