栗焼酎とはどんなお酒?

Photo by Hansjörg Keller on Unsplash

Photo by Hansjörg Keller on Unsplash
栗焼酎の歴史は、1970年代後半ごろからといわれています。愛媛県の蔵元である媛囃子(ひめばやし)でつくられたのが最初とされ、その後も高知県や徳島県など、栗の名産地である四国を中心につくられ広まりました。近年ではさまざまな栗の産地でつくられるようになってきています。
栗焼酎の特徴は、飲んだ直後に香り立つ栗の甘い香りとまろやかな飲み口です。自然な甘さを含むことで、ほかの焼酎との違いがきわだっています。アルコール度数も25〜35度の間くらいで、芋焼酎や麦焼酎に比べて飲みやすく、焼酎初心者の方にも挑戦しやすい味が魅力です。
栗焼酎おすすめ8選
ここからは、栗焼酎のおすすめ商品をご紹介します。栗の甘みは産地や使用率によって違いがあります。甘みの強い栗焼酎なのか、初心者でも飲みやすいタイプの栗焼酎なのか、イメージできると選びやすくなるでしょう。
栗の名産地、笠間の栗が生む上品ですっきりした味
茨城県笠間市の特産品である栗を、地元有志と老舗の酒蔵が手を組んでつくりあげた栗焼酎。栗を贅沢に使用し、やわらかな口あたりと芳醇な栗の香り、ほのかな甘さを感じられます。
殺虫処理をほどこさず、鬼皮だけをむいた栗を使っています。あえて渋皮を残しているため、あとに残らないすっきりとした甘さが特徴。甘いお酒は苦手だけど栗焼酎を試してみたい、という方にぴったりの味です。
※各社通販サイトの 2024年12月02日時点 での税込価格
| タイプ | 乙類焼酎 |
|---|---|
| 蒸留方式 | 単式 |
| 栗使用比率 | 75% |
| アルコール度 | 25度 |
| 産地 | 茨城県 |
| タイプ | 乙類焼酎 |
|---|---|
| 蒸留方式 | 単式 |
| 栗使用比率 | 75% |
| アルコール度 | 25度 |
| 産地 | 茨城県 |
四万十時間も長期熟成された希少な古酒
プレミア感あふれる、特別限定の古酒。希少性が高く、秘蔵というべき栗焼酎の古酒「四万十川特産栗焼酎原酒」です。高知県でも有数の栗の産地である四万十川上流域の栗を使用したダバダ火振の上級品で、酒蔵の地下のトンネル貯蔵庫で四万十時間(約4年7カ月)もの間、熟成された長期貯蔵酒です。
長期熟成によって、旨味とコクがいっそう引き出された贅沢な味わいが堪能できるでしょう。栗焼酎ファンのみならず、焼酎ファンなら一度は味わっておきたい銘品です。
※各社通販サイトの 2024年12月02日時点 での税込価格
| タイプ | 乙類焼酎 |
|---|---|
| 蒸留方式 | - |
| 栗使用比率 | 50% |
| アルコール度 | 33度 |
| 産地 | 高知県 |
| タイプ | 乙類焼酎 |
|---|---|
| 蒸留方式 | - |
| 栗使用比率 | 50% |
| アルコール度 | 33度 |
| 産地 | 高知県 |
あの「半沢直樹」も愛飲! 栗焼酎の代名詞
もともとは高知県の四万十川上流域で古くから酒づくりをしていた無手無冠に、地元で採れた規格外サイズの栗を有効活用できないか、というところから生まれた「ダバダ火振」。今や郷土産品として希少な栗焼酎となりました。
その魅力は地元の栗を50%使用することで醸し出された豊かな香りと、ソフトな甘み。スイーツにも活用され、地域を盛り上げる銘品です。実は小説「半沢直樹」の作中でこのダバダ火振が登場し、ファンのあいだで話題になっています。
※各社通販サイトの 2024年12月02日時点 での税込価格
| タイプ | 乙類焼酎 |
|---|---|
| 蒸留方式 | 常圧蒸留 |
| 栗使用比率 | 50% |
| アルコール度 | 25度 |
| 産地 | 高知県 |
| タイプ | 乙類焼酎 |
|---|---|
| 蒸留方式 | 常圧蒸留 |
| 栗使用比率 | 50% |
| アルコール度 | 25度 |
| 産地 | 高知県 |
丹波の栗を使用したまろやかな焼酎
栗の名産地として知られる兵庫県丹波市。その地で採れた栗を丁寧に蒸し、香ばしさと甘みを引き出した栗焼酎が「古丹波」です。超軟水と清酒用の麹や酵母を使用し、まろやかな味わいに仕上げられています。
さらに、香りやおいしさを長持ちさせるためのひと手間として、低温ろ過製法を用いて造られています。口に含むと、栗の香ばしさやほのかな甘みがふわっと抜けていくのを楽しめます。ロック、ストレート、お湯割りなど、お好みでどうぞ。
※各社通販サイトの 2024年12月02日時点 での税込価格
| タイプ | 本格焼酎 |
|---|---|
| 蒸留方式 | - |
| 栗使用比率 | - |
| アルコール度 | 25度 |
| 産地 | 兵庫県 |
| タイプ | 本格焼酎 |
|---|---|
| 蒸留方式 | - |
| 栗使用比率 | - |
| アルコール度 | 25度 |
| 産地 | 兵庫県 |
長期貯蔵で引き出された愛媛栗のうま味と香りを満喫
愛媛県産の栗を使用した、長期貯蔵の栗焼酎。常圧蒸留と減圧蒸留を組みあわせてつくられた原酒を、長期間にわたって貯蔵しました。栗本来の香りや旨味が、余すところなく表現された焼酎に仕上げられています。
やさしい口あたりに、栗の風味が豊かに感じられるまろやかな味わいが特徴的。まずはストレートかロックで飲んで、その風味を堪能するのがおすすめです。
※各社通販サイトの 2024年12月02日時点 での税込価格
| タイプ | 本格焼酎 |
|---|---|
| 蒸留方式 | 常圧、減圧混和 |
| 栗使用比率 | - |
| アルコール度 | 25度 |
| 産地 | 愛媛県 |
| タイプ | 本格焼酎 |
|---|---|
| 蒸留方式 | 常圧、減圧混和 |
| 栗使用比率 | - |
| アルコール度 | 25度 |
| 産地 | 愛媛県 |
南国宮崎の生栗の旨味がたっぷりつまった味わい
宮崎県延岡市の特産生栗が生む、上品な香りとほんのりした甘さが特徴の栗焼酎です。延岡の清流が育てた栗が醸し出す旨味をしっかりと活かすべく、ひとつひとつ丹念につくられています。
生栗の上品な香りとやさしい口あたり、やわらかい味わいが特徴的。レトロなタッチのラベルも愛らしく、プレゼントとしても喜ばれるでしょう。
※各社通販サイトの 2024年12月02日時点 での税込価格
| タイプ | 本格焼酎 |
|---|---|
| 蒸留方式 | - |
| 栗使用比率 | - |
| アルコール度 | 25度 |
| 産地 | 宮崎県 |
| タイプ | 本格焼酎 |
|---|---|
| 蒸留方式 | - |
| 栗使用比率 | - |
| アルコール度 | 25度 |
| 産地 | 宮崎県 |
熊本の栗をふんだんに使ったまろやかな焼酎
生産量全国2位を誇る熊本県産の栗を、惜しみなく使った本格栗焼酎です。口に含むと広がる甘くとろけるような風味が特徴的。アルコール度数も25度で、焼酎初心者も比較的飲みやすい味わいといえるでしょう。
飲み込んだあとにも、香り高い栗のフレーバーがまろやかな余韻となって口のなかに残ります。優雅な趣きが感じられる一本です。
※Yahooは12本セットです
※各社通販サイトの 2024年12月02日時点 での税込価格
| タイプ | - |
|---|---|
| 蒸留方式 | - |
| 栗使用比率 | - |
| アルコール度 | 25度 |
| 産地 | 熊本県 |
| タイプ | - |
|---|---|
| 蒸留方式 | - |
| 栗使用比率 | - |
| アルコール度 | 25度 |
| 産地 | 熊本県 |
ストレートで! 鮮明なる笠間栗の香りと甘み
先にご紹介した十三天狗の伝説のプレミアム「原酒」です。栗の優雅な香りと上品な甘さが味わえる、おだやかでやわらかな飲み口の銘品です。水などを一切混入していない原酒は、質のいい栗の香りと甘みをより鮮明に感じられます。
化粧箱入りで、ボトルのデザインや手提げ用の袋もおしゃれ。お酒好きな方へのプレゼントとしても喜ばれる一本。
※各社通販サイトの 2024年12月02日時点 での税込価格
| タイプ | 乙類焼酎 |
|---|---|
| 蒸留方式 | - |
| 栗使用比率 | - |
| アルコール度 | 35度 |
| 産地 | 茨城県 |
| タイプ | 乙類焼酎 |
|---|---|
| 蒸留方式 | - |
| 栗使用比率 | - |
| アルコール度 | 35度 |
| 産地 | 茨城県 |
おすすめ商品の比較一覧表
| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | タイプ | 蒸留方式 | 栗使用比率 | アルコール度 | 産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| うまい栗焼酎を作る研究会『笠間の栗焼酎 十三天狗の伝説』 |
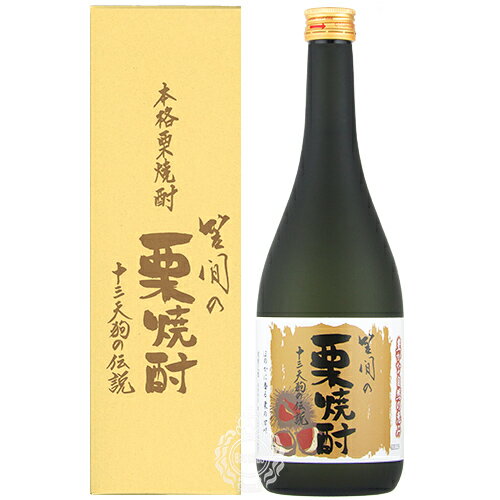
|
※各社通販サイトの 2024年12月02日時点 での税込価格 |
栗の名産地、笠間の栗が生む上品ですっきりした味 | 乙類焼酎 | 単式 | 75% | 25度 | 茨城県 |
| 無手無冠『栗焼酎原酒 四万十ミステリアスリザーブ ボトル』 |

|
※各社通販サイトの 2024年12月02日時点 での税込価格 |
四万十時間も長期熟成された希少な古酒 | 乙類焼酎 | - | 50% | 33度 | 高知県 |
| 無手無冠『栗焼酎 ダバダ火振 普及びん』 |

|
※各社通販サイトの 2024年12月02日時点 での税込価格 |
あの「半沢直樹」も愛飲! 栗焼酎の代名詞 | 乙類焼酎 | 常圧蒸留 | 50% | 25度 | 高知県 |
| つづみや『小鼓 栗の本格焼酎 古丹波』 |

|
※各社通販サイトの 2024年12月02日時点 での税込価格 |
丹波の栗を使用したまろやかな焼酎 | 本格焼酎 | - | - | 25度 | 兵庫県 |
| 媛囃子『奥伊予 長期熟成』 |
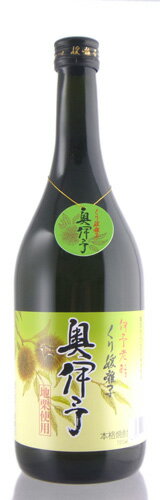
|
※各社通販サイトの 2024年12月02日時点 での税込価格 |
長期貯蔵で引き出された愛媛栗のうま味と香りを満喫 | 本格焼酎 | 常圧、減圧混和 | - | 25度 | 愛媛県 |
| 佐藤焼酎製造場『本格くり焼酎 三代の松』 |

|
※各社通販サイトの 2024年12月02日時点 での税込価格 |
南国宮崎の生栗の旨味がたっぷりつまった味わい | 本格焼酎 | - | - | 25度 | 宮崎県 |
| 山都酒造『肥後の里山』 |

|
※各社通販サイトの 2024年12月02日時点 での税込価格 |
熊本の栗をふんだんに使ったまろやかな焼酎 | - | - | - | 25度 | 熊本県 |
| うまい栗焼酎を作る研究会『笠間の栗焼酎・十三天狗の伝説 Premium原酒』 |

|
※各社通販サイトの 2024年12月02日時点 での税込価格 |
ストレートで! 鮮明なる笠間栗の香りと甘み | 乙類焼酎 | - | - | 35度 | 茨城県 |
通販サイトの最新人気ランキングを参考にする 栗焼酎の売れ筋をチェック
楽天市場での栗焼酎の売れ筋ランキングも参考にしてみてください。
※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。
栗焼酎の選び方
基本情報があまり知られていない蒸留酒である栗焼酎の選び方のポイントは、製法や原料である栗の産地などが挙げられます。それぞれ少しだけ掘り下げて見ていきましょう。
蒸留方式に着目してみよう
焼酎の蒸留の仕方は大きくわけて、乙類と呼ばれる「単式蒸留」と甲類と呼ばれる「連続式蒸留」の2通りです。さらに、「単式蒸留」には「常圧蒸留」と「減圧蒸留」の2通りの蒸留方法があります。
一般的に栗焼酎は「単式蒸留」でつくられているので、ここでは「単式蒸留」の特徴と、「常圧蒸留」「減圧蒸留」の違いについてご紹介しましょう。
「単式蒸留」で本格焼酎の味わいを知る
単式蒸留機を用いて一度だけ蒸留して焼酎をつくる製法を「単式蒸留」と呼びます。
一方、連続式蒸留機を用いて連続的に蒸留操作をおこなう「連続式蒸留」は純度の高いアルコールを抽出する製法。クセのない味わいの焼酎を生み出すことができますが、原料の風味や香りは失われてしまいます。
その点、「単式蒸留」でつくられる焼酎の場合、香味成分なども抽出されているため、原料本来の香りや味わいが現れます。なお、「単式蒸留」でつくられた焼酎のなかでも、酒税法に指定された原料を使ったものだけが「本格焼酎」と名乗ることができます。ほとんどの栗焼酎は「単式蒸留」でつくられており、「本格焼酎」に該当します。
「常圧蒸留」で栗の風味をたのしむ
常圧蒸留はもっともスタンダードな蒸留方法といわれており、その起源ははるか昔のメソポタミア文明まで遡るとされています。蒸留する液体やもろみに熱を加え、その蒸気を集める方法です。
常圧蒸留の場合、高温で熱することから、原料の成分を多く抽出できます。そのため、常圧蒸留でつくられた栗焼酎は、栗本来の風味をしっかり味わうことができます。
「減圧蒸留」ですっきりとした飲み口に
減圧蒸留は蒸留釜の内部の気圧を下げることで蒸留する方法です。気圧が下がると沸点も低くなるため、減圧蒸留では低い温度で蒸留することができます。低温で蒸留することで、雑味のもととなる成分の抽出も抑えられ、クセがなく口あたりのいい味に仕上がるのです。
減圧蒸留でつくった栗焼酎は、栗本来の風味を残しつつもすっきりとした飲み口に仕上がっています。
栗の産地と使用比率もチェック
栗焼酎は多くの場合、栗の産地でつくられています。「媛囃子」がある愛媛県の城川の栗や茨城県笠間の栗、高知県・四万十の栗などを使用した焼酎がよく知られています。
また、栗の使用率も重要なチェックポイント。基本的には50〜85%くらいまでといわれており、使用率が高いほど甘みが増します。栗本来の味をたのしみたい方や、甘みの強い焼酎が好きな方には、栗の使用率が高めの栗焼酎がいいでしょう。
贈答用ならパッケージも選ぶ要素
栗焼酎は一般的には珍しいお酒なので、贈答用にも向いています。ギフトの場合は味も大事ですが、ボトルや箱も、シャレたものや雰囲気のあるものを選びたいですね。
製造元によって高級感がある木箱やユニークなデザインのボトルに入っていますので、選ぶのもたのしいですよ。
エキスパートのアドバイス
産地や製法に着目!
全国の栗の名産地を中心につくられている栗焼酎。芋焼酎や麦焼酎ほどメジャーではありませんが、ほくほくとした栗の風味が感じられることから、近年じわじわと人気が高まっています。産地や製法、味わいなどに着目して、ぜひあなたにピッタリの一本をみつけてくださいね。
栗焼酎のおいしい飲み方


ストレート・ロック
栗焼酎本来の甘みや香りを味わうなら、ストレートかロックで飲むのがいいでしょう。口に含むと、鼻から栗の香りがふわっと抜けていきます。アルコール度数が高くなるので、お酒に強い方におすすめです。
水割り・お湯割り
お酒に強くない方は、水割りでも香りを充分たのしむことができます。配分は、栗焼酎2:水3程度がおすすめ。甘みをしっかりと感じたいなら、氷はなるべく入れずに飲んでみてください。また、お湯割りであれば、香りや風味が引き立つのでより強く感じられるでしょう。
ソーダ割り
スッキリ軽めに飲みたい方はソーダ割がおすすめ。レモンやライムなど、柑橘系のフルーツを加えてアクセントをつけるのもいいですね。焼酎のクセが少し苦手という方も飲みやすいですよ。
【関連記事】そのほかの焼酎はこちら! グラスもあります
まとめ
この記事では栗焼酎のおすすめ8商品をご紹介しました。
全国にある栗の名産地がそれぞれ自信をもって打ち出しているので、まずは産地に注目しながら選んでみるのがおすすめです。また、蒸留方法や栗の使用率などによっても、焼酎の個性ががらりと変わってくるので、慣れてきたらそのような点にも注目してみましょう。
飲み比べるのもたのしいので、ぜひ、さまざまな栗焼酎を味わってみてはいかがでしょうか。
◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。
















