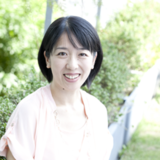| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 茶葉の種類 | 原産国 | 抽出タイプ | 内容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 シーアンドエー 彩香『烏龍茶 凍頂烏龍茶』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月4日時点 での税込価格 |
今までのイメージを覆す革命的な烏龍茶! | 青茶 | 台湾 | ティーバッグ | 茶葉50g、ティーバッグ18包 |
| 2位 marumero(マルメロ)『中国茶 西湖龍井茶(緑茶)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月4日時点 での税込価格 |
香ばしい香りとうまみと甘さで愛好家が多い龍井茶 | 緑茶 | 中国 | 茶葉 | 250g、50g |
| 3位 RIMTAE(リムテー)『工芸茶詰め合わせ10種セット』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月4日時点 での税込価格 |
贈ると喜ばれる花茶詰め合わせセット | 花茶(工芸茶) | 中国 | 茶葉 | 萬紫千紅・金花彩彩・茉莉仙子・花開吉祥・一見鐘情・東方美人・百合花籠・花開富貴・萬寿富貴・心心相印 各1個 |
| 4位 久順茶業『鉄観音茶 』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月4日時点 での税込価格 |
日本でも人気の芳醇な香りと濃厚な味がする烏龍茶 | 青茶 | 台湾 | ティーバッグ | 500g(5g×100包) |
| 5位 久順銘茶『プーアル茶』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月4日時点 での税込価格 |
作り置きでき1年中おいしく飲めるプーアル茶 | 黒茶 | 中国 | ティーバッグ | (2g×10包)×3袋 |
| 7位 苦丁茶(一葉茶)専門店『特選台湾高山茶 阿里山金萱』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月4日時点 での税込価格 |
バニラを思わせる甘い香りと滑らかな味わいの青茶 | 青茶 | 台湾 | 茶葉 | 50g(2023年3月現在、期間限定で100gに増量中) |
| 8位 ルピシア(LUPICIA)『白桃烏龍 極品』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月4日時点 での税込価格 |
ほのかに甘い烏龍茶に白桃の香りが加わり大人気! | 花茶 | 台湾 | 茶葉 | 50g |
| 9位 台湾茶工房『特級 四季春茶』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月4日時点 での税込価格 |
甘みと香りのバランスがよい人気のお茶 | 青茶 | 台湾 | 茶葉 | 200g |
| 10位 シーアンドエー 彩香『黄茶 君山銀針』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月4日時点 での税込価格 |
黄茶の王様ともいわれる君山銀針 | 黄茶 | 中国 | 茶葉 | 20g |
中国茶とは?
「中国茶」とは、中国で作られるお茶の総称。中国には数百種類のお茶が存在すると言われていますが、発酵度により緑茶、白茶、黄茶、青茶、紅茶、黒茶の6種類に分類されます。
日本でもメジャーな烏龍茶(ウーロン茶)は「青茶」、普洱茶(プーアール茶)は「黒茶」に分類されます。
中国茶の選び方ポイント
先ほどもお伝えしました「中国茶」とひと口に言っても、実はたくさんの種類があります。ふだん飲んでいるお茶とは違うものにチャレンジしようと思っても、どれがいいのか迷ってしまうでしょう。
そこで、管理栄養士で料理ライターの山田由紀子さんのアドバイスを基に、中国茶の選び方のポイントをまとめました。
ポイントは下記。
【1】種類(分類)から選ぶ
【2】等級の高さで選ぶ
【3】ティーバッグタイプを選ぶ
自分に合う中国茶を選ぶためのヒントにしてください。
【1】種類(分類)から選ぶ
先述しましたが、中国茶は茶葉の発酵の種類と度合によって、6種類に分類できます。
発酵度合の低い順に緑茶、白茶、黄茶、青茶、紅茶、そして微生物による後発酵を施した黒茶となります。それぞれの種類で味や香りに特徴があるので、自分に合った中国茶を選ぶときの参考にしてください。
香りを楽しめる「緑茶」
日本でも中国でも多くの方に飲まれている「緑茶」。しかし、日本茶と中国茶では製造方法が異なるので、当然ながら風味も異なります。
日本の一般的な緑茶は蒸すことで味をしっかりと引き出し、中国の緑茶は炒ることで香りを引き出しています。味よりも香りを楽しみたい方は、中国の緑茶が合うかもしれません。緑茶は中国でも生産量が多く、価格も低く手に入りやすいため、気軽に飲めるでしょう。
【代表的な緑茶】
龍井茶(ろんじんちゃ)、碧螺春(ぴろちゅん)、緑牡丹(りょくぼたん)、黄山毛峰(こうざんもうほう)
花の香りと甘い味わいが特徴の「白茶」
「白茶(しろちゃ)」は日本ではあまり知られていませんが、中国では古くから飲まれていて、お茶の起源を感じながら飲むことができるでしょう。緑茶に近い味わいで、花の香りとわずかな甘みが特徴です。
茶葉が白っぽく見える理由は、茶葉を揉まずに長期間風通しのよい暗所で乾燥させるため産毛が残っているからです。シンプルな製造過程のため、品質には材料と技術が大きく影響するといわれているので、いろいろな産地やメーカーの白茶を飲み比べるのもよいでしょう。
【代表的な白茶】
銀針白毫(ぎんしんはくごう)、白牡丹(ぱいむーたん)
さわやかで深い味わいと香りの「黄茶」
「黄茶」は製造に手間がかかるため生産量が少なく、希少価値が高いお茶です。
緑茶をわずかに発酵させた黄色い茶葉で、味も香りも緑茶に近いですが、緑茶よりもさわやかで深い味わいと強い香りが特徴としてあげられます。高価なお茶のため、飲む前に香りをゆっくり楽しみ、十分に味わって飲みましょう。
【代表的な黄茶】
君山銀針(くんざんぎんしん)
烏龍茶の別名でもある「青茶」
中国茶選びで悩んでいる方は、日本では烏龍茶として知られている「青茶」をチェックしてみましょう。緑茶よりもさわやかで深い味わいと強い香りが特徴。紅茶のように少し甘さがあるものや、緑茶のようにさわやかな渋みがあるものなどさまざまです。
いろいろな種類の青茶を飲んでみたら、今まで持っていた烏龍茶のイメージが変わるかもしれません。青茶はお茶の色ではなく、茶葉が発酵の過程で青みがかって見えることから、呼ばれるようになったといわれています。
【代表的な青茶】
凍頂烏龍(とうちょううーろん)、鉄観音(てつかんのん)、武夷岩茶(ぶいがんちゃ)、黄金桂(おうごんけい)、水仙(すいせん)、色種(しきしゅ)
中国の「紅茶」は甘みが強いのが特徴
中国の「紅茶」は、インド産やスリランカ産の紅茶よりも渋みが弱く甘みが強いため、ふだん紅茶を飲むときにお砂糖を入れている人でも入れなくてよいと感じるかもしれません。
甘みが強いので濃い目に入れてもストレートで飲みやすいため、中国紅茶は世界中に愛好家がいるほど人気があります。スリランカのウバ、インドのダージリンとともに世界三大紅茶と呼ばれている祁門紅茶(きーまんこうちゃ)が有名です。
【代表的な紅茶】
祁門紅茶(きーまんこうちゃ)、正山小種(らぷさんすーちょん)
プーアル茶の別名でもある「黒茶」
「黒茶」はクセが強いため好みが分かれますが、その独特な味わいのためにほかのお茶では満足できなくなるほど好きな人もいるでしょう。日本でも飲まれているプーアル茶は黒茶のひとつですが、飲みやすいように加工されているため、中国の黒茶とは少し違います。
「黒茶」は、熟茶と生茶に分類されます。熟茶は、麹菌で発酵を早めるために、独特な香りが、生茶は、茶葉の酵素で発酵させた茶葉のため、熟茶よりも香りが弱く飲みやすいお茶です。
黒茶は長期間保存可能で、年代物の黒茶は高額で取り引きされています。
【代表的な黒茶】
普洱茶(ぷーあーるちゃ)、六堡茶(ろっぽちゃ)
緑茶に花の香りをつけた「花茶」
中国茶の分類は上記の6種類ですが、中国ではそこに「花茶」を加えて七大茶と呼んでいます。
「花茶」は、緑茶などに花の香りをつけたもので、香りを楽しみたい人にぴったりなお茶です。花茶でよく知られているのが茉莉花茶(ジャスミン茶)で、日本でも多くの人に飲まれています。
花茶のなかにはお湯を注ぐと花が開くように茶葉を加工した「工芸茶」というものも。お茶を飲んだあと花を水のなかに入れ替えればしばらく楽しめるため、贈りものとして贈ると喜ばれるでしょう。
【代表的な花茶】
茉莉花茶(じゃすみんちゃ)、桂花茶(けいかちゃ)、米蘭茶(まいらんちゃ)
【2】等級の高さで選ぶ
中国茶には品質を表す等級があります。等級は「特級」>「1級」>「2級」>「3級」となっていて、茶葉の大きさや香りや味などを基準に判断されます。
お茶の種類ごとに基準が異なっていて、製造元が勝手に等級を決めることはできません。等級が高いほど品質が高いということになります。
ちなみに「極上」といったグレードは中国茶には存在しません。これは日本の販売者などが後から記載したものである場合が多いので、等級で選ぶ際はご注意ください。
【3】ティーバッグタイプを選ぶ
日本では急須を使ってお茶を入れるのが一般的ですが、中国茶は湯飲みに茶葉を直接入れてお湯を注ぎ、茶葉が沈むのを待って上澄みを飲むのが一般的です。そのため、茶葉でもティーバッグでも、お茶を入れる手間は大差ありません。
茶葉かティーバッグのどちらを選ぶかの基準は、香りを楽しみたい方は茶葉、後片付けがらくでどこでも気軽に飲みたい方はティーバッグを選択するとよいでしょう。
中国茶のおすすめランキング9選
ここからは、中国茶のおすすめをランキング形式でご紹介! お気に入りを見つけて、飲み比べて楽しんでくださいね。
黄金色のお茶の色、甘みのある味、鼻から抜ける花のような香りと、烏龍茶の魅力を一度に体験できます。
今までのイメージを覆す革命的な烏龍茶!
凍頂烏龍茶(とうちょううーろんちゃ)は、黄金色で優しい花の香りがする烏龍茶。渋みが少なく、わずかに甘みを感じられるのが特徴です。烏龍茶を茶色く少し苦いものと考えていた方は、びっくりすることでしょう。
ティーバッグ1包で3杯ほど飲むことができます。手軽に飲めて後片付けもらくなティーバッグタイプの凍頂烏龍茶18包入り。ティーバッグを職場や外出先に持って行き、簡単に楽しめます。
※各社通販サイトの 2025年3月4日時点 での税込価格
| 茶葉の種類 | 青茶 |
|---|---|
| 原産国 | 台湾 |
| 抽出タイプ | ティーバッグ |
| 内容量 | 茶葉50g、ティーバッグ18包 |
| 茶葉の種類 | 青茶 |
|---|---|
| 原産国 | 台湾 |
| 抽出タイプ | ティーバッグ |
| 内容量 | 茶葉50g、ティーバッグ18包 |
2位の『中国茶【西湖龍井茶(緑茶)100g】』は、香ばしい香りとうまみ、甘さが特徴の高級緑茶。食事中に飲むワンランク上のお茶を求める方に。
香ばしい香りとうまみと甘さで愛好家が多い龍井茶
中国を代表する緑茶(龍井茶)は、熟練した職人によって作られる高級緑茶。香ばしい香りとうまみと甘さで愛好家が多い人気のお茶です。
昔から龍井茶(ろんじんちゃ)は、近年の研究ではアミノ酸やビタミンCなどの成分が多く含まれていることもわかりました。少し疲れているとき、リラックスして龍井茶の豊かな香りを楽しみ、ゆったりとした時間を過ごしてください。
※Amazon・楽天市場は250g、Yahoo!ショッピングは50gの価格です。
※各社通販サイトの 2025年3月4日時点 での税込価格
| 茶葉の種類 | 緑茶 |
|---|---|
| 原産国 | 中国 |
| 抽出タイプ | 茶葉 |
| 内容量 | 250g、50g |
| 茶葉の種類 | 緑茶 |
|---|---|
| 原産国 | 中国 |
| 抽出タイプ | 茶葉 |
| 内容量 | 250g、50g |
3位の『工芸茶詰め合わせ10種セット』は、母の日や誕生日など女性への贈り物におすすめ。お湯を注ぎ花が開く瞬間、誰もがときめき、笑顔になるでしょう。
贈ると喜ばれる花茶詰め合わせセット
一瞬で華やかな空間を演出する花茶の詰め合わせセットは、贈りものにぴったりです。お湯を注ぐと花が開く美しさは、見ているだけで楽しめます。いつでも新鮮なお茶を味わるように、ひとつずつパッケージに包まれています。
すっきりした味わいのジャスミン茶は、ティータイムを華やかに彩ってくれるでしょう。頂きもののお返しや、ギフトに悩んでいる方はいかがでしょうか。
※各社通販サイトの 2025年3月4日時点 での税込価格
| 茶葉の種類 | 花茶(工芸茶) |
|---|---|
| 原産国 | 中国 |
| 抽出タイプ | 茶葉 |
| 内容量 | 萬紫千紅・金花彩彩・茉莉仙子・花開吉祥・一見鐘情・東方美人・百合花籠・花開富貴・萬寿富貴・心心相印 各1個 |
| 茶葉の種類 | 花茶(工芸茶) |
|---|---|
| 原産国 | 中国 |
| 抽出タイプ | 茶葉 |
| 内容量 | 萬紫千紅・金花彩彩・茉莉仙子・花開吉祥・一見鐘情・東方美人・百合花籠・花開富貴・萬寿富貴・心心相印 各1個 |
日本でも人気の芳醇な香りと濃厚な味がする烏龍茶
鉄観音茶(てっかんのんちゃ)は日本でも人気が高い烏龍茶です。深みのある芳醇な香りと濃厚な味わいが特徴です。烏龍茶が1包で1リットル入れることができます。
こちらの商品には100包入っているため、非常にリーズナブルです。お湯だけではなく、水出しもできるため、1年通して楽しめます。烏龍茶が好きな方は、ぜひ一度購入してみてはいかがでしょうか。
※各社通販サイトの 2025年3月4日時点 での税込価格
| 茶葉の種類 | 青茶 |
|---|---|
| 原産国 | 台湾 |
| 抽出タイプ | ティーバッグ |
| 内容量 | 500g(5g×100包) |
| 茶葉の種類 | 青茶 |
|---|---|
| 原産国 | 台湾 |
| 抽出タイプ | ティーバッグ |
| 内容量 | 500g(5g×100包) |
作り置きでき1年中おいしく飲めるプーアル茶
10年間熟成させたため、カビ臭がなくまろやかな味のプーアル茶です。黒茶はクセが強く好みが分かれますが、このプーアル茶は飲みやすいため試してみてください。
この商品には100包入っていて、ティーバッグ1包で1リットル入れることができます。水出しもできるため、夏は作り置きして冷やしておいてもよいでしょう。今まで一度もプーアル茶を飲んだことがない方は、非常にリーズナブルですので購入してみてはいかがでしょうか。
※各社通販サイトの 2025年3月4日時点 での税込価格
| 茶葉の種類 | 黒茶 |
|---|---|
| 原産国 | 中国 |
| 抽出タイプ | ティーバッグ |
| 内容量 | (2g×10包)×3袋 |
| 茶葉の種類 | 黒茶 |
|---|---|
| 原産国 | 中国 |
| 抽出タイプ | ティーバッグ |
| 内容量 | (2g×10包)×3袋 |
バニラを思わせる甘い香りと滑らかな味わいの青茶
高山茶は、台湾中南部山岳地帯の阿里山(ありさん)の標高1,200m地区で栽培された茶葉で作られた烏龍茶です。高級な金萱種(きんせんしゅ)を使っているにもかかわらず、手ごろな価格で提供されています。
バニラを思わせる甘い香りと滑らかな味わいは、今まで持っていた烏龍茶のイメージを変えてしまうでしょう。味と飲みやすさから、1杯飲むと何杯でも飲みたくなってしまうお茶です。
※各社通販サイトの 2025年3月4日時点 での税込価格
| 茶葉の種類 | 青茶 |
|---|---|
| 原産国 | 台湾 |
| 抽出タイプ | 茶葉 |
| 内容量 | 50g(2023年3月現在、期間限定で100gに増量中) |
| 茶葉の種類 | 青茶 |
|---|---|
| 原産国 | 台湾 |
| 抽出タイプ | 茶葉 |
| 内容量 | 50g(2023年3月現在、期間限定で100gに増量中) |
ほのかに甘い烏龍茶に白桃の香りが加わり大人気!
「白桃烏龍 極品」は、台湾産の文山包種(ぶんさんぼうしゅ)に白桃の甘い香りをつけた烏龍茶です。文山包種は、発酵の度合いが低い烏龍茶で日本の緑茶に似た味わいと、花を思わせる香りが特徴です。
花の香りが漂う文山包種に、さらにみずみずしく甘い白桃の香りをつけたことで、世界中で注目される商品となりました。
※各社通販サイトの 2025年3月4日時点 での税込価格
| 茶葉の種類 | 花茶 |
|---|---|
| 原産国 | 台湾 |
| 抽出タイプ | 茶葉 |
| 内容量 | 50g |
| 茶葉の種類 | 花茶 |
|---|---|
| 原産国 | 台湾 |
| 抽出タイプ | 茶葉 |
| 内容量 | 50g |
甘みと香りのバランスがよい人気のお茶
四季春茶(しきしゅんちゃ)は、台湾で1990年以降に作られるようになったお茶です。四季春という名前は、季節に関係なく品質の高い茶葉が摘めることからつけられたそうです。お茶はにごりがなく薄い黄色で、茶色の烏龍茶を見慣れている方はおどろかれるでしょう。
さわやかでほんのり甘い味わいと花の香りは、凍頂烏龍茶に引けをとりません。凍頂烏龍茶を飲まれている方は、ぜひ一度飲んでみてはいかがでしょうか。
※各社通販サイトの 2025年3月4日時点 での税込価格
| 茶葉の種類 | 青茶 |
|---|---|
| 原産国 | 台湾 |
| 抽出タイプ | 茶葉 |
| 内容量 | 200g |
| 茶葉の種類 | 青茶 |
|---|---|
| 原産国 | 台湾 |
| 抽出タイプ | 茶葉 |
| 内容量 | 200g |
黄茶の王様ともいわれる君山銀針
君山銀針は、中国湖南省の君山島で栽培された茶葉から作られた黄茶。年間の生産量がわずか300キロ程度で、なかなか手に入れることは難しい希少茶です。
君山銀針のかすかな甘みを感じながら、ゆっくりと奥深い味を楽しんでください。休日に、君山銀針を飲みながら過ごすことは、もっとも贅沢な時間といえるでしょう。
※各社通販サイトの 2025年3月4日時点 での税込価格
| 茶葉の種類 | 黄茶 |
|---|---|
| 原産国 | 中国 |
| 抽出タイプ | 茶葉 |
| 内容量 | 20g |
| 茶葉の種類 | 黄茶 |
|---|---|
| 原産国 | 中国 |
| 抽出タイプ | 茶葉 |
| 内容量 | 20g |
「中国茶」のおすすめ商品の比較一覧表
| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 茶葉の種類 | 原産国 | 抽出タイプ | 内容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 シーアンドエー 彩香『烏龍茶 凍頂烏龍茶』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月4日時点 での税込価格 |
今までのイメージを覆す革命的な烏龍茶! | 青茶 | 台湾 | ティーバッグ | 茶葉50g、ティーバッグ18包 |
| 2位 marumero(マルメロ)『中国茶 西湖龍井茶(緑茶)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月4日時点 での税込価格 |
香ばしい香りとうまみと甘さで愛好家が多い龍井茶 | 緑茶 | 中国 | 茶葉 | 250g、50g |
| 3位 RIMTAE(リムテー)『工芸茶詰め合わせ10種セット』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月4日時点 での税込価格 |
贈ると喜ばれる花茶詰め合わせセット | 花茶(工芸茶) | 中国 | 茶葉 | 萬紫千紅・金花彩彩・茉莉仙子・花開吉祥・一見鐘情・東方美人・百合花籠・花開富貴・萬寿富貴・心心相印 各1個 |
| 4位 久順茶業『鉄観音茶 』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月4日時点 での税込価格 |
日本でも人気の芳醇な香りと濃厚な味がする烏龍茶 | 青茶 | 台湾 | ティーバッグ | 500g(5g×100包) |
| 5位 久順銘茶『プーアル茶』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月4日時点 での税込価格 |
作り置きでき1年中おいしく飲めるプーアル茶 | 黒茶 | 中国 | ティーバッグ | (2g×10包)×3袋 |
| 7位 苦丁茶(一葉茶)専門店『特選台湾高山茶 阿里山金萱』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月4日時点 での税込価格 |
バニラを思わせる甘い香りと滑らかな味わいの青茶 | 青茶 | 台湾 | 茶葉 | 50g(2023年3月現在、期間限定で100gに増量中) |
| 8位 ルピシア(LUPICIA)『白桃烏龍 極品』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月4日時点 での税込価格 |
ほのかに甘い烏龍茶に白桃の香りが加わり大人気! | 花茶 | 台湾 | 茶葉 | 50g |
| 9位 台湾茶工房『特級 四季春茶』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月4日時点 での税込価格 |
甘みと香りのバランスがよい人気のお茶 | 青茶 | 台湾 | 茶葉 | 200g |
| 10位 シーアンドエー 彩香『黄茶 君山銀針』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月4日時点 での税込価格 |
黄茶の王様ともいわれる君山銀針 | 黄茶 | 中国 | 茶葉 | 20g |
通販サイトの最新人気ランキングを参考にする 中国茶の売れ筋をチェック
Amazon、楽天市場での中国茶の売れ筋ランキングも参考にしてみてください。
※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。
初心者は烏龍茶や緑茶から試してみて
本格的な中国茶ははじめてという方は、青茶の烏龍茶や緑茶から試してみるのがいいでしょう。ペットボトル飲料では感じられないふくよかな香りに驚かれるかもしれません。中国紅茶や、黒茶のプーアール茶、花茶のジャスミン茶などはふだん飲んでいるものと、味や香りが違うので、試してみるのも楽しいでしょう。
お気に入りの中国茶を淹れて、リラックスした時間を過ごしてみましょう。
【中国菓子や茶器セット】はこちらからチェック
中国茶で新しい発見を体験してみてください
中国茶の選び方のポイントやおすすめの商品を紹介しました。味や香りが微妙に異なるものも多いため、すぐに自分の好きな中国茶を見つけるのは、難しいかもしれません。
まずは少量購入して、いろいろな種類の中国茶を飲んでみて、自分に合った中国茶を探してみてください。今まで味わったことのないお茶に出会え、楽しみながら選べるでしょう。
◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。