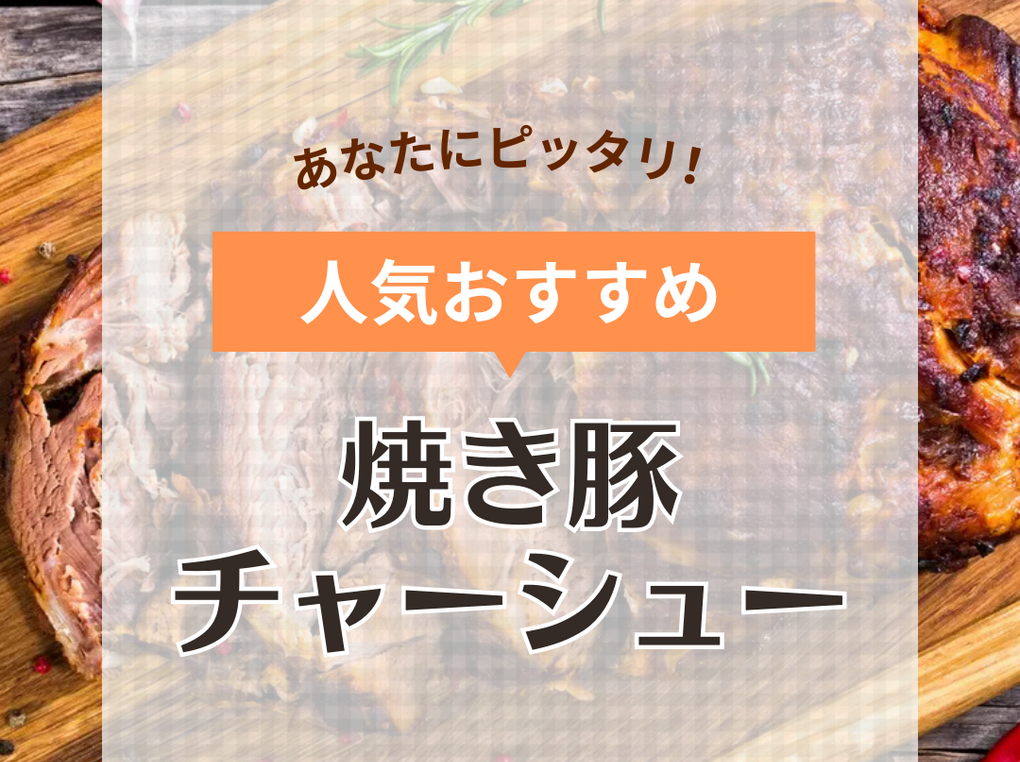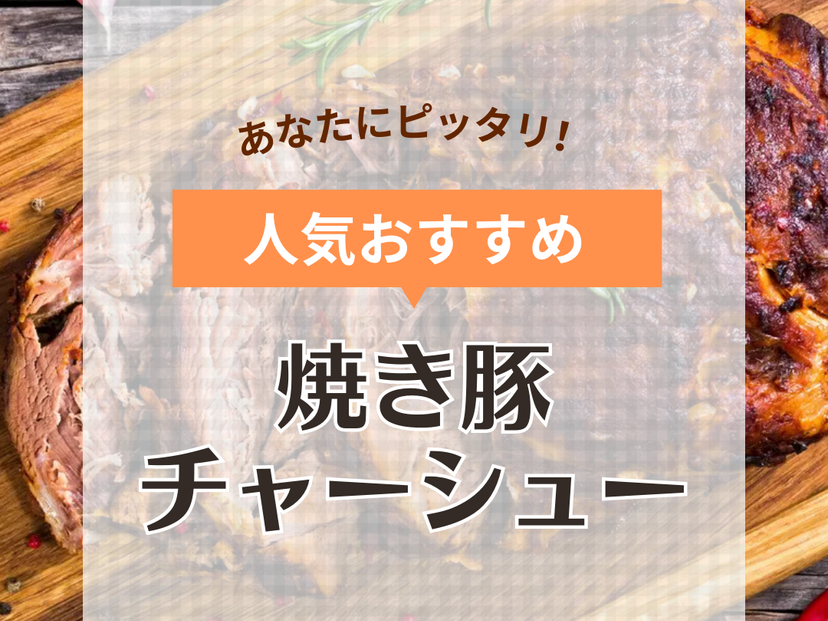| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 使用部位 | 形状 | 保存方法 | 内容量 | 賞味期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スマイルワーク『本当に美味しい丸太 チャーシュー』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月14日時点 での税込価格 |
二郎系ラーメンのトッピングにぴったりな焼豚 | バラ肉 | ブロック | 冷凍 | 約700g | 冷凍で30日 |
| 会津ブランド館『ラーメン屋が作る本物のチャーシュー』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月14日時点 での税込価格 |
ほしい分だけ無駄なく使えるカット済み焼豚 | バラ肉 | スライス | 冷凍 | 800g | 製造日より365日 |
| 山野井『焼豚2本セット(Y-30)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月14日時点 での税込価格 |
専用の焼き釜、炭火で焼き上げた逸品 | モモ肉 | ブロック | 10℃以下 | 320g | - |
| わたせい『三つ編みバラ叉焼』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月14日時点 での税込価格 |
珍しい三つ編みの焼豚 | バラ肉 | ブロック | 冷凍 | 約360~390g | 165日 |
| みんみん『みんみんのとろけるチャーシュー』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月14日時点 での税込価格 |
とろとろの食感が味わえる絶品焼豚 | - | ブロック | 冷凍 | 300g | 365日 |
| Meat-Gen『江戸っ子焼豚』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月14日時点 での税込価格 |
タレがたっぷり入っている焼豚 | 肩ロース | ブロック | 冷凍 | 約350g | - |
| イエノミ『豚バラ つるし焼 切り落とし』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月14日時点 での税込価格 |
たっぷり1kgの肉厚つるし焼豚! | 豚バラ | 切り落とし | 冷凍 | 500g×2 | 90日 |
| 筑波ハム『つくば焼豚』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月14日時点 での税込価格 |
味がなかまでしっかりしみこんだヘルシーな焼豚 | もも肉 | ブロック | 冷蔵 | 230g | 20日間(未開封) |
お取り寄せ焼豚の選び方 ラーメンやチャーハンをもっと美味しく!
焼豚を選ぶときは、使用部位や保存方法をよく確認することが大切。詳しく解説していくのでぜひチェックしてみてください!
ポイントは下記。
【1】好みに合わせて部位を選ぶ
【2】料理に合った形状を選ぶ
【3】用途に合った味付けを選ぶ
【4】使用頻度に見合った保存方法を選ぶ
上記のポイントを押さえることで、より欲しい商品をみつけることができます。一つひとつ解説していきます。
【1】好みに合わせて部位を選ぶ
最初に確認してほしいポイントは、肩ロースやバラといった「部位」です。使用部位によって食感や風味が異なります。
バラ肉|こってり派、脂身が好きな方に
豚の特徴的な脂身が好きな方は、バラ肉を選びましょう。バラ肉は豚の部位のなかでも脂身が多く、肉質はやわらか。赤身と白身が層になっているところも特徴です。
「チャーシュー」という名称で、ラーメンなどにトッピングされていることが多い部位でもあります。バラ肉は脂身が多い分、旨みやコクが強く感じられます。ラーメン以外にもチャーシュー丼など、焼豚の味がしっかりと感じられる料理にも適しています。
肩ロース|適度な脂身がほしい方に
バラ肉はちょっと脂が多すぎるかなと感じる方は、適度に脂身がついている肩ロースや腕肉を選びましょう。肩ロースは赤身のなかに脂身が網目状にはりめぐされている部位で、一般的なロースよりも脂身の部分が多くなっています。
そのため、旨みやコクがほどよく楽しめます。ラーメンのトッピングのほか、おつまみ、チャーハンの具材にもおすすめです。
ロースやもも肉|さっぱり派、低カロリーを求める方に
さっぱりとした味わいが好みなら、脂身が少ないロースやもも肉を選びましょう。ロースは赤身と脂身がバランスよく配置されている部位です。
一方、もも肉は豚のよく動くお尻の肉なので赤身が中心です。もも肉はタンパク質も多く含まれ、焼豚で使用されている部位のなかではカロリーも低め。豚汁などの汁物や煮込み料理に適しています。
【2】料理に合った形状を選ぶ
部位の次にチェックしたいのが、焼豚の形状。あらかじめカットされているものか、かたまりのまま(ブロックタイプ)なのかで、お料理との相性や使いやすさが変わってきます。
ラーメンなどのトッピングには「スライス」
ラーメンなどの麺類のトッピングとして使用するなら、スライスタイプが適しています。もともと切り分けられている商品ならそのままうえに乗せるだけなので、包丁やまな板がいらず洗いものも少なくて済みます。
また、短冊切りにしてトッピングする場合も、スライスタイプなら素早く切り分けられます。できるだけ家事を減らしたい人はスライスタイプが楽チン!
チャーハンなどの具材には「ブロック」
チャーハンなどの具材として焼豚を考えているなら、角切りにできるブロックタイプが適しています。焼豚丼を作りたいときは、少し厚めにカットして丼のうえに乗せるのがおすすめ。ブロックタイプは料理に合わせて自由に切り分けられる点が便利です!
お腹の空き具合や、そのときの人数に合わせられるのも魅力です。カットしてから冷凍しておけば、時短料理にも役立ちます。料理の幅を広げるならブロックタイプの購入がおすすめです。
野菜炒めやおつまみに「切り落とし」
野菜と一緒に炒めたいとか、軽くおつまみを作りたいというときには「切り落としタイプ」がおすすめ。
切り落としタイプは脂身が多いバラ肉のほか、赤身が多いロースなど、さまざまな部位を混ぜ合わせて販売されていることが多いです。そのため、ひとつの部位だけを使っている焼豚よりもいろんな味わいが楽しめます!さらに、価格もお手ごろなことが多いので大量に使う料理や節約中の人にもおすすめですよ。
【3】用途に合った味付けを選ぶ
一口に焼豚と言っても味わいはさまざま。メーカーによってタレの配合や調味方法が大きく異なるので、自分好みの味わいを見つけるのも焼豚選びでは大切になってきます。
たとえばラーメンのトッピングなら、ほかの素材の味を邪魔しないような豚肉本来の味が味わえるようなものを、炒め物に使う場合はしっかりと濃い目の味付けがされた焼豚を選ぶことでバランスよく仕上がります。
どんな用途で使うのかを考慮した上で、焼豚の味付けをチェックしてみてくださいね。
【4】使用頻度に見合った保存方法を選ぶ
焼豚は商品や販売している店舗によって「冷蔵」や「冷凍」など保存方法が異なります。そのため、商品によって賞味期限も数週間〜1年間と大きく異なります。
すぐに食べきってしまうのであれば、比較的、賞味期限の短い冷蔵タイプでもよいのですが、使用頻度がそんなに多くないという方は冷凍タイプを選びましょう。焼豚を選ぶ際は使用頻度を考慮して保存方法にも注目してみてください。
お取り寄せ焼豚のおすすめ8選 美味しい焼き豚厳選! コスパ抜群の大容量パックも!
ここからは、市販のおいしい焼豚を紹介していきます!
二郎系ラーメンのトッピングにぴったりな焼豚
大分市にある「まる重」という二郎系ラーメン店の ブロックチャーシュー。Amazon、楽天、Yahoo!ショッピングでベストセラーを獲得している一品です。
お好みの厚さにカットして、ラーメンのトッピングにするのはもちろん、 チャーシュー丼やおつまみ、料理の具材としても使えます。そのままでも美味しいですが、フライパンで軽く焼くと脂がトロトロしてより絶品に!
タレの味もバランスがよく、ラーメンのスープにも、ほかの料理にもピッタリと好評です。
※各社通販サイトの 2025年3月14日時点 での税込価格
| 使用部位 | バラ肉 |
|---|---|
| 形状 | ブロック |
| 保存方法 | 冷凍 |
| 内容量 | 約700g |
| 賞味期限 | 冷凍で30日 |
| 使用部位 | バラ肉 |
|---|---|
| 形状 | ブロック |
| 保存方法 | 冷凍 |
| 内容量 | 約700g |
| 賞味期限 | 冷凍で30日 |
ほしい分だけ無駄なく使えるカット済み焼豚
人気の高い『ラーメン屋が作る本物のチャーシュー800g』のカット済みタイプ。1袋に2枚ずつ入っていて、ほしい分だけ無駄なく使うことができます。しかも真空冷凍なので、おいしさが長持ちします。
職人が手巻きしている本格豚バラ巻きのチャーシューで、脂身と赤身がバランスよく層になっているのが特徴。お店でそのまま使えるレベルのチャーシューが、自宅で手軽に味わえます!
※各社通販サイトの 2025年3月14日時点 での税込価格
| 使用部位 | バラ肉 |
|---|---|
| 形状 | スライス |
| 保存方法 | 冷凍 |
| 内容量 | 800g |
| 賞味期限 | 製造日より365日 |
| 使用部位 | バラ肉 |
|---|---|
| 形状 | スライス |
| 保存方法 | 冷凍 |
| 内容量 | 800g |
| 賞味期限 | 製造日より365日 |
専用の焼き釜、炭火で焼き上げた逸品
豚モモ肉を独自のタレに付け込んで炭火で焼き上げた商品です。食材選びだけでなく焼き方にもこだわっていて、職人が1本ずつ手作業で行っています。しかも専用の焼き釜、特注の炭を使用。
そのまま温めて食べてもおいしいですし、切り分けてチャーハンやサラダにトッピングしてもいいですね。
※各社通販サイトの 2025年3月14日時点 での税込価格
| 使用部位 | モモ肉 |
|---|---|
| 形状 | ブロック |
| 保存方法 | 10℃以下 |
| 内容量 | 320g |
| 賞味期限 | - |
| 使用部位 | モモ肉 |
|---|---|
| 形状 | ブロック |
| 保存方法 | 10℃以下 |
| 内容量 | 320g |
| 賞味期限 | - |

切り落としタイプとは違いブロックなので、大人数で切り分ける際に便利です。味もしっかり染み込んでいるため、ご飯が進む一品に。
珍しい三つ編みの焼豚
バラ肉を独自の製法で三つ編みにし、1934年の創業当時から継ぎ足している秘伝の醤油ダレをしっかり豚肉に染み込ませた焼豚です。ブロックタイプなので自由に切り分けが可能。
また、三つ編み形状のため、切り分けたあとの断面が美しいことも特徴です。脂身が多いバラ肉ですが、低温でじっくりとローストすることで余分な脂を落とし、コクがありくどくない仕上がりです。
こまかく切らずにスライスしてお皿に並べたり、料理のトッピングで乗せたりすると、見た目にも楽しい食卓が作れますよ。
※各社通販サイトの 2025年3月14日時点 での税込価格
| 使用部位 | バラ肉 |
|---|---|
| 形状 | ブロック |
| 保存方法 | 冷凍 |
| 内容量 | 約360~390g |
| 賞味期限 | 165日 |
| 使用部位 | バラ肉 |
|---|---|
| 形状 | ブロック |
| 保存方法 | 冷凍 |
| 内容量 | 約360~390g |
| 賞味期限 | 165日 |
とろとろの食感が味わえる絶品焼豚
中華料理店が販売している本格的な焼豚。袋のままボイルするだけでとろける絶品チャーシューの出来上がりです。ブロックタイプなので、自由に切り分けられさまざまな料理に使うことができます。実際に店舗を構えるラーメン屋や中華料理屋も使っている商品なだけあって、自宅で手軽に本格的な味が楽しめます。
冷凍保存状態で届くため賞味期限は1年間です。とろとろの焼豚なので、ボイルしたあとは厚めに切り分けして使いましょう。
※各社通販サイトの 2025年3月14日時点 での税込価格
| 使用部位 | - |
|---|---|
| 形状 | ブロック |
| 保存方法 | 冷凍 |
| 内容量 | 300g |
| 賞味期限 | 365日 |
| 使用部位 | - |
|---|---|
| 形状 | ブロック |
| 保存方法 | 冷凍 |
| 内容量 | 300g |
| 賞味期限 | 365日 |
タレがたっぷり入っている焼豚
脂身がやや多めで赤身とのバランスがよい肩ロースを使っている焼豚です。ブロックタイプなので自由に切り分けられるのもポイント。約350gとひとつの家庭で使いやすい量で届きます。
20分湯煎すると熱々の美味しい焼豚をすぐに食べることが可能です。タレもたっぷりとパッキングされているので、あまったらほかの料理に使うこともできます!
※各社通販サイトの 2025年3月14日時点 での税込価格
| 使用部位 | 肩ロース |
|---|---|
| 形状 | ブロック |
| 保存方法 | 冷凍 |
| 内容量 | 約350g |
| 賞味期限 | - |
| 使用部位 | 肩ロース |
|---|---|
| 形状 | ブロック |
| 保存方法 | 冷凍 |
| 内容量 | 約350g |
| 賞味期限 | - |
たっぷり1kgの肉厚つるし焼豚!
つるし直火焼きとタレの二段仕込みで豚肉の旨味を凝縮させた本格つるし焼豚。正規品は、きれいな化粧箱に入り贈答用にも使用されています。その切り落としなので、味わいはそのままなのにお買い得なんです。500gが2袋入っていてこの値段は破格です。
そのままおつまみにしてもよし、ラーメンに乗せてもよし。肉厚なのでご飯に乗せて丼にするのもおすすめです!
※各社通販サイトの 2025年3月14日時点 での税込価格
| 使用部位 | 豚バラ |
|---|---|
| 形状 | 切り落とし |
| 保存方法 | 冷凍 |
| 内容量 | 500g×2 |
| 賞味期限 | 90日 |
| 使用部位 | 豚バラ |
|---|---|
| 形状 | 切り落とし |
| 保存方法 | 冷凍 |
| 内容量 | 500g×2 |
| 賞味期限 | 90日 |
味がなかまでしっかりしみこんだヘルシーな焼豚
赤身の多いもも肉を焼豚に仕上げたヘルシーな商品です。タレは丸大豆醤油とザラメ、砂糖をベースに生姜を加えた日本人に馴染みのある味わい。ブロックタイプですが、なかまで味がしっかりと染み込んでいてしっとりやわらかな食感が楽しめます。
冷蔵保存なので、サラダのトッピングにするなど毎日食べる料理に適していますよ。さっぱりした焼豚を食べたい人やカロリー控えめの焼豚を探している人はぜひチェックしてください!
※各社通販サイトの 2025年3月14日時点 での税込価格
| 使用部位 | もも肉 |
|---|---|
| 形状 | ブロック |
| 保存方法 | 冷蔵 |
| 内容量 | 230g |
| 賞味期限 | 20日間(未開封) |
| 使用部位 | もも肉 |
|---|---|
| 形状 | ブロック |
| 保存方法 | 冷蔵 |
| 内容量 | 230g |
| 賞味期限 | 20日間(未開封) |
「焼豚」のおすすめ商品の比較一覧表
| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 使用部位 | 形状 | 保存方法 | 内容量 | 賞味期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スマイルワーク『本当に美味しい丸太 チャーシュー』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月14日時点 での税込価格 |
二郎系ラーメンのトッピングにぴったりな焼豚 | バラ肉 | ブロック | 冷凍 | 約700g | 冷凍で30日 |
| 会津ブランド館『ラーメン屋が作る本物のチャーシュー』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月14日時点 での税込価格 |
ほしい分だけ無駄なく使えるカット済み焼豚 | バラ肉 | スライス | 冷凍 | 800g | 製造日より365日 |
| 山野井『焼豚2本セット(Y-30)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月14日時点 での税込価格 |
専用の焼き釜、炭火で焼き上げた逸品 | モモ肉 | ブロック | 10℃以下 | 320g | - |
| わたせい『三つ編みバラ叉焼』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月14日時点 での税込価格 |
珍しい三つ編みの焼豚 | バラ肉 | ブロック | 冷凍 | 約360~390g | 165日 |
| みんみん『みんみんのとろけるチャーシュー』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月14日時点 での税込価格 |
とろとろの食感が味わえる絶品焼豚 | - | ブロック | 冷凍 | 300g | 365日 |
| Meat-Gen『江戸っ子焼豚』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月14日時点 での税込価格 |
タレがたっぷり入っている焼豚 | 肩ロース | ブロック | 冷凍 | 約350g | - |
| イエノミ『豚バラ つるし焼 切り落とし』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月14日時点 での税込価格 |
たっぷり1kgの肉厚つるし焼豚! | 豚バラ | 切り落とし | 冷凍 | 500g×2 | 90日 |
| 筑波ハム『つくば焼豚』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月14日時点 での税込価格 |
味がなかまでしっかりしみこんだヘルシーな焼豚 | もも肉 | ブロック | 冷蔵 | 230g | 20日間(未開封) |
通販サイトの最新人気ランキングを参考にする 焼豚の売れ筋をチェック
Amazon、楽天市場での焼豚の売れ筋ランキングも参考にしてみてください。
※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。
部位別カロリー&アレンジレシピを紹介 低カロリー部位はダイエット中にも!
焼豚と聞くとカロリーの高い食べ物としてイメージする人も多いですが、使用部位によってカロリーが異なります。ここからは、各部位のカロリーについて解説し、焼豚のアレンジレシピも紹介していきます!
各部位のカロリーを確認する
まずは、各使用部位のカロリーをご紹介します。
●脂身が多いバラ肉は100gあたり約390Kcal
●肩ロースは赤身なら100gあたり約150Kcal、脂身は約250Kcal
●もも肉は赤身なら約130Kcal、脂身は約180Kcal
このように、使用部位によってカロリーに差が出ることがわかりますね。
焼豚はカロリーが低い食べ物というわけではありませんが、原材料の豚肉はビタミンB1が豊富。豚肉がもつビタミンは、脂肪を燃焼させる働きや代謝のサイクルをスムーズにする働きがあるため、脂身の少ない部位を選んで食べ方を工夫すればダイエット中にも楽しめます。
ほかの食材をたっぷり加えてローカロリー料理にアレンジ!
焼豚をラーメンにトッピングするなら、もやしや長ネギ、ニラ、レタス、キャベツをたっぷり入れて麺を少なめにします。チャーシュー丼として楽しむなら、ご飯の量を少なめにして葉野菜をたっぷり乗せるといいです。チャーハンの具材としてなら、ご飯の量を減らし玉ねぎ、ピーマン、人参の量を増加。
おつまみにするなら、もやしや長ネギと一緒にあえ、中華ドレッシングやノンオイルドレッシングをかけてみましょう。
焼豚は食べたいけれどカロリーは抑えたいというときは、炭水化物の量を減らし、野菜を多く加えるアレンジレシピをお試しください。
調理方法や好みで使い分けよう 温活料理研究家からのアドバイス
焼豚と一口にいっても、さまざまなタイプがあります。さっぱりが好きなのか、こってりが好きなのか?または、どんな調理に使うのかで焼豚を見つけてみるとよいですね。
味付けしてあるものが好きなのか、後づけのたれがあったほうがよいのか? などお好みに合わせて選んでみてください。
焼豚に合わせたいチャーハンやラーメンの記事はこちら 【関連記事】
お取り寄せ焼豚で美味しい食卓にしよう!
本記事では、焼豚の選び方とおすすめの商品を温活料理研究家・渡辺愛理さんと編集部で紹介しました。焼豚は使用部位によって味わいが異なります。脂身多めが好みならバラ肉、赤身と脂身のバランスを重視したい場合は肩ロース、カロリーを抑えてさっぱりと食べたいときはロースやもも肉を使った焼豚を選びましょう。
また、使う料理によって適した形状も異なります。紹介商品を参考にして、美味しい焼豚で食卓を彩ってください。
◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。