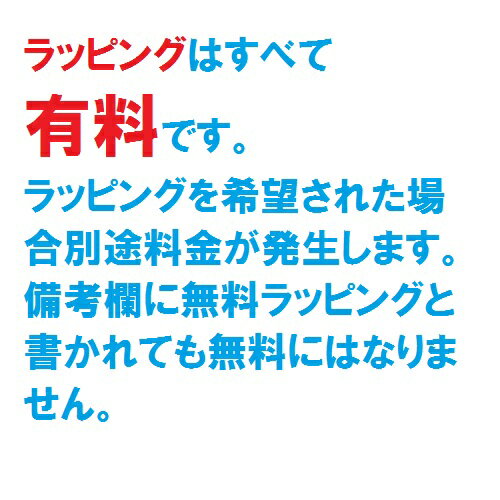| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | タイプ | 材質 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI(スズキ)『教育用カスタネット (SC-100W)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |
赤・青が懐かしい教育用の定番 | 丸型 | 木製 | 直径55mm |
| YAMAHA(ヤマハ)『ハンドカスタネット YHC-C4』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |
パステルカラーの色合いが可愛らしい | 丸型 | バーチ材 | 直径58mm |
| YAMAHA(ヤマハ)『ハンドカスタネット YHC-G4』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |
木目調デザインがおしゃれ | 丸型 | バーチ材 | 直径58mm |
| ゼンオン 『カスタネット』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |
丈夫な教育用カスタネット | 丸型 | 木製 | 直径:57mm |
| PLAYWOOD(プレイウッド)『カスタネット (CA-20MB)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |
低価格ながら本格派のフラメンコスタイル | 貝殻型 | フィブラ樹脂 | 70×90mm |
| KC(ケーシー)『Flapper Castanet (OP-FCA01)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |
振るだけで高速連打できる柄付きタイプ | 柄付き | プラスチック | 約195×50×45mm |
| GROVER(グローバー)『コンサート・カスタネット (GV-GWC3G)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |
本格的な演奏の練習に最適 | 柄付き | グラナディージョ(木製) | - |
| GITRE(ジトレ)『スティックカスタネット (GI722)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |
小さなお子さまへのプレゼント用にも | 柄付き | プラスチック | 17センチ |
| LP(エルピー)『Castanet Machine (LP427)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |
両手で叩けるスタンドタイプ | スタンドタイプ | 樹脂製 | 約152,4×50,8mm |
カスタネットの選び方 音楽ライターがおすすめする
それでは、カスタネットの基本的な選び方を見ていきましょう。ポイントは下記の3つ。
【1】種類・形状で選ぶ
【2】素材で選ぶ
【3】サイズは手の大きさにあわせて選ぶ
上記の3つのポイントをおさえることで、より具体的に欲しい機能を知ることができます。一つひとつ解説していきます。
【1】種類・形状で選ぶ
カスタネットは形状に応じて「丸型」「貝殻型」「柄付きタイプ」の3種類のタイプに大きく分けることができます。それぞれどのような特徴があるのでしょうか。
丸型:小学校でおなじみの定番カスタネット
カスタネットといえば、多くの人が思い浮かべるのが赤と青に色分けされた子ども用の「丸型」のものでしょう。片手で持って叩けば音が出る簡単な仕組みなので、教育用にも使われていて、子どもが音楽に親しんだりリズムを身につけたりするのに最適です。
貝殻型:フラメンコなど本格的な演奏に
クラシックのオーケストラやフラメンコで使われるのがこの「貝殻型」です。音程の異なる1組を両手に持って複雑なリズムを鳴らせるのが特徴。
通常は閉じた状態なのできちんと技術を身につけないと鳴らせませんが、慣れればドラマチックな演奏ができるようになります。本格的な演奏をしたいなら貝殻型を使いましょう。
柄付きタイプ:扱いやすく種類が豊富
貝殻型のカスタネットに柄が付いたものが「柄付きタイプ」です。手や脚に打ち付けて鳴らすこのカスタネットは、初心者でも演奏しやすいのが特徴です。
なお、貝殻型の練習に最適なコンサートカスタネットや、子どもでも扱いやすいスティックカスタネット、振るだけで音が鳴るフラッパーカスタネットなど、さらに種類が分かれています。
スタンドタイプ:パーカッション奏者向き
卓上に置いたり、スタンドにマウントして利用するカスタネットが「スタンドタイプ」です。これはさまざまな楽器を並べてプレイするパーカッション奏者向きになります。
【2】素材で選ぶ
カスタネットに使用される素材はおもに「木製」と「樹脂製」です。それぞれどのような違いがあるのでしょうか。
木製:深みのある音が特徴
木製のカスタネットは見た目の雰囲気がよく、音には深みがあって響きもよいので、あたたかい音で演奏したい人や複数人数でカスタネットを演奏する人にも向いています。ただし、希少な高級木材を使ったものは値段も高価です。
樹脂製:抜けのよい音が特徴
樹脂製のカスタネットは湿気などの影響を受けにくく、スティックなどで叩いても破損しにくいなどの特徴があり長期間使えます。また、木製より音の抜けがよいのでほかの楽器がたくさんあってもしっかり聞こえてきます。バンドで使うなどの場合は樹脂製をおすすめします。
【3】サイズは手の大きさにあわせて選ぶ
カスタネットにも色々なサイズがあります。サイズが大きいほど音量も大きく音程が低くなり、コンパクトなものは音量が小さく高い音になりますが、演奏のしやすさを考えると、音よりも自分の手の大きさに合わせることのほうが重要です。できれば一度は店頭などで手に取って、しっくりくるサイズかどうかを確認しておきましょう。
また、カスタネットのサイズは、5号、6号というように号数で表されることがありますが、メーカーによって同じ号数でもサイズが異なることがあるので注意してください。
カスタネットのおすすめ9選 音楽ライターが厳選!
ここまで紹介したカスタネットの選び方のポイントをふまえて、音楽ライターの田澤 仁さんと編集部がおすすめする商品を紹介します。

赤・青が懐かしい教育用の定番
教育現場で最も使われている大定番モデルのひとつです。幼稚園や小学校で使う子どもへのプレゼントにもよいし、壊れてしまったときの交換用、うっかりなくしてしまった場合の予備にも最適です。
木製ならではの軽やかであたたかい音を鳴らせますし、音量も必要十分です。子どもに最適な小ぶりのサイズで、指にかけるゴムひもも子ども向けに合わせてあります。ですが、ひもは簡単に結び直すことができるので大人でも十分使うことができます。コストパフォーマンスも抜群です。
※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格
| タイプ | 丸型 |
|---|---|
| 材質 | 木製 |
| サイズ | 直径55mm |
| タイプ | 丸型 |
|---|---|
| 材質 | 木製 |
| サイズ | 直径55mm |
パステルカラーの色合いが可愛らしい
幼児の音楽教育から小学校の器楽合奏まで幅広く使える教育用カスタネットです。傷や水に強いバーチ材が使われており、落ち着いた柔らかい音質が特徴です。パステルカラーの塗装は優しく可愛らしい印象で、おしゃれ心をくすぐります。
※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格
| タイプ | 丸型 |
|---|---|
| 材質 | バーチ材 |
| サイズ | 直径58mm |
| タイプ | 丸型 |
|---|---|
| 材質 | バーチ材 |
| サイズ | 直径58mm |
木目調デザインがおしゃれ
安価で人と被らないおしゃれなカスタネットが欲しい方にはこちらがおすすめ。ナチュラルかつシンプルな木目調のデザインは、幅広い年齢層にハマります。バーチ材の色と風合いを活かしたクリア塗装も魅力的です。
※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格
| タイプ | 丸型 |
|---|---|
| 材質 | バーチ材 |
| サイズ | 直径58mm |
| タイプ | 丸型 |
|---|---|
| 材質 | バーチ材 |
| サイズ | 直径58mm |
丈夫な教育用カスタネット
全音楽譜出版社ことゼンオンが手掛ける定番カラーのカスタネット。重さは37gと軽量で、子どもでも負担なく使えます。幼稚園、小学校など教育用にオススメです。学校の音楽授業でも区別がしやすいように、カスタネットの内側には名前シールが貼られています。
※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格
| タイプ | 丸型 |
|---|---|
| 材質 | 木製 |
| サイズ | 直径:57mm |
| タイプ | 丸型 |
|---|---|
| 材質 | 木製 |
| サイズ | 直径:57mm |

低価格ながら本格派のフラメンコスタイル
日本カスタネット協会公認というこのモデル、低価格ながら本格的なフラメンコスタイルに仕上がっているので、誰にでもおすすめできる製品です。材質はフィブラ樹脂で、従来の木製やプラスチック製に比べて耐久性が高く、長い間使い続けることができます。
高度な演奏に対応できるよう、プロのカスタネット奏者をアドバイザーに迎えて開発したというだけあって、音の抜けはよいし、音量も十分。これからフラメンコを始めようという人はもちろん、ブラスバンドやラテンバンドのパーカッション奏者にもおすすめです。ブラックのほか、レッドやグリーンのカラーバリエーションもラインナップされています。
※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格
| タイプ | 貝殻型 |
|---|---|
| 材質 | フィブラ樹脂 |
| サイズ | 70×90mm |
| タイプ | 貝殻型 |
|---|---|
| 材質 | フィブラ樹脂 |
| サイズ | 70×90mm |

振るだけで高速連打できる柄付きタイプ
柄付きカスタネットは、フラメンコカスタネットに柄を付けたものと、2枚の板の間に中板を挟んだものの2タイプがありますが、こちらは後者。柄を持って振るだけで、よさこい鳴子のようにパタパタと開閉し、中板に接触することで発音します。
初心者でも、ドラムのロール奏法のような連打が簡単にできます。両手に1本ずつ持って振れば、さらなる超高速連打や、複雑なリズムも打ち鳴らせます。プラスチック製で音色はとても明るく、抜けもよいです。パーカッション奏者におすすめです。
※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格
| タイプ | 柄付き |
|---|---|
| 材質 | プラスチック |
| サイズ | 約195×50×45mm |
| タイプ | 柄付き |
|---|---|
| 材質 | プラスチック |
| サイズ | 約195×50×45mm |
本格的な演奏の練習に最適
弦楽器のペグで有名なグローバー社が作ったコンサートカスタネット。スペイン製のカスタネットの形を研究し、コンピューター制御を駆使して完成させました。材質には木製ながら壊れにくい耐久性を備えた「グラナディージョ」を採用。柄を手に持って、膝を打ちながらリズムをとる演奏スタイルに適しています。保管や持ち運びに役立つ専用ポーチも付属しています。
※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格
| タイプ | 柄付き |
|---|---|
| 材質 | グラナディージョ(木製) |
| サイズ | - |
| タイプ | 柄付き |
|---|---|
| 材質 | グラナディージョ(木製) |
| サイズ | - |
小さなお子さまへのプレゼント用にも
「ジトレ」のスティックカスタネット。ジトレの製品は幼稚園や学校のほか、音楽セラピーの現場でも使用されている親しみやすさが魅力です。柄付きで音が鳴らしやすいので、小さい子どもへのプレゼントにも適しています。
※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格
| タイプ | 柄付き |
|---|---|
| 材質 | プラスチック |
| サイズ | 17センチ |
| タイプ | 柄付き |
|---|---|
| 材質 | プラスチック |
| サイズ | 17センチ |

両手で叩けるスタンドタイプ
スタンドにマウントしたり、テーブルに置いたりして使えるタイプ。2つのカスタネットが並んでいて、コンガやボンゴのように両手で叩いて鳴らせるので、初心者でも簡単に複雑なリズムを演奏することができます。指先をうまく使えば、フラメンコのような高度な演奏も可能です。耐久性の高い樹脂製なので、スティックでの演奏も問題ありません。ドラムセットやパーカッションのスタンドに簡単に取り付けられるので、バンドのドラマーやパーカッション奏者が使う場合もとても便利です。
※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格
| タイプ | スタンドタイプ |
|---|---|
| 材質 | 樹脂製 |
| サイズ | 約152,4×50,8mm |
| タイプ | スタンドタイプ |
|---|---|
| 材質 | 樹脂製 |
| サイズ | 約152,4×50,8mm |
おすすめ商品の比較一覧表
| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | タイプ | 材質 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI(スズキ)『教育用カスタネット (SC-100W)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |
赤・青が懐かしい教育用の定番 | 丸型 | 木製 | 直径55mm |
| YAMAHA(ヤマハ)『ハンドカスタネット YHC-C4』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |
パステルカラーの色合いが可愛らしい | 丸型 | バーチ材 | 直径58mm |
| YAMAHA(ヤマハ)『ハンドカスタネット YHC-G4』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |
木目調デザインがおしゃれ | 丸型 | バーチ材 | 直径58mm |
| ゼンオン 『カスタネット』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |
丈夫な教育用カスタネット | 丸型 | 木製 | 直径:57mm |
| PLAYWOOD(プレイウッド)『カスタネット (CA-20MB)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |
低価格ながら本格派のフラメンコスタイル | 貝殻型 | フィブラ樹脂 | 70×90mm |
| KC(ケーシー)『Flapper Castanet (OP-FCA01)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |
振るだけで高速連打できる柄付きタイプ | 柄付き | プラスチック | 約195×50×45mm |
| GROVER(グローバー)『コンサート・カスタネット (GV-GWC3G)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |
本格的な演奏の練習に最適 | 柄付き | グラナディージョ(木製) | - |
| GITRE(ジトレ)『スティックカスタネット (GI722)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |
小さなお子さまへのプレゼント用にも | 柄付き | プラスチック | 17センチ |
| LP(エルピー)『Castanet Machine (LP427)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |
両手で叩けるスタンドタイプ | スタンドタイプ | 樹脂製 | 約152,4×50,8mm |
通販サイトの最新人気ランキングを参考にする カスタネットの売れ筋をチェック
Amazon、楽天市場でのカスタネットの売れ筋ランキングも参考にしてみてください。
※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。
カスタネットに関するQ&A よくある質問


ハンドカスタカスタネットを左手で表にして持ちます。右手の人差指、また中指を 中央のくぼみにつけて、離さないようにして打ちます。


スペイン語で「栗の実」を意味する「カスターニャ(castana)」が語源といわれています。大昔、栗の木で作っていたという話や、栗の形に似ているからということが由来とされています。
音楽ライターからのアドバイス メンテナンスや演奏環境にも注意
カスタネットの2枚の板を結びつけるひもは、消耗品です。演奏中にゆるんだり切れたりしないよう普段からチェックし、劣化したら迷わず交換してください。メーカー純正の交換用ひもが用意されている場合もあるし、その他にもいろいろな製品があるので、いくつか試して自分の奏法に合ったものを見つけてください。
また、カスタネットは意外に大きな音がするので、自宅での練習を躊躇(ちゅうちょ)している人もいるかもしれません。そんな場合は、カスタネット用の消音パッドで音を小さくすることができます。これにも打面のみを覆うタイプ、全体を覆うタイプなどさまざまなタイプがあるので、家でも気兼ねなく練習したい人はチェックしてみてください。
そのほかの楽器に関連する記事はこちら 【関連記事】
使い方にあわせて最適なカスタネットを選びましょう
これまでカスタネットの選び方とおすすめの商品を紹介してきました。
小学校で定番のカスタネットだけでなく、フラメンコといった大人の趣味にも活用できるものまで種類はさまざま。お子さんの誕生日プレゼントとしてもよいかもしれません。
バリエーション豊富なカスタネットのなかから、あなたにぴったりのカスタネットを見つけてみてください。
◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。