| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | フィルムサイズ | 質量 | 絞り | シャッタースピード | ISO感度 | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUJIFILM(富士フイルム)『instax mini 12』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月03日時点 での税込価格 |
スタンダードなチェキの最新作 | 86×54mm | 306g | - | 1/2~1/250 秒 | - | 単三乾電池 |
| FUJIFILM(富士フイルム)『インスタントカメラ チェキ instax mini 11』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月03日時点 での税込価格 |
その場でプリント!チェキカメラのニューモデル | 20x30x13mm | 約387g | - | - | - | 電池式 |
| FUJIFILM (富士フイルム)『写ルンです シンプルエース 27枚撮り』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月03日時点 での税込価格 |
1番手軽にフィルムカメラを始めるならばこれ! | 35mm版 | 90g | F=10 | 1/140秒 | ISO400 | 内蔵使い切り(乾電池) |
| Polaroid(ポラロイド)『Polaroid Snap デジタルインスタントカメラ』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月03日時点 での税込価格 |
デジタルカメラの機能を搭載した小型軽量モデル | 5×7.6 cm | 408g | - | - | - | 充電式 |
| FUJIFILM (富士フイルム)『instax mini 40 INS MINI 40』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月03日時点 での税込価格 |
クラシックな新デザインのインスタントカメラ | 富士フイルム インスタントフィルム instax mini | 約330g | - | 1/2~1/250秒 | - | 単3形アルカリ電池(LR6)2本 |
| Kodak(コダック)『KODAK EKTAR H35ハーフフレームフィルムカメラ(EKTAR H35)』 |
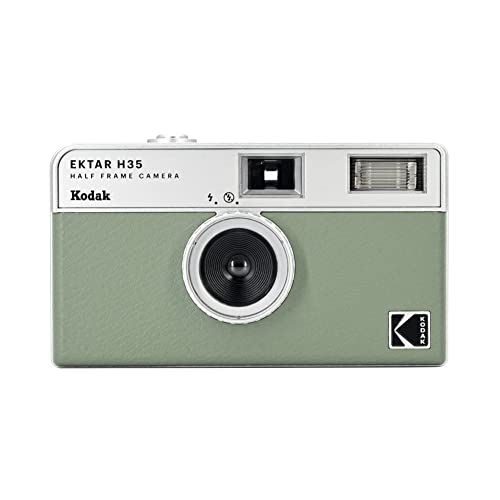
|
※各社通販サイトの 2024年10月03日時点 での税込価格 |
1コマに2枚の写真を撮影できる! | 35mm(ハーフフレーム) | 約120g | 9.5 | 1/100秒 | ‐ | 単四アルカリ乾電池1個 |
| Leica(ライカ)『ライカ MP』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月5日時点 での税込価格 |
「撮ること」に集中させた究極のM型ライカ | 35mm版 | 約585g | - | 1〜1/1000秒(1ステップ) 「B」:バルブ(無制限) フラッシュ同調速度:1/50秒 | ISO6/9°〜6400/39°(マニュアル設定) | 電池式 |
| YASHICA(ヤシカ)『MF-1』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月5日時点 での税込価格 |
水陸両方の撮影も可能な簡易カメラ | 35mm版 | 77g | - | 1/120 s | 400 | - |
| FUJIFILM (富士フイルム)『instax mini LiPlay』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月03日時点 での税込価格 |
録音した音を「撮れる」新しいタイプのチェキ | 35mm版 | 255g | F2.0 | 1/4秒~1/8000秒(自動切換え) | 100~1600(自動切換え) | リチウムイオン電池(内蔵型:取り外し不可) |
| Leica(ライカ)『ライカ M-A(Typ127)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月03日時点 での税込価格 |
60年の歴史をもつ、M型ライカの基本形 | 35mm版 | 約578g | - | 1 〜 1/1000秒(1ステップ)、 「B」:バルブ(無制限) | - | - |
| YASHICA(ヤシカ)『MF-2 super』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月03日時点 での税込価格 |
持ち運びしやすい片手で持てるサイズ感 | 35mm版 | 約210g | f3.8 | 1/125ss | 400 | ‐ |
| Leica(ライカ)『ゾフォート』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月03日時点 での税込価格 |
憧れライカのインスタントカメラ | ライカ ゾフォート用フィルム、instax mini | 約305g | - | - | - | 充電式 |
| Kodak(コダック)『フィルムカメラM35』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月03日時点 での税込価格 |
簡単操作でフィルムカメラ初心者にもおすすめ | 35mm版 | 約100g | F10 | 1/120秒 | - | 電池式 |
| Lomography『Lomo LC-A 120』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月03日時点 での税込価格 |
真四角な画面が写せる中判カメラ | 中判 | - | - | - | - | 電池式 |
| Nikon(ニコン)『Nikon FM2/T 』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月5日時点 での税込価格 |
35mm | - | - | - | - | 電池式 |
フィルムカメラとは? レトロな魅力満載!
「フィルムカメラ」とは、レンズを通した光をフィルムに感光させて記録する撮影機器のことです。撮れた写真がすぐに見られるデジタルカメラやスマホとは違い、現像を見るまでのワクワク感は、フィルムカメラでしか味わうことのできない醍醐味です。
フィルム特有の、柔らかくレトロな雰囲気の仕上がりになるのが特徴です。また、カメラのフィルムがおよそ1本あたり24〜36カットと、撮影回数が限られているのも特徴です。フィルムの種類や撮影時の天候によっても写真の仕上がりが変わるので、そんなところもデジタルでは味わえない楽しみのひとつです。
フィルムカメラ選び方 初心者は要チェック!
カメラのデジタル化が進む一方で、レトロでおしゃれな写真が撮れる「フィルムカメラ」も人気です。フィルムごとに変わる色味や風合いもまた楽しみですよね。カメラ自体も、レトロなものから機械的なものまで、おしゃれな製品がさまざま販売されています。
この記事では、フィルムカメラの選び方をご紹介します。「どんどん外に持ち出したくなる」「大事にしたい」、そんなカメラをぜひ見つけてくださいね。
ポイントは下記。
【1】使用するフィルムタイプをチェック
【2】カメラの種類で選ぶ
【3】交換レンズ購入のことも考えておく
【4】デジタルカメラとは異なる点を知っておく
【5】機能のチェック
上記のポイントを押さえることで、より欲しい商品をみつけることができます。一つひとつ解説していきます。
【1】使用するフィルムタイプを事前にチェック
フィルムカメラは使用するフィルムのタイプが決まっています(『写ルンです』などレンズ付きフィルムカメラを除く)。現在、一般に使用されているフィルムには2つのタイプがあります。
1つは35mmフィルム(135タイプとも言います)で、パトローネとよばれる金属製の密封装置に入っています。もう1つは、ブローニーフィルム(120タイプまたは220タイプ)で、こちらは遮光用紙に包まれてロール状になっています。
フィルムには、ネガカラーフィルム、リバーサルカラーフィルム(ポジフィルム)、そしてモノクロ(白黒)ネガフィルムの3種類がありますので、撮影目的や表現目的にあわせて選ぶ必要があります。
【2】カメラの種類で選ぶ
フィルムカメラには、おもに一眼レフ、二眼レフ、コンパクトカメラ、チェキなどがあります。もちろん性能はそれぞれ違いますので、自分の用途に合ったー台を見つけてください。
なお、初心者におすすめなのは一眼レフです。アイテム数が多いので、はじめてフィルムカメラを購入する際にも自分に合ったものを選べやすいです。フィルムやレンズの数が多いのも、初心者におすすめする理由のひとつです。徐々にレベルアップしたら、レンズなどを変えていきましょう。
コンパクトカメラやチェキなどは、とくに女性に人気があります。軽量で持ち運びしやすいので、旅行やお出かけに活躍すること間違いなし!
二眼レフは、カメラ上級者や一風変わった写真を楽しみたい方におすすめです。正方形の写真が撮れるのも魅力。ファインダーから見える画像と実際の写真にズレが生じたりするので、初心者には扱いが難しいかも知れません。
【3】交換レンズ購入のことも考えておく
ここに紹介したフィルムカメラは、レンズ交換式カメラとレンズ内蔵式カメラの2種類です。レンズ交換式カメラは言うまでもなく交換レンズが必要で、交換レンズを持っていなければ、カメラボディを購入するときに必ず購入しなければなりません。
メーカーによってはとても高価な交換レンズしかないこともありますので、「カメラ+レンズ」のことを考えて予算を立てておきましょう。
レンズ交換式カメラのメーカーではフィルムカメラだけでなく、デジタルカメラも販売していますから、購入した交換レンズはフィルムカメラにもデジタルカメラにも使えるというメリットもあります。
はじめてレンズ交換式カメラを購入する予定で、どんなレンズを選んでいいか迷っているなら、まずは標準ズームレンズまたは50mm標準レンズを選ぶことをおすすめします。
【4】デジタルカメラとは異なる点を知っておく
フィルムカメラはフィルムをカメラにセットして、指定された撮影枚数を撮影し終えればフィルムを巻き戻して取り出し、さらに撮影を続けるのであれば別の新しいフィルムをカメラにセットする必要があります。また、一度使用したフィルムは再使用できません。
1本のフィルムは最大でも36カットしか撮影できないので(特殊なカメラを除く)、デジタルカメラのように何十カット何百カットも連続して撮影し続けることができません。撮影してもその結果を確認するまでに数時間、数日かかるうえに、デジタルカメラのようにすぐに液晶モニターを見て写っていることを確認することもできません。ワンカットずつ慎重に露出やピントを合わせて撮影する必要があります。
とくにはじめてフィルムカメラを使う人は、そうした「フィルムカメラの不便さ」をよく理解しておくことが重要です。
【5】機能のチェック
撮影する場所や天候によって、光を取り込む量を設定する必要があります。「露出計」がついているとファインダー内で適正設定をガイドしてくれるので便利です。
また、フィルムカメラの操作を楽しむなら「マニュアルフォーカス」、ピントを合わせたいときには「オートフォーカス」など、ピントの合わせ方もそれぞれの特色で選ぶのもいいですよね。
フィルムカメラのおすすめメーカー
ここからは、フィルムカメラのおすすめメーカーの一部をご紹介します。メーカーごとにカメラの特徴がありますので、それもふまえて、見た目とメーカーでカメラを選ぶのもありです。
見た目が気に入ると愛着がわき、カメラの出番が多くなることも。多くなればカメラの腕前も上達し、素敵な写真が上手に撮れるようになっていきます。お気に入りのデザインと機能があるメーカーを見つけてみてくださいね。
▼FUJIFILM(富士フイルム)
写真フィルムの国産化を志して1934年に創業した、日本の精密化学メーカー「FUJIFILM(富士フイルム)」。カメラ、デジタルカメラ、映画用フィルムから、複写機などのOA機器や医療機器、化粧品などを製造・販売しています。
はじめてカメラを買う人や初心者にも使いやすい、小型・軽量でお手頃な価格のものから、コンセプトが明確でカメラファンから人気のものなど、さまざまなカメラ製品を取り扱っています。
▼Kodak(コダック)
Kodak(コダック)は、世界で初めてロールフィルムおよびカラーフィルムを発売したメーカーです。Kodakのフィルムは黄色味がかったあたたかみのある色味と言われています。
デザインがおしゃれでかわいいのが特徴。フィルムカメラデビューもしやすいので、初心者のカメラ女子や子どもにおすすめのメーカーです。
▼Leica(ライカ)
高価で独特な存在感をもつ「Leica(ライカ)」。いつかは手にしたい!と思われてるカメラファンも多いのではないでしょうか。
Leica(ライカ)のフィルムカメラは、コンパクトかつ耐久性に優れた高品質のボディを採用しているのが特徴。プロが使う大きな機材と同程度、またはそれ以上のものを撮影できるにもかかわらず、コンパクトなサイズに収まる製品があるのが魅力です。
フィルムカメラおすすめ15選 さまざまな製品をピックアップ!
フィルムカメラの選び方のポイントをふまえて、おすすめ商品をご紹介します。自分が使いやすそうな機種を選ぶ際の参考にしてください。
スタンダードなチェキの最新作
2023年に発売された「instax mini」シリーズの新作で、撮影したらすぐにプリントされるアナログタイプの製品。周囲が明るくても暗めであっても自動的に適切なシャッタースピードとフラッシュ光量を調整するので、きれいに撮影できます。
「クローズアップモード」も搭載しているので、料理や花などに近づいて撮影することも可能。セルフィーもミラーで確認しながら簡単に撮れます。
※各社通販サイトの 2024年10月03日時点 での税込価格
| フィルムサイズ | 86×54mm |
|---|---|
| 質量 | 306g |
| 絞り | - |
| シャッタースピード | 1/2~1/250 秒 |
| ISO感度 | - |
| 電源 | 単三乾電池 |
| フィルムサイズ | 86×54mm |
|---|---|
| 質量 | 306g |
| 絞り | - |
| シャッタースピード | 1/2~1/250 秒 |
| ISO感度 | - |
| 電源 | 単三乾電池 |
その場でプリント!チェキカメラのニューモデル
手軽に雰囲気のあるおしゃれな写真が撮れるとして大人気のチェキシリーズ。その場ですぐにプリントされるので、日常使いはもちろん、パーティーシーンでも活躍します。撮影するシーンによって自動でシャッタースピードやフラッシュ光量が調整されるので、より明るくきれいな写真が撮れるようになります。
※各社通販サイトの 2024年10月03日時点 での税込価格
| フィルムサイズ | 20x30x13mm |
|---|---|
| 質量 | 約387g |
| 絞り | - |
| シャッタースピード | - |
| ISO感度 | - |
| 電源 | 電池式 |
| フィルムサイズ | 20x30x13mm |
|---|---|
| 質量 | 約387g |
| 絞り | - |
| シャッタースピード | - |
| ISO感度 | - |
| 電源 | 電池式 |
1番手軽にフィルムカメラを始めるならばこれ!
プラスティックレンズのゆるっとした輪郭と、フィルム独特の低コントラストな画質がデジタルにはないおしゃれな雰囲気を醸し出してくれます。ボディも軽く、細かい設定もいらないため、気軽にフィルム写真が楽しめます。
※各社通販サイトの 2024年10月03日時点 での税込価格
| フィルムサイズ | 35mm版 |
|---|---|
| 質量 | 90g |
| 絞り | F=10 |
| シャッタースピード | 1/140秒 |
| ISO感度 | ISO400 |
| 電源 | 内蔵使い切り(乾電池) |
| フィルムサイズ | 35mm版 |
|---|---|
| 質量 | 90g |
| 絞り | F=10 |
| シャッタースピード | 1/140秒 |
| ISO感度 | ISO400 |
| 電源 | 内蔵使い切り(乾電池) |
デジタルカメラの機能を搭載した小型軽量モデル
約1,000万画素のデジタルカメラの機能を内蔵した、インスタント写真も撮れるカメラです。液晶モニターはありませんが、撮影した画像をMicroSDカードを経由してPCなどに保存することもできます。クエアや長方形のフチなしに仕上げる撮影モードも搭載。
※各社通販サイトの 2024年10月03日時点 での税込価格
| フィルムサイズ | 5×7.6 cm |
|---|---|
| 質量 | 408g |
| 絞り | - |
| シャッタースピード | - |
| ISO感度 | - |
| 電源 | 充電式 |
| フィルムサイズ | 5×7.6 cm |
|---|---|
| 質量 | 408g |
| 絞り | - |
| シャッタースピード | - |
| ISO感度 | - |
| 電源 | 充電式 |
クラシックな新デザインのインスタントカメラ
撮ったその場で楽しめる!特徴的なシルバーフレームとレザー調の疾患がクラシックな、おしゃれなデザインです。「自動露光調整機能」が搭載されているので、特別な操作をしなくても、周りの明るさに応じて最適なシャッタースピードやフラッシュ光量になります。
レンズリングを引き出すだけでセルフィーモードに切替され、セルフショットミラー付で写る範囲も確認できるすぐれもの。
※各社通販サイトの 2024年10月03日時点 での税込価格
| フィルムサイズ | 富士フイルム インスタントフィルム instax mini |
|---|---|
| 質量 | 約330g |
| 絞り | - |
| シャッタースピード | 1/2~1/250秒 |
| ISO感度 | - |
| 電源 | 単3形アルカリ電池(LR6)2本 |
| フィルムサイズ | 富士フイルム インスタントフィルム instax mini |
|---|---|
| 質量 | 約330g |
| 絞り | - |
| シャッタースピード | 1/2~1/250秒 |
| ISO感度 | - |
| 電源 | 単3形アルカリ電池(LR6)2本 |
1コマに2枚の写真を撮影できる!
フィルム1本あたり2倍の画像数を撮影できるので、フィルムを節約できるモデルです。1コマの中に2コマ撮影できる設計で、36枚撮りのフィルムの場合は72枚のハーフフレーム写真が撮影可能。
軽くて小さいポケットサイズ。毎日持ち歩くのに便利です。フラッシュは、レンズ周りのシルバーリングを回転させてオン/オフを切り替えます。使い方がかんたんなので、フィルムカメラ初心者にもおすすめです。
※各社通販サイトの 2024年10月03日時点 での税込価格
| フィルムサイズ | 35mm(ハーフフレーム) |
|---|---|
| 質量 | 約120g |
| 絞り | 9.5 |
| シャッタースピード | 1/100秒 |
| ISO感度 | ‐ |
| 電源 | 単四アルカリ乾電池1個 |
| フィルムサイズ | 35mm(ハーフフレーム) |
|---|---|
| 質量 | 約120g |
| 絞り | 9.5 |
| シャッタースピード | 1/100秒 |
| ISO感度 | ‐ |
| 電源 | 単四アルカリ乾電池1個 |
「撮ること」に集中させた究極のM型ライカ
簡易的な露出計を内蔵していますが、撮影モードは完全マニュアル式。使い勝手のよさという点ではM-AよりもMPのほうでしょう。古くからのM型ライカの伝統をしっかりと受け継いで完成域にまで高めたカメラなので、M型ライカにあこがれていて、中古カメラはいやだという人には、このカメラが一押しです。
※各社通販サイトの 2024年10月5日時点 での税込価格
| フィルムサイズ | 35mm版 |
|---|---|
| 質量 | 約585g |
| 絞り | - |
| シャッタースピード | 1〜1/1000秒(1ステップ) 「B」:バルブ(無制限) フラッシュ同調速度:1/50秒 |
| ISO感度 | ISO6/9°〜6400/39°(マニュアル設定) |
| 電源 | 電池式 |
| フィルムサイズ | 35mm版 |
|---|---|
| 質量 | 約585g |
| 絞り | - |
| シャッタースピード | 1〜1/1000秒(1ステップ) 「B」:バルブ(無制限) フラッシュ同調速度:1/50秒 |
| ISO感度 | ISO6/9°〜6400/39°(マニュアル設定) |
| 電源 | 電池式 |
初心者でも使いやすいフィルムカメラ
露出やレンズなどを変えることはできませんが、フィルムを交換するだけですぐに撮影ができる使いやすいフィルムカメラです。汎用性の高い35mmフィルムに対応。レンズはF11・31mmで固定のため、複雑な設定なしでも雰囲気のある風景写真を残せます。
※各社通販サイトの 2024年10月5日時点 での税込価格
| フィルムサイズ | 35mm版 |
|---|---|
| 質量 | 77g |
| 絞り | - |
| シャッタースピード | 1/120 s |
| ISO感度 | 400 |
| 電源 | - |
| フィルムサイズ | 35mm版 |
|---|---|
| 質量 | 77g |
| 絞り | - |
| シャッタースピード | 1/120 s |
| ISO感度 | 400 |
| 電源 | - |
録音した音を「撮れる」新しいタイプのチェキ
スマホアプリを使って、録音した音声をQRコードとして写真と一緒に印刷、再生できるチェキ。スマホでの遠隔操作も可能で、便利な機能を豊富に搭載しています。一見デジタルカメラのように見えるおしゃれなデザインと本体が255gと軽量なので、いつでも持ち歩きたくなる一台です。
フィルムカメラだけど、モニターを見て撮影のやり直しが可能なのが魅力的。画像データ送信からフィルムが排出されるまで約12秒というのもポイントです。
※各社通販サイトの 2024年10月03日時点 での税込価格
| フィルムサイズ | 35mm版 |
|---|---|
| 質量 | 255g |
| 絞り | F2.0 |
| シャッタースピード | 1/4秒~1/8000秒(自動切換え) |
| ISO感度 | 100~1600(自動切換え) |
| 電源 | リチウムイオン電池(内蔵型:取り外し不可) |
| フィルムサイズ | 35mm版 |
|---|---|
| 質量 | 255g |
| 絞り | F2.0 |
| シャッタースピード | 1/4秒~1/8000秒(自動切換え) |
| ISO感度 | 100~1600(自動切換え) |
| 電源 | リチウムイオン電池(内蔵型:取り外し不可) |
60年の歴史をもつ、M型ライカの基本形
完全マニュアル・完全機械式のカメラで、カメラのオート撮影機能に頼りたくない、露出もピント合わせもカメラを操作してすべて自分で決めて写したいというマニュアル撮影にこだわりのある人におすすめのカメラです。
※各社通販サイトの 2024年10月03日時点 での税込価格
| フィルムサイズ | 35mm版 |
|---|---|
| 質量 | 約578g |
| 絞り | - |
| シャッタースピード | 1 〜 1/1000秒(1ステップ)、 「B」:バルブ(無制限) |
| ISO感度 | - |
| 電源 | - |
| フィルムサイズ | 35mm版 |
|---|---|
| 質量 | 約578g |
| 絞り | - |
| シャッタースピード | 1 〜 1/1000秒(1ステップ)、 「B」:バルブ(無制限) |
| ISO感度 | - |
| 電源 | - |
持ち運びしやすい片手で持てるサイズ感
細かな設定が必要なく、手軽に撮影をスタートできる初心者にも優しいコンパクトフィルムカメラ。デザインは懐かしいレトロ感で、カメラにはグリップが付いていてしっかり掴むことができ、安定した撮影ができます。
フィルム室にはセンサーがついており、対応フィルムだとフィルムに設けられた電気接点を読み取って自動的にISO感度を設定してくれます。なお、レンズから1.5m先までのものはピンボケするので注意してくださいね。
※各社通販サイトの 2024年10月03日時点 での税込価格
| フィルムサイズ | 35mm版 |
|---|---|
| 質量 | 約210g |
| 絞り | f3.8 |
| シャッタースピード | 1/125ss |
| ISO感度 | 400 |
| 電源 | ‐ |
| フィルムサイズ | 35mm版 |
|---|---|
| 質量 | 約210g |
| 絞り | f3.8 |
| シャッタースピード | 1/125ss |
| ISO感度 | 400 |
| 電源 | ‐ |
憧れライカのインスタントカメラ
高級カメラメーカー「LEICA(ライカ)」から発売されたインスタントカメラ『ゾフォート』です。他のライカのカメラ同様、ひと目でわかる赤い「LEICA」ロゴマークがボディ前面にプリントされています。フィルムは、ライカの『ライカ ゾフォート用フィルム』のほか、富士フイルムのチェキ用フィルム「INSTAX MINI」が使用できます。
※各社通販サイトの 2024年10月03日時点 での税込価格
| フィルムサイズ | ライカ ゾフォート用フィルム、instax mini |
|---|---|
| 質量 | 約305g |
| 絞り | - |
| シャッタースピード | - |
| ISO感度 | - |
| 電源 | 充電式 |
| フィルムサイズ | ライカ ゾフォート用フィルム、instax mini |
|---|---|
| 質量 | 約305g |
| 絞り | - |
| シャッタースピード | - |
| ISO感度 | - |
| 電源 | 充電式 |
簡単操作でフィルムカメラ初心者にもおすすめ
シャッターを押すだけのシンプル操作で、フィルムカメラを初めて使う方やお子さんでも安心して撮影を楽しめます。フィルムカメラならではのレトロで味のある写真が簡単に撮れますよ。フラッシュ内蔵なので、屋内や暗い場所の撮影も可能です。
※各社通販サイトの 2024年10月03日時点 での税込価格
| フィルムサイズ | 35mm版 |
|---|---|
| 質量 | 約100g |
| 絞り | F10 |
| シャッタースピード | 1/120秒 |
| ISO感度 | - |
| 電源 | 電池式 |
| フィルムサイズ | 35mm版 |
|---|---|
| 質量 | 約100g |
| 絞り | F10 |
| シャッタースピード | 1/120秒 |
| ISO感度 | - |
| 電源 | 電池式 |

真四角な画面が写せる中判カメラ
ブローニーフィルムを使用してスクエア画面(実画面サイズは56×56mm)が写せる中判フィルムカメラです。ブローニーフィルムとは35mmフィルムよりも大型サイズで120タイプともよびます。大きな画面で撮影ができますので大きく引き伸ばしプリントをつくってもフィルム粒状性が目立たないきめ細かな描写ができることが特長。
LC-A120にはMINIGON XL38mmF4.5レンズが内蔵されています。35mm判換算すると約21mm相当の超広角レンズです。深いピント幅を利用してピント合わせは4段階のゾーンフォーカス方式です。絞り値は2ステップ切り替え式の自動露出カメラで、カメラ上部にはホットシューアダプタがありますので外光式の一般ストロボが使用可能。シャッターボタンにはレリーズ穴があるのでケーブルレリーズ(付属)を使って低速シャッタースピード撮影もできます。
なお、ロモグラフィーには同じブローニーフィルムを使用する二眼レフタイプの中判カメラ「Lomo Lubitel 166+」もあります。ブローニー判カメラのファンはカメラ選びの参考にしてください。
※各社通販サイトの 2024年10月03日時点 での税込価格
| フィルムサイズ | 中判 |
|---|---|
| 質量 | - |
| 絞り | - |
| シャッタースピード | - |
| ISO感度 | - |
| 電源 | 電池式 |
| フィルムサイズ | 中判 |
|---|---|
| 質量 | - |
| 絞り | - |
| シャッタースピード | - |
| ISO感度 | - |
| 電源 | 電池式 |
※各社通販サイトの 2024年10月5日時点 での税込価格
| フィルムサイズ | 35mm |
|---|---|
| 質量 | - |
| 絞り | - |
| シャッタースピード | - |
| ISO感度 | - |
| 電源 | 電池式 |
| フィルムサイズ | 35mm |
|---|---|
| 質量 | - |
| 絞り | - |
| シャッタースピード | - |
| ISO感度 | - |
| 電源 | 電池式 |
【ランキング】通販サイトの最新人気! フィルムカメラの売れ筋をチェック
Amazon、楽天市場でのフィルムカメラの売れ筋ランキングも参考にしてみてください。
※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。
【おすすめフィルム】カメラと一緒に購入しよう
多くのメーカーがフィルム製造を撤退する中、価格を上げつつも作り続けているのがコダック。彩度やコントラストが高く、ややシャープに写るのが特徴。青色が強く発色するため、空や海など風景を撮る際に使いたいフィルムです。
青がきれいなフィルム
多くのメーカーがフィルム製造を撤退する中、価格を上げつつも作り続けているのがコダック。彩度やコントラストが高く、ややシャープに写るのが特徴。青色が強く発色するため、空や海など風景を撮る際に使いたいフィルムです。
※各社通販サイトの 2024年10月03日時点 での税込価格
| フィルムサイズ | 35mm版 |
|---|---|
| ISO感度 | ISO400 |
| フィルムサイズ | 35mm版 |
|---|---|
| ISO感度 | ISO400 |
発色の良さと高い粒状性が特徴のフィルムです。まるで映画のワンシーンのような、彩度とコントラストの高い描写が期待できます。やや高級な価格ですが、ちょっと特別な撮影時に使いたいフィルムです。
高彩度なコダックのブローニー版
発色の良さと高い粒状性が特徴のフィルムです。まるで映画のワンシーンのような、彩度とコントラストの高い描写が期待できます。やや高級な価格ですが、ちょっと特別な撮影時に使いたいフィルムです。
※各社通販サイトの 2024年10月03日時点 での税込価格
| フィルムサイズ | ブローニー版(中判) |
|---|---|
| ISO感度 | ISO100 |
| フィルムサイズ | ブローニー版(中判) |
|---|---|
| ISO感度 | ISO100 |
【Q&A】よくある質問


レンズやボディは必ず防湿庫の中で保管するようにしましょう。レンズはカビやホコリの混入を防ぐため、ボディはグリップ部分の加水分解をふせぐためです。また、ボディ内にもホコリは侵入します。定期的にブロワーで拭くなど掃除しましょう。


バルブモードとは、「長時間露光」のことを指します。フィルムカメラにはダイヤルに「B」と表記されたモードがあります。これがバルブモードです。バルブは、シャッタースピードをマニュアルにすることができる機能です。シャッターボタンを押した分だけシャッターを開いた状態にすることができるため、夜景や天体撮影、花火など極端に光量の少ない夜間撮影時に適しています。
ただし、実際の撮影では、非常に手ぶれがおきやすくなるため、あえて光の軌道や被写体の残像などを残すなどの意図がなければ、レリーズや三脚が必須となります。
フィルムカメラ初心者向けの書籍を紹介! フィルム装填もこれでOK
「フィルム写真を“いま"楽しむためのQ&A」がテーマの本書。
フィルムカメラの購入方法や楽しみ方をはじめ、プリント講座、写真展開催を目指す人のための疑問集、撮影に役立つ基礎知識など、フィルムに関する内容を幅広く紹介しています。
作例も掲載されているため、フィルム初心者からベテラン愛好家まで、多くのフィルムカメラ好きに向けた1冊です。
【関連記事】ほかのカメラをチェック
【まとめ】フィルムカメラ選びに困ったときは 写真家・カメラ評論家からのアドバイス
フィルムの取扱にはご注意を
言うまでもありませんが、フィルムはほんのわずかな「光」を受けても感光して使いものにならなくなります。明るい日中、カメラにフィルムを装填するときはじゅうぶんに注意したいものです。
フィルムは高温多湿を嫌います。生もの、生鮮食料品と同じように取り扱いには注意してください。フィルムには「使用期限」があり、フィルムパッケージに必ず記載されています。フィルムを購入するときは使用期限をチェックしておくことが大切。一度、光を受けたフィルムはじわじわと化学変化が進みます。撮影したフィルムはできるだけ早く現像処理をして仕上げましょう。
現像を終えたネガフィルムは直射日光を受けない、湿気のないところに大切に保存しておきましょう。
フィルムカメラ初心者向けの入門書
はじめてフィルムカメラを始めたい人に向けた入門書です。
「フィルムカメラをはじめたいけど難しそう」「『写ルンです』からステップアップしたい」という方に向けて、コラムを交えながらフィルムカメラの機種選びから使い方までを解説。誌面には、QRコードの動画リンクが掲載されており、スマートフォンやPCで、動画を観ながらフィルムの入れ方やカメラの操作方法を学べます。
※各社通販サイトの 2024年10月03日時点 での税込価格
フィルムに関するO&Aを紹介!
「フィルム写真を“いま"楽しむためのQ&A」がテーマの本書。
フィルムカメラの購入方法や楽しみ方をはじめ、プリント講座、写真展開催を目指す人のための疑問集、撮影に役立つ基礎知識など、フィルムに関する内容を幅広く紹介しています。
作例も掲載されているため、フィルム初心者からベテラン愛好家まで、多くのフィルムカメラ好きに向けた1冊です。
※各社通販サイトの 2024年10月03日時点 での税込価格
「フィルムカメラ」のおすすめ商品の比較一覧表
| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | フィルムサイズ | 質量 | 絞り | シャッタースピード | ISO感度 | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUJIFILM(富士フイルム)『instax mini 12』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月03日時点 での税込価格 |
スタンダードなチェキの最新作 | 86×54mm | 306g | - | 1/2~1/250 秒 | - | 単三乾電池 |
| FUJIFILM(富士フイルム)『インスタントカメラ チェキ instax mini 11』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月03日時点 での税込価格 |
その場でプリント!チェキカメラのニューモデル | 20x30x13mm | 約387g | - | - | - | 電池式 |
| FUJIFILM (富士フイルム)『写ルンです シンプルエース 27枚撮り』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月03日時点 での税込価格 |
1番手軽にフィルムカメラを始めるならばこれ! | 35mm版 | 90g | F=10 | 1/140秒 | ISO400 | 内蔵使い切り(乾電池) |
| Polaroid(ポラロイド)『Polaroid Snap デジタルインスタントカメラ』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月03日時点 での税込価格 |
デジタルカメラの機能を搭載した小型軽量モデル | 5×7.6 cm | 408g | - | - | - | 充電式 |
| FUJIFILM (富士フイルム)『instax mini 40 INS MINI 40』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月03日時点 での税込価格 |
クラシックな新デザインのインスタントカメラ | 富士フイルム インスタントフィルム instax mini | 約330g | - | 1/2~1/250秒 | - | 単3形アルカリ電池(LR6)2本 |
| Kodak(コダック)『KODAK EKTAR H35ハーフフレームフィルムカメラ(EKTAR H35)』 |
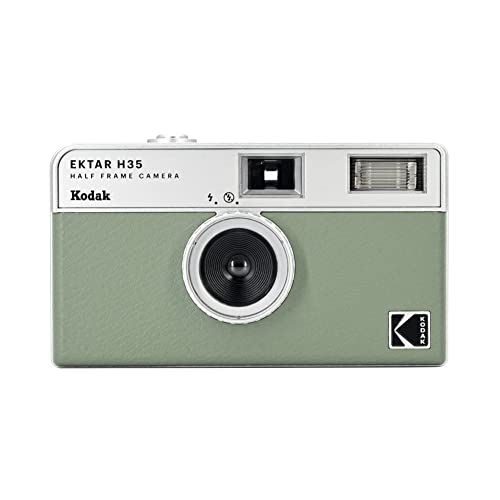
|
※各社通販サイトの 2024年10月03日時点 での税込価格 |
1コマに2枚の写真を撮影できる! | 35mm(ハーフフレーム) | 約120g | 9.5 | 1/100秒 | ‐ | 単四アルカリ乾電池1個 |
| Leica(ライカ)『ライカ MP』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月5日時点 での税込価格 |
「撮ること」に集中させた究極のM型ライカ | 35mm版 | 約585g | - | 1〜1/1000秒(1ステップ) 「B」:バルブ(無制限) フラッシュ同調速度:1/50秒 | ISO6/9°〜6400/39°(マニュアル設定) | 電池式 |
| YASHICA(ヤシカ)『MF-1』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月5日時点 での税込価格 |
水陸両方の撮影も可能な簡易カメラ | 35mm版 | 77g | - | 1/120 s | 400 | - |
| FUJIFILM (富士フイルム)『instax mini LiPlay』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月03日時点 での税込価格 |
録音した音を「撮れる」新しいタイプのチェキ | 35mm版 | 255g | F2.0 | 1/4秒~1/8000秒(自動切換え) | 100~1600(自動切換え) | リチウムイオン電池(内蔵型:取り外し不可) |
| Leica(ライカ)『ライカ M-A(Typ127)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月03日時点 での税込価格 |
60年の歴史をもつ、M型ライカの基本形 | 35mm版 | 約578g | - | 1 〜 1/1000秒(1ステップ)、 「B」:バルブ(無制限) | - | - |
| YASHICA(ヤシカ)『MF-2 super』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月03日時点 での税込価格 |
持ち運びしやすい片手で持てるサイズ感 | 35mm版 | 約210g | f3.8 | 1/125ss | 400 | ‐ |
| Leica(ライカ)『ゾフォート』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月03日時点 での税込価格 |
憧れライカのインスタントカメラ | ライカ ゾフォート用フィルム、instax mini | 約305g | - | - | - | 充電式 |
| Kodak(コダック)『フィルムカメラM35』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月03日時点 での税込価格 |
簡単操作でフィルムカメラ初心者にもおすすめ | 35mm版 | 約100g | F10 | 1/120秒 | - | 電池式 |
| Lomography『Lomo LC-A 120』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月03日時点 での税込価格 |
真四角な画面が写せる中判カメラ | 中判 | - | - | - | - | 電池式 |
| Nikon(ニコン)『Nikon FM2/T 』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月5日時点 での税込価格 |
35mm | - | - | - | - | 電池式 |
◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。








































































































































