| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | アラーム音量 | 電池 | 鳴らし方のタイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソニック『 防犯ブザー ピブート リアナティアラ バイオレット GS-147RT-V』 |

|
※各社通販サイトの 2025年6月16日時点 での税込価格 |
ハート型がかわいい! 女の子向け防犯ブザー | 93db | 単4形 | 紐を引くタイプ |
| ソニック 『防犯ブザー ピブート ブレイブ コンパクト レッド GS-120BR-R』 |

|
※各社通販サイトの 2025年06月10日時点 での税込価格 |
かっこいいデザインで男の子におすすめ! | 91db | コイン型リチウム電池(CR2032) | 紐を引くタイプ |
| リヒトラブ『防犯ブザー A-7718』 |

|
※各社通販サイトの 2025年06月10日時点 での税込価格 |
かわいい動物のイラスト入りで低学年の子におすすめ | 85db | 単4形 | 紐を引くタイプ |
| アスカ『防犯ブザー LEDライトつき GE069B』 |

|
※各社通販サイトの 2025年06月10日時点 での税込価格 |
ストラップが長めなので緊急時もひっぱりやすい | 88db | コイン型リチウム電池(CR2032) | 紐を引くタイプ |
| アスカ『 プリンセス防犯ブザー ショコラ GE076』 |

|
※各社通販サイトの 2025年06月10日時点 での税込価格 |
防犯ブザーに見えないおしゃれなチョコレート型 | 89db | コイン型リチウム電池(CR2032または同規格のもの) | ピンを引くタイプ |
| クツワ『プーマ 防犯アラーム PM317BK』 |

|
※各社通販サイトの 2025年06月10日時点 での税込価格 |
防水機能にすぐれているので濡れても安心! | 90db | 単4形 | ピンを引くタイプ |
| レイメイ藤井『防犯ブザー EBB257B』 |

|
※各社通販サイトの 2025年06月10日時点 での税込価格 |
充電式タイプなので長時間稼働可能で緊急時も安心 | 97db | 不要(充電式) | ボタンを押すタイプ |
小学生向けの防犯ブザーの選び方
防犯ブザーは緊急時、恐怖で大きな声が出せなくなってしまったときも、ピンを引き抜くなどのかんたんな操作方法で大音量のブザー音を出すことができます。
ここでは防犯ブザーの選び方をポイントごとに紹介するので購入時の参考にしてくださいね。
防犯ブザーの音量は85dB以上
防犯ブザーの音は遠くでも気づきやすい高めの音が鳴るようになっています。音量はデシベル(db)であらわされ、数字が大きければ大きいほど大音量が出ることをあらわしています。
警視庁が定めている防犯ブザーの性能基準は、85db以上の音量が出るもの。さらに大音量の100db以上のものもあるので、音量の数値をチェックしてから購入するようにしましょう。

体験談
ブザーの音量は大きければ大きいほど安心!
小学校の入学準備品のなかに防犯ブザーが含まれていたので購入することに。緊急時はとにかく遠くの人にもブザー音が聞こえたほうがいいと思ったので、大音量のブザー音が鳴るものを選びました。
ブザー音が大きい分、誤作動を起こしたときに周囲の人を驚かせてしまう可能性も高いため、誤作動防止の機能がついているかどうかも確認してから購入するようにしました。(Uさん/8歳女の子)
鳴らし方の種類で選ぶ
防犯ブザーの鳴らし方はおもに、「ピンを引くタイプ」「ボタンを押すタイプ」「紐を引くタイプ」の3タイプとなっています。緊急時にどの方法であればブザー音を鳴らしやすいか、子どもと相談してから購入するとよいですね。

体験談
入学時の小さい手でも引きやすいリングつきを購入
小学校に入学するときはまだ子どもの手も小さめでした。防犯ブザーは恐怖のなかでも確実に紐やリングを引っ張って音を出さないといけないため、小さい手でも引きやすい紐がついている商品を検索しました。
商品を検索していると、紐にリングがついているものがあり「これなら小さい手でも引っ張りやすいかも」と購入してみました。なにかが起こったとき、通常では考えられない思考や行動を起こしてしまうものです。緊急時のことを想定して使いやすいものを選ぶことをおすすめします。(Eさん/10歳男の子)
誤作動防止機能や防水機能、ライトつきなども便利
防犯ブザーを緊急時以外に鳴らしてしまうと、周囲の人を驚かせてしまうきっかけにもなります。子どもがなにかの拍子に紐やピンを引っ張ってしまったりボタンを押してしまったりしたときに、ブザー音が鳴ってしまう誤作動を防止する機能がついているものを選ぶようにしましょう。
そのほか、雨に濡れても安心な防水機能がついているもの、暗い道を歩く際などに足元などを明るく照らすことができるライトつきのものを選ぶのもおすすめです。

体験談
キャラクターものだとよろこんでつけてくれる
通信教育の付録でもらったキャラクターの防犯ブザーをつけていました。入学時に学校で配布されたシンプルなものもありましたが、子どもはキャラクターのイラストが描かれている防犯ブザーをつけたがりました。
子どもにとっては防犯の意識で防犯ブザーをつける感覚が大人よりも薄いようです。キーホルダー感覚でつけられるキャラクターものの防犯ブザーを選ぶこともひとつの方法かなと実感しました。(Iさん/7歳女の子)
小学生向けの防犯ブザーおすすめ7選
小学生向けの防犯ブザーを8選集めました。それぞれの機能やタイプを比較して、購入時の参考にしてくださいね。
ハート型がかわいい! 女の子向け防犯ブザー
◆ピンを紐で引っ張るタイプでピンが抜けきらないので紛失しない
◆固定ベルトと金属フックの両方を使用してランドセルにつけられるので落ちにくい
◆生活防水設計で雨の日も安心! 丈夫で軽い!
※各社通販サイトの 2025年6月16日時点 での税込価格
| アラーム音量 | 93db |
|---|---|
| 電池 | 単4形 |
| 鳴らし方のタイプ | 紐を引くタイプ |
| アラーム音量 | 93db |
|---|---|
| 電池 | 単4形 |
| 鳴らし方のタイプ | 紐を引くタイプ |
かっこいいデザインで男の子におすすめ!
◆ベルト、電池を含んでも総重量約33gなので軽い
◆雨に濡れても安心な生活防水設計
◆緊急時、慌てていても引っ張りやすい大きめのリングが特徴
※各社通販サイトの 2025年06月10日時点 での税込価格
| アラーム音量 | 91db |
|---|---|
| 電池 | コイン型リチウム電池(CR2032) |
| 鳴らし方のタイプ | 紐を引くタイプ |
| アラーム音量 | 91db |
|---|---|
| 電池 | コイン型リチウム電池(CR2032) |
| 鳴らし方のタイプ | 紐を引くタイプ |
かわいい動物のイラスト入りで低学年の子におすすめ
◆さまざまな動物キャラクターのイラストがあり選べる
◆ブザーピンを下に引くだけなので操作もかんたん
◆単4電池使用で長持ちする
※各社通販サイトの 2025年06月10日時点 での税込価格
| アラーム音量 | 85db |
|---|---|
| 電池 | 単4形 |
| 鳴らし方のタイプ | 紐を引くタイプ |
| アラーム音量 | 85db |
|---|---|
| 電池 | 単4形 |
| 鳴らし方のタイプ | 紐を引くタイプ |
ストラップが長めなので緊急時もひっぱりやすい
◆LEDライトつきでブザー音と同時にLEDライトが点滅するからどこで鳴っているかがわかりやすい
◆ミニサイズでランドセルにつけても邪魔にならない
◆値段が比較的リーズナブルでお財布に優しい
※各社通販サイトの 2025年06月10日時点 での税込価格
| アラーム音量 | 88db |
|---|---|
| 電池 | コイン型リチウム電池(CR2032) |
| 鳴らし方のタイプ | 紐を引くタイプ |
| アラーム音量 | 88db |
|---|---|
| 電池 | コイン型リチウム電池(CR2032) |
| 鳴らし方のタイプ | 紐を引くタイプ |
防犯ブザーに見えないおしゃれなチョコレート型
◆ピンが抜けないタイプだからピンがなくならない
◆誤作動防止スイッチつきで安心
◆電池フタはネジつきなので、小さい子がご家庭にいてもボタン電池誤飲の心配なし
※各社通販サイトの 2025年06月10日時点 での税込価格
| アラーム音量 | 89db |
|---|---|
| 電池 | コイン型リチウム電池(CR2032または同規格のもの) |
| 鳴らし方のタイプ | ピンを引くタイプ |
| アラーム音量 | 89db |
|---|---|
| 電池 | コイン型リチウム電池(CR2032または同規格のもの) |
| 鳴らし方のタイプ | ピンを引くタイプ |
防水機能にすぐれているので濡れても安心!
◆男の子に人気のPUMAのデザイン入りでスタイリッシュ
◆笛つきなので万が一電池が切れていても緊急時危険を知らせることが可能
◆ブザーは長い時間大音量で鳴り響く
※各社通販サイトの 2025年06月10日時点 での税込価格
| アラーム音量 | 90db |
|---|---|
| 電池 | 単4形 |
| 鳴らし方のタイプ | ピンを引くタイプ |
| アラーム音量 | 90db |
|---|---|
| 電池 | 単4形 |
| 鳴らし方のタイプ | ピンを引くタイプ |
充電式タイプなので長時間稼働可能で緊急時も安心
◆3種類の点灯タイプが選べる安全ライトつきで、暗い夜道を歩くときに使える
◆USBプラグ一体型構造なので専用ケーブルなしで充電できる
◆防水防塵機能つきで災害時にも使用できる
※各社通販サイトの 2025年06月10日時点 での税込価格
| アラーム音量 | 97db |
|---|---|
| 電池 | 不要(充電式) |
| 鳴らし方のタイプ | ボタンを押すタイプ |
| アラーム音量 | 97db |
|---|---|
| 電池 | 不要(充電式) |
| 鳴らし方のタイプ | ボタンを押すタイプ |
「防犯ブザー」のおすすめ商品の比較一覧表
| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | アラーム音量 | 電池 | 鳴らし方のタイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソニック『 防犯ブザー ピブート リアナティアラ バイオレット GS-147RT-V』 |

|
※各社通販サイトの 2025年6月16日時点 での税込価格 |
ハート型がかわいい! 女の子向け防犯ブザー | 93db | 単4形 | 紐を引くタイプ |
| ソニック 『防犯ブザー ピブート ブレイブ コンパクト レッド GS-120BR-R』 |

|
※各社通販サイトの 2025年06月10日時点 での税込価格 |
かっこいいデザインで男の子におすすめ! | 91db | コイン型リチウム電池(CR2032) | 紐を引くタイプ |
| リヒトラブ『防犯ブザー A-7718』 |

|
※各社通販サイトの 2025年06月10日時点 での税込価格 |
かわいい動物のイラスト入りで低学年の子におすすめ | 85db | 単4形 | 紐を引くタイプ |
| アスカ『防犯ブザー LEDライトつき GE069B』 |

|
※各社通販サイトの 2025年06月10日時点 での税込価格 |
ストラップが長めなので緊急時もひっぱりやすい | 88db | コイン型リチウム電池(CR2032) | 紐を引くタイプ |
| アスカ『 プリンセス防犯ブザー ショコラ GE076』 |

|
※各社通販サイトの 2025年06月10日時点 での税込価格 |
防犯ブザーに見えないおしゃれなチョコレート型 | 89db | コイン型リチウム電池(CR2032または同規格のもの) | ピンを引くタイプ |
| クツワ『プーマ 防犯アラーム PM317BK』 |

|
※各社通販サイトの 2025年06月10日時点 での税込価格 |
防水機能にすぐれているので濡れても安心! | 90db | 単4形 | ピンを引くタイプ |
| レイメイ藤井『防犯ブザー EBB257B』 |

|
※各社通販サイトの 2025年06月10日時点 での税込価格 |
充電式タイプなので長時間稼働可能で緊急時も安心 | 97db | 不要(充電式) | ボタンを押すタイプ |
通販サイトの最新人気ランキングを参考にする 防犯ブザーの売れ筋をチェック
楽天市場での防犯ブザーの売れ筋ランキングも参考にしてみてください。
※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。
小学生に持たせる防犯ブザーのQ&A
防犯ブザーの使用方法についての疑問を紹介します。


防犯ブザーの鳴らし方はおもに3とおりあります。
◆ピンを引くタイプは、ピンを引き抜いたあと再度ピンを差し込むまでブザーが鳴りつづけるのが特徴です。防犯ブザーを鳴らすと犯人はブザー音を消そうとするかもしれません。ピンを差し込めないよう、防犯ブザーを遠くに投げてしまうことで犯人の気をそらすことも可能です。
◆ボタンを押すタイプは、ボタンを押している間のみブザー音がなります。ボタンを押すだけのかんたん操作で子どもも扱いやすく、音を出す、止めるを自分で操作できる点がポイントです。
◆紐を引くタイプはランドセルの肩ベルト部分に取り付けやすく、紐を引っ張るだけでブザーが鳴るため子どもでもかんたんに音を出すことができます。紐になにかが引っ掛かった拍子にも抜けやすく、誤作動を起こしやすいため注意が必要です。


不審者などは必ずしも見た目が怪しいとは限りません。子どもへの声掛けは巧妙化しており、「もしかしたら悪い人ではないかもしれない」などと考えていると防犯ブザーを鳴らすきっかけを見失ってしまいます。子どもには少しでも「おかしいな」と感じたら防犯ブザーを鳴らすように伝えておくとようでしょう。

体験談
オオカミ少年の話をして使い方を教えるのがおすすめ
学校までの距離が遠いので、子どもには「誰かに連れていかれそうになったとき」「ケガをして誰かの助けを呼びたいとき」などに躊躇なく防犯ブザーを鳴らすように伝えました。一度鳴らしてみたいというので試しに鳴らしてみると、あまりに大きい音で驚いたようでした。
「何度もふざけて鳴らすと、オオカミ少年みたいに本当に助けてほしい時に助けてもらえなくなるから鳴らさないでね」と約束しました。ちょうどオオカミ少年の話をした後だったので、子どももしっくりきていました。(Мさん/8歳女の子、1歳男の子)

体験談
怪我をしたときなどの緊急事態のときも鳴らすように
防犯ブザーは不審者などに遭遇したときに鳴らすものという認識は、教える前からあったようです。私は不審者に遭遇したとき以外にも、怪我をしてしまって動けなくなってしまったときや、一緒に登下校しているお友達になにかあったときも防犯ブザーを鳴らしてよいことを子どもに伝えました。
いざというときに使い方がわからなくて使用できなかった、ということを防ぐために防犯ブザーを購入したら、家のなかなどのまわりに迷惑をかけない場所などでブザーを鳴らす練習をしておくことをおすすめします。(Aさん/9歳女の子)


ランドセルの肩ベルトに取り付けることをおすすめします。肩ベルトに防犯ブザーをつけることで、すぐに手が届くので防犯ブザーを鳴らしやすくなります。
【関連記事】小学生の安全対策に!
子どものいざというときに守る防犯ブザーは必需品
小学校向けの防犯ブザーを紹介しました。緊急時に適切に防犯ブザーを使用できるよう、日ごろから親子で防犯ブザーの使い方を習得しておくようにしましょう。さまざまな状況の予測をしながら練習しておくと、使い方が身につきやすいのでおすすめです。
◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。


































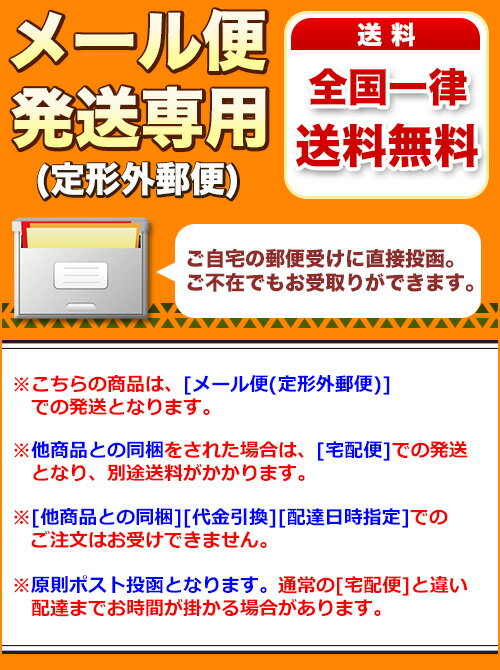


「ベビー・キッズ」「食品・ドリンク」カテゴリー担当。1児のママ編集者。育児と家事に忙しいママ目線での時短グッズ選び、家族の栄養とおいしさを考えた食品選び、束の間のリラックスタイムを楽しむためのスイーツ選びにに自信あり。鋭い目線で商品を見極め、少しでも日々の生活が豊かになるものを紹介します。