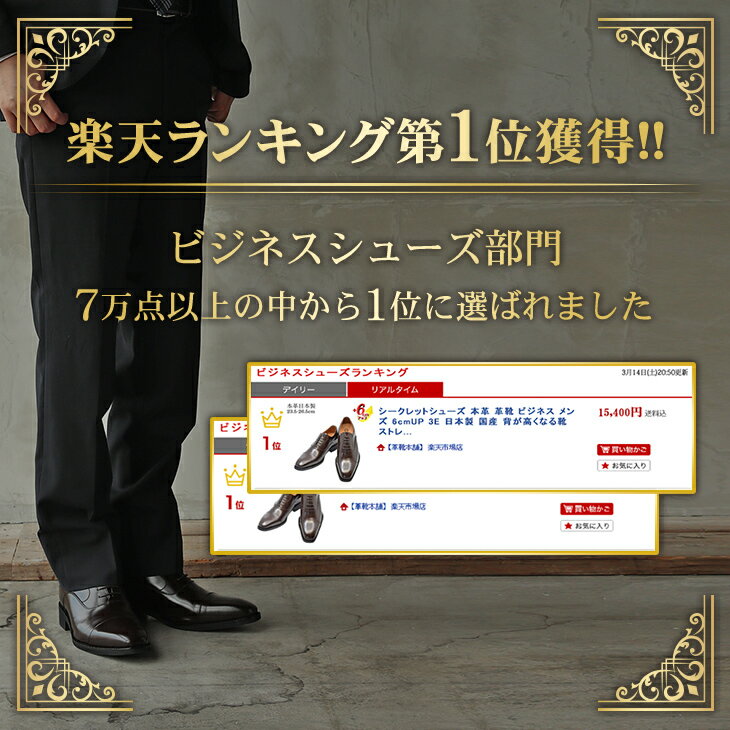| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | サイズ展開 | 身長アップ | 素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北嶋製靴工業所『6cmアップ モンクストラップ 』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月10日時点 での税込価格 |
大人らしいおしゃれを演出するシューズ | 23.5~26.5cm | 6cm | アッパー:牛革、靴底:合成ゴム |
| HAVILAH MODE『シークレットシューズ』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月10日時点 での税込価格 |
ビジネスシーンにぴったりのシークレットシューズ | 23.0~27.0cm | 7cm | アッパー:合成皮革 |
| CLOUD 9『シークレットシューズ』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月10日時点 での税込価格 |
エナメルとマットから選べるテクスチャー | 24.0~27.5cm | 7cm | アッパー:合成皮革、靴底:ゴム |
| 北嶋製靴工業所『6cmアップ 内羽根ストレートチップ』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月10日時点 での税込価格 |
牛革を使用した本格的なシークレットシューズ | 23.5~26.5cm | 6cm | アッパー:牛革、靴底:合成ゴム |
| マドラス×TALLSHOES『モデロ シークレットシューズ』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月10日時点 での税込価格 |
伝統的なフォルムが美しいシークレットシューズ | 23.5~27.0cm | 5cm | アッパー:牛革、靴底:合成ゴム |
| マドラス『モデロ segretaシリーズ 外羽根ストレートチップ・ドレススシューズ』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月10日時点 での税込価格 |
エナメルの光沢が美しいシューズ | 23.0~27.0cm | 6cm | アッパー:本革、靴底:合成ゴム |
| TALLSHOES『OMS-PLUB(シークレット メンズ ビジネスシューズ)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月10日時点 での税込価格 |
豊富なデザインが魅力! 底の高さは4cmから | 23.5~27.0cm | 4cm | アッパー:牛革、靴底:合成ゴム |
| Cartoden『シークレット スニーカー』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月10日時点 での税込価格 |
最大10cm! 3種類の高さから選べる | 23.5~26.5cm | 6cm、8cm、10cm | アッパー:合成繊維、靴底:ゴム |
| ziitop『シークレットスニーカー』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月10日時点 での税込価格 |
革靴っぽいスニーカーで高級感も◎ | 23.0~27.5cm | 6cm | アッパー:PU、靴底:ゴム |
| MY SELECTED『シークレットファッションスニーカー』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月10日時点 での税込価格 |
軽量で履きやすいカジュアルなシューズ | 23.5~26.5cm | 5~6cm | アッパー:PU、靴底:ゴム |
| オーナイン(O-NINE)『シークレットシューズ』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月10日時点 での税込価格 |
スエード風のアッパーがおしゃれなシューズ | 24.5~28.0cm | 6.5cm | アッパー:合成皮革、靴底:ゴム |
| TONDEMON『シークレット スニーカー』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月10日時点 での税込価格 |
足元にボリュームを持たせたデザイン | 23.0~28.5cm | 6cm、8cm、10cm | アッパー:合成繊維、靴底:ゴム |
シークレットシューズの選び方 バレない商品の選び方とは?
シークレットシューズの選び方を解説していきます。選び方のポイントは下記。
【1】歩きやすい高さ
【2】シーンに合わせたデザイン
【3】サイズの選び方
上記のポイントをおさえることで、よりほしい商品をみつけることができます。一つひとつ解説していきます。
【1】歩きやすさを考慮した高さを選ぶ
シークレットシューズなので底の高さがもちろん大切になってきますが、高すぎると歩きづらくなります。底が4cm前後であればスポーツ用のシューズにもある高さなので、違和感なく歩けるでしょう。
まずは低いものから履いてみて徐々にステップアップしていくと、底が高い靴にも慣れることができます。上げ底が高い靴を選ぶときは、つま先側も高くなっているものを選ぶと歩きやすくなります。かかと側のみが高くなっていると歩く際に違和感を覚え、つまずきやすくなるので注意しましょう。
【2】シーンに合ったデザインを選ぶ
シーンに合わせた靴選びも大切。ビジネスシーンでは革靴タイプなど落ち着いたシークレットシューズを、プライベートではカジュアルなシークレットシューズなど、状況に合ったデザインのものを履きましょう。
ドレスアップされたシークレットシューズもあるので、イベントなどにはそうしたシークレットシューズを選ぶといいですよ。
【3】サイズの選び方も要チェック
シークレットシューズは、靴のタイプに応じてサイズを見極めることが肝心です。ビジネスシューズには、つま先部分に「捨て寸」とよばれるゆとりが設けてあります。ビジネスシューズの場合は、ふだん通りのサイズを試してみましょう。
一方、余裕寸法のないスニーカーの場合、いつものサイズだと窮屈で小さいと感じる可能性があります。スニーカーは「実際の足のサイズ+1~1.5cm」を目安に選ぶとよいでしょう。
シークレットシューズおすすめ|ビジネスシューズ
それではさっそくシークレットシューズのおすすめ商品をご紹介します。使用するシーンに合わせて選べるよう「ビジネスシューズ」と「スニーカー」にわけて紹介していくのでぜひチェックしてみてくださいね。

大人らしいおしゃれを演出するシューズ
デザイン性と履き心地の両方を追求した北嶋製靴工業所のシークレットシューズです。モンクストラップデザインが、大人らしいおしゃれをかなえてくれます。
足が前滑りしにくい立体カップのインヒールを採用。長時間履いても疲れにくいクッション入り。ベルトの下に隠しゴムがついているので、脱ぎ履きがしやすいのもうれしいポイントです。
※各社通販サイトの 2025年3月10日時点 での税込価格
| サイズ展開 | 23.5~26.5cm |
|---|---|
| 身長アップ | 6cm |
| 素材 | アッパー:牛革、靴底:合成ゴム |
| サイズ展開 | 23.5~26.5cm |
|---|---|
| 身長アップ | 6cm |
| 素材 | アッパー:牛革、靴底:合成ゴム |
ビジネスシーンにぴったりのシークレットシューズ
名古屋のオーダースーツ専門店のシークレットシューズ。上品な印象を与えてくれるデザインで、スーツスタイルに合わせやすいアイテムです。合皮は本革と比べて水に強く、ふだん使いしやすいのもうれしいポイント。
比較的手ごろな価格なので、はじめてのシークレットシューズにもおすすめです。ビジネスシーンをスマートに演出したい方はぜひ検討してみてください。
※各社通販サイトの 2025年3月10日時点 での税込価格
| サイズ展開 | 23.0~27.0cm |
|---|---|
| 身長アップ | 7cm |
| 素材 | アッパー:合成皮革 |
| サイズ展開 | 23.0~27.0cm |
|---|---|
| 身長アップ | 7cm |
| 素材 | アッパー:合成皮革 |
エナメルとマットから選べるテクスチャー
おしゃれな足元を演出できるシークレットシューズです。レースアップなので主張しすぎず、自然に履けますよ。シーンを選ばないデザインなので、ビジネスだけでなくフォーマルな場面にも使いやすいでしょう。
ヒールは7cmと高めで、シューズを履くだけでスタイルアップ。テクスチャーはマットとエナメルから選べるので、自分のファッションスタイルに合わせて選んでくださいね。
※各社通販サイトの 2025年3月10日時点 での税込価格
| サイズ展開 | 24.0~27.5cm |
|---|---|
| 身長アップ | 7cm |
| 素材 | アッパー:合成皮革、靴底:ゴム |
| サイズ展開 | 24.0~27.5cm |
|---|---|
| 身長アップ | 7cm |
| 素材 | アッパー:合成皮革、靴底:ゴム |
牛革を使用した本格的なシークレットシューズ
創業50年以上の国内シューズメーカー、北嶋製靴工業所が手がけるシークレットシューズです。甲材は牛革、内張は豚革を使用した高級感のあるシューズで、ビジネスシーンにもふさわしいです。
また、立体的な作りの中敷きにより、前のめりになる感覚が少なく、長時間履いても疲れにくいのが特徴。デザイン性、履き心地、自然な身長アップを兼ね備えた、優秀な一足です。
※各社通販サイトの 2025年3月10日時点 での税込価格
| サイズ展開 | 23.5~26.5cm |
|---|---|
| 身長アップ | 6cm |
| 素材 | アッパー:牛革、靴底:合成ゴム |
| サイズ展開 | 23.5~26.5cm |
|---|---|
| 身長アップ | 6cm |
| 素材 | アッパー:牛革、靴底:合成ゴム |
伝統的なフォルムが美しいシークレットシューズ
イタリアのシューズブランド、マドラスとコラボして作られたシークレットシューズです。ヒールは5cmなので、さりげなく身長アップしたい方におすすめです。
本革製なのにスニーカーのようなやわらかな履き心地。伝統的なフォルムなので、ビジネスシーンだけでなく、冠婚葬祭にも合わせることができますよ。
※各社通販サイトの 2025年3月10日時点 での税込価格
| サイズ展開 | 23.5~27.0cm |
|---|---|
| 身長アップ | 5cm |
| 素材 | アッパー:牛革、靴底:合成ゴム |
| サイズ展開 | 23.5~27.0cm |
|---|---|
| 身長アップ | 5cm |
| 素材 | アッパー:牛革、靴底:合成ゴム |
エナメルの光沢が美しいシューズ
足元のおしゃれをしたい方にぴったりの本革シークレットシューズです。エナメルの光沢が美しく、パーティーなどの華やかな場にも使いやすいデザインに仕上がっています。脱いだときには真紅のライニングがよく映え、上品な印象を与えるデザインです。
さりげなく6cmのヒールアップを実現。素材は本革を使用しているので、履き続けるほどに足になじみ、味が出てきます。
※各社通販サイトの 2025年3月10日時点 での税込価格
| サイズ展開 | 23.0~27.0cm |
|---|---|
| 身長アップ | 6cm |
| 素材 | アッパー:本革、靴底:合成ゴム |
| サイズ展開 | 23.0~27.0cm |
|---|---|
| 身長アップ | 6cm |
| 素材 | アッパー:本革、靴底:合成ゴム |
豊富なデザインが魅力! 底の高さは4cmから
自然な身長アップを叶える、セミオーダーのシークレットシューズです。底の高さは4cmと比較的低めで履きやすく、はじめてシークレットシューズに挑戦する方にもおすすめ。
デザインのバリエーションは14種類もあり、コーディネートに合うものを見つけやすいでしょう。また、同シリーズは底の高さが4~13cmまでそろっており、自分好みの一足を探しやすくなっています。靴選びに妥協したくない方は要チェックのアイテムです。
※各社通販サイトの 2025年3月10日時点 での税込価格
| サイズ展開 | 23.5~27.0cm |
|---|---|
| 身長アップ | 4cm |
| 素材 | アッパー:牛革、靴底:合成ゴム |
| サイズ展開 | 23.5~27.0cm |
|---|---|
| 身長アップ | 4cm |
| 素材 | アッパー:牛革、靴底:合成ゴム |
シークレットシューズおすすめ|スニーカー
つづいては、カジュアルコーデに合うシークレットスニーカーをご紹介します。

最大10cm! 3種類の高さから選べる
スポーティーなデザインで、カジュアルなコーディネートに合わせやすいシークレットスニーカー。ヒールの高さは6・8・10cmの3種類がラインアップされており、自然に身長アップできます。
通気性があるので、蒸れにくく快適に履けます。歩いて汗をかいても不快になりにくいので、通学などにも使いやすいでしょう。
※各社通販サイトの 2025年3月10日時点 での税込価格
| サイズ展開 | 23.5~26.5cm |
|---|---|
| 身長アップ | 6cm、8cm、10cm |
| 素材 | アッパー:合成繊維、靴底:ゴム |
| サイズ展開 | 23.5~26.5cm |
|---|---|
| 身長アップ | 6cm、8cm、10cm |
| 素材 | アッパー:合成繊維、靴底:ゴム |
革靴っぽいスニーカーで高級感も◎
スマートなデザインのシークレットシューズです。柔軟性と屈曲性があり、軽量なので、歩きやすく疲れにくいのが特徴。レザーで仕上げているため、カジュアルなデザインながらも上品さがあります。デートでも使いやすいアイテムです。
靴底には滑り止め加工が施してあるので、路面が濡れている日なども安心して履くことができます。
※各社通販サイトの 2025年3月10日時点 での税込価格
| サイズ展開 | 23.0~27.5cm |
|---|---|
| 身長アップ | 6cm |
| 素材 | アッパー:PU、靴底:ゴム |
| サイズ展開 | 23.0~27.5cm |
|---|---|
| 身長アップ | 6cm |
| 素材 | アッパー:PU、靴底:ゴム |
軽量で履きやすいカジュアルなシューズ
カジュアルなデザインのシークレットシューズです。4色のカラーバリエーションがあるので、自分のファッションに合ったデザインをみつけてくださいね。
ヒールは5~6cmと比較的履きやすい高さ。軽いので1日履いていても疲れにくいですよ。価格もお手頃なので、シークレットシューズを試してみたいという方にもおすすめです。
※各社通販サイトの 2025年3月10日時点 での税込価格
| サイズ展開 | 23.5~26.5cm |
|---|---|
| 身長アップ | 5~6cm |
| 素材 | アッパー:PU、靴底:ゴム |
| サイズ展開 | 23.5~26.5cm |
|---|---|
| 身長アップ | 5~6cm |
| 素材 | アッパー:PU、靴底:ゴム |
スエード風のアッパーがおしゃれなシューズ
シークレットシューズには見えないスマートなデザインが魅力的。ナチュラルなスエードを表現しているので、足元に存在感が出せます。落ち着きもあり、大人カジュアルに合わせやすい一足です。
横から見ても気づかれにくいバランスでデザインされており、6.5cmもの身長アップが可能。より自然に身長を上げたい方はぜひ試してみてください。
※各社通販サイトの 2025年3月10日時点 での税込価格
| サイズ展開 | 24.5~28.0cm |
|---|---|
| 身長アップ | 6.5cm |
| 素材 | アッパー:合成皮革、靴底:ゴム |
| サイズ展開 | 24.5~28.0cm |
|---|---|
| 身長アップ | 6.5cm |
| 素材 | アッパー:合成皮革、靴底:ゴム |
足元にボリュームを持たせたデザイン
足元にボリュームを持たせた斬新なデザインが目を引くシークレットスニーカー。ストリートファッションにぴったりな一足です。
通気性のある3Dメッシュ素材を使用しているので、防臭・吸湿速乾性が高く、快適に履くことができます。衝撃吸収性にすぐれたアウトソールを採用しており、疲れにくいのもうれしいポイント。歩くことの多い旅行などでも使いやすいでしょう。
※各社通販サイトの 2025年3月10日時点 での税込価格
| サイズ展開 | 23.0~28.5cm |
|---|---|
| 身長アップ | 6cm、8cm、10cm |
| 素材 | アッパー:合成繊維、靴底:ゴム |
| サイズ展開 | 23.0~28.5cm |
|---|---|
| 身長アップ | 6cm、8cm、10cm |
| 素材 | アッパー:合成繊維、靴底:ゴム |
「シークレットシューズ」のおすすめ商品の比較一覧表
| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | サイズ展開 | 身長アップ | 素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北嶋製靴工業所『6cmアップ モンクストラップ 』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月10日時点 での税込価格 |
大人らしいおしゃれを演出するシューズ | 23.5~26.5cm | 6cm | アッパー:牛革、靴底:合成ゴム |
| HAVILAH MODE『シークレットシューズ』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月10日時点 での税込価格 |
ビジネスシーンにぴったりのシークレットシューズ | 23.0~27.0cm | 7cm | アッパー:合成皮革 |
| CLOUD 9『シークレットシューズ』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月10日時点 での税込価格 |
エナメルとマットから選べるテクスチャー | 24.0~27.5cm | 7cm | アッパー:合成皮革、靴底:ゴム |
| 北嶋製靴工業所『6cmアップ 内羽根ストレートチップ』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月10日時点 での税込価格 |
牛革を使用した本格的なシークレットシューズ | 23.5~26.5cm | 6cm | アッパー:牛革、靴底:合成ゴム |
| マドラス×TALLSHOES『モデロ シークレットシューズ』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月10日時点 での税込価格 |
伝統的なフォルムが美しいシークレットシューズ | 23.5~27.0cm | 5cm | アッパー:牛革、靴底:合成ゴム |
| マドラス『モデロ segretaシリーズ 外羽根ストレートチップ・ドレススシューズ』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月10日時点 での税込価格 |
エナメルの光沢が美しいシューズ | 23.0~27.0cm | 6cm | アッパー:本革、靴底:合成ゴム |
| TALLSHOES『OMS-PLUB(シークレット メンズ ビジネスシューズ)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月10日時点 での税込価格 |
豊富なデザインが魅力! 底の高さは4cmから | 23.5~27.0cm | 4cm | アッパー:牛革、靴底:合成ゴム |
| Cartoden『シークレット スニーカー』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月10日時点 での税込価格 |
最大10cm! 3種類の高さから選べる | 23.5~26.5cm | 6cm、8cm、10cm | アッパー:合成繊維、靴底:ゴム |
| ziitop『シークレットスニーカー』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月10日時点 での税込価格 |
革靴っぽいスニーカーで高級感も◎ | 23.0~27.5cm | 6cm | アッパー:PU、靴底:ゴム |
| MY SELECTED『シークレットファッションスニーカー』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月10日時点 での税込価格 |
軽量で履きやすいカジュアルなシューズ | 23.5~26.5cm | 5~6cm | アッパー:PU、靴底:ゴム |
| オーナイン(O-NINE)『シークレットシューズ』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月10日時点 での税込価格 |
スエード風のアッパーがおしゃれなシューズ | 24.5~28.0cm | 6.5cm | アッパー:合成皮革、靴底:ゴム |
| TONDEMON『シークレット スニーカー』 |

|
※各社通販サイトの 2025年3月10日時点 での税込価格 |
足元にボリュームを持たせたデザイン | 23.0~28.5cm | 6cm、8cm、10cm | アッパー:合成繊維、靴底:ゴム |
通販サイトの最新人気ランキングを参考にする シークレットシューズの売れ筋をチェック
Yahoo!ショッピングでのシークレットシューズの売れ筋ランキングも参考にしてみてください。
※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。
靴のデザインはパンツと合わせよう ファッションライターからのアドバイス
最近は厚底スニーカーやボリュームスニーカーと呼ばれるスニーカーが人気を集め、高さのあるソールが広く受け入れられつつあります。比較的シークレットシューズを選びやすい環境になっていますので、トライするなら今がおすすめ! パンツと色を合わせると靴が悪目立ちせず履きこなしやすいので、ふだんよくはくパンツになじむシューズから試してみてください。
高さやデザインもいろいろ
シークレットシューズのおすすめ商品をご紹介しました。
シークレットシューズには、さまざまな種類があります。高さやデザインなど、ポイントを絞ってチェックすることで、用途に合ったシークレットシューズを見つけやすくなりますよ。
あなたがほしいシークレットシューズを選んでみてくださいね。
◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。



![ライター/編集者、[着こなし工学]提唱者:平 格彦](/uploads/profile/image/73/thumb_lg_5087d321-e817-49a1-b188-cf78f43b373e.jpg)