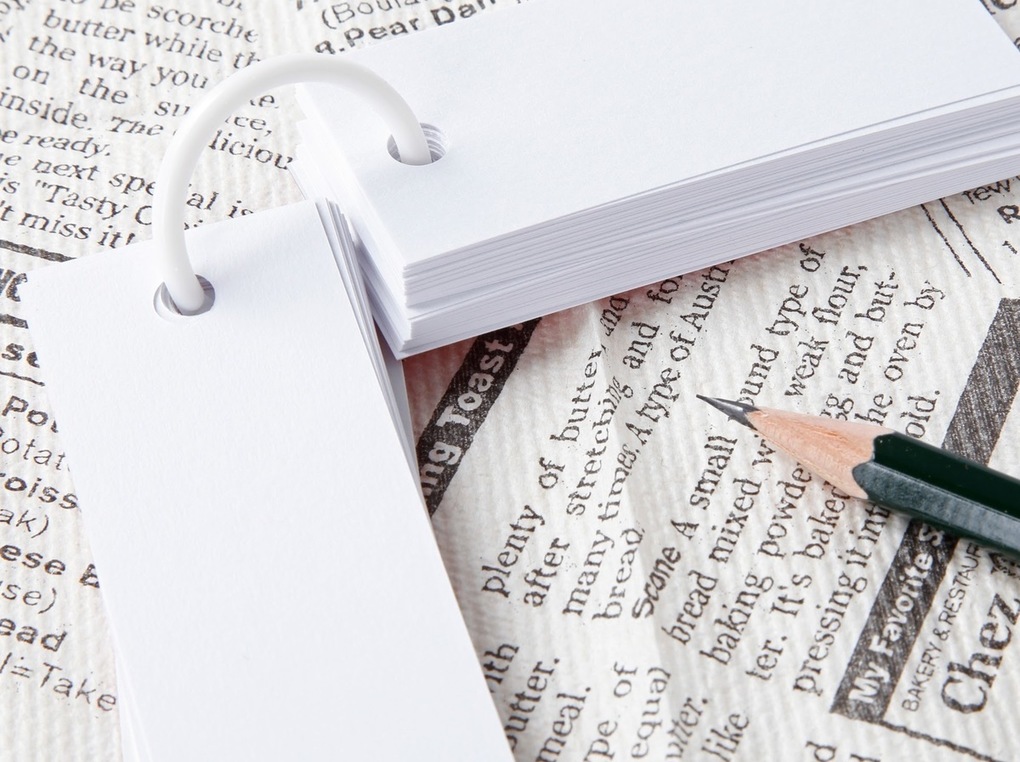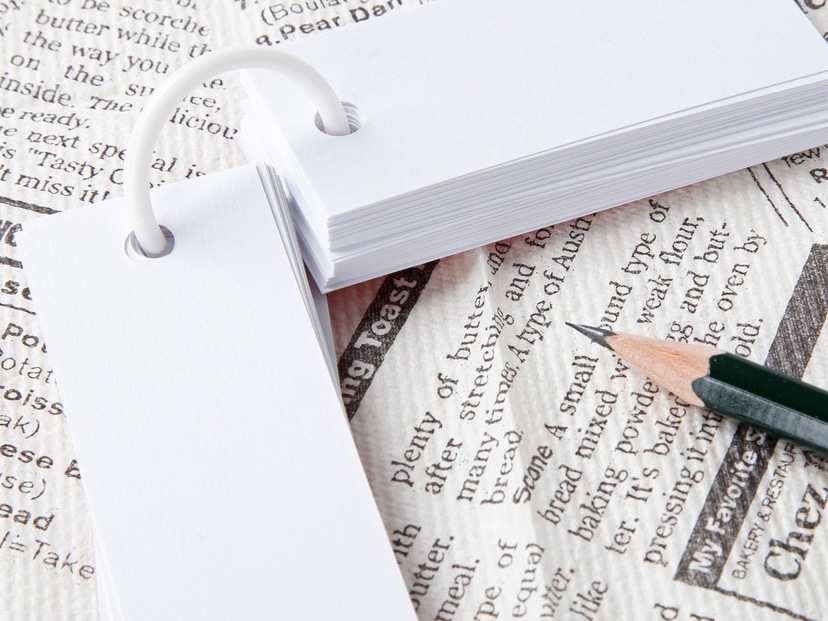| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | サイズ | 枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| レイメイ藤井『単語カード ミニサイズ(WD10)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年09月27日時点 での税込価格 |
暗記シート付きで簡単暗記ができる | 縦30×横72mm | 111枚 |
| コクヨ『キャンパス 単語カード中 カードリングとじ85枚(101B)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年09月27日時点 での税込価格 |
シンプルなベストセラー | 縦30×横68mm | 85枚 |
| クツワ『STAD 暗記単語カード小(SC109)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年09月27日時点 での税込価格 |
赤と緑の暗記シート付単語カード | 縦30×横70mm | 70枚 |
| A-one(エーワン)『マルチカード 単語カード』 |

|
※各社通販サイトの 2024年09月27日時点 での税込価格 |
プリンター対応の単語カード | 縦70×横29.7mm | 5シート(150枚) |
| ぺんてる『手ぶらで暗記 Smatan(スマ単)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年09月27日時点 での税込価格 |
スマホでパシャ!暗記単語カードアプリ | - | - |
| クツワ『STAD 風呂単(大)(SC220)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年09月27日時点 での税込価格 |
お風呂での勉強にぴったり | 縦78×横52mm | 60枚 |
| 泰明紙加工『他の受験生には教えたくない 色で覚える単語帳(TKK-TAN)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年09月27日時点 での税込価格 |
カラフルなデザインで高級感のある単語カード | 直径70mm | 60枚 |
| KAHNIs『単語カード』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月1日時点 での税込価格 |
大容量タイプで文章を書くスペースもある | 縦40×横70mm | 100枚 |
| ライフ『イコール 単語カード(P317a)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年09月27日時点 での税込価格 |
方眼タイプで書きやすい!大きい単語カード | 縦125×横75mm | 100枚 |
【ユーザーが選んだ】イチオシ5選
ここからは、ユーザーがイチオシの単語カードを紹介。5点満点で「コスパ」「使いやすさ」「機能性」を評価してもらいました。イチオシのポイント、おすすめする理由や口コミもぜひ参考にしてください!
その他にもおすすめしたい商品があるよという方は、ぜひ記事の下部にある投稿フォームからご紹介をお願いします。

愛用者
紙がしっかりしていていい
いつもこちらの単語カードを使っています。紙がしっかりしているので裏映りもしないし、小さいので持ち運びにも最適。学生のころは自分が使っていましたが、最近は、子どもたちが漢字を覚えるのに一緒になって使っています。(T.M.さん/女性/43歳/会社員)
※各社通販サイトの 2024年09月27日時点 での税込価格
| コスパ | ★★★★★ |
|---|---|
| 使いやすさ | ★★★★★ |
| 機能性 | ★★★★★ |
| 総合評価 | 5.0点 |
| コスパ | ★★★★★ |
|---|---|
| 使いやすさ | ★★★★★ |
| 機能性 | ★★★★★ |
| 総合評価 | 5.0点 |

愛用者
めくらないから効率よく使える
表紙で単語カードの半分を隠せるのが気に入っています。めくって答えを確認するのが個人的にあまり好きではないので……。学生時代にはこのタイプの商品を見かけたことがなかったのですが、もっと早く使いたかったなと思いました。(Y.T.さん/女性/37歳/フリーランス)
※各社通販サイトの 2024年09月27日時点 での税込価格
| コスパ | ★★★☆☆ |
|---|---|
| 使いやすさ | ★★★★★ |
| 機能性 | ★★★★★ |
| 総合評価 | 4.3点 |
| コスパ | ★★★☆☆ |
|---|---|
| 使いやすさ | ★★★★★ |
| 機能性 | ★★★★★ |
| 総合評価 | 4.3点 |

愛用者
絵が描ける! 大きめ単語カード
まだ字の読めない息子が、恐竜の名前を覚えるのに使える絵が描ける単語カードを探していました。この商品は大きめなので絵を描きやすく、無地なのもうれしいポイント。しっかりとした厚さのある紙で、耐久性もばっちりです。(Y.B.さん/女性/41歳/自営業)
※各社通販サイトの 2024年09月27日時点 での税込価格
| コスパ | ★★★★☆ |
|---|---|
| 使いやすさ | ★★★★★ |
| 機能性 | ★★★★★ |
| 総合評価 | 4.7点 |
| コスパ | ★★★★☆ |
|---|---|
| 使いやすさ | ★★★★★ |
| 機能性 | ★★★★★ |
| 総合評価 | 4.7点 |

愛用者
手軽に使えるメモカードとして使用
仕事のメモやアイデア整理などに使っています。ペンの書き味がよく、インクがにじみにくいのでとても助かっています。また、安価で手軽に使い捨てできるので、お財布にもやさしいです。携帯して、いつでもどこでもメモができるので重宝しています。(T.K.さん/男性/55歳/自営業)
※各社通販サイトの 2024年09月27日時点 での税込価格
| コスパ | ★★★★★ |
|---|---|
| 使いやすさ | ★★★★★ |
| 機能性 | ★★★★☆ |
| 総合評価 | 4.7点 |
| コスパ | ★★★★★ |
|---|---|
| 使いやすさ | ★★★★★ |
| 機能性 | ★★★★☆ |
| 総合評価 | 4.7点 |

愛用者
移動中でも片手でめくれる
表紙に人差し指を差し込んで親指でぺらぺらめくることができるので、通勤や通学の移動中、電車やバスのなかなど、立ちながらでも片手でめくって使えます。子どもの勉強にも便利で使いやすいようです。受験生へのプレゼントにもおすすめします。(Y.T.さん/女性/43歳/主婦)
※各社通販サイトの 2024年09月27日時点 での税込価格
| コスパ | ★★★☆☆ |
|---|---|
| 使いやすさ | ★★★★☆ |
| 機能性 | ★★★★☆ |
| 総合評価 | 3.7点 |
| コスパ | ★★★☆☆ |
|---|---|
| 使いやすさ | ★★★★☆ |
| 機能性 | ★★★★☆ |
| 総合評価 | 3.7点 |
単語カード(単語帳)のおすすめ9選
それでは、数ある単語カードのなかでも、とくにおすすめしたい商品をご紹介します。商品ごとに特徴を紹介していくので、使ってみたい単語カードがないかチェックしてみてください。

暗記シート付きで簡単暗記ができる
表紙に「暗記シート」がついている単語カードです。同じ色のペンで覚えたい文字をなぞり、シートをかぶせるとその文字が消えるので、めくりながら効率よく暗記できます。
単語カードにあらかじめ暗記シートが付属しているのでカードを裏返さなくても覚えられます。100枚以上のボリュームがありますのでたくさん単語を書くことができます。
※各社通販サイトの 2024年09月27日時点 での税込価格
| サイズ | 縦30×横72mm |
|---|---|
| 枚数 | 111枚 |
| サイズ | 縦30×横72mm |
|---|---|
| 枚数 | 111枚 |

シンプルなベストセラー
ノートで定番、コクヨのキャンパスシリーズの単語帳です。スタンダードでシンプルなこの単語カードは際立った特徴がないのが最大のメリットで、どんな暗記シーンにもマッチする心強い存在です。
シンプルで丈夫な単語帳を求めている方にもおすすめの商品です。安価なのでまとめ買いにも適しています。もちろんキャンパスシリーズだけあって書きやすく、ある程度の厚みもあるので、折れ曲がりにくく、耐久性もあります。表紙が3色あるので、ジャンル別に使い分けができるのもうれしいところです。
※各社通販サイトの 2024年09月27日時点 での税込価格
| サイズ | 縦30×横68mm |
|---|---|
| 枚数 | 85枚 |
| サイズ | 縦30×横68mm |
|---|---|
| 枚数 | 85枚 |

赤と緑の暗記シート付単語カード
こちらの単語カードには、赤と緑の2色の暗記シートが付属しています。どちらのシートにも対応しているペンを使うことで、学習の幅を広げることができる優れものです。
英単語を覚える際には動詞を赤、名詞を緑シートを使うなど分けて学習ができますし、数学の公式や答えを分けることもできますね。
年号を覚えたい場合には時事問題や歴史で色分けしてもいいかもしれません。シンプルで持ち歩きやすいコンパクトな単語カードですので学生に使いやすいと評判です。
※各社通販サイトの 2024年09月27日時点 での税込価格
| サイズ | 縦30×横70mm |
|---|---|
| 枚数 | 70枚 |
| サイズ | 縦30×横70mm |
|---|---|
| 枚数 | 70枚 |
プリンター対応の単語カード
手書きはもちろん、インクジェット・レーザー・熱転写・コピー・ドットの各種プリンターでの印刷にも対応した単語カードです。カード1枚1枚に穴があいているので、印刷してから穴を開ける手間がありません。
メーカーサイトでは、きれいに印刷できる専用ソフトがフリーダウンロードできます。
一度にたくさんの単語カードをつくりたい人や、手書きするのが苦手な人にぴったりです。
※各社通販サイトの 2024年09月27日時点 での税込価格
| サイズ | 縦70×横29.7mm |
|---|---|
| 枚数 | 5シート(150枚) |
| サイズ | 縦70×横29.7mm |
|---|---|
| 枚数 | 5シート(150枚) |

スマホでパシャ!暗記単語カードアプリ
単語カードを作ったり、持ち歩くのは面倒という人のためのアプリ式単語カード。覚えたい単語とその意味を書いたらスマートフォンで撮影し、専用アプリをインストールするとスマホが単語カードに早変わりします。
とても便利なアイテムですがたくさん撮るのは大変ということもあり、ちょっとだけ覚えたいときにおすすめのアイテムです。集中的に覚えたいといったようなポイント学習にはよいのではないでしょうか。
※各社通販サイトの 2024年09月27日時点 での税込価格
| サイズ | - |
|---|---|
| 枚数 | - |
| サイズ | - |
|---|---|
| 枚数 | - |
お風呂での勉強にぴったり
試験の直前時期は入浴の時間さえ惜しい、と感じる人も多いのではないでしょうか。お風呂で学習効率を上げたい人にご紹介したいのがクツワの『STAD風呂単』です。
この単語カードは耐水ペーパーで作られているため、入浴中の学習にぴったりです。水に濡らせば浴室の壁に貼ることもできるので、テストや受験などの勉強に活用できますね。
※各社通販サイトの 2024年09月27日時点 での税込価格
| サイズ | 縦78×横52mm |
|---|---|
| 枚数 | 60枚 |
| サイズ | 縦78×横52mm |
|---|---|
| 枚数 | 60枚 |
カラフルなデザインで高級感のある単語カード
おしゃれなデザインの単語カードです。20色が3枚ずつセットになっています。カラフルなので、使い方次第で色で識別しながら効率よく覚えられるでしょう。普通の紙ではなく、紀州の上質紙が使われていて、高級感があるのも特徴です。一つ一つが丁寧に手作りで作られています。
他の人とはひと味違う単語カードで、気分を高めながら勉強をしたい方におすすめです。受験生の勉強に、テスト対策に自分のニーズに合わせて活用しましょう。
※各社通販サイトの 2024年09月27日時点 での税込価格
| サイズ | 直径70mm |
|---|---|
| 枚数 | 60枚 |
| サイズ | 直径70mm |
|---|---|
| 枚数 | 60枚 |
大容量タイプで文章を書くスペースもある
表紙と裏表紙が黒色無地なのでシンプルなデザインです。光沢素材の紙を使用していて、シャープペンシルだけでなく色鉛筆や水性ペン、油性ペンなどに対応しています。一つに100枚入っている大容量タイプ。
覚えたい単語などが多いときに便利です。単語だけでなく、補足の説明文などを書くスペースも十分にあるので、英語の会話文など少し長めの文章を書くときにもおすすめ。単語カードを作り、通学や通勤中を活用し勉強しましょう。
※各社通販サイトの 2024年10月1日時点 での税込価格
| サイズ | 縦40×横70mm |
|---|---|
| 枚数 | 100枚 |
| サイズ | 縦40×横70mm |
|---|---|
| 枚数 | 100枚 |
方眼タイプで書きやすい!大きい単語カード
紙のサイズが大きめで、縦長タイプの単語カードです。リングが大きいので紙をめくりやすく、勉強の効率アップにつながるでしょう。紙は方眼タイプで書きやすいのが特徴。メモ書きにもおすすめです。表紙の色はミントグリーンをはじめ4色あるので、自分の好みのものを選びましょう。
おしゃれさがありながらもシンプルなデザインなので、飽きることなく使えます。覚えたい単語が多い方は、100枚をフルで活用してみてくださいね。
※各社通販サイトの 2024年09月27日時点 での税込価格
| サイズ | 縦125×横75mm |
|---|---|
| 枚数 | 100枚 |
| サイズ | 縦125×横75mm |
|---|---|
| 枚数 | 100枚 |
おすすめ商品の比較一覧表
| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | サイズ | 枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| レイメイ藤井『単語カード ミニサイズ(WD10)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年09月27日時点 での税込価格 |
暗記シート付きで簡単暗記ができる | 縦30×横72mm | 111枚 |
| コクヨ『キャンパス 単語カード中 カードリングとじ85枚(101B)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年09月27日時点 での税込価格 |
シンプルなベストセラー | 縦30×横68mm | 85枚 |
| クツワ『STAD 暗記単語カード小(SC109)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年09月27日時点 での税込価格 |
赤と緑の暗記シート付単語カード | 縦30×横70mm | 70枚 |
| A-one(エーワン)『マルチカード 単語カード』 |

|
※各社通販サイトの 2024年09月27日時点 での税込価格 |
プリンター対応の単語カード | 縦70×横29.7mm | 5シート(150枚) |
| ぺんてる『手ぶらで暗記 Smatan(スマ単)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年09月27日時点 での税込価格 |
スマホでパシャ!暗記単語カードアプリ | - | - |
| クツワ『STAD 風呂単(大)(SC220)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年09月27日時点 での税込価格 |
お風呂での勉強にぴったり | 縦78×横52mm | 60枚 |
| 泰明紙加工『他の受験生には教えたくない 色で覚える単語帳(TKK-TAN)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年09月27日時点 での税込価格 |
カラフルなデザインで高級感のある単語カード | 直径70mm | 60枚 |
| KAHNIs『単語カード』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月1日時点 での税込価格 |
大容量タイプで文章を書くスペースもある | 縦40×横70mm | 100枚 |
| ライフ『イコール 単語カード(P317a)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年09月27日時点 での税込価格 |
方眼タイプで書きやすい!大きい単語カード | 縦125×横75mm | 100枚 |
通販サイトの最新人気ランキングを参考にする 単語カードの売れ筋をチェック
Amazonでの単語カードの売れ筋ランキングも参考にしてみてください。
※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。
単語カード(単語帳)の選び方
暗記する際の便利アイテム「単語カード(単語帳)」。スマホと連携できるものもあり、スタンダードなものから最新のものまで、さまざまな種類が販売されています。この記事では、単語カードの選び方を解説していきます。ポイントは下記5点!
【1】サイズで選ぶ
【2】単語カードの枚数で選ぶ
【3】めくりやすいものを選ぶ
【4】材質やデザインで選ぶ
【5】より便利に使える機能をチェック
とくに【5】では、さまざまな機能の単語帳を紹介しているので、ぜひチェックしてみてください。
【1】サイズで選ぶ
単語カードを選ぶときは、持ち運びやすいサイズのものを選びましょう。大きすぎるものは持ち運びにくく、単語帳を開く頻度が下がります。
3×7cm程度のものは、手のひらにすっぽり収まるサイズで持ち運びやすく、電車やバスでの移動中にも学習できるのがポイント。解説や付随する情報などを書き込みたいときは、少し大きめのものを選ぶと書きやすいです。
机のうえでのみ使うのであれば、たくさん書き込めるノートサイズの単語帳もよいでしょう。
【2】単語カードの枚数で選ぶ
単語カードを選ぶ際には、紙の枚数も重要なポイントです。用途にあった枚数の単語カードを選ぶことで学習の効率が上がります。
たとえば、シンプルに単語や年号などをたくさん覚えたい場合には、枚数が多い単語カードがよいでしょう。何度も繰り返し学習し、覚えたものからどんどん外していくことで、なかなか覚えられない部分を重点的に学習することができます。
ふだんは参考書やノートを使って勉強し、隙間時間の活用のために単語カードを取り入れたいという人には、持ち歩きやすい枚数が少ないものが使いやすいでしょう。
【3】めくりやすいものを選ぶ
単語カードは基本的にはめくって使うもののため、めくりやすい紙質、設計のものを選ぶのがおすすめです。大きなノートタイプの単語カードの場合、半分を隠して使用するものも多いですが、暗記の便利アイテムという単語カードの性質上、ノートタイプでもページをめくるシーンは多くなります。
めくりにくいと「覚える気もなくなる」となりますから、しっかり学習したい人はさっとめくれるものを選んでくださいね。
また、良質な紙であれば何度めくってもやぶれづらいです。厚めで硬めの紙のものを選ぶと長持ちします。
【4】材質やデザインで選ぶ
カードの材質は、筆記用具の種類に応じて「使いやすい」「使いづらい」があります。学習スタイルでいうと、シャーペンやボールペン、蛍光ペンや油性ペンなどが多く使用されると思いますが、「シャーペンには書きやすく向いていたが、そのうえから蛍光ペンを引いたらにじんでしまった」や、「油性ペンで書いたら裏うつりする」など、対応する筆記用具の種類によっても異なりますので、自分がよく使うペンの種類で材質を選びましょう。
また、デザインについても、長方形や円形、動物型など、さまざまな形が販売されています。単語帳を見るたびにホッとするかわいいデザインを選ぶのも、使うのが楽しみになるのでおすすめです。
【5】より便利に使える機能をチェック
単語カードは、書き込めるカード以外にもいろいろな機能が付いているものがあり、勉強以外のシーンにも使用できます。使用シーンに応じて、便利に使える機能もチェックしてみましょう。
キッチンやお風呂場でも使える「防水タイプ」
単語カードには防水カバーのついているものや汚れや水に強いような加工が施されているものもあります。お風呂場での学習やキッチン用のレシピカードなどの用途に使えて便利です。繰り返し使うなら、リングを通している穴のところが切れにくく、しっかりした紙質のものを選ぶとよいでしょう。
また、防水仕様のカードはリングを外すと、お風呂場の壁に貼り付けられるものもあります。
インクにじみやカード折れを防ぐ「カバー付き」
毎日カバンに入れて持ち歩くことが多い単語カードは汚れてしまったり外側が折れたりしやすいものですが、透明カバーがついているだけできれいに保存できますし、かばんのなかで単語カードがバラバラになりにくいというメリットもあります。
なかのインクがにじんでしまったりすることも防げますし、気持ちよく使えます。利便性という特徴から見ると、チェック用の暗記シートが付いているものもあり、目的に合わせて特徴のある単語カードを選ぶとよいでしょう。
多様な使い方が可能な「入れ替えできるタイプ」
英単語カード・単語帳の使い方は、覚えたい単語を書いて、繰り返しめくって暗記するのが一般的です。英語の単語だけでなく、古文の単語や元素記号などさまざまな単語の暗記に使えます。
金具を外してカードの順番を入れ替えられる単語カードは、よりしっかりと暗記したいときにぴったり。カードの順番を入れ替えてランダムにすることで、書いた順番で覚えてしまうことが防げます。
長く使うなら「耐久性が高いもの」
単語カードは、繰り返しめくって使うものです。長く使うのであれば、耐久性が高い素材でできたものを選びましょう。耐久性が高い素材には、厚手の画用紙やポリプロピレンなどがあります。
薄くてやわらかい紙でできた単語カードの場合、何度もめくっているうちに破れたり折れ曲がったりしてしまうことがあります。厚みがある紙でできた単語カードは丈夫なので、頻繁に単語カードを使って勉強する人にぴったりです。
書き込みの手間を省ける「印刷機能付き」
単語カードには、プリンターを使ってそのまま印刷できるタイプの商品もあります。プリンターで印刷するときにも、専用ソフトを使うとかんたんです。大量に単語カードを作りたいときや、手書きの手間を省きたいときに向いています。
また、手書きよりも文字がきれいで見やすいというメリットもあります。勉強はもちろん、いろいろな単語カード作りに活用できます。
スマホでかんたんに学習できる「アプリ連動機能付き」
単語カードには、専用アプリと連動しているものもあります。単語カードに覚えたい単語や意味を書き込んでからスマホで撮影すると、アプリに取り込めます。単語カード自体が手元になくても、スマホアプリを開けばいつでも単語カードを活用できます。
単語カードを持ち歩く手間を省きたい人や、隙間時間などにいつでも単語カードを見たい人に向いています。
単語カードの作り方
単語カードの一般的な作り方は、例えば英単語の場合、表に英単語、裏に日本語を書く方法があります。この方法で作れば、表からは日本語→英語、裏からは、英語→日本語として使うことができるのでとても便利です。書き込む内容もシンプルな方が良いですが、正式名称で書くことを心掛けましょう。発音記号やカタカナなどを追記しておくことで、より覚えやすくなりますよ。
また、一問一答形式で作る方法もあります。表にエピソードを書き込み、裏で説明をすることもできます。重要である単語は、目立つように文字を大きくしたり、色を付けたりすることでどこを重点的に覚えるべきか分かるようになります。
一度作れば、繰り返し使えるものなので自分が使いやすい方法で作るようにしましょう。
単語カードに関するQ&A
ここでは、単語カードに関するQ&Aをご紹介します。ぜひ参考にしてくださいね。


暗記グッズの定番、単語カード。そのメリットは、小さいため持ち運びに便利で、電車のなかなどどこでも勉強できることです。また、自分で作るため、作ってる工程がすでに勉強になりますよ。
一方デメリットは、書き込める情報量が少ないこと、防水機能がなければ濡らせないためお風呂場などでは使用できないことが挙げられます。


単語カードを作ったら、順番にめくって覚えていきますよね。それにプラスして、「裏面からもめくってみる」「単語カードをシャッフルして暗記チェック」というような方法もやってみることをおすすめします。
オリジナル単語カードをつくるならこちらの記事も! 【関連記事】
最近では単語カードを手作りして面白い使い方をしてる方やオリジナルなものを作る方も増えています。手作りしたい方には以下の記事がぴったり! 便利で役立つアイテムを紹介しているので参考にしてみてください。
自分にぴったりの単語カードを選ぼう!
単語カードは、英単語など英語以外に、歴史の出来事や化学式や理科の用語など、さまざまな教科で暗記するときに使えます。かんたんな使い方なので、受験や資格試験の勉強には心強いアイテムです。
人気の100均や無印良品などでも売っている単語カードですが、サイズや材質などの違いでさまざまな種類の商品が販売されています。使いにくいものは勉強へのモチベーションを下げてしまうこともありますよね。
そのため、単語カードを使う場所や勉強する科目など、自分の使い方に合わせた単語カードを選ぶことが大切です! 使いやすい単語カードを手に入れて、空いた時間も効率よく勉強して合格を目指しましょう。
おすすめ商品・口コミの投稿はこちら
※メーカーや販売店の方は、ページ下部の「お問い合わせはこちら」から商品情報をお送りください。
ユーザーのおすすめ商品や口コミ情報は、マイナビおすすめナビを閲覧したユーザー、マイナビニュース会員、外部パートナー企業と契約する一般ユーザーからの投稿をもとにしています。
◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。