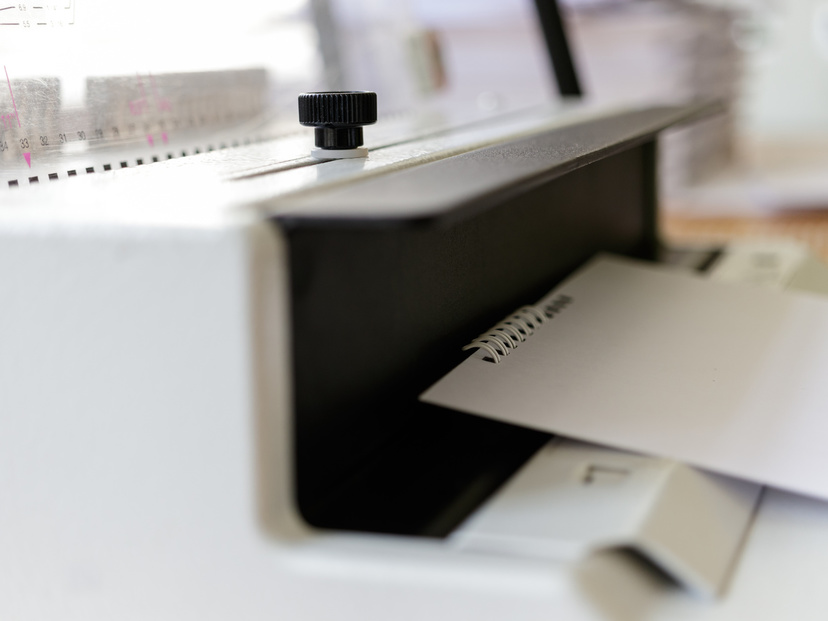| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | サイズ | 製本タイプ | 対応用紙サイズ | 製本厚 | 重量 | 製本時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIC(ジャパンインターナショナルコマース)『卓上製本機 とじ太くん3000(JICTJ3000)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年06月17日時点 での税込価格 |
ビジネスや家庭用に! くるみ製本の小型モデル | 幅390×奥行165×高さ175mm | ホットメルト製本 | A5タテ、B5、A4、B4、A3ヨコ | 最大背幅30mm(1~300枚) | 約1580g | 45秒 |
| アスカ『Asmix パーソナル製本機(B2500)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年06月17日時点 での税込価格 |
手に取りやすい価格が魅力! 本をばらす用途にも | 幅423×奥行90×高さ178mm | くるみ製本 | A4、B5 | 24mm | 約900g | 60秒 |
| KOKUYO(コクヨ)『パーソナル製本機(セキ-GTS500)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年06月17日時点 での税込価格 |
素早くくるみ製本ができるおしゃれな製本機 | 幅360×奥行111×高さ150mm | サ―マタイプ製本 | A4-S長辺とじ | 1~120枚 | - | 40秒 |
| INTER COSMOS(インターコスモス)『製本機 ファーストバック 9(A65FB9)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年06月17日時点 での税込価格 |
1台で4つの製本スタイルが可能! | 幅490×奥行282×高さ318mm | テープ製本、くるみ製本、契約書製本、ハードカバー製本 | A4、A5 | 2~250枚(最大500ページ) | 7.2kg | 30~60秒 |
| MAX(マックス)『電子製本機(TB-1000A)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年6月23日時点 での税込価格 |
1冊約10秒で背表紙にテープが貼れる! | 幅491×奥行415×高さ292mm | テープ製本 | A4短め方向(210mm)〜A4長め方向、A3短め方向(297mm)まで | 6~100枚 | 13.6 g | 10秒 |
| JIC(ジャパンインターナショナルコマース)『とじ太くん flex(45000-Flex)』 |
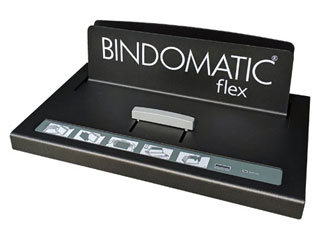
|
※各社通販サイトの 2025年06月17日時点 での税込価格 |
幅広い用紙サイズに対応したコンパクトな1台! | 幅440×奥行275×高さ158mm | ホットメルト製本 | B5、B4、A5、A4、A3 | 1~540枚 | - | - |
| ACCO BRANDS(アコ・ブランズ)『GBC プラスチックリング用 綴じ専用機(GP16DB)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年6月23日時点 での税込価格 |
見開きしやすいプラスチックリング専用 | 幅510×奥行330×高さ140mm | プラスチックリングバインド製本 | ~420mm | 50mm(コピー用紙最大410枚程度) | - | - |
製本機とは?
製本機とは、文書や契約書など複数の書類を1冊の冊子にまとめるための機械のこと。専門の業者に頼まなくても自宅やオフィスなどで手軽に製本することができるよう、近年では業務用だけでなく安価でコンパクトなタイプも販売されています。
想像以上に完成度の高い製本機もあるので、ぜひ、各商品をチェックしてみてくださいね。
製本機の選び方 製本タイプ、サイズ、厚み、消耗品で
製本機は、製本方法や用紙の厚みなどによって、選び方が異なります。製本のタイプや機能について、選び方のポイントを解説するので、ぜひ参考にしてみてください。ポイントは下記のとおり。
【1】製本タイプで選ぶ
【2】製本したい用紙のサイズに対応しているか
【3】背幅の厚みに対応しているかもチェック
【4】コストパフォーマンスで選ぶ
上記のポイントを押さえることで、より欲しい商品をみつけることができます。一つひとつ解説していきます。
【1】製本タイプで選ぶ
まずは、製本タイプの種類について紹介します。具体的な製本方法を知ることで、どのタイプがどういった冊子をつくるのに向いているのかをイメージできます。小説のような形にしたい、雑誌のような綴じ方がいいなど、完成品のイメージから製本機を選んでみるといいでしょう。
『くるみ製本』市販の書籍と同じ仕上がりを
「くるみ製本」は「背のり方式」ともいわれる、市販の書籍で多く利用されている一般的な製本タイプです。単行本や小説、参考書などはほとんどくるみ製本で作成されています。専用のカバーを使い、表紙となかの冊子をのりで貼り合わせ、熱を加えて仕上げる方法です。
また、くるみ製本タイプの製本機はリーズナブルなものが多いのも特徴。専用カバーを別途購入する必要はありますが、見た目を美しく仕上げたい人に向いています。
『中綴じ製本』雑誌に使われている
薄手の雑誌などに使用されている製法が「中綴じ製本」です。紙を折り、中央をホチキスで留めるタイプで、ランニングコストが少ないのが特徴です。
業務用途では専用の製本機が必要になりますが、個人で使うものだと大きなホチキスのようなタイプもあります。中綴じ製本は折り曲げる作業も必要で手間がかかりますが、自動で折り曲げてくれる製本機もあるので、用途に合わせて選ぶといいでしょう。
『テープ製本』手軽にオリジナルノートができる
「テープ製本」は、その名のとおりテープで製本する方法です。ホチキスでまとめた書類の背にテープを貼ることで、見栄えと耐久性が向上します。コストを掛けず、見た目のよい簡易的な製本がしたい方におすすめです。
製本用のテープは手で貼ることもできますが、1冊ずつ貼っていると時間がかかるので、テープ製本用の製本機を活用したほうがいいでしょう。
『リング製本』リングノートができる
リングノートと同じように製本できるのが「リング製本」です。試験勉強などで自分でまとめた資料を、リングノートとして保管しておきたい人に適しています。見開きしやすい構造なので、勉強時に使いやすいでしょう。ただし、リング部分がかさばるので、配布目的には適していません。
製本方法は、穴を開けてリングをとおすといったシンプルなもの。書類を製本機にはさんでレバーを引くだけ、といったカンタンな操作で制作できるものが多くあります
【2】製本したい用紙のサイズに対応しているか
製本機は、本にしたい用紙のサイズに対応したものを選びましょう。よくある勘違いが「A3まで対応しているからA5も作れるだろう」というもの。製本機ごとに対応する用紙サイズが決まっており、大きいサイズに対応しているからといって、小さいサイズの製本ができるわけではありません。用紙の対応サイズは必ず確認しましょう。
【3】背幅の厚みに対応しているかもチェック
用紙サイズを確認すると同時に、作成する冊子の厚みも気にしなければなりません。製本する厚さを事前に確認して、厚みに対応できるものを選びましょう。
また、どのぐらいの厚さかわからないから、分厚い製本が可能なタイプを選ぶというのはあまりおすすめできません。分厚い本にも対応できるスペックの高いものでも、製本に時間がかかる、高価なものが多いなどデメリットがあります。きちんと自分に合っているサイズを選ぶほうがお得ですよ。
【4】コストパフォーマンスで選ぶ
本体の機能や価格で選ぶのも必要ですが、別途かかる消耗品のコストなども事前に把握しておきましょう。リング製本はリープリング、中綴じ製本はホッチキスの芯、くるみ製本は背のり方式専用のカバーなど、製本方法によって必要な消耗品があります。
頻繁に使用する場合や、そこまで製本方法にこだわらない場合には、本体価格以外にも消耗品が安いタイプを選んだほうがいいでしょう。
消耗品が入手しやすいかにも着目 文具研究家がアドバイス
製本機の購入を検討している場合、使用目的が明確だと思うので「製本の方法」「対応サイズ・厚み」が希望に合っていることをしっかり確認しましょう。特に「厚み」は綺麗に製本できるかを左右するポイントになります。
また、見落としがちなのは製本カバーやリングなどの「消耗品」。価格は勿論ですが、手に入りやすいかどうかもチェックを! カンタンに入手できない場合は、本体購入時に消耗品もある程度の量を買っておきましょう。
製本機おすすめ7選 本格用から家庭用まで! 多彩な機能も
さまざまな製本機の中から厳選したものを紹介していきます。本格的に製本したい人から、家庭でちょっと使いたい人まで適した商品を紹介しますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
ビジネスや家庭用に! くるみ製本の小型モデル
1.5mm幅の厚さなら18冊まで一度に製本ができる、くるみ製本タイプの卓上製本機。生徒数が多い学校の文集作成や、新人研修資料が大量に必要なオフィスでの使用に向いています。
見た目はコンパクトでブックスタンドのよう。使わないときには、目立たないところに収納できるので、家庭で使用しても邪魔になりません。年間200冊以上を製本する利用者向けなので、利用頻度が多い人にピッタリですね。
※各社通販サイトの 2025年06月17日時点 での税込価格
| サイズ | 幅390×奥行165×高さ175mm |
|---|---|
| 製本タイプ | ホットメルト製本 |
| 対応用紙サイズ | A5タテ、B5、A4、B4、A3ヨコ |
| 製本厚 | 最大背幅30mm(1~300枚) |
| 重量 | 約1580g |
| 製本時間 | 45秒 |
| サイズ | 幅390×奥行165×高さ175mm |
|---|---|
| 製本タイプ | ホットメルト製本 |
| 対応用紙サイズ | A5タテ、B5、A4、B4、A3ヨコ |
| 製本厚 | 最大背幅30mm(1~300枚) |
| 重量 | 約1580g |
| 製本時間 | 45秒 |
手に取りやすい価格が魅力! 本をばらす用途にも
比較的低価格なくるみ製本タイプの商品です。コンパクトでデスク上でも邪魔にならないサイズ感。邪魔になりづらく、手に取りやすい価格なのではじめて製本機を買う方にもおすすめできます。
A4サイズ、厚さ24mmまで対応可能。製本以外にも、糊付けされた本やノートを分解する用途にも使用可能で、電子書籍への自炊にも活用できます。
※各社通販サイトの 2025年06月17日時点 での税込価格
| サイズ | 幅423×奥行90×高さ178mm |
|---|---|
| 製本タイプ | くるみ製本 |
| 対応用紙サイズ | A4、B5 |
| 製本厚 | 24mm |
| 重量 | 約900g |
| 製本時間 | 60秒 |
| サイズ | 幅423×奥行90×高さ178mm |
|---|---|
| 製本タイプ | くるみ製本 |
| 対応用紙サイズ | A4、B5 |
| 製本厚 | 24mm |
| 重量 | 約900g |
| 製本時間 | 60秒 |
素早くくるみ製本ができるおしゃれな製本機
流線型のおしゃれなデザインが目を惹きます。コンパクトなサイズで置き場所を選ばず、ご家庭からオフィスまで幅広いシーンで活躍してくれるでしょう。
1冊約40秒ほどのスピードで製本が可能。製本完了時にはブザーが鳴るので、ほかの作業と並行して製本作業が行えます。事務作業が多い部署でも効率よく作業ができるでしょう。
※各社通販サイトの 2025年06月17日時点 での税込価格
| サイズ | 幅360×奥行111×高さ150mm |
|---|---|
| 製本タイプ | サ―マタイプ製本 |
| 対応用紙サイズ | A4-S長辺とじ |
| 製本厚 | 1~120枚 |
| 重量 | - |
| 製本時間 | 40秒 |
| サイズ | 幅360×奥行111×高さ150mm |
|---|---|
| 製本タイプ | サ―マタイプ製本 |
| 対応用紙サイズ | A4-S長辺とじ |
| 製本厚 | 1~120枚 |
| 重量 | - |
| 製本時間 | 40秒 |
1台で4つの製本スタイルが可能!
テープ、くるみ、ハードカバー、契約書製本の4つの製本スタイルが可能な製本機。マルチな製本を求めるオフィス用として重宝します。
ウォームアップの必要もなく、約30秒のカンタン3ステップで製本できる高スペックな商品。500ページまで製本可能で、180度見開き製本もできます。官公庁での使用実績もあるので、製本頻度が多い部署でも安心して使えますよ。
※各社通販サイトの 2025年06月17日時点 での税込価格
| サイズ | 幅490×奥行282×高さ318mm |
|---|---|
| 製本タイプ | テープ製本、くるみ製本、契約書製本、ハードカバー製本 |
| 対応用紙サイズ | A4、A5 |
| 製本厚 | 2~250枚(最大500ページ) |
| 重量 | 7.2kg |
| 製本時間 | 30~60秒 |
| サイズ | 幅490×奥行282×高さ318mm |
|---|---|
| 製本タイプ | テープ製本、くるみ製本、契約書製本、ハードカバー製本 |
| 対応用紙サイズ | A4、A5 |
| 製本厚 | 2~250枚(最大500ページ) |
| 重量 | 7.2kg |
| 製本時間 | 30~60秒 |
1冊約10秒で背表紙にテープが貼れる!
自動でテープ製本ができる製本機。ホチキスでまとめた書類を本体に差し込みボタンを押すだけで、慣れた人でも1冊約50秒かかるテープ製本が、約10秒で完成します。テープを張ることでホチキスで留めただけの状態よりも耐久性がアップ! 修学旅行のしおりなど、すぐに破けると困る配布物に適しています。
手貼り作業だったテープ貼りを効率化したい方や、学校やオフィスなどで重宝するアイテムです。
※各社通販サイトの 2025年6月23日時点 での税込価格
| サイズ | 幅491×奥行415×高さ292mm |
|---|---|
| 製本タイプ | テープ製本 |
| 対応用紙サイズ | A4短め方向(210mm)〜A4長め方向、A3短め方向(297mm)まで |
| 製本厚 | 6~100枚 |
| 重量 | 13.6 g |
| 製本時間 | 10秒 |
| サイズ | 幅491×奥行415×高さ292mm |
|---|---|
| 製本タイプ | テープ製本 |
| 対応用紙サイズ | A4短め方向(210mm)〜A4長め方向、A3短め方向(297mm)まで |
| 製本厚 | 6~100枚 |
| 重量 | 13.6 g |
| 製本時間 | 10秒 |
幅広い用紙サイズに対応したコンパクトな1台!
ブックスタンドと見間違うほどコンパクトなデザインの製本機。設置スペースが限られてくる自宅での使用にも便利です。
B5・B4・A5・A4・A3と幅広いサイズに対応。分厚い書類や、何冊かの製本も一気にできます。プリンタやコピー機のそばに置けば、印刷した用紙をその場で美しく製本できるので、オフィスでも大活躍してくれるでしょう。
※各社通販サイトの 2025年06月17日時点 での税込価格
| サイズ | 幅440×奥行275×高さ158mm |
|---|---|
| 製本タイプ | ホットメルト製本 |
| 対応用紙サイズ | B5、B4、A5、A4、A3 |
| 製本厚 | 1~540枚 |
| 重量 | - |
| 製本時間 | - |
| サイズ | 幅440×奥行275×高さ158mm |
|---|---|
| 製本タイプ | ホットメルト製本 |
| 対応用紙サイズ | B5、B4、A5、A4、A3 |
| 製本厚 | 1~540枚 |
| 重量 | - |
| 製本時間 | - |
見開きしやすいプラスチックリング専用
プラスチックリング専用の製本機。美しくすっきりとしたリングで見栄えがよく、社内だけでなく、社外に提出する書類用の製本にも向いているアイテムです。
180度見開きも可能になり、折りたたんで資料を確認できるので、忙しい上司や取引先にも喜ばれますよ。410枚ほどの製本も可能なので、大量の会議資料をまとめることもできます。
※各社通販サイトの 2025年6月23日時点 での税込価格
| サイズ | 幅510×奥行330×高さ140mm |
|---|---|
| 製本タイプ | プラスチックリングバインド製本 |
| 対応用紙サイズ | ~420mm |
| 製本厚 | 50mm(コピー用紙最大410枚程度) |
| 重量 | - |
| 製本時間 | - |
| サイズ | 幅510×奥行330×高さ140mm |
|---|---|
| 製本タイプ | プラスチックリングバインド製本 |
| 対応用紙サイズ | ~420mm |
| 製本厚 | 50mm(コピー用紙最大410枚程度) |
| 重量 | - |
| 製本時間 | - |
「製本機」のおすすめ商品の比較一覧表
| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | サイズ | 製本タイプ | 対応用紙サイズ | 製本厚 | 重量 | 製本時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIC(ジャパンインターナショナルコマース)『卓上製本機 とじ太くん3000(JICTJ3000)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年06月17日時点 での税込価格 |
ビジネスや家庭用に! くるみ製本の小型モデル | 幅390×奥行165×高さ175mm | ホットメルト製本 | A5タテ、B5、A4、B4、A3ヨコ | 最大背幅30mm(1~300枚) | 約1580g | 45秒 |
| アスカ『Asmix パーソナル製本機(B2500)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年06月17日時点 での税込価格 |
手に取りやすい価格が魅力! 本をばらす用途にも | 幅423×奥行90×高さ178mm | くるみ製本 | A4、B5 | 24mm | 約900g | 60秒 |
| KOKUYO(コクヨ)『パーソナル製本機(セキ-GTS500)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年06月17日時点 での税込価格 |
素早くくるみ製本ができるおしゃれな製本機 | 幅360×奥行111×高さ150mm | サ―マタイプ製本 | A4-S長辺とじ | 1~120枚 | - | 40秒 |
| INTER COSMOS(インターコスモス)『製本機 ファーストバック 9(A65FB9)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年06月17日時点 での税込価格 |
1台で4つの製本スタイルが可能! | 幅490×奥行282×高さ318mm | テープ製本、くるみ製本、契約書製本、ハードカバー製本 | A4、A5 | 2~250枚(最大500ページ) | 7.2kg | 30~60秒 |
| MAX(マックス)『電子製本機(TB-1000A)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年6月23日時点 での税込価格 |
1冊約10秒で背表紙にテープが貼れる! | 幅491×奥行415×高さ292mm | テープ製本 | A4短め方向(210mm)〜A4長め方向、A3短め方向(297mm)まで | 6~100枚 | 13.6 g | 10秒 |
| JIC(ジャパンインターナショナルコマース)『とじ太くん flex(45000-Flex)』 |
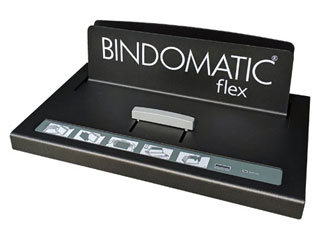
|
※各社通販サイトの 2025年06月17日時点 での税込価格 |
幅広い用紙サイズに対応したコンパクトな1台! | 幅440×奥行275×高さ158mm | ホットメルト製本 | B5、B4、A5、A4、A3 | 1~540枚 | - | - |
| ACCO BRANDS(アコ・ブランズ)『GBC プラスチックリング用 綴じ専用機(GP16DB)』 |

|
※各社通販サイトの 2025年6月23日時点 での税込価格 |
見開きしやすいプラスチックリング専用 | 幅510×奥行330×高さ140mm | プラスチックリングバインド製本 | ~420mm | 50mm(コピー用紙最大410枚程度) | - | - |
通販サイトの最新人気ランキングを参考にする 製本機の売れ筋をチェック
Amazon、楽天市場での製本機の売れ筋ランキングも参考にしてみてください。
※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。
【番外編】製本機と一緒に持っておきたいアイテム
ここでは、番外編として製本機と一緒に持っておくと便利なアイテムをご紹介します。効率も良くなるのでぜひ参考にしてみてください。
清和産業『製本テープ A4カット 業務用(契約書割印用)(50枚入)』
>> Amazonで詳細を見るKOKUYO(コクヨ)『製本カバー 195 A4 5冊入 紺 セホ-CA4DB』
>> Amazonで詳細を見るあなたにおすすめの記事はこちら
出来上がりをイメージして選ぼう
製本機のおすすめ商品を紹介しました。本の完成形をイメージして、適切な製本方法を選びましょう。また、用紙の対応サイズや製本可能な厚みは必ず確認してくださいね。
消耗品や本体価格などコストも考え、使用用途に合っている製本機を見つけてください。
◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。