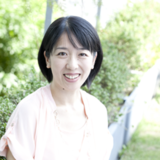| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 容量 | サイズ | だしの取り方 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハリオ『だしポット(DP-600-W)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
電子レンジ対応! 口が広くて洗いやすい | 600ml | 154×115×130mm | 電子レンジ | フタ/ストレーナーフレーム:ポリプロピレン、ストレーナーメッシュ:ポリエステル |
| 曙産業『レンジで美味しいおだし(RE-1510)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
目盛りつきで計量いらず! たっぷり使える大容量 | 1000ml | 120×158×150mm | 電子レンジ | フタ/こし網枠/容器:ポリプロピレン、メッシュ:ポリエステル |
| サラサデザインストア『b2c ウォータージャグ』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
横置きも可能! スリムでおしゃれなデザイン | 1,200ml | 87×87×275mm | 水だし | 本体:メタクリル、ABS、シリコン フィルター:PP、ポリエステル |
| 大塚硝子『耐熱だしポット やさい(19P417)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月12日時点 での税込価格 |
手軽に料理も作れる!簡単だしポット | 500ml | 76mm×160mm | 水だし、電子レンジ、お湯だし | 耐熱ガラス蓋,ポリプロピレン |
| CtoC JAPAN『レンジで簡単だしポット』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月12日時点 での税込価格 |
だしの増産で和食パーティーをしましょう! | 600ml | 19.8x11.8x13cm | お湯だし | 磁器 |
| ハリオ『フィルターインボトル(FIB-75)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
だしポットにも使えるおしゃれなワイン型ボトル | 750ml(実用容量) | 87×84×300mm | 水だし | 注口/栓:シリコンゴム、茶こし:ポリプロピレン |
だしポットの選び方 サイズ・使い方など
まずはだしポットの選び方をチェックしていきましょう。自分の使い方にぴったりのだしポットを選ぶために参考にしてくださいね。
必要な容量を踏まえてサイズを選ぶ
まずは、毎日使っているだしの量を考えてみましょう。たとえば、お味噌汁1杯には約200mlのだしを使います。このためひとり暮らしであれば小さめなものでじゅうぶんですが、3人家族であればお味噌汁だけで約600mlのだしが必要になります。そのほかの料理にも使うなら、さらに余裕を持った大きさを選びたいところ。
また、毎食だしをとるのか、まとめて作り置きしておくのかによっても使い勝手のいい容量は異なります。必要なだしの量と使い方に合わせてだしポットを選んでくださいね。
使い方に合うタイプを選ぶ
思い立ったときにすぐだしを使いたいか、ひと手間かけてでもその都度できたてのだしを使いたいかによって、選ぶべきだしポットは変わってきます。
「水だしタイプ」「お湯だしタイプ」「電子レンジタイプ」の特徴を押さえつつ、自分に合うものを考えてみましょう。
作り置きするなら「水だしタイプ」を
お湯を沸かす作業を省きたい方は、だし素材と水を入れて置いておくだけの「水だしタイプ」のだしポットがぴったり。だしができあがるまでに時間はかかりますが、一晩ほど寝かせておけば、ほとんど手間いらずでだしがとれます。
このタイプはまとめて作って保存できる容量が大きいものが多いので、冷蔵庫の収納スペースも考えつつ選びましょう。なかには横置きできるタイプもありますよ。
一食分ずつ取るならコンパクトな「お湯だしタイプ」
その都度だしをとりたい方は「お湯だしタイプ」が向いています。このタイプは急須のような形のものが多く、お茶を作るように濾し器にだし素材を入れてお湯を入れます。
作り方は、だしをとるのに適しているとされる85℃前後のお湯で5分ほど蒸らすだけ。短時間で新鮮なおいしいだしがとれます。ポットが熱くなるので、取っ手があるもののほうが使いやすいですよ。
便利な「電子レンジタイプ」
「電子レンジタイプ」のだしポットは、水だしとお湯だしのいいとこ取り! だし素材と水をポットに入れて電子レンジにかけるだけなので、お湯を沸かす手間もなく短時間でだしがとれます。
一度冷蔵庫で冷やしただしを容器のまま温め直せるのも便利。耐熱製なので、水だしとお湯だしの両方に使えるところも大きな魅力です。
ストレーナーは底まであるものが使いやすい!
使いやすさを重視するなら、だしポットに内蔵されているストレーナー(濾し器)はなるべく大きめのものを選ぶのがポイント。ストレーナーが底まであるような形なら、少量の水でもしっかりとだし素材が浸かるので必要なぶんだけのだしを作れます。また、この部分はだし素材が詰まりやすいですが、ストレーナーが大きければお手入れがしやすく清潔さをたもてます。
管理栄養士からのメッセージ
だしの取り方で3タイプから選びましょう
だしポットは、だしにこだわって料理をワンランク格上げしたい方、手軽に本格的なだしをとりたい方におすすめしたいアイテムです。だしの取り方によって、水出し、お湯出し、電子レンジの3タイプがあります。
時間はかかってもお湯を沸かす手間を省きたいなら水出しタイプ、短時間で少量のだしをとりたいならお湯出しタイプ、電子レンジで手軽にだしをとりたいなら電子レンジタイプを選びましょう。
だしポットのおすすめ6選
それでは、さっそくおすすめのだしポットをご紹介していきます。使うだしの量や使い方に合う、自分にぴったりのものを探してくださいね。
電子レンジ対応! 口が広くて洗いやすい
電子レンジで使えるハリオのだしポットです。大きくて底まであるストレーナーは、口が広いので奥までしっかり洗えるのが魅力的。また、ストレーナー底はポットのフチに引っ掛けられるようにへこんでいるので最後の一滴までだしがとれます。
キッチンのインテリアに自然になじむシンプルなデザインもポイント。フタは裏返すとストレーナー置きとしても使えますよ。
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| 容量 | 600ml |
|---|---|
| サイズ | 154×115×130mm |
| だしの取り方 | 電子レンジ |
| 材質 | フタ/ストレーナーフレーム:ポリプロピレン、ストレーナーメッシュ:ポリエステル |
| 容量 | 600ml |
|---|---|
| サイズ | 154×115×130mm |
| だしの取り方 | 電子レンジ |
| 材質 | フタ/ストレーナーフレーム:ポリプロピレン、ストレーナーメッシュ:ポリエステル |
目盛りつきで計量いらず! たっぷり使える大容量
作り置きや家族で使うのにも便利な大きめサイズのだしポット。電子レンジにかけるだけで本格だしがとれます。目盛りつきなので作っただしを使った量が一目でわかり、計量の手間が省けて便利。
また、ストレーナーは底が外れるので、だしがらをかんたんに取り出せてお手入れもかんたんです。食洗機と乾燥機にも対応していますよ!
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| 容量 | 1000ml |
|---|---|
| サイズ | 120×158×150mm |
| だしの取り方 | 電子レンジ |
| 材質 | フタ/こし網枠/容器:ポリプロピレン、メッシュ:ポリエステル |
| 容量 | 1000ml |
|---|---|
| サイズ | 120×158×150mm |
| だしの取り方 | 電子レンジ |
| 材質 | フタ/こし網枠/容器:ポリプロピレン、メッシュ:ポリエステル |
横置きも可能! スリムでおしゃれなデザイン
スタイリッシュなボトルとフィルターがセットになったウォータージャグです。だしポットとしてはもちろん、お茶ポットや水だしコーヒーなど幅広い用途に使えます。スリムな角型で、冷蔵庫のドアポケットにもすっぽり収まるのが魅力。
さらに、フタの密閉製が高いので横向きでも保存できます。複数そろえて、だし用、お茶用、コーヒー用などに使い分けてもいいですね。
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| 容量 | 1,200ml |
|---|---|
| サイズ | 87×87×275mm |
| だしの取り方 | 水だし |
| 材質 | 本体:メタクリル、ABS、シリコン フィルター:PP、ポリエステル |
| 容量 | 1,200ml |
|---|---|
| サイズ | 87×87×275mm |
| だしの取り方 | 水だし |
| 材質 | 本体:メタクリル、ABS、シリコン フィルター:PP、ポリエステル |
手軽に料理も作れる!簡単だしポット
この耐熱機能を持つ電子レンジ対応のだしポットは、調理を簡単に楽しくするアイテムです。無機質なガラス素材一色だけではなく、かわいらしい柑橘の絵が描いてあるのもポイント。少ない材料で簡単にだしを作れるので、忙しい日常でも手軽においしい煮物も作れちゃいます!熱湯を注ぐだけで手軽にだしが出せ、レンジでの加熱も可能です。フィルター付きの蓋で、注ぐときもスムーズ。料理の幅を広げるこのアイテムをぜひ手に入れてください!
※各社通販サイトの 2024年11月12日時点 での税込価格
| 容量 | 500ml |
|---|---|
| サイズ | 76mm×160mm |
| だしの取り方 | 水だし、電子レンジ、お湯だし |
| 材質 | 耐熱ガラス蓋,ポリプロピレン |
| 容量 | 500ml |
|---|---|
| サイズ | 76mm×160mm |
| だしの取り方 | 水だし、電子レンジ、お湯だし |
| 材質 | 耐熱ガラス蓋,ポリプロピレン |
だしの増産で和食パーティーをしましょう!
コロンとした見た目が特徴の本商品は、茶こしや内側に目盛りが付いており、急須のような形の磁器製だしポットです。そして、茶こしが大き目なのがポイント。およそ600ccも入るこのだしポットで、お吸い物や卵焼き、煮物など和食には欠かせないだしを簡単に作ることができます。このポットを使って、従来よりも少し手軽に様々な和風料理にチャレンジしてみませんか?
※各社通販サイトの 2024年11月12日時点 での税込価格
| 容量 | 600ml |
|---|---|
| サイズ | 19.8x11.8x13cm |
| だしの取り方 | お湯だし |
| 材質 | 磁器 |
| 容量 | 600ml |
|---|---|
| サイズ | 19.8x11.8x13cm |
| だしの取り方 | お湯だし |
| 材質 | 磁器 |
だしポットにも使えるおしゃれなワイン型ボトル
ハリオのおしゃれなワイン型ボトルです。水出し茶用のボトルですが、注ぎ口の部分にセットされているフィルターがだし素材をしっかり濾してくれるため、だしポットとしても応用が可能です。
お茶や水出しコーヒーのほか、サングリア作りなどにも使えるので、一本持っておくと便利。耐熱製なので熱湯や食洗機にも対応しています。
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格
| 容量 | 750ml(実用容量) |
|---|---|
| サイズ | 87×84×300mm |
| だしの取り方 | 水だし |
| 材質 | 注口/栓:シリコンゴム、茶こし:ポリプロピレン |
| 容量 | 750ml(実用容量) |
|---|---|
| サイズ | 87×84×300mm |
| だしの取り方 | 水だし |
| 材質 | 注口/栓:シリコンゴム、茶こし:ポリプロピレン |
「だしポット」のおすすめ商品の比較一覧表
| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 容量 | サイズ | だしの取り方 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハリオ『だしポット(DP-600-W)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
電子レンジ対応! 口が広くて洗いやすい | 600ml | 154×115×130mm | 電子レンジ | フタ/ストレーナーフレーム:ポリプロピレン、ストレーナーメッシュ:ポリエステル |
| 曙産業『レンジで美味しいおだし(RE-1510)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
目盛りつきで計量いらず! たっぷり使える大容量 | 1000ml | 120×158×150mm | 電子レンジ | フタ/こし網枠/容器:ポリプロピレン、メッシュ:ポリエステル |
| サラサデザインストア『b2c ウォータージャグ』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
横置きも可能! スリムでおしゃれなデザイン | 1,200ml | 87×87×275mm | 水だし | 本体:メタクリル、ABS、シリコン フィルター:PP、ポリエステル |
| 大塚硝子『耐熱だしポット やさい(19P417)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月12日時点 での税込価格 |
手軽に料理も作れる!簡単だしポット | 500ml | 76mm×160mm | 水だし、電子レンジ、お湯だし | 耐熱ガラス蓋,ポリプロピレン |
| CtoC JAPAN『レンジで簡単だしポット』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月12日時点 での税込価格 |
だしの増産で和食パーティーをしましょう! | 600ml | 19.8x11.8x13cm | お湯だし | 磁器 |
| ハリオ『フィルターインボトル(FIB-75)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |
だしポットにも使えるおしゃれなワイン型ボトル | 750ml(実用容量) | 87×84×300mm | 水だし | 注口/栓:シリコンゴム、茶こし:ポリプロピレン |
通販サイトの最新人気ランキングを参考にする だしポットの売れ筋をチェック
楽天市場でのだしポットの売れ筋ランキングも参考にしてみてください。
※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。
本格だしとおいしい味噌で絶品の味噌汁を!
だしポットを取り入れていつもの料理を格上げ!
だしは和食の味を左右する大切な要素。市販のだしの素でもおいしく作れますが、素材からとった繊細なだしの風味はやっぱり格別。だしポットを使えば、大きな鍋やざるを使って煮出さなくても、かんたんに本格的でおいしいだしがとれます。
料理によってだし素材の分量を変えてみたり、お湯の温度や抽出時間にもこだわってみるとより料理が楽しくなってきますよ! ぜひだしポットを取り入れて、いつもの料理を手軽にワンランクアップさせてみてはいかがでしょうか。
◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。