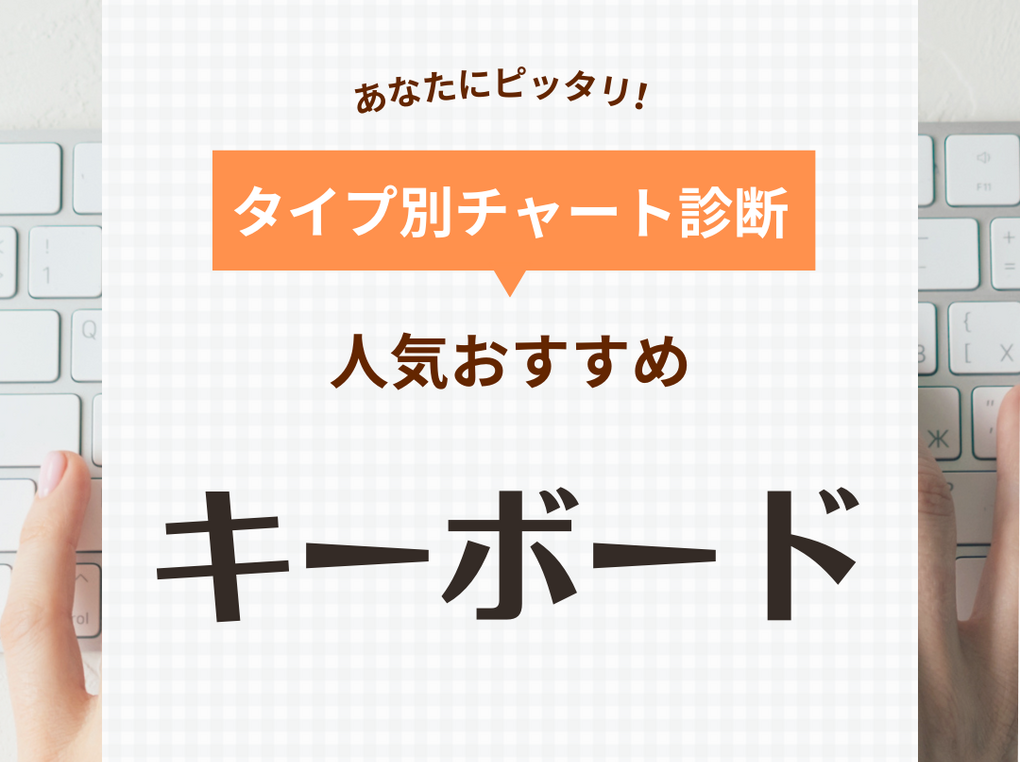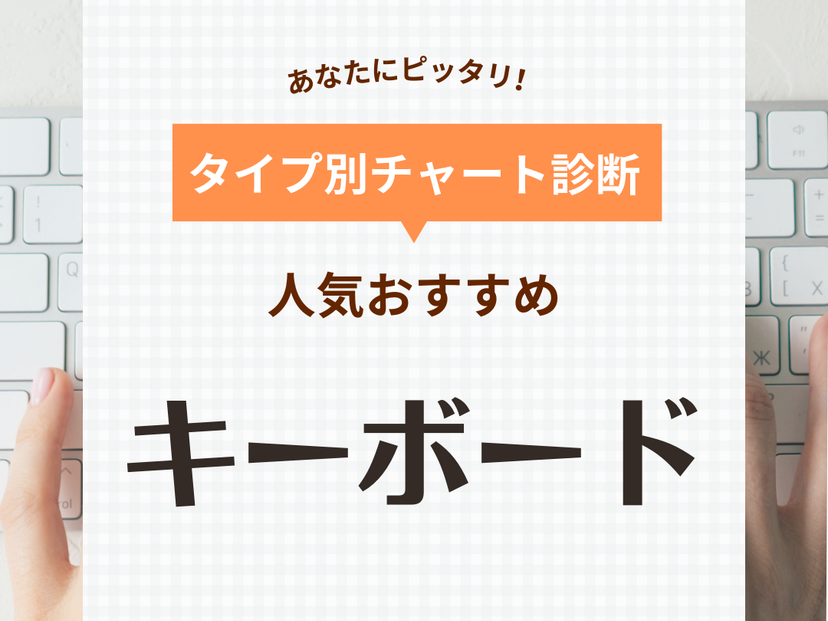| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | キー数/配列 | スイッチ方式 | 押下圧 | キーピッチ/ストローク | テンキー/カーソルキー | 接続方式 | 本体サイズ/本体重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logicool(ロジクール)『WAVE KEYS K820』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |
タイピングの際の負担を減らすキーボード | -/日本語配列 | - | - | キーピッチ:-/ストローク:- | テンキー:あり/カーソルキー:あり | Bluetooth/Logi Bolt | 21.9×37.6×3.1cm/750g |
| Logicool(ロジクール)『PEBBLE KEYS 2(K380sGY)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |
丸いキートップと柔らかなデザインが特長 | 84キー/日本語配列 | - | - | キーピッチ:-/ストローク:- | テンキー:なし/カーソルキー:あり | Bluetooth/Logi Bolt | 12.4×27.9×1.6cm/415g |
| Logicool(ロジクール)『ワイヤレスキーボード(KX1000s)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月12日時点 での税込価格 |
異なるデバイス間で統一した操作感を実現 | 113キー/日本語レイアウト | パンタグラフ | 60±20g | キーピッチ:19mm/ストローク:1.8mm | テンキー:あり/カーソルキー:あり | Bluetooth low energy、USBワイヤレスアダプタ(ロジクールUnifying2.4GHzワイヤレステクノロジー | W430×D149×H32mm /960g |
| Logicool(ロジクール)『ワイヤレスキーボード(K295GP)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |
静音キーボードを探している人はこれ! | 108キー/JIS配列 | メンブレン | 60g | キーピッチ:19/ストローク:3.2mm | テンキー:あり/カーソルキー:あり | USBレシーバー | W441×D149×H18mm/498g |
| Logicool(ロジクール)『MX KEYS S KX800sPG』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |
ショートカット機能を重視するなら! | 83キー・113キー/⽇本語レイアウト | - | 60±20 | 19/1.8 | テンキーなし・テンキーあり/- | ワイヤレス | 296 x 21 x 132mm・430 x 20.5 x 131mm/506.4g・810g |
| Logicool(ロジクール)『ワイヤレス タッチ キーボード(K400 PLUS)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |
カーソル操作もできるキーボード | 84キー/日本語レイアウト | - | - | 18.8/2.7 | テンキーなし/- | ワイヤレス | 37.1 x 15.2 x 3.2 cm/500 g |
| Logicool(ロジクール)『ワイヤレスキーボード(K275)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |
操作性が高いフルサイズ | -/- | - | - | -/- | テンキ―あり/カーソルキーあり | ワイヤレス | 約18×450×155mm/約470g |
| Logicool(ロジクール)『K295サイレント ワイヤレス キーボード(K295OW)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |
タイピング音が気にならない | 108キー/日本語レイアウト | 60 | 19・3.2 | テンキーあり/カーソルキーあり | ワイヤレス | 横441×奥行149×高さ18mm/498 g | |
| Logicool(ロジクール)『Combo Touch(iK1275GRAr)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月12日時点 での税込価格 |
キーボードでタブレット端末を操作できる | 80キー/日本語配列 | シザー(パンタグラフ) | - | キーピッチ:-/ストローク:- | テンキー:なし/カーソルキー:あり | Smart Connector接続 | 22.57×28.56×1.74cm/780g |
| Logicool(ロジクール)『KEYS-TO-GO(iK1042CB)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |
まるで書類のように持ち運べる薄型軽量のキーボード | 78キー/英語配列 | パンタグラフ | - | キーピッチ:17mm/ストローク:1.2mm | テンキー:なし/カーソルキー:あり | Bluetooth | 0.6×24.2×13.7cm/180g |
| ELECOM(エレコム)『Slint(TK-TM10BPBK)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |
持ち運び/複数デバイス使いに便利なキーボード | 83キー/日本語配列 | パンタグラフ | - | キーピッチ:19mm/ストローク:2.0mm | テンキー:なし/カーソルキー:なし | Bluetooth | W29.1×D13.1×H1.7cm/290g |
| ELECOM(エレコム)『キーボードワイヤレス (TK-FDM110M)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |
キー操作が充実していて使い勝手がよい | 109キー/日本語レイアウト | - | - | キーピッチ:19mm/ストローク:2.5mm | テンキー:あり/カーソルキー:あり | USBレシーバー | -/505g |
| ELECOM(エレコム)『トラックボール付きキーボード(TK-TB01DM)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |
トラックボール搭載でマウス操作できる | 108キー/日本語レイアウト | メンブレン | - | キーピッチ:19mm/ストローク:4mm | テンキー:あり/カーソルキー:あり | USBレシーバー | W470×D264×H64mm/1540g |
| ELECOM(エレコム)『有線キーボード(TK-FFCM01BK)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |
コストNo.1!コンパクトさも◎ | 109キー/JIS配列 | メンブレン | - | キーピッチ19mm/キーストローク2.8mm | テンキー:あり/カーソルキー:あり | USB接続 | W435×D128×H23.7mm/563g |
| ELECOM(エレコム)『ワイヤレスキーボード(TK-FBM120KBK)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |
抗菌仕様で清潔に使える! | 109キー/日本語配列 | - | - | 19.0/2.5 | テンキーあり/カーソルキーあり | ワイヤレス | 幅441.5mm×奥行127.6mm×高さ25.0mm(スタンド含まず)/約515g ) |
| Razer(レイザー)『Huntsman V3 Pro』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |
高速連打が可能なラピッドトリガーに対応 | 104キー/英語配列 | 光学式 | 40g | キーピッチ:-/ストローク:- | テンキー:あり/カーソルキー:あり | 有線 | 44.5×13.9×3.9cm/880g |
| Razer(レイザー)『BlackWidow V4 75%』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |
キースイッチの交換でキーボードを自分好みに | -/英語配列 | 光学式 | - | キーピッチ:-/ストローク:- | テンキー:なし/カーソルキー:あり | 有線 | 32.1×15.55×2.4cm/815g |
| Razer(レイザー)『DeathStalker V2 Pro(RZ03-04371400-R3J1)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |
長時間プレイしても快適 | -/日本語配列・英語配列 | Razer リニア薄型オプティカルスイッチ | - | - | なし/カーソルキーあり | ワイヤレス | 13.9 x 35.7 x 2.6 cm/644 g |
| BUFFALO(バッファロー)『ワイヤレス フルキーボード(BSKBW325SBK)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |
優れた耐久性で1000万回の打鍵テストをクリア | 108キー/日本語レイアウト | メンブレン | - | キーピッチ:19mm/ストローク:3mm | テンキー:あり/カーソルキー:あり | USBレシーバ | W443×D152×H31mm/496g |
| BUFFALO(バッファロー)『有線フルキーボード Macモデル(BSKBM01WH)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |
コスパ抜群Macユーザーにおすすめ | 105キー/JIS配列 | パンタグラフ | - | キーピッチ:19mm/キーストローク:2.5mm | テンキー:なし/カーソルキー:あり | USB有線 | W444×D129×H23mm/516g |
| SANWA SUPPLY(サンワサプライ)『マグネット内蔵防水防塵キーボード(SKB-BS8BK)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |
防塵・防水性能に優れたキーボード | 92キー/日本語配列 | - | - | キーピッチ:17mm/ストローク:2.0mm±0.5mm | テンキー:なし/カーソルキー:あり | 有線 | W286×D148×H12.4mm/約650g |
| SANWA SUPPLY(サンワサプライ)『SKB-BT37BK』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |
薄型、軽量でビジネスにも | 109キー/日本語配列 | - | - | 18/3.2 | テンキーあり/カーソルキーあり | ワイヤレス | W423×D122×H30mm/410g |
| Apple(アップル)『Magic keyboard(MLA22J)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |
よりスリムになったMacのためのキーボード | -/日本語レイアウト | シザー | - | - | テンキー:なし/カーソルキー:あり | Bluetooth | W279×D114.9×H10mm/231g |
| Anker(アンカー)『ウルトラスリム Bluetooth ワイヤレスキーボード』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |
シンプル、軽量でコンパクトなのに快適な使い心地 | - | - | - | - | テンキー:なし/カーソルキー:あり | Bluetooth | W284×D122×H185mm/- |
| PFU(ピーエフユー)『HHKB professional HYBRID Type-S』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |
無駄を省いたキー配列と抜群の押し心地 | 69キー/US配列 | 静電容量無接点方式 | 45g | キーピッチ:19.05mm/ストローク:3.8mm | テンキー:なし/カーソルキー:なし | Bluetooth、USB接続 | W294×D120×H40mm/540g |
| Lenovo(レノボ)『ThinkPadトラックポイント キーボード II』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |
マウス機能搭載で作業効率抜群 | 89キー/日本語レイアウト | シザー | - | - | テンキー:なし/カーソルキー:あり | USB有線接続 | W305×D164×H13.5mm/- |
| iClever『ワイヤレスキーボード マウスセット』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |
デザイン性と耐久性に優れたキーボード | -/日本語レイアウト | パンタグラフ | - | 19mm/18mm | あり/あり | USBレシーバー | W366×D125×H16mm/620g |
| Ewin『ワイヤレスキーボード(EW-B009)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月12日時点 での税込価格 |
快適なタイピングと持ち運びのしやすさを両立 | 80キー/US配列 | パンタグラフ式 | - | キーピッチ:19mm | テンキー:なし/カーソルキー:なし | Bluetooth | W295×D120×H20mm/290g |
| 東プレ『REALFORCE GX1 初音ミクコラボカラーデザインモデル(X1UCM1 KB0771)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |
コラボデザインに加えて本格的な機能性も | 91キー/日本語配列 | 静電容量無接点方式 | 45g | キーピッチ:-/ストローク:4.0mm | テンキー:なし/カーソルキー:あり | 有線 | W143.1×L365×H38.2mm/1.3kg |
| CHERRY XTRFY(チェリー エクストリファイ)『CHERRY MX2A赤軸 ゲーミングキーボード(G80-3890HJACN-0)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |
快適なキーストロークで快適なゲームプレイを | -/英語配列 | - | - | キーピッチ:-/ストローク:- | テンキー:あり/カーソルキー:あり | 有線 | W435×D138×H35mm/1120g |
| ASUS(エイスース)『ROG Falchion RX Low Profile』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |
1.0mmの作動点で素早い入力が可能に | -/US配列 | - | - | キーピッチ:-/ストローク:- | テンキー:なし/カーソルキー:あり | Bluetooth/2.4GHz/有線USB | W306×D110×H26.5mm/595g(ケーブルなし) |
あなたにぴったりのキーボードは?

出典:マイナビおすすめナビ

出典:マイナビおすすめナビ
キーボードは、商品によって搭載する機能がさまざま。まず、どんな商品がぴったり合うのか、チェックしてみてくださいね。
診断チャートで簡単チェック!


キーボードは利用する目的や使い方、好みに合う商品を選ぶようにしましょう。上の図を参考にしてみてくださいね。
キーボードの選び方
ITライターの戸津弘貴さんに、キーボードを選ぶときのポイントを教えてもらいました。どのような用途に向いているか、選ぶ基準がわからないなど、キーボード選びに迷っている方は参考にしてください。ポイントは下記。
【1】接続方法で選ぶ(有線・無線)
【2】スイッチの方式
【3】対応OS
【4】使いやすさ
【5】耐久性・防水性
【6】ゲーム用か
それぞれ解説していくのでチェックしてみましょう。
【1】接続方法で選ぶ(有線・無線)
キーボードの接続方法には、有線タイプと無線タイプ(Bluetooth、USBトランシーバー)があります。キーボードによっては、有線と無線の両方に対応するものもあります。無線タイプはBluetoothとUSBトランシーバーにも分けられるのでご確認くださいね。
有線接続
有線接続は、基本的にパソコンとUSB接続で接続します。USB以外にもPS/2規格で接続することができるタイプもあります。有線接続のメリットとして、パソコンと直の接続になるので、通信の遅延が発生しません。
また、有線接続は定期的に充電することが必要となりますが、コードから電源を供給するので残量の電源を気にすることなく使うことができます。
無線接続(Bluetooth、USBトランシーバー)
無線接続には、配線がないのでデスク周りをスッキリできるほか、キーボードの位置を自由にできます。半面、電波の発する機器が多い環境だと接続が不安定だったりします。また、わずかですがキー入力の反応が遅れます。そうした点を気にする人はUSB接続の有線式を選びましょう。
無線接続では、Bluetoothは汎用性が高く、PCでもスマホやタブレットにも使えます。USBレシーバーを使用する方式は、反応速度は有線に近くなりますが、ドライバーソフトのインストールが必要になり、使える機種が限られることもあるので注意しましょう。
【2】キータッチに大きな差が出る、スイッチの方式をチェック!
キーボードは、入力機構によって操作感が異なります。
ノートパソコンに多いパンタグラフ式、安価なキーボードではメンブレン式が多く採用されていますが、ゲーミングキーボードや高級キーボードにはメカニカル式や静電容量式など複雑な機構を採用するものが多いです。押下圧やストロークを選べるなど好みに応じて選べるのも特徴です。
メンブレン式
メンブレン式は、キートップの下にラバードームがあるタイプのスイッチ方式になります。キーストロークが深めになるので、しっかりと押し込むように打つことができます。
シンプルな構造なので、手が出しやすい価格帯に設定されています。デスクトップのキーボードでよく見られるキーボードになります。
パンタグラフ式
パンタグラフ式は、キートップの下にひし形のスプリングがあるタイプのスイッチ方式になります。ソフトな軽いタッチで入力することができるので、長時間の作業でも疲れにくいです。
キーストロークが浅めで、キーボードが薄い構造になるのでノートパソコンなどのキーボードとして使われています。
メカニカル式
メカニカル式は、一つ一つのキーが独立しているので、もしもキーボードのキーに不具合が起きてしまっても故障している箇所だけ修理することで引き続き使えます。
耐久性にも優れているので長く愛用することができ、パソコンゲームやプログラミングなどの用途で心配することなく使えます。
静電容量無接点方式
静電容量無接点方式はキーと基盤の物理的な接触がなく、一定以上近づけると静電気を起こして反応させる方式です。
物理接触がないためキーが摩耗しづらく、耐久性に優れているのが大きな特徴。接点がないのでキータッチが滑らかなのも要点です。また、物理接点がないため、キーの二重押しで発生するチャタリングが発生しないのもいいですね。
しかし、製品の数が少ないことに加え高価。また、静電気を発生させる機構を持っているので、水などの液体には非常に弱いです。
【3】対応OSをチェック
対応OSをチェックしておくのも重要なポイント。WindowsやMacなど、使用しているOSに合わせて選びましょう。
複数のデバイスやOSで使用したい方は、WindowsとMacの両方に対応しているキーボードがおすすめです。そのほか、AndroidやiOS、iPadOSなどに対応したモデルもあるので、併せてチェックしてくださいね。
【4】使いやすさを左右するポイント
使いやすさを左右するポイントをいくつか紹介していきます。利用する場所や好みなどを考慮に入れて選ぶようにしましょう。
コンパクトか利便性か、テンキーやカーソルキーは必要?
ノートパソコンに慣れている人、デスクが狭い場合には、テンキーやカーソルキーがないモデルのほうがコンパクトでいいかもしれませんが、効率を重視する人はテンキーやカーソルキーがあったほうがよいでしょう。最近はテンキーレスでボディが最小限に抑えられている製品も多いです。
また、キーの大きさやキーピッチ(間隔)などが小さすぎない、狭すぎないもののほうがタイプしやすいです。コンパクトさを重視する場合にはこの点も妥協ポイントとなります。
キーピッチは19mm程度が標準
キーピッチとは、キーの中央から、隣のキーの中央までの距離のことです。通常は、18.5mm~19mmが標準になります。
キーピッチが広いと打ちやすいですが、自分の普段から使っているキーボードと同じサイズのものを選んだほうが作業が快適に。キーピッチが狭いとキーボードが小さくなり持ち運びしやすくなります。
好みのキー配列を選ぶ(日本語配列?英語配列?)
一般的にはJIS配列のキーボードが多いですが、プログラマーやデザイナーなど一部の人にはUS配列のキーボードを愛用する人がいます。また、親指シフトなど独自の配列を好む人もいます。
かな入力なのかローマ字入力なのか、文字の入力方式によっても適したキー配列は異なりますので、自分の使い方にあったキー配列を選びましょう。
長時間作業するなら、疲れにくいエルゴノミクスキーボードもあり
エルゴノミクスキーボードとは、人間工学に基づいた設計をしたキーボードのこと。長時間作業していても疲れにくいデザインなので、仕事で一日中タイピングをする人はチェックしてみてください。
特に手や腕、肩が凝りやすいという人におすすめ。中にはキーボードが2つに分離したタイプもあります。両手を目の前に置かなくても、タイピングできる仕様になっています。
【5】耐久性・防水性に優れているか
そもそも本体が壊れにくい仕様・構造か、耐水性はあるかなどはチェックしておくべきです。飲み物を飲みながら作業しているときに、水分がかかってしまうと壊れてしまう商品もあります。また、長期間使っているとキーボードに汚れが付いたり、手垢が媚びれついてしまったりすることもあります。防水対応で流水で丸洗いできるモデルもあるのでチェックしてみましょう。
何回キータップに耐えられるかも確認。最大1,000万回のキーストロークに耐えられるモデルもありますよ。
【6】ゲーム用途なら、専用のゲーミングキーボードが吉
FPSやTPSといったシューティングゲームをするなら、反応速度が速いゲーム専用のモデルを選ぶようにしましょう。独自の機能もあり、複数のキーを同時に押してもしっかり反応する「Nキーロールオーバー」や、1つのキーでアクションを割り当てることができる「キーバインド」などを搭載しているモデルも。
メーカー・ブランドの特徴・比較
どれがいいか迷ってしまったら、メーカーやブランドで商品を絞っていくのもひとつの手。ここでは、人気の高いメーカー・ブランドをいくつか紹介していきます。
Logicool(ロジクール)
ロジクールはスイスイに本社を置くPC周辺機器・デジタルデバイスを展開するメーカー。安価で使いやすい一般家庭向けから高価で高性能なゲーミング向けまで、幅広い商品が人気を集めています。接続方法やキー構造などもバリエーション豊かなので、自分が使いやすいキーボードが見つかるはずですよ。
ELECOM(エレコム)
1986年に創業した日本の大手IT機器メーカー。PCスマホの周辺機器やデジタル機器の開発・販売を行っています。スマホの充電アダプタやケーブルなども展開しているのでなじみのあるブランドかもしれません。
そんなエレコムのキーボードは、リーズナブルな価格ながら安定感のある使い心地で信頼を集めています。薄型やコンパクト、テンキー付きのフルキーボード、ゲーミングキーボードなどいろんなモデルがありますよ。
Razer(レイザー)
レイザーは、アメリカ・カリフォルニア州に本社を置くゲーミングデバイスメーカーです。PCゲームを楽しむ人で知らない人はいないと言えるほど有名。キーボードだけでなく、マウスやヘッドセットなどいろんなゲーム関連機器を展開しています。
キーボードは独自のメカニカルスイッチを採用しており、複数種あるタイピング方法から好みの打鍵感を選ぶことが可能。また各キーにRGBライティングが施されており、自分好みにカスタマイズすることも!
ユーザーが選んだイチオシ5選
ここでは、みんながおすすめする「キーボード」だけを紹介します。商品の口コミはもちろん、コスパや機能性、使いやすさといった評価ポイントも聞いてみたので、各項目にも注目して商品選びの参考にしてください!
その他にもおすすめしたい商品があるよという方は、ぜひ記事後半にある投稿フォームからご紹介をお願いします。

愛用者
PCやiPhoneを切り替えて操作できる!
多くのPCを使ってきました。これは作業効率のいいフルサイズ・フルピッチのキーボードでいつも持ち歩いています。3つの親機(Win・iOS・Mac)を登録でき、ワンタッチで切り替えることができます。(Y.M.さん/男性/69歳/カメラマン)
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格
| コスパ | ★★★★☆ |
|---|---|
| 機能性 | ★★★★★ |
| 使いやすさ | ★★★★★ |
| 総合評価 | 4.7点 |
| コスパ | ★★★★☆ |
|---|---|
| 機能性 | ★★★★★ |
| 使いやすさ | ★★★★★ |
| 総合評価 | 4.7点 |

愛用者
コンパクト・おしゃれ・機能性抜群!
ずっと気になっていて、PCを買い替えるタイミングで購入。ハの字型に曲がり波打つようなデザインに惹かれました。テンキー付きながらコンパクトなので、デスク上のワークスペースも有効活用できます。何より3層構造の高反発パームレストのおかげで疲れ知らず! 作業に集中できますよ。(G.A.さん/男性/44歳/会社員)
【デメリットや気になった点】
ほとんどありませんが強いてあげるとすると、右クリックキーがないことくらいでしょうか。(G.A.さん/男性/44歳/会社員)
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格
| コスパ | ★★★★☆ |
|---|---|
| 機能性 | ★★★★★ |
| 使いやすさ | ★★★★☆ |
| 総合評価 | 4.3点 |
| コスパ | ★★★★☆ |
|---|---|
| 機能性 | ★★★★★ |
| 使いやすさ | ★★★★☆ |
| 総合評価 | 4.3点 |

愛用者
充電不要! 使いやすい有線キーボード
USB接続で充電する必要がないのがいい!Mac配列のフルキーボードなので、普段Mac Bookを使っている人が会社でWindowsのPCを使うときにおすすめです。ホワイトなので清潔感のあるおしゃれな雰囲気!(H.F.さん/男性/49歳/自営業)
【デメリットや気になった点】
テンキー付きなので本体が長めで、スペースを取ってしまいます。(H.F.さん/男性/49歳/自営業)
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格
| コスパ | ★★★★★ |
|---|---|
| 機能性 | ★★★★★ |
| 使いやすさ | ★★★★★ |
| 総合評価 | 5.0点 |
| コスパ | ★★★★★ |
|---|---|
| 機能性 | ★★★★★ |
| 使いやすさ | ★★★★★ |
| 総合評価 | 5.0点 |

愛用者
夜中でも音を気にせず集中! 子育て中に重宝します
操作音が本当に静かなので、カタカタと音をさせずにタイピングできます。子どもを寝かしつけてから仕事をするときも重宝しています。テンキーを備えていますが、配置のおかげで横幅がコンパクトなのもいいですね。(S.S.さん/男性/33歳/会社員)
【デメリットや気になった点】
少しキーの押し込みが独特なので、慣れていないうちはタイピングしにくかったです。(S.S.さん/男性/33歳/会社員)
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格
| コスパ | ★★★★☆ |
|---|---|
| 機能性 | ★★★★★ |
| 使いやすさ | ★★★★☆ |
| 総合評価 | 4.3点 |
| コスパ | ★★★★☆ |
|---|---|
| 機能性 | ★★★★★ |
| 使いやすさ | ★★★★☆ |
| 総合評価 | 4.3点 |

愛用者
バックライトと安定感が魅力
ゲーム中もキーボードがしっかり固定されるようゴム製のパッドがしっかり設置されていて、動きにくく安定しています。メンブレンとキーフレームの耐久性も高く、長時間の使用も安心です。バックライトのモードや色、輝度レベルを自由に選べるのも嬉しいですね。(H.Y.さん/男性/40歳/自営業)
※各社通販サイトの 2024年11月12日時点 での税込価格
| コスパ | ★★★★☆ |
|---|---|
| 機能性 | ★★★★☆ |
| 使いやすさ | ★★★★☆ |
| 総合評価 | 4.0点 |
| コスパ | ★★★★☆ |
|---|---|
| 機能性 | ★★★★☆ |
| 使いやすさ | ★★★★☆ |
| 総合評価 | 4.0点 |
キーボードのおすすめ31選
ご紹介したハイエンド向けキーボードの選び方のポイントをふまえて、ITライターの戸津さんに厳選してもらったおすすめ商品を紹介します。それぞれの機種の機能の違いを見比べて自分の用途に合うものを選んでください。
タイピングの際の負担を減らすキーボード
使用者の負担を減らすことを考えて作られた、エルゴノミックキーボードです。まるで波打っているかのような個性的なデザインをしています。人間工学に基づいて開発されました。キーは八の字型かつ曲線上に配置されており、無理のない姿勢でタイピングすることができます。パームレストには形状記憶素材を使用していて、手首をしっかり支えることで疲れにくくしてくれます。比較的コンパクトなところも嬉しいポイントです。
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格
| キー数/配列 | -/日本語配列 |
|---|---|
| スイッチ方式 | - |
| 押下圧 | - |
| キーピッチ/ストローク | キーピッチ:-/ストローク:- |
| テンキー/カーソルキー | テンキー:あり/カーソルキー:あり |
| 接続方式 | Bluetooth/Logi Bolt |
| 本体サイズ/本体重量 | 21.9×37.6×3.1cm/750g |
| キー数/配列 | -/日本語配列 |
|---|---|
| スイッチ方式 | - |
| 押下圧 | - |
| キーピッチ/ストローク | キーピッチ:-/ストローク:- |
| テンキー/カーソルキー | テンキー:あり/カーソルキー:あり |
| 接続方式 | Bluetooth/Logi Bolt |
| 本体サイズ/本体重量 | 21.9×37.6×3.1cm/750g |
丸いキートップと柔らかなデザインが特長
丸みを帯びた柔らかいデザインが印象的なキーボードです。丸いキートップが指先にしっかりフィットします。カラーはグレージュやローズなど5種類。コンパクトなので持ち運びにも便利です。キーボード上部にはショートカットキーが配置されていて、絵文字の使用やスクリーンショットをすぐに行えます。Easy-Switchに対応しており、3台までのデバイスと接続し、ボタン1つで簡単に切り替えることが可能です。
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格
| キー数/配列 | 84キー/日本語配列 |
|---|---|
| スイッチ方式 | - |
| 押下圧 | - |
| キーピッチ/ストローク | キーピッチ:-/ストローク:- |
| テンキー/カーソルキー | テンキー:なし/カーソルキー:あり |
| 接続方式 | Bluetooth/Logi Bolt |
| 本体サイズ/本体重量 | 12.4×27.9×1.6cm/415g |
| キー数/配列 | 84キー/日本語配列 |
|---|---|
| スイッチ方式 | - |
| 押下圧 | - |
| キーピッチ/ストローク | キーピッチ:-/ストローク:- |
| テンキー/カーソルキー | テンキー:なし/カーソルキー:あり |
| 接続方式 | Bluetooth/Logi Bolt |
| 本体サイズ/本体重量 | 12.4×27.9×1.6cm/415g |

異なるデバイス間で統一した操作感を実現
Mac、Windows、スマホやタブレットなど、異なるデバイスで使えるワイヤレスキーボードです。
パンタグラフ式ですがタイプ感は非常に良好。ノートパソコンなど浅い打鍵感に慣れている人には適しているでしょう。
キーボード本体の左上にあるクリエイティブ入力ダイヤルは、Adobe CCやMicrosoft Office など対応アプリに応じて拡大縮小や設定値の変更などさまざまな機能が用意されています。
※各社通販サイトの 2024年11月12日時点 での税込価格
| キー数/配列 | 113キー/日本語レイアウト |
|---|---|
| スイッチ方式 | パンタグラフ |
| 押下圧 | 60±20g |
| キーピッチ/ストローク | キーピッチ:19mm/ストローク:1.8mm |
| テンキー/カーソルキー | テンキー:あり/カーソルキー:あり |
| 接続方式 | Bluetooth low energy、USBワイヤレスアダプタ(ロジクールUnifying2.4GHzワイヤレステクノロジー |
| 本体サイズ/本体重量 | W430×D149×H32mm /960g |
| キー数/配列 | 113キー/日本語レイアウト |
|---|---|
| スイッチ方式 | パンタグラフ |
| 押下圧 | 60±20g |
| キーピッチ/ストローク | キーピッチ:19mm/ストローク:1.8mm |
| テンキー/カーソルキー | テンキー:あり/カーソルキー:あり |
| 接続方式 | Bluetooth low energy、USBワイヤレスアダプタ(ロジクールUnifying2.4GHzワイヤレステクノロジー |
| 本体サイズ/本体重量 | W430×D149×H32mm /960g |
静音キーボードを探している人はこれ!
シンプルなデザインのフルサイズキーボード。ワイヤレス接続にも関わらず、価格も手頃なため、まず1代目という人にもおすすめ。
最大の魅力は、ロジクール独自のテクノロジーで従来モデルに比べ、操作音を90%削減した点。とても静かなので、会社で使用したい人や、テレワークで家族に負担をかけたくない、という人にはピッタリです。
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格
| キー数/配列 | 108キー/JIS配列 |
|---|---|
| スイッチ方式 | メンブレン |
| 押下圧 | 60g |
| キーピッチ/ストローク | キーピッチ:19/ストローク:3.2mm |
| テンキー/カーソルキー | テンキー:あり/カーソルキー:あり |
| 接続方式 | USBレシーバー |
| 本体サイズ/本体重量 | W441×D149×H18mm/498g |
| キー数/配列 | 108キー/JIS配列 |
|---|---|
| スイッチ方式 | メンブレン |
| 押下圧 | 60g |
| キーピッチ/ストローク | キーピッチ:19/ストローク:3.2mm |
| テンキー/カーソルキー | テンキー:あり/カーソルキー:あり |
| 接続方式 | USBレシーバー |
| 本体サイズ/本体重量 | W441×D149×H18mm/498g |
ショートカット機能を重視するなら!
ロジクールの人気MXシリーズの薄型キーボードがアップデート。マクロ機能を搭載し、複雑なマウス・キー操作をワンクリックで完結することもできます。
ボタンは指先の形状に合うように、くぼんでおり滑らかなタイピングが可能に。操作するときには自動でバックライトが点灯するシステムも搭載。
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格
| キー数/配列 | 83キー・113キー/⽇本語レイアウト |
|---|---|
| スイッチ方式 | - |
| 押下圧 | 60±20 |
| キーピッチ/ストローク | 19/1.8 |
| テンキー/カーソルキー | テンキーなし・テンキーあり/- |
| 接続方式 | ワイヤレス |
| 本体サイズ/本体重量 | 296 x 21 x 132mm・430 x 20.5 x 131mm/506.4g・810g |
| キー数/配列 | 83キー・113キー/⽇本語レイアウト |
|---|---|
| スイッチ方式 | - |
| 押下圧 | 60±20 |
| キーピッチ/ストローク | 19/1.8 |
| テンキー/カーソルキー | テンキーなし・テンキーあり/- |
| 接続方式 | ワイヤレス |
| 本体サイズ/本体重量 | 296 x 21 x 132mm・430 x 20.5 x 131mm/506.4g・810g |
カーソル操作もできるキーボード
タッチパッドを内蔵しており、デスク以外でも操作しやすいワイヤレスキーボード。静音性が高くカチカチ音が気になることも少ないでしょう。
10m先からのワイヤレス操作ができるのもポイントで、ソファなどでリラックスしながらキー操作ができます。
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格
| キー数/配列 | 84キー/日本語レイアウト |
|---|---|
| スイッチ方式 | - |
| 押下圧 | - |
| キーピッチ/ストローク | 18.8/2.7 |
| テンキー/カーソルキー | テンキーなし/- |
| 接続方式 | ワイヤレス |
| 本体サイズ/本体重量 | 37.1 x 15.2 x 3.2 cm/500 g |
| キー数/配列 | 84キー/日本語レイアウト |
|---|---|
| スイッチ方式 | - |
| 押下圧 | - |
| キーピッチ/ストローク | 18.8/2.7 |
| テンキー/カーソルキー | テンキーなし/- |
| 接続方式 | ワイヤレス |
| 本体サイズ/本体重量 | 37.1 x 15.2 x 3.2 cm/500 g |
操作性が高いフルサイズ
テンキーや拡張Fキー、矢印キーなどが付いたフルサイズながら、わかりやすいインターフェイスで快適に操作できるキーボードです。
8つのホットキーが備わり、メールをチェックしたり、音楽を再生・一時停止したり、ボリュームを調整したりするのもラクラク。耐水仕様でうっかり水をこぼした時も安心。
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格
| キー数/配列 | -/- |
|---|---|
| スイッチ方式 | - |
| 押下圧 | - |
| キーピッチ/ストローク | -/- |
| テンキー/カーソルキー | テンキ―あり/カーソルキーあり |
| 接続方式 | ワイヤレス |
| 本体サイズ/本体重量 | 約18×450×155mm/約470g |
| キー数/配列 | -/- |
|---|---|
| スイッチ方式 | - |
| 押下圧 | - |
| キーピッチ/ストローク | -/- |
| テンキー/カーソルキー | テンキ―あり/カーソルキーあり |
| 接続方式 | ワイヤレス |
| 本体サイズ/本体重量 | 約18×450×155mm/約470g |
タイピング音が気にならない
タイピングのノイズを自社製品比で90%も軽減したワイヤレスキーボード。8つのホットキーとテンキーを搭載し、仕事効率もアップするでしょう。
キーボードスタンドの傾斜をつけることもでき、フィット感も良好です。電池式で最大24ヶ月のロングバッテリーなのも嬉しいポイント。
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格
| キー数/配列 | 108キー/日本語レイアウト |
|---|---|
| スイッチ方式 | |
| 押下圧 | 60 |
| キーピッチ/ストローク | 19・3.2 |
| テンキー/カーソルキー | テンキーあり/カーソルキーあり |
| 接続方式 | ワイヤレス |
| 本体サイズ/本体重量 | 横441×奥行149×高さ18mm/498 g |
| キー数/配列 | 108キー/日本語レイアウト |
|---|---|
| スイッチ方式 | |
| 押下圧 | 60 |
| キーピッチ/ストローク | 19・3.2 |
| テンキー/カーソルキー | テンキーあり/カーソルキーあり |
| 接続方式 | ワイヤレス |
| 本体サイズ/本体重量 | 横441×奥行149×高さ18mm/498 g |
キーボードでタブレット端末を操作できる
タブレット端末をまるでノートパソコンのように使用できるキーボードです。ペアリング作業は必要なく、また電池ではなくタブレットの電源を使っているので、接続するだけですぐに使用が可能です。キーボードはケースから取り外し可能で、タブレットで読書をしたりする際には避けておくことができます。さらにショートカットキーを搭載しており、キー1つで画面の明るさや音量調節を簡単にできて便利です。
※各社通販サイトの 2024年11月12日時点 での税込価格
| キー数/配列 | 80キー/日本語配列 |
|---|---|
| スイッチ方式 | シザー(パンタグラフ) |
| 押下圧 | - |
| キーピッチ/ストローク | キーピッチ:-/ストローク:- |
| テンキー/カーソルキー | テンキー:なし/カーソルキー:あり |
| 接続方式 | Smart Connector接続 |
| 本体サイズ/本体重量 | 22.57×28.56×1.74cm/780g |
| キー数/配列 | 80キー/日本語配列 |
|---|---|
| スイッチ方式 | シザー(パンタグラフ) |
| 押下圧 | - |
| キーピッチ/ストローク | キーピッチ:-/ストローク:- |
| テンキー/カーソルキー | テンキー:なし/カーソルキー:あり |
| 接続方式 | Smart Connector接続 |
| 本体サイズ/本体重量 | 22.57×28.56×1.74cm/780g |
まるで書類のように持ち運べる薄型軽量のキーボード
厚さ6mm、重さ180gの薄型軽量のキーボードです。ハンドバッグに入れて簡単に持ち運べます。静音設計なので、カフェなど公共の場で使用しても周りの迷惑になりません。耐水性のあるカバーがキーボードを水こぼれやゴミから守ってくれるため、汚れてもすぐに綺麗にすることができます。お子さまに使っていただく際も安心です。キーボードを使用してスマートフォンに文章を打つ際に便利な、スマートフォンスタンドも付属します。
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格
| キー数/配列 | 78キー/英語配列 |
|---|---|
| スイッチ方式 | パンタグラフ |
| 押下圧 | - |
| キーピッチ/ストローク | キーピッチ:17mm/ストローク:1.2mm |
| テンキー/カーソルキー | テンキー:なし/カーソルキー:あり |
| 接続方式 | Bluetooth |
| 本体サイズ/本体重量 | 0.6×24.2×13.7cm/180g |
| キー数/配列 | 78キー/英語配列 |
|---|---|
| スイッチ方式 | パンタグラフ |
| 押下圧 | - |
| キーピッチ/ストローク | キーピッチ:17mm/ストローク:1.2mm |
| テンキー/カーソルキー | テンキー:なし/カーソルキー:あり |
| 接続方式 | Bluetooth |
| 本体サイズ/本体重量 | 0.6×24.2×13.7cm/180g |
持ち運び/複数デバイス使いに便利なキーボード
軽量・薄型で持ち運びに便利なキーボードです。Bluetooth接続なので、レシーバーやケーブルを持ち歩く必要もありません。コンパクトながら、キーピッチは19mmとタイピングしやすい設計になっています。デバイスは3台までペアリングができて、切り替えボタンで簡単に切り替えが可能です。また、接続先のOSを自動で判別し、適切な配列に切り替える機能も搭載されています。デバイスを複数使用する方にオススメです。
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格
| キー数/配列 | 83キー/日本語配列 |
|---|---|
| スイッチ方式 | パンタグラフ |
| 押下圧 | - |
| キーピッチ/ストローク | キーピッチ:19mm/ストローク:2.0mm |
| テンキー/カーソルキー | テンキー:なし/カーソルキー:なし |
| 接続方式 | Bluetooth |
| 本体サイズ/本体重量 | W29.1×D13.1×H1.7cm/290g |
| キー数/配列 | 83キー/日本語配列 |
|---|---|
| スイッチ方式 | パンタグラフ |
| 押下圧 | - |
| キーピッチ/ストローク | キーピッチ:19mm/ストローク:2.0mm |
| テンキー/カーソルキー | テンキー:なし/カーソルキー:なし |
| 接続方式 | Bluetooth |
| 本体サイズ/本体重量 | W29.1×D13.1×H1.7cm/290g |
キー操作が充実していて使い勝手がよい
日本語配列で数字入力に便利なテンキー付きです。エクセルなどの表計算にもおすすめ。12種類のファンクションキーで作業効率が上がります。キーストロークが2.5mmで、軽いうち心地を実現。薄型なので早打ちにも適しています。
マウス付きでカーソル操作しやすく、BlueLEDを使用しているので場所を選ばず使えます。キーボード・マウスは共通レシーバーを差すだけで使用でき、面倒な作業がいりません。最薄部が12.7mmと見た目もスタイリッシュ。機能とデザインに満足できるキーボードです。
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格
| キー数/配列 | 109キー/日本語レイアウト |
|---|---|
| スイッチ方式 | - |
| 押下圧 | - |
| キーピッチ/ストローク | キーピッチ:19mm/ストローク:2.5mm |
| テンキー/カーソルキー | テンキー:あり/カーソルキー:あり |
| 接続方式 | USBレシーバー |
| 本体サイズ/本体重量 | -/505g |
| キー数/配列 | 109キー/日本語レイアウト |
|---|---|
| スイッチ方式 | - |
| 押下圧 | - |
| キーピッチ/ストローク | キーピッチ:19mm/ストローク:2.5mm |
| テンキー/カーソルキー | テンキー:あり/カーソルキー:あり |
| 接続方式 | USBレシーバー |
| 本体サイズ/本体重量 | -/505g |
トラックボール搭載でマウス操作できる
トラックボール搭載で、マウス操作もできる同時にできるキーボードです。ワイヤレスなので、狭いデスクや外出先でも場所を気にせず使用できます。傾斜のある作りで疲れを軽減、耐久性にも優れています。キーの上部にくぼみを作ることで指にフィットし、無駄な力をかけず確実に入力できます。
2.5mmの大型のトラックボールを使用することで、手垢やゴミの付着を軽減、掃除の頻度も少なく済みます。専用ドライバーにソフトを登録すればワンクリックで切り替えが可能になり、作業効率が上がるでしょう。
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格
| キー数/配列 | 108キー/日本語レイアウト |
|---|---|
| スイッチ方式 | メンブレン |
| 押下圧 | - |
| キーピッチ/ストローク | キーピッチ:19mm/ストローク:4mm |
| テンキー/カーソルキー | テンキー:あり/カーソルキー:あり |
| 接続方式 | USBレシーバー |
| 本体サイズ/本体重量 | W470×D264×H64mm/1540g |
| キー数/配列 | 108キー/日本語レイアウト |
|---|---|
| スイッチ方式 | メンブレン |
| 押下圧 | - |
| キーピッチ/ストローク | キーピッチ:19mm/ストローク:4mm |
| テンキー/カーソルキー | テンキー:あり/カーソルキー:あり |
| 接続方式 | USBレシーバー |
| 本体サイズ/本体重量 | W470×D264×H64mm/1540g |
コストNo.1!コンパクトさも◎
フルキーボードながら、幅が435mmのコンパクト設計で、デスク周りのスペースを有効に活用できます。また、メンプレン方式を採用しており、キーストロークも2.8mmとしっかりとしたタッチ感があるので、押し心地も快適。
最大の魅力は、値段の安さ。この性能でこの価格は中々ありません。まず1台目という人にもおすすめです。
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格
| キー数/配列 | 109キー/JIS配列 |
|---|---|
| スイッチ方式 | メンブレン |
| 押下圧 | - |
| キーピッチ/ストローク | キーピッチ19mm/キーストローク2.8mm |
| テンキー/カーソルキー | テンキー:あり/カーソルキー:あり |
| 接続方式 | USB接続 |
| 本体サイズ/本体重量 | W435×D128×H23.7mm/563g |
| キー数/配列 | 109キー/JIS配列 |
|---|---|
| スイッチ方式 | メンブレン |
| 押下圧 | - |
| キーピッチ/ストローク | キーピッチ19mm/キーストローク2.8mm |
| テンキー/カーソルキー | テンキー:あり/カーソルキー:あり |
| 接続方式 | USB接続 |
| 本体サイズ/本体重量 | W435×D128×H23.7mm/563g |
抗菌仕様で清潔に使える!
抗菌加工されたワイヤレスキーボードで、スマホやタブレット、PCなど3台の端末に同時接続できます。キーを押す重さが従来比で18%軽くなったメンブレン方式を採用。
リーズナブルに購入できる価格で、Windows、macOS、android、iOSなどに対応しています。
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格
| キー数/配列 | 109キー/日本語配列 |
|---|---|
| スイッチ方式 | - |
| 押下圧 | - |
| キーピッチ/ストローク | 19.0/2.5 |
| テンキー/カーソルキー | テンキーあり/カーソルキーあり |
| 接続方式 | ワイヤレス |
| 本体サイズ/本体重量 | 幅441.5mm×奥行127.6mm×高さ25.0mm(スタンド含まず)/約515g ) |
| キー数/配列 | 109キー/日本語配列 |
|---|---|
| スイッチ方式 | - |
| 押下圧 | - |
| キーピッチ/ストローク | 19.0/2.5 |
| テンキー/カーソルキー | テンキーあり/カーソルキーあり |
| 接続方式 | ワイヤレス |
| 本体サイズ/本体重量 | 幅441.5mm×奥行127.6mm×高さ25.0mm(スタンド含まず)/約515g ) |
高速連打が可能なラピッドトリガーに対応
ラピッドトリガー対応のゲーミングキーボードです。指を離してキーが戻り始めた瞬間キーがリセットされるため、FPSなどのゲームで役立つ高速連打が可能です。アクチュエーションポイントは0.1~4.0mmの範囲で調整可能で、自分のプレイスタイルに合わせた設定ができます。また、ラピッドトリガーとアクチュエーションのクイック調整モードも搭載されており、特定のキーを押すだけで簡単に調整が可能です。
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格
| キー数/配列 | 104キー/英語配列 |
|---|---|
| スイッチ方式 | 光学式 |
| 押下圧 | 40g |
| キーピッチ/ストローク | キーピッチ:-/ストローク:- |
| テンキー/カーソルキー | テンキー:あり/カーソルキー:あり |
| 接続方式 | 有線 |
| 本体サイズ/本体重量 | 44.5×13.9×3.9cm/880g |
| キー数/配列 | 104キー/英語配列 |
|---|---|
| スイッチ方式 | 光学式 |
| 押下圧 | 40g |
| キーピッチ/ストローク | キーピッチ:-/ストローク:- |
| テンキー/カーソルキー | テンキー:あり/カーソルキー:あり |
| 接続方式 | 有線 |
| 本体サイズ/本体重量 | 44.5×13.9×3.9cm/880g |
キースイッチの交換でキーボードを自分好みに
ホットスワップ(キースイッチの交換)が可能なゲーミングキーボードです。搭載されているスイッチを他のスイッチに交換して、自分好みのキーボードにすることができます。大きさはコンパクトながらもファンクションキーと矢印キーが揃った75%レイアウトです。キーボードの手前には優れたクッション性のリストレストが付属しており、長時間でも快適にゲームをプレイできます。
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格
| キー数/配列 | -/英語配列 |
|---|---|
| スイッチ方式 | 光学式 |
| 押下圧 | - |
| キーピッチ/ストローク | キーピッチ:-/ストローク:- |
| テンキー/カーソルキー | テンキー:なし/カーソルキー:あり |
| 接続方式 | 有線 |
| 本体サイズ/本体重量 | 32.1×15.55×2.4cm/815g |
| キー数/配列 | -/英語配列 |
|---|---|
| スイッチ方式 | 光学式 |
| 押下圧 | - |
| キーピッチ/ストローク | キーピッチ:-/ストローク:- |
| テンキー/カーソルキー | テンキー:なし/カーソルキー:あり |
| 接続方式 | 有線 |
| 本体サイズ/本体重量 | 32.1×15.55×2.4cm/815g |
長時間プレイしても快適
わずか2.6cmと超薄型仕様のゲーミングキーボード。本シリーズの特性といえば、圧倒的なレスポンスの速さでゲームを有利に運びます。
業界最高水準の2.4GHz接続性能で遅延を限りなく少なくしており、ストレスなくゲームプレイに集中できるはずです。
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格
| キー数/配列 | -/日本語配列・英語配列 |
|---|---|
| スイッチ方式 | Razer リニア薄型オプティカルスイッチ |
| 押下圧 | - |
| キーピッチ/ストローク | - |
| テンキー/カーソルキー | なし/カーソルキーあり |
| 接続方式 | ワイヤレス |
| 本体サイズ/本体重量 | 13.9 x 35.7 x 2.6 cm/644 g |
| キー数/配列 | -/日本語配列・英語配列 |
|---|---|
| スイッチ方式 | Razer リニア薄型オプティカルスイッチ |
| 押下圧 | - |
| キーピッチ/ストローク | - |
| テンキー/カーソルキー | なし/カーソルキーあり |
| 接続方式 | ワイヤレス |
| 本体サイズ/本体重量 | 13.9 x 35.7 x 2.6 cm/644 g |
優れた耐久性で1000万回の打鍵テストをクリア
1000万回の打鍵テストをクリアした耐久性に優れるワイヤレスキーボードです。マウスとセットになっていて、共有のUSBレシーバを差し込むだけで簡単に使用できます。メンブレン方式を採用しているので、しっかりしたキータッチです。
下部にカーブをつけることでスペースキーに幅を持たせ、親指の動きを軽くしてくれます。マウスは好感度のBlueLEDで、使う場所を選びません。シンメトリーなデザインなので、右手・左手どちらでも使えます。
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格
| キー数/配列 | 108キー/日本語レイアウト |
|---|---|
| スイッチ方式 | メンブレン |
| 押下圧 | - |
| キーピッチ/ストローク | キーピッチ:19mm/ストローク:3mm |
| テンキー/カーソルキー | テンキー:あり/カーソルキー:あり |
| 接続方式 | USBレシーバ |
| 本体サイズ/本体重量 | W443×D152×H31mm/496g |
| キー数/配列 | 108キー/日本語レイアウト |
|---|---|
| スイッチ方式 | メンブレン |
| 押下圧 | - |
| キーピッチ/ストローク | キーピッチ:19mm/ストローク:3mm |
| テンキー/カーソルキー | テンキー:あり/カーソルキー:あり |
| 接続方式 | USBレシーバ |
| 本体サイズ/本体重量 | W443×D152×H31mm/496g |
コスパ抜群Macユーザーにおすすめ
commandキーなどMac用キー配列を採用しているため、Macユーザーにおすすめです。テンキーやファンクションキーを装備しておりExcelでの表計算や音量調整、輝度調整なども便利です。
薄型でパンタグラフ方式採用ながらキー底面にメタルシートを採用しており、キータッチは適度な重量感があります。3,000円を下回るお手頃価格も魅力。
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格
| キー数/配列 | 105キー/JIS配列 |
|---|---|
| スイッチ方式 | パンタグラフ |
| 押下圧 | - |
| キーピッチ/ストローク | キーピッチ:19mm/キーストローク:2.5mm |
| テンキー/カーソルキー | テンキー:なし/カーソルキー:あり |
| 接続方式 | USB有線 |
| 本体サイズ/本体重量 | W444×D129×H23mm/516g |
| キー数/配列 | 105キー/JIS配列 |
|---|---|
| スイッチ方式 | パンタグラフ |
| 押下圧 | - |
| キーピッチ/ストローク | キーピッチ:19mm/キーストローク:2.5mm |
| テンキー/カーソルキー | テンキー:なし/カーソルキー:あり |
| 接続方式 | USB有線 |
| 本体サイズ/本体重量 | W444×D129×H23mm/516g |
防塵・防水性能に優れたキーボード
IP68基準を満たしているキーボードです。防塵・防水性能に優れているので、多少のホコリや水がついても安心して使えます。飲み物をこぼしてしまっても、水で洗い流すことが可能です。また、中央下部にあるキーでマウスカーソルの操作が行えます。マウスがいらなくなり、スペースの節約に繋がるので便利です。裏面にはマグネットが内蔵されていて、キーボードを使用しない際に机の側面などに貼り付けておけます。
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格
| キー数/配列 | 92キー/日本語配列 |
|---|---|
| スイッチ方式 | - |
| 押下圧 | - |
| キーピッチ/ストローク | キーピッチ:17mm/ストローク:2.0mm±0.5mm |
| テンキー/カーソルキー | テンキー:なし/カーソルキー:あり |
| 接続方式 | 有線 |
| 本体サイズ/本体重量 | W286×D148×H12.4mm/約650g |
| キー数/配列 | 92キー/日本語配列 |
|---|---|
| スイッチ方式 | - |
| 押下圧 | - |
| キーピッチ/ストローク | キーピッチ:17mm/ストローク:2.0mm±0.5mm |
| テンキー/カーソルキー | テンキー:なし/カーソルキー:あり |
| 接続方式 | 有線 |
| 本体サイズ/本体重量 | W286×D148×H12.4mm/約650g |
薄型、軽量でビジネスにも
PC、スマホ、タブレットなどの端末を同時に3台まで接続できるキーボード。ボタン一つで機器の切り替えが簡単にできるのも嬉しいですね。
静音性が高く、職場や図書館などで作業しても周囲に迷惑をかける心配もありません。
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格
| キー数/配列 | 109キー/日本語配列 |
|---|---|
| スイッチ方式 | - |
| 押下圧 | - |
| キーピッチ/ストローク | 18/3.2 |
| テンキー/カーソルキー | テンキーあり/カーソルキーあり |
| 接続方式 | ワイヤレス |
| 本体サイズ/本体重量 | W423×D122×H30mm/410g |
| キー数/配列 | 109キー/日本語配列 |
|---|---|
| スイッチ方式 | - |
| 押下圧 | - |
| キーピッチ/ストローク | 18/3.2 |
| テンキー/カーソルキー | テンキーあり/カーソルキーあり |
| 接続方式 | ワイヤレス |
| 本体サイズ/本体重量 | W423×D122×H30mm/410g |
よりスリムになったMacのためのキーボード
スタイリッシュなデザインのMac専用キーボードです。薄型のボディは見た目だけでなく指のピッチがスムーズで、打鍵がとても快適です。Bluetooth搭載ワイヤレスで、デスクの上を広々使えます。充電式のバッテリーを内蔵していているので、持ち運びに非常に便利。
シザー式のキー構造は安定性が高く、タイピングも素早く正確になります。Macに自動的に接続するので、購入後すぐに作業ができるのが嬉しいですね。バッテリーのパワーも強く、一度の充電で1か月ほど長持ちします。
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格
| キー数/配列 | -/日本語レイアウト |
|---|---|
| スイッチ方式 | シザー |
| 押下圧 | - |
| キーピッチ/ストローク | - |
| テンキー/カーソルキー | テンキー:なし/カーソルキー:あり |
| 接続方式 | Bluetooth |
| 本体サイズ/本体重量 | W279×D114.9×H10mm/231g |
| キー数/配列 | -/日本語レイアウト |
|---|---|
| スイッチ方式 | シザー |
| 押下圧 | - |
| キーピッチ/ストローク | - |
| テンキー/カーソルキー | テンキー:なし/カーソルキー:あり |
| 接続方式 | Bluetooth |
| 本体サイズ/本体重量 | W279×D114.9×H10mm/231g |
シンプル、軽量でコンパクトなのに快適な使い心地
従来のキーボードの3分の2ほどのコンパクトなサイズで、重さも約200gと軽く持ち運ぶのに便利です。iOS、Windows、Android、Macに対応しています。ワイヤレスなので、オフィスのデスクやカフェなどの狭い場所でも無理なく使えます。
キー1つずつが独立しているので打ちやすく、コンパクトサイズでも快適な使い心地です。電源は単4電池を使用しています。約3か月連続使用が可能というパワーも魅力です。
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格
| キー数/配列 | - |
|---|---|
| スイッチ方式 | - |
| 押下圧 | - |
| キーピッチ/ストローク | - |
| テンキー/カーソルキー | テンキー:なし/カーソルキー:あり |
| 接続方式 | Bluetooth |
| 本体サイズ/本体重量 | W284×D122×H185mm/- |
| キー数/配列 | - |
|---|---|
| スイッチ方式 | - |
| 押下圧 | - |
| キーピッチ/ストローク | - |
| テンキー/カーソルキー | テンキー:なし/カーソルキー:あり |
| 接続方式 | Bluetooth |
| 本体サイズ/本体重量 | W284×D122×H185mm/- |
無駄を省いたキー配列と抜群の押し心地
A4ハーフサイズ強のコンパクトサイズで且つ比較的軽く、有線でも無線でも使用できるので、携帯性が抜群。また、無駄を削ぎ落としたキー配列で、指の動きも最小限になります。
静電容量無接点方式を採用しており、深いストロークと程よいキータッチを実現したのも魅力。押し心地の良いキー入力で、持ち運べるものを探している人におすすめのキーボードです。
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格
| キー数/配列 | 69キー/US配列 |
|---|---|
| スイッチ方式 | 静電容量無接点方式 |
| 押下圧 | 45g |
| キーピッチ/ストローク | キーピッチ:19.05mm/ストローク:3.8mm |
| テンキー/カーソルキー | テンキー:なし/カーソルキー:なし |
| 接続方式 | Bluetooth、USB接続 |
| 本体サイズ/本体重量 | W294×D120×H40mm/540g |
| キー数/配列 | 69キー/US配列 |
|---|---|
| スイッチ方式 | 静電容量無接点方式 |
| 押下圧 | 45g |
| キーピッチ/ストローク | キーピッチ:19.05mm/ストローク:3.8mm |
| テンキー/カーソルキー | テンキー:なし/カーソルキー:なし |
| 接続方式 | Bluetooth、USB接続 |
| 本体サイズ/本体重量 | W294×D120×H40mm/540g |
マウス機能搭載で作業効率抜群
USB有線タイプのキーボード。機能性には定評があり、一度使うとその便利さにリピート買いする人が多い人気商品です。通信に誤差がなく、他のUSBポートに接続する心配がありません。キーボードの真ん中にはトラックポイントを搭載しているので、マウスがなくても自在にカーソルを操れます。
コンパクトなデザインで、シザー式のキーを採用。軽いキータッチで、長時間のタイピングにもおすすめです。キーピッチも人間工学にもとづいて作られています。
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格
| キー数/配列 | 89キー/日本語レイアウト |
|---|---|
| スイッチ方式 | シザー |
| 押下圧 | - |
| キーピッチ/ストローク | - |
| テンキー/カーソルキー | テンキー:なし/カーソルキー:あり |
| 接続方式 | USB有線接続 |
| 本体サイズ/本体重量 | W305×D164×H13.5mm/- |
| キー数/配列 | 89キー/日本語レイアウト |
|---|---|
| スイッチ方式 | シザー |
| 押下圧 | - |
| キーピッチ/ストローク | - |
| テンキー/カーソルキー | テンキー:なし/カーソルキー:あり |
| 接続方式 | USB有線接続 |
| 本体サイズ/本体重量 | W305×D164×H13.5mm/- |
デザイン性と耐久性に優れたキーボード
3.95mmという薄型のボディでとてもスタイリッシュなキーボードです。裏には亜鉛メッキ剛版を使っているので、デザイン性と耐久性に優れています。高速充電に対応し、一度の充電で90時間も使用可能。USBレシーバーはキーボードとマウス共用なので、差し込むだけで使えます。
パンタグラフ方式を採用しているので軽い力で打鍵でき、1.9mmのキーピッチで指もスムーズに動かせストレスなくタイピングできます。静音性に優れているので、外出先での使用や打鍵音が気になる方におすすめです。
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格
| キー数/配列 | -/日本語レイアウト |
|---|---|
| スイッチ方式 | パンタグラフ |
| 押下圧 | - |
| キーピッチ/ストローク | 19mm/18mm |
| テンキー/カーソルキー | あり/あり |
| 接続方式 | USBレシーバー |
| 本体サイズ/本体重量 | W366×D125×H16mm/620g |
| キー数/配列 | -/日本語レイアウト |
|---|---|
| スイッチ方式 | パンタグラフ |
| 押下圧 | - |
| キーピッチ/ストローク | 19mm/18mm |
| テンキー/カーソルキー | あり/あり |
| 接続方式 | USBレシーバー |
| 本体サイズ/本体重量 | W366×D125×H16mm/620g |
快適なタイピングと持ち運びのしやすさを両立
コンパクト、ワイヤレスに特化したEwinらしく、幅295mm、重さ290gとバッグに入れてどこにでも持ち運びラクラクなキーボード。それでいて、キーピッチは19mmと快適なタイピングが可能です。
Bluetoothに対応したパソコンやタブレットであれば、レシーバ無しで接続可能、最大3台までのデバイスをペアリングでき、ワンタッチで使用機器を切り替えることができるのも便利です。
※各社通販サイトの 2024年11月12日時点 での税込価格
| キー数/配列 | 80キー/US配列 |
|---|---|
| スイッチ方式 | パンタグラフ式 |
| 押下圧 | - |
| キーピッチ/ストローク | キーピッチ:19mm |
| テンキー/カーソルキー | テンキー:なし/カーソルキー:なし |
| 接続方式 | Bluetooth |
| 本体サイズ/本体重量 | W295×D120×H20mm/290g |
| キー数/配列 | 80キー/US配列 |
|---|---|
| スイッチ方式 | パンタグラフ式 |
| 押下圧 | - |
| キーピッチ/ストローク | キーピッチ:19mm |
| テンキー/カーソルキー | テンキー:なし/カーソルキー:なし |
| 接続方式 | Bluetooth |
| 本体サイズ/本体重量 | W295×D120×H20mm/290g |
コラボデザインに加えて本格的な機能性も
人気キャラクターとのコラボデザインのゲーミングキーボードです。デザイン性もさることながら、機能面も充実しています。指の動きに合わせてオンオフの切り替わるポイントを調整してくれるため、ゲームで高速入力をしても、キーストロークが浅くて反応してくれないといった心配はありません。任意の組み合わせのキーの同時入力を無効化する機能も搭載されていて、左右移動に使用するAキーとDキーを指定すれば、FPSのストッピング操作に役立ちます。
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格
| キー数/配列 | 91キー/日本語配列 |
|---|---|
| スイッチ方式 | 静電容量無接点方式 |
| 押下圧 | 45g |
| キーピッチ/ストローク | キーピッチ:-/ストローク:4.0mm |
| テンキー/カーソルキー | テンキー:なし/カーソルキー:あり |
| 接続方式 | 有線 |
| 本体サイズ/本体重量 | W143.1×L365×H38.2mm/1.3kg |
| キー数/配列 | 91キー/日本語配列 |
|---|---|
| スイッチ方式 | 静電容量無接点方式 |
| 押下圧 | 45g |
| キーピッチ/ストローク | キーピッチ:-/ストローク:4.0mm |
| テンキー/カーソルキー | テンキー:なし/カーソルキー:あり |
| 接続方式 | 有線 |
| 本体サイズ/本体重量 | W143.1×L365×H38.2mm/1.3kg |
快適なキーストロークで快適なゲームプレイを
キースイッチにCHERRY MX2Aの赤軸を使用し、約1億回のキーストローク寿命を可能にしたゲーミングキーボードです。制震構造のおかげでカタカタ音が鳴りにくく、ゲームに集中しやすくしてくれます。キーストロークの感覚も柔らかいので、長時間ゲームをしていても手が疲れにくく快適です。また、CHERRYソフトウェアでキーボードのライティング、マクロの作成、ショートカットなどのカスタマイズが行えます。
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格
| キー数/配列 | -/英語配列 |
|---|---|
| スイッチ方式 | - |
| 押下圧 | - |
| キーピッチ/ストローク | キーピッチ:-/ストローク:- |
| テンキー/カーソルキー | テンキー:あり/カーソルキー:あり |
| 接続方式 | 有線 |
| 本体サイズ/本体重量 | W435×D138×H35mm/1120g |
| キー数/配列 | -/英語配列 |
|---|---|
| スイッチ方式 | - |
| 押下圧 | - |
| キーピッチ/ストローク | キーピッチ:-/ストローク:- |
| テンキー/カーソルキー | テンキー:あり/カーソルキー:あり |
| 接続方式 | 有線 |
| 本体サイズ/本体重量 | W435×D138×H35mm/1120g |
1.0mmの作動点で素早い入力が可能に
オプティカルスイッチを搭載したゲーミングキーボードです。作動点は1.0mmで、素早く入力してもしっかり反応してくれます。同時に、初期作動力は40gfに設定されているので、誤入力の心配もありません。スイッチのスプリングやステムには潤滑剤を塗布していて、柔らかいクリック感と静音性を実現しました。また、Bluetooth/2.4GHz/有線USBの3通りの方法で接続が可能で、場面に分けて使い分けることができます。
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格
| キー数/配列 | -/US配列 |
|---|---|
| スイッチ方式 | - |
| 押下圧 | - |
| キーピッチ/ストローク | キーピッチ:-/ストローク:- |
| テンキー/カーソルキー | テンキー:なし/カーソルキー:あり |
| 接続方式 | Bluetooth/2.4GHz/有線USB |
| 本体サイズ/本体重量 | W306×D110×H26.5mm/595g(ケーブルなし) |
| キー数/配列 | -/US配列 |
|---|---|
| スイッチ方式 | - |
| 押下圧 | - |
| キーピッチ/ストローク | キーピッチ:-/ストローク:- |
| テンキー/カーソルキー | テンキー:なし/カーソルキー:あり |
| 接続方式 | Bluetooth/2.4GHz/有線USB |
| 本体サイズ/本体重量 | W306×D110×H26.5mm/595g(ケーブルなし) |
通販サイトの最新人気ランキングを参考にする キーボードの売れ筋をチェック
Amazon、楽天市場でのキーボードの売れ筋ランキングも参考にしてみてください。
※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。
机が小さいならキーボードスライダーが便利!
キーボードスライダーとは、パソコンのキーボードを机やデスクトップモニターの下に収納できるアイテム。商品によっては、マウスも一緒にしまえるものもあり、机の上のスペースに余裕ができるのが魅力です。
下記でいくつか商品を紹介するので、チェックしてみてください!
リストレスト付きで長時間のパソコン作業にも
手首の当たる部分にクッションとしてリストレストのついたキーボードスライダーです。手首に机やキーボードスライダーが当たらず、手や腕が疲れにくいのが特徴です。
キーボードを使用しないときは、リストレスト部分を重ねてよりコンパクトに収納することができます。毎日長時間パソコンの画面に向かう人におすすめのキーボードスライダーです。
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格
| サイズ(幅×奥行×高さ) | 60×22.5×10cm |
|---|---|
| 固定方法 | 机上タイプ |
| 耐荷重 | 約20kg |
| 対応できる机の厚さ | - |
| サイズ(幅×奥行×高さ) | 60×22.5×10cm |
|---|---|
| 固定方法 | 机上タイプ |
| 耐荷重 | 約20kg |
| 対応できる机の厚さ | - |
耐荷重が大きく、安定感のあるキーボードスライダー
机に穴を開けずに使える、クランプ式のキーボードスライダーです。耐荷重は7kgと大きく、手の体重をかけても安定感を感じられます。
滑らかなスライダーレールつきなので、机の下からすぐにキーボードを手元に引き寄せられます。反対に、キーボードを使わないときには机の下にしまっておけるので、机を広々と使えるのがメリットです。
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格
| サイズ(幅×奥行×高さ) | 63.5×30.5×17.8cm |
|---|---|
| 固定方法 | クランプ式 |
| 耐荷重 | 7kg |
| 対応できる机の厚さ | 12〜54mm |
| サイズ(幅×奥行×高さ) | 63.5×30.5×17.8cm |
|---|---|
| 固定方法 | クランプ式 |
| 耐荷重 | 7kg |
| 対応できる机の厚さ | 12〜54mm |
ワイドサイズの引き出し付きで作業用にぴったり
キーボード台に引き出しが付属した一石二鳥のキーボードスライダーです。引き出しはノートパソコンが収納できるほどワイドサイズな点がうれしいポイント。
キーボード台が10kg、引き出し部分が5kgと耐荷重が大きいのも魅力です。天板のみのテーブルを作業机や事務机にしたい人にぴったりのキーボードスライダーです。
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格
| サイズ(幅×奥行×高さ) | 最大約81.7×31×22.7cm |
|---|---|
| 固定方法 | クランプ式 |
| 耐荷重 | 10kg |
| 対応できる机の厚さ | 15〜40mm |
| サイズ(幅×奥行×高さ) | 最大約81.7×31×22.7cm |
|---|---|
| 固定方法 | クランプ式 |
| 耐荷重 | 10kg |
| 対応できる机の厚さ | 15〜40mm |
シンプルかつ機能性の高いキーボードスライダー
付属品のないシンプルなデザインが使いやすいキーボードスライダー。コの字の金具で机をはさむクランプ式は、取り付けや机の移動もかんたんにできます。
キーボード台の奥にある穴にコードを通し、机の裏側のごちゃつきを軽減できます。シンプルなデザインと機能性の高さを兼ね備えたキーボードスライダーを探している人にぴったりの商品です。
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格
| サイズ(幅×奥行×高さ) | 約82×31.2×13cm |
|---|---|
| 固定方法 | クランプ式 |
| 耐荷重 | 5kg |
| 対応できる机の厚さ | 10〜40mm |
| サイズ(幅×奥行×高さ) | 約82×31.2×13cm |
|---|---|
| 固定方法 | クランプ式 |
| 耐荷重 | 5kg |
| 対応できる机の厚さ | 10〜40mm |
「キーボード」のおすすめ商品の比較一覧表
| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | キー数/配列 | スイッチ方式 | 押下圧 | キーピッチ/ストローク | テンキー/カーソルキー | 接続方式 | 本体サイズ/本体重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logicool(ロジクール)『WAVE KEYS K820』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |
タイピングの際の負担を減らすキーボード | -/日本語配列 | - | - | キーピッチ:-/ストローク:- | テンキー:あり/カーソルキー:あり | Bluetooth/Logi Bolt | 21.9×37.6×3.1cm/750g |
| Logicool(ロジクール)『PEBBLE KEYS 2(K380sGY)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |
丸いキートップと柔らかなデザインが特長 | 84キー/日本語配列 | - | - | キーピッチ:-/ストローク:- | テンキー:なし/カーソルキー:あり | Bluetooth/Logi Bolt | 12.4×27.9×1.6cm/415g |
| Logicool(ロジクール)『ワイヤレスキーボード(KX1000s)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月12日時点 での税込価格 |
異なるデバイス間で統一した操作感を実現 | 113キー/日本語レイアウト | パンタグラフ | 60±20g | キーピッチ:19mm/ストローク:1.8mm | テンキー:あり/カーソルキー:あり | Bluetooth low energy、USBワイヤレスアダプタ(ロジクールUnifying2.4GHzワイヤレステクノロジー | W430×D149×H32mm /960g |
| Logicool(ロジクール)『ワイヤレスキーボード(K295GP)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |
静音キーボードを探している人はこれ! | 108キー/JIS配列 | メンブレン | 60g | キーピッチ:19/ストローク:3.2mm | テンキー:あり/カーソルキー:あり | USBレシーバー | W441×D149×H18mm/498g |
| Logicool(ロジクール)『MX KEYS S KX800sPG』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |
ショートカット機能を重視するなら! | 83キー・113キー/⽇本語レイアウト | - | 60±20 | 19/1.8 | テンキーなし・テンキーあり/- | ワイヤレス | 296 x 21 x 132mm・430 x 20.5 x 131mm/506.4g・810g |
| Logicool(ロジクール)『ワイヤレス タッチ キーボード(K400 PLUS)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |
カーソル操作もできるキーボード | 84キー/日本語レイアウト | - | - | 18.8/2.7 | テンキーなし/- | ワイヤレス | 37.1 x 15.2 x 3.2 cm/500 g |
| Logicool(ロジクール)『ワイヤレスキーボード(K275)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |
操作性が高いフルサイズ | -/- | - | - | -/- | テンキ―あり/カーソルキーあり | ワイヤレス | 約18×450×155mm/約470g |
| Logicool(ロジクール)『K295サイレント ワイヤレス キーボード(K295OW)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |
タイピング音が気にならない | 108キー/日本語レイアウト | 60 | 19・3.2 | テンキーあり/カーソルキーあり | ワイヤレス | 横441×奥行149×高さ18mm/498 g | |
| Logicool(ロジクール)『Combo Touch(iK1275GRAr)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月12日時点 での税込価格 |
キーボードでタブレット端末を操作できる | 80キー/日本語配列 | シザー(パンタグラフ) | - | キーピッチ:-/ストローク:- | テンキー:なし/カーソルキー:あり | Smart Connector接続 | 22.57×28.56×1.74cm/780g |
| Logicool(ロジクール)『KEYS-TO-GO(iK1042CB)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |
まるで書類のように持ち運べる薄型軽量のキーボード | 78キー/英語配列 | パンタグラフ | - | キーピッチ:17mm/ストローク:1.2mm | テンキー:なし/カーソルキー:あり | Bluetooth | 0.6×24.2×13.7cm/180g |
| ELECOM(エレコム)『Slint(TK-TM10BPBK)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |
持ち運び/複数デバイス使いに便利なキーボード | 83キー/日本語配列 | パンタグラフ | - | キーピッチ:19mm/ストローク:2.0mm | テンキー:なし/カーソルキー:なし | Bluetooth | W29.1×D13.1×H1.7cm/290g |
| ELECOM(エレコム)『キーボードワイヤレス (TK-FDM110M)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |
キー操作が充実していて使い勝手がよい | 109キー/日本語レイアウト | - | - | キーピッチ:19mm/ストローク:2.5mm | テンキー:あり/カーソルキー:あり | USBレシーバー | -/505g |
| ELECOM(エレコム)『トラックボール付きキーボード(TK-TB01DM)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |
トラックボール搭載でマウス操作できる | 108キー/日本語レイアウト | メンブレン | - | キーピッチ:19mm/ストローク:4mm | テンキー:あり/カーソルキー:あり | USBレシーバー | W470×D264×H64mm/1540g |
| ELECOM(エレコム)『有線キーボード(TK-FFCM01BK)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |
コストNo.1!コンパクトさも◎ | 109キー/JIS配列 | メンブレン | - | キーピッチ19mm/キーストローク2.8mm | テンキー:あり/カーソルキー:あり | USB接続 | W435×D128×H23.7mm/563g |
| ELECOM(エレコム)『ワイヤレスキーボード(TK-FBM120KBK)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |
抗菌仕様で清潔に使える! | 109キー/日本語配列 | - | - | 19.0/2.5 | テンキーあり/カーソルキーあり | ワイヤレス | 幅441.5mm×奥行127.6mm×高さ25.0mm(スタンド含まず)/約515g ) |
| Razer(レイザー)『Huntsman V3 Pro』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |
高速連打が可能なラピッドトリガーに対応 | 104キー/英語配列 | 光学式 | 40g | キーピッチ:-/ストローク:- | テンキー:あり/カーソルキー:あり | 有線 | 44.5×13.9×3.9cm/880g |
| Razer(レイザー)『BlackWidow V4 75%』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |
キースイッチの交換でキーボードを自分好みに | -/英語配列 | 光学式 | - | キーピッチ:-/ストローク:- | テンキー:なし/カーソルキー:あり | 有線 | 32.1×15.55×2.4cm/815g |
| Razer(レイザー)『DeathStalker V2 Pro(RZ03-04371400-R3J1)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |
長時間プレイしても快適 | -/日本語配列・英語配列 | Razer リニア薄型オプティカルスイッチ | - | - | なし/カーソルキーあり | ワイヤレス | 13.9 x 35.7 x 2.6 cm/644 g |
| BUFFALO(バッファロー)『ワイヤレス フルキーボード(BSKBW325SBK)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |
優れた耐久性で1000万回の打鍵テストをクリア | 108キー/日本語レイアウト | メンブレン | - | キーピッチ:19mm/ストローク:3mm | テンキー:あり/カーソルキー:あり | USBレシーバ | W443×D152×H31mm/496g |
| BUFFALO(バッファロー)『有線フルキーボード Macモデル(BSKBM01WH)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |
コスパ抜群Macユーザーにおすすめ | 105キー/JIS配列 | パンタグラフ | - | キーピッチ:19mm/キーストローク:2.5mm | テンキー:なし/カーソルキー:あり | USB有線 | W444×D129×H23mm/516g |
| SANWA SUPPLY(サンワサプライ)『マグネット内蔵防水防塵キーボード(SKB-BS8BK)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |
防塵・防水性能に優れたキーボード | 92キー/日本語配列 | - | - | キーピッチ:17mm/ストローク:2.0mm±0.5mm | テンキー:なし/カーソルキー:あり | 有線 | W286×D148×H12.4mm/約650g |
| SANWA SUPPLY(サンワサプライ)『SKB-BT37BK』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |
薄型、軽量でビジネスにも | 109キー/日本語配列 | - | - | 18/3.2 | テンキーあり/カーソルキーあり | ワイヤレス | W423×D122×H30mm/410g |
| Apple(アップル)『Magic keyboard(MLA22J)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |
よりスリムになったMacのためのキーボード | -/日本語レイアウト | シザー | - | - | テンキー:なし/カーソルキー:あり | Bluetooth | W279×D114.9×H10mm/231g |
| Anker(アンカー)『ウルトラスリム Bluetooth ワイヤレスキーボード』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |
シンプル、軽量でコンパクトなのに快適な使い心地 | - | - | - | - | テンキー:なし/カーソルキー:あり | Bluetooth | W284×D122×H185mm/- |
| PFU(ピーエフユー)『HHKB professional HYBRID Type-S』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |
無駄を省いたキー配列と抜群の押し心地 | 69キー/US配列 | 静電容量無接点方式 | 45g | キーピッチ:19.05mm/ストローク:3.8mm | テンキー:なし/カーソルキー:なし | Bluetooth、USB接続 | W294×D120×H40mm/540g |
| Lenovo(レノボ)『ThinkPadトラックポイント キーボード II』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |
マウス機能搭載で作業効率抜群 | 89キー/日本語レイアウト | シザー | - | - | テンキー:なし/カーソルキー:あり | USB有線接続 | W305×D164×H13.5mm/- |
| iClever『ワイヤレスキーボード マウスセット』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |
デザイン性と耐久性に優れたキーボード | -/日本語レイアウト | パンタグラフ | - | 19mm/18mm | あり/あり | USBレシーバー | W366×D125×H16mm/620g |
| Ewin『ワイヤレスキーボード(EW-B009)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月12日時点 での税込価格 |
快適なタイピングと持ち運びのしやすさを両立 | 80キー/US配列 | パンタグラフ式 | - | キーピッチ:19mm | テンキー:なし/カーソルキー:なし | Bluetooth | W295×D120×H20mm/290g |
| 東プレ『REALFORCE GX1 初音ミクコラボカラーデザインモデル(X1UCM1 KB0771)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |
コラボデザインに加えて本格的な機能性も | 91キー/日本語配列 | 静電容量無接点方式 | 45g | キーピッチ:-/ストローク:4.0mm | テンキー:なし/カーソルキー:あり | 有線 | W143.1×L365×H38.2mm/1.3kg |
| CHERRY XTRFY(チェリー エクストリファイ)『CHERRY MX2A赤軸 ゲーミングキーボード(G80-3890HJACN-0)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |
快適なキーストロークで快適なゲームプレイを | -/英語配列 | - | - | キーピッチ:-/ストローク:- | テンキー:あり/カーソルキー:あり | 有線 | W435×D138×H35mm/1120g |
| ASUS(エイスース)『ROG Falchion RX Low Profile』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |
1.0mmの作動点で素早い入力が可能に | -/US配列 | - | - | キーピッチ:-/ストローク:- | テンキー:なし/カーソルキー:あり | Bluetooth/2.4GHz/有線USB | W306×D110×H26.5mm/595g(ケーブルなし) |
キーボードが反応しない時は??
パソコンで文字を入力するためには必要不可欠なキーボードですが、何かの不具合や誤作動で正常に反応しないことがあります。そんなときは、むやみに作業せず原因を調べて対処法を確認しましょう。
主な原因としては、以下のようなことが挙げられます。
・かな入力に切り替わっている
・NumLockが無効または有効になっている
・上書きモードになっている
・Caps Lockが有効になっている
・キーボードがトラブルを起こしている
原因はさまざまで、機種やモデルによっても異なるので購入時に同梱されていた取扱説明書のよくある質問などを読み直してみましょう。
そのほかのキーボードのおすすめ商品はこちらから 【関連記事】
購入の際には種類を間違えないように!
ゲーマーや熟練のパソコンユーザーに限らず、あらゆる人とってキーボードは、操作の正確さや作業の効率に直結する重要なデバイスです。
そんなことを意識せずに普段パソコンを使っているという人も、ぜひ一度、上で挙げたようなキーボードを試してみてください。これまでのタイピングとはまったく異なる快適な入力環境が見つかるかもしれません!
最後に、購入の際には同じ商品シリーズでも、キー配列などの種類違いが多いので間違えないようによく注意しましょう!
おすすめ商品・口コミの投稿はこちら
※メーカーや販売店の方は、ページ下部の「お問い合わせはこちら」から商品情報をお送りください。
ユーザーのおすすめ商品や口コミ情報は、マイナビおすすめナビを閲覧したユーザー、マイナビニュース会員、外部パートナー企業と契約する一般ユーザーからの投稿をもとにしています。
◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。