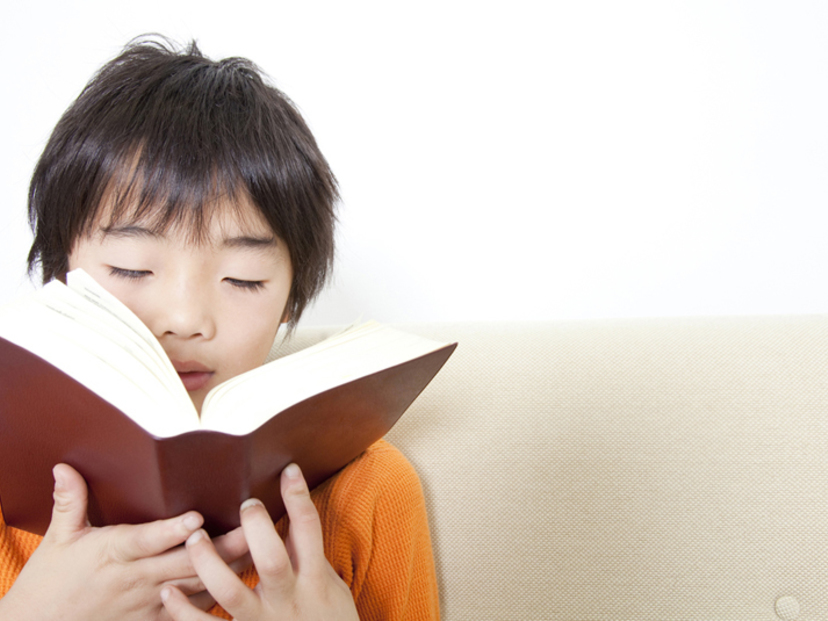| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 出版社 | 著者 | 収録字数 | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学館『例解学習漢字辞典〔第九版・オールカラー版〕』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月5日時点 での税込価格 |
軽さが特徴、中身も充実 | 小学館 | 藤堂明保・編/深谷圭助・編集代表 | 熟語数 約2万5,000語 | 2019年11月27日 |
| 三省堂『例解小学漢字辞典 第六版』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月21日時点 での税込価格 |
製紙会社と共同開発した軽量専用用紙を使用 | 三省堂 | 林四郎、大村はま・監修/月本雅幸、濱口富士雄・編 | 親字数 3,200字 | 2019年11月21日 |
| 光村教育図書『小学新漢字辞典 三訂版』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月19日時点 での税込価格 |
光村の教科書を使っている人にはおすすめ | 光村教育図書 | 監修・甲斐睦朗 | 約3,200字 | 2019年12月1日 |
| 旺文社『小学生のための漢字をおぼえる辞典 第五版』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月19日時点 での税込価格 |
イラストは子どもになじみのある五味太郎さんが担当 | 旺文社 | 川嶋 優・編集/五味太郎・絵 | 新教育漢字1,026字に完全対応 | 2018年3月7日 |
| 小学館『ドラえもん はじめての漢字辞典 第2版』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月19日時点 での税込価格 |
ドラえもんと一緒に学ぶ入門編漢字辞典 | 小学館 | 小学館国語辞典編集部・編 | 新教育漢字1,026字に完全対応 | 2018年11月29日 |
| 学研プラス『学研 現代標準漢和辞典 改訂第4版』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月19日時点 での税込価格 |
中学生の学びに特化した漢和辞典 | 学研プラス | 藤堂明保、加納喜光・編集 | 親字数 7,556字、熟語数 2万5,000語 | 2020年11月26日 |
| 大修館書店『新漢語林 第二版』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月19日時点 での税込価格 |
漢字の歴史に関して内容が充実、高校生におすすめ | 大修館書店 | 鎌田 正、米山寅太郎 | 親字数 1万4,629字、熟語数 5万語 | 2011年1月29日 |
| 学研プラス『漢字源 改訂第六版 特別装丁版』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月19日時点 での税込価格 |
引きやすく内容も充実! 高校生や社会人におすすめ | 学研プラス | 藤堂明保、松本 昭、竹田 晃、加納喜光・編 | 親字1万7,500字、熟語9万6,000語 | 2019年2月19日 |
| 学研プラス『新漢和大字典 普及版』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月19日時点 での税込価格 |
豊富な情報を掲載、深く理解した人におすすめ | 学研プラス | 藤堂明保、加納喜光・編 | 親字数 約2万字、熟語数12万語 | 2005年5月19日 |
| 漢検『漢字辞典』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月19日時点 での税込価格 |
漢検監修の漢字辞典 | 日本漢字能力検定協会 | ー | 6300字 | 2014年10月17日 |
| ベネッセコーポレーション『チャレンジ小学漢字辞典カラー版』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月19日時点 での税込価格 |
子ども目線にこだわった漢字辞典 | ベネッセコーポレーション | 桑原隆 | 1026字 | 2019年12月11日 |
| 学研プラス『新レインボー小学漢字辞典』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月5日時点 での税込価格 |
ディズニーキャラと漢字を学べる | 学研プラス | 加納喜光 | 3150語 | 2019年11月28日 |
| 三省堂『難読漢字辞典』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月19日時点 での税込価格 |
難読漢字をピックアップ | 三省堂 | 佐竹秀雄 | 25000語 | 2009年5月29日 |
あえて 「紙の辞典」を使う必要性とは? ひと目でさまざまな情報をキャッチできる
近年では、スマホアプリや電子辞書が広く普及しつつあるため、アナログで紙の辞典を引く必要性は少なくなっています。しかし紙の辞典を使うと、ひと目でさまざまな情報を見られるメリットがあります。
漢字の意味を調べるだけで終わらず、熟語や類語の解説などもあわせて確認できるため、より多くの知識が得られるでしょう。
「漢字辞典」と「漢和辞典」との違い 必要に応じて使い分けよう
「漢字辞典」のほかに、「漢和辞典」と書かれた商品もたくさん販売されています。どちらも漢字を扱った辞典ですが、一般的に漢字辞典は漢字の意味を調べるためのものです。一方、漢和辞典は意味のほかにも、漢字の成り立ちや熟語などをこまかく確認できるのが特徴です。
漢和辞典は、元々、漢語・漢文を和語で調べるための辞書として作られたので、漢字辞典よりも詳しくてレベルが高い内容になっています。そのため、基礎を学ぶ段階の小学生は漢字辞典、さらに詳しく勉強する中学生以上は漢和辞典が適しているでしょう。
漢字辞典の選び方 索引方法などをチェック!
まずは漢字辞典の選び方をチェックしていきましょう。帝京平成大学 現代ライフ学部 児童学科 講師(元公立小学校教師)・鈴木邦明さんのアドバイスもご紹介しています。ポイントは下記の4つです。
【1】索引で漢字が探しやすいか
【2】筆順・画数などの情報もチェック
【3】学習する年齢に適した見やすさや収録漢字数を選ぶ
【4】持ち運びやすさもチェック
自分の使い方にぴったりの漢字辞典を選ぶために参考にしてみてくださいね。
【1】索引で漢字が探しやすいか確認
漢字辞典を選ぶ際に重要なのは、漢字を調べやすいことです。どんな検索方法ができるかは必ずチェックしましょう。
「音訓索引」「部首索引」「総画索引」ができるか
漢字辞典で調べる方法には、おもに「音訓索引」「部首索引」「総画索引」の3種類があります。
音訓索引は漢字の読み方から、部首索引は漢字の部首から、総画索引は画数から漢字を検索可能です。この3つの調べ方は基本なので、すべてそろっているかは必ず確認しましょう。
また、辞典ごとに索引の掲載順序が異なっているため、自分が使いやすいものをチェックするといいでしょう。
小学生が使うなら、習う学年ごとに漢字を引けると便利
小学生向けの辞典なら、習う学年ごとに漢字が引けるようになっているタイプがおすすめです。小学生は漢字辞典を引くのに慣れていないので、「○年生で習う漢字」というざっくりとした探し方ができると使いやすいはず。
また、習う学年ごとに漢字が一覧で表示されているタイプも便利です。探している漢字だけでなく、近くにある漢字も一緒に学べますよ。
漢検を受けるなら、テーマ別索引があると便利
漢検(日本漢字能力検定)受験に備えた漢字辞典を探しているなら、テーマ別に索引できるタイプがおすすめ。四字熟語や故事、ことわざ、熟字訓、当て字、同訓異義語などの出題が多いので、それに即した勉強ができますよ。
効率よく勉強して知識をどんどん増やしていきましょう!
【2】筆順・画数などの情報もチェック
はじめて漢字を勉強する小学生にとって、筆順や画数は大切な情報です。そのため、とくに小学生用の漢字辞典を探す方は、基本的な情報がきちんと載っているかどうかも、事前に確認しておきましょう。
オンライン上の商品説明で判断がつかないときは、辞典の一部が閲覧できるサイトを探してみるほか、購入者による口コミを参考にしてください。
【3】学習する年齢に適した見やすさや収録漢字数を選ぶ
文部科学省の学習指導要領では、小学校で1,026字、中学校では1,110字の漢字学習が定められています。さらに高校では、これまでに学んだ常用漢字(2,136字)の読み書きに慣れ、文章の中で使えることが目標です。
小学生が使う漢字辞典:漢字についての言い伝えなどが、イラストとともに掲載されていると、パッと目にはいってかりやすい。
中学生が使う漢字辞典:熟語・派生語・類義語などの関連情報も充実していると、そのぶん知識も増えていく。
高校生が使う漢字辞典:漢文の学習もおこなうため、漢字辞典にも漢文の情報があるとさらに便利。
小学生にはイラスト入りがおすすめ
小学生は漢字辞典に慣れていないうえ、漢字ばかり並んでいる辞典を見るのが負担になることも考えられます。そのため、イラストや漫画が入っていたり、カラフルなページになっていたりと、視覚的に楽しめる辞典を選ぶのがおすすめです。
また、学校で使うことを想定して教科書と同じメーカーの辞典を使うという手も。他にも雑学やなぞなぞといった子どもが興味を持つ企画を取り入れているタイプもあります。小学生にとって親しみやすいものを選びましょう。
中学生には漢字の関連情報も充実しているものがおすすめ
小中学校で習う漢字が掲載されている、最低2,136文字以上の収録漢字数がある辞典を選択しましょう。さらに、熟語や派生語、類義語などの関連情報も充実しているタイプなら、より漢字に対する知識と理解を深められますよ。
また、小学生のときに使っていたのと同じ出版社の辞典を使えば、早く使い方に慣れることができるでしょう。
高校生には古文や漢文に関する情報があるものがおすすめ
小口に部首の画数が印刷されています。ほかにも、同画数の部首一覧を本文の全ページの上部に設けるなど、引きやすさの工夫がこらされています。
高校生向けの辞典としては、カバーしている漢字の数が多く、関連情報も充実しているものが良いでしょう。
また、高校生からは本格的な古文・漢文の学習もあるため、漢字辞典にもそれらの関連情報があるとさらに便利です。古文や漢文では普段見慣れない漢字が出てくるため、そうした漢字も掲載されているかをチェックしてくださいね。
【4】持ち運びやすさもチェック
漢字辞典に限ったことではありませんが、子どもが使う学習用具の選び方では、どういった環境で使うのかを考えることがとても大切です。
たとえば、毎日辞書を持ち歩かなければならない子どもにとって、重い辞書は、内容がよかったとしても、使いづらいかもしれません。対して、家だけで使うのであれば、あまり重さは気にせず、内容を重視して選ぶことができます。
こういった「使い方」というものは、その人それぞれで違ってくるため、子どもの環境によって「使いやすい辞書」が違ってきます。どういった使い方をするのか、しっかりと考えてから選びたいものです。
ユーザーが選んだイチオシ4選
ここからは、漢字辞典を購入したことのある人がおすすめするイチオシの商品を紹介。5点満点で「わかりやすさ」「充実度」「携帯性」を評価してもらいました。イチオシのポイント、おすすめする理由や口コミもぜひ参考にしてください!
その他にもおすすめしたい商品があるよという方は、ぜひ記事の下部にある投稿フォームからご紹介をお願いします。

愛用者
カラフルな語呂合わせで楽しく漢字を覚える
息子が小2の時に漢字に苦手意識をもつようになり、自分で調べる力をつけてほしいと思い購入。この辞典は書き順もありイラストもあり、さらに覚えやすい語呂合わせもありとカラフルな仕様で見ていて楽しいです! まだまだ苦手そうですが、宿題のときに用意しておくと息子が自分で検索しているので買ってよかったです。(U.H.さん/女性/37歳/主婦)
【デメリットや気になった点】
全部カラフルなのでマーカーで目立たせたりはできないです。(U.H.さん/女性/37歳/主婦)
※各社通販サイトの 2024年11月21日時点 での税込価格
| わかりやすさ | ★★★★★ |
|---|---|
| 充実度 | ★★★★★ |
| 携帯性 | ★★★★☆ |
| 総合評価 | 4.7点 |
| わかりやすさ | ★★★★★ |
|---|---|
| 充実度 | ★★★★★ |
| 携帯性 | ★★★★☆ |
| 総合評価 | 4.7点 |

愛用者
見るだけで楽しい漢字辞典
まさに、漢字を学びはじめた小さな子どものはじめての一冊にぴったりです。見やすいレイアウトとかわいいイラスト、さらにわかりやすい解説で、楽しく漢字を学べます。眺めているだけでも楽しいので、漢字が苦手な子どもの興味を引き出すのにもおすすめです。(R.T.さん/女性/27歳/会社員)
【デメリットや気になった点】
小学校で習う漢字が収録されているので、中学生以上には向きません。(R.T.さん/女性/27歳/会社員)
※各社通販サイトの 2024年11月19日時点 での税込価格
| わかりやすさ | ★★★★★ |
|---|---|
| 充実度 | ★★★★★ |
| 携帯性 | ★★★★☆ |
| 総合評価 | 4.7点 |
| わかりやすさ | ★★★★★ |
|---|---|
| 充実度 | ★★★★★ |
| 携帯性 | ★★★★☆ |
| 総合評価 | 4.7点 |

愛用者
ワクワクしながら勉強できる
息子が使っています。かわいいイラスト入りでオールカラーなのが見やすく楽しく勉強できているようです。学校用にと購入しましたが、家庭用にも1冊ほしいくらいです。息子も自分から辞書をひくようになり、語彙力も上がっているように感じます。(I.Y.さん/女性/35歳/会社員)
【デメリットや気になった点】
熟語の数が少ないように感じました。(I.Y.さん/女性/35歳/会社員)
※各社通販サイトの 2024年11月19日時点 での税込価格
| わかりやすさ | ★★★★☆ |
|---|---|
| 充実度 | ★★★★★ |
| 携帯性 | ★★★★★ |
| 総合評価 | 4.7点 |
| わかりやすさ | ★★★★☆ |
|---|---|
| 充実度 | ★★★★★ |
| 携帯性 | ★★★★★ |
| 総合評価 | 4.7点 |

愛用者
文字が大きく読みやすい一冊
小学校の授業に使うため購入。色味もはっきりしていて分かりやすく、文字も大きいのでとても見やすいです。壁張りポスターもあるので、子どもが漢字を早く覚えるのに役立っています。知らない言葉がたくさん載っているので、子どもが自ら意欲的に勉強してくれて、たいへん助かっています。(I.R.さん/女性/29歳/会社員)
【デメリットや気になった点】
小学生用なので、大きい子どもには不向きです。(I.R.さん/女性/29歳/会社員)
※各社通販サイトの 2024年11月19日時点 での税込価格
| わかりやすさ | ★★★★★ |
|---|---|
| 充実度 | ★★★★★ |
| 携帯性 | ★★★★☆ |
| 総合評価 | 4.7点 |
| わかりやすさ | ★★★★★ |
|---|---|
| 充実度 | ★★★★★ |
| 携帯性 | ★★★★☆ |
| 総合評価 | 4.7点 |
漢字辞典のおすすめ13選 定番の三省堂や旺文社、小学館など
元公立小学校教師で子どもの教育を研究されている鈴木邦明さんと編集部が選んだおすすめを紹介します。

軽さが特徴、中身も充実
この辞典は特別仕様の紙を使うことで、軽量化が実現されています。小学生はふだんから荷物が重いので、学校に漢字辞典を持って行かなければならないときなどにとても役立ちます。
この漢字辞典は「辞書引き学習」で有名な深谷圭助先生が編集されているもので、中身もとても充実。ふせんを貼りやすいレイアウトになっていることも特色のひとつです。オールカラーでイラスト、写真を多用し、見やすいデザインとなっているため、文字だけではイメージしにくいものの理解がしやすくなります。
また、約25,000個の熟語が収録されており、子どもが作文を書く際などにも役立ちます。
※各社通販サイトの 2025年2月5日時点 での税込価格
| 出版社 | 小学館 |
|---|---|
| 著者 | 藤堂明保・編/深谷圭助・編集代表 |
| 収録字数 | 熟語数 約2万5,000語 |
| 発売日 | 2019年11月27日 |
| 出版社 | 小学館 |
|---|---|
| 著者 | 藤堂明保・編/深谷圭助・編集代表 |
| 収録字数 | 熟語数 約2万5,000語 |
| 発売日 | 2019年11月27日 |

製紙会社と共同開発した軽量専用用紙を使用
小学館の『例解学習漢字辞典』同様、軽さが特徴です。製紙会社と新たに共同開発した専用の用紙を使用し、軽さを実現しています。漢字に関しては、全常用漢字、全人名漢字、よく使われる表外漢字を合計3,200字収録。それぞれの漢字において用例を重視しており、わかりやすさ、理解のしやすさへの配慮がなされています。例文が多いため、子どもが作文に取り組む際などにもとても役立つでしょう。
漢字の学習では、単にその漢字や熟語が書けるだけでなく、文章のなかで使えるということが大切です。用例が充実しているこの漢字辞典は、そういった学びを深める際に役立ちます。
※各社通販サイトの 2024年11月21日時点 での税込価格
| 出版社 | 三省堂 |
|---|---|
| 著者 | 林四郎、大村はま・監修/月本雅幸、濱口富士雄・編 |
| 収録字数 | 親字数 3,200字 |
| 発売日 | 2019年11月21日 |
| 出版社 | 三省堂 |
|---|---|
| 著者 | 林四郎、大村はま・監修/月本雅幸、濱口富士雄・編 |
| 収録字数 | 親字数 3,200字 |
| 発売日 | 2019年11月21日 |

光村の教科書を使っている人にはおすすめ
小学校の国語の教科書も出版している「光村」の漢字辞典です。光村の教科書を使っている子どもにとっては、こちらの漢字辞典も使いやすいのではないでしょうか。
出版社が出版物(教科書、辞典など)を作成する際には、その出版社のテイストや、大事だと思っている部分が形となって表れます。そのため、学校でふだんから使っている「教科書」と、漢字の調べ物などで使う「漢字辞典」の出版社が同じであるということは大きなメリットのひとつです。
また、こちらの漢字辞典は、身につけたい「重要語」を大きく表示したり、「和語」「ことわざ」「慣用句」「四字熟語」などを多数収録しているなどの特徴もあります。
※各社通販サイトの 2024年11月19日時点 での税込価格
| 出版社 | 光村教育図書 |
|---|---|
| 著者 | 監修・甲斐睦朗 |
| 収録字数 | 約3,200字 |
| 発売日 | 2019年12月1日 |
| 出版社 | 光村教育図書 |
|---|---|
| 著者 | 監修・甲斐睦朗 |
| 収録字数 | 約3,200字 |
| 発売日 | 2019年12月1日 |

イラストは子どもになじみのある五味太郎さんが担当
イラストは有名な絵本作家の五味太郎さんが担当されています。子どもにとって、とてもなじみのあるイラストなので、親近感を覚えるでしょう。収録されているすべての漢字にイラストが添えられています。
五味さんの絵本を小さなころから何度も読んでいる子どもにとっては、この漢字辞典は絵本のようなものにも感じられるかもしれません。絵本を読むように漢字辞典に接するなかで、自然と漢字や言葉についての知識が身についていくことでしょう。
また、小学校低学年から使うことを考え、すべての漢字にふりがなが振られています。「ことわざ」「慣用句」「故事成語」なども多数掲載しており、学びが広がります。
※各社通販サイトの 2024年11月19日時点 での税込価格
| 出版社 | 旺文社 |
|---|---|
| 著者 | 川嶋 優・編集/五味太郎・絵 |
| 収録字数 | 新教育漢字1,026字に完全対応 |
| 発売日 | 2018年3月7日 |
| 出版社 | 旺文社 |
|---|---|
| 著者 | 川嶋 優・編集/五味太郎・絵 |
| 収録字数 | 新教育漢字1,026字に完全対応 |
| 発売日 | 2018年3月7日 |

ドラえもんと一緒に学ぶ入門編漢字辞典
小学校低学年(1、2年生)の漢字は1ページにひとつだけ載せるなど、入門編の漢字辞典として、分かりやすくまとめられています。
「とめ、はね、はらい」などをドラえもんやのび太くんがわかりやすく説明してくれるほか、「にている漢字」「とくべつな読み方をする漢字」「この字のヒミツ」など、子どもが興味を持つ内容がたくさん収録されています。小学校低学年や、あまり漢字などが得意ではないと感じている子どもにおすすめ。はじめて購入する漢字辞典としてもピッタリです。
※各社通販サイトの 2024年11月19日時点 での税込価格
| 出版社 | 小学館 |
|---|---|
| 著者 | 小学館国語辞典編集部・編 |
| 収録字数 | 新教育漢字1,026字に完全対応 |
| 発売日 | 2018年11月29日 |
| 出版社 | 小学館 |
|---|---|
| 著者 | 小学館国語辞典編集部・編 |
| 収録字数 | 新教育漢字1,026字に完全対応 |
| 発売日 | 2018年11月29日 |

中学生の学びに特化した漢和辞典
漢字辞典は一般的に「小学生向け」と「中・高校生向け」で分けられることが多いです。そのため、中学生が漢和辞典を使おうとした場合、少し難しさを感じてしまう場合があります。そんななか、この漢和辞典は中学生向けに作られています。
中学の教科書に対応し、漢詩や漢文をコラムとして掲載しています。また、辞典に慣れていない人でも読みやすいように、ふりがなの位置が文字の横(通常は文字の下)になっています。
※各社通販サイトの 2024年11月19日時点 での税込価格
| 出版社 | 学研プラス |
|---|---|
| 著者 | 藤堂明保、加納喜光・編集 |
| 収録字数 | 親字数 7,556字、熟語数 2万5,000語 |
| 発売日 | 2020年11月26日 |
| 出版社 | 学研プラス |
|---|---|
| 著者 | 藤堂明保、加納喜光・編集 |
| 収録字数 | 親字数 7,556字、熟語数 2万5,000語 |
| 発売日 | 2020年11月26日 |

漢字の歴史に関して内容が充実、高校生におすすめ
この辞典の特長は「引きやすさ」です。部首を間違えても、調べている漢字にたどり着くことができるよう、参照見出しを多く掲載しています。
また、漢字の歴史についてとても詳しく書かれており、甲骨(こうこつ)文、金文などが約6,000収録されています。加えて高校の教科書の漢文教材を詳しく調査し、頻出漢字を掲載しています。
※各社通販サイトの 2024年11月19日時点 での税込価格
| 出版社 | 大修館書店 |
|---|---|
| 著者 | 鎌田 正、米山寅太郎 |
| 収録字数 | 親字数 1万4,629字、熟語数 5万語 |
| 発売日 | 2011年1月29日 |
| 出版社 | 大修館書店 |
|---|---|
| 著者 | 鎌田 正、米山寅太郎 |
| 収録字数 | 親字数 1万4,629字、熟語数 5万語 |
| 発売日 | 2011年1月29日 |

引きやすく内容も充実! 高校生や社会人におすすめ
この辞典はとても引きやすく作られています。小口に部首画数が印刷されていることや音訓索引に歴史的仮名遣いが掲載されていることなどです。また、内容も充実しており、親字1万7,500字、熟語9万6,000語、古代文字4,300点など、非常に多くの言葉が収録されています。
辞典の使い勝手のよさは学習の質に大きく影響を与えます。高校での学習だけではなく、卒業後、社会人になってもずっと使うことができる本格的な辞典です。ケースと表紙には人気絵師の「へびつかい」さんのイラストを採用。雰囲気ある装丁に仕上がっています。
※各社通販サイトの 2024年11月19日時点 での税込価格
| 出版社 | 学研プラス |
|---|---|
| 著者 | 藤堂明保、松本 昭、竹田 晃、加納喜光・編 |
| 収録字数 | 親字1万7,500字、熟語9万6,000語 |
| 発売日 | 2019年2月19日 |
| 出版社 | 学研プラス |
|---|---|
| 著者 | 藤堂明保、松本 昭、竹田 晃、加納喜光・編 |
| 収録字数 | 親字1万7,500字、熟語9万6,000語 |
| 発売日 | 2019年2月19日 |

豊富な情報を掲載、深く理解した人におすすめ
一般向け漢和辞典です。2,392ページと他の辞典と比べてもページ数が多く、非常に多くの情報を掲載しています。
親字は約2万字、熟語は12万語となっています。篆文(てんぶん)を多数追加、JIS第1〜4水準・補助漢字の文字コードやUnicodeも記載されており、専門的なことを調べる際にも便利です。
※各社通販サイトの 2024年11月19日時点 での税込価格
| 出版社 | 学研プラス |
|---|---|
| 著者 | 藤堂明保、加納喜光・編 |
| 収録字数 | 親字数 約2万字、熟語数12万語 |
| 発売日 | 2005年5月19日 |
| 出版社 | 学研プラス |
|---|---|
| 著者 | 藤堂明保、加納喜光・編 |
| 収録字数 | 親字数 約2万字、熟語数12万語 |
| 発売日 | 2005年5月19日 |
漢検監修の漢字辞典
漢字能力を示す検定である漢検。漢検の受験のために大人になってから感じの勉強を始めたという方も多いのではないでしょうか。そんな方におすすめなのが、漢検が監修したこちらの漢字辞典です。
新常用漢字表にも対応しており、見出しの字が大きくなっていますので使いやすいのが特徴となっています。とても引きやすいのでずっと使える漢字辞典となっています。
※各社通販サイトの 2024年11月19日時点 での税込価格
| 出版社 | 日本漢字能力検定協会 |
|---|---|
| 著者 | ー |
| 収録字数 | 6300字 |
| 発売日 | 2014年10月17日 |
| 出版社 | 日本漢字能力検定協会 |
|---|---|
| 著者 | ー |
| 収録字数 | 6300字 |
| 発売日 | 2014年10月17日 |
子ども目線にこだわった漢字辞典
タイトルからもわかるとおり、子ども向けの感じ辞典です。子どもが使いやすい漢字辞典を作るために、徹底的に子ども目線にこだわっています。文字の見やすさや引きやすさはもちろんのこと、小学生にとってのわかりやすさを重視して、1字1字が丁寧に解説されています。カラーイラストや写真なども多数掲載されていますので、楽しく漢字を学べます。
※各社通販サイトの 2024年11月19日時点 での税込価格
| 出版社 | ベネッセコーポレーション |
|---|---|
| 著者 | 桑原隆 |
| 収録字数 | 1026字 |
| 発売日 | 2019年12月11日 |
| 出版社 | ベネッセコーポレーション |
|---|---|
| 著者 | 桑原隆 |
| 収録字数 | 1026字 |
| 発売日 | 2019年12月11日 |
ディズニーキャラと漢字を学べる
ディズニーキャラクターと一緒に楽しみながら漢字を学ぶことのできる漢字辞典となっています。小学生向けの漢字辞典ですが、収録されている熟語もかなり多いので、長く使うことのできる漢字辞典となっています。
カラーイラストや、漢字の成り立ちといったさまざまなコンテンツが収録されていますので、読み物としても楽しめる漢字辞典です。
※各社通販サイトの 2025年2月5日時点 での税込価格
| 出版社 | 学研プラス |
|---|---|
| 著者 | 加納喜光 |
| 収録字数 | 3150語 |
| 発売日 | 2019年11月28日 |
| 出版社 | 学研プラス |
|---|---|
| 著者 | 加納喜光 |
| 収録字数 | 3150語 |
| 発売日 | 2019年11月28日 |
難読漢字をピックアップ
その名の通り、難読漢字をピックアップしてまとめた漢字辞典となっています。日常生活の中で目にする機会の多い読みにくい字や、間違えやすい字や言葉をピックアップして25000語を収録しています。
部首や音訓索引、総画索引などさまざまな引き方ができますので、よく目にするものの読みなどを素早く確認することができます。
※各社通販サイトの 2024年11月19日時点 での税込価格
| 出版社 | 三省堂 |
|---|---|
| 著者 | 佐竹秀雄 |
| 収録字数 | 25000語 |
| 発売日 | 2009年5月29日 |
| 出版社 | 三省堂 |
|---|---|
| 著者 | 佐竹秀雄 |
| 収録字数 | 25000語 |
| 発売日 | 2009年5月29日 |
「漢字辞典」のおすすめ商品の比較一覧表
| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 出版社 | 著者 | 収録字数 | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学館『例解学習漢字辞典〔第九版・オールカラー版〕』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月5日時点 での税込価格 |
軽さが特徴、中身も充実 | 小学館 | 藤堂明保・編/深谷圭助・編集代表 | 熟語数 約2万5,000語 | 2019年11月27日 |
| 三省堂『例解小学漢字辞典 第六版』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月21日時点 での税込価格 |
製紙会社と共同開発した軽量専用用紙を使用 | 三省堂 | 林四郎、大村はま・監修/月本雅幸、濱口富士雄・編 | 親字数 3,200字 | 2019年11月21日 |
| 光村教育図書『小学新漢字辞典 三訂版』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月19日時点 での税込価格 |
光村の教科書を使っている人にはおすすめ | 光村教育図書 | 監修・甲斐睦朗 | 約3,200字 | 2019年12月1日 |
| 旺文社『小学生のための漢字をおぼえる辞典 第五版』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月19日時点 での税込価格 |
イラストは子どもになじみのある五味太郎さんが担当 | 旺文社 | 川嶋 優・編集/五味太郎・絵 | 新教育漢字1,026字に完全対応 | 2018年3月7日 |
| 小学館『ドラえもん はじめての漢字辞典 第2版』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月19日時点 での税込価格 |
ドラえもんと一緒に学ぶ入門編漢字辞典 | 小学館 | 小学館国語辞典編集部・編 | 新教育漢字1,026字に完全対応 | 2018年11月29日 |
| 学研プラス『学研 現代標準漢和辞典 改訂第4版』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月19日時点 での税込価格 |
中学生の学びに特化した漢和辞典 | 学研プラス | 藤堂明保、加納喜光・編集 | 親字数 7,556字、熟語数 2万5,000語 | 2020年11月26日 |
| 大修館書店『新漢語林 第二版』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月19日時点 での税込価格 |
漢字の歴史に関して内容が充実、高校生におすすめ | 大修館書店 | 鎌田 正、米山寅太郎 | 親字数 1万4,629字、熟語数 5万語 | 2011年1月29日 |
| 学研プラス『漢字源 改訂第六版 特別装丁版』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月19日時点 での税込価格 |
引きやすく内容も充実! 高校生や社会人におすすめ | 学研プラス | 藤堂明保、松本 昭、竹田 晃、加納喜光・編 | 親字1万7,500字、熟語9万6,000語 | 2019年2月19日 |
| 学研プラス『新漢和大字典 普及版』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月19日時点 での税込価格 |
豊富な情報を掲載、深く理解した人におすすめ | 学研プラス | 藤堂明保、加納喜光・編 | 親字数 約2万字、熟語数12万語 | 2005年5月19日 |
| 漢検『漢字辞典』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月19日時点 での税込価格 |
漢検監修の漢字辞典 | 日本漢字能力検定協会 | ー | 6300字 | 2014年10月17日 |
| ベネッセコーポレーション『チャレンジ小学漢字辞典カラー版』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月19日時点 での税込価格 |
子ども目線にこだわった漢字辞典 | ベネッセコーポレーション | 桑原隆 | 1026字 | 2019年12月11日 |
| 学研プラス『新レインボー小学漢字辞典』 |

|
※各社通販サイトの 2025年2月5日時点 での税込価格 |
ディズニーキャラと漢字を学べる | 学研プラス | 加納喜光 | 3150語 | 2019年11月28日 |
| 三省堂『難読漢字辞典』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月19日時点 での税込価格 |
難読漢字をピックアップ | 三省堂 | 佐竹秀雄 | 25000語 | 2009年5月29日 |
子どもが漢字辞典を違和感なく使うには、漢字辞典と国語辞典が同じ出版社だと使いやすくなります。また、出版社が同じであれば、レイアウトや説明の仕方なども同じであることが多いので、子どもにとって違和感なく使うことができます。すでに国語辞典が手元にある場合には、それと合わせるといいでしょう。
なお、同じ考え方で、学校の国語の教科書と同じ出版社の漢字辞典があれば、それにすることもおすすめです。
通販サイトの最新人気ランキングを参考にする 漢字辞典の売れ筋をチェック
Amazonでの漢字辞典の売れ筋ランキングも参考にしてみてください。
※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。
漢字辞典のアプリやウェブサイトもおすすめ! 外出先でササッと調べるなら
紙の辞典は家で使って、外出先では手軽に調べられるスマホアプリを利用するのもおすすめ。紙媒体のように直接辞典にメモ書きや付箋を残せないといったデメリットもありますが、いつでも気軽にササッと調べものをするには便利ですよ。必要に応じて使い分けてみてはいかがでしょうか?
ウェブサイトでは漢字辞典オンラインがおすすめです。
漢字辞典に関するQ&A よくある質問


漢字辞典は、言葉の意味や使い方、書き方を調べるのに使うのに対し、国語辞典は、言葉の意味や使い方を説明したものになります。


必ずしも間違っているとは言えません。辞書に載っていない漢字のなかには、書き手が誤って書き記しているケースと社会的な習慣として一部で使われているものなどがあります。
俗字や略字、書写体などと呼ばれるものがそれです。これらは辞書には登録されませんが、辞書に載っている感じのなかにも誤字があえて掲載されていたりします。
漢字辞典とあわせて漢字ドリルや漢検問題集もチェック 【関連記事】小学生の中学受験にも役立つ
漢字辞典は子どもの学びの武器 最後に
とくに子どもにとっての漢字辞典は、国語辞典などと同様、学びの「武器」です。すぐれたもの、その子どもに合ったものを選びたいものです。
漢字辞典は、国語辞典、国語の教科書などと密接に関連しています。揃えられるようであれば、出版社をそろえることで、子どもの使い勝手が向上し、学力の向上に役立てることができます。
また、持ち運びをするのかしないのかということも大きなポイントです。辞書を使う子どもは、日ごろからたくさんの荷物を持って登下校しています。辞典を学校に持っていく必要があるのであれば、軽めのものを選んだほうがいいかもしれません。
おすすめ商品・口コミの投稿はこちら
※メーカーや販売店の方は、ページ下部の「お問い合わせはこちら」から商品情報をお送りください。
ユーザーのおすすめ商品や口コミ情報は、マイナビおすすめナビを閲覧したユーザー、マイナビニュース会員、外部パートナー企業と契約する一般ユーザーからの投稿をもとにしています。
◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。