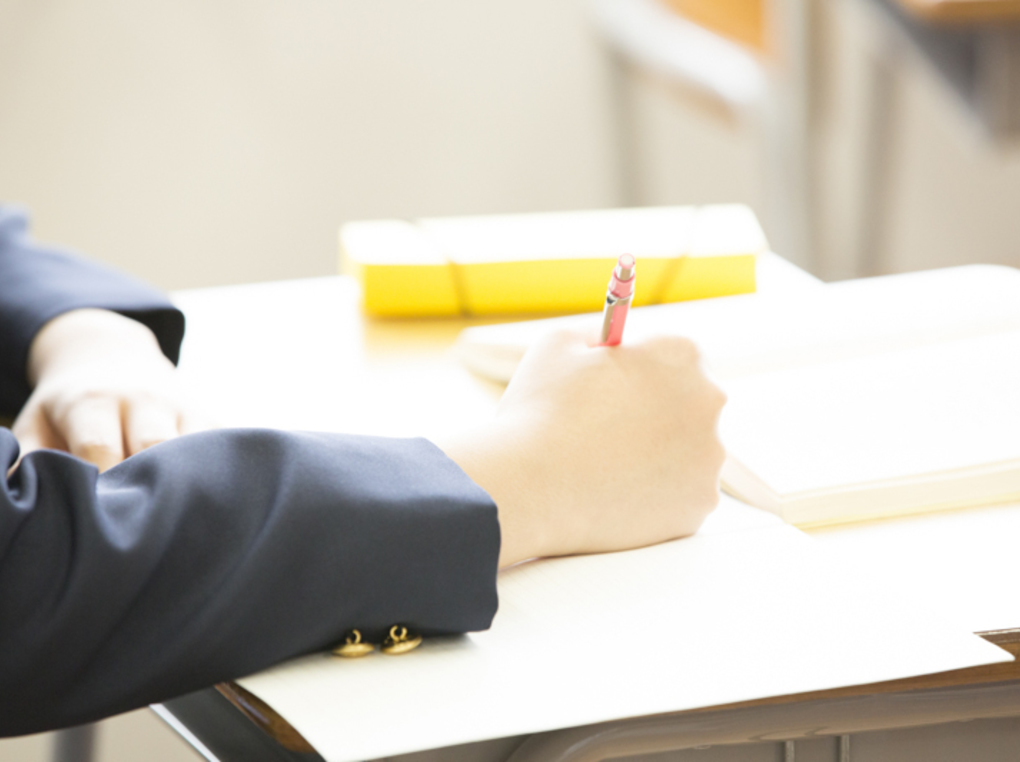| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | ページ数 | 発売日 | 出版社 | 著者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KADOKAWA/中経出版『何を準備すればいいかわからない人のための 総合型選抜・学校推薦型選抜(AO入試・推薦入試)のオキテ55』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月06日時点 での税込価格 |
小論文の基本をおさえた初心者向けの1冊 | 192 | 2012年8月9日 | KADOKAWA/中経出版 | 鈴木 鋭智 |
| 河合出版『医学部の小論文』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |
医学部の基礎と演習が学べる一冊 | 136ページ | 2017年10月28日 | 河合出版 | 広川 徹、鶴田 博之 |
| 東洋経済新報社『大学受験合格請負シリーズ 樋口裕一の小論文トレーニング』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月06日時点 での税込価格 |
小論文指導の第一人者のメソッドが身に着けられる | 226 | 2005年3月1日 | 東洋経済新報社 | 樋口 裕一 |
| 東洋経済新報社『小論文これだけ! 書き方 経済・経営編』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |
244ページ | 2020年10月9日 | 東洋経済新報社 | 樋口 裕一 | |
| 旺文社『全国大学小論文入試出題内容5か年ダイジェスト 2023年受験対策』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月06日時点 での税込価格 |
入試本番向け「シメの参考書」としても | 466 | 2022 年9月 | 旺文社 | 旺文社編集 |
| ダイヤモンド社『全試験対応! 直前でも一発合格! 落とされない小論文』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月8日時点 での税込価格 |
小論文の減点対象をあらかじめ把握できる | 192 | 2018年2月9日 | ダイヤモンド社 | 今道 琢也 |
| かんき出版『採点者の心をつかむ 合格する看護医療系の小論文 』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |
184ページ | 2019年9月4日 | かんき出版 | 中塚光之介 | |
| かんき出版『採点者の心をつかむ 合格する小論文』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月8日時点 での税込価格 |
得点につながるポイントがわかる1冊 | 160 | 2017年10月10日 | かんき出版 | 中塚 光之介 |
| 青春出版社『まるごと図解 面白いほど点がとれる!小論文』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月06日時点 での税込価格 |
小論文指導の第一人者が教える小論文のノウハウ | 159 | 2008年10月18日 | 青春出版社 | 樋口裕一、白藍塾 |
| 文英堂『ぶっつけ小論文―大学入試・秘伝公開!!』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月06日時点 での税込価格 |
どんな問題にも対応できる小論文の型について解説 | 143 | 2006年7月1日 | 文英堂 | 樋口裕一 |
| 桐原書店『吉岡のなるほど小論文講義10』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月06日時点 での税込価格 |
小論文の書き方のコツをわかりやすく解説 | 296 | 2017年3月18日 | 桐原書店 | 吉岡友治 |
| 文英堂『小論文の完全ネタ本改訂版 社会科学系編』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月06日時点 での税込価格 |
小論文に登場するテーマやキーワードについて解説 | 392 | 2020年7月15日 | 文英堂 | 神崎史彦 |
| 山川出版社『小論文を学ぶ―知の構築のために』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月8日時点 での税込価格 |
出題意図や小論文の本質について学べる | 264 | 2001年8月1日 | 山川出版社 | 長尾達也 |
用途に合うかどうかチェック!

出典:マイナビおすすめナビ

出典:マイナビおすすめナビ
小論文の参考書は、どんな学校を受験するか、学部を受験するかに応じて適切なものがあります。上の図を参考にチェックしてみてくださいね。
小論文参考書の選び方 大学入試対策のほか、看護学校、教員採用試験、就活にも使える
受験対策のプロである教育・受験指導専門家の西村 創さんのアドバイスをもとに、大学入試小論文の参考書の選び方を紹介します。ポイントは下記の3つです。
【1】学習の進み具合に合わせる
【2】小論文にかけられる時間
【3】課題に合ったもの
上記の3つのポイントをおさえると、より具体的に自分に合う大学入試小論文の参考書を選ぶことができます。一つひとつ解説していきます。
学習の進み具合に合ったものを選ぶ これから取り組むのか、すでに進んでいるか
これから始める人は手軽に読めるものを
これから小論文に取り組む人、すでに書く練習を進めている人では選ぶ参考書が変わってきます。
初学者用としては、「そもそも小論文とはどういうものなのか、どのようなことをどのように書くのか」についてわかりやすく紹介されているものを選んでください。
あまり厚い参考書だと挫折する可能性が高くなるので、手軽に読めるものを選ぶとよいでしょう。
小論文の練習にかけられる時間に合ったものを選ぶ AO入試か一般受験か、早稲田・慶応レベル以上か
ほかの受験準備とのバランスを考えて
小論文の練習だけに専念できる人はいないはずです。一般入試を受験するのなら学科試験の勉強、AO入試であっても、「志望理由書」や「活動報告書」の作成に相当量の時間が必要です。
ほかの準備にかかる時間とのバランスを考え、小論文にどれくらいの時間をかけて取り組むのかをふまえたうえで、選択しましょう。紹介している参考書はどれも比較的短時間で取り組み可能なものを挙げています。
自分の小論文の課題に合ったものを選ぶ 減点箇所、具体事例パターン、経済、国際小論文など
自分が抱えている課題を知ってから選ぼう
書いた小論文の添削をしてもらうことを進めていくと、自分の小論文の課題が見えてくるはずです。たとえば「減点される箇所が多い」「内容が浅い」「課題によって書けるときとそうでないときの差が大きい」などが挙げられます。
「減点される箇所が多い」のであれば、減点されるポイントが明示されているもの、「内容が浅い」のであれば、提示する具体事例のパターンが多く紹介されているものなど、自分の抱える課題克服につながるものを選ぶといいでしょう。
あなたにピッタリの小論文参考書は? タイプ別診断で発見!

出典:マイナビおすすめナビ

出典:マイナビおすすめナビ
あなたの目的に合うぴったりの小論文参考書はどんな商品タイプか、診断チャートで確認してみましょう。
小論文参考書のおすすめ13選 人気の著者、樋口先生の参考書ほか、医学部、法学部志望の人にも
それでは、教育・受験指導専門家の西村 創さんが選んだおすすめ商品、編集部で選んだ商品を紹介します。

小論文の基本をおさえた初心者向けの1冊
小論文に関する参考書を初めて購入する方には、最初の1冊としてこの参考書をおすすめします。「小論文」というよりは、AO入試・推薦入試全般に関わる参考書で、小論文に関する内容は第4章に書かれています。
小論文に特化した参考書ではないものの、4章の小論文についての説明は、小論文を作成するにあたって必要なことがコンパクトにまとめられ、その内容もよくわかりやすいです。すぐに読める初学者用の参考書として最適です。
※各社通販サイトの 2024年11月06日時点 での税込価格
| ページ数 | 192 |
|---|---|
| 発売日 | 2012年8月9日 |
| 出版社 | KADOKAWA/中経出版 |
| 著者 | 鈴木 鋭智 |
| ページ数 | 192 |
|---|---|
| 発売日 | 2012年8月9日 |
| 出版社 | KADOKAWA/中経出版 |
| 著者 | 鈴木 鋭智 |
医学部の基礎と演習が学べる一冊
「医学部の小論文の基礎知識編」と「演習問題編」で基礎と演習を学ぶことができる一冊。必ず押さえたいテーマから出題頻度が高いテーマまで幅広く収録しています。
なお、医学部小論文のNG解答例も紹介していて、自分の回答と比較できる点もポイントです。
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格
| ページ数 | 136ページ |
|---|---|
| 発売日 | 2017年10月28日 |
| 出版社 | 河合出版 |
| 著者 | 広川 徹、鶴田 博之 |
| ページ数 | 136ページ |
|---|---|
| 発売日 | 2017年10月28日 |
| 出版社 | 河合出版 |
| 著者 | 広川 徹、鶴田 博之 |

小論文指導の第一人者のメソッドが身に着けられる
小論文指導の第一人者である樋口裕一氏は数多くの参考書を出していますが、この参考書がもっともわかりやすいと思います。わたしもかつて、予備校で彼の講義を1年間受けたひとりですが、その講義のエッセンスがこの参考書に詰まっています。
基本的には、4段落構成の型と、受験学部に関連の深い具体事例を数パターン覚え、短時間で完成度の高い小論文を作成するというメソッドです。
※各社通販サイトの 2024年11月06日時点 での税込価格
| ページ数 | 226 |
|---|---|
| 発売日 | 2005年3月1日 |
| 出版社 | 東洋経済新報社 |
| 著者 | 樋口 裕一 |
| ページ数 | 226 |
|---|---|
| 発売日 | 2005年3月1日 |
| 出版社 | 東洋経済新報社 |
| 著者 | 樋口 裕一 |
経済学部と経営学部の違いや、自分がどちらに向いているのかを解説。よく出る23の基本テーマの基礎知識、書くネタも満載で知識がしっかりと身につきます。
累計30万部を突破した受験生から圧倒的な支持を集める一冊になります。
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格
| ページ数 | 244ページ |
|---|---|
| 発売日 | 2020年10月9日 |
| 出版社 | 東洋経済新報社 |
| 著者 | 樋口 裕一 |
| ページ数 | 244ページ |
|---|---|
| 発売日 | 2020年10月9日 |
| 出版社 | 東洋経済新報社 |
| 著者 | 樋口 裕一 |

入試本番向け「シメの参考書」としても
いわゆる「入試過去問」です。過去5年間のさまざまな大学・学部の過去問が掲載されています。
巻頭特集では、小論文の書き方のポイントを解説、例題のNG答案・OK答案がついているのでポイントを直感的に理解することができます。小論文試験対策として、学部系統別の小論文重要テーマをはじめ、事前準備をしておきたいキーワードやニュース・トピックスなどのコンテンツも充実しています。
※各社通販サイトの 2024年11月06日時点 での税込価格
| ページ数 | 466 |
|---|---|
| 発売日 | 2022 年9月 |
| 出版社 | 旺文社 |
| 著者 | 旺文社編集 |
| ページ数 | 466 |
|---|---|
| 発売日 | 2022 年9月 |
| 出版社 | 旺文社 |
| 著者 | 旺文社編集 |

小論文の減点対象をあらかじめ把握できる
ある程度小論文の書き方がわかり、実際に何本か書く練習をしている人におすすめの参考書です。この参考書の特徴は、ほかの多くの参考書のように「いかに書くか」ということではなく、「いかに減点されないか」にフォーカスした内容となっている点です。
ありがちな減点対象ポイントが具体的に紹介されているので、その減点ポイントを避けて書けるようになれば、合格点に達する小論文に近づけるはずです。
※各社通販サイトの 2024年11月8日時点 での税込価格
| ページ数 | 192 |
|---|---|
| 発売日 | 2018年2月9日 |
| 出版社 | ダイヤモンド社 |
| 著者 | 今道 琢也 |
| ページ数 | 192 |
|---|---|
| 発売日 | 2018年2月9日 |
| 出版社 | ダイヤモンド社 |
| 著者 | 今道 琢也 |
出題傾向はもちろん、受験生がやりがちな失敗例や採点者に評価されやすい書き方をしっかり学ぶことができます。
また、読むだけで看護・医療系の小論文に必要な医療の背景知識、専門用語も身につきます。
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格
| ページ数 | 184ページ |
|---|---|
| 発売日 | 2019年9月4日 |
| 出版社 | かんき出版 |
| 著者 | 中塚光之介 |
| ページ数 | 184ページ |
|---|---|
| 発売日 | 2019年9月4日 |
| 出版社 | かんき出版 |
| 著者 | 中塚光之介 |

得点につながるポイントがわかる1冊
こちらもある程度小論文の練習が進んだ人向けの参考書です。しかし、前述の参考書とはアプローチが正反対。タイトルどおり「いかに採点者の心をつかんで高得点をもらえる小論文にするか」について紹介されている参考書です。
とりあえず書けるけれど、高評価をもらえる小論文にならないという方にはぜひ読んでもらいたい内容です。
※各社通販サイトの 2024年11月8日時点 での税込価格
| ページ数 | 160 |
|---|---|
| 発売日 | 2017年10月10日 |
| 出版社 | かんき出版 |
| 著者 | 中塚 光之介 |
| ページ数 | 160 |
|---|---|
| 発売日 | 2017年10月10日 |
| 出版社 | かんき出版 |
| 著者 | 中塚 光之介 |
小論文指導の第一人者が教える小論文のノウハウ
著者は、20年間に10万通もの小論文指導をこなしてきた、まさに小論文の神様とも言えるような人物です。豊富な指導の経験から、「これに沿って書けばよい」という小論文の型や、受験生がよくやってしまうミスについてなど、小論文のノウハウを教えてくれます。
押さえておくポイントを絞って解説しているので、試験直前に見直すのにもおすすめの参考書です。
※各社通販サイトの 2024年11月06日時点 での税込価格
| ページ数 | 159 |
|---|---|
| 発売日 | 2008年10月18日 |
| 出版社 | 青春出版社 |
| 著者 | 樋口裕一、白藍塾 |
| ページ数 | 159 |
|---|---|
| 発売日 | 2008年10月18日 |
| 出版社 | 青春出版社 |
| 著者 | 樋口裕一、白藍塾 |
どんな問題にも対応できる小論文の型について解説
大学入試で実施される小論文ではどのような力が求められているのかを、受験生に理解しやすいように解説してくれています。どんな形式の問題が出てきても対応できるような、小論文の基本の型を中心に説明されています。
試験本番の緊張の中でも、どういう書き方をすれば点数を取れるのかについて詳しい解説が載っています。
※各社通販サイトの 2024年11月06日時点 での税込価格
| ページ数 | 143 |
|---|---|
| 発売日 | 2006年7月1日 |
| 出版社 | 文英堂 |
| 著者 | 樋口裕一 |
| ページ数 | 143 |
|---|---|
| 発売日 | 2006年7月1日 |
| 出版社 | 文英堂 |
| 著者 | 樋口裕一 |
小論文の書き方のコツをわかりやすく解説
小論文とは何か?という基本的なところから始まり、「課題文問題」「ビジュアル問題」など、入試に出る問題までを体系的に解説している参考書です。この本を読めば、説得力のある小論文の書き方を納得しながら学ぶことが出来ます。
志望理由書や自己申告書の書き方も載っているので、推薦入試やAO入試を考えている人にもおすすめです。
※各社通販サイトの 2024年11月06日時点 での税込価格
| ページ数 | 296 |
|---|---|
| 発売日 | 2017年3月18日 |
| 出版社 | 桐原書店 |
| 著者 | 吉岡友治 |
| ページ数 | 296 |
|---|---|
| 発売日 | 2017年3月18日 |
| 出版社 | 桐原書店 |
| 著者 | 吉岡友治 |
小論文に登場するテーマやキーワードについて解説
社会科学系学部の入試に特によく出るテーマを42個、そのテーマに関連するキーワードを521個扱っています。テーマでは、その定義や問題点、対応策について解説されており、それを小論文にどう生かすかというポイントも載っています。
過去に入試で出された問題も掲載されており、学んだテーマが実際の入試でどのように問われるのか実践的に勉強することも出来ます。
※各社通販サイトの 2024年11月06日時点 での税込価格
| ページ数 | 392 |
|---|---|
| 発売日 | 2020年7月15日 |
| 出版社 | 文英堂 |
| 著者 | 神崎史彦 |
| ページ数 | 392 |
|---|---|
| 発売日 | 2020年7月15日 |
| 出版社 | 文英堂 |
| 著者 | 神崎史彦 |
出題意図や小論文の本質について学べる
この参考書は、「小論文とは時代を反映する鏡のようなものであり、時代全体を見渡す目を持っていないと書くことはできない」という観点から小論文の正体をはっきりと解説した本です。
大学入試の小論文で問われているものの本質は何か、出題する大学側の意図は何か、ということを学ぶことが出来ます。基本を学ぶのではなく、より高得点を目指したい方におすすめできる参考書です。
※各社通販サイトの 2024年11月8日時点 での税込価格
| ページ数 | 264 |
|---|---|
| 発売日 | 2001年8月1日 |
| 出版社 | 山川出版社 |
| 著者 | 長尾達也 |
| ページ数 | 264 |
|---|---|
| 発売日 | 2001年8月1日 |
| 出版社 | 山川出版社 |
| 著者 | 長尾達也 |
「小論文参考書」のおすすめ商品の比較一覧表
| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | ページ数 | 発売日 | 出版社 | 著者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KADOKAWA/中経出版『何を準備すればいいかわからない人のための 総合型選抜・学校推薦型選抜(AO入試・推薦入試)のオキテ55』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月06日時点 での税込価格 |
小論文の基本をおさえた初心者向けの1冊 | 192 | 2012年8月9日 | KADOKAWA/中経出版 | 鈴木 鋭智 |
| 河合出版『医学部の小論文』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |
医学部の基礎と演習が学べる一冊 | 136ページ | 2017年10月28日 | 河合出版 | 広川 徹、鶴田 博之 |
| 東洋経済新報社『大学受験合格請負シリーズ 樋口裕一の小論文トレーニング』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月06日時点 での税込価格 |
小論文指導の第一人者のメソッドが身に着けられる | 226 | 2005年3月1日 | 東洋経済新報社 | 樋口 裕一 |
| 東洋経済新報社『小論文これだけ! 書き方 経済・経営編』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |
244ページ | 2020年10月9日 | 東洋経済新報社 | 樋口 裕一 | |
| 旺文社『全国大学小論文入試出題内容5か年ダイジェスト 2023年受験対策』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月06日時点 での税込価格 |
入試本番向け「シメの参考書」としても | 466 | 2022 年9月 | 旺文社 | 旺文社編集 |
| ダイヤモンド社『全試験対応! 直前でも一発合格! 落とされない小論文』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月8日時点 での税込価格 |
小論文の減点対象をあらかじめ把握できる | 192 | 2018年2月9日 | ダイヤモンド社 | 今道 琢也 |
| かんき出版『採点者の心をつかむ 合格する看護医療系の小論文 』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |
184ページ | 2019年9月4日 | かんき出版 | 中塚光之介 | |
| かんき出版『採点者の心をつかむ 合格する小論文』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月8日時点 での税込価格 |
得点につながるポイントがわかる1冊 | 160 | 2017年10月10日 | かんき出版 | 中塚 光之介 |
| 青春出版社『まるごと図解 面白いほど点がとれる!小論文』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月06日時点 での税込価格 |
小論文指導の第一人者が教える小論文のノウハウ | 159 | 2008年10月18日 | 青春出版社 | 樋口裕一、白藍塾 |
| 文英堂『ぶっつけ小論文―大学入試・秘伝公開!!』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月06日時点 での税込価格 |
どんな問題にも対応できる小論文の型について解説 | 143 | 2006年7月1日 | 文英堂 | 樋口裕一 |
| 桐原書店『吉岡のなるほど小論文講義10』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月06日時点 での税込価格 |
小論文の書き方のコツをわかりやすく解説 | 296 | 2017年3月18日 | 桐原書店 | 吉岡友治 |
| 文英堂『小論文の完全ネタ本改訂版 社会科学系編』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月06日時点 での税込価格 |
小論文に登場するテーマやキーワードについて解説 | 392 | 2020年7月15日 | 文英堂 | 神崎史彦 |
| 山川出版社『小論文を学ぶ―知の構築のために』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月8日時点 での税込価格 |
出題意図や小論文の本質について学べる | 264 | 2001年8月1日 | 山川出版社 | 長尾達也 |
通販サイトの最新人気ランキングを参考にする 小論文参考書の売れ筋をチェック
Amazonでの小論文参考書の売れ筋ランキングも参考にしてみてください。
※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。
大学受験参考書やオンラインサービス 【関連記事】
練習進行度や自分の課題に合わせて選択を! 教育・受験指導専門家からのアドバイス
複数併用すると小論文作成の視野が広がる
小論文の参考書は、英語や数学など他の学科の参考書に比べて、本によって解説の方向性が大きく異なります。小論文の練習進行度合いや、練習にかけられる時間、自分の小論文の課題に合っているかなどの観点から参考書を選んでください。
また、1冊に入念に取り組むよりも、複数の参考書を「参考」にすることで、小論文作成の視野が広がります。これは小論文という科目自体が主観的要素が大きいので、著者の思考が参考書の内容に影響しやすいからです。複数の参考書を活用して合格を目指してください。
◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。