| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 区分 | タイプ | 形状 | 内容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久光製薬『サロンパス』 |

|
※各社通販サイトの 2024年08月23日時点 での税込価格 |
肌にフィットするしなやかな貼り心地 | 第一世代 | - | パップ | 40枚、80枚、120枚 |
| 久光製薬『のびのびサロンシップFα』 |

|
※各社通販サイトの 2024年08月23日時点 での税込価格 |
フィット感が高く密着してはがれにくい | - | 冷感 | パップ | 12枚 |
| 久光製薬『フェイタス5.0温感』 |

|
※各社通販サイトの 2024年08月23日時点 での税込価格 |
心地よい温感刺激が長く続く | 第二世代 | 温感 | テープ | 7枚、14枚 |
| 久光製薬『サロンシップインドメタシンEX』 |

|
※各社通販サイトの 2024年08月23日時点 での税込価格 |
しつこい痛みにじんわり作用 | 第二世代 | 冷感 | - | 12枚、24枚 |
| 久光製薬『サロンパスEX温感』 |

|
※各社通販サイトの 2024年08月23日時点 での税込価格 |
温感作用で症状をやわらげてくれる | 第二世代 | 温感 | - | 20枚、40枚 |
| 第一三共ヘルスケア『ロキソニンSテープ』 |

|
※各社通販サイトの 2024年08月23日時点 での税込価格 |
痛みの芯まで浸透してやわらげてくれる | 第二世代 | - | テープ | 7枚、14枚 |
| 第一三共ヘルスケア『パテックスうすぴたシップ』 |

|
※各社通販サイトの 2024年08月23日時点 での税込価格 |
ピタッと密着してはがれにくい | 第一世代 | 冷感 | パップ | 24枚、48枚 |
| 第一三共ヘルスケア『キュウメタシンパップH』 |

|
※各社通販サイトの 2024年08月23日時点 での税込価格 |
冷たい患部にぴったりな温感湿布 | 第二世代 | 温感 | パップ | 12枚、24枚 |
| 興和『バンテリンコーワパップS』 |

|
※各社通販サイトの 2024年9月3日時点 での税込価格 |
肌にやさしいソフトな使用感 | 第二世代 | 冷感 | パップ | 12枚、24枚 |
| ライオン『ハリックス55EX冷感A』 |
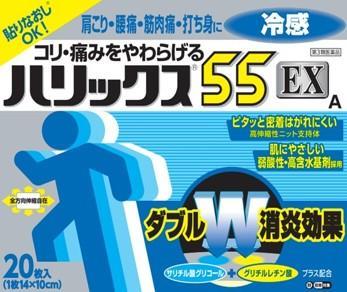
|
※各社通販サイトの 2024年9月4日時点 での税込価格 |
心地よい清涼感が魅力 | 第一世代 | 冷感 | パップ | 10枚、20枚、ハーフサイズ12枚 |
| gsk『ボルタレンEXテープ』 |

|
※各社通販サイトの 2024年9月3日時点 での税込価格 |
痛みを原因からおさえるすぐれた鎮痛力 | 第二世代 | - | テープ | 7枚、14枚、21枚、L:7枚 |
| 大正製薬『トクホン』 |

|
※各社通販サイトの 2024年08月23日時点 での税込価格 |
ひんやり心地よい使用感が魅力 | 第一世代 | - | プラスター剤 | 普通版:40枚、80枚、140枚 |
| 祐徳薬品工業『パスタイムFXこはる』 |

|
※各社通販サイトの 2024年08月23日時点 での税込価格 |
さわやかなアロマの香りがする湿布薬 | 第二世代 | - | - | 20枚、40枚 |
| 大石膏盛堂『フェルビナファインα』 |

|
※各社通販サイトの 2024年08月23日時点 での税込価格 |
痛みを原因からやわらげてくれる | 第二世代 | - | プラスター剤 | 80枚 |
| テイコクファルマケア『オムニードFBプラスターα』 |

|
※各社通販サイトの 2024年08月23日時点 での税込価格 |
ほどよい冷感刺激で痛みをやわらげてくれる | 第二世代 | - | プラスター剤 | 16枚、40枚 |
| 東光薬品工業 ラクール『ラクペタンうすップ』 |

|
※各社通販サイトの 2024年08月23日時点 での税込価格 |
薄型で患部に密着しやすい | 第一世代 | 冷感 | パップ | 48枚 |
打撲・捻挫について
症状にあった湿布を選ぶためにも、まずは打撲と捻挫について原因や症状を把握しておきましょう。
打撲の原因と症状
打撲は、転んだりぶつかったりなど体に衝撃が加わることにより、体の一部にダメージを受けることです。筋肉や皮下組織にダメージを受けるもので、骨折は含まれません。一般的に「打ち身」ともいわれます。
切りキズや刺しキズとは違って外への出血はありませんが、ダメージを受けた部分には腫れ、内出血による青アザなどの症状がみられます。
捻挫の原因と症状
なにかにつまずいたり転んだりしたときに、不自然な形にひねるなど関節に無理な力がかかり、関節が動く範囲をこえる動きをした場合に起きるのが捻挫です。関節内で骨と骨をつなぐ役割をもつ靱帯にダメージを受けた状態です。
靱帯が伸びる程度の症状から靱帯が部分的に切れたり、すべて切れたりする場合など、捻挫のなかでもダメージの受け方によって症状の度合いが異なります。
打撲・捻挫にはまず「RICE処置」をしよう
打撲や捻挫によって患部に炎症や腫れなどの症状がある場合には、応急処置として「RICE処置」(※)を取りましょう。まずは患部を動かさずテーピングや包帯で固定し、氷や保冷剤などを使って冷やしましょう。
その後、腫れの原因となる内出血を抑えるため、患部をテーピングや包帯で軽く圧迫するように固定し、患部を心臓より高い位置に上げます。「RICE処置」によって患部の腫れやむくみ、内出血を抑え、しばらく様子を見てから腫れや内出血などの症状が残る場合には整形外科を受診しましょう。そして、必要に応じて湿布を貼りましょう。
※「RICE処置」とは、安静(Rest)にし、冷却(Icing)し、包帯やテーピングで圧迫(Compression)し、患肢を挙上すること(Elevation)の4つの頭文字をとったものです。
打撲・捻挫用湿布の選び方
医療ライター・編集者である宮座美帆さんに取材をして、打撲・捻挫用湿布を選ぶポイントを教えてもらいました。症状や患部の状態などをよくチェックすることが大切です。ぜひ打撲・捻挫用湿布を選ぶ参考にしてください。
症状や患部の状態で決める
湿布に含まれる鎮静成分の違いにより「第一世代」と「第二世代」にわけられます。まずは違いを把握して症状や患部の状態にあわせて湿布を選びましょう。
「第一世代」はスーッと患部を冷やしたい時に
第一世代の湿布は、サリチル酸グリコールやサリチル酸メチルなどの鎮痛成分が含まれているのが特徴です。以前から湿布に使用されている成分で、打撲や捻挫の患部をスーッと冷やしたい場合に向いています。
よくいわれる「湿布くさい」とは、サリチル酸メチルによるものです。子どもでも保護者の管理下であれば使用に制限はありません。
「第二世代」はより強い鎮痛作用が期待できる
第二世代の湿布にはインドメタシンやフェルビナク、ジクロフェナクナトリウムなど非ステロイド性の鎮痛成分が含まれているのが特徴。患部に非ステロイド性鎮痛成分が浸透することにより症状をやわらげます。
第一世代とは異なり、15歳未満の方やぜんそくの持病がある方など使用できない場合があるため、添付文書や説明文書をしっかりと読んだうえで使用しましょう。
粘着性・伸縮性が強いタイプを選ぼう
湿布は患部に貼りつけて使用するため、粘着性が強いものを選びましょう。捻挫のように足首や膝など、頻繁に動かす関節が患部になる場合には、粘着性の強さだけでなく伸縮性があるかどうかもチェックしておきたいポイント。
市販の湿布には全方向性伸縮自在など、あらゆる方向に対して伸縮性にすぐれた湿布も販売されているので、動いてもはがれにくいものを選ぶようにしましょう。
微香性タイプを選ぶと匂いがおさえられる
湿布特有の匂いは自分だけでなく、まわりの方にまで伝わってしまう場合が少なくありません。匂いが気になる場合は「微香性」と記載がある湿布を選ぶとよいでしょう。
湿布特有の匂いは第一世代に含まれる鎮痛成分によるものですが、微香性タイプの湿布は、匂いの原因となる鎮痛成分が含まれているものでも匂いがおさえられるように作られています。
冷湿布・温湿布はどちらを選ぶといい?
市販の湿布には患部を冷やす「冷湿布」と温める「温湿布」があります。患部の状態によってどちらを選ぶのがよいか把握しておきましょう。
急性期には冷湿布
冷湿布は打撲や捻挫によって腫れなどの症状がみられる急性期に使用します。患部を冷やしながら炎症を鎮められるので、「RICE処置」をしたあとに使うなら冷湿布を選びましょう。
冷感タイプと記載されていない湿布でも、成分表のなかにメントールやハッカ油などの成分が含まれているものには、ひんやりと感じさせる作用があります。
慢性期には温湿布
患部を温められる「温湿布」は、トウガラシ成分のカプサイシンの働きによって患部を温めて血行をよくするのが特徴。筋肉痛や腰痛、肩こりなど慢性的な症状をやわらげることができます。
患部を温めたり、お風呂に入ったりすると症状が和らぐような場合は、患部を温められる温湿布を試してみてください。
強い痛み・腫れ・内出血がある場合は整形外科の受診を 医療ライター・編集者がアドバイス
アウトドアシーズンなどは、打撲などによるけがに注意が必要です。応急処置として湿布を使い数時間たっても強い痛みや、腫れ、内出血があれば整形外科の受診を。
ケガ直後には素人には見た目の変化がなく判断がつかないことも多くあります。症状が続くようであれば、まずは整形外科を受診してください。
打撲・捻挫用湿布おすすめ16選 剥がれにくい、フィット感のあるもので
ここからは医療ライター・編集者の宮座美帆さんと編集部が選んだ打撲・捻挫用湿布をご紹介します。選び方を参考にしながらチェックしてみてください。
肌にフィットするしなやかな貼り心地
サリチル酸メチルによって肩こりや腰痛、筋肉痛などをやわらげてくれるのが特徴。肌にぴったりフィットしてつっぱらない、しなやかな貼り心地が魅力です。
湿布の角を丸くすることで、衣類とこすれてもはがれにくくなっています。肌なじみのよいベージュ色なので、薄手の服でも目立ちにくいのも魅力的なポイントです。
※各社通販サイトの 2024年08月23日時点 での税込価格
| 区分 | 第一世代 |
|---|---|
| タイプ | - |
| 形状 | パップ |
| 内容量 | 40枚、80枚、120枚 |
※この商品は第3類医薬品です。
| 区分 | 第一世代 |
|---|---|
| タイプ | - |
| 形状 | パップ |
| 内容量 | 40枚、80枚、120枚 |
※この商品は第3類医薬品です。
フィット感が高く密着してはがれにくい
軽くて薄いので肌にしっかり密着するのが特徴。伸縮性にもすぐれているので、肘や膝などの関節部位に貼ってもぴったりフィットしています。湿布の角を丸くすることで衣類に引っかかりにくく、はがれにくいのもうれしいポイントです。
心地よい冷感により患部を冷やして症状をやわらげてくれます。無臭性なので湿布独特の匂いが気になる方でも使いやすくなっています。
※各社通販サイトの 2024年08月23日時点 での税込価格
| 区分 | - |
|---|---|
| タイプ | 冷感 |
| 形状 | パップ |
| 内容量 | 12枚 |
※この商品は第3類医薬品です。
| 区分 | - |
|---|---|
| タイプ | 冷感 |
| 形状 | パップ |
| 内容量 | 12枚 |
※この商品は第3類医薬品です。
心地よい温感刺激が長く続く
肩や腰などのつらい症状をやわらげてくれるフェルビナクを5.0%配合した湿布薬です。温感成分のノニル酸ワニリルアミドを配合することで、ほどよい温感刺激が持続します。
テープは伸縮性にすぐれていて肌にぴったりフィットし、はがれにくいのが魅力。洋服とこすれてもはがれにくいので長く使い続けられるようになっています。
※各社通販サイトの 2024年08月23日時点 での税込価格
| 区分 | 第二世代 |
|---|---|
| タイプ | 温感 |
| 形状 | テープ |
| 内容量 | 7枚、14枚 |
| 区分 | 第二世代 |
|---|---|
| タイプ | 温感 |
| 形状 | テープ |
| 内容量 | 7枚、14枚 |
しつこい痛みにじんわり作用
非ステロイド性鎮痛消炎薬であるインドメタシンを0.5%配合した湿布薬です。成分がじんわりと肌に浸透し、肩や腰、関節などのしつこい痛みに直接作用することで、患部の痛みをやわらげてくれます。
ほどよい冷感刺激もあるので、打撲や捻挫などで患部に熱がこもってしまった場合でも冷やしながら症状をおさえることが可能です。
※各社通販サイトの 2024年08月23日時点 での税込価格
| 区分 | 第二世代 |
|---|---|
| タイプ | 冷感 |
| 形状 | - |
| 内容量 | 12枚、24枚 |
※この商品は第2類医薬品です。
| 区分 | 第二世代 |
|---|---|
| タイプ | 冷感 |
| 形状 | - |
| 内容量 | 12枚、24枚 |
※この商品は第2類医薬品です。
温感作用で症状をやわらげてくれる
消炎鎮痛成分のインドメタシン3.5%や、トウガラシエキスによるじんわりと心地よい温感作用によって、肩こりなどの症状をやわらげてくれるのが特徴。
肌色のパッドに微香性と、湿布をつけていることが分かりにくいので、外出時にもぴったりです。肩や首のつけ根や肩甲骨周りなどに貼りやすいサイズ感で使いやすいです。
※各社通販サイトの 2024年08月23日時点 での税込価格
| 区分 | 第二世代 |
|---|---|
| タイプ | 温感 |
| 形状 | - |
| 内容量 | 20枚、40枚 |
※この商品は第2類医薬品です。
| 区分 | 第二世代 |
|---|---|
| タイプ | 温感 |
| 形状 | - |
| 内容量 | 20枚、40枚 |
※この商品は第2類医薬品です。
痛みの芯まで浸透してやわらげてくれる
鎮痛消炎作用のあるロキソプロフェンナトリウム水和物が配合されている湿布です。患部に貼ることで成分が痛みの芯まで直接浸透してやわらげてくれます。
テープは肌になじみやすいモカベージュ色なので、目立ちにくいのも魅力。かすかなメントールが香る微香性なので、外出時に貼りたい方にもぴったりです。
※各社通販サイトの 2024年08月23日時点 での税込価格
| 区分 | 第二世代 |
|---|---|
| タイプ | - |
| 形状 | テープ |
| 内容量 | 7枚、14枚 |
※この商品は第2類医薬品です。
| 区分 | 第二世代 |
|---|---|
| タイプ | - |
| 形状 | テープ |
| 内容量 | 7枚、14枚 |
※この商品は第2類医薬品です。

貼るとひんやり感じられる、第一三共ヘルスケア『パテックスうすぴたシップ』やライオン『ハリックス55EX冷感A』は熱を持つ患部を心地よい清涼感で癒してくれます。
ピタッと密着してはがれにくい
サリチル酸グリコールが含まれている第一世代の湿布です。厚さが約0.9mmと薄型で肌にしっかりと密着することで、肘や膝などの関節に貼ってもはがれにくいのが特徴。
メントールが配合されているので、貼ったときに清涼感があり、痛みをやわらげてくれます。
※各社通販サイトの 2024年08月23日時点 での税込価格
| 区分 | 第一世代 |
|---|---|
| タイプ | 冷感 |
| 形状 | パップ |
| 内容量 | 24枚、48枚 |
※こちらの商品は第3類医薬品です。
| 区分 | 第一世代 |
|---|---|
| タイプ | 冷感 |
| 形状 | パップ |
| 内容量 | 24枚、48枚 |
※こちらの商品は第3類医薬品です。
冷たい患部にぴったりな温感湿布
肩や腰、関節など、つらい痛みの原因となる物質の生成をおさえてくれるインドメタシンを配合した湿布薬です。トウガラシエキス入りでじんわり温かいので、患部が冷たい場合におすすめです。
縦、横、ななめと全方向に伸びるので、ひじやひざなど頻繁に動かす関節にもフィットしてはがれにくいのも魅力です。
※各社通販サイトの 2024年08月23日時点 での税込価格
| 区分 | 第二世代 |
|---|---|
| タイプ | 温感 |
| 形状 | パップ |
| 内容量 | 12枚、24枚 |
※この商品は第2類医薬品です。
| 区分 | 第二世代 |
|---|---|
| タイプ | 温感 |
| 形状 | パップ |
| 内容量 | 12枚、24枚 |
※この商品は第2類医薬品です。
肌にやさしいソフトな使用感
鎮痛成分のインドメタシンが患部から浸透して炎症などの症状をやわらげてくれるのが特徴。高粘着パッドとはタテヨコ自在に伸びるすぐれた伸縮性をもち、関節に貼ってもはがれにくくなっています。
水分を含んだパップ剤なので、ソフトな使用感が魅力。肩こりや腰痛、関節痛などの症状をやわらげたい方にぴったりです。
※各社通販サイトの 2024年9月3日時点 での税込価格
| 区分 | 第二世代 |
|---|---|
| タイプ | 冷感 |
| 形状 | パップ |
| 内容量 | 12枚、24枚 |
| 区分 | 第二世代 |
|---|---|
| タイプ | 冷感 |
| 形状 | パップ |
| 内容量 | 12枚、24枚 |

心地よい清涼感が魅力
メントールによる心地よい清涼感が魅力的な湿布です。サリチル酸グリコールと抗炎症成分のグリチルレチン酸をダブルで配合することで、患部のコリや痛みをやわらげてくれます。
粘着力が強く、全方向伸縮自在のニット支持体を採用することにより、肘や膝、足首など頻繁に動かす部分に貼ってもはがれにくくなっています。
※各社通販サイトの 2024年9月4日時点 での税込価格
| 区分 | 第一世代 |
|---|---|
| タイプ | 冷感 |
| 形状 | パップ |
| 内容量 | 10枚、20枚、ハーフサイズ12枚 |
※こちらの商品は第3類医薬品です。
| 区分 | 第一世代 |
|---|---|
| タイプ | 冷感 |
| 形状 | パップ |
| 内容量 | 10枚、20枚、ハーフサイズ12枚 |
※こちらの商品は第3類医薬品です。

薄着になる時期にぴったりなのが、gsk『ボルタレンEXテープ』。肌になじみやすいテープのため、女性でも使いやすい商品です。
痛みを原因からおさえるすぐれた鎮痛力
有効成分のジクロフェナクナトリウムにより、痛みの原因となる物質の生成を阻害することで痛みや炎症をやわらげてくれます。有効成分が患部まで素早く浸透するように工夫されているので、肩や腰に辛い症状を抱える方にぴったり。
1日1回で24時間持続するため、何度も湿布を貼り替える手間がないのもうれしいポイントです。
※各社通販サイトの 2024年9月3日時点 での税込価格
| 区分 | 第二世代 |
|---|---|
| タイプ | - |
| 形状 | テープ |
| 内容量 | 7枚、14枚、21枚、L:7枚 |
※こちらの商品は第2類医薬品です。
| 区分 | 第二世代 |
|---|---|
| タイプ | - |
| 形状 | テープ |
| 内容量 | 7枚、14枚、21枚、L:7枚 |
※こちらの商品は第2類医薬品です。
ひんやり心地よい使用感が魅力
有効成分としてサリチル酸メチルを配合した湿布薬です。肩こりや腰痛、筋肉痛などをやわらげてくれます。
l-メントールとdl-カンフルが配合されることにより、ひんやりと清涼感のある使い心地になっています。通常サイズのほか、少し大きめな中判サイズもあるので、患部にあわせて選ぶとよいでしょう。
※各社通販サイトの 2024年08月23日時点 での税込価格
| 区分 | 第一世代 |
|---|---|
| タイプ | - |
| 形状 | プラスター剤 |
| 内容量 | 普通版:40枚、80枚、140枚 |
※この商品は第3類医薬品です。
| 区分 | 第一世代 |
|---|---|
| タイプ | - |
| 形状 | プラスター剤 |
| 内容量 | 普通版:40枚、80枚、140枚 |
※この商品は第3類医薬品です。
さわやかなアロマの香りがする湿布薬
ラベンダーやベルガモット、オレンジなど天然成分由来の香料を使用した爽やかで甘い香りが感じられる湿布薬です。小さめのサイズなので片手で貼りやすく、使いやすさも考えられているのが特徴。
有効成分のフェルビナクにより痛みをやわらげてくれるほか、清涼感のあるl-メントールのひんやりとした刺激も心地よく感じられます。
※各社通販サイトの 2024年08月23日時点 での税込価格
| 区分 | 第二世代 |
|---|---|
| タイプ | - |
| 形状 | - |
| 内容量 | 20枚、40枚 |
※この商品は第2類医薬品です。
| 区分 | 第二世代 |
|---|---|
| タイプ | - |
| 形状 | - |
| 内容量 | 20枚、40枚 |
※この商品は第2類医薬品です。
痛みを原因からやわらげてくれる
有効成分のフェルビナクにより、痛みの原因物質の生成をおさえることで、肩や腰、関節などの痛みをやわらげてくれるのが特徴。微香性タイプなので匂いが気になる方にもぴったりです。
穴あきタイプで蒸れにくく、天然ゴムを配合していないので肌が弱い方でも使いやすくなっています。メントールによる爽快感も心地よいです。
※各社通販サイトの 2024年08月23日時点 での税込価格
| 区分 | 第二世代 |
|---|---|
| タイプ | - |
| 形状 | プラスター剤 |
| 内容量 | 80枚 |
※この商品は第2類医薬品です。
| 区分 | 第二世代 |
|---|---|
| タイプ | - |
| 形状 | プラスター剤 |
| 内容量 | 80枚 |
※この商品は第2類医薬品です。
ほどよい冷感刺激で痛みをやわらげてくれる
鎮痛成分のフェルビナク5.0%配合により、痛みの原因であるプロスタグランジンの発生をおさえてくれるのが特徴。ビタミンEの作用により、末梢の血流をうながし、l-メントールのほどよい冷感刺激により患部の痛みをやわらげます。
肌なじみのよい肌色の基布なので、外出時にも使用したい方にぴったりです。
※各社通販サイトの 2024年08月23日時点 での税込価格
| 区分 | 第二世代 |
|---|---|
| タイプ | - |
| 形状 | プラスター剤 |
| 内容量 | 16枚、40枚 |
※この商品は第2類医薬品です。
| 区分 | 第二世代 |
|---|---|
| タイプ | - |
| 形状 | プラスター剤 |
| 内容量 | 16枚、40枚 |
※この商品は第2類医薬品です。
薄型で患部に密着しやすい
有効成分のサリチル酸メチルを含んだ湿布薬です。超薄型で縦、横、ななめと全方向に伸びがよいため、首すじや肩、関節などにも貼りやすくはがれにくいのが特徴。
貼ってから洋服を着てもごわつきを感じにくく、違和感なく過ごせるのも魅力です。l-メントールなどによりひんやり冷感作用も心地よく、患部の痛みをやわらげてくれます。
※各社通販サイトの 2024年08月23日時点 での税込価格
| 区分 | 第一世代 |
|---|---|
| タイプ | 冷感 |
| 形状 | パップ |
| 内容量 | 48枚 |
※この商品は第3類医薬品です。
| 区分 | 第一世代 |
|---|---|
| タイプ | 冷感 |
| 形状 | パップ |
| 内容量 | 48枚 |
※この商品は第3類医薬品です。
「打撲・捻挫用湿布」のおすすめ商品の比較一覧表
| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 区分 | タイプ | 形状 | 内容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久光製薬『サロンパス』 |

|
※各社通販サイトの 2024年08月23日時点 での税込価格 |
肌にフィットするしなやかな貼り心地 | 第一世代 | - | パップ | 40枚、80枚、120枚 |
| 久光製薬『のびのびサロンシップFα』 |

|
※各社通販サイトの 2024年08月23日時点 での税込価格 |
フィット感が高く密着してはがれにくい | - | 冷感 | パップ | 12枚 |
| 久光製薬『フェイタス5.0温感』 |

|
※各社通販サイトの 2024年08月23日時点 での税込価格 |
心地よい温感刺激が長く続く | 第二世代 | 温感 | テープ | 7枚、14枚 |
| 久光製薬『サロンシップインドメタシンEX』 |

|
※各社通販サイトの 2024年08月23日時点 での税込価格 |
しつこい痛みにじんわり作用 | 第二世代 | 冷感 | - | 12枚、24枚 |
| 久光製薬『サロンパスEX温感』 |

|
※各社通販サイトの 2024年08月23日時点 での税込価格 |
温感作用で症状をやわらげてくれる | 第二世代 | 温感 | - | 20枚、40枚 |
| 第一三共ヘルスケア『ロキソニンSテープ』 |

|
※各社通販サイトの 2024年08月23日時点 での税込価格 |
痛みの芯まで浸透してやわらげてくれる | 第二世代 | - | テープ | 7枚、14枚 |
| 第一三共ヘルスケア『パテックスうすぴたシップ』 |

|
※各社通販サイトの 2024年08月23日時点 での税込価格 |
ピタッと密着してはがれにくい | 第一世代 | 冷感 | パップ | 24枚、48枚 |
| 第一三共ヘルスケア『キュウメタシンパップH』 |

|
※各社通販サイトの 2024年08月23日時点 での税込価格 |
冷たい患部にぴったりな温感湿布 | 第二世代 | 温感 | パップ | 12枚、24枚 |
| 興和『バンテリンコーワパップS』 |

|
※各社通販サイトの 2024年9月3日時点 での税込価格 |
肌にやさしいソフトな使用感 | 第二世代 | 冷感 | パップ | 12枚、24枚 |
| ライオン『ハリックス55EX冷感A』 |
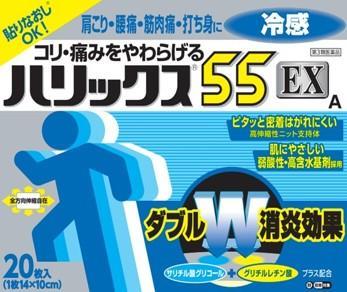
|
※各社通販サイトの 2024年9月4日時点 での税込価格 |
心地よい清涼感が魅力 | 第一世代 | 冷感 | パップ | 10枚、20枚、ハーフサイズ12枚 |
| gsk『ボルタレンEXテープ』 |

|
※各社通販サイトの 2024年9月3日時点 での税込価格 |
痛みを原因からおさえるすぐれた鎮痛力 | 第二世代 | - | テープ | 7枚、14枚、21枚、L:7枚 |
| 大正製薬『トクホン』 |

|
※各社通販サイトの 2024年08月23日時点 での税込価格 |
ひんやり心地よい使用感が魅力 | 第一世代 | - | プラスター剤 | 普通版:40枚、80枚、140枚 |
| 祐徳薬品工業『パスタイムFXこはる』 |

|
※各社通販サイトの 2024年08月23日時点 での税込価格 |
さわやかなアロマの香りがする湿布薬 | 第二世代 | - | - | 20枚、40枚 |
| 大石膏盛堂『フェルビナファインα』 |

|
※各社通販サイトの 2024年08月23日時点 での税込価格 |
痛みを原因からやわらげてくれる | 第二世代 | - | プラスター剤 | 80枚 |
| テイコクファルマケア『オムニードFBプラスターα』 |

|
※各社通販サイトの 2024年08月23日時点 での税込価格 |
ほどよい冷感刺激で痛みをやわらげてくれる | 第二世代 | - | プラスター剤 | 16枚、40枚 |
| 東光薬品工業 ラクール『ラクペタンうすップ』 |

|
※各社通販サイトの 2024年08月23日時点 での税込価格 |
薄型で患部に密着しやすい | 第一世代 | 冷感 | パップ | 48枚 |
通販サイトの最新人気ランキングを参考にする 打撲・捻挫用湿布の売れ筋をチェック
Amazonでの打撲・捻挫用湿布の売れ筋ランキングも参考にしてみてください。
※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。
湿布の使い方と注意点
湿布の使い方として、貼り方と剥がし方、注意点をご紹介します。正しく使って効果を実感しましょう。また、各メーカーでも使用方法が異なることがありますので、添付文書を読んで確認してくださいね。
貼るタイミング・貼り方
湿布を貼るタイミングとしては、お風呂上がりがベストです。血行が落ち着いてきた頃に痛みを軽減させるようなイメージです。お休み前に貼ることもおすすめです。
フィルムを丁寧に剥がして、軽く伸ばしながら貼りたい部位に当てながら貼りましょう。
剥がすタイミングと剥がし方
剥がすタイミングは、貼ってから5時間から6時間経過した頃です。製品によって効果時間も異なるのでパッケージをみて確認しましょう。
剥がし方としては、周りの皮膚を手で押さえて、ゆっくりと剥がします。痛みを感じないためにもゆっくりと剥がすことがポイントです。
注意点
長時間使用すると、皮膚がかぶれてしまうことがあるので、皮膚が弱い人は特に注意が必要です。
また、傷口や湿疹のある部位には使用しないようにしましょう。入浴の30分前には湿布を剥がしておくこともポイントです。
症状に合わせて適切な湿布を選ぼう!
市販されている湿布薬には含まれている成分や冷感、温感など貼り心地などさまざまな種類があります。古くから使われてきた湿布薬のように匂いが気になるものだけでなく、できるだけ匂いをおさえた微香性タイプもたくさんあるので、外出時などでも使いやすくなっているのも特徴です。
打撲や捻挫など患部の症状によっても選ぶべき湿布が異なるので、この記事で紹介した選び方のポイントやおすすめの商品を参考にしながら選んでみてください。
◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。



















































