レコードクリーナーの選び方
レコードクリーナーを選ぶときのポイントは以下の3つです。
【1】クリーナーのタイプ
【2】針のクリーニング
【3】乾燥グッズを用意
上記ポイントをおさえることで、より具体的に欲しい商品を知ることができます。一つひとつ解説していきます。
【1】レコードの盤面は乾式+湿式クリーナーが基本
レコードの盤面は、ホコリがつくと音飛びするおそれがあります。そこで盤面をキズつけずキレイにするためにレコードクリーナーの出番。もっともスタンダードなタイプは乾式クリーナーで、レコード盤の音溝に付着したホコリを拭き取ります。ただし、柔らかい布とはいえあまりに強くこすると傷になってしまい、音の歪みに繋がる場合もあるため注意しましょう。
また、液体のクリーニング剤を併用するタイプを湿式クリーナーと呼びます。湿式クリーナーは静電気を抑える効果があり、ホコリを付着しにくくするのが特徴。なお、静電気防止のクリーニング液にはスプレータイプも利用できます。
【2】レコードの針先には専用クリーナー
レコードクリーナーというとレコードの盤面のクリーニングを想像しがちですが、忘れてはいけないのがレコードプレイヤーに取りつけられたレコード針のクリーニングです。
レコードを再生する際には針が音溝に接触して振動として読み出すことで音声信号を取り出すため、針の側にホコリや汚れが付着していると音飛びが発生します。こちらも専用クリーナーを購入して用意しておきましょう。
また、長期間使用していると針自体が歪んだり錆びてきたりということもあります。その際はレコード針自体を交換する必要が出てきます。
【3】水洗いするなら乾燥グッズを忘れずチェック
レコードをクリーニングする効果的な方法は、実は水洗いです。音楽が記録されている市販のレコードを水で洗っていいの!? と心配する人も多いかもしれませんが、水洗いは昔から専門家からも認められた定番のクリーニング方法。キッチンで用いられる食器用の中性洗剤を使って優しく洗ってホコリを落としましょう。
注意したい点として、レコード盤は「反り」が起こると回転速度が狂うので、レコードを乾燥させる際に気をつけなくてはいけません。「反り」が起こりにくい専用の乾燥グッズを用意しましょう。また、レコードの顔でもあるラベル部分が濡れてしまうことを避けるための、プロテクターなどのアイテムもあります。
もちろん水洗い後はしっかりと乾燥させ、水気のない状態にしなければいけません。
レコードクリーナーおすすめ5選
ここまで紹介したレコードクリーナーの選び方のポイントをふまえて、編集部で選んだおすすめ商品を紹介します。
日々のメンテナンスに重宝するクリーナー
レコード用のカートリッジメーカーが手掛ける乾式クリーナーです。高級ベルベット素材でレコード音溝の汚れやほこりをクリーニングします。
本体幅がレコード幅と合っているので、一周ひとふきするだけで盤面をキレイにできるのがメリット。本格的な汚れ落としというよりも、レコードをかける前の日常的なメンテナンスアイテムとしておすすめです。
| 用途 | レコード用 |
|---|---|
| タイプ | 乾式 |
| 用途 | レコード用 |
|---|---|
| タイプ | 乾式 |
シーンに応じて乾式と湿式を使い分けられる
オーディオテクニカによる乾式/湿式クリーナーです。湿式のクリーニング剤には静電気を抑える効果があるので、長期的なメンテナンスにも向いています。
ほこりを拭いてすぐに音楽を聴きたい場合には乾式のクリーニング部分だけを使い、保管前にクリーニングする際にはクリーニング液を併用するなど使い分けも可能です。
乾式/湿式をセットでそろえたい人におすすめです。
| 用途 | レコード用 |
|---|---|
| タイプ | 乾式/湿式 |
| 用途 | レコード用 |
|---|---|
| タイプ | 乾式/湿式 |
手軽に使えるスプレー式のクリーナー
レコード針の名門ブランド、ナガオカが手掛けるアナログレコード盤用のクリーニングスプレーです。
使い方は湿式クリーニング液と同じ。スプレーをかけたあとに乾式クリーナーで拭き取ることで、静電気を避けることができホコリの付着を防止できます。
| 用途 | レコード用 |
|---|---|
| タイプ | - |
| 用途 | レコード用 |
|---|---|
| タイプ | - |
レコード針をメンテナンスするならコレ
盤面に直接触れるレコード針をクリーニングするための専用クリーニング液です。レコード針は盤面に触れて熱を持つため、チリやホコリが針先に焼きつきます。その焼つきが音飛びの原因になるため、レコードの盤面だけでなく針にもクリーニングが必要。
音飛びがなくても針先のチリやホコリはレコードプレーヤーやレコード盤をいためる可能性もあるので、こまめなメンテナンスにはこちらのクリーナーがおすすめです。
| 用途 | 針先用 |
|---|---|
| タイプ | - |
| 用途 | 針先用 |
|---|---|
| タイプ | - |
わずか数秒でゴミやホコリが除去可能
握りやすいグリップ形状のクリーニングパッドと洗浄液がセットになったレコードクリーナー。記録面と同じサイズになっているので、専用液を数滴たらし、くるっと一蹴させるだけでゴミやホコリを取り除くことが可能。掃除後はクリアなサウンドが蘇ります。
日常的なお手入れを手軽に済ませたい方におすすめの商品です。
| 用途 | レコード用 |
|---|---|
| タイプ | ‐ |
| 用途 | レコード用 |
|---|---|
| タイプ | ‐ |
【番外編】便利なお助けアイテムもご紹介! レコードクリーニングがしやすくなる
丸洗いの際にラベルが濡れてしまうのを防ぐ
レコード盤を水洗いする際に頭を悩ませるのがレコード中央部にあたるレーベル部分の浸水対策。ナガオカの「CLP01」はレコードラベルを覆うように両面からはさみ込むプロテクターです。
ねじで締めつけることによりレコードラベルをカバーできるので、浸水を気にせずレコード盤面をクリーニングできます。定期的に水洗いをする人は持っておきたいアイテムです。
| 用途 | ラベル保護用 |
|---|---|
| タイプ | - |
| 用途 | ラベル保護用 |
|---|---|
| タイプ | - |
デリケートなレコードを乾燥させるときに役立つ
レコードを水洗いしたらレコードを乾燥させなくてはいけません。これは実は頭を悩ませる工程で、乾燥時に起こるレコードの反りを避けるためにレコードを立て掛けて乾燥させる必要があります。そのための便利グッズがこの商品。
10枚のレコードを干して乾燥できます。レコードの形状はお皿に近い円盤型なのでキッチン用品でも代用できますが、サイズの問題もあるのでレコード専用の「BD-LKD11」をおすすめします。
| 用途 | レコード乾燥用 |
|---|---|
| タイプ | - |
| 用途 | レコード乾燥用 |
|---|---|
| タイプ | - |
「レコードクリーナー」のおすすめ商品の比較一覧表
通販サイトの最新人気ランキングを参考にする レコードクリーナーの売れ筋をチェック
Amazonでのレコードクリーナーの売れ筋ランキングも参考にしてみてください。
※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。
レコードプレーヤーをお探しの方はこちら 【関連記事】
クリーナーはさまざまなタイプを揃えよう
レコードクリーナーだけでも何種類もあるので、いきなり買いそろえるのは大変ですが、まずはかんたんにケアできる乾式+湿式クリーナーをセットにした製品から購入しましょう。
多数のレコードで音飛びが発生する場合、また長く使っていなかったレコードプレイヤーを使う際には針クリーナーもおすすめ。水洗いするならプロテクターや乾燥台を用意するなど、必要に応じてそろえていきましょう。
◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。


















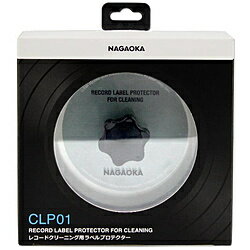




「家電・AV機器」「PC・スマホ・カメラ」カテゴリーを担当。シンプルでミニマルなガジェットには目がなく、つい散財してしまう。とくに、白無地のガジェットが大好物。ひそかに、折りたたみ式のスマートフォンへの乗り換えを計画中。