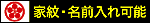| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | セット内容 | サイズ | 仕上げ | デザイン | 家紋・名入れ代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳永のぼり『五月用タペストリー(大)登龍門(152-870-k)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月03日時点 での税込価格 |
鯉の滝のぼりを幻想的に描く | タペストリー飾り台(4本継)、黄金球 | 巾38×長さ75cm、飾り台の高さ207cm | タペストリー仕立て | 登龍門 | 家紋1種類または名入れ代込み |
| 武者絵の里大畑『鍾馗軸(M-5)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月4日時点 での税込価格 |
厄除けの神様「鍾馗」のパワー | 掛軸 | 巾41×長さ140cm | 手描き | 鍾馗図 | 名入れ(横書き)代込み |
| ワタナベ鯉のぼり『手描き本染タペストリー(鯉の滝のぼり(大))』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月03日時点 での税込価格 |
立身出世を願う登龍門 | 4寸切房2個 横棒つき | 巾68×長さ160cm | 手描き本染 | 鯉の滝のぼり | 家紋・名入れ代込み |
| 徳永こいのぼり『ミニ節句幟ベランダセット 龍虎之図幟(151-280)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月03日時点 での税込価格 |
力強さと立身出世を願う龍虎図 | ベランダセット(2.3m掲揚ポール、4寸赤房、ベランダ取りつけ金具、回転球) | 巾45×長さ180cm、ポールの長さ230cm | 格子タイプ | 龍虎之図 | 別 |
| ワタナベ鯉のぼり『1.7mベランダ用武者絵幟セット Bタイプホルダーセット 川中島(wtk-vm17bkn-k)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月03日時点 での税込価格 |
信玄と謙信の戦いを豪華に再現 | ホルダーセット(2.3mポール、Bタイプホルダー、回転球、横棒) | 巾40×長さ170cm、ポールの長さ230cm | ベランダ用 | 川中島 | 家紋または名入れ代込み |
| 徳永こいのぼり『ミニ節句幟ベランダセット 加藤清正幟(151-290)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月4日時点 での税込価格 |
虎退治で知られる勇猛な加藤清正を描く | ベランダセット(2.3m掲揚ポール、4寸赤房、ベランダ取りつけ金具、回転球) | 巾45×長さ180cm、ポールの長さ230cm | 格子タイプ | 加藤清正 | 別 |
| ワタナベ鯉のぼり『1.7mベランダ用武者絵幟セット 金太郎柄金箔付(Wtk-kn-17-c-k)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月4日時点 での税込価格 |
金太郎のように元気いっぱいの男の子になって | スタンドセット(2.3mポール、Cタイプスタンド、回転球、横棒) | 巾45×長さ170cm、ポールの長さ230cm、スタンド設置サイズ:50.5×50cm | アルミ金箔 | 金太郎 | 家紋または名入れ代込み |
| 武者絵の里大畑『鍾馗のぼり(9号角 I-4)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月03日時点 での税込価格 |
厄除けの神様・鍾馗を名人の手描きで | 小旗(掲揚器具、ポール別売り) | 巾102×長さ260cm、小旗の巾27×長さ107cm | 房つき | 鍾馗 | 別 |
武者のぼりとはどのようなもの? 節句のお祝いでおなじみの伝統的なアイテム
武者のぼりとは、勇壮な戦国武将のデザインなどで男の子の健やかな成長を願う端午の節句のお祝いでおなじみの伝統的なアイテムです。室内用のものから玄関先や一戸建ての庭に飾るものまで、さまざまなサイズや図案、設置方法があります。
選び方のポイントは、自宅のスペースやデザインの好みに合った商品を見つけること。まずは武者のぼりの選び方を学んでいきましょう。
武者のぼりの起源 武士が目印に使用していたもの
武者絵のぼりは節句幟とも呼ばれていて、江戸時代のはじめに生まれたものです。もともと、武士が戦いのとき自分の目印として用いた旗指物が起源。江戸の太平の時代になると、飾るための装飾品に変化しました。
江戸時代はこの武者絵のぼりがとても盛んで、さまざまな絵師がその腕を競いあってデザインの凝ったものが次々と登場しました。
今のように華やかでサイズも多彩な武者のぼりが市販されるようになったのは、戦後のこと。鯉のぼりが誕生したのも戦後です。武者のぼりは鯉のぼりとセットで飾ることが多くなって、今に至ります。
武者のぼりの選び方
武者のぼりの選び方を紹介します。ポイントは以下です。
【1】絵柄の種類
【2】サイズと立て方
【3】家紋や名入れ
それぞれ詳しくみていきましょう。
【1】絵柄の種類で選ぶ
武者のぼりという名前ですが、デザインに使われているのは武将ばかりではありません。定番人気の戦国武将のほかにも、立身出世にあやかった鯉の滝のぼりや縁起のよい龍や虎、鍾馗など、さまざまです。
デザインの主役となるキャラクターによって、武者のぼりに込める思いや見た目の印象も変わってきます。具体的にどのようなデザインがあるのか、見ていきましょう。
定番人気の「戦国武将」
武者のぼりに使われる戦国武将には、信長の草履取りから天下を取った豊臣秀吉がとくに人気です。立身出世のシンボルでトントン拍子に才覚を現した太閤秀吉にあやかる気持ちは現代にも通じます。
また、川中島の戦いで激突した武田信玄や上杉謙信の勇壮な図案、虎退治で知られる加藤清正の絵柄もあります。好きな戦国武将が描かれた武者のぼりを選ぶのがポイントです。
「鯉の滝のぼり」は出世を願う心にぴったり
鯉は急流の滝を上流に向かってのぼっていくイメージから、昔から「鯉の滝のぼり」として縁起がいいといわれています。鯉のぼりと同じように、逆境にも負けない力強い男の子になってほしいという気持ちが込められていますね。
また、将来出世して世のなかで活躍してほしいという願いにもぴったりです。もとは古代中国で滝のぼりに成功した鯉が天にのぼって龍に変身するという故事が由来です。
「鍾馗図」は無病息災や厄除けにおすすめ
中国の道教の神様である「鍾馗(しょうき)」は、無病息災や厄除けのご利益があると信仰されています。唐の皇帝・玄宗が病気にかかったとき、鍾馗が病魔を退治したという故事があるほど。
鍾馗の人気は日本にも入ってきて、武士から庶民まで、広く厄除けの神様として愛されてきました。武者のぼりにもよく使われるモチーフのひとつです。
「龍虎柄」は勇ましい男子を願うのにぴったり
空想上の動物の龍も、地上では動物の王者である虎も、どちらも闘争心が強いといわれます。そんな両者が激突して戦いを繰り広げる様子は、勇猛な男の子に育ってほしいという願いを込めて、武者のぼりによく描かれています。
おめでたい図案として中国から日本にも伝わって、今でも根強い人気のあるのが龍虎図です。たくましい男の子の成長を願います。
「金太郎」は健やかな成長と出世を祈願
「まさかりかついで金太郎」と童謡にも歌われる金太郎。中世に金時山で活躍した「坂田金時」をモデルにした端午の節句にもなじみのあるモチーフです。
金太郎は、熊と相撲を取って投げ飛ばしたり、大きな鯉を軽々と捕まえたりなど、力自慢な武士でした。丈夫で健やかに育って活躍してほしいという願いが込められています。
【2】サイズや立て方で選ぶ
武者のぼりは鯉のぼりのように、サイズや立て方もいくつか種類があります。以前は一戸建ての庭で木材や竹を使った竿にのぼりを立てる光景が一般的でした。
しかし、住宅事情の変化で、今は玄関先やベランダに、省スペースで気軽に立てられるタイプの商品が増えています。お家のニーズによって選びやすくなっていますよ。
屋内用・ベランダ用・庭園用の3つから選ぶ
武者のぼりを飾る場所は、住宅事情の移り変わりで庭園から一戸建て、マンションやアパートまで、変化してきました。かつて武者のぼりのサイズは、現在、庭園用と呼ばれる縦の長さが7mから9m近いものが主流でした。そのため、庭つきの家でなければ飾れない大きなものでした。
しかし、最近は住まいのサイズに合わせた商品が多く市販されています。家の中で気軽に飾れる屋内用や、スタンド式やポールタイプのベランダ用も増えています。
飾る場所を想定して、とくに高さ、そして竿の立て方のふたつのポイントから武者のぼりを選びましょう。
自宅は一戸建て? 庭つき? マンション?
武者のぼりを選ぶ前に、まず自宅がどのような住宅なのかを把握しましょう。一戸建てでも庭の有無によって立てられる武者のぼりのサイズが変わってきます。また、庭のない一戸建てやマンションの場合も、サイズや設置方法を工夫すれば、それぞれのご家庭の飾りたい場所に合わせた商品を選べるでしょう。
一般的に、庭園用や玄関先なら3m以上、ベランダ用は2m前後、屋内用は1m程度のものが人気です。
購入の前に設置場所のスペースや高さをチェックしよう
武者のぼりを設置する庭や玄関、ベランダや室内の広さ、そしてどのくらいの高さまで飾れるかを調べましょう。そのサイズにもとづいて、商品情報ののぼりの長さや幅、スタンドの高さや飾る際に必要なスペースをイメージしていくのがポイントです。
たとえばベランダの場合は、上階までの高さが限られているので、のぼりのタテの長さが大切に。また、玄関先に竿をくくりつけるところがない場合は、スタンドタイプの武者のぼりを選ぶ必要があります。
【3】家紋や名入れも忘れずに
商品によって家紋や子どもの名前が入れられます。なかには家紋や名入れ代も込みの商品価格で販売されているものもあるので、チェックしましょう。
家紋を入れると武者のぼりの雰囲気が引き立つとともに、わが家だけのオリジナルな味わいが生まれます。また、子どもの名前を入れれば、飾っておく楽しみが増えるでしょう。
屋外で飾る場合は家紋入りがおすすめです 保育士からのメッセージ
男の子の健やかな成長を願って飾られる、鯉のぼりとともに武者飾りがあると子どもも喜ぶことでしょう。室内飾りは名入れもいいですが、屋外で飾る場合は誰の目に触れるかわからないので、家紋入りにするといいでしょう。ふだん見慣れない家紋から歴史に興味を持ったり、家のルーツを話すきっかけにもなります。
武者のぼりおすすめ3選【屋内用】
ここからは、保育士・すぎ けいこさんと編集部が選んだおすすめ商品をご紹介します。
屋内用・ベランダ用・庭用のタイプ別にわけて紹介するので、家のスペースや設置したい場所をイメージしながらチェックしてみてください。
『五月用タペストリー登龍門』は、手頃な値段で、名前か家紋が入れられるタペストリーです。室内に飾るのにちょうどよいサイズ。日本画テイストの絵柄に名前が入ることで、男の子の勇壮さが感じられ特別感が増します。少し目上の方への贈りものにも。

鯉の滝のぼりを幻想的に描く
立身出世を願う鯉の滝のぼりを日本画のテイストに仕上げたタペストリーです。中央でダイナミックに跳ね上がる鯉は、上部に描かれた勇猛な龍を目指します。小柄なサイズで室内でも気軽に飾れるのが特徴です。
家紋または名前も入れられるので、武者飾りの横に置くと豪華な印象になりますよ。リーズナブルな価格なので、2本目やお祝いにも選びやすい商品です。
※各社通販サイトの 2024年10月03日時点 での税込価格
| セット内容 | タペストリー飾り台(4本継)、黄金球 |
|---|---|
| サイズ | 巾38×長さ75cm、飾り台の高さ207cm |
| 仕上げ | タペストリー仕立て |
| デザイン | 登龍門 |
| 家紋・名入れ代 | 家紋1種類または名入れ代込み |
| セット内容 | タペストリー飾り台(4本継)、黄金球 |
|---|---|
| サイズ | 巾38×長さ75cm、飾り台の高さ207cm |
| 仕上げ | タペストリー仕立て |
| デザイン | 登龍門 |
| 家紋・名入れ代 | 家紋1種類または名入れ代込み |
厄除けの神様「鍾馗」のパワー
ダイナミックで力強く描かれているのは、中国の道教の神様「鍾馗(しょうき)」です。栃木県無形文化財に指定されている大畑耕雲氏の手によるもの。中国から日本へと伝えられた無病息災や立身出世の神様の勇ましい姿を室内に飾ることができます。
タペストリーのサイズはコンパクトなので、省スペースで本格的な武者のぼりが用意できますよ。
※各社通販サイトの 2024年10月4日時点 での税込価格
| セット内容 | 掛軸 |
|---|---|
| サイズ | 巾41×長さ140cm |
| 仕上げ | 手描き |
| デザイン | 鍾馗図 |
| 家紋・名入れ代 | 名入れ(横書き)代込み |
| セット内容 | 掛軸 |
|---|---|
| サイズ | 巾41×長さ140cm |
| 仕上げ | 手描き |
| デザイン | 鍾馗図 |
| 家紋・名入れ代 | 名入れ(横書き)代込み |
立身出世を願う登龍門
3匹の飛び跳ねる鯉が大きく描かれています。そして下部には端午の節句らしく菖蒲の花も描いた、室内用の武者のぼりです。生地は綿生地で質感豊かなものを使用。天を自由に駆け巡る龍、立身出世を願う鯉に男の子の健やかな成長を願います。
色使いが大胆で迫力満点。力強い雰囲気に仕上がっています。家紋や名入れ代も込みのお値段です。
※各社通販サイトの 2024年10月03日時点 での税込価格
| セット内容 | 4寸切房2個 横棒つき |
|---|---|
| サイズ | 巾68×長さ160cm |
| 仕上げ | 手描き本染 |
| デザイン | 鯉の滝のぼり |
| 家紋・名入れ代 | 家紋・名入れ代込み |
| セット内容 | 4寸切房2個 横棒つき |
|---|---|
| サイズ | 巾68×長さ160cm |
| 仕上げ | 手描き本染 |
| デザイン | 鯉の滝のぼり |
| 家紋・名入れ代 | 家紋・名入れ代込み |
武者のぼりおすすめ4選【ベランダ用】
力強さと立身出世を願う龍虎図
格子タイプのベランダにかんたんに取りつけられるベランダ用武者絵のぼりです。伝統的なモチーフである龍と虎の戦う様子を水墨画のテイストで描いています。
龍は天に昇るというイメージから立身出世の願いを込める空想上の動物。一方、虎は陸で荒々しく生き抜く力強いイメージがあります。家紋や名前も入れられるので、オリジナルの武者のぼりに仕立てることが可能です。
※各社通販サイトの 2024年10月03日時点 での税込価格
| セット内容 | ベランダセット(2.3m掲揚ポール、4寸赤房、ベランダ取りつけ金具、回転球) |
|---|---|
| サイズ | 巾45×長さ180cm、ポールの長さ230cm |
| 仕上げ | 格子タイプ |
| デザイン | 龍虎之図 |
| 家紋・名入れ代 | 別 |
| セット内容 | ベランダセット(2.3m掲揚ポール、4寸赤房、ベランダ取りつけ金具、回転球) |
|---|---|
| サイズ | 巾45×長さ180cm、ポールの長さ230cm |
| 仕上げ | 格子タイプ |
| デザイン | 龍虎之図 |
| 家紋・名入れ代 | 別 |
信玄と謙信の戦いを豪華に再現
伝統的な大和絵の雰囲気がどこかユーモラスな武者のぼり。大胆な構図で川中島の戦いで活躍した武田信玄、上杉謙信、そして信玄の家臣で勇猛果敢な戦いぶりで知られる高坂弾正を描いています。浮世絵のような和の配色が見事です。
のぼり上部には家紋または名前を入れられるので、わが家だけのオリジナルの絵のぼりが届きます。
※各社通販サイトの 2024年10月03日時点 での税込価格
| セット内容 | ホルダーセット(2.3mポール、Bタイプホルダー、回転球、横棒) |
|---|---|
| サイズ | 巾40×長さ170cm、ポールの長さ230cm |
| 仕上げ | ベランダ用 |
| デザイン | 川中島 |
| 家紋・名入れ代 | 家紋または名入れ代込み |
| セット内容 | ホルダーセット(2.3mポール、Bタイプホルダー、回転球、横棒) |
|---|---|
| サイズ | 巾40×長さ170cm、ポールの長さ230cm |
| 仕上げ | ベランダ用 |
| デザイン | 川中島 |
| 家紋・名入れ代 | 家紋または名入れ代込み |
虎退治で知られる勇猛な加藤清正を描く
秀吉の家臣の中でも勇猛果敢で知られる加藤清正をモチーフに、男の子の元気な成長を願った武者絵のぼりです。清正は虎を退治したことで知られ、戦国時代を大胆不敵に生き抜きました。そんな清正のエピソードを思い浮かべながら飾ってみると、子どもの今後の成長が楽しみになるのでは?
1.8mでポールや金具つきなので、すぐにベランダに取りつけられます。
※各社通販サイトの 2024年10月4日時点 での税込価格
| セット内容 | ベランダセット(2.3m掲揚ポール、4寸赤房、ベランダ取りつけ金具、回転球) |
|---|---|
| サイズ | 巾45×長さ180cm、ポールの長さ230cm |
| 仕上げ | 格子タイプ |
| デザイン | 加藤清正 |
| 家紋・名入れ代 | 別 |
| セット内容 | ベランダセット(2.3m掲揚ポール、4寸赤房、ベランダ取りつけ金具、回転球) |
|---|---|
| サイズ | 巾45×長さ180cm、ポールの長さ230cm |
| 仕上げ | 格子タイプ |
| デザイン | 加藤清正 |
| 家紋・名入れ代 | 別 |
金太郎のように元気いっぱいの男の子になって
大きな鯉をバックに、雄々しい金太郎を描いた商品です。
現在の神奈川県の山中で活躍したという伝説的な侍・坂田金時にあやかった武者絵のぼりです。金太郎として知られている金時は、子どものころ、熊と相撲を取って勝ったり、大きな鯉を生け捕りにしたりなど、元気いっぱいの男児に成長しました。その後源氏に仕えて、活躍することになります。今でも金太郎のモチーフは男の子の元気で健やかな成長を願う気持ちを込めるのにピッタリといえるでしょう。
※各社通販サイトの 2024年10月4日時点 での税込価格
| セット内容 | スタンドセット(2.3mポール、Cタイプスタンド、回転球、横棒) |
|---|---|
| サイズ | 巾45×長さ170cm、ポールの長さ230cm、スタンド設置サイズ:50.5×50cm |
| 仕上げ | アルミ金箔 |
| デザイン | 金太郎 |
| 家紋・名入れ代 | 家紋または名入れ代込み |
| セット内容 | スタンドセット(2.3mポール、Cタイプスタンド、回転球、横棒) |
|---|---|
| サイズ | 巾45×長さ170cm、ポールの長さ230cm、スタンド設置サイズ:50.5×50cm |
| 仕上げ | アルミ金箔 |
| デザイン | 金太郎 |
| 家紋・名入れ代 | 家紋または名入れ代込み |
武者のぼりおすすめはコレ【庭園用】
『一富士二鷹三茄子』は、黒地に金銀の糸を使っているのが目を引く、豪華で勇壮な武者飾りです。表裏で金銀を使い分けているので、風が吹いてはためくと、キラキラと輝き目を引くことでしょう。
厄除けの神様・鍾馗を名人の手描きで
無病息災や厄除けで知られる道教の鍾馗図が描かれた武者絵のぼりです。黒を基調に鍾馗をダイナミックに描いて、今にも動き出しそうな勢いが伝わってきます。
鍾馗図を掲げると、疫病除けのほか学業成就にもご利益が得られるとも。端午の節句にふさわしく、元気に成長を見守る鍾馗様ののぼりを庭園に飾ってみませんか。
※各社通販サイトの 2024年10月03日時点 での税込価格
| セット内容 | 小旗(掲揚器具、ポール別売り) |
|---|---|
| サイズ | 巾102×長さ260cm、小旗の巾27×長さ107cm |
| 仕上げ | 房つき |
| デザイン | 鍾馗 |
| 家紋・名入れ代 | 別 |
| セット内容 | 小旗(掲揚器具、ポール別売り) |
|---|---|
| サイズ | 巾102×長さ260cm、小旗の巾27×長さ107cm |
| 仕上げ | 房つき |
| デザイン | 鍾馗 |
| 家紋・名入れ代 | 別 |
「武者のぼり」のおすすめ商品の比較一覧表
| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | セット内容 | サイズ | 仕上げ | デザイン | 家紋・名入れ代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳永のぼり『五月用タペストリー(大)登龍門(152-870-k)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月03日時点 での税込価格 |
鯉の滝のぼりを幻想的に描く | タペストリー飾り台(4本継)、黄金球 | 巾38×長さ75cm、飾り台の高さ207cm | タペストリー仕立て | 登龍門 | 家紋1種類または名入れ代込み |
| 武者絵の里大畑『鍾馗軸(M-5)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月4日時点 での税込価格 |
厄除けの神様「鍾馗」のパワー | 掛軸 | 巾41×長さ140cm | 手描き | 鍾馗図 | 名入れ(横書き)代込み |
| ワタナベ鯉のぼり『手描き本染タペストリー(鯉の滝のぼり(大))』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月03日時点 での税込価格 |
立身出世を願う登龍門 | 4寸切房2個 横棒つき | 巾68×長さ160cm | 手描き本染 | 鯉の滝のぼり | 家紋・名入れ代込み |
| 徳永こいのぼり『ミニ節句幟ベランダセット 龍虎之図幟(151-280)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月03日時点 での税込価格 |
力強さと立身出世を願う龍虎図 | ベランダセット(2.3m掲揚ポール、4寸赤房、ベランダ取りつけ金具、回転球) | 巾45×長さ180cm、ポールの長さ230cm | 格子タイプ | 龍虎之図 | 別 |
| ワタナベ鯉のぼり『1.7mベランダ用武者絵幟セット Bタイプホルダーセット 川中島(wtk-vm17bkn-k)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月03日時点 での税込価格 |
信玄と謙信の戦いを豪華に再現 | ホルダーセット(2.3mポール、Bタイプホルダー、回転球、横棒) | 巾40×長さ170cm、ポールの長さ230cm | ベランダ用 | 川中島 | 家紋または名入れ代込み |
| 徳永こいのぼり『ミニ節句幟ベランダセット 加藤清正幟(151-290)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月4日時点 での税込価格 |
虎退治で知られる勇猛な加藤清正を描く | ベランダセット(2.3m掲揚ポール、4寸赤房、ベランダ取りつけ金具、回転球) | 巾45×長さ180cm、ポールの長さ230cm | 格子タイプ | 加藤清正 | 別 |
| ワタナベ鯉のぼり『1.7mベランダ用武者絵幟セット 金太郎柄金箔付(Wtk-kn-17-c-k)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月4日時点 での税込価格 |
金太郎のように元気いっぱいの男の子になって | スタンドセット(2.3mポール、Cタイプスタンド、回転球、横棒) | 巾45×長さ170cm、ポールの長さ230cm、スタンド設置サイズ:50.5×50cm | アルミ金箔 | 金太郎 | 家紋または名入れ代込み |
| 武者絵の里大畑『鍾馗のぼり(9号角 I-4)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年10月03日時点 での税込価格 |
厄除けの神様・鍾馗を名人の手描きで | 小旗(掲揚器具、ポール別売り) | 巾102×長さ260cm、小旗の巾27×長さ107cm | 房つき | 鍾馗 | 別 |
通販サイトの最新人気ランキングを参考にする 武者のぼりの売れ筋をチェック
Amazonでの武者のぼりの売れ筋ランキングも参考にしてみてください。
※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。
すてきな武者のぼりを選んで男児誕生のお祝いをしよう
端午の節句におすすめの武者のぼりをいくつかの角度からまとめてご紹介しました。
武者のぼりは設置場所によって屋内用、ベランダ用、庭園用などサイズや設置方法が異なります。また、子どもの健やかな成長を願って描かれるデザインにも、定番の戦国武将や龍虎図のほか鍾馗や桃太郎など、バリエーションが豊富です。
まず、設置したい場所のスペースを調べて、どの程度のサイズが合うのか考えてみましょう。子どもの元気な成長を願う心をどのような絵柄に込めるのか、豊富なデザインから選んでみてくださいね。
◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。