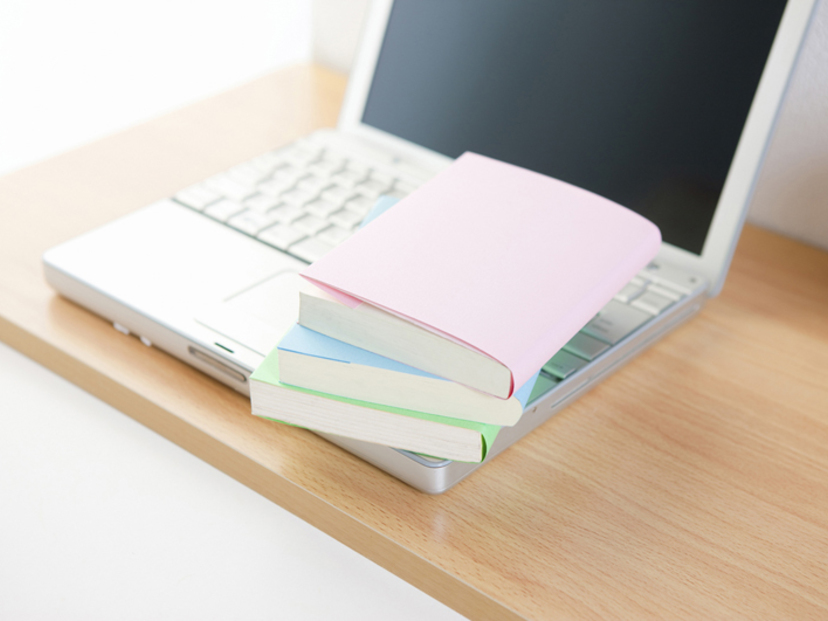| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 解像度 | センサー | 読み取りサイズ | 読み取り速度 | インターフェース | 本体サイズ | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plustek 『OpticBook 4800』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月01日時点 での税込価格 |
本を裁断せずキレイにスキャンしたい人に | 1200dpi | CCD | 216 x 297 mm (A4/ Letter) | 3.6秒 | USB2.0 | 491 × 291 × 102mm | 3.45kg |
| Canon(キヤノン)『CANOSCAN LIDE 400』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月01日時点 での税込価格 |
高性能で持ち運びやすい | 4800dpi | CIS | A4 | 300dpi/4800dpi | - | ‐ | 約1.7kg |
| Canon(キヤノン)『imageFORMULA (DR-C225W II)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月01日時点 での税込価格 |
設置スペースが狭くてすむドキュメントスキャナー | 600dpi | CIS | A4対応(最大216 × 356mm) | 15枚/分(カラー300dpi)/25枚/分(白黒・グレースケール300dpi) | USB2.0/無線LAN(IEEE802.11n対応) | 300 × 235 × 339mm | 2.8kg |
| FUJITSU(富士通)『スキャナー ScanSnap iX100(FI-IX100A)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月01日時点 での税込価格 |
どこでも使える小型サイズのスキャナー | - | - | A4 | - | USB | 幅273mm×奥行47.5mm×高さ36mm | 400g |
| iOCHOW『ブックスキャナー』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月01日時点 での税込価格 |
コンパクトサイズで折りたためる!持ち運びにも◎ | - | - | 最大でA3 | - | - | 約8.5×7×36.1cm | 約0.75kg |
| PFU ScanSnap『FI-SV600A』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月01日時点 での税込価格 |
大きな本もそのままスキャンできる | カラー/グレー300dpi、白黒600dpi相当(スーパーファイン時) | CCD | A3(最大 432×300mm) | 3秒 | USB2.0 | 210 × 156 × 383mm | 3kg |
| PFU ScanSnap『FI-IX1500』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月01日時点 での税込価格 |
定評のあるドキュメントスキャナーが大きく進化 | 600dpi | カラーCIS×2 | A4、A5、A6、B5、B6、はがき、名刺、レター、リーガル、カスタムサイズ | 30枚/分(スーパーファイン時) | USB3.1/無線LAN(IEEE802.11ac対応) | 292 × 494 × 293mm | 3.4kg |
| brother(ブラザー)『brother スキャナー(ADS-1700W)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月01日時点 での税込価格 |
文字のスキャンや両面コピーに最適 | 光学解像度/最大600×600dpi、ソフトウェア補間解像度/最大1200×1200dpi | CIS | A4 | カラー 150dpi:片面約25枚/分 (両面約50面/分)他、白黒 150dpi:片面約25枚/分 他 | 無線LAN/Micro USB 3.0/IEEE802.11 b/g | 300×103×83mm | 約1.41kg |
| FUJITSU(富士通)『ScanSnap S1300i(FI-S1300B)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月01日時点 での税込価格 |
大切な思い出やデータを電子化に | 600dpi | CIS×2 | A4、A5、A6、B5、B6、はがき、名刺、レター、リーガル、カスタムサイズ(最大:216×360mm) | カラー、グレー/300dpi、白黒/600dpi | USB2.0 | 99×284×77mm | 1.4kg |
| FUJITSU(富士通)『PFUドキュメントスキャナー ScanSnap A4 両面カラースキャナー (FI-7140G)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月01日時点 での税込価格 |
原稿の損傷を防ぎ、スマートにスキャン | 600dpi | ‐ | A4 | カラー 300dpi:毎分40枚/80面 | USB2.0/USB1.1 | 170×300×163mm | 4.2kg |
| EPSON(エプソン)『DS-870』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月01日時点 での税込価格 |
業務用途でも使える高速ドキュメントスキャナー | 1200dpi | CIS×2 | A4、USレターサイズ、リーガル、長尺紙(216×6,096mm) | 約65枚/分(カラー・モノクロ/A4・300dpi) | USB3.0/有線LAN(1000BASE-T/オプション) | 296 × 212 × 217mm | 約3.6kg |
ブックスキャナーとは
ブックスキャナーとは、本・書籍をスキャンし、PDFなどへデータ化してくれるデバイス。コピー機のスキャナーのようなタイプもあれば、本専用のスタンドタイプまで様々な種類があります。
ブックスキャナーを使用することで、大きな質量の本・書籍をデータ化できるため、本棚を整理することができます。さらに、データ化した書籍はPDFやアプリなどでいつでも読むことができるため、場所を選ばず読めるメリットもあります。
ブックスキャナーの種類・タイプ
ブックスキャナーには、大きく分けて「シートフィード型」「フラットベッド型」「オーバーヘッド型」の3種類に分けられます。一つひとつ解説していきます。
かんたんさを求めるなら「シートフィード型」
仕事中に本の一部をスキャンしたいときは、素早くかんたんにおこないたいもの。そのようなシーンに適しているのが「シートフィード型」。別名「ドキュメントスキャナー」とも呼ばれます。
原稿などの書類はまとめてセットすれば、自動的に1枚ずつ読み取り可能。しかも高速です。ただし本の場合はページをばらして分解する必要があります。本をそのまま残しておきたい場合は向いていません。
精度にこだわるなら「フラットベッド型」
平らな形状をしているのが「フラットベッド型」。本をスキャンするときはページを開いて置くだけなので、ページをばらす必要がありません。本を大切にしたい場合に便利です。
厚みのある本でも影が入らないような設計になっており、読み取り精度にすぐれています。ただし設置スペースが必要で、一度にスキャンできないのがデメリット。スキャンするたびにページをめくらなくてはなりません。
手軽さ重視なら「オーバーヘッド型」
シートフィード型やオーバーヘッド型よりも値段は高くなりますが、手軽に本をスキャンできるのが「オーバーヘッド型」。デスク用ライトと同じような形状で、本を読み取り機の下に置くだけです。
本のページを分解する必要がなく、厚みのある本でも手軽にスキャンが可能。ゆがみを補正する機能がついている製品もあります。
ブックスキャナーの選び方
それでは、ブックスキャナーの基本的な選び方を見ていきましょう。ポイントは下記の5つ。
・本を裁断するかどうか
・解像度
・読み取りセンサー
・本のサイズ
・付加機能
上記の5つのポイントをおさえることで、より具体的に欲しい機能を知ることができます。一つひとつ解説していきます。
【1】本を裁断するかどうかチェック
本をスキャンしてデジタルデータに変換することを通称「自炊」と呼びますが、自炊の方法は、「本を裁断して、1ページごとに切り離してスキャン」と「本をそのままスキャン」に大別されます。
本の置き場所に困っている場合は、前者の方法でデジタルデータ化したあと、本を処分することをおすすめします。ですが、元の本もそのままの形で保存しておきたいなら、こちらの方法ではデータ化できません。
裁断してスキャンする場合は「シートフィード型」、そのままスキャンしたい場合は、「フラットベッド型」か「オーバーヘッド型」が適しています。
【2】解像度をチェック
せっかくスキャンしても精度が劣ると読みづらかったりします。それを防ぐには、ブックスキャナーを選ぶときに解像度をチェックしましょう。
解像度が高いほど精密な読み取りが可能です。ただし解像度が高くなるとファイルサイズは重くなりますので要注意。
一般的に文字のみを読み取るのなら300dpi、写真や絵などもきれいに読み取りたいなら600dpiの解像度が目安です。
【3】読み取りセンサーをチェック
ブックスキャナーを選ぶとき、読み取りセンサー機能も大事なポイントです。スキャナーの読み取りセンサーには「CCD」と「CIS」の2種類があります。
CCDは読み取り精度とスピードにすぐれ、本をきれいにスキャンしたいときに便利。ただし値段が高めでサイズも大型です。
小型で値段が安めなのがCIS。ただし読み取り精度とスピードが遅くなります。使い勝手で選ぶならCCDのブックスキャナーでしょう。
【4】本のサイズをチェック
一般的なブックスキャナーが読み取れるサイズはA4です。単行本や文庫本サイズならA4でもじゅうぶんですが、大きい本になるとA3サイズが読み取れるスキャナーを選ぶことになります。
とくに絵本、地図などを多く読み取る場合は、最初からA3対応のブックスキャナーを選んだほうが使いやすいです。A4で読み取ろうとすると、分割してスキャンしなくてはなりません。
【5】付加機能をチェック
本をスキャンするとき、紙質によっては裏が写ってしまう場合があります。また、少しでもぶれるとまっすぐに読み取れません。
そのような不安があるときは、付加機能がついているブックスキャナーを選びましょう。裏写りを補正したり、取り込んだ画像のゆがみを補正できたりします。
そのほかにも、自分の指が写り込んだのを消す機能やパソコンで自動分割できる機能、スマホ読み取りが可能になる機能などがあるので、チェックしてみてください。
プリント整理にもおすすめなデバイスです エキスパートのアドバイス
ブックスキャナーは、本を自炊してデジタルデータ化するための製品ですが、小中学校で配布されるお知らせのプリントなどを整理したいという人にも向いています。とくに、シートフィード型のドキュメントスキャナーなら気軽にプリントをデジタル化できるので、もらったはずのお知らせが見つからなくなって困ることも防げます。
プリントを片っ端からスキャンして、クラウドに保存しておけば、スマートフォンを使っていつでもどこでもその内容が確認可能。このように、家庭内のペーパーレス化にもブックスキャナーはとても役立ちますよ。
ブックスキャナーおすすめ11選
上で紹介したブックスキャナーの選び方のポイントをふまえて、おすすめ商品を紹介します。シートフィーダ型やフラットベッド型、オーバーヘッド型と各種ご紹介していますので、使い方にあったスキャナーを選んでください。

本を裁断せずキレイにスキャンしたい人に
フラットベッド型のA4対応ブックスキャナーです。読み取り面とエッジの間の幅がわずか2mmしかなく、本を裁断せずにしっかりとスキャンすることができます。最大解像度は1200×2400dpiと高く、A4原稿なら1枚3.6秒でスキャンが可能。
インターフェースはUSB 2.0で、光源にはLEDを、センサーにはCCDを採用しています。そのためピントが合う範囲も深く、高品質なスキャン結果が得られます。本を裁断せずに、そのままスキャンしたい人におすすめです。
※各社通販サイトの 2024年11月01日時点 での税込価格
| 解像度 | 1200dpi |
|---|---|
| センサー | CCD |
| 読み取りサイズ | 216 x 297 mm (A4/ Letter) |
| 読み取り速度 | 3.6秒 |
| インターフェース | USB2.0 |
| 本体サイズ | 491 × 291 × 102mm |
| 重量 | 3.45kg |
| 解像度 | 1200dpi |
|---|---|
| センサー | CCD |
| 読み取りサイズ | 216 x 297 mm (A4/ Letter) |
| 読み取り速度 | 3.6秒 |
| インターフェース | USB2.0 |
| 本体サイズ | 491 × 291 × 102mm |
| 重量 | 3.45kg |
高性能で持ち運びやすい
低消費電力で、パソコンとUSBケーブルを繋ぐだけで使用が可能。薄型で軽量なので、立てて収納ができます。また、スタンドを使うと立てたままスキャンして使用もできるので、限られたスペースでの作業時にもとても便利です。
原稿の判別や、使用したデータのファイル保存を自動でしてくれます。文字や画像も鮮明にスキャンできるので、雑誌や書類などのスキャンに最適です。
※各社通販サイトの 2024年11月01日時点 での税込価格
| 解像度 | 4800dpi |
|---|---|
| センサー | CIS |
| 読み取りサイズ | A4 |
| 読み取り速度 | 300dpi/4800dpi |
| インターフェース | - |
| 本体サイズ | ‐ |
| 重量 | 約1.7kg |
| 解像度 | 4800dpi |
|---|---|
| センサー | CIS |
| 読み取りサイズ | A4 |
| 読み取り速度 | 300dpi/4800dpi |
| インターフェース | - |
| 本体サイズ | ‐ |
| 重量 | 約1.7kg |

設置スペースが狭くてすむドキュメントスキャナー
コンパクトなシートフィード型のA4対応ドキュメントスキャナーです。原稿がUターンして本体前部に収まる、排紙スペースのいらない「ラウンドスキャン」方式採用で、わずかなスペースにも設置できることが魅力です。最大解像度は600dpiで、両面読み取りに対応。スキャン速度も15枚(30面)/分(300dpi時)とじゅうぶんな性能を実現しています。A3ふたつ折り原稿のスキャンも可能で、最大約30枚までの原稿を一度にスキャンできます。
インターフェースはUSB 2.0と無線LANに対応しています。本をスキャンするには、本を裁断する必要がありますが、気軽に机の上に置けるスキャナーがほしいという人におすすめです。
※各社通販サイトの 2024年11月01日時点 での税込価格
| 解像度 | 600dpi |
|---|---|
| センサー | CIS |
| 読み取りサイズ | A4対応(最大216 × 356mm) |
| 読み取り速度 | 15枚/分(カラー300dpi)/25枚/分(白黒・グレースケール300dpi) |
| インターフェース | USB2.0/無線LAN(IEEE802.11n対応) |
| 本体サイズ | 300 × 235 × 339mm |
| 重量 | 2.8kg |
| 解像度 | 600dpi |
|---|---|
| センサー | CIS |
| 読み取りサイズ | A4対応(最大216 × 356mm) |
| 読み取り速度 | 15枚/分(カラー300dpi)/25枚/分(白黒・グレースケール300dpi) |
| インターフェース | USB2.0/無線LAN(IEEE802.11n対応) |
| 本体サイズ | 300 × 235 × 339mm |
| 重量 | 2.8kg |
どこでも使える小型サイズのスキャナー
重量わずか400gと軽量でコンパクトなスキャナーです。Wi-FiがあればUSBを使わなくても、接続可能。コードレスなので持ち運んで便利に使うことができます。また、クラウドサービスとの連携も可能です。
分厚い本などのスキャンには向いていませんが書類やレシートなどを手軽にスキャンしたい方におすすめです。
※各社通販サイトの 2024年11月01日時点 での税込価格
| 解像度 | - |
|---|---|
| センサー | - |
| 読み取りサイズ | A4 |
| 読み取り速度 | - |
| インターフェース | USB |
| 本体サイズ | 幅273mm×奥行47.5mm×高さ36mm |
| 重量 | 400g |
| 解像度 | - |
|---|---|
| センサー | - |
| 読み取りサイズ | A4 |
| 読み取り速度 | - |
| インターフェース | USB |
| 本体サイズ | 幅273mm×奥行47.5mm×高さ36mm |
| 重量 | 400g |
コンパクトサイズで折りたためる!持ち運びにも◎
1700万画素と高解像度でありながら高速でスキャンできるので効率的に使えるオーバーヘッド型のブックスキャナーです。最大でA3サイズまで読みとれて、多言語対応のOCR文字認識機能を搭載しています。さらに、自動トリミングでスキャン対象以外の不要部分を削除する機能や自動連続撮影、自動補正など実用的な機能も備わっているので、ぜひ、チェックしてみてください。
※各社通販サイトの 2024年11月01日時点 での税込価格
| 解像度 | - |
|---|---|
| センサー | - |
| 読み取りサイズ | 最大でA3 |
| 読み取り速度 | - |
| インターフェース | - |
| 本体サイズ | 約8.5×7×36.1cm |
| 重量 | 約0.75kg |
| 解像度 | - |
|---|---|
| センサー | - |
| 読み取りサイズ | 最大でA3 |
| 読み取り速度 | - |
| インターフェース | - |
| 本体サイズ | 約8.5×7×36.1cm |
| 重量 | 約0.75kg |

大きな本もそのままスキャンできる
オーバーヘッド型のA3対応スタンドスキャナーです。光学解像度は、主走査が285~218dpi、副走査が283~152dpiですが、カラー/グレースケールなら最大600dpi相当、モノクロなら最大1200dpi相当でのスキャンが可能。
読み取り速度は1枚あたり3秒で、「ブック補正機能」により、読み取った画像のゆがみも自動的に補正されます。また、ページめくり検出機能も備えているので、効率のよいスキャンが可能です。
インターフェースはUSB 2.0対応です。A3サイズの大型本や図鑑などを取り込みたい人に向いています。
※各社通販サイトの 2024年11月01日時点 での税込価格
| 解像度 | カラー/グレー300dpi、白黒600dpi相当(スーパーファイン時) |
|---|---|
| センサー | CCD |
| 読み取りサイズ | A3(最大 432×300mm) |
| 読み取り速度 | 3秒 |
| インターフェース | USB2.0 |
| 本体サイズ | 210 × 156 × 383mm |
| 重量 | 3kg |
| 解像度 | カラー/グレー300dpi、白黒600dpi相当(スーパーファイン時) |
|---|---|
| センサー | CCD |
| 読み取りサイズ | A3(最大 432×300mm) |
| 読み取り速度 | 3秒 |
| インターフェース | USB2.0 |
| 本体サイズ | 210 × 156 × 383mm |
| 重量 | 3kg |

定評のあるドキュメントスキャナーが大きく進化
シートフィード型のA4対応ドキュメントスキャナーです。従来から人気の製品ですが、最新モデルでは大型液晶タッチパネルを搭載。設定をスキャナー本体で変更、確認できるようになり、使い勝手が向上しています。最大解像度は600dpiで、両面読み取りに対応、スキャン速度も30枚(60面)/分と高速です。A3ふたつ折り原稿にも対応しています。
最大50枚までの原稿を1度にスキャンでき、インターフェースはUSB 3.1と無線LANに対応しています。本を裁断してもいいから、効率よくスキャンしたいという人におすすめです。
※各社通販サイトの 2024年11月01日時点 での税込価格
| 解像度 | 600dpi |
|---|---|
| センサー | カラーCIS×2 |
| 読み取りサイズ | A4、A5、A6、B5、B6、はがき、名刺、レター、リーガル、カスタムサイズ |
| 読み取り速度 | 30枚/分(スーパーファイン時) |
| インターフェース | USB3.1/無線LAN(IEEE802.11ac対応) |
| 本体サイズ | 292 × 494 × 293mm |
| 重量 | 3.4kg |
| 解像度 | 600dpi |
|---|---|
| センサー | カラーCIS×2 |
| 読み取りサイズ | A4、A5、A6、B5、B6、はがき、名刺、レター、リーガル、カスタムサイズ |
| 読み取り速度 | 30枚/分(スーパーファイン時) |
| インターフェース | USB3.1/無線LAN(IEEE802.11ac対応) |
| 本体サイズ | 292 × 494 × 293mm |
| 重量 | 3.4kg |
文字のスキャンや両面コピーに最適
幅約30cmと、場所を取らないコンパクトサイズ。Wi-Fi完備で、スマホからデータを送り込んでスキャンできるので、使用の幅が広がりますよ。家庭での使用に限らず、会社や病院の窓口など、業務での使用にも最適です。
カラー自動判別機能を搭載しており、自動で識別してデータを適切に処理してくれます。また、USBメモリーを接続して、スキャンしたデータを直接USBにデータの保存が可能なので、持ち運びにも便利ですよ。
※各社通販サイトの 2024年11月01日時点 での税込価格
| 解像度 | 光学解像度/最大600×600dpi、ソフトウェア補間解像度/最大1200×1200dpi |
|---|---|
| センサー | CIS |
| 読み取りサイズ | A4 |
| 読み取り速度 | カラー 150dpi:片面約25枚/分 (両面約50面/分)他、白黒 150dpi:片面約25枚/分 他 |
| インターフェース | 無線LAN/Micro USB 3.0/IEEE802.11 b/g |
| 本体サイズ | 300×103×83mm |
| 重量 | 約1.41kg |
| 解像度 | 光学解像度/最大600×600dpi、ソフトウェア補間解像度/最大1200×1200dpi |
|---|---|
| センサー | CIS |
| 読み取りサイズ | A4 |
| 読み取り速度 | カラー 150dpi:片面約25枚/分 (両面約50面/分)他、白黒 150dpi:片面約25枚/分 他 |
| インターフェース | 無線LAN/Micro USB 3.0/IEEE802.11 b/g |
| 本体サイズ | 300×103×83mm |
| 重量 | 約1.41kg |
大切な思い出やデータを電子化に
コンパクトなスキャナーですが、白黒、カラーと選んで両面の印刷ができるためとても便利です。かさばる書類や本など、必要なところを必要な分だけ家庭で簡単にスキャンして保存できます。年賀状や貯まったレシートなどの効率的な整理整頓を考えている方や、コンパクトにまとめたい方などにおすすめです。
電子化をして残しておくといつでも振り返りができ、検索も簡単にできますよ。スキャンできるサイズも幅広いので、大事な思い出や必要なものを手軽に電子化してみませんか。
※各社通販サイトの 2024年11月01日時点 での税込価格
| 解像度 | 600dpi |
|---|---|
| センサー | CIS×2 |
| 読み取りサイズ | A4、A5、A6、B5、B6、はがき、名刺、レター、リーガル、カスタムサイズ(最大:216×360mm) |
| 読み取り速度 | カラー、グレー/300dpi、白黒/600dpi |
| インターフェース | USB2.0 |
| 本体サイズ | 99×284×77mm |
| 重量 | 1.4kg |
| 解像度 | 600dpi |
|---|---|
| センサー | CIS×2 |
| 読み取りサイズ | A4、A5、A6、B5、B6、はがき、名刺、レター、リーガル、カスタムサイズ(最大:216×360mm) |
| 読み取り速度 | カラー、グレー/300dpi、白黒/600dpi |
| インターフェース | USB2.0 |
| 本体サイズ | 99×284×77mm |
| 重量 | 1.4kg |
原稿の損傷を防ぎ、スマートにスキャン
家庭で簡単に、とっておくとかさばりやすい本や雑誌、はがきなどのスキャンができます。電子化すると振り返りもしやすく、必要に応じて印刷ができるので一台あると便利ですよ。年賀状のシーズンには特に、データを簡単に探し、スキャンできるので重宝するでしょう。
両面カラースキャンができるため、免許証や必要な書類の印刷にも最適です。高性能で使いやすさも抜群で、コスト面にも優れているため、初めて使用される方やコスト面で不安がある方にもおすすめです。
※各社通販サイトの 2024年11月01日時点 での税込価格
| 解像度 | 600dpi |
|---|---|
| センサー | ‐ |
| 読み取りサイズ | A4 |
| 読み取り速度 | カラー 300dpi:毎分40枚/80面 |
| インターフェース | USB2.0/USB1.1 |
| 本体サイズ | 170×300×163mm |
| 重量 | 4.2kg |
| 解像度 | 600dpi |
|---|---|
| センサー | ‐ |
| 読み取りサイズ | A4 |
| 読み取り速度 | カラー 300dpi:毎分40枚/80面 |
| インターフェース | USB2.0/USB1.1 |
| 本体サイズ | 170×300×163mm |
| 重量 | 4.2kg |

業務用途でも使える高速ドキュメントスキャナー
シートフィード型のA4対応ドキュメントスキャナーです。最大解像度は1200dpiで、両面読み取りに対応。スキャン速度は、最大65枚(130面)/分(300dpi時)と超高速です。オートシートフィーダで最大100枚の給紙が可能で、継ぎ足しスキャンにも対応していますので、大量の文書も短時間でスキャン可能。インターフェースはUSB 3.0ですが、オプションで有線LANにも対応します。
A3やB4サイズの原稿も別売りのキャリアシートに挟むことでスキャンが可能。書籍を裁断してデジタルデータにしたいという人はもちろん、大量の文書をデジタルデータ化して、ペーパーレスを推進したいという人にもおすすめです。
※各社通販サイトの 2024年11月01日時点 での税込価格
| 解像度 | 1200dpi |
|---|---|
| センサー | CIS×2 |
| 読み取りサイズ | A4、USレターサイズ、リーガル、長尺紙(216×6,096mm) |
| 読み取り速度 | 約65枚/分(カラー・モノクロ/A4・300dpi) |
| インターフェース | USB3.0/有線LAN(1000BASE-T/オプション) |
| 本体サイズ | 296 × 212 × 217mm |
| 重量 | 約3.6kg |
| 解像度 | 1200dpi |
|---|---|
| センサー | CIS×2 |
| 読み取りサイズ | A4、USレターサイズ、リーガル、長尺紙(216×6,096mm) |
| 読み取り速度 | 約65枚/分(カラー・モノクロ/A4・300dpi) |
| インターフェース | USB3.0/有線LAN(1000BASE-T/オプション) |
| 本体サイズ | 296 × 212 × 217mm |
| 重量 | 約3.6kg |
「ブックスキャナー」のおすすめ商品の比較一覧表
| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 解像度 | センサー | 読み取りサイズ | 読み取り速度 | インターフェース | 本体サイズ | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plustek 『OpticBook 4800』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月01日時点 での税込価格 |
本を裁断せずキレイにスキャンしたい人に | 1200dpi | CCD | 216 x 297 mm (A4/ Letter) | 3.6秒 | USB2.0 | 491 × 291 × 102mm | 3.45kg |
| Canon(キヤノン)『CANOSCAN LIDE 400』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月01日時点 での税込価格 |
高性能で持ち運びやすい | 4800dpi | CIS | A4 | 300dpi/4800dpi | - | ‐ | 約1.7kg |
| Canon(キヤノン)『imageFORMULA (DR-C225W II)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月01日時点 での税込価格 |
設置スペースが狭くてすむドキュメントスキャナー | 600dpi | CIS | A4対応(最大216 × 356mm) | 15枚/分(カラー300dpi)/25枚/分(白黒・グレースケール300dpi) | USB2.0/無線LAN(IEEE802.11n対応) | 300 × 235 × 339mm | 2.8kg |
| FUJITSU(富士通)『スキャナー ScanSnap iX100(FI-IX100A)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月01日時点 での税込価格 |
どこでも使える小型サイズのスキャナー | - | - | A4 | - | USB | 幅273mm×奥行47.5mm×高さ36mm | 400g |
| iOCHOW『ブックスキャナー』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月01日時点 での税込価格 |
コンパクトサイズで折りたためる!持ち運びにも◎ | - | - | 最大でA3 | - | - | 約8.5×7×36.1cm | 約0.75kg |
| PFU ScanSnap『FI-SV600A』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月01日時点 での税込価格 |
大きな本もそのままスキャンできる | カラー/グレー300dpi、白黒600dpi相当(スーパーファイン時) | CCD | A3(最大 432×300mm) | 3秒 | USB2.0 | 210 × 156 × 383mm | 3kg |
| PFU ScanSnap『FI-IX1500』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月01日時点 での税込価格 |
定評のあるドキュメントスキャナーが大きく進化 | 600dpi | カラーCIS×2 | A4、A5、A6、B5、B6、はがき、名刺、レター、リーガル、カスタムサイズ | 30枚/分(スーパーファイン時) | USB3.1/無線LAN(IEEE802.11ac対応) | 292 × 494 × 293mm | 3.4kg |
| brother(ブラザー)『brother スキャナー(ADS-1700W)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月01日時点 での税込価格 |
文字のスキャンや両面コピーに最適 | 光学解像度/最大600×600dpi、ソフトウェア補間解像度/最大1200×1200dpi | CIS | A4 | カラー 150dpi:片面約25枚/分 (両面約50面/分)他、白黒 150dpi:片面約25枚/分 他 | 無線LAN/Micro USB 3.0/IEEE802.11 b/g | 300×103×83mm | 約1.41kg |
| FUJITSU(富士通)『ScanSnap S1300i(FI-S1300B)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月01日時点 での税込価格 |
大切な思い出やデータを電子化に | 600dpi | CIS×2 | A4、A5、A6、B5、B6、はがき、名刺、レター、リーガル、カスタムサイズ(最大:216×360mm) | カラー、グレー/300dpi、白黒/600dpi | USB2.0 | 99×284×77mm | 1.4kg |
| FUJITSU(富士通)『PFUドキュメントスキャナー ScanSnap A4 両面カラースキャナー (FI-7140G)』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月01日時点 での税込価格 |
原稿の損傷を防ぎ、スマートにスキャン | 600dpi | ‐ | A4 | カラー 300dpi:毎分40枚/80面 | USB2.0/USB1.1 | 170×300×163mm | 4.2kg |
| EPSON(エプソン)『DS-870』 |

|
※各社通販サイトの 2024年11月01日時点 での税込価格 |
業務用途でも使える高速ドキュメントスキャナー | 1200dpi | CIS×2 | A4、USレターサイズ、リーガル、長尺紙(216×6,096mm) | 約65枚/分(カラー・モノクロ/A4・300dpi) | USB3.0/有線LAN(1000BASE-T/オプション) | 296 × 212 × 217mm | 約3.6kg |
通販サイトの最新人気ランキングを参考にする ブックスキャナーの売れ筋をチェック
Amazon、楽天市場でのブックスキャナーの売れ筋ランキングも参考にしてみてください。
※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。
種類ごとの特徴を把握しよう
本記事では、ブックスキャナーの種類や選び方、そしておすすめ商品をご紹介しましたが、いかがでしたか?商品を選ぶ際は、種類ごとの特徴を抑えた上で、下記の5つのポイントを抑えておきましょう。
・本を裁断するかどうか
・解像度
・読み取りセンサー
・本のサイズ
・付加機能
上記のポイントをおさえることで、より使いやすいブックスキャナーを選べるはずです。
ブックスキャナーは保管に困ってしまった本・書籍をデータ化してスリムにしてくれるだけでなく、電子書籍として、手軽にどこでも読書ができるようにしてくれます。スキャンすることで、部屋もスリムになるので、部屋の本の整理を考えている方は、ぜひ本記事を参考に、自分にピッタリの商品を見つけてくださいね。
◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。